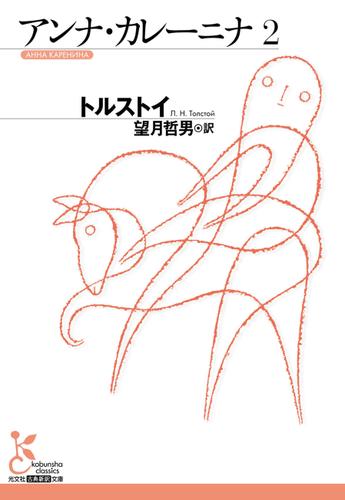
総合評価
(26件)| 8 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログリョーヴィンとキティの偶然の再開。彼女がこちらを見つけた時の一瞬の輝いた目を見てもう一度確信する。自分には彼女しかないと。このシーンがとてつもなく好きだった。 リョーヴィンを軸とした田舎の描写、恋愛描写は、ナボコフをはじめとした一定数の読者から不評とのことで、確かに一理あると思った。アンナを取り巻く環境に比べ、リョーヴィンの恋愛は生ぬるい。確かにアンナとカレーニン、そしてヴロンスキーらのそれぞれの心情描写、何に悩んでいるかを考える方が有意義なように見える。 カレーニンはアンナの不倫を離婚などという、かえって妻が得するような形で罰するのではなく、別の形で、しかも世間に知られることなく罰したいと考えていたが、我慢できなくなる。 しかしアンナが死にそうになった際、いっそアンナが死んでくれれば良いとさえ願ったものの、いざ妻の姿を見ると、自分がアンナを心から憎むことができないと悟り、そんなことを願った自分を悔いてアンナとその不倫相手ヴロンスキーをも許す。 ここのシーンがあまりにも深い。議論の余地を多分に残している。実際、この時のカレーニンにヴロンスキーは驚き、どう対応して良いかわからなくなってしまい、銃で自殺未遂するほど追い込まれている。 世間体で離婚したくないという単純なものではなく、「離婚してしまえば妻が本当の意味で破滅してしまう」ということを懸念して離婚できずにいたのがカレーニン。リョーヴィンではなく、カレーニンこそ第二の主人公に相応しいように思えてきた。 アンナとヴロンスキーがいくら逃避行しようとも、この後も誰も幸せにならない未来が見える。
0投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
*リョービンが農民と共に草刈りをするシーンは、のびのび、活き活きとしている。田舎でのドリーの子どもとのやりとり、通りすがりの人々とのやりとりものびのび、いきいきしている。その二人が村で出会う! *リョービンとキティの決裂してからの熱愛ぶりの描き方。 *アンナの出産に際しての死の間際にまでいってしまうことに、夫カレーニンと愛人ヴロンスキーの大変化。そして、その人間的な皮相ぶり。自殺の衝動性の描き方の傑出。
0投稿日: 2025.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれがロシア革命前であると思いながら読むと、リョーヴィンの思想がいかに危ういものだったか分かってしまう。今回は幸福のうちに終わったが、善良ゆえに、一手に大衆の悪意も担ってしまいそうで、続きがなんだかおそろしい…。とはいえ、共産主義たりえなかった白樺派がトルストイを精神的支柱とした理由は分かった気がする。
0投稿日: 2025.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作を読もうシリーズ。とっつきやすさから光文社の新訳文庫で。3部はアンナがメインじゃないため少し退屈さを感じてしまいました。ごめんなさい。
0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時のロシアの女性の立場がどのようなものだったのか、学ぶことができました。不貞は肯定できないけど、アンナもカレーニンも、難しい選択だなあと。1巻よりは少し読みやすかったです。 リョーヴィンとキティの両想いになるときのやり取りがかわいかったです。
1投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ第3部はリョーヴィンの農業経営、第4部はアンナの愛という感じ。最後にリョーヴィンとキティが惹かれあう…。 1巻と同じでやはり読書ガイドが面白い。結婚が神による結合と考えられており、そのため離婚は基本的に認められず、身体的な欠陥、失踪、不貞しか離婚が認められない。しかも不貞をした側は再婚が認められない。そして離婚は宗務院法廷で実施すると聞いて、カレーニンの離婚の大変さが実感できた。アンナがヴロンスキーと結ばれるには、カレーニンの協力が不可欠、しかもカレーニンが不貞をしたことにしないといけない、というとんでもない事態が必要らしい。そしてロシアの貴族社会では、不貞は隠蔽されやすく、社交界では夫婦関係を破綻させない限り、多少の恋愛行為はOKとのこと。驚きとともにアンナの破滅的な行動が当時驚くべきだったことがわかる。これ物語の着地はどうするのか…
1投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語が進むにつれますます面白くなっていく! ただこの巻の終わりの方の登場人物の言動がイマイチ掴みきれず。何故あんな変化をしたのだろう。 ぐちゃぐちゃになっていく人もいれば、急に全てが上手く行き始める人も。これからどうなるかな。楽しみ。
1投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ23.2.14〜21 リョーヴィンとキティ、最高。ラブ。黒板のゲームみたいところ、読みながら泣きそうになった。 shut the fuck up when you hear love talkin'だと思った。それと、リョーヴィンの家のばあや。 カレーニンの俗物性。
0投稿日: 2023.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ第3部と第4部を収録。農業経営の理想に燃えるリョーヴィンと、妻の不貞行為に苦悩するカレーニンを描く。 第3部はほぼリョーヴィン編。農業の労働の描写は新鮮。いっぽうかなりのページ数が割かれる経営の話は1861年の農奴解放という背景からくる難しい状況があり、巻末の読書ガイドに頼らないとわかりづらい。しかしここで、欠点も多いが魅力的なリョーヴィンという人物像が明確になり、第4部に続く彼の新しい人生展開の伏線ともなるので、軽く読み飛ばさないほうがいいだろう。 第4部では妻に裏切られた夫カレーニンの、ある意味では当然とも思える反応に男性としては少し共感。さらに土壇場で、『戦争と平和』のアンドレイにも見られた、信仰と許しという至福の力による霊的な成長に感動。しかし、当時のロシア社会における「離婚」の難しさが事態を複雑にしており、ありえない展開に「これはひどい」と思わず声に出して言ってしまったところで2巻終了。どうなんねんこれ……。
1投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022年10月21日から。 14頁4行目「その多く他の社会活動家」は「その他多くの社会活動化」? 99頁11行目「神かけて誓ってみせたが」
0投稿日: 2022.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ髭を蓄えた世捨て人のようなトルストイがここまで繊細で機微ある愛を描けることに感嘆。特に13章のキティとリョーヴィンとの愛が通じ合う瞬間は、これまでのリョーヴィンの葛藤や苦悩や自尊心を深く描いただけに、何とも言えない感動を覚える。一方で寛容が破滅を呼び崩壊が自由をもたらすアンナとカレーニンのさまは面子を重んじる帝政ロシアの貴族社会の世相を映し出しているように感じる。
1投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
3部が300ページ 4部が200ページほどなんですが、 3部は… リョービンの農業への思いと、草刈り、 カレーニンの政治観ばかりで、まあちょっと大変だけれども、 これがあるがゆえの、後半4部のおもしろさ、エンタメぶりと言ったら!200ページの中にてんこ盛りのエピソードたち。 以下ネタバレ ・アンナ、あれほど約束したのに、家にブロンスキーを呼びつけ、カレーニンと鉢合わせ。 ・カレーニン、いよいよ弁護士の所へ。 ・カレーニン、早口でまくしたて、舌がもつれて「憔悴」を「そう……ひょう……そうすい」となってしまう ・ロシア一の伊達男(今は自分の口利きで、ボリショイバレエに入団させてやった、可愛いバレリーナちゃんにお熱)オブロンスキーのホームパーティーにおいて伏線の回収のごとく集められるキャラクターたち。え、キティちゃん来てたの? ・リョービンのキティ崇拝「これからはけっして人のことを悪く思わないように心がけますから!」 ・眠らないリョービンと、彼の黒日記? ・さて、ブロンスキーはリストカットさながらのレボルバー自殺未遂。 ・オブロンスキー、カレーニンを説き伏せたつもり?うまくやった。この出来事を謎掛けにしてまたパーティーで披露せねば✨ ・ヴロンスキー、友人の計らいでタシケントへの勤務を用意されたのに、アンナに一目あっただけで、退役してしまう。 など。 狂乱の日々でした。 私たちはいつになったらアンナの魅力に気づくことができるのかしら
2投稿日: 2021.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログとうとうヴロンスキーとの関係をカレーニンに打ち明けたアンナ。第2巻は離婚をめぐる双方の心の葛藤がえげつないほど緻密に描写されている。 カレーニンがアンナを許せないという気持ち、いや許せないどころか不幸にさせたい、不幸のどん底に落としてやりたいと憎悪するのは当然の感情だよね。離婚してあげたら彼女はヴロンスキーとくっつく。だったら絶対に離婚しない。歪な夫婦関係だけど、いやそれはもう夫婦と呼べる関係ではないね。 アンナもアンナで、カレーニンとは元々利害関係のみで結婚したようなものだったのを、ヴロンスキーと出会って愛してしまって一緒になりたい、でも息子のセリョージャは手放したくない。自分がどうしたいのか分からない、何も分からない、と身体ごと真っ二つに分裂してしまいそうな苦しみの渦中にいる。愛している、愛していない、そのことだけは明確であるはずなのに、それでも分からなくなってしまうんだ。不倫して間男の子を孕んだアンナは断じて被害者ではないけれど、「分からない」という言葉は紛れもなく悲鳴だった。 そして生死をさまよう難産、からのカレーニンの赦し、それを知ったヴロンスキーの絶望&別れ。しかし復縁そして出奔。いやとんでもないよこの人たち……。アンナにとっての幸せってなんなんだろう。 怒涛の展開を見せるアンナたちに比べて、リョーヴィンとキティのなんと可愛らしいことだろう。一度はリョーヴィンからの告白をすげなく断ったキティだったけれど、ドイツでの療養を経て彼のもつ魅力に気づくことができた。「ぼくには、何ひとつ、忘れることも、許すことも、ありません。ぼくは、ずっと、あなたが、好きでした」!!照れまくる二人にもうこっちがきゅんきゅんしちゃって赤面ものだよ。あーーリョーヴィンが喜んでて笑顔でいて幸せを手にしてくれたことがシンプルに嬉しい。
2投稿日: 2021.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ1巻に引き続き、引き込まれる展開であった。登場人物の考え方や気持ちの変化の模様を絶妙に表現している。また、貴族や官僚、農民などロシアの生活様式が興味深い。どの階級でも、夕食後にいろいろな活動をしていることは新たな発見であった。面白い。 「牛馬に引かせるプルークのほうが人の手でやる鋤よりもよく耕せるし、速耕機を使えば効率が上がるということは彼ら(農民)も心得ているのだが、いざとなると彼らはいずれの道具も使うわけにはいかなぬという理由を無数に見つけてくるのである」p268 「ロシアには素晴らしい土地があり、素晴らしい労働力がある。そして場合によっては、あの道中で立ち寄った農家のように、働く者と土地の力で大きな収穫を上げている。だがヨーロッパ流の資本投入をするならば、たいていの場合生産性は低い。それはひとえに、農民たちがひたすら自分たち固有のやり方で働くことを望み、またそのほうが成果が上がるからだ。こうした外国流への抵抗は単なる個別事例ではなくて一貫した、国民の精神に根ざした現象なのだ」p274 「「汝憎む者を愛せ」ドリーがつぶやいた。そんな教えは先刻承知だったが、この場合には当てはまりようがない。「自分を憎む者を愛するのは結構ですが、自分が憎む相手を愛することは不可能です」」p402
0投稿日: 2020.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
夫婦の問題が劇的に変わっていってる心模様が描かれているが、まぁ不倫とも言えるし、貴族階級の話はやはりどっぷりと浸かることができない。リョービンの想いが成就したのはよかったなと思う。
0投稿日: 2019.05.30リョーヴィンが主人公……?
お話としては(古典だし、ネタバレというほどでもないでしょうが)、 アンナとヴロンスキーとの破滅的な愛、という切り口がクローズアップされていますが。 実際に読んでいると、群像劇ともいえて、 特にアンナ×ヴロンスキーカップルから 多大に影響(被害?)を受けたキティ×リョーヴィン夫妻側のお話もとても面白いです。 領地管理、農作業への思いなどが、リョーヴィンの熱い思いが滴るようです。 またトルストイはひとつひとつのエピソードというか仔細な描写が面白く、 浮ついたように見える色男ヴロンスキーがだらしないところが大嫌いで結構なけちんぼで 「財布の洗濯」なる作業に勤しむ、なんて箇所は感心してしまいます。 古典は偉大だから面白い、というよりは 面白いものがぎゅうぎゅう詰まっているから、偉大なのだと思いました。 長いことは認めますが。
0投稿日: 2017.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログロシアの広大な自然も、貴族達の愛憎模様も、実に活き活きと描かれている。 アンナとリョーヴィンの、見事に対比されたダブルストーリー。 2人ともどこか「あやうさ」が漂い、見ていてハラハラしてしまう。 続刊もあっという間に読み終わってしまいそうである。
0投稿日: 2016.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの巻ではリョーヴィンが百姓と草刈りをする場面が1番好き。疲れと清々しさがよくわかる。 この巻の前半ではリョーヴィンの農業に対する考えや場面が展開され、その後はアンナの問題。 巻末のガイドでは、リョーヴィンの農業の話は退屈に思う人が多いようだと書かれていたけれど、私は退屈に思えなかった。 結婚や離婚の考え方が複雑。 アンナも今まで結婚生活についてはかわいそうだったので…というのを踏まえて、だからこうなっちゃったんだよ…みたいに読めばいいの? アンナ、どっちやねん!ってツッコミ入れたくなる。 時代背景がわかれば、こういう複雑なことが起こりうるということがわかりました。
0投稿日: 2016.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リョービンの充実っぷりとアンナ・ヴロンスキー両人の不貞の恋の行方が周辺人物を巻き込み詳細に描かれている。またアンナの言動に頭を悩ませるカレーニンの苦悩も手に取るように理解できた。にわかに風雲急を告げる予感がするか、どうなるかは三巻に期待。個人的には不器用ながら真面目なリョービンに好印象。
0投稿日: 2014.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログリョービンとアンナ。対照的な情景が描かれる。 「恋愛の魔法」にかかったリョービン。それまで無意味だと感じ、憎み、嫌い、軽んじていた周りのあらゆるものが光り輝く描写は微笑ましい。 アンナを知ろうとせず、アンナからは憎まれた夫カレーニンに起こった「赦しの愛」。 ――私を憎む相手を愛することはできるかもしれませんが、私が憎む相手を愛することはできません―― 理性でこう答えたカレーニンが、アンナを「愛した」瞬間は、描写されていない。 「汝の敵を愛せよ」「右の頬を打たれたら左の頬も打たれよ」という、理解に苦しむキリスト教の教義と同様、頭で理解するものではなく、心でしか感じられないものだからなのだろう。 リョービンは死にゆく兄の姿を見て人生の無意味さについて考え、自分の本当の気持ちに気づく。 カレーニンは死にゆくアンナにほんのわずかだが同情し、初めてアンナの気持ちに気づく。 リョービンとニコライ、リョービンとキティ、アンナとカレーニンの会話は言葉ではなく魂で伝わり、ロシアの改革者、学者と農民の会話は、結局のところ「伝わらない」言葉の繰り返しに終わる。 言葉という不確かなコミュニケーション手段しか持たない人間が、それでも言葉を使って互いを理解しようとする物語。
0投稿日: 2014.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアンナの物語とリョービンの物語が好対照。 アンナの物語よりもリョービンの物語のが好きだけど、農業については良くわからない……。 「読書ガイド」を読み飛ばしてしまっているのが原因だとは分かっているけど、読み始めた勢いを削ぎたくないんだよなー……。 カレーニンのように自分の感情を素直に表せない人もいれば、オブロンスキーのように極めて自然体で上手に人と付き合える人もいる。 人生これからだ!な弟と人生これまでだ……な兄の対照や、人を愛することで明るい方へ行けるキティと愛することでどんどん苦しくなるアンナの対照が面白い。 (簡単に二項対立の構図にしてしまうと浅い読みになってしまうけど、楽しんで読むんならこれが一番わかりやすい、と思う) 色々な人がいて、それぞれがいきいきとしているのは凄いなあ。 カレーニンが善玉になってしまって、これからますますアンナとヴロンスキーの物語を読むのがつらくなってくるぞ。 これでようやく半分か!
0投稿日: 2014.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめはこのページの多さに辟易しちゃう。 でもいったん読み始めてしまうと そのコメントはどこへやら、になっちゃう不思議さ。 扱っている世界が社交界という 貴族の世界なのもやはり惹かれる理由かな。 普通では体感できない世界というのが。 私はメインのアンナよりも 不器用で、時に意見を言うときにも 何かと後悔ばっかりしている リョーヴィンが好きです。 農業経験のある私は この描写は全然退屈じゃなかったなぁ。 人によっては退屈かなぁ。
0投稿日: 2013.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本作に主人公は二人存在しているのだと気付く。一人は煌びやかな社交界に身を置き高名な夫を持ちながらも、ヴロンスキーとの情愛によって身を落としていくアンナ。もう一人は地方地主ながら都会の公爵とも繋がりを持ち、そこの娘キティに恋焦がれながら農場経営の改革に頭を巡らすリョーヴィン。この二人が直接出会う事はないものの、対照的な両者を描くことによって当時のロシアの全景を描き出すことに成功している。特にリョーヴィンの「ロシアには労働者の問題なんてありえない。あるのは働く農民と土地との関係の問題さ」という言葉は象徴的だ。
0投稿日: 2013.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ官僚的な夫の態度に苦悩しつつ、アンナはヴロンスキーとの愛にますます傾倒していく・・・。 むむむ? てっきり、ヴロンスキーとの恋に悩みつつ、高潔かつ清らかさを失わない人妻が描かれるものと思っていた私としては、この巻でのアンナの描かれ方が意外であった。 アンナの心理がさっぱりわからないのである。彼女の場面場面の恐怖や戸惑い、自分の立場に悩む姿は非常に丁寧に描写してあって、そのときどきでは共感するのだが、いざ行動というときになると、なぜそうなったのかさっぱりわからない。臨場感がすごくあるのに、説明に納得いかないのである。 なので、なぜそこまで彼女がムキになって、果てはあてつけとも取れる夫への怒りへと走るのか、読んでいてこちらが戸惑ってしまう。 あまりにアンナの行動が唐突なので、彼女よりもむしろ彼女がなじる夫のカレーニンのほうに同情してしまう始末だ。 しかし文章は相変わらず読みやすくて素晴らしい。 アンナとヴロンスキーが、自分たちの状況に苦悩しながらも、その状況がにっちもさっちもいかないために、何か突然奇跡のようなことが起こって、自分たちをこの状況から解放してくれるのではないか・・・なんて考えているところなどは、読んでいて「うわー、わかる」と頷いていた。 (なのにその心理がアンナの行動に繋がらない気がするから、変な気がしてしまうのだけど・・・)。 アンナがこのまま行くとなると、ちょっと苦しいなぁ、と思いつつ読了。 それにしても、リョーヴィンのプロポーズは可愛すぎて、読んでいるとき思わず顔が「ふふふ」と笑ってしまいましたよ。。
1投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログアンナ編とリョーヴィン編に好みが分かれそうな二冊目。 リョーヴィンの議論大会ぶりは確かに途中飽きかけたけど。 学校教育の是非がさんざん議論されていた当時、日本では寺子屋が当たり前のようにあったわけで、日本って立派な国だわとつくづく思いました。 ただキティの出番が少なくて物足りなかった。 彼女の心情描写がほとんどないまま終わり、えーっ。 三冊目に期待するとしましょう。
0投稿日: 2009.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ後書きに書かれていた通り、リョービンの農場経営の話がつまらなすぎてそこで一ヶ月くらい停滞してしまった。苦笑 アンナをめぐる修羅場はすごく楽しいんだけどね。 あ、でもリョービンはキティと愛を取り戻せてよかったね…頭文字で会話するのはちょっと笑ってしまったけど。キティにリョービンが自分の記録を見せる場面は、すごく自分に重ねて読んでしまった。 結局アンナは離婚せずにヴロンスキーとの逃避行を選ぶらしいが…んーどうなることやら。これはハッピーエンドはありえないでしょう。
0投稿日: 2009.01.17
