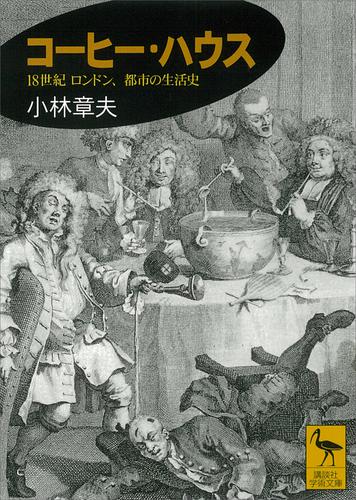
総合評価
(15件)| 0 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ色んな立場の人間が入り混じってた頃の辺りの描写好きだな。説明解説を書きながら要所に、当時の状況が頭に浮かぶような会話だったり情景描写を混ぜ込んでて読みやすかった。
0投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログコーヒーハウス。店には美しい女店員がいて、店を明るい感じにしている。それら美人が愛嬌のある眼差しで、タバコの煙に満ちた店内に誘い込む。空いてる席があればどこでも座ってもいい。大きなテーブルが一つあり、そこでいろいろな話題について議論している。あちこちのテーブルには官報や新聞、雑誌などが置かれて客の用に供されている。字の読めない人のために、読んで聞かせている人もいる(当時、新聞や雑誌で情報を得る場所はコーヒーハウスなどに限られていた)。壁には、盗品を見つけた人への報酬を描いた広告、実母を探す男の広告、逃亡奴隷の捜索依頼などが貼られている。p.40 初期のコーヒーハウスでは、身分・職業・上下貴賎の区別なく、ぼろを着た人も、流行の衣装を着たおしゃれな男も、誰でも店に出入りできる人間のるつぼだった。怪しげな人間が数多く出没する場所でもあった。p.36 男性客のみ出入りでき、女性客は出入り禁止だった。p.41 賭博や喧嘩、宗教問題を議論することを禁止して罰金をとるコーヒーハウスもあった。p.41 コーヒーが二日酔いの特効薬とされたこともあり、ほとんどのコーヒーハウスはアルコールを出さなかった。p.37 トーリー系のコーヒーハウス、ホイッグ系のコーヒーハウスがあった。p.117 ***** 1554年、イスタンブールに世界初のコーヒーハウスが開店。1650年、オックスフォード東部の聖ペテロ教区で、イギリス初のコーヒーハウスをユダヤ人のジェイコブという人が作る。1655年、オックスフォードにティリヤード・コーヒーハウスが開店。王党派の学生たちのたまり場として栄える。1670年代、夕方5時になるとコーヒーハウスに多くの学生が集まった。たむろして駄弁ってばかりいると真面目な学問が衰えると批判が起こった。1675年、チャールズ2は、コーヒーハウスで人々が国王の政策を非難しているとして閉鎖を命じた(多くの抵抗にあってすぐに撤回された)。1688年頃、ロイズ・コーヒーハウスがロンドンで開店。海上保険を担うように。
0投稿日: 2024.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ拾い読み。保険ってコーヒーハウスから始まってるんだ。郵便との関係も深い。戸別配達はまだ確立しておらず宿屋やコーヒーハウスが留め置き場所になってる。 コーヒーハウスが果たした役割も衰退していった理由もそれぞれ面白かった。
2投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者、小年林章夫さん、どのような方かというと、ウィキペディアには次のように書かれています。 小林 章夫(こばやし あきお、1949年12月29日 - 2021年8月5日)は、英文学者、英国文化研究家、上智大学名誉教授。 2021年8月5日、心不全のため死去。71歳没。 著者のことは知らなかったのですが、訃報を見て、『コーヒー・ハウス』を手にしました。 この本は、原本が1984年に刊行されたので、著者が35歳位の時に書かれたものになります。 この本に内容は、次のとおり。(コピペです) 十七世紀半ばから一世紀余にわたり繁栄を見せた欧州カフェ文化の先駆、コーヒー・ハウス。そこは政治議論や経済活動の拠点であると同時に、文学者たちが集い、ジャーナリズムを育んだ場として英国に多大な影響を与えた、社会の情報基地でもあった。近代都市・ロンドンを舞台にした、胡乱で活力にみちた人間模様と、市民の日常生活を活写する。 この本は、拾い読みにて読了としました。
10投稿日: 2021.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログコーヒーハウスには身分職業上下貴戝の区別なく誰でも見せに出入りすることができた。いわば人間のるつぼ 政治、文学、経済の話、科学実験などが行われた 17世紀のイギリスでは限られた場所でしか、情報、ニュースを得ることができなかった そんな中でそれをまとめるジャーナリズムが生まれた なぜコーヒーハウスではいろんなジャンルの議論が活発に行われていたのだろうか? とにかく様々なバックグラウンドを持った人が集まってる場所に、少しお金を払えばアクセルできて直接話ができるわけだから、単純に好奇心が掻き立てられて活発な議論が行われたのでは? 著名人と話ができる可能性もあるし。 現代でそう言った環境ってある?少なくとも今の喫茶店にはない。 スナックは若干そういう性質があるかも?
1投稿日: 2021.08.25文学、文芸史が主題かも
ブリテンといえば紅茶の国という印象はあるが、そうなったのは19世紀以降にすぎない。本書では「紅茶の国」になる前の17、18世紀に興隆したコーヒーハウスが扱われている。 第1、2章でコーヒーハウスの勃興と流行店の入れ替わりを描き、第3章でコーヒーハウスを舞台とした文人、才子らの言論空間の変化を扱っている。あくまで主題はコーヒーではなく、コーヒーハウスと文学、文芸となっている。どちらかといえば著者の書きたかったのは第3章という印象。また最後の方でコーヒーハウスの衰退についても説明はしているものの、要因をいくつか挙げているだけで駆け足という印象はぬぐえない。コーヒーハウスの衰退については詳しく知るためには、紅茶なり、パブなり、別のテーマの文献を読む必要があろう。
0投稿日: 2016.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
イギリス社会の発展においてコーヒー・ハウスが果たした役割について概略的に紹介している本。もう少し掘り下げて紹介してほしいかな、と感じる部分も何か所かあったけど、総じて読みやすく、18世紀以降の流れを知るには有益だと思います。 コーヒー・ハウスが保険業や郵便業の拠点となったというのは他の本でも読んだことがあったけど、ジャーナリズムの一つとして雑誌もコーヒー・ハウスを軸に発展したというのが個人的には新しいポイントでした。考えてみたら、報道機関としての新聞がここを拠点とした以上、同じ紙媒体である雑誌も影響を受けていない訳がないんだけど、それが自分の中では繋がっていなかったので、この本できちんと整理できた感じです。 さらに、所期の作家たちの作品発表の場としても機能していたということを知り、イギリスの社交と文字文化が発展するにあたって不可欠な場所であったことが分かりました。後半、若干息切れしている感も否めませんが、読んで損はない。
1投稿日: 2015.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスと言えば紅茶のイメージしかなかったのだが、 コーヒーが流行っていた時期もあったのだなぁ。 その裏には文化、政治、はては植民地までもつながっているのが興味深い。
1投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
○17世紀半ばから18世紀半ばのイギリスで流行したコーヒー・ハウス(喫茶店の前身)。人やモノ、そして情報の集まる拠点として機能し、それが衰退(変質)してゆくまでにどのような経緯があったのか。コーヒー・ハウスの社会的な役割を捉える面白い一冊です。 ○コーヒー・ハウスはコーヒーの流入と合わせて17世紀半ばのイギリスに登場しますが、こんにちの喫茶店と異なるのは、人や情報の集まる社会の拠点だったということです。もちろん仕事や娯楽(会話)の場という今日的な空間でもありましたが、そこは、才人が集まって議論を交わす政治、経済、文学の拠点であり、当時最新の情報が集まる場だったといいます(ちなみに、エドワード・ロイドがつくった商取引・情報やジャーナリズムの拠点としてのコーヒー・ハウスの延長線上に、保険会社のロイズが誕生する)。この本は、コーヒー・ハウスがイギリスに登場し、そのような拠点としての性格をもって政論や職業などによって分化するようになり、やがて19世紀に入ってその性格を失ってゆくという経緯、つまり「コーヒー・ハウスという場所」の性質が変化してゆく様子を、イギリスの歴史のなかから描き出しています。 ○コーヒー・ハウスは政治や文学の議論の場としての色彩が色濃かったため、ときには政府が密偵を送り込んで、反乱分子の動向を確かめていたそうです。そうした議論の場としてのコーヒー・ハウスがやがて衰退し、トランプゲームなどの娯楽にふける人達だけが残ってしまうという話のは、コーヒー・ハウスの大衆化といえるのかもしれません。しかし、もともとコーヒー・ハウスは”人間のるつぼ”、暇をつぶす人や、商談に使う人、さらには恋人を募る人やうさんくさい藪医者が出入りしていた場所でもありました。そう考えると、コーヒー・ハウスという場所がどのように変質していったのかということが気になります。 ○すこし読み進めづらい感じだという印象をうけたので、ぼくのおすすめの読み方は、内容全体が見事に要約された262ページで全体を押さえて、そこから全体を通読するという読み方です。
0投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ18世紀のロンドンで流行したコーヒーハウスは、ただコーヒーを飲むだけの場所ではない。様々な人が集い、議論するこの場所で、ジャーナリズムや文学が育った。保険や郵便のシステムも。 難しくはないのに知的好奇心がくすぐられ、満たされた、心に残っている本です。大学時代の最初の一冊。
1投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は1949年生まれ。専門はイギリス文学、文化。本著は1984年に刊行されたものが2000年に学術文庫として出版されたもの。
0投稿日: 2012.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ注目した点はおもしろく、網羅的。当時の書物からの引用が多く、時代の雰囲気を少し味わうことができる。ただ、それぞれの項目において、コーヒーハウスとの関わりを深く分析してほしかった。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリス好きのオーナーがやるカフェということでロンドンでの「コーヒー・ハウス」の勉強をしてみました。「コーヒー・ハウス」は、17世紀ロンドンで広がり、文化、政治、経済と様々な分野に影響を与えました。現代のカフェが、どのような役割を果たしていくのか。ちょっと考えるきっかけにしましした。
0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログざっと読んだ、又読んだら感想がかわるかもしれないけど、 嗜好品は高級品だってのがものの基本、コーヒーだろうと紅茶だろうとチョコレートだろうと、やはりお金が絡んでくる。 紅茶の本読んだ時もそうだけど嗜好飲料系、結構、お酒との対比が描かれる事が多い、 安酒が流行った歴史がある場所だととくに。
0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ17〜18世紀のわずか100年の間に、コーヒーハウスがメディアをいかに進化させたかを研究した論文。まだ情報の媒介が「人づて」であった頃のメディア論であり、王政復古前後のイギリスの動静を描く歴史論でもある。 テーマが硬い割に読みやすいが、もう少し読者を引き込む工夫がほしい。範囲を拡幅して、革命の流れとコーヒーハウスにおける物語を組み込めば、一般に読み物として受け入れられ得るだろうが、それは著者の意図するところでないかもしれない。
0投稿日: 2011.03.24
