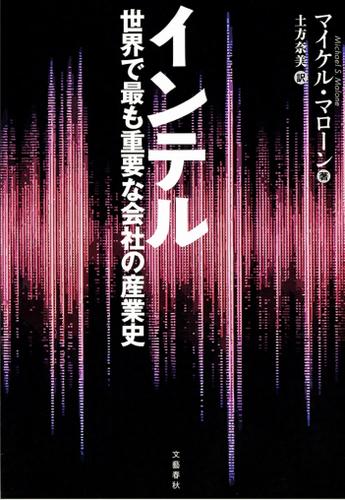
総合評価
(10件)| 1 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログp169 シャープの佐々木正 ボブの椅子を崇拝 p172 ビジコン 嶋正利 p278 マイクロプロセッサ4004の開発者 テッド=ホフ、フェデリコ=ファジン、スタン=メイザー、嶋正利 ファジン、嶋はザイログへ 集積回路 ノイスとキルビー トランジスタ バーディーン、ブラッテン、ショックレー
0投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ産業に史上最も重要な変化を与えたインテルの物語。ノイス、ムーア、グローブという3人の個性が織りあって経営が進められていくが、それぞれは偉大ではあるが不完全な特徴もあり、マイクロプロセッサにしても偶然の要素が強く働いていることが興味深い。ただ、その偶然を掴み取り、実現するところに経営としての実力があるのか、と推察。
0投稿日: 2021.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間つぶしの読み物としては、面白いしボリュームもあるのでちょうどよい。 なにか学ぶことがあるかといえばそんなにないかもしれない。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ急に半導体に興味を持ったので、業界を代表する会社の歴史を知りたくて読んでみた。これだけの会社だから、創業以来いろんなドラマがあるのは当たり前だし、その意味で特に関心も失望もなし。 奢れるものは久しからず、PCが明らかに衰退期に入り、替わって台頭してきたモバイル端末でARMコアやクアルコムに出遅れたインテルが巻き返しを図れるのか、むしろ今後の方が注目される。
0投稿日: 2018.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読了。昔、「アップル」を読んだことがあるが、それに比べると非常に読みやすかった。しかし、500ページを越えるボリュームは、読むのにエネルギーを要した。自分の1ヶ月に掛ける読書力の大半を必要とした。 終戦間際からの話があり、壮大なエレクトロニクスの話であった。パソコンの心臓部CPUを独占して作った会社である。自分たちの生活(携帯を含むあらゆる家電)に大きくかかわりのあったことだったと再認識させられた。原題は、「インテル トリニティ」である。トリニティは三位一体という意味で、3人の創業者のことである。創業者は、以下である。 ロバート・ノイス(ノーベル物理学賞受賞者営業担当) ゴードン・ムーア (ムーアの法則 提唱博士 技術担当)アンディ・グローブ(ホロコーストサバイバー 実務責任者) カッコに思い付く肩書きをいれてみたが、本書を読むとそれ以上の役割を感じると思う。帯文に「全管理職必読!」とあった。平社員であるが、読んでみた。仕事の悩み解決方法は、なかった。今が絶頂期の会社であれば、ソリューションがいくつもちりばめられ、気持ち良く、読み終えたと思う。しかしどこの会社もそうであるが、いつまでも君臨できる訳ではなさそうである。さて普通のサラリーマンはどうしていくかなと、考えてしまう。
0投稿日: 2017.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ文字量が多かったのでさらさらーと。 読み応えがあって、物語として面白い産業史だったが、 その中に「日米半導体戦争」が書かれていてすこし驚く。 日本企業が半導体戦争で負けた原因の一つは 「きわめて短い時間軸で働いていたこと」。 これは、今の日本社会全体に当てはまりますね。
0投稿日: 2016.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界で最も価値のある企業のひとつであるインテルの、創業から現在での企業史。 三人の創業者が創りだす「インテル・トリニティ」が、いかに同社の成長に大きく関わっているのかが細やかに書かれている。 ITに詳しくなくても、インテルがどのような理念を持って邁進してきたか、世界で最も価値のある企業は何を重視してきたのかを読むことで、学べるものは非常に多いと感じた。 創業者の一人で三代目CEOのグローブが著した「インテル経営の秘密」も読んでみた方が良さそうだ。
0投稿日: 2016.02.24私がこの1~2年の間に読んだ本の中では最高の本でした。
「インテル、はいってる」のキャッチフレーズが有名なインテル。 私がパソコンに触り始めたばかりの頃(その頃はCPUとメモリとハードディスクの区別もついていなくて、パソコンの速度を上げるためにハードディスクのデータを消そうとしたこともありました(焦))、ペンティアムというCPUの名前を頻繁に聞くと同時に、その評判やカタログスペック、ペンティアム搭載のパソコンにはなかなか「いい値段」がついていたことなどから、「ペンティアムは超高級なブランド」というイメージを刷り込まれました。 そんなペンティアムを製造している会社が、インテルという名のアメリカの会社だと知ったのはずっと後になってから。今使っているパソコンにも当然のようにインテルのCPU(今はCore i7 とか Core i5 というブランド名ですが)が使われていて日々お世話になっているものの、そういえばインテルのこと何も知らないな…と本書を手に取ってみたのですが…この本はすごいです。 日本の戦後の産業史や、ソニーやホンダを始めとする戦後誕生して世界的なブランドにまで育った会社の歴史を御存知の方は多いと思いますが、同じ時期のアメリカの産業界や企業の歴史をご存知の方はそれに比べれば少ないだろうと思います。インテルはシリコンバレーに誕生した半導体メーカーです。本書を通して、インテルの歴史はもちろんのこと、その周囲にあるシリコンバレーの歴史やアメリカ半導体産業の歴史、日本との関わり、さらに半導体の進化の歴史を知ることができます。知的好奇心が刺激され、またソニー発展の歴史を知った時と同じような感動もあり、私がこの1~2年の間に読んだ本の中では最高の本でした。 ちなみに相当分量が多いです。 登場人物や企業も多いため、「この人、誰だっけ?」ということもよくありました。 また時々ですが「SRAM」「DRAM」「RISC」「CISC」のような技術用語も出てくるので、これもまた「これ何だっけ?」と思ってGoogleで調べてメモしておくことが何度かありました。 手元にメモ帳とペンを用意して、腰を据えて、じっくり読むことをお薦めしたいです。 繰り返しになってしまいますが、本当にそれだけの価値がある本です。
3投稿日: 2016.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログロバート・ノイス初めて知りました。 ムーアの法則がいかに生まれたか。グローブ含めた3人の歴史。 人間関係と経営。 気にする必要あるのか、ないのか…
0投稿日: 2016.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み応えあります。8080とか、8086とか、中学生の時のintelはそれほど大きな会社ではなく、zilogや68000、6809みたいな石がどんな立ち位置だったのか?というのが説明されていきます。ロバート・ノイスのことは全く知らなかった。
0投稿日: 2015.12.13
