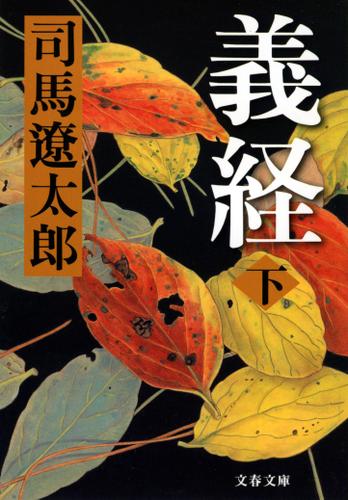
総合評価
(94件)| 18 | ||
| 45 | ||
| 23 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ源義経の強さは弱さでもある。報連相の大切さ。上司の背景の理解の大切さに気づかさせれる。 義経の最期はとても哀しい。 韓信を彷彿とさせる。 敵がいるうちは華。敵を倒した後には味方との闘い。世の中の複雑さに気づける。
0投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログまず、歴史の知識が皆無の人間が書いていることをご承知おきください。 義経、頼朝、弁慶、壇ノ浦の戦い、単語は知っているけど単語しか知らないという状態で読みました。 ところどころで関連書物を引用していると思われる部分があり、事実と司馬遼太郎さんの空想が入り混じって描かれた世界なのだと思います。 表現力巧みな上一人一人のキャラクター設定が緻密で物語の中に引き込まれます。 また、出来事が一通り書かれた後につまりは〜ということである。というような要約もあり無知な私でも物語のスピードに置いていかれることはありませんでした。 上辺だけを知っている私は様々なところで衝撃を受け、また義経がこれほどに人懐っこく愛嬌のある人間だとは思いもせず、最後まで心がギュッと動かされました。 司馬遼太郎さんの作品を初めて読みましたが、面白い、面白すぎる。これからたくさん読み漁ることにします。
6投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
政治が苦手 血縁を重んじる 女好き お洒落 涙脆い 生涯を通じて そのキャラクターはブレないように 描かれていたけども 義経を義経にしたのは 後世を生きる私たちなのかも 不遇な運命に 作用した人物は描かれていた 最後、どんな思いで死んでいったのか 読みたかったな
0投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ平安時代末期から鎌倉時代初期が舞台です。 源義経が主人公ですが、色んな人の視点から物語が語られます。 1,000ページに迫る大作でした。 馬鹿と天才は紙一重といいますが、義経はその両方だったのかもしれません。
0投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ痛恨のミスで、まさかの下巻から読んでしまった。 元々義経は興味があったので、深く知れて良かったけど、頼朝と後鳥羽が大嫌いになった。当時の歴史観から致し方なしとも思いつつ、不愉快な奴らだ。 これから上巻を読む憂よ…
1投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2冊合わせて900ページ弱の超大作。歴史上でも指折りの悲劇のヒーロー、源義経。その半生を司馬遼太郎節全開で描く。最近ではよくよく分かってきたことであるが、この作品を読む中では義経という人物はおよそ幼稚で政治感覚の優れなかった人物だったのだな、というのが分かる。ただ戦、という面においては圧倒的なセンスの持ち主で天才肌だったのだろう。それ故に兄の頼朝に疎まれて最終的には敵対するまでに至るのが寂しい。作品としては頼朝に弓を弾いてからはサクッと終わってしまうのでそこに至るまでの過程を楽しむ作品だったのだろう。
1投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがの司馬遼太郎。キャラが立っている。 義経だけでなく、すでに死んでいる登場人物すら、キャラが立っている。 義経は全然爽やかではないけど、一芸に秀でていて、それによって身を滅ぼす、という、すごいけどすごくないという感じが同情を誘うのかも。
0投稿日: 2024.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログついに義経さんの活躍が鮮やかに!と思いきや、彼の極端な性質によって、勝ちも勝ちではなくなってしまう。 なるほど、頼朝さんや後鳥羽様は本心のわかりにくい、というより本心を明らかにできない立場だけれども、それにしても2人に挟まれた義経さんが哀れだった。 でも、彼が謙虚であれば、まだなんとかなっただろうけど、傲岸なところがとても残念。まあそういう時代だったのだろうけど、とにかく残念で哀れなお話。 最後はあっさりしてしまっていたけど、顛末も哀れすぎるだろうから、これでよかったのかも。。 とにかく哀れ。ポジティブはどこに泣
1投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ歪な義経が次第に際立ってくる感じが、終幕の気配を掻き立てます。終わりの呆気なさは、伝聞物らしさが出ていいと思います。実は後白河法皇に支えられた物語だったのかも、と思って妙に納得しました。
0投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022/2/11読了 当時、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』もあって、タイムリーな内容であった。 司馬遼太郎は、物語の中で義経と頼朝の対立の原因を、義経の「空気読まない」具合と共に、都人と坂東武士の思考回路・価値基準の違いに帰していたが、大河では、純粋過ぎ、強過ぎる故に、却って周囲から怖れられ、疎まれ、やがて兄弟がすれ違っていく悲劇を描いていたように思う。――それにしても、菅田将暉の義経はクレイジーで素敵だった。 (どっちの感想だ?)
0投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログなんぼヒーローでも阿呆はあかんのやなと思った。どうやって義経が死ぬのか知らなかったのでサラリと書かれていたのが残念。
2投稿日: 2023.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ1000年経っても残る判官贔屓の言葉、その人物と影響力の大きさは、日本史上の傑出した人物の一人であることを理解することができた。
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経って不幸だなと思った。子供のまま大人になってしまった、その生い立ちも政治感覚の無さに関係してるんだろう。頼朝の考え方、葛藤もよく書けてるなーと思った。
0投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の舞台に華やかに登場する「源義経」の下巻。木曽義仲の討伐、平家一族を相手に「一の谷の合戦(鵯越)」「屋島の戦い(讃岐)」での奇襲戦法、潮流を逆手に取った「壇の浦の戦い」で大勝利に至るまでのくだりは、息を吞む間もない一気読みの痛快さ。 平家を討滅させた戦功が兄頼朝を狂喜させると信じた義経。その大功がかえって兄頼朝を戦慄恐怖させるとは思い至らず 「自分は鎌倉殿の弟である」の観念を拭えぬまま鎌倉幕府の露と消えた義経、朝廷安泰と称し、義仲、義経らを利用した後白河法皇の悪辣さに唖然・・・歴史の闇を知る。
3投稿日: 2022.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦での歴戦の雄でも思い浮かべられないような戦略と決断の早さ。一方で政治面の無知さや純粋さ幼さ。昔の英雄ならあたり前ではあっただろう好色さ。やはり切ない。追討の院宣が出て以降の最期は意外にシンプルに書かれているのが、多くのファンがいる義経への敬意なのかなと勝手に納得しました。
1投稿日: 2022.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説ってだいたい前半を苦労して読んで後半やっと面白くなっていく印象がある。 だけど本作は初っ端から面白い。どんどん読める。義経の生い立ちからしてドラマチックだからかな。 むしろ後半の死の予感が辛くて壇ノ浦あたりから読む気力がなくなっていってしまう。 死ぬ時(エンディング)があっさり過ぎて取り残された感じの読了感だった。 2つの視点から見て面白かった。 一つは歴史的考察。 朝廷という古くからの権威に対して新興の武家勢力。 義経はある意味両勢力に踊らされて犠牲になったと言える。 奥州、板東、京都の勢力図も勉強になる。 二つめは義経という日本人が大好きなキャラクターの魅力。 中性的で色白の小兵というルックスでありながら戦の天才というギャップ。しかも大の女好き(というかシモ半身が奔放w)という。 マンガキャラ的要素満載で、これは愛されてきた理由がわかる。だからこそ夭折がつらい。 派手に咲いて一瞬で散っていく。ロックスターみたいな感じかな。 R.I.P
1投稿日: 2022.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の頃、日本昔ばなしの「牛若丸」を観て以来の「判官びいき」です。 今回、司馬遼太郎さんの作品を読んでみて、源氏と平氏の争いと言うよりは、源頼朝と後白河法皇の争いと言う印象を強く持ちました。 今、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を毎週見ていることもあって大変興味深く読むことができました。
1投稿日: 2022.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経が一ノ谷の戦いで鵯越の逆落としをやった際に文中で「人よりも百倍臆病であるとすれば、百倍勇気を奮い立たせればいいではないか」という表現がとても人間味に溢れていて好きだ。 いくら奇襲だとしても、崖を目の前に馬に乗りながら駆け下りるなんて相当怖いだろう。 当時、就職の面接を控えていてこの言葉に勇気を貰った記憶がある。
0投稿日: 2022.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ源義経の生涯を描く司馬遼太郎の上下2巻の歴史小説。数奇な義経の生涯を司馬遼太郎が料理し、一流のエンタメ小説に仕上げたという印象です。ブックオフの110円コーナーで見つけ、何気なく読み始めたらやめられなくなりました。 義経の平家に対する怨み、一ノ谷、屋島、壇ノ浦の戦いで見せる天才的戦術、後白河院に弄ばれる幼稚さ、痴呆な政治的無感覚者ぶり、すでに危険視されている頼朝への思慕がテンポ良く描かれます。もちろん、日本人として義経の生涯を知っていますが、それでも司馬遼太郎の軽快な文章によって義経を身近に感じることができました。一方、戦術家としての義経の歴史的意義等にも触れられ、単なる歴史小説として終わっていません。 本当に面白い歴史小説。「鎌倉殿の13人」の菅田将暉は本書の義経に近いと思います。
6投稿日: 2022.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻でついに義経登場!という感じです。 天才的戦術で勝ち誇っていくたびに、その後訪れる悲劇の種が何度も何度も描かれ、壇ノ浦のところでは「この戦を読み終えたら悲劇しかないー!」と思ってなかなか読み進められなかった思い出です。笑 ですが悲劇の種が描かれていたからこそ、その悲しみを受け止められたかなと思います。 最後はあっさりした終わり方ではありましたが、読みごたえはじゅうぶんにあります。
2投稿日: 2022.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログいやー面白い! こんな天才的な人物ひどく惜しい。 が政治的能力がまるでないので頼朝に嫌われるのも仕方ないかな。 つい義経目線で読むので頼朝を憎みそうになるけど。 大河ドラマ、今後の展開楽しみ!
8投稿日: 2022.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大河ドラマ観てるので、源平合戦あたりの様子を知るために母の蔵書より。 義経は大河ドラマのキャラと通じる感じ。 戦は天才肌だけど、政治感覚皆無で感情的なダメなやつ。でも幼少期の境遇を考えると… ただ肉親(頼朝)に愛されたかっただけなのかなぁと同情しつつもキャラとしては好きにはなれませんでした。 かと言って頼朝も…好きになれないし仲間内で敵対する梶原景時も嫌い。 義経の郎党たちとか、敵の平維盛とかサブサブキャラが魅力的だったかな。 あと頼朝鎌倉から動かないし平家倒すのに何にもしてなくない??と思っちゃった… 大将ってそんなものなのかしら。 全体通して倫理観、法律とかもない時代だからみんな自分勝手で野蛮…性に奔放な時代だなぁという印象。。 司馬さんの作品で戦国時代より前の作品は初めて読んだので面食らいつつも著者安定の面白さで読了
0投稿日: 2022.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦の天才は平家を滅亡させて京へ凱旋する。この単純な思考を持つ天才は、なぜ頼朝が上洛しないのか?を理解することは生涯なかった。相手の立場を理解せずただ自分を見て欲しいとせがむ純粋さが悲哀。 奥州への都落のシーン、弁慶との逸話などが書かれていない。何故?あっさり終わる理由とは?謎に包まれた下巻である。
0投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ遮那王がただひたすらに法と秩序の名を冠した獣の顎の下で時を過ごし・待ち・窺い続けたのが上巻ならば、あとはもう楔から解かれた猟犬の如くそれら獣が老いさばらえたのを目敏く見抜き、喉元に食らいつき、そして"役"を勤め上げて煮らるるのが下巻 といった具合だろうか。そんな所感
0投稿日: 2021.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代人がイメージする主従関係、戦術、戦略は、戦国時代のもので、平安末期、鎌倉時代のそれは非常に淡白であるけとがよくわかった。 結局、最後まで頼朝の考えを理解できなかった義経。 天才でありながら、鈍感。登場、活躍、栄華、没落が一生のなかで如実に分かれ、最後は悲しみを抱えながら、消えていく。 作中にもあるように人々を惹きつける魅力が義経には揃っている。 まさに、諸行無常を体現する人物。 欲を言えば、義経が平泉で滅亡するまでを詳細に描いてほしかった。それにしても、頼朝、戦に行かなすぎ。
0投稿日: 2020.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人ならほとんどの人が知ってるであろう義経。 日本人の義経像の形成にもかなりの影響を及ぼしたであろう小説。 意外にも講談や多くの物語で取り上げられてい弁慶との逸話や、奥州落ちの物語が欠落して、最後はアッサリ終わっている。何かしらの意図があるのかな。 いくらでも大冊にできたであろうに、文庫二冊に納めている。もっと書き込んで欲しい部分もあった。
1投稿日: 2020.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後に、「悪とは、なんだろう」とあるが、本当になんだろうか。戦功があるから輝いて見えていただけで、それがなければダメ男。あまり魅力を感じなかった。かといって、法皇のように義経を愉しめるわけでもなく。こういう男性が身近にいたら厄介だろうなあと思った。別の角度から見たら魅力的に映るのだろうか。
0投稿日: 2020.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「国盗り物語」から司馬遼太郎さんの作品を読み始め、二作目です。 相変わらず、作者の知識量のすごさに圧倒されます。 日本史史上で珍しい「騎馬隊」を用いた武将で、とってもかっこいいです。そして、愛されるキャラクターでもあります。それ故に、頼朝に追われることになるのですが、、、 義経の結末は有名なだけに、読み進めていくことが少し辛くなっていきました。
0投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
義経への解釈が、私のイメージに近くてよかった。 周囲に鈍感で生意気に見える戦の天才…みたいな。 民衆からみれば判官贔屓や伝説が生まれるような、魅力的な人物なのだと思うけど、 敵味方から見ると、「何をしでかすかわからないヤバいやつ」「イレギュラー」と言いたくなるような…そんな人物な気がする。 革新的な戦法は今でこそ当たり前だけど、当時は掟破りのルール違反。誇りやタブーを気にしない革新的な戦法。 兄に認められたいが、まるで兄のことがわかっていない。嫌われることばかりやる。 陰謀渦巻く時代において、あまりにもピュアな人物だったのでは。政治がわからないってそういうことかなと思いました。 司馬先生といえば資料だし、現実的に見た義経像なんじゃないかな。 それにしても司馬先生は戦国時代以前は苦手なのかな…と感じます…。キレがない…。
0投稿日: 2020.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ私がこれまで描いていた義経像とは、まったく違う義経が描かれており新鮮で面白かったです。 子供のまま成人になってしまい哀れに感じるほど政治感覚がない本書での義経は、うっすら記憶に残っている大河ドラマの義経とはかけ離れていました。 この本から、周りの反応がおかしいなと感じたら、直す直さないは別にして自分の行動を反省するのは重要なことだと再認識しました。
0投稿日: 2018.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都生まれだからか牛若丸は馴染みと親しみがあり、なんとなくな感じで好きだった。改めて歴史を知ることで京都人の判官贔屓が理解できたことでその根拠が解った気がした。 義経の“青さ”と“不器用な実直さ”は魅力でもあり、それに弁慶たちも京都人もそして私も引き込まれたんだろう。 また昔は弁慶は強いとの印象があったが、ただの強さではなく父親のような温かな強さであったと改めて感じた。
1投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経を評して「政治的痴呆」という形容が数限りなく出てきて可哀想な位だが、政治のみに長けた新宮行家よりは断然カッコいい。 地元唐津は義経とは何の関係もないが、唐津くんち四番曳山が「源義経の兜」な位ずっと義経が愛されてる「判官贔屓」の由来を、Wikipediaは「北条執権政治を正当化するために書かれた吾妻鏡による情報操作」として解説している。 義経は合戦の天才か?という点については、典型的な選択バイアスとも思えるが、伝説はとうの昔に完成しており、義経は永遠に英雄だ。
0投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ義仲の滅亡から一ノ谷、矢島、壇ノ浦の戦いを経て義経の滅亡までを描く下巻。義経の戦における才能と裏腹に政治的才能も情勢を見極める事ができる家臣もなく、やがて落ちぶれていく過程が上手く描かれている。物語のきっかけとなる政治家の行家とうまく折り合えばと考えるが、それにしても歴史というものは際どい所で成り立っているものか。 終盤はかなり急ぎ足で締めくくっており、その後の頼朝の状況や義経の敗走のエピソード、安宅の関での弁慶との勧進帳の逸話も触れることなし。弁慶は出会いこそ劇的に描かれているが活躍の場があまりなく残念。 法王のあまりの俗人的なところは宮内庁あたりから文句が出そうな描かれ方で、ある意味人間臭さがあり面白い。 ともあれ、物語としてとても面白かった。
2投稿日: 2017.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ異文化コミュニケーション、だと感じた。頼朝と義経は。 言葉は意味をなさなかったのだ。いや、「心を伝える」という機能は、この物語においては求められなかったのだ。求められたのは、何かしらの企図を構築するブロックとしての役割だった。 ---------- 2017_013【読了メモ】(170617 6:27)司馬遼太郎『義経』下巻/文春文庫/978-4-16-766312-4
0投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ機動戦士ガンダム。アムロ・レイ。zガンダム。カミーユ・ビダン。シャア・アズナブル。 うーん。彼らの原型が、「源九郎義経」だったとは。 ガンダムファン、必見、必読の作品だと思いました。 # 司馬遼太郎さん「義経」(文春文庫、上下)。1968年発表だそうです。 これは、面白い。 つまり、司馬遼太郎版の「平家物語」なんですね。 平清盛の栄華から。 少年義経の放浪。 頼朝の挙兵、木曽義仲の挙兵。 富士川の戦い、宇治川の戦い。木曽義仲の敗死。 一の谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦い。義経の絶頂。 義経と頼朝の対立、腰越状。 そして、義経の没落まで...。 いわゆる「源平」の美味しいところをわしづかみにした、上下巻です。 # この小説と、「街道をゆく 三浦半島記」を読むと、立体的に判ってくるのが、司馬さんの解説する「鎌倉時代」というものです。 平安時代までは、基本の土地所有の仕組みがどうなっていたかというと。 つまり、日本全国の土地は全て、「政府=朝廷」のものだったんです。 ただこれは当然、徐々に形骸化していきます。 どうしてかというと、朝廷という言葉の中身が、実力者が、徐々に藤原一門にスライドしていきますね。 そうすると、藤原一門は、簡単に言うと私有財産が欲しい。私有地が欲しい。 そこで、新たに開発した新田などを、「荘園」として、一部貴族が所有できるようにしました。 これが味噌で、特殊例外以外は、「土地私有」が認められていなかったんですね。 さて、東国、関東を中心に、徐々に技術が進み、新しい田畑が増えていきます。 これを新田開発した、開発農民たちは、地域でのいざこざを日々乗り越えるために、たくましく武装します。 そして、一族で新たに開発した土地に執着します。必要なら戦います。「一所懸命」。 これが、武士の誕生です。 ただし、この武士たちは、頑張って新田開発しても、制度上、土地を私有できなかったんですね。 自分たちの親分にお願いをする。 お願いされた親分は、京都の貴族たちのところに行って、召使のような奉公をする。それも、ノーギャラで。 そうやってぺこぺこして、ようやっと、自分たちの田畑の、管理権みたいなものを認めてもらう。 かろうじて、「管理権」な訳です。 ところが、もう実際に現地で武力を持って土地を守って、耕作して収穫まで、一切は土地の農民=つまり武士、が経営している訳です。 なんだけど、貴族に、つまりピンハネされる。 みかじめ料みたいなものです。 それも、相手は物凄く威張ってて。見下される。 これは、おかしいなあ、と。改革が、革命が必要なんぢゃないか。 不満が溜まっていたわけです。 (恐らく、平将門の乱なども、こういう現象の延長にあるのでしょう) # 大事なのは、この不満を取りまとめた英雄が、「朝廷=京都=貴族」というシステムと、決別することなんですね。 平清盛がそうですが、武士の大将が京都で実権を握っても、「貴族化」してしまったら、意味が無い。 「藤原」が「平氏」に代わるだけで、仕組みが変わらない。 仕組みを変えるためには、「朝廷=京都=貴族」というシステムを壊さないといけない。 # これを痛いほど自覚していたのが、源頼朝。北条政子。北条時政。北条義時。このあたりだった。 と、言うのが司馬さんの説です。 この人たちは、圧倒的に革命家な訳です。 何しろ、「日本史上、全く前例のない、世の中の仕組み」を作らなくてはなりません。 平氏を武力で滅亡させるんだけど、「朝廷=京都=貴族」に、どれだけ誘われても、そこに参加しない。 圧倒的な武力で実力を握っておいて、「各地の土地所有の割り振り権限」を朝廷から奪って。 「幕府」という新しい政治の仕組みを作る。それも中心地を近畿ではなくて関東、「鎌倉」に置く。 これは全て、ずっと「朝廷=京都=貴族」に虐げられ、理不尽に搾取されてきた、「東日本を中心とした開発農民団体=武士」たちにとって、ついに訪れた「自分たちの時代」だった訳です。 # というこの辺が、「地球に残った人類」「スペースコロニーの民」「コロニーの民の権利」「ニュータイプ」と言った、ガンダムの世界に良く似ていますね。 まあ、当然、過去の歴史的な葛藤から作られたフィクションな訳で、当たり前なんですが... # 頼朝なぞは、挙兵した瞬間は、信じられないことに、総勢20名くらいだった訳です。 それも、「やばい、このままではどのみち平家に殺されるから仕方なく挙兵」だったそうです。 それが、連戦して割と連敗するんだけど、どんどん豪族たち、武士たちが味方についてくる。膨れ上がる。 それは全て、頼朝に「朝廷に隷属しない、新しい仕組み」を期待していたからなんですね。 それを、頼朝は判っていた。 判っていなかったのは、義経だった。 # 義経は、父を平氏に殺されて。(まあこれは当然、頼朝も同じなんですが) 幼かったから、色々苦労をして育ち。 ある時点で、復讐=平家の滅亡、だけを夢見て成人し。 あとは若いながらに戦争の現場に入ってしまったので、政治や土地所有の仕組みが判っていない。 単純に、平氏を滅ぼして、源氏が入れ替わりに京都を、朝廷を、我が物にすればそれで万々歳だと思っています。 なにより、兄・頼朝もそう思っている、と、思っている。 そして、平氏と、藤原氏と同じように、「血縁」であるがゆえに自分も尊重されるべきだ、と思っている。 これはこれ、京都的にはその頃の常識なわけです。 だけど、東国では、違いました。 まだ、長子相続すらちゃんと決まっていない。 兄弟でも武力で戦争が当たり前。 さらには、頼朝に求められているのは、「第二、第三の平氏や藤原氏になって、一族でウハウハになる」ことではなくて。 「東国の開発農民団の利益を誘導してくること」なんです。 東国の開発農民団=武士、からすれば、義経が弟だからって、重宝されて、領地とかばんばんもらったりしたら、噴飯ものなわけです。 このあたりの機微を、頼朝は痛いほどわかっていた。 そして、義経は笑えるほど、判っていなかった。 # ただ、問題は。 その義経が、「戦争の天才だった」ということなんですね。 その天才ぶりが、哀しい輝きという感じですね。 なんかもう、機動戦士ガンダムのアムロであり、鉄腕アトムであり。 つまり、強い、かっこいいんだけど、それが幸せに繋がらない。却って疎まれたりする理由になる...。 そういう、「哀しい不器用な、強すぎる戦士」というヒーロー像の、元祖なのではないでしょうか。 # とにかく、強い。 圧倒的に強い。 数年はかかる、かかっても無理かも、と思われた、「平家を滅亡させて、三種の神器を取り返す」という難行を、 またたく間に達成してしまう。作戦は常に電光石火。独断専行。天才の技。 そして、イッキに武士たちの間でその才は認められ、貴族平民の間ですらヒーローになってしまう... # その有様を、描くのに、司馬遼太郎さんはうってつけですね。 鎌倉時代、という分析や、物語能力に加えて。 何と言っても司馬さんの個性は、なんだかんだ言って「元軍人」ということだと思います。 凄くゆがんだ形で、結局は「戦争行為」というもの事態に興味があって、ある種の愛着があって。造詣が深い。 # この「義経」が、小説として素晴らしいのは、 「鎌倉時代、という新しい、革命的な動きの中で。義経というのは貴種でありながら、野盗風情の仲間しか居ない、という、革新の動きの中でも、更に例外で異例な存在だった」 という、二重構造、入れ子構造が凄く、判りやすく面白く描かれます。 さらにもはや、善悪とかモラルではなく、 「新しい時代を判っている男」=頼朝 「判ってない男」=義経 という、ほぼ抱腹絶倒なすれ違いが、はっきりくっきり判ります。 もう、これは殺しあうしかないんですね... (この延長線上に、頼家や実朝の悲劇があります。そのあたりは「街道をゆく 三浦半島記」が実にすばらしい。) # という視点がありながら、平家物語の美味しいドラマチックな名場面がてんこ盛り。 これは、たまりません。 最後、義経の没落の始まりで筆をおいて、死の場面までは描かない。 そんな手法が実に、司馬さんらしい合理性。つまり、もう司馬さんの描きたいドラマは終わってます、ということなんでしょうね。(あるいは、司馬さんが、飽きたのか) # 実はこの「義経」上下巻。 多分、10歳の頃に生まれて初めて読んだ司馬遼太郎さん作品。 個人的には思い入れがあります。 それからもう30余年になりますが、多分どこかで一度は再読していたんだと思いますが、今回、初めて舐めるように魅力を味わえた気がします。 歳を取るのも愉しいものですね。
0投稿日: 2017.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ高橋克彦氏しかり、 川原正敏氏しかり他の書物に書かれている「義経」は多分に美化されていると思いはする。それ程、魅力的な人物だろう。欲はないが強い意志があり、後生にも通用するような、当時では斬新な軍事的戦略を使い、次と勝利を収める。 私の歴史観は多分に司馬氏に引っ張られて居るので、義経のイメージもまた修正されたが、それにしても義経の描写は厳しいと感じる。 下記のようにこの時代のイメージが膨らんだのは楽しい。 【学】 武士とは大農場主、大牧場主といった様なものである 源氏は東国に地盤を持ち、騎馬戦が強く、平家は西国に地盤を持ち、海戦と貿易に長じていた
0投稿日: 2017.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容紹介 悲劇の英雄が、活字の大きな新装版で甦る 源氏の棟梁の子に生まれながら寺に預けられた少年時代。英雄に昇りつめ、遂に非業の死をとげた天才の数奇な生涯を描いた長篇小説 --このテキストは、文庫版に関連付けられています。 内容(「BOOK」データベースより) 義経は華やかに歴史に登場する。木曽義仲を京から駆逐し、続いて平家を相手に転戦し、一ノ谷で、屋島で、壇ノ浦で潰滅させる…その得意の絶頂期に、既に破滅が忍びよっていた。彼は軍事的には天才であったが、あわれなほど政治感覚がないため、鎌倉幕府の運営に苦慮する頼朝にとって毒物以外の何物でもなくなっていた。 --このテキストは、文庫版に関連付けられています。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 司馬遼太郎 大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみち1”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大仏次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。平成5年、文化勲章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) --このテキストは、文庫版に関連付けられています。 本の感想 (オフィス樋口Booksより転載、http://books-officehiguchi.com/archives/4733965.html) この本は昭和40年代に連載されていたものを本にしたものである。 上では、冒頭に藤原長成(通称:一条長成)という中年で、出世の見込めない貴族の話から始まる。この中年の貴族と義経の母となる常盤御前との出会い、幼少期に遮那王として鞍馬寺に預けられた頃の話、奥州藤原氏のもとに行く話へと展開されている。 下では 、源平合戦の一ノ谷の戦い・屋島の戦い・壇ノ浦の戦いにおける義経の活躍、梶原景時との対立が描かれている。軍事的に天才であるが、政治的感覚が鈍く、悲劇に巻き込まれていくというストーリーである。 大河ドラマのストーリーと同じであるという印象を受けるが、昭和40年代から義経の人物像が定着したのだろうか。その点が気になる。
0投稿日: 2016.10.22ジャンプ打ち切り作品を思わせる鮮烈なラスト(主人公死亡END)
上巻で描かれた少年時代の那須与一との出会い、藤原秀衡との交流に加え、下巻では静御前が登場します。そしてそれらの伏線を一切回収することなく終了。敦盛も勧進帳も弁慶の立往生もなし。屋島での那須与市より、壇ノ浦の阿佐利余一(別人)の方がまだ会話があるというのはなんなのか。
0投稿日: 2016.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ平安、鎌倉時代の公家と武家の価値観の違いを具体的に知ることができる。連戦連勝の戦神義経は政治感覚の欠落により周りに踊らされたあげく、慕っていた兄に殺されるという悲劇の最期を遂げる。しかしその短すぎる一生は鎌倉武士ならではの華やかさに満ちている。
0投稿日: 2016.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016/01/17 悲しきヒーロー義経。 でも司馬遼太郎の描く義経は一般的に描かれてきた義経像とは若干違っている。 とても淡々と語り、そして最後があまりにあっけない。
0投稿日: 2016.01.17頼朝も哀れ?
判官贔屓だが、頼朝の立場もよくわかる。三代で終わることが、解ってるので頼朝も哀れである。しかし後白河法王は凄い。
0投稿日: 2015.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
子供の頃は義経に感情移入して頼朝をひとでなしだと感じていたものの、今になって読むと頼朝の気持ちも分からなくもない でもやっぱりビビり過ぎの保身家という感じで好きにはなれないなあ
0投稿日: 2015.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経、戦の才能は類い稀なり。ただ、感情が多すぎる為、兄とは闘えなかった。兄との戦はいやだと、この戦略家は駄々をこねた。
0投稿日: 2014.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経についての知識と言えば、小学生の頃に読んだ歴史漫画の記憶しか無い。弁慶と橋の上で闘う場面、壇ノ浦の合戦で舟から舟へと身軽に飛び移る場面、弁慶が無数の矢で討たれ仁王立ちで死ぬ場面。 この小説にはそんなシーンはなかったけど(笑)。 まったく無名の主人公が、木曾義仲を倒し、一の谷の合戦で勝利、屋島の合戦で勝利、壇ノ浦の合戦でついに平家を滅ぼす。 その当時常識とされていた戦い方をしない(人数的にできなかった理由もある)。自力で考えだした奇襲戦法や、圧倒的な行動力と判断力のすごさ。 最後は兄に追われ自害する。文献が残ってないのか、わざとなのか(多分後者)最後の終わり方が非常にあっけない。 血の争い、自己保身の為の政治的策略、正義とは正しいとは何なのか。 最後の終わり方を読む限り、作者は義経の人生を通して人間とは何なのか?という問いを投げかけたかったのかな。 “むしろ騎射の能力や力業といったその個人的武勇は亡父の義朝や、なき叔父の鎮西八郎為朝や亡兄の悪源太義平よりはるかに劣るであろう。しかし将としての戦場の姿がいい。宇治川の敵を蹴散らして京に突入して行ったときの義経の颯々としたすがたは、いまも目にみえるようである。ーーどこか、神に似通うていた。と、重忠はいう。ひるまず恐れず、一陣の風のように敵陣へ駆けてゆくその姿には、神秘的な風韻さえあったと重忠はいうのであろう。” “(こどもだ)と、行家はおもうのである。驚嘆すべき勇敢さはあっても、人心の表裏を考え、世間を思惑し、配慮し、自分の保身を考えてゆくというおとなとしての感覚がまるで未熟であり、危険なほどに未熟であった。”
0投稿日: 2014.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の天衣無縫ともいうべき戦術と頼朝の冷酷非情なまでの政治力の2つが日本を変えたのだが、最後はやはり無常な結末…
0投稿日: 2014.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻で初めて大江広元が登場する。 頼朝と大江広元がふたりきりで今後のことを相談する場面がある。 大江広元が謀臣という感じで素敵。 司馬遼太郎が、頼朝を「平素は古沼のように澄ましこんだこの男が」と 表現するのが面白くてツボに入った。 「世間というもの」が義経にとって冷酷すぎる。 義経は、頼朝の創りあげようとしている組織について理解が浅く、 頼朝が自分に対してどのような理由で疎ましく思っているか、 全くわかっていない。 しかも、肉親だから会って話せば誤解が解ける、と思っている。 そんな鈍感な人間でありながら、軍事的には天才であるために、 悲劇が起こった。
0投稿日: 2013.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ政治のわからない義経は、白拍子の静や公家たちと京での生活に明け暮れる。鎌倉の頼朝にとって義経は毒物以外の何物でもなくなっていることにも気付かずに・・・。その間も後白河法皇は人の悪い笑みで情勢を見守る。
0投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経が後世の人々に愛される理由がわかった。だめなところがまた可愛く思えるのか。現代に生きてたらいいところ発揮できないだろうし、どんな風なんだろう。想像すると楽しい。生まれ変わった時には幸せに生きてほしいなと思う。
1投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 あえて、そこで終わるのかという結末。 司馬さんの本は結構読んでたつもりでしたが、 本当に楽しめた。2年も本棚で寝かしただけはあるw
1投稿日: 2013.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ頼朝と義経の関係はなんとなく知っていたが、これほど憎悪に満ち溢れていたとは。。。意外な展開と結末のあっけなさ。
1投稿日: 2013.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり歴史上の人物で義経が1番好き! 書く人や目線で人物像は変わるので、もっといろんな作品を読みたいと思いました。 私のイメージの義経とは違うため残念と思いつつ星4つ。
0投稿日: 2012.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本作品は、吉川英治作品ほど細部を書かず、他の司馬遼太郎作品に比べて戦闘シーンが少なく人物描写がメインというのが特徴。何より、義経とその兄:頼朝との確執がかなりウエイトを占めており、対平家の合戦は主題と言うより刺身のつまと言った感じだった。また、吉野での遭難も奥州落ちも全く描かれず、後白河の義経追討の院宣から僅か数行で自害に至ってしまった。当然、お決まりとされている静との悲恋などほとんど描かれず、後半に母親共々少し登場したばかり。義経の数いる女性の一人という描かれ方だった。 上記のとおり、義経絡みのドラマではお約束とされているシーンがばっさり切られているため、初心者向けではなく、ある程度この時代の小説やドラマに馴染んだ人が、「こんな描き方もあるんだ」と感じ楽しめるという作品なのだろう。 以下に、興味深かった点を引用したい。 ・義経の側近にはしかるべき訳知りの人材がおらず、それがおそらく義経の致命的な弱点になるであろう。なるほど、弁慶や伊勢三郎など戦場の勇者がそろっているが、みな浮浪人あがりで、鎌倉の正規の御家人ではない。鎌倉に工作しようにも、手づるをもたず、方法も知らなかった。もし大江広元が義経の郎党なら、鎌倉の権勢家に賄賂を贈っておく。頼朝の舅の北条時政やこの大江広元に充分なわたりをつけておき、それを通じて頼朝に働きかけてもらう。 →なるほど、義経の悲劇は側近の陣営にも原因があった訳である。もっとも、そんな人材がいたとしても義経が取り上げたかどうかは別であるが。 ・「夜は物をお考えあそばすな。」大江広元は頼朝に囁くような小声で言った。「夜ものを考えると次第次第に心が消極的になり、物事の両面のうち不運なことのみ予想し、ついには破滅すら考える。物事は太陽のあるうちにお考え遊ばせ、頼朝殿の悪い癖でございます。」 →現代でいうところの、夜型人間よりも朝型人間を勧めるということか。 ・渡辺党は嵯峨天皇から出た源融が初代。以後、この族党は必ず一字名前であり、その後の日本人における一時名前の元祖になっている。 →なるほど。この時代にしては一字名前は珍しいが、ここが起源とは。面白い。 ・平宗盛は、清盛と時子との間に生まれた子でははく、女子が生まれたため世嗣の男子が生まれなければ時子の実家に威福がめぐってこないとして、出入りの傘職人の家に生まれた男子と児を取り変えた。清盛もそれを知っても宗盛を愛する態度に少しの陰もなかった。 →時子の兄:時忠がやりそうなことである。それにしても清盛、器が大きい。自身が平忠盛の子ではないというバックグラウンドのためであろう。 ・義経の正室となった平時忠の娘は、平家戦に勝利した義経に取り上げられた時忠記載の日記を返してもらうために、時忠によって差し向けられた。 →これは他作品でも書かれていなかった。司馬氏独自の色付けか…。 本作を含め司馬遼太郎作品の読破数は15作品目となった。まだまだ読みたい司馬作品が盛りだくさん。次は何を読もうか…。「菜の花の沖」「覇王の家」あたりが読みたいリストである。
0投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「義経は政治感覚を持たなかったから滅びた」ということを強調しすぎている気がする。判官びいきな私としては、もう少し幅広い解釈を期待していた。
0投稿日: 2012.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家追討の最大の功労者であり自分の弟でもある義経を、自分の武家政権擁立のために悪として誅する頼朝に対し、正義とは何なのかと考えさせられる作品だった。惜しいのは義経の最期。奥州に落ちてから、死の描写が完全に簡略されていることと、京、鎌倉、平泉の三竦み状態だったはずなのに下巻では平泉の情勢などが省かれてしまっていたのが心残り。
1投稿日: 2012.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大将としての義経の凄さと、それ以外の時の義経の幼さに、大きなギャップを感じて、そこがまた魅力なんじゃないかと思いました。 京を離れた後、詳しいことは書かれていませんが、奥州へ逃れた時、自害した時は一体義経がどんな心境であったのか、非常に気になります。結局一度も頼朝と戦おうとはしなかった義経は、最後まで頼朝を慕っていたんじゃないかな...
1投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「司馬遼太郎そろそろ読まなきゃだけど『坂の上の雲』とか長いしどうしよう!」という、どうしようもない理由で買ってみた。入門として。 が、後からフリークの人に話を聞いたところ、どうやら入門としてはアレな模様。 一通り読んでみると、なるほどその通りかな、と思った次第。 本書の義経像は、だいたい以下の3点に集約される。 ・(多分に先天的な)戦術の際を以って、戦場で華々しい活躍をすることによってのみ存在意義があったこと。 ・関東武士団を中核とする御家人集団からは、頼朝による秩序を乱す者として白眼視され続けたこと。 ・私生活はぐだぐだで、かつ大した教養もなかったこと。 というわけで、壇ノ浦で平家が滅亡した時点で、義経その人の存在意義も消滅したということになる。 だから、そこから終わりまでの記述は非常にあっさり。もともとあっさりだけど、特に。 でも、もともとが時代の相をマクロ的に描き気味なので、衣川まで引っ張って悲劇性を煽るよりは、すんなり受け入れられたのかもしれない。 個人的にはドラマ的要素を求めちゃいなかったので、納得と言えば納得なのだけど、スペクタクルを求めがちな方にはお勧めできないかなあ。
1投稿日: 2012.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの時代については「1192つくろう鎌倉幕府」程度にしか知らなかった。戦国、幕末と日本史で人気の時代がたしかにある。あるのだが、あえてわたしは『義経』を押す。律令制から武家政治に変革する変わり目に現れた天才義経はとても魅力がある。わたしの中では信長越えまちがいなし、なぜなら800年以上前に騎馬戦術を理解し行動しえたのだから、すごいとしかいえない。いつの時代も改革者は変人なのである。
1投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ評価が低いように言われていますが、大河ドラマの平清盛、私は好きですね。中井貴一の忠盛がよい。この本で同じ時代を丁度裏表から眺めて見て面白い。判官贔屓。今もこの国に残る感覚であり、汎用表現。九郎判官義経。よく知っているつもりの物語も、やはり司馬遼太郎の物語で新たな納得感がありますね。決してヒーローではない。
1投稿日: 2012.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが司馬遼太郎というかんじ。典型的な義経と弁慶のドラマなどは描かず、司馬独自の史観とおそらく調査の裏付けに基づきストーリーを組立て、十分に魅力的な義経の物語になっている。 義経と頼朝の人となりを最期まで引いた目線で客観的に叙述し、最後はさらりと終わらせ、読者に義経の想いを想像させる。
0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の儚い生涯を描いた作品。自分が欲しいものを求めただけなのに、それによって殺される羽目になる。世に生きるということは、時に理不尽であるのかもしれない。
1投稿日: 2012.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ来年は司馬遼太郎作品を時代順に読んでみよう。義経は以前読んだので早速登録。読む前は絵本の牛若丸のイメージだったが、読んでみると義経の人物像が深堀されていて面白い。 軍事的天才は政治的には幼稚。バランスを欠いたキャラゆえに物語になるのかな。それにしても英雄や京男はモテてエエなぁ。
2投稿日: 2011.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代のヒーローではない義経がみえる小説です。 華々しい戦果から天才と呼ばれ、浮き名を流す義経とは違った一面が読めました。 精神的にも子供がそのまま大人になったようなその姿が逆に新線でした。 また、公家の社会から武家の社会へと移り変わる政治的な動きが、現代に通じるどろどろとした物があり、非常に怖い。
1投稿日: 2011.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説はそれぞれの思い入れが入ってくるから、 ほんとの史実は別にあると思う。 しかし、この義経は少し馬鹿すぎないかと思う、 逆に頼朝はそこまで完璧な人間であってかというところも疑問にわく。
1投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の華々しい合戦の描写はあるのだが、結局残るのは、 鎌倉どの(頼朝)と白河上皇の役者が違う存在感だった。 司馬遼太郎の大作は何度も読んでいるのでこの作品は片手間で書いているようなのは見ればわかる。 片手間であるが故に、素の文章に近くて面白い。 それにしても、司馬遼太郎はあまり皇室を描くのが上手ではないような気がする、もしくは好きではないのか。 やはり、幕末ものに代表される武士を描くのが性に合っているのだろう。 私も鎌倉へ行き、頼朝の墓に手を合わせた事をふと思い出した。
1投稿日: 2011.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経と頼朝以外の描写が薄っぺらで、まったく物語になっていない。物語に重要なはずのエピソードもあっさりしていて、ホント盛り上がらない。
0投稿日: 2011.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経という軍事的天才がなぜ、兄である頼朝に討たれたのかということが、この本を読んでよく分かりました。
0投稿日: 2011.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【83/150】抱いていた義経とはちょっと違うイメージだったなぁ〜。でも小説としてはあんまりおもしろくない。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり頼朝は嫌な奴だ。でも彼じゃ無ければ幕府が成り立たないこともわかる。でも藤原氏が本気になれば鎌倉を倒せた気はします。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ『義経 上』では、木曾義仲が京の都に入って占領し、平家がその都を退去、瀬戸内海沿岸一帯に拠ったところまでが描かれている。源義経が、かつて幼少期を過ごした都へ颯爽と登場するのは、この『義経 下』からである。木曾義仲は、後白河院の住まう法住寺御所を焼き払い、あまつさえ後白河院を幽閉するなど、その行為は横暴を極めていたが、西国に拠った平家軍は大いに軍威を上げ、京都への捲土重来を期する勢いを見せていた。また、鎌倉からも、源範頼(みなもとののりより)と義経とが、義仲追討のために派兵されることとなり、木曾義仲は袋小路に迷い入った猪のごとき様子を呈していたのであった。後白河院にとって懸念であったのは、追い詰められた義仲が自棄(やけ)を起こして都を放擲(ほうてき)し、自分を北陸の地に連れ去るか、悪くすれば殺してしまわないか、ということであった。 後白河院が義仲に対して、「旭将軍」と尊称を送るなどして懐柔を進めていた頃に、頼範・義経軍は近江瀬田を大手、宇治を搦手(からめて)として、いよいよ京都を望見(ぼうけん)したのであった。軍勢はさして多くない。頼範軍八千騎、義経軍にいたっては僅か千騎ほどで義仲軍を制圧し、都を院の手に取り戻すのである。搦手を請け負うは御曹司(おんぞうし)義経、うち乗る駿馬は太夫黒(たゆうぐろ)、奥州仕込みの手綱さばきと華奢な体つきによって、あたかも雲上を行くが如くの軽々とした疾駆は、どこか神彩を帯びてさえいる。彼にとっては、この宇治川の合戦が初陣であるが、この鮮やかな身のこなしと馬の御し方は、居並ぶ戦巧者(いくさごうしゃ)たちを感心させたようである。 そしてさらに、味方の軍勢を驚かせたのが、義経の指揮する行軍の速さと戦術であった。通常、大将や指揮官というものは中軍に在って、首を取られぬよう周囲の武者共に守られているものだが、義経の場合は違う。彼自身が前線に立って馬を駆けさせ、他の将校らを叱咤しながら、ぐいぐいと軍勢を引っ張っていくのである。自然、義経軍の行軍は圧倒的な速度を持つ。この速度あるがゆえに、義経軍の通る道々の住人たちは、その速度を超えて噂を伝播させることが出来なくなってしまう。義経軍がどこへ参集し、どこに埋伏し、どこから攻撃を仕掛けるのか、そういった諸々の情報を平家軍が得ることを不可能にしてしまうのである。「兵は神速を尊ぶ」(魏志)とか「兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なるを賭(み)ざるなり」(孫子)といった唐(もろこし)の兵法を、義経が知っていたかどうかは不明だが、速度を維持することの重要性と、それによって自軍と敵軍の情報をもコントロールする有益性を理解する、そういった感覚を彼は生得的に身に付けていたように思われる。 それから、彼の戦術・戦法。現代人から見れば、騎兵や歩兵を戦術的に配置し、展開させることは、至極当然のように思えるが、司馬遼太郎氏の言葉によれば、義経の時代には、そういった考え方自体がなかったようである。戦はとにかく数量的な勢いだけであり、数を恃(たの)んでひた押しに押していく。兵の数が敵軍よりも劣っていれば、個々の武勇と士気を頼りに切り結ぶ。要するに、騎兵も歩兵も戦闘フィールドをバラバラに動くのであり、個人個人の戦いの結果として軍全体の勝ち負けが決まるということだ。しかし、義経は自軍を、戦術・戦法という軸によって、一個の機動力として扱った。武将ら個人の勇猛果敢さに依存するのではなく、戦場を武士(もののふ)の名誉を主体とした華麗な働き場とするのでもなく、軍勢を、勝つために有機的に動かし、戦場を、勝つためのフィールドとして措定(そてい)した。それは、源平の当時にあっては非常に画期的なことだったのである。 宇治川の合戦では、木曾義仲の配下である志田義広勢を切り崩しつつ宇治川を渡りきり、本来ならそのまま、当時の流儀通りに各々が義仲の陣所へどやどやと押し寄せるはずだったのが、義経の采配で、その勢いはまず一旦とどめられた。そして彼は少ない自軍をさらに四隊に分け、四方から義仲を包囲していく戦法を採ったのである。鎌倉を発してから洛中に到るまでの進軍が速やかであったことも手伝って、木曾義仲は義経の到来予想を読み違え、包囲されたことで敗退し、結果、近江で戦死した。兵数という物量によって勝敗が決まるのではなく、迅速な進軍と情報、そして、たとえ小人数であろうとも戦術によって勝利を得ることが出来るということを、義経麾下の坂東武者たちは目の当たりにしたわけである。 これ以後、源義経という若者は、一ノ谷、讃岐の屋島、長門の壇ノ浦へと転戦していく。一ノ谷や屋島の合戦では、難路を迂回して平家軍の背後に出現し、これを大いに破り、壇ノ浦の海戦では、戦に先立って激しい潮流の観測までも行って、どの潮が源氏にとって勝てる潮かを見極めている。速度、機動力、戦術、情報、誰に習ったわけでもないが、戦という局面に関して云えば、この武将は稀有な才能を有していた。それぞれの戦の勝敗は歴史が物語る通りである。 しかしながら、義経のこの才能は、兄・頼朝の息のかかった武将らには非常に受けが悪かった。義経が新しい戦い方を持ち込んだために、先陣を切って疾駆するために、彼らは従来どおりの戦が出来ない。義経自身が誰よりも先に大将の首級を狙おうとするため、彼らは手柄を立てることも覚束なくなるのである。身分ある武将の首級が取れなければ、御家人は恩賞にあずかることが難しくなる。義経の新思想は、坂東の御家人たちの生活までをも脅かすかもしれない、極めて迷惑なものであったのである。加えて、彼ら坂東武者にとっては鎌倉の頼朝こそが主上であり、義経は腹違いの弟とはいえ、頼朝の御家人、いわば自分たちと同等の立場であるに過ぎない。そこを、義経は理解せず、鎌倉衆を家臣扱いした上、彼らにとっては呑み込みにくい戦い方を、十分な説明もなしに下知することがしばしばであった。義経を嫌う軍監・梶原景時(かじわらのかげとき)などは、戦況報告書を、あえて義経の戦功を無視した形で認(したた)めて鎌倉へ送るほどに、義経と反目しあっていたのである。 合理的―――というのであろうか。義経の戦の仕方だけを見ると、作戦に冗長な部分がなく、極めて合理的な戦い方をしているのである。そして何よりも、刻々と移り変わっていく戦況を敏感に読むということに長けている。戦という主題が目の前にあれば、義経は確かに、奇才を発揮することが出来たのである。それが一旦、戦という大きな主題から離れて、例えば宮廷での人付き合いや鎌倉方面との関係構築といった政治的・サロン的な場に置かれると、その合理的精神や場の空気を読むといった感受性は嘘のように引っ込んでしまう。他人の真情を図れない、政治的配慮が出来ない、そういった無邪気すぎる子供のような男になってしまうのが、本作品の義経なのだ。この源平の時代には珍しい合理的精神を持って生まれながら、平家打倒のみが悲願、亡父・源義朝の仇を雪(すす)がねば、という直情径行型の性格も形成されたことが、義経にとっては不遇の人生の始まりだったのかもしれない。 義経は孤立していく。頼朝の御家人とされながら、後白河院の覚えもめでたい彼は、頼朝の許しを得ることもせず、検非違使の太夫尉(たゆうのじょう)、俗に云う、判官(ほうがん)の位を受けてしまう。れっきとした殿上人であり、これによって彼は鎌倉の武家でありつつ、京都の公家でもあるという矛盾する立場に立つことになった。合理的性格と直情的性格、武家でありながら公家という二重の矛盾が、彼を孤立へと追いやるのだ。義経もまさか、あれほど憎んだかつての平家のように、自分が武家と公家との二面性を持つとは思わなかっただろう。 この司馬遼太郎氏の『義経(上下巻)』では、演劇や講談で語られるような伝説的で美麗な義経というものはあまり書かれていない。書かれているのは、人間・義経である。兄との関係を好転させることも出来ず、後白河院に利用されていることにも気付けず、矛盾や破綻を抱えながら、平家打倒に没頭していくしかなかった義経の姿である。そして、源氏の血を愛し、源氏の悲願成就の大功労者であった彼が、その戦功に一切報いられことなく、尾羽打ち枯らして追い立てられていく姿に、我々読者はそっと自分を重ね合わせてみるのだ。 人間・義経には、奥州を脱しての北行伝説もない。彼は衣川で自害し、酒漬けの首級となって初めて鎌倉の兄の元へと帰還することが出来たのであった―――。 平成二十三年六月十日 読了
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に上巻にしるすことにする。私の読書人生を変えた作品。中学生のときにこの作品に出合っていなかったら読書は今でも嫌いだったように思う。
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の源義経が主人公の歴史小説。義経の視点で、源平合戦を楽しめる本。義経ファンは、是非、ご一読を。
0投稿日: 2011.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経ってこんな人生だったんですね。 愛らしいキャラだっただけに、最期が悲しいかも、、、 だけど、レビューを読むとあまり好かれてないみたい(笑) 私は好きなんだけどな~
0投稿日: 2011.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ・5/7 読了.最後はどうなったのかまでは書いてなかった.やっぱりそこから先は伝説がいろいろあるゆえんかもしれない。ちゃんとした資料がないんだろう.
0投稿日: 2010.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 昔の憧れの人、義経。 色白で横笛を吹きつつ橋の上に立つ。 そんなイメージでしたが。。 司馬遼太郎の描く義経のイメージは 戦術家ではあるけれど あまったれで血縁に弱い。 (そういう人間の方が好きだけど) 頼朝の思惑や嫉妬心もすごく伝わってくるし、 源氏に関わる人々の思惑がよくわかる。 「義経」というよりも「源氏」な感じで ぐいぐい引き込まれていきました。 印象に残ったのは あの一ノ谷の合戦の際に怖気づいた自分に言った義経の一言。 「人よりも百倍臆病であるとすれば、 百倍勇気をふるい立たせればいいではないか」 この信念とプライドが彼をのし上げさせたのだと思うと 響きました。
0投稿日: 2010.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログある意味とてもおもしろく読めました。 …悲劇の人というけれど、こんなのが身内にいたら頼朝だってたまらないよな、と思う。
0投稿日: 2010.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしてだろう。義経を他人とは思えない。女っぽくて感情的で、家族の縁を大切にする。 頼朝に悪とされた、義経。 平家を倒したのは、間違いなく義経だったのに。 天下をとるために、大切なものの基準が変わってしまう。 名を残した人が全てじゃない。 何が本当に大切かは、わからない。
0投稿日: 2010.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ手に汗握る平家との合戦の描写はさすがという感じ。 義経の戦における天才ぶりが素晴らしい。 たとえその後の運命が悲劇でも、やっぱりこの人は永遠に日本の英雄なんだと、しみじみ。 皆さんの感想にあるように、終わり方がちょっと尻切れとんぼ?
0投稿日: 2010.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家に対する復讐のみを目指した義経と、鎌倉幕府という組織形成を目指した頼朝。血縁関係を重要視する義経と、血縁関係よりも組織を重要視する頼朝。政治感覚に乏しい義経と、それに長けた頼朝。当作品を通じて、綺麗ごとではない「政治感覚」の重要性を教えられた。
0投稿日: 2010.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の奇襲に破れた宗盛は、屋島の本営を捨て彦島にいた知盛の元へと逃げたが、 義経はすぐ後を追わなかった。 屋島に居座り、 「瀬戸内海一帯の水軍に対ししきりに軍使を出して 船数を得ようとしていた。」 遠征軍を送るには兵もさることながら、軍糧や馬糧の補給が 大切なのだが、この時代はまだそれほど発達していなかった。 この戦に勝って源頼朝が開いた鎌倉幕府は その後源氏から政権が変わりながらも、約150年程続く。
0投稿日: 2009.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経がもし現代にいたらって妄想するとすごくたのしいい! このメンバーで学園モノとかおいしいと思う。
0投稿日: 2009.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ一の谷の戦い、矢島の戦い、壇ノ浦の戦いとかの詳細な記述がすごい面白かった。 楽勝で勝利したと思ってたんだけど、そうでもないんだね。 木曾の義仲とかのことも知れてよかった。
0投稿日: 2009.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の下巻。木曽義仲を京から駆逐した義経は、平家を一の谷や屋島で倒し、最後には壇ノ浦でついに平家を滅ぼす。しかし、この戦いによって高まった義経の武功のひとつひとつが、鎌倉にいる頼朝には、権力を脅かす存在として映り、大きな懸念材料となっている。結局、頼朝から義経を討つ命令が下され、義経一行は日本を転々とし奥州で最後のときを向える。歌舞伎「勧進帳」の場面はでてこないが、最後まで弁慶は義経の忠実な部下として働いている。義経の政治力の欠如が自分の死の原因であるが、それがまた義経の大きな魅力となっている。
0投稿日: 2008.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の天才的な戦いぶりを読みとることができる。 義経がいなければ、鎌倉幕府なんてものは存在できなかったのではないか。 好色という点をのぞけば、一つの思いに向かってひたすら突き進む義経の姿は憧れを感じてしまう。 義経をかっこいいヒーローとしてではなく、あくまで客観的に悪いところもすごいところも語り尽くした、おもしろい小説であった。 なんとなく、職場での自分の行動の仕方を感じ取ることができるようなものがあった。 義経を真似するか、反面教師とするか…。 2008年1月10日読了
0投稿日: 2008.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻は木曽義仲の都落ち〜義経の死まで。 下巻から義経の軍神ぶりが如何なく発揮されますが、そのバカッぷりにイラつきもしました。 政治的資質がここまで足りないってどうよ!? けれど、このアンバラスさも彼の魅力なんだなぁとも思う。 何より、ここまで魅力的な義経をかける司馬さんはスゴイ。
0投稿日: 2007.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログどこかで見た『義経は歴史上もっとも古いヒーローである』という言葉が忘れられません。歴史物は苦手なのですがこの本は読みやすかったのですんなり読了しました。ちょっと義経に詳しくなった気がします。
0投稿日: 2007.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好きっすから。自分義経大好きっすから。ちょっと残念なところは義経の最後、衣川の戦いが書かれていないところかなぁ。だからそこが好きな人には物足りないかも。でも、あたしは義経は北上して生きていたってほうがヒーローっぽくて好きだけどね(*'ー'*)
0投稿日: 2006.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと終盤がね。。司馬さん途中で面倒くさくならなかった?とか敢えて突っ込みたい。まぁそれでも最後まで読んでしまうのだけど。
0投稿日: 2006.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の本っていっぱいあるんだよね。この義経を読むと、萩尾望都さんが描いてた義経像とは、ちょっと違う感じがした。こっちの義経の方が、もう少し、どろどろしてる感じがする。きっと、他の義経を読んたら、もっといろんな義経像がでてくるんだろうな。。大河ドラマ、みとけばよかった。
0投稿日: 2005.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家は滅び、藤原氏も滅び、そして、政治的インテリが欠如していた、といわれる義経も、兄頼朝に命を狙われるべき人物となり、権力のあるものに趣く朝廷は頼朝のみかたをし、次第に追い詰められていく。鎌倉時代到来直前、義経物語下巻。
0投稿日: 2005.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の義経は、単純で甘ったれで、政治に疎く、そして魅力にあふれています。 感想はこちら。 http://xxxsoraxxx.blog11.fc2.com/blog-entry-35.html
0投稿日: 2005.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKで放送中なので慌てて読みました!上・下と2巻だけなので大事なシーンが大幅にカットされており期待したよりガッカリでした。でも司馬遼太郎は面白いよ♪
0投稿日: 2005.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ義經といへば、辨慶と牛若丸の話で知つてゐる人が多い。 私も知つてゐることといへば、 源平の戰ひでの「ひよどり越え」だとか「屋島の戰ひ」だとか、 兄・頼朝に追はれて、平泉の藤原を頼つて逃げたものの、最後は殺されてしまつたとか、 一説によれば大陸まで逃げ延びて、チンギス・ハンになつたとか、 せいぜい、その程度のことしか知らなかつた。 この小説は、何故義經が兄・頼朝に討たれることになつたか、がよく判るやうに書かれてゐる。 要約して云つてしまへば、次のとほりだらう。 義經は戰術能力に關しては天才だつたが、戰略やましてや政治についてはまるで子供だつた。 兄は源氏といふ武家の棟梁としての立場からものを考へたが、義經にはまつたくその考へ方が理解できなかつた。 つまり、兄は武家政治を行なふ上での組織や規律を築かうとしたが、義經は目の前の戰にしか興味がなかつたと云へる。 そして、兄との血の繋がりを過大視しすぎた。 一言で云つてしまへば、義經はまるで子供のやうな男だつたといふことだ。 しかし、さうは云つても、その戰術勘は天才であつた。 騎兵の機動力を驅使した奇襲戰法といふものは、 義經が「ひよどり越え」で採用するまで誰も行なつたことがないらしい。 それどころか、義經以降では、信長が「桶狹間」で行なつた以外にはなく、 その次となると日露戰爭で秋山好古が採用するまで無かつたさうだ。 まさに天才と云つても過言ではない。 この作品は義經の逃避行についてはまつたく描かれてゐない。 作者に義經の悲劇を描く氣持ちはなかつたやうである。 私がこの作品で一番魅力的だと感じたのは、後白河法皇である。 この人を中心としてこの時代を描いた作品を讀んでみたいと思つた。 2004年12月15日讀了
0投稿日: 2005.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨日の夜に読み終わった〜〜〜〜!! 最後まで義経は報われなかったけど…(T_T) 読み始めたのは「何で頼朝はあんなに義経を嫌ったんだろう」っていう理由が知りたかったから。 それで読み終わってみて、まだ統治国家が出来上がっていない頃の日本の生き残っていく厳しさが背景にあったのかなあってちょっと分かったかな… 義経は才能を持ち過ぎていたために、頼朝から将来自分の作ろうといている鎌倉国家の敵になると恐れられて、結局疎まれたけど、なんかやっぱりとっても切なかった… 話の中では、義経は肉親に育てられていなかったから、普通以上に兄からの愛情を求めていたって書かれていたけど、もちろんフィクションだから実際はどうだったかは分からないよに… でも義経がそれまで戦争と言えば、ただ真っ向勝負だった日本で、初めて戦法を用いた人間で、しかもそれを何回も大成功させていることは事実で、その義経が実の兄に正当に評価されずに、殺されたってのは、彼が今でも人気のある史実上の人物である 理由なんだろうなあ。「悲劇のヒロイン」だね。 とにかく、面白かった☆☆☆ 大河見ちゃいそうだなあ〜〜〜A^^;)
0投稿日: 2005.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終え。 大河開始に間に合った! けど、司馬遼の書く義経は、私の好きな義経像じゃなかったから、ちょっとガッカリ。 まぁ、大河前に、時代背景と流れはおさらいできたから、それはそれでよし。
0投稿日: 2005.01.07
