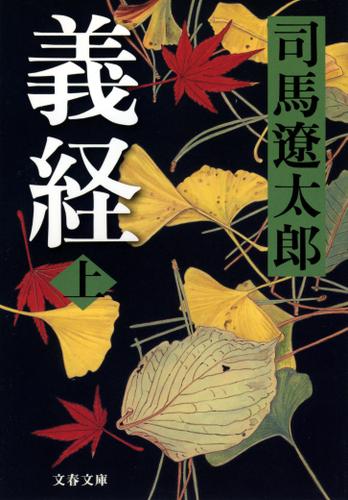
総合評価
(92件)| 18 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ頼朝と義経のすれ違いが随所出てきますね。 慢心、環境の違い。 もう少し義経の大活躍が見たかったかな。
1投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の幼少期を中心とした上巻。 義経の華々しい活躍というものは少ないが、この頃からすでに頼朝との微妙な関係が執拗に描写されている。 嵐の前の静けさのような上巻。
0投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ平安時代末期から鎌倉時代初期が舞台です。 源義経が主人公ですが、色んな人の視点から物語が語られます。 1,000ページに迫る大作でした。 馬鹿と天才は紙一重といいますが、義経はその両方だったのかもしれません。
0投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ誤って下巻から読んだこの話し、義経の月末を見てから生い立ちを見る、まさにスターウォーズ的な読み方をしてしまったけど、それはそれで面白い。 欲を言えば武蔵坊弁慶や那須与一、義経の逃避行のエピソードがもっと欲しかった。上下巻だけで物足りない。でもそれくらい面白かった。
0投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経と名乗るまでの成長過程の話。なんだけど、あまり活躍がない。伝説めいた物語ではなく現実的な描写としたのかもだけど、肩透かしな感じ。 平家に源氏、朝廷に奥州藤原氏、有名な歴史を彩る様々な人物が出てくるけど、どの人物もイマイチパッとしない。この時代の人物像に適ったものなのかも知れないけど、もっと盛り上がりというか、それぞれの魅力の迸り、それらの激突がほしかったなあ。 自分にとっては、どうも残念な上巻。
0投稿日: 2024.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経の欠落した性質を、その生い立ちにまで遡って創り上げているので無理なく読み進められます。焦点を当てるべき人物が少ないので、義経に集中して描かれている分、かなりはまり込んで読めました。
0投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022/2/11読了 当時、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』もあって、タイムリーな内容であった。 司馬遼太郎は、物語の中で義経と頼朝の対立の原因を、義経の「空気読まない」具合と共に、都人と坂東武士の思考回路・価値基準の違いに帰していたが、大河では、純粋過ぎ、強過ぎる故に、却って周囲から怖れられ、疎まれ、やがて兄弟がすれ違っていく悲劇を描いていたように思う。――それにしても、菅田将暉の義経はクレイジーで素敵だった。 (どっちの感想だ?)
0投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりの司馬遼太郎。知らん事をそれっぽく書くなと思ってしまった。なので歴史小説なのか。 義経には子供の頃から興味を持っていたので「へー。」と思いながら読めた。
1投稿日: 2023.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ1000年経っても残る判官贔屓の言葉、その人物と影響力の大きさは、日本史上の傑出した人物の一人であることを理解することができた。
0投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経から離れ平家マイナー武士など描かれると司馬節ではあるが自分的に盛り下がりページが進まず困った。あの連載打ち切りとしか思えないような結末描写は総ページ数に見合わずどうしても許せない。
0投稿日: 2022.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ父は源氏の棟梁「源義朝」、母は皇妃侍女の「常盤」、 幼名「牛若」から「源九郎義経」「九郎判官義経」と呼ばれた数奇波乱の伝説的英雄「源義経」の生涯を中心にして、登場人物の思想と言動が克明に再現された長編歴史小説。 上巻では、保元・平治の乱後の平家の権勢下の様子、鞍馬寺に「遮那王」の名で預けられた後、関東奥州を転々とする源九郎、平泉の藤原秀衡の庇護、 武蔵坊弁慶との邂逅、源氏の再興をかけ挙兵した異母兄・源頼朝との合流、木曽義仲による京での平家討伐の模様など、息も継がせぬ緊迫感で刻々と語られていく。
3投稿日: 2022.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ邪道かもしれませんが、大河ドラマを見てから読むと、人物に現実味が出て面白い。鎌倉殿の13人、結構忠実にこの流れに乗ってるなと。昔から気になってた木曾義仲やっぱり切ない。勿論義経もだけど。わかっていても後半が楽しみ。
2投稿日: 2022.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて歴史小説を読みました。 義経の伝説はちょこちょこ知ってるものの、ちゃんとは理解できてなかったので、今年の大河ドラマの予習も兼ねて手に取ったのですが。 上巻は説明的なところが多く、いつ義経出てくんねん!と思いながら読んでましたが、最終的にはその状況説明がかえって重要で、平安時代にぐっとのめり込むように読み進めてました。
0投稿日: 2022.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすくて面白い。 鎌倉殿の13人を見ているので頭の中を整理したくて読み始めました。 歴史って面白い。
10投稿日: 2022.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者の文体に引き込まれる。義経と義仲の対峙直前までが描かれている。ようやく表舞台に現れた義経。小さな頃の記憶では僕の中でヒーローだった彼の生い立ちに同情し、頼朝を毛嫌いしていたが、この年になって読み返すと、頼朝の大局観と政治力、そして既得権に左右されない、武家社会の樹立を志した偉大な人物に映る。義経の死生観は復讐心に見えてしまう。
1投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が初めて手に取った司馬遼太郎作品です。 著名ではありましたが、小難しい言葉で歴史を語る教科書の様な歴史小説の苦手イメージが、司馬遼太郎さんのこの一冊で払拭されました。とても読みやすく、面白く、その当時単純な私は義経の大ファンになりました。
0投稿日: 2021.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の描く義経の何と愛らしいことか。 源義経、日本人ならば誰もが知っているその英雄の非凡人的な部分は、物事を極端にしか見ることしか出来ない政治的常識の欠落、牛若のころから変わらぬ思考であるとした。その欠落こそが、危なっかしくて放って置けない人としての魅力であると。 上巻では義経の華々しい活躍が一切ないため、義経という名を聞いて期待をすると物足りなく感じる。 だが、その人物像の無垢さを丁寧に書いているからこそ、皆が知っている晩年に更なる哀愁を感じさせる。
0投稿日: 2020.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し意外だったのは、義経像をビジュアル面では決して美丈夫としては書いていない、言わば今風の表現でいう雰囲気イケメンの類として描写し、かつ特異であっても才覚の人物として書いていない点だろうか。 歪、あるいは異物と呼ばれるものは必ずしも自ずからそう産まれるものでなく、空気の滞留した環境とそれに根ざす人々とが升形になって形造られるのが本作に於ける牛若であり遮那王であり九郎義経と言える。 あと鞍馬寺ちんちんフェスタ
0投稿日: 2020.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ京都生まれだからか牛若丸は馴染みと親しみがあり、なんとなくな感じで好きだった。改めて歴史を知ることで京都人の判官贔屓が理解できたことでその根拠が解った気がした。 義経の“青さ”と“不器用な実直さ”は魅力でもあり、それに弁慶たちも京都人もそして私も引き込まれたんだろう。 また昔は弁慶は強いとの印象があったが、ただの強さではなく父親のような温かな強さであったと改めて感じた。
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作品を読むまでは、源義経と聞けば、半ば神格化された英雄だと思っていました。 しかし、本作品で描かれている義経は人間臭く読んでいて新鮮でした。弁慶との出会いもある意味、史実に忠実なのかなーと感じました。 上巻はまだ義経が雌伏の時にあるので、下巻が楽しみです。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ軍神と称された幼稚な義経の物語。多くの点において、自らを重ねるところあり、政治感覚の無さ、他者への気持ちのわからなさ、自分を正しいと思う、思い込みの強さ、自らを重ねるようである。 しかし、痛快な30年弱の人生であっただろう。 初陣から壇ノ浦まで、古今類を見ない奇跡的な勝利、それはこの時代になかった、 戦術、策、を用いた初めての戦いであり、またそれにより価値、勝てない戦を勝って、英雄となった。 鎌倉が恐れること、仲間だと思っていた身内が恐れることを「まったく」分からなかった。 その純粋さ、つまり「親のかたき討ち」以外には思いを寄せることが出来なかったことが、 結果、さわやかで痛快な、そして悲壮な人生を創造し、永久に忘れられない青春となった。
0投稿日: 2017.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ今から約1000年前の時代ではあるが大方史実に則ったものなのでしょう。もやもやした歴史知識が明確になり、相変わらず司馬作品は読後の充実感があります。平安から鎌倉時代は激乱の時代だったのですね。皇室も含めとても節操なく、道徳心や法律が育っていない時代ならではの展開に驚きます。司馬の作品は人物のセリフはすごく簡素に、心情はすごく深く描くもので、とても気に入っています。思慮ある弁慶の下巻での活躍が楽しみです。
0投稿日: 2017.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ機動戦士ガンダム。アムロ・レイ。zガンダム。カミーユ・ビダン。シャア・アズナブル。 うーん。彼らの原型が、「源九郎義経」だったとは。 ガンダムファン、必見、必読の作品だと思いました。 # 司馬遼太郎さん「義経」(文春文庫、上下)。1968年発表だそうです。 これは、面白い。 つまり、司馬遼太郎版の「平家物語」なんですね。 平清盛の栄華から。 少年義経の放浪。 頼朝の挙兵、木曽義仲の挙兵。 富士川の戦い、宇治川の戦い。木曽義仲の敗死。 一の谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦い。義経の絶頂。 義経と頼朝の対立、腰越状。 そして、義経の没落まで...。 いわゆる「源平」の美味しいところをわしづかみにした、上下巻です。 # この小説と、「街道をゆく 三浦半島記」を読むと、立体的に判ってくるのが、司馬さんの解説する「鎌倉時代」というものです。 平安時代までは、基本の土地所有の仕組みがどうなっていたかというと。 つまり、日本全国の土地は全て、「政府=朝廷」のものだったんです。 ただこれは当然、徐々に形骸化していきます。 どうしてかというと、朝廷という言葉の中身が、実力者が、徐々に藤原一門にスライドしていきますね。 そうすると、藤原一門は、簡単に言うと私有財産が欲しい。私有地が欲しい。 そこで、新たに開発した新田などを、「荘園」として、一部貴族が所有できるようにしました。 これが味噌で、特殊例外以外は、「土地私有」が認められていなかったんですね。 さて、東国、関東を中心に、徐々に技術が進み、新しい田畑が増えていきます。 これを新田開発した、開発農民たちは、地域でのいざこざを日々乗り越えるために、たくましく武装します。 そして、一族で新たに開発した土地に執着します。必要なら戦います。「一所懸命」。 これが、武士の誕生です。 ただし、この武士たちは、頑張って新田開発しても、制度上、土地を私有できなかったんですね。 自分たちの親分にお願いをする。 お願いされた親分は、京都の貴族たちのところに行って、召使のような奉公をする。それも、ノーギャラで。 そうやってぺこぺこして、ようやっと、自分たちの田畑の、管理権みたいなものを認めてもらう。 かろうじて、「管理権」な訳です。 ところが、もう実際に現地で武力を持って土地を守って、耕作して収穫まで、一切は土地の農民=つまり武士、が経営している訳です。 なんだけど、貴族に、つまりピンハネされる。 みかじめ料みたいなものです。 それも、相手は物凄く威張ってて。見下される。 これは、おかしいなあ、と。改革が、革命が必要なんぢゃないか。 不満が溜まっていたわけです。 (恐らく、平将門の乱なども、こういう現象の延長にあるのでしょう) # 大事なのは、この不満を取りまとめた英雄が、「朝廷=京都=貴族」というシステムと、決別することなんですね。 平清盛がそうですが、武士の大将が京都で実権を握っても、「貴族化」してしまったら、意味が無い。 「藤原」が「平氏」に代わるだけで、仕組みが変わらない。 仕組みを変えるためには、「朝廷=京都=貴族」というシステムを壊さないといけない。 # これを痛いほど自覚していたのが、源頼朝。北条政子。北条時政。北条義時。このあたりだった。 と、言うのが司馬さんの説です。 この人たちは、圧倒的に革命家な訳です。 何しろ、「日本史上、全く前例のない、世の中の仕組み」を作らなくてはなりません。 平氏を武力で滅亡させるんだけど、「朝廷=京都=貴族」に、どれだけ誘われても、そこに参加しない。 圧倒的な武力で実力を握っておいて、「各地の土地所有の割り振り権限」を朝廷から奪って。 「幕府」という新しい政治の仕組みを作る。それも中心地を近畿ではなくて関東、「鎌倉」に置く。 これは全て、ずっと「朝廷=京都=貴族」に虐げられ、理不尽に搾取されてきた、「東日本を中心とした開発農民団体=武士」たちにとって、ついに訪れた「自分たちの時代」だった訳です。 # というこの辺が、「地球に残った人類」「スペースコロニーの民」「コロニーの民の権利」「ニュータイプ」と言った、ガンダムの世界に良く似ていますね。 まあ、当然、過去の歴史的な葛藤から作られたフィクションな訳で、当たり前なんですが... # 頼朝なぞは、挙兵した瞬間は、信じられないことに、総勢20名くらいだった訳です。 それも、「やばい、このままではどのみち平家に殺されるから仕方なく挙兵」だったそうです。 それが、連戦して割と連敗するんだけど、どんどん豪族たち、武士たちが味方についてくる。膨れ上がる。 それは全て、頼朝に「朝廷に隷属しない、新しい仕組み」を期待していたからなんですね。 それを、頼朝は判っていた。 判っていなかったのは、義経だった。 # 義経は、父を平氏に殺されて。(まあこれは当然、頼朝も同じなんですが) 幼かったから、色々苦労をして育ち。 ある時点で、復讐=平家の滅亡、だけを夢見て成人し。 あとは若いながらに戦争の現場に入ってしまったので、政治や土地所有の仕組みが判っていない。 単純に、平氏を滅ぼして、源氏が入れ替わりに京都を、朝廷を、我が物にすればそれで万々歳だと思っています。 なにより、兄・頼朝もそう思っている、と、思っている。 そして、平氏と、藤原氏と同じように、「血縁」であるがゆえに自分も尊重されるべきだ、と思っている。 これはこれ、京都的にはその頃の常識なわけです。 だけど、東国では、違いました。 まだ、長子相続すらちゃんと決まっていない。 兄弟でも武力で戦争が当たり前。 さらには、頼朝に求められているのは、「第二、第三の平氏や藤原氏になって、一族でウハウハになる」ことではなくて。 「東国の開発農民団の利益を誘導してくること」なんです。 東国の開発農民団=武士、からすれば、義経が弟だからって、重宝されて、領地とかばんばんもらったりしたら、噴飯ものなわけです。 このあたりの機微を、頼朝は痛いほどわかっていた。 そして、義経は笑えるほど、判っていなかった。 # ただ、問題は。 その義経が、「戦争の天才だった」ということなんですね。 その天才ぶりが、哀しい輝きという感じですね。 なんかもう、機動戦士ガンダムのアムロであり、鉄腕アトムであり。 つまり、強い、かっこいいんだけど、それが幸せに繋がらない。却って疎まれたりする理由になる...。 そういう、「哀しい不器用な、強すぎる戦士」というヒーロー像の、元祖なのではないでしょうか。 # とにかく、強い。 圧倒的に強い。 数年はかかる、かかっても無理かも、と思われた、「平家を滅亡させて、三種の神器を取り返す」という難行を、 またたく間に達成してしまう。作戦は常に電光石火。独断専行。天才の技。 そして、イッキに武士たちの間でその才は認められ、貴族平民の間ですらヒーローになってしまう... # その有様を、描くのに、司馬遼太郎さんはうってつけですね。 鎌倉時代、という分析や、物語能力に加えて。 何と言っても司馬さんの個性は、なんだかんだ言って「元軍人」ということだと思います。 凄くゆがんだ形で、結局は「戦争行為」というもの事態に興味があって、ある種の愛着があって。造詣が深い。 # この「義経」が、小説として素晴らしいのは、 「鎌倉時代、という新しい、革命的な動きの中で。義経というのは貴種でありながら、野盗風情の仲間しか居ない、という、革新の動きの中でも、更に例外で異例な存在だった」 という、二重構造、入れ子構造が凄く、判りやすく面白く描かれます。 さらにもはや、善悪とかモラルではなく、 「新しい時代を判っている男」=頼朝 「判ってない男」=義経 という、ほぼ抱腹絶倒なすれ違いが、はっきりくっきり判ります。 もう、これは殺しあうしかないんですね... (この延長線上に、頼家や実朝の悲劇があります。そのあたりは「街道をゆく 三浦半島記」が実にすばらしい。) # という視点がありながら、平家物語の美味しいドラマチックな名場面がてんこ盛り。 これは、たまりません。 最後、義経の没落の始まりで筆をおいて、死の場面までは描かない。 そんな手法が実に、司馬さんらしい合理性。つまり、もう司馬さんの描きたいドラマは終わってます、ということなんでしょうね。(あるいは、司馬さんが、飽きたのか) # 実はこの「義経」上下巻。 多分、10歳の頃に生まれて初めて読んだ司馬遼太郎さん作品。 個人的には思い入れがあります。 それからもう30余年になりますが、多分どこかで一度は再読していたんだと思いますが、今回、初めて舐めるように魅力を味わえた気がします。 歳を取るのも愉しいものですね。
2投稿日: 2017.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017_012【読了メモ】(170520)司馬遼太郎『義経』上巻/文春文庫/4-16-766311-2
0投稿日: 2017.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容紹介 悲劇の最期をとげた源義経は、軍事の天才ではあったが、政治の力学にはまるきり鈍感であった。それが破滅へと彼を導いてゆく。歴史小説の巨匠が描く斬新な義経像 内容(「BOOK」データベースより) みなもとのよしつね―その名はつねに悲劇的な響きで語られる。源氏の棟梁の子に生まれながら、鞍馬山に預けられ、その後、関東奥羽を転々とした暗い少年時代…幾多の輝かしい武功をたて、突如英雄の座に駆け昇りはしたものの兄の頼朝に逐われて非業の最期を迎えてしまう。数奇なその生涯を生々と描き出した傑作長篇小説。 --このテキストは、文庫版に関連付けられています。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 司馬遼太郎 大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみち1”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大仏次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。平成5年、文化勲章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) --このテキストは、文庫版に関連付けられています。 本の感想 (オフィス樋口Booksより転載、http://books-officehiguchi.com/archives/4733965.html) この本は昭和40年代に連載されていたものを本にしたものである。 上では、冒頭に藤原長成(通称:一条長成)という中年で、出世の見込めない貴族の話から始まる。この中年の貴族と義経の母となる常盤御前との出会い、幼少期に遮那王として鞍馬寺に預けられた頃の話、奥州藤原氏のもとに行く話へと展開されている。 下では 、源平合戦の一ノ谷の戦い・屋島の戦い・壇ノ浦の戦いにおける義経の活躍、梶原景時との対立が描かれている。軍事的に天才であるが、政治的感覚が鈍く、悲劇に巻き込まれていくというストーリーである。 大河ドラマのストーリーと同じであるという印象を受けるが、昭和40年代から義経の人物像が定着したのだろうか。その点が気になる。
0投稿日: 2016.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
義経も頼朝も義仲も、当然といえば当然だけど、歴史上の偉人なだけではなくて、憎らしかったりマヌケだったりもするのだなあと改めて思った。源氏と平家の性格の違いも知らなかった。 この時代の小説は「君の名残を」しか読んだことないので、どうしても義仲側にたって読んでしまう。先を思うとつらいなあ。 弁慶や文覚や義時や、平家や皇族や、知ってる名前が続々でてくるけど詳しくは知らないので人物相関図が欲しいところ。 下巻へ。
0投稿日: 2016.08.10あたらしい義経のはなし
鞍馬天狗から兵法の極意を授かり、五条大橋で弁慶と渡り合う、そんな講談、おとぎ話じみたエピソードは一切ありません。その代わりに鞍馬山を脱走し奥州平泉へと向かう途中で少年時代の那須与一に出会い、平泉では藤原秀衡との交流があったりします。「流石は司馬遼太郎、そうくるか」と感心するとともに、後の再会への期待が高まります。 にもかかわらず、下巻の那須与一再登場の場面(屋島の「扇の的」です)は1ページほどで終わり、義経との会話もまったくありません。藤原秀衡に至っては、再登場そのものが無し。平泉どころか、平家撃滅後、義経が京を追われた後はあれよあれよという間に生首になって頼朝の眼前に出されているという有様。これは何なのか。前振りだけが多くて、本来の見どころがまるっきりスルーとは。作者の意図がまったく分からない。……と、しばし考えた所で、何かに似ていることに気付く訳です。「ああ、これはジャンプ打ち切り作品のパターンだ」と。 斬新すぎる義経が評判悪かったのか、それとも作者のやる気がなくなったのか、伏線を張って下ごしらえを終えた所で、風呂敷を広げたまま無理矢理終了。そう考えると、なんとなく下巻の体たらくも許せる気がしてきます。弘法にも筆の誤り、司馬の打ち切り。 上巻は面白いだけに本当に残念です。
0投稿日: 2016.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の義経、上下巻読み終えた。 源平合戦がどのような戦いであったか、平家側の心理状況もよく分かり、戦いの描写も臨場感を感じながら読むことができた。 なぜ義経が頼朝に追われ、そして殺されなければならなかったのか、意外と理解していなかったのだが、義経の人物像からそれが十分伝わってきた。 どれだけ才能があったとしても、組織の中で動く以上、政治がわからないといけない。組織で働く方にとっても示唆に富んだ内容だったと思う。
0投稿日: 2015.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ頼朝、義経の出会いのシーンが感動的であったために、兄に従順な義経に胸が痛む… 頼朝、義仲視点で進む章も面白く、各所に挟まれる補足説明も勉強になります
0投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
個性的な登場人物たちの数奇な運命は現在の創作物語に通じるほど特徴的なのにこれが完全にフィクションではないというのが不思議なところ 構成の脚色により物語として描かれているとはいえ、運命を感じざるをえないようなファンタジックな物語が我が国の歴史として存在しているのだからおもしろい
0投稿日: 2015.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎さんの「可憐」の使い方、私には面白く感じられてしまう。義経さんに付き従う部下のみんなは、義経公可憐!って心酔してたのかなあ。いとおかし。
0投稿日: 2015.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経に関してほとんど知識を持ち合わせていなかったので、歴史的背景もすっと入ってこなかったし、登場人物もわからない人ばかり。 それでもおもしろかった。 源氏と平家の複雑な血の関係。人間のいろいろな欲。 弁慶と弓の名手与一の登場。 下巻が楽しみ。 “後世、人前での涙はめめしいものという規律ができたが、この時代、人はよく泣いた。頼朝ははじめてあうこの弟の顔をじっとみつめ、亡父の面影をさぐっていたが、すでに両眼から涙があふれ、見つづけることができない。義経も頼朝をあおぎ、なき義朝はこのようなお顔であったかとおもううち、顔をあげられぬほどに涙がこぼれた。どちらもあいさつのことばすらなく、見つめては泣き、ひたすら無言でいた。この情景は、並みいるひとびとをいやがうえにも感動させた。みなこの情景を待ちかねたように貰い泣きし、悪四郎といわれた岡崎義実などは馬のいななくような声をあげ、一座を主導するかのごとく華やかに泣いた。泣くことにも華やぎをあらわしたいというのが、坂東武者の心意気というものであろう。”
0投稿日: 2014.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻は、義経の母である常磐が藤原長成に嫁ぐところから。 義経を中心にしつつ、鎌倉の頼朝、京に入った義仲にも スポットを当てつつ司馬遼太郎の語る源平時代が繰り広げられる。 義経は、政治感覚が皆無の情に厚い人間として描かれる。
0投稿日: 2013.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家の驕りと源氏の血族間の争いが生々しい。 政治家の頼朝、田舎者の義仲、若々しい義経のそれぞれの人間が見事に描かれている。
0投稿日: 2013.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ大河ドラマの平清盛を見終わった後だし、登場人物を頭に思い浮かべながら読めてよかった。鞍馬にいる時は辛かったんだな。
1投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「戦争は天才、政治は痴呆」と言われた源義経の生涯を描く。 義経には日本人が好きな要素が詰まっている。義経はいくら頼朝に敵意をむき出しにされ、反逆者扱いされても、あくまで兄が自分を理解してくれるということを信じ抜いたことが、民衆の心の琴線に触れ同情を買った。本来一番の功労者として讃え称せられるべき立場であったにも関わらず、逆に「悪」として処刑された。本当の悪とは何なのだどうと言う言葉で締めくくられる。 兄に対する一途で向う見ずな感情や、政治のいろはの分からない、また理解しようとしない義経の少年っぽさ、それに似つかない、それまでの日本史にはあり得なかった戦術で平家を倒した天才的実力、また端正な外見といった点は、義経の持つ愛嬌だ。一方で、政治的感覚が薄いのであれば、それを学びとる姿勢を持っていたのであれば、あるいは別の結末が導かれたかもしれない。義経の美徳としての純粋な、一途な心を持った大人になるのも、いいかもしれない。 義経が幼少期、寺に預けられていたころ、源氏の残党である正近から自らの出生を知らされ、震え上がった。この時の感覚を義経は一生持ち続けたに違いない。血が騒ぐという感覚を大事にしたい。
0投稿日: 2013.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012年の大河「清盛」は、低視聴率で有名になったが、平氏VS源氏について今までよくわかっていなかった自分にとっては見がいがあった。その一方、大河が真実をどこまで語っているか疑問であるため読書により、違う目で歴史について考える機会を持つために、この一冊を手にした。司馬遼太郎だけに、これまたどこまで真実かはわからないが、清盛と義経の関係、北条政子と頼朝・義経の関係は大河とは違う視点からのアプローチだったため、違う印象を受けた。義経だったら視聴率とれていたかもと思わせる作品であった。司馬作品の中でも1、2位を争うぐらい面白かった。
0投稿日: 2012.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日、 「新・平家物語(吉川英治著)」全16巻を読破した が、その後に読んでみたい筆頭として本書を挙げたが、さっそく手に取ってみたものである。 ベタな感想。「むちゃくちゃ面白い!」。 登場人物が被るため、ついつい吉川作品と比べてしまうが、読みやすさや面白さは私にとっては司馬作品に軍配を上げたい。吉川作品も勿論素晴らしいが、文体や表現、言葉が高尚過ぎて、司馬作品に比べると多少読みづらいのである。まあ、吉川作品を読破しておいたお陰で本書をより楽しめるという因果関係もあるのだろうが。 今まで何となく気付いていたのが、源氏は平家に比べて家族や兄弟の結束が弱いということ。 義朝が弟:義賢を長男:義平に討たせたり、保元の乱において父:為朝や弟数人と袂を分かったのはその代表例であるが、本作品においても、頼朝は顕著である。義経を警戒して見ており、叔父の行家を軽んじ、範頼や義円らの弟も粗末に扱い、従弟の義仲にははっきりと敵対…。棟梁がこれではまとまるものもまとまらない。肉親よりも北条など関東武士を重んずる姿勢。なればこそ三代で潰え、北条にとって代わられる訳である。 対して平家は清盛を中心に兄弟仲や叔父甥間などの親族関係が実に良い。大河を見ていて平家ファミリーが談笑しているシーンを見ると心が温まる。 この辺りが、私が頼朝を好まず、清盛を贔屓にしたい点なのかもしれない。 以下に本書の特徴を紹介したい。 ・吉川作品においては義経主従として頻繁に登場した鎌田正近が、本作品では義経(当時は牛若丸)に出自を教えるためだけに存在し、その後は登場しないという設定。 ・吉川作品においては吉次と共に奥州に向かう途中、熱田神宮で元服をするという描き方だが、本作品では吉次との道中という点では同じであるが、京都で夜に1人で行うというもの。 ・吉川作品と同様、那須与一が奥州へ赴く道中というかなり早い段階から登場。他作品(例えば2005年の大河ドラマ「義経」など)では屋島の戦いで忽然と登場することが多いが、両作品とも早くから伏線をひいている。 ・弁慶の登場は、義経が奥州から一度京都に戻り、清水詣での時に声をかけてきたという設定。五条大橋や刀狩のエピソードは一切なし。また、熊野の別当:堪増の子とはっきり明言している。のち、平家追討の際にはその血すじを如何なく利用して堪増を味方に引き入れるのだろうか。 ・義経主従が、奥州を経ち頼朝に拝謁するまでは伊勢三郎と二人という設定で少々淋しい。後に奥州から佐藤兄弟が追い付き、弁慶も京都から合流。 490ページもありそこそこのボリュームであったが、数時間で読了出来た。下巻も楽しみだ。
0投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこの小説の源義経は、半ば阿呆だ。そうした独特な人物描写に面食らうあまり、拾い読みをしてしまって、結局読んだのか読んでないのか、判然としない。 人の感情の機敏に疎すぎる本作の源義経には、一種の愛嬌があり、悪くない。 が、人を将棋盤の駒か何かように観ている後白河法皇のような人物には、反吐が出る。 人を一体何だと思っているのだ、お前は一体何様のつもりだ、策を巡らして愉しむのは勝手だが、信義と情誼に欠けすぎだろう、などと憤慨してしまった。 追記:その後、『夢の守り人』のシハナに対しても全く同じ憤慨を覚えた。
0投稿日: 2012.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の教科書にはただ淡々と「鎌倉幕府を作った男」とだけ書かれている頼朝の見る血縁関係と義経の持つ血縁に関する純粋な気持ちの対比が興味深い一冊。兄弟同士が血で血を洗う戦国時代が訪れるのはこの頃から定められていたのだと感ぜずにはいられない。
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎はまるでその時代を見てきたかのような文章を書く。歴史小説というより、むしろ伝記に近い。郷土愛ではなく、あるのは人間への愛か。
0投稿日: 2012.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ全2巻。 言わずと知れた司馬遼版義経。 あんま好きじゃない司馬遼だし、 たった2巻で義経が語れるかと思っていたので ずっと敬遠してた本著。 源平合戦じゃなくて義経に焦点を合わせて書かれているので、 それほど物足りなさや薄さは感じなかった。 それほど。 むしろ、いわゆるヒーロー化された義経じゃなく、 人間義経が客観的に書かれている感じでとても理解しやすく、 今まで個人的にホワッとしてた部分が腑に落ちた。 説教臭さもそれほど感じず好感。 が。 やっぱり少しカチンときたのが 物語序盤の那須与一のくだり。 ここだけ小説的。 その後、客観性を大事にって思い返したのか、 せっかく用意した小説的要素を全く活かさず。 こういうとこ嫌い。 どっちつかずで。 物語として十分面白いのに、 きちんと書かなきゃってなる感じが。 きちんと書きたいなら最初から。 物語として作りたいなら最後まで書いてほしい。 賢しげでイラッとする。 あと、 歴史的に不明な所を サラッと割愛してる感じもちょっと鼻につく。 そここそ書けよ。小説として。 と思う。 そこまで嫌いな本じゃなく、 どちらかと言えば好きな本だったけど、 著者をまた嫌いになった。 つくづくこの人が評価されてる意味が分からない。
0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ源頼朝が、平家討伐の頭と世間が認めるまでを上巻で描く。異母兄弟の義経は兄、頼朝の家臣でしかなく大きな力と周囲には今だ、認知されていない。彼の才能をひそかに恐れる頼朝がどのような行動にでるのか、策略家の頼朝は運(時代の風)も味方につけ巨大な力を持つにいたる経緯はちょっと出来過ぎている。
0投稿日: 2012.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分は義経に魅力を感じなかった。 源義経と言ったら、一の谷の合戦、屋島上陸など天才的な軍略家である一方、純粋すぎる政治的愚者として、結局実兄の頼朝の討たれるという、悲劇のヒーローとして古今日本人の好きな歴史人物として脈々と語り継がれてきた人物だろう。 自分はこのような「時代、運命に翻弄されてきた」人物類型には魅力を感じない。そういうウエットな悲劇的人物よりも「国盗り物語」の斎藤道三、「新史太閤記」の木下藤吉郎のように軍事能力以上の圧倒的な対人能力、政治的な智力、構想力、どこか狂言のようなカラッとした明るさを身にまとっている人物に一人の人間の存在を越えたような底知れなさを感じ、憧れ、魅力を感じる。 また頼朝にもさして魅力を感じなかった。ただ平家を打倒する以前から東国武士中心の政権を作ろうとする構想を抱いていたのは凄いと思った。結構早い時期から北条時政や政子の影響力が強かったのだと知った。 本書で一番魅力的だった人物は後白河法皇だ。位打ちなど、政治が趣味というように、退屈な公家の生活からその政治力、頭の回転の速さで、力を持つようになった武士達の世界を一段高い所から眺めている様は、魅力的であった。
0投稿日: 2012.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ源氏と平家の戦いと単純に思っていたこの時代も、実際はとても複雑で様々な思惑が入り乱れる不安定な時代だったことを知った。 そんな折りに現れた義経は、父義朝の復讐のために戦う。 感情的、直情的な義経と、武家全体を俯瞰的に見、冷静で慎重な頼朝との対比が、当時の血縁関係を超えた争いを行なっていた武士の姿を映し出し、読んでいて痛々しい。 鎌倉御家人たちの思惑に絡められている頼朝が、義経の首を見たとき、彼はどう感じたのだろうか。
0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが司馬遼太郎というかんじ。典型的な義経と弁慶のドラマなどは描かず、司馬独自の史観とおそらく調査の裏付けに基づきストーリーを組立て、十分に魅力的な義経の物語になっている。
0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
平家に敗れた源氏の子孫達が平家に復讐をする。世の権力者が目まぐるしく変わる展開の中で、人を巧みに利用する智者、田舎育ちの豪傑、復讐のみを生きる目標にしている悲劇の末裔など、色々な立場・性格の人物が登場する。頼朝のような、自分の利益のみを考えて生きる者が頂点に立つのか、義仲のような気のいい豪傑が頂点に立つのか、社会の縮図を描いてる作品だと思います。頼朝に操られて死ぬのは嫌だな。それに対応するためには、頼朝のような、利益を極限に考える視点を持つことが大切だと思う。
0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史上のある種の美談になっている源平合戦。 この小説はその合戦のまったく違う一面を教えてくれます。 政治的などろどろとした争乱を描き、イメージとはまったく違う義経像を想像させてくれます。 天皇や源氏また公家などこの時代の人たちは自分の血に誇りやこだわりをもって生きている。それはすごい。 ある種のWASPに通じるエリート思考です。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なぜ奥州藤原氏は落ちのびてくる負けるとわかっている義経をかくまったのか? 歴史好きの社長のこの疑問に答えるべく読み始めましたが、落ち延びるところまでは書かれていないので残念でした。 永遠のヒーロー源義経に対する見方が変わった作品でした。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ一時代に美術や音楽の天才というものは必ずいるものだ。 芸術の才能は人の才能の中で貴重ではない。 だがしかし、人の才能の中で最も持ちにくいものがある。 それが「軍事的な才能」つまり兵隊さんの能力である。 これは一時代どころか、一民族に一人か二人いればいいほうで、 それでは、日本人(大和民族)では誰なのかという事になると、 間違いなく名前があがるのが、この義経である。 上巻ではまだその真髄は見せられない。 日本人ならだれでも知ってるであろう頼朝と義経の物語はその才能を中心にくるくる旋回していき、そして日本人が誰でも知ってるであろう哀しい結末と誘うのである。
0投稿日: 2011.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた義経です。 ちょいちょい文章の流れを止めて、蘊蓄を傾けてくれるので、義経のことを大体のことは知っている人が読むとへえ〜ということが多いです。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の読書人生を変えてくれた作品。中学三年生にしてこの本で初めて頭に情景が浮かぶという体験をした。(きっと、それは大河ドラマの影響もあるのだろうけれども)本を読むことの楽しさが初めて分かった作品だったように思う。思春期の自分に義経の姿を重ねて自分もこんな風に、世に名をあげたいと心から思った。私は、女に生まれてきたが、この願望は未だに持っている。義経の強く悲しく儚い一生がとてもうらやましく思う。司馬作品が私にあっているのか、他の作家の(歴史)作品には感情移入して読めないことが多かった。この作品から私の司馬作品読み漁りが始まるのだが、高校に入ると忙しくて読書の時間もとれなくなり今に至る。今は、少々時間ができたので関ヶ原を読み進めている。だが、やはりあの頃の義経に勝る感動は味わえないかもしれないと思っている。作品的にも19歳になってしまった私の心的にも。
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時の生活風習や価値観、源氏と平家の違いなど読んでいておもしろかった。義経といえば悲劇のヒーローと言うイメージだか、司馬遼太郎の描き方では、軍事の天才だが政治能力の欠如した人物として描かれていて、頼朝や後白河法皇に利用されていく様がおもしろい。ただ終盤は駆け足で話が進むためもっとじっくり読ませて欲しかった。
0投稿日: 2011.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻の感想です。 義経というと戦国のスターの一人という印象でしかとらえていなかったが、その才能が極端なものであり、決してバランスの取れた人間ではなく描かれていたのは新鮮だった。 戦はできても政治はさっぱり理解しない。それ故に兄と対立しても対立する理由も察せない。とても甘い人物だったのだと感じた。ただこの時代に出来る限りのことをやりきって生きた姿は、完璧な人間でない分だけ心に残った。
0投稿日: 2011.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経ってこんな人だったの? かなりの女好きじゃぁないですか(笑) 時代小説って言葉遣いが難しくて、読み辛い本もあるけれど この本は読みやすかった。
0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ源義経―――。彼ほど、華麗な逸話に彩られた武将もいないのではあるまいか。そして、華麗であるだけではなく、どこまでもひたすら哀しい。義経の名を口にのぼす時、人々は、一の谷や屋島、壇ノ浦と、数々の合戦において彼が華々しく疾駆したことを思い浮かべると同時に、兄・頼朝から疎まれて、北へ北へと落ち延びていく敗残の姿をも思わずにはいられないのだ。それは現代人のみならず、源義経と同時代を生きた人々にとっても同じことだったかもしれない。 我々が源義経に対して抱く、颯爽かつ貴公子然としたイメージとは裏腹に、本書『義経』(司馬遼太郎)での彼ときたら、どうにもこうにも甘ったれで手に負えない。兄・源頼朝に向かって「兄上、兄上」とすり寄っていきそうな勢いなのである。その上、政治感覚にも疎く、平家打倒を唯一の悲願とするばかりで、源氏の同族内においても、後白河院に対しても、上手く立ち回ることが出来ないでいる。自分が源家や北条家に連なる者たちから、どのような目で見られているかの内省もできず、ゆえに空気を読むことも苦手。不器用の塊のような男なのである。 疎まれても疎まれても兄を慕い続ける義経とは裏腹に、その当の兄である頼朝は、あくまでも義経に対して冷淡だ。頼朝は傍流の源氏、例えば新宮十郎行家や木曾次郎義仲といった面々にも親愛の情は見せなかったが、この腹違いの弟に関しては特に警戒を怠らなかったといえる。 石橋山で敗残の将となり、安房にて再起し、鎌倉の地で武家政権を発足させたばかりの彼は、妻・政子の背後にある北条氏という大族の支援によって、いわば鎌倉大本営の元帥となることが出来た。けれども当時の頼朝自身には、後ろ盾となるような濃い血縁がいなかったのである。頭ノ殿(こうのとの:源義朝)の遺児として、源氏の棟梁を務めていながらも、下手をすれば北条家に権力が移行してしまうかもしれないという危惧が、頼朝の中には少なからずあったであろう。したがって富士川の合戦の際、義経が自分のもとに馳せ参じた時には、彼はすこぶる感激したのである。だが、その兄弟邂逅におけるお互いの感激にもおのずから温度差があって、義経が兄との出会いを無邪気に喜んでいる反面、頼朝は、自分の源氏棟梁としての地位を確固たるものにしてくれる手駒として、義経の到来を喜んだ部分があるのだ。 義経の着陣を配下から告げられた時、頼朝はこう強調することを忘れなかった。 「その路上の者はきっと九郎に違いない。母はいやしき雑仕女(ぞうしめ)ながら」 義経の母・常盤御前の出自をチラリと周囲にのぞかせておくことで、自分の武名を慕って参集する兄弟がいることと、その兄弟が自分よりもはるかに格下であることを印象付けたのである。これより後、義経と頼朝の意識のズレが埋まることはない。むしろ深い深い溝となっていく。その溝があるせいで、兄に認められようと義経が懸命になればなるほど、頼朝の方では、秩序を乱す行為、出すぎた真似、俺が俺がという功名心として処理されてしまうのだから、やりきれない。 司馬遼太郎は、この『義経』の上下巻を通して、源氏と平氏の全体的な性格の違いを解説している。それは、端的に言えば、平氏の同族に対する情の深さに比べて、源氏のそれは浅いわけではないが、どこか手厳しく辛辣だということである。 東国の源氏武者の強悍(きょうかん)で復讐心のつよいのにひきくらべ、涙もろさは西国の平家侍の共通性であったろう。かれらはこの繊細な心情美のゆえに、のちに「平家物語」の作者に美しい主題をあたえた。 とあるように、荒夷(あらえびす)の雰囲気を濃厚に残している関東の源氏と半ば公家化した京の平氏とでは、同じく武家ではありながら、決定的な性格の違いが生まれているのである。それを個人に問題に還元すれば、配流先の伊豆で成長した兄・頼朝と、鞍馬山の稚児として狭い世界で生きてきたものの京育ちには違いない義経の性情の違いとして現れてくるわけだ。 また、義経が鞍馬から奥州へと逃れ、多感な時期をその奥州で過ごしたことも、頼朝と義経を全く違う性情へと導いたのかもしれない。剽悍な坂東武者らの間で、この時期、「京都の公家政権何するものぞ」という機運が高まりつつあった一方で、当時、化外の地とされていた奥州では、京という圧倒的な王土をまえにして、いまだ強い憧れと遠慮と畏れとがあり、その心情が、源義経という京育ちの若者を奇貨としたともいえるのである。本書でも書かれていることだが、奥州人は京の文化を少しずつ取り入れる為に義経を歓待した。とりわけ京風の容貌を獲得する為に、奥州人は彼の血を引く落胤を欲したのである。数年の奥州滞在の後、義経は鎌倉の頼朝のもとへと参じるが、京文化の中で幼少期を送り、今また、京への憧憬を持つ奥州文化で成長した義経と、鎌倉政権を樹立させようとしている頼朝の間には、基本的な考え方において深い断絶があったのである。 平家を打倒したいという悲願は同じであったろう、しかし義経が、平家を除いた後にすべきこととして、公家文化そのものの否定を視野に入れていなかったのとは異なり、頼朝は、平家なき後の世は武家が治めねばならないと考えていた。そこに、この兄弟の分かり合えない部分があったということなのだろうと思う。 ありえない話ではあるが、この兄弟が、流人生活を送るにしても一つ処で過ごすことが出来ていれば、それも二人が共に関東で育つことが出来ていれば、この兄弟の結びつきは非常に堅固なものになったかもしれない。兄弟が反目せず合力できれば、それは、頼朝にとっては北条家とは違う系統の後ろ盾が出来るということであり、そこからの支援で、鎌倉幕府は三代で途絶えることなく、もう少し長く運営された可能性もある。詮無きことながら、源平の物語を読むときは、そんな「もしも」を想像してしまうのである。 それにつけても、源氏と平氏の両方を手玉にとりながら貴族社会を守ろうとする後白河院の強(したた)かさ。さすが「日本国第一之大天狗」と評されるだけのことはある。そして、後白河院以下、京の並み居る公家連は、鄙(ひな)からやって来た武者達を表面では巧言で持ち上げながら、裏面ではあげつらい、指をさして嘲弄し、軽蔑するのだ。 アレアレ、アノ、アヅマエビスドモヲ、ゴランジアワセヨ。ヒトトモ、オモワレヌ、オロカナ、フルマイニテ。マコト、ミヤコノ、フウモ、シラヌ、ウタテゲナル、モノドモヨ。ホホホホホ………。ヒヒヒヒヒ………。 雅(みやび)の世界に住む公家は、最早、土から切り離された種族である。鄙において土を耕し、馬を肥やし、食物を育てている者にこそ、社稷(しゃしょく)の神の守護と寿(ことほぎ)があるが、鄙(ひな)の世界を捨てて雅(みやび)の世界の住人となった者は、土地と五穀とを司る神の守護と寿はもう得られない。公家たちは、耕さなくなった引け目負い目を隠蔽するように、自らが権威となることを画策する。雅が尊く、鄙が卑しいと決めてしまうことで、彼らは社稷の営みから離れてしまった自分たちを正当化しているのである。その正当化の表れが坂東武者や都風に振る舞えない者に対する嘲弄なのである。 源平の戦いは、単に源氏と平氏の相克というわけではない。それは、公家から武家への実質的な権力移譲であり、京(近畿)から鎌倉(関東)へという政治の場の歴史的な転換であり、雅に対する鄙の、武力を伴う挑戦でもある。司馬遼太郎のこの『義経』は、そういったことに気付かせてくれる様々な要素に満ちている。 平成二十二年九月一日 読了
0投稿日: 2010.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。 血を大切にするのでしょうか。 血を愛する義経と 権威主義の頼朝。 義経の才を恐れつつ、黙認しようとしますが 彼の才能は発揮されていく。 自然に愛されていく。 その思惑など、義経の知られざる物語など すごく面白いです。 血統主義を嫌う頼朝だけど、 結局は源氏の血を尊とんでいる部分は なんか納得できないけど。
0投稿日: 2010.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログシバリョーの名作、上・下の全2巻です。 実はかなりの酷評を浴びているようですが、義経ファンとして、決して一押しではないけど(笑)、やはりおすすめします。 さて、多くの義経像というのは、やはり『義経記』に依拠している部分が大きいと思います。 エンターテイメント性の高い華やかさと、ドラマチックな悲劇的運命。 「それは後世で作り出された義経であって、実際は違う」という話も多いですね。 で、ちゃんとした研究は学者さんにお任せしつつ。 ほとんどの人は、現実の義経を知りたいと思いつつ、夢もあまり壊したくない、というのが本音ではないでしょうか? 将雪もそうです(頭をひねって史実を考えるような本も好きですが)。 そして、この『義経』は実にバランスがいい! ほどよくヒーローとしての義経像を壊しつつ、しかし魅力を感じてしまうのです。 ここで描かれる義経は、政治力の極端に欠如した、一本気な青年です。 彼は戦においてでしか、その天才性を発揮できません。 しかも彼はただ、父の仇討ちという一種の正義的快感だけで動いていたのです。 逆にその純粋さが素敵ではないでしょうか? この作品は義経一番の涙シーン、静御前との別れなど、逃避行が始まってからの記述はほぼありません。 なのに、どの義経よりも、読後に切なくなるのがすごいです。 政治と無縁のピュアな心を、あなたはどう感じるでしょうか? 完璧な義経を描いた村上元三さんの『源義経』と、欠点だらけのシバリョー版『義経』。 どちらを読んでも義経ファンになってしまうのは、やはり義経自身の魅力がそうさせるのかもしれません。
0投稿日: 2010.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経・・・かわいそう・・・悲劇の人・・・ って言いたいけど、 この作品での義経は中々クセのある奴で描かれていて そこまでかわいそうに感じなかった。まぁしょうがないよね。って感じ。 天下を取るのは政治力に長けた人って どの世界でもいえそうだね。
0投稿日: 2010.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい義経像に出会った本。歴史物で取り上げられる人物像には「実際と異なるのではないか」という懐疑心を持つことがあるが、資料研究に真摯な司馬氏の本だと、素直に安心して受け入れられてしまう。 また、昔、日本の東と西とでは随分と文化が異なっていたということを初めて知った。
0投稿日: 2010.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ大河とは全く異なります。 歯がゆくてなりませんでした‥ 個人的に「四条の聖」の話が切なく、気になりました。
0投稿日: 2009.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎に作品を読んだのは初めてだったが、非常に読みやすかった。 その理由として、描かれている人物が非常に人間くさいからだろう。今の私達と変わらず、喜び、怒り、嫉む姿は親近感を覚える。 特に、自分の中で伝説的なヒーローであった義経が人間くさくてよい。
0投稿日: 2009.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ上は、遮那王の話がちょっと少なかったのがざんねん。というか、きっとほんとに歴史に出てきた時期って、人生後半のちょっとだけだったんだなぁ。頼朝のイメージ変わります。まぁ義経もだけど。でもやっぱ伝説だな。すごいな。
0投稿日: 2009.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「海上の平家軍は瀬戸内海一帯に浮かんでいるにせよ、 その本営は陸地にある。讃岐(香川県)の屋島である。」 『義経』(司馬遼太郎著 文春文庫) 「屋島は大坂湾の湾外、四国の東北角にあり、もしここに十艘の船でもあれば そして死士を百騎でも乗せればその本営を覆滅できるではないか。」 「平家は、讃岐(香川県)の屋島にいる。 屋島は四国の東北角にあたる。」 「陽が落ちたころから大坂湾を吹く風の方向が一変した。 それまでは南風であったが、北風に転じ、雨をまじえ、 刻々風速が強くなり、樹木をはげしく鳴らしはじめた。」 あえて大暴風雨に出陣を決めたのは、 制海権を平家に握られている以上、凪いだ海を渡れば必ず討たれるからだ。 このように「義経」が戦法に長けていたのは衆知の事実。 『司馬遼太郎の日本史探訪』(司馬遼太郎著 角川文庫)でも 「義経」の戦法が当時としてはいかに優れていたかが書かれている。 一、騎兵の集団戦法 一、奇襲攻撃 一、敵の虚をつく これはその後の戦国時代における、武将の戦法に通ずるものを感じる。 「三日を要する行程を、その数倍もの速さで四国に渡った義経は、・・・ ・・・屋島の対岸牟礼から古高松のあたりに迫った。・・・・・ ここであたり一帯の民家に火を放つ。大軍に見せかけるための策である。」 まさか背後から迫ってくるとは予想していなかった平家は 屋島を捨て、あわてて退散する。そして壇ノ浦へ。
0投稿日: 2009.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ平家の滅亡〜鎌倉幕府の成立、頼朝と義経の争いという話を人間の内面の感情、世論などの面から描きだした作品。 戦の天才としての義経と政治の幼児という相反する両面を持っていた義経が頼朝から妬まれ滅んでいったストーリーは 人間がどれだけ合理的になろうともやはり人の感情で政治は動くのだと考えさせられる。 政争は今でもそんな要因があるのだろう。
0投稿日: 2008.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の歴史書、1977年、2004年、2005年。勧進帳などで知られる義経の話。頼朝、義経、義仲の源氏兄弟を中心に物語が展開していき、その中で弁慶や余市との出会いがある。平家と源氏における親族に対する感情はまったく異なり、源氏では兄弟といえども敵という観点が面白く、また、それが歴史の大きなポイントとなっているようだ。本書では、義仲が京を制すまでが描かれている。
0投稿日: 2008.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史小説が好きです、と言いつつ なぜか司馬遼太郎を心のどこかで敬遠してた。 古本屋で見かけたので立ち読みしたら、見事にはまった。 ◆ 義経を読めば奥州藤原氏が出てくるだろうという読み。 そして見事に当たった。こういう描き方もあるのか、と思った。 どのくらい資料に基づいて登場人物を作ってるのかは分らないけど どの主人公も人間味が溢れてて面白い。 ◆ ところどころ昔っぽい表記があるけど、別に気にならない。 特に読みにくいというわけでもない。 ストーリー展開のテンポが良い。気に入った。 早く下巻も読みたい。
0投稿日: 2008.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々なエピソードを交えて話は進んでいく。 時代背景を理解しやすく、読みやすい。 義経の大活躍を見ることができるのかと思ったら、政治的に扱いにくい人物として、活躍の場は無し。 ばしばし戦うイメージだったから、司馬遼太郎「義経」の姿は新鮮。 下巻での活躍を待つ。 2008年1月5日読了
0投稿日: 2008.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近はしばさんの読み物にもはまる。。 源氏という血の重さ。人や政を動かす人格、政治手腕、この頃から上にたつ人はやはり非凡な才能の持ち主だなあ、と今更ながら実感。でもやっぱ純粋でまっすぐな義経には魅かれます。で、やっぱり英雄豪傑は男ばっかだなあと、これまた今更ながら男社会を実感。最近それが感心事。
0投稿日: 2007.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬さんの義経です。 上巻は義経の幼少期〜木曽義仲の入京まで。 そんなわけで、源氏の旗揚げがメインとなっていて、義経の活躍はほとんどなし。 むしろ頼朝と義仲のほうが目立ってる。 個人的に巴御前のファンなので、その登場をどきどき待ったのですが、結局彼女は登場しませんでした。無念。
0投稿日: 2007.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとって初めての司馬遼太郎さんの本。 義経ってほんとにまっすぐすぎて猪突猛進すぎる。よく言えば純粋。悪く言えば子供。戦のためには無茶と思えることも、自分の考えを最後まで押し通す。それも頼朝の弟とはいえ、妾の子供として生まれてきたし、でもお兄ちゃんに認めてもらいたいがためのことなのかな。弁慶をはじめ、周りの家来が大人です。 難しいと思って読んだ本だけど、意外に読みやすい。
0投稿日: 2007.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎のすごさが分かった気がする一冊。 「現場を見てたんですか!?」と思わせるくらいの細かな描写、心理状況が書かれている。 義経のことは名前程度しか知らず、予備知識はゼロの状態で読み始めた。(大河ドラマすら見てない) 私は本を読み始めて最初に意識することは「自分の中で登場人物の人物像を作ること」である。この作業がすんなり出来るか出来ないかで、以降の読み進めるスピードが大きく変わる。 歴史モノはこの作業に時間がかかってしまいそうなイメージがあって、今までは避けていたのだが、この本は違う。 人物像を想像するのに充分な描写・心理状況の記述がある。 だから分かりやすい。 目の前にその時の状況、人物の心理・表情まで想像させる。 これが司馬遼太郎の上手さ・凄さというコトなんだろうか。。。 一冊目にこれを読んだのは正解かな。収穫大。 というコトで、 ☆☆☆☆☆で。
0投稿日: 2007.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ義経好きと見せかけた頼朝好きなんですが、大河義経で「あー義経ってさあ…もっとばかじゃね?」と思って手に取った本。※大河原作は宮尾の方ですよね。
0投稿日: 2007.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ源氏の棟梁の子に生まれながら、鞍馬山に預けられ、その後、関東奥羽を転々とした暗い少年時代…幾多の輝かしい武功をたて、突如英雄の座に駆け昇りはしたものの兄の頼朝に逐われて非業の最期を迎えてしまう。
0投稿日: 2007.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が一番最初に読んだ義経の小説。有名な歴史小説家、司馬遼太郎先生に「義経」を書いて頂けて嬉しいです!一番最初にこの本に出会ったのは中学生の頃で読んでいて難しかったのですが大人になって読み直しました。 司馬先生の義経は悲劇の英雄、義経!というより、人間味ある義経です。なんだか子供みたいで可愛いです。 印象に強く残っているのは、義経と梶原景時の言い争いです。景時が先陣をお願いした時「来た」と心の中で思った義経がなんだか景時への嫌な気持ちが露骨に出てておかしかったです(笑) あと残念なのは義経の都落ち後からの内容が短い・・安宅関も静の舞いも書かれてないのです。そして奥州平泉での最後も・・。義経の名場面を司馬先生の義経でも読みたかったなぁ。 上下巻あります。
0投稿日: 2006.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻。 最後に頼朝が言った、「悪はほろんだ。」そして人々の言った、「悪とはなんだろう。」の課題がどの時代でも当てはまる。 司馬遼太郎はやはり読みやすい。 しかし、義経記であるのに、義経の最後の落ちぶれようはほとんど書かれていない。英雄でいたせたかったのだろうか。結構悪の部分も書かれてあるのにね・・・。まぁ頼朝も良いようには書かれていないけれど。 学生の時に勉強する歴史のなかでこういう本を読めば良かったんだろうなぁ。 この場合、勝ちは手を出さずに謀略し続けた第3者の法皇だろう。 歴史の教科書では頼朝の勝ち、としか分からないからね。。
0投稿日: 2006.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好きvvv義経ハマっていちばん最初に買って、難しくてwそれでも何回も読んだんね(*'ー'*)少し難しいけどやっぱ有名な人が書いただけあっておもしろい(*'ー'*)
0投稿日: 2006.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ大河ドラマが義経だった時に読んだものです。こ、こんな人だったのか・・・!確かにこんなんじゃ兄上に嫌われるよ、義経さん・・・!(全上下巻)
0投稿日: 2006.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ所謂古典常識がちょこちょこっと勉強になります。那須与一。弁慶。木曾義仲。一の谷。屋島。壇ノ浦。安徳帝の入水。これらトピックを生々しく文章化、小説化できるのが筆者のすごいところ。 ・・・しかし、この義経をタッキーがやったのか。。^^;
0投稿日: 2006.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜか上巻のみ。面白かったのになぜ?途中で別の本が読みたくなったらしい。。。もう一度初めから最後まで読みたい。
0投稿日: 2006.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ文庫で上下巻。絵本や少年向きの本(題名や出版社は不明)で子供の頃から義経好きだったので、高校時代に叔父の部屋で見付けて手に取ったが、期待したような「悲運の天才」として書かれていなくてがっかりした記憶がある。今読み返せばまた違う面白さを見付けられるだろうか?
0投稿日: 2006.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログただ判官びいきに書かれているのではなく、義経という人物をとても人間らしく、飾らずに書かれていて改めて司馬氏のすばらしさに感動しました
0投稿日: 2006.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史について、とにかく、知らなければ!!と思い、たまたま読んでいた、萩尾望都さんの「あぶない家の丘」に義経のお話があったので、読んでみることに。 中学生の時に、司馬遼太郎を読んで以来、わからん・・・と苦手意識をもってたけど、すごい、わかりやすかった!!しかも、すっと映像が頭に入ってきた。
0投稿日: 2005.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本史上、最も平安が続いた平安時代の末期から、鎌倉幕府成立までの源義経(みなもとのよしつね)と藤原氏と源氏と平家と朝廷の物語。頼朝(よりとも)の命を受けて戦っていた義経は、いつの間にか、頼朝を攻撃する側になって、いつの間にか、朝敵になり、最期は頼朝の指令によって殺されることになる、ちょっと江戸幕末にも似た時代が変わるときの悲劇です。
0投稿日: 2005.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎著の作品で最初に読んだもの。 それ以来、司馬遼太郎ファンになったくらい影響力が大きかった。 歴史小説なのに、主人公の心の動きに入り込める文章は必読☆
0投稿日: 2005.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ鞍馬山での義経は、とてもかわいそうでした。大河ドラマで熱演していたお坊さんが、何やらいかがわしく見えました(^^;) 感想はこちら。 http://xxxsoraxxx.blog11.fc2.com/blog-entry-35.html
0投稿日: 2005.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻にわたって,義経は馬鹿だ,と言い続ける小説.義経論に対する司馬の見解が「義経および取り巻きが馬鹿だっただけ」というもので,それを言うために書いたような本である.弁慶の活躍などはまったく登場しない.
0投稿日: 2005.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKで放送中なので慌てて読みました!上・下と2巻だけなので大事なシーンが大幅にカットされており期待したよりガッカリでした。でも司馬遼太郎は面白いよ♪
0投稿日: 2005.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ義經といへば、辨慶と牛若丸の話で知つてゐる人が多い。 私も知つてゐることといへば、 源平の戰ひでの「ひよどり越え」だとか「屋島の戰ひ」だとか、 兄・頼朝に追はれて、平泉の藤原を頼つて逃げたものの、最後は殺されてしまつたとか、 一説によれば大陸まで逃げ延びて、チンギス・ハンになつたとか、 せいぜい、その程度のことしか知らなかつた。 この小説は、何故義經が兄・頼朝に討たれることになつたか、がよく判るやうに書かれてゐる。 要約して云つてしまへば、次のとほりだらう。 義經は戰術能力に關しては天才だつたが、戰略やましてや政治についてはまるで子供だつた。 兄は源氏といふ武家の棟梁としての立場からものを考へたが、義經にはまつたくその考へ方が理解できなかつた。 つまり、兄は武家政治を行なふ上での組織や規律を築かうとしたが、義經は目の前の戰にしか興味がなかつたと云へる。 そして、兄との血の繋がりを過大視しすぎた。 一言で云つてしまへば、義經はまるで子供のやうな男だつたといふことだ。 しかし、さうは云つても、その戰術勘は天才であつた。 騎兵の機動力を驅使した奇襲戰法といふものは、 義經が「ひよどり越え」で採用するまで誰も行なつたことがないらしい。 それどころか、義經以降では、信長が「桶狹間」で行なつた以外にはなく、 その次となると日露戰爭で秋山好古が採用するまで無かつたさうだ。 まさに天才と云つても過言ではない。 この作品は義經の逃避行についてはまつたく描かれてゐない。 作者に義經の悲劇を描く氣持ちはなかつたやうである。 私がこの作品で一番魅力的だと感じたのは、後白河法皇である。 この人を中心としてこの時代を描いた作品を讀んでみたいと思つた。 2004年12月15日讀了
0投稿日: 2005.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歌舞伎の「勧進帳」を見て、源義経に興味を持ったので、司馬遼太郎の義経を読んでみました☆ 最初はそこまで期待しないで読み始めたらかなりはまった(笑) 上巻を読み終わって、今は下巻に移動したが、もちろんフィクションが入ってるのは分かるけど、電車で読みながら何回も泣きそうになった…(笑) あの時代は血(血統)に対する信仰心とかが強かったんだなあとか思って、映画「トロイ」とかの「忠誠心」モノに弱い私のストライクでした。もちろん忠誠心とかだけじゃなくて、みんな自分の利害とかで動くんだけど… やっぱり司馬遼太郎はすごいなあ〜☆☆☆
0投稿日: 2005.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻おわり。 次早く下巻読まないと、大河まで間に合わないっ! しかし、司馬遼の書く義経は、よわっちー感じがするよ〜。 ちょっと、私の中の義経像と違うから、ギャップに戸惑い気味。
0投稿日: 2004.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり日本人は、判官びいきなのです(笑) なんていうか、かわいそうだよね。別に反逆するつもりは全然なかったのに、うまいように朝廷に利用されちゃって。 そこがまた、後世の人々に愛されるゆえんなわけですが。
0投稿日: 2004.10.11
