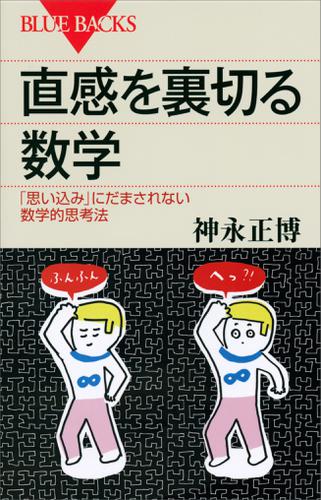
総合評価
(19件)| 2 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の時間に読んでいたら、担任の数学の先生に褒められた。体育の見学中に読んでいたら、体育の先生に取り上げられた。
0投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
証明の美しさを知り、数学の面白さを感じた。 ・パロンドのパラドックス 期待値がマイナスの2つのゲームを組み合わせることで、勝てることがある。 ・ヒストグラムの線引境界を操作すると、全体的にはプラスでも、各階層の平均値は下がることがある。 ・ジップの法則 2群のデータを両対数グラフでみることで、その傾きから何乗則の関係化が分かる。 ・ベンフォードの法則 数字の使用頻度はべき乗則+定数に従う。粉飾決算を見破る。 ・待ち行列の時間 コンビニのレジ打ち店員が一人から二人になると、待ち時間は半分よりも更に短くなる。 ・否定も肯定も不可能な命題がある。連続体仮説とZFC
0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学の興味の引ける現象をまとめている本 慣れているのもあれば知らないのもある。知らないのは説明しにくいものが多いね
0投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に読みやすく面白かった。 モンティホールや四色問題は有名なお馴染みだが、平均の見方や確率的に分の悪い負けゲームを2つ組み合わせると勝てるゲームになる。などの話は勉強になった。
0投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ直感って役に立たないんだなと思った。 僕はモンティホール問題なんかは、直感でもある程度理解出来るのだけど、統計の誤魔化しなんかには、結構騙されてしまう。 大切なのは 「直感を疑うスキル」 なのだと思う。 論理的にきちんと説明できていないのに、何となく合ってるような気がしている時 「これは、正しいとは限らないぞ」 と立ち止まれるようにしたい。
1投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ確率・統計分野で多いのだが数学的な結論が直感と反することがある。たとえば誕生日のパラドックスなど。本書はそういったネタを集めたものだが、だいたい知っているネタで新鮮味に欠けたのが残念だ。
0投稿日: 2017.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計に関心があり、手にしたが、図形(2次元・3次元)や無限とは何かなど、普段気にしない数学の世界に引き込まれた。過去の成功体験や直感に頼らず、数学的に思考する重要性を実感させてくれる。
0投稿日: 2016.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ地道な思考の積み重ねを大切にするのが数学。専門家でさえ間違いを犯してしまう「思い込みの罠」を紹介しながら、論理的に正しく考えるための思考法を伝授。
0投稿日: 2015.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログサブタイトルは「思い込みにだまされない数学的思考法」とありますが、思考法を指南する本ではなく、私たちの日常生活の中に数学の法則に従う現象や数学的な考え方で処理されている事例がたくさんあり、それらの事象の裏付けとなる数学的側面をきわめて簡潔に説明するという趣旨の本です。例えば、都市の人口とランキングの両者には法則がある!(ジップの法則)、迷惑メールを判定するアルゴリズムの基礎(ベイズの理論)、DNA鑑定で同一人物と判定されてしまう確率は?(バースデーパラドックス)、粉飾決算を見抜く数学的法則がある?(ベンフォードの法則)、蓋が落ちてしまわないマンホールの形は円形だけか、など。そして古くから知られている有名な数学の問題(一見簡単そうなんだけれど、実は大半の人が思い込みで誤ってしまう、まさに「直観に裏切られる問題」)、例えばモンティ・ホール問題、ビュフォンの針の問題、ルーローの三角形、トリチェリのトランペットなどなど。それぞれの問題についての説明は割愛します(ウィキペディア等で簡単な解説もあるでしょう)が、なかなか好奇心をそそられる問題ばかりです。厳密に証明しようとすると非常に難解な概念などが必要となる問題を、さらっとイメージがつかめる程度の内容で解説してあります。数学っていろんな現象を扱うんだな、という事が良く分かります。ちなみに数式などはかなり少なく、できる限り文章や図を多用してあるので、数学が苦手な人、文系の人でも大丈夫だと思います。
0投稿日: 2015.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「確率」は、よく人の直感を裏切るよなぁ。 内容は具体例もあり分かりやすく、酒場での小ネタにも使えそうでした。
0投稿日: 2015.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
図書館で借りた本。 がん検診で、実際にがんと診断された患者さんの「要精密検査」診断は90%である。 この検診で「要精密検査」結果が出たら、ガンである可能性は非常に高いのか?結果はNO。最終的にガンと診断される人は、検診を受けた人の0.1%、つまり、1000人に1人しかいない。対して、999人うち、10%、約100人の人が要精密検査の診断となる。このことから、「要精密検査」という結果が来ても悲観することはない。 など、よくよく考えると「そうか!」と分かることが書かれている。ただし、説明されても理解できないこともいくつか・・・あった・・・。
0投稿日: 2015.07.19直感という近道はなし
直感的には正しそうに思えても、実は数学的には正しくないということが証明されている、 そんな事例を分かりやすく紹介したのが本書です。 私が本書を読んで一番興味をもったのが、「アークサインの法則」です。 例えば、野球でもサッカーでも、実力が拮抗しているチームと対戦を続ける場合、最初に勝とうが負けようが、勝率は5割に落ち着くように思うのですが、数学的にはさにあらず。 最初に負けると後まで影響してなかなか逆転できない、ということが数学的にも証明されているとのことです。 勝負事は初戦が大事、ということですね。 その他にも、3択ゲームで、2度目の選択では1度目の選択を変えた方が当たる確率が上がるという、アメリカのゲームショー番組で有名になった「モンティ・ホール問題」も取りあげられていて、興味深く読ませていただきました。 著者の神永正博氏は言います。 『数学に「直感」という近道はありません。結局は、問題を粘り強く考え続けること、論理を一つ一つ丁寧に追いかけることが、正解への唯一の道なのです』 このことは、数学にかぎらず、日常生活や仕事などで我々がなにか問題に直面した時に必要な態度でもあります。
1投稿日: 2015.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い。 こういう感じの本は確率を扱ったものが多いんだが、確率論だけではなく、図形や、無限などにも話が及んでいる。 面白いのだが、数式が出てくるあたりになると頭がついていけなくなるのが難。
0投稿日: 2015.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ知らないトピックもあるし、知っているトピックも具体例が丁寧で著者が自分の言葉で解説しているため、読みがいがある。各章を膨らませて一冊ずつにしても良いかとも思う。
0投稿日: 2015.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「モンティ・ホール問題」など、ちょっと直感と違うなあという数学の問題についてとても分かり易く解説している本です。 それぞれは、ググれば情報が得られるものばかり たとえば、「モンティ・ホール問題」ならこちら http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C で十分ですが、面白かったです。
0投稿日: 2015.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白くて意外な数学の話題を易しく解説。しかし,重大な間違いを見つけてしまった…。副題が"「思い込み」にだまされない数学的思考法"なのに,これは著者の思い込みに他ならない…。 ルーローの三角形みたいな定幅図形の話で,マンホールの蓋が正奇数角形なら落ちないとしてるのは明らかに誤り。偶数でも奇数でも落ちるよ! 「一般に、正奇数角形のふたならうまくいく一方、正方形など正偶数角形のふたはマンホールの穴に落ちる」p.129 http://ow.ly/i/8vuNp あとこれは流儀の問題かもだけど,p.223からの最終節では,「連続体仮説」がすべて「連続体仮設」という表記に。 これ,ブルーバックスの校閲の仕事…?
0投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ年収1000万以上の層も、年収500万以上1000万未満の層も、年収500万未満の層もみな平均年収が上がっているというのに、全体としては平均年収が下がっている、そんな状況が確かにある。それが、小学5年生くらいでわかる。はい、もうすでに3回くらい授業のネタに使わせていただきました。こんな簡単な例で、統計にだまされてはいけないということを実感させることができる。この第1節を読んだだけで本書を購入した値打ちがありました。数えられる無限と数えられない無限の話は以前他の先生の講演会にも出てきて何度かネタに使わせていただいています。掛谷問題もよく話に出しますが、自分の理解がちょっといい加減だったようで、本書で逆に分からなくなってしまいました。コマ大数学科でやっていた話がけっこうあって復習にもなりました。
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学数学の面白さを堪能できる。論理を積み重ねることの大切さ。そこから「直感」の落とし穴が見つかる。全て理解できる説明のうまさと文章量、深みにはまらないような配慮があり、息抜きにはちょうど良い。ここから本格的な数学に進む入門書ではない。
0投稿日: 2015.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生以来、久しぶりに数字と親しんでみたいと思って買った。忘れてたけど自分は数学が一番得意だった。面白い実例が沢山で楽しい一冊
0投稿日: 2014.12.15
