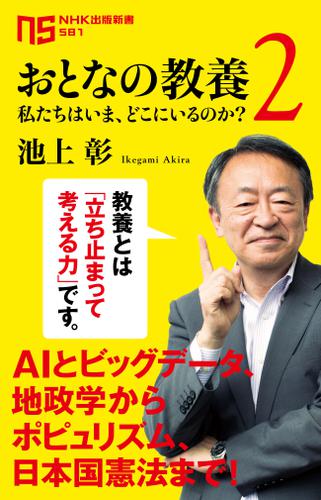
総合評価
(33件)| 10 | ||
| 17 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 のんびり読んでます"powered by"
のんびり読んでます"powered by"
分かりやすい。 とにかく遡って例示をしてくれるので分かりやすく、読みやすい。 地政学が面白かった ・歴史と今の社会の状況が繋がっていることがよく分かったから ・ニュースをより深い目で見れそうと感じたから 6年前の本だけど、今と状況はそんなに変わらないと感じた。
0投稿日: 2025.03.10 ktak"powered by"
ktak"powered by"
ベストセラー「おとなの教養」の続編。著者は、教養には二つの側面(普遍的な考えを身につけること、立ち止まり知識を駆使してニュースや出来事を捉え直すこと)があり、「私たちはいま、どこにいるのか?」をたえず意識する力であると言う。教養を得るきっかけとして、幅広い分野(?AIとビッグデータ?キャッシュレス社会と仮想通貨?想像の共同体?地政学?ポピュリズム?日本国憲法)について解説している。確かに、知識がないと深く考えることができないし、広げることもできない。学び続けたいと思わせてくれるとてもいい本だと思った。
0投稿日: 2025.01.19 flounder532002"powered by"
flounder532002"powered by"
わかりやすい解説で、すっと読み通酢ことができる。テレビで見慣れた顔を思い浮かべながら読んだ。2019年発行と内容も少し古くなってきたので、続編も読みたい。2024.6.4
0投稿日: 2024.06.04 marin2011"powered by"
marin2011"powered by"
現代を生きる私達にとって必要な知識を分かりやすく解説してくれる。アウトプットを意識して池上さんの著書を読むことでさらに理解が深まる。AI,キャシュレス、民族紛争、地政学、ポピュリズム、憲法と、多くの視点から世界を読み解くと、未来についてある程度の予知(予測)もできるようになると私は考えている。 まず知ること、そして誰かに伝えられるだけの定着をさせ、今後について考える。その第一歩として本書及び池上さんの著書を読むことはとても有用だと思う。
1投稿日: 2023.05.07 1826484番目の読書家"powered by"
1826484番目の読書家"powered by"
テレビ番組「池上彰のニュースそうだったのか」を本にした感じの内容です。 まず池上さんらしく大変わかりやすい内容です。本が書かれた当時の時事ニュースについて、その基礎的事項の説明からニュースの見方などを説明してくれています。 リベラルアーツという事で、今の大学生はこういう内容の授業を受けられるということです羨ましく思います。 私が大学生の頃はリベラルアーツなんていう思想を学生に伝える事なく、学校を卒業するための義務(必須単位)として受けさせられている感じでした。 大人は生きていく(食べていく)ために働いているものの、こうした教養を備えて仕事に臨むのが良い社会を築いていくために望ましいことではないかと、本を読んだ感想として特に残りました。
0投稿日: 2023.01.03 レモン"powered by"
レモン"powered by"
池上さんもダン・ブラウン読まれるのか、と親近感が湧いた。AIについてはまったく脅威とも思わないので軽く読んだが、ブレグジットやポピュリズムの章が興味深かった。地政学は以前読んだイラスト付きの本がとても面白く、記憶に残っていたので、本書の内容もするすると頭に入ってきた。2019年に刊行され、ウクライナ「危機」について触れられているが、まさか「戦争」になろうとは。 現代史の勉強として、『世界の大問題』シリーズも読もうかな。
1投稿日: 2022.07.29 ドラソル"powered by"
ドラソル"powered by"
文字通り池上彰が、リベラルアーツと呼ばれるものについて語った一冊。 いつもながらわかりやすくて勉強になった。
0投稿日: 2021.08.02 Kenta"powered by"
Kenta"powered by"
最近流行りの時事ネタの概要をまとめてくれている。背景は何かから、相変わらず池上さんらしいコンパクトでわかりやすい内容だった。 また、その中でも印象に残りやすい具体的なエピソードを適宜挟んでくれるため、基本的な考え方に対する理解が促進された。 各トピックに対して、もっと進んで学習していきたいと思える本であった。
0投稿日: 2021.06.06 官兵衛"powered by"
官兵衛"powered by"
前回は「今まで」を、今回は「今から」を学ばせていただきました。 先日話題になったカショギ記者の事も書かれており、少し興奮しました。地政学という、世界を分析するには新たな視点を得ました。
0投稿日: 2021.03.04 まみ"powered by"
まみ"powered by"
池上さんの本はいつも分かりやすく為になる。 他の本とダブル内容はあるけど、とても勉強になった。 教養を身に付けることで、ニュースに流されることなく、自分で考えられるようになりたい。 Kindle Unlimited
0投稿日: 2020.10.07 pomet"powered by"
pomet"powered by"
1章のAIとビックデータについて。読解力、理解力の限界についてや、そもそも分析する元となるデータにバイアスがかかっていた場合全く異なる結論がでることなどから、人間を凌駕するAIが現れることに懐疑的な見方です。この本で語っているのは、10年、20年という短い未来でしかないことに注意が必要だと思います。 2章では、ただの紙やデータでしかない貨幣について。価値があるのは、互いの共同幻想から成り立っているという貨幣の説明から、3章の民族紛争についてつながっているのは、とてもわかりやすい。 国や民族というものは、お金と同様に互いにそうであるという幻想である、と。確かに、民族など明確に見分ける方法などなく、自分がどの民族であるか自覚から成り立っています。 また、5章の民主主義と選挙の問題点、ポピュリズムは大変勉強になりました。 最初から最後まで、とてもわかりやすく、面白く読ませていただきました。
0投稿日: 2020.10.05 有井 努 Tsutomu Arii"powered by"
有井 努 Tsutomu Arii"powered by"
前作はリベラルアーツについての教養を 高める内容となっていましたが、今回は どちらかと言うと、池上氏得意の現在 起きている世界情勢をしっかりと歴史を 紐解きつつ学ぶという内容です。 しかし、ただ「こうですよ」と伝える だけではなく、 ①AIとビッグデータ ②キャッシュレス社会と仮想通貨 ③想像の共同体 ④地政学 ⑤ポピュリズム ➅日本国憲法 という6つのテーマに絞っています。 特に「想像の共同体」は、現代社会に 通底する思考であり、これを柱に 時事問題を解説する姿勢は、池上氏の 真骨頂です。
1投稿日: 2020.09.23 yuuichioka"powered by"
yuuichioka"powered by"
前作に続いての教養の本。 教養とは「立ち止まって考える力」と池上さんは言う。自分としては、「ファクトフルネス」にもあったように、考えるために真実を知り、知識をもつということも教養の大事な部分であると思う。出来事には立場が違えば様々な側面がある。正しい知識といえども様々。情報は情報として知り、様々な中からどれが正いのか、過去の真実と照らし合わせながら自分なりに考えていくことも大事である。と思う。 今回はAIや地政学、ポピュリズムなど非常に学びが深まった。さっそく新聞を読んでいても、この本で紹介されていたことがらと関連することがあり、自分なりに考えることができた。
3投稿日: 2020.08.30 猿田彦"powered by"
猿田彦"powered by"
前作も名著であったが、今回はより「今」にフォーカスした内容。AIやビッグデータの欠点について、国や個人が翻弄される現代を学びました。他にも中国とアメリカやポピュリズムについても面白かった。
0投稿日: 2020.08.09 min"powered by"
min"powered by"
このレビューはネタバレを含みます。
教養=リベラルアーツは、人を自由にする学問 リベラルアーツを学ぶことで、普遍的な考え方を身につけ環境に流されることなく自由に考えられるようになる。
0投稿日: 2020.06.28 なかじ"powered by"
なかじ"powered by"
国内や世界で起こっている出来事の根本を理解できたと思います。理解できたというのは、原因があって今があると納得できたということ。日々流れてくる情報は出来事として知っていても、どうしてそうなったかまでは考えが及ばない。教養というのは、知ることの欲求を目覚めさるものではないかと。
0投稿日: 2020.06.18 schmetterling"powered by"
schmetterling"powered by"
2014年4月に発売された『おとなの教養』の続編 AIとビッグデータ、キャッシュレス社会、民族紛争、地政学、ポピュリズム、日本国憲法の6つのテーマについて書かれています。 どの章もとても面白かったです。 特に、AIとビッグデータ、地政学、日本国憲法の章は興味深くて勉強になります。 本当に分かりやすいです。 その時だけでも『もっと知りたい!』と意欲をかき立てられます(笑) 冷めないうちに次の本を読みたいと思います(笑) 参考文献のいくつかを図書館で予約しました。 あと、前作の『おとなの教養』を再読したいと思います!
0投稿日: 2020.04.13 gizumon"powered by"
gizumon"powered by"
お金の価値は幻想だ、 今まで当たり前で疑問に思わなかったことを見直すことができる素晴らしい本だと思いました。
0投稿日: 2020.02.26 蚊焼"powered by"
蚊焼"powered by"
著者の解説シリーズは分かりやすい。本書ではテーマを6つに絞り、現在の情勢を基本に立ち返って解説されていた。とても勉強になった。 欠点は、…これは著者が悪いのではなく編集部の問題だと思うのだが、「おとなの教養」というタイトルと本書の中身はミスマッチしているのではないかと感じた。その「教養」をどうやって身に付けるべきか、を説いているのだろうという期待を寄せるタイトルではないのか。まだ、前著『おとなの教養』なら、このテーマを学びなさいという趣旨を感じることが出来たが、残念ながら今作は期待を裏切る。その期待に応える本を著者はほかにも出しているから、そっちを読めばいい。 あと、中身の7割方は『知らないと恥をかく世界の大問題10』(角川新書)と丸被りしている。「知ら恥」が本書より2ヶ月後に出ているので、情報も少し更新されている分、本書は分が悪い。
0投稿日: 2019.12.01 sino"powered by"
sino"powered by"
安定の読みやすさだが、若干情報の寄せ集め感有りか?このくらいなら、知ってる人多いと思う。まぁ、地政学あたりは参考になったかな。
0投稿日: 2019.09.25 sakumi0624"powered by"
sakumi0624"powered by"
◯AIには、例えばチェス等、特定の用途だけに使用できる特化型AIと、人間のように自律的に思考して様々な能力を発揮できる汎用型AIがある。 ◯汎用型AIに期待をかける人は、2045年頃に人間の知性を凌駕するAIが誕生する、技術的特異点つまり、シンギュラリティが起こると述べている。 ◯AIの著しい進歩は、人間の脳神経をシュミレーションした学習方法である、深層学習つまり、ディープラーンニングに支えられている。AIは過去のビッグデータから自力で解析して学習をできるようになった。 ◯Siriの様な質問型AIは文章の意味を理解しているのではなく、文章に出てくる単語の組み合わせを統計的に処理している。この情報処理の手順をアルゴニズムという。 ◯シンギュラリティが起こらなくても、文章の意味を理解しなくても務まる仕事はAIに代替される ◯ビッグデータを使ったAIは、データ自体にバイアスががかっていると分析結果にそれが反映されてしまう ◯私たちは、どうあるべきかという問題は、哲学や倫理学によって考えていかなければならない ◯日本政府はやっきになって、キャッシュレス社会を推進している。これは東京五輪にあたり、現金主義の不便な国だという印象を与えたくないから ◯増税に対してのキャッシュレスでの還元は経済産業省が旗振りを行なっているが、財務省は歓迎していない。なぜなら増税で見込まれる収入がキャッシュレス還元で余計に金がかかるから ◯仮想通貨のメリットは海外送金。一瞬で終わり手数料もほぼかからない。 ◯ビットコインは10分ごとに取引結果を全員で共有、承認することで全員で監視する。それをずっと続けるというブロックチェーンと呼ばれる仕組みとなっている。 ◯ブロック確定には複雑な計算が求められる。それを見事に成し遂げるとビットコインがもらえる。これをマイニングという。 ◯新しく事業を始める際、株式の代わりに自家製の仮想通貨を発行して、メジャーな仮想通貨を出資してもらうICOがある。株式だと、上場するのに手続きが複雑だが、ICOは手続きが簡単で配当もいらない。 ◯民族とは、物理的な特徴を有しているわけではなく、「我々は同じ民族だ!」という考えが共有されることによりせいりつする、想像上の共同体 ◯人種とは、生物学的な特徴によって区別された集団。部族とは、血縁や地縁に基づいた集団 ◯民族が生まれるのには、何らかの要因が必要であるが、とりわけ大きな要因は言葉 ◯民族でも、ユダヤ人は例外。ユダヤ人とは、ユダヤ教を信じている人であり、ユダヤ教の母から生まれた子、という定義がある。ユダヤ教への改宗は困難。学科試験と実技試験がある ◯イスラエルの歴史、2000年前、パレスチナにあったユダヤ人の王国がローマ帝国によって滅ぼされた。ユダヤ人は故郷から追い出され散り散りバラバラになった。その後、パレスチナにはアラブ人が住み着いた。ナチスドイツのユダヤ虐殺により、ユダヤ人はかつての故郷パレスチナに帰ってきて、イスラエルを建国した。また2018年の国会で、イスラエルはユダヤ人の国であるという法律を可決した。 ◯クルド人は独自の国家を持たない世界最大の民族と言われている。かつては、オスマン帝国の中のクルディスタンという地域に住んでいたが、オスマン崩壊後、その地方は、イラン、イラク、トルコ、シリアに分割された。この分断をキッカケに、クルド人という民族意識が芽生え、イラクの北部の旧クルディスタン地域に自治区を作った。彼らはイラク戦争時にアメリカに大きく貢献した。クルド人の独立運動を行う武装集団をペシュメルガという ◯アメリカ大統領は過去の経過として、イスラエルとパレスチナ両方に自重をするように伝え、和解策を取っていた。しかし、トランプ大統領は2018年5月にイスラエルにあるアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移転した。これはアメリカがイスラエルに肩入れするというメッセージ。 ◯民族意識が宗教意識を乗り越えた例として、イランイラク戦争ごある。両国はイスラム教のシーア派だが、イランはペルシア人、イラクはアラブ人として両国は対立した。 ◯中国はユーラシア大陸の一帯一路構想を描いている。陸路はシルクロード経済ベルト、海路は二十一世紀海上シルクロードとして、沿岸国にインフラを整備して、中国を中心とした経済圏を作ることを目指している。 ◯中国の政策として、中国が主導して作ったアジアインフラ銀行(AIIB)の活用がある。やり方として、AIIBが融資して各国のインフラを整備。作成した国はお金の貸し手の中国の方針には逆らえない。そして借りた側はまだ経済が発展しておらず、金を返せない。そうなると整備したインフラは中国に奪われる。そういった流れになっている。 ◯安倍政権は北方領土のロシアの不法占拠という言葉を使わなくなった。最近では帰属問題の解決ということを言っている。これはどちらに帰属するかを確定させるというニュアンス。四島返還は無理でも、歯舞と色丹だけはという思いになっている。 ◯ロシアはクリミア半島の問題には躍起になっている。ウクライナがロシアの歴史に大きく関わるということまあるが、クリミア半島のセバストポリにはロシアの軍事基地があり、ここを手放したくないという思いがある。またウクライナは西側諸国の緩衝地帯にもなっているので、余計に西側にある着くのは上手くないと思っている。 ◯中東ではイランとサウジアラビアの仲が最悪。アメリカはサウジアラビアについている。何故ならイランはイスラエルと敵対しているから。アメリカは政財界とユダヤ人の関係を考える上でイスラエルと仲良くしてしておきたい。 ◯ポピュリズムとは、議論を尽くすより、大衆が喜びそうなメッセージを集めていく政治スタイル。トランプ政権やイギリスのブレグジットはこれにあたる。 ◯イギリスのEU脱退の第一原因はポーランドからの難民問題。ポーランド人は、イギリス人がやりたがらない仕事をやるし、低賃金でも喜んではたらく。イギリスでは低賃金でもポーランド人にとっては高賃金。こうなると大量にポーランド人が入ってくる。さらにポーランド人がイギリスの社会福祉制度に乗っかることになる。そしてイギリス人の働き口が少なくなり、賃金も相対的に下がる。こうして不満が高まりEU脱退に繋がった。 ◯しかし、イギリスのポピュリズム政党もまさか本当に脱退することになるとは思わなかった。実は脱退支持層は高齢者。若者的にはEUに加盟していた方が働き口も他国も含めて広がるし、移動の便もいいので、割と離脱に反対派も多い。しかし、若者はまさか離脱しないだろうとタカをくくり、選挙に行かなかった結果、国民投票で脱退が決定してしまった。 ◯イギリスのEU脱退にあたり、問題になるのは、北アイルランド問題。北アイルランドはイギリスの一部。しかし、アイルランドは国としてアイルランドである。宗教的な問題でも北アイルランドはカトリックでイギリスはプロテスタントであるため、北アイルランドはアイルランドの一部になりたがっている。これの妥協案がEUだった。しかしイギリスの脱退により北アイルランドとアイルランドに国境が復活する。イギリスのメイ首相は、当分の間、アイルランド問題には国境を設けないとした。しかし、こうなると、ポーランド人がアイルランドを通じて北アイルランドに入ってくる。こうなるとそもそも脱退した理由が崩れる。 ◯ポピュリズムであるアメリカのトランプとイギリスのブレグジットの共通点は自国ファーストという考え。 ◯日本の憲法で今議論されている問題は2つ、日本国憲法はアメリカから押し付けられたものか、自衛隊は憲法9条に違反していないか ◯安倍首相は2015年に平和安全法制整備法を可決した。これにより、今まで個別的自衛権までしか認められていなかった憲法9条に集団的自衛権まで認めるという解釈になった。解釈により9条の内容を実質的に変えることになった。 ◯安倍首相は9条はそのままに自衛隊の存在を9条に書き加えるという、自衛隊加憲論を提案。しかしこの加憲論に対して文民統制が逆転するという者もいる。自衛隊は防衛省の指揮下、防衛省は防衛省設置法という法律で設置されている。もし憲法で自衛隊の存在を記載すると、防衛省との関係が逆転する。極論的には、自衛隊は憲法で規定されていることを根拠に命令の拒否も可能になるのではないか?そうなれば文民である政治家が軍隊を統制する仕組み、即ち文民統制が逆転してしまうという説もある。
0投稿日: 2019.09.23 コロちゃん"powered by"
コロちゃん"powered by"
やっぱり池上さん面白い。 これだけTVに出て、これだけ本を出していても、必ず新しい知識をきちんと盛り込んでいる。 「もう知ってるよ」と思っていたテーマにも必ず「ほう!」とうなるような深い知識をいくつか散りばめている。 やさしい文章で深い知識を語る本であると思った。
1投稿日: 2019.07.16 rocco"powered by"
rocco"powered by"
2019.06.28 #022 とにかくわかりやすい! ニュースの見方も変わり、ちゃんと考えられるようになった。 深いところが分かると何事も面白い。 そして、池上さんの説明は端的でわかりやすい。
0投稿日: 2019.07.01 はじめ"powered by"
はじめ"powered by"
このレビューはネタバレを含みます。
池上彰さんの本は、読みやすく、勉強になる。 他にも知っていることをどんどん本にしてほしい。 ・ビックデータを使ったAIはデータ自体にバイアスがかかっていると、それが分析結果にも反映されてしまう危険がある ・国民投票は、民主主義が内に抱えるポピュリズムという危うさを増幅してしまう危険性がある。ドイツではナチスの反省から国民投票を導入していない。 ・憲法はその国の権力者が守るべきもので、権力者の暴走を抑える働きがある。
0投稿日: 2019.06.23 じょ~ろん"powered by"
じょ~ろん"powered by"
前作が面白かったので購入。 著者のこの手の本は毎回時事ニュースを深く知るために読んでいるが、毎回きちんと本代以上の価値になっていると思わせる内容となっている。 おそらく、これからも購入し続けていくのだろう。
0投稿日: 2019.05.19 molidoup"powered by"
molidoup"powered by"
わかりやすい。 インサイダーじゃなければわからないことを書くというよりも、調べればわかるが簡単には調べられないことをわかりやすく書いたという本だと思うが、それがいい。
0投稿日: 2019.05.15 kaede-1982"powered by"
kaede-1982"powered by"
2019.6th トピックとしては「知らないと恥をかく」シリーズ(以下「シリーズ」)と大差ない感じでした。 AIや仮想通貨など近年ホットなトピックとシリーズでも毎回取り上げられている世界情勢(トランプ、ブレグジット、中東、パレスチナ、中国など)それと憲法について取り上げられています。 世界情勢については「民族」の性質が「想像の共同体」と定義されていたり、地政学やポピュリズムなどの視点から整理されていたりして、シリーズとは構成が若干違いますね。 前作はリベラルアーツを解説するというコンセプトで作られていたので、シリーズとは違った面白い本だったのですが、今回はシリーズの復習?角度を変えて説明してみました?くらいの位置付けなので、シリーズ読者には特にオススメはしないかな。 勉強にはなりますけどね(^^)
0投稿日: 2019.05.15 しーにんぐヒロ"powered by"
しーにんぐヒロ"powered by"
今回の内容は、AIとビックデータ、キャッシュレスなど、日本はだいぶ遅れているみたいですが、これから大きな変化がありそうな話題から入ってます。 その後、私の苦手な、民族関係の話題があり、地政学の話はなかなか良かったです。 そして、1番我々が常に気をつけていなければならないポピュリズムから日本憲法のはなしになりますが、今回も分かりやすく解説されていて色々参考になりました。 以下に本文から気に留めたフレーズを記しておきます。 気になった人は本書を読んでみて下さい。 ・場所が変われば見方も変わる。 頭では理解しているつもりでも、私たちは気づかぬうちに偏った見方に陥っている事がしばしばある。 知識を深めていくと、こうした一面的な見方を相対化することを身に付けることができる。 ・AI登場後はこれまで以上にデータが価値を持つ時代になってます。 データの扱いに盲点があるのならば、その影響力もはかりしれない。 ・現在の中国はキャッシュレス社会になっている。 なんでもアリババの、アリペイで決済する。 その膨大なデータがアリババに蓄積されるが、アリババの創業者である馬雲氏が中国共産党であるため、データは全て中国共産党に蓄積されている。 中国では現在、顔認識ソフトによる監視が行われており、コンサートの入り口などでカメラが設置され、指名手配犯などが何人も捕まっている。 また、顔認識ソフトを使った無人コンビニが実用化されていたり、音声だけで人物を特定できるソフトの研究も進んでいるので、電話で名乗らなくても人物が特定できてしまう。 ・AIの分析結果を無反省に受け入れるのは非常に危険なこと。 アルゴリズムをプログラムする人の中には、社会的な常識が欠落している人がいる可能性もあります。 世間の人々の思いが理解できないデータサイエンティストが作ったアルゴリズムによって社会が大きな影響を受けることにもなりかねない。 ・地理は、政治、歴史、文化と密接に結びついています。 地政学のような地理的思考は、世界情勢を読み解くための必須の教養といってもいいのです。 ・直接投票というと、極めて民主的な選び方だと思ってしまう。 しかし、国民投票は、民主主義が内に抱えるポピュラリズムという危うさを増幅してしまう危険性がある。 ・立憲主義の精神に反する自民党改正案 第百二条 すべての国民は、この憲法を尊重しなければならない。 憲法は国民が権力者に対して守るように命令するものであるというのが立憲主義の精神ですから、国民に憲法を守らせるのは本末転倒です。 多くの憲法学者から立憲主義を理解していないと批判がでました。 ・ただし日本国憲法には、国民の三大義務が定められています。 教育の義務 勤労の義務 納税の義務 憲法は本来、国民に保障される権利が書かれているのに、この3つだけは義務になってます。それは、国家を維持するために不可欠だからです。
0投稿日: 2019.05.02 シップ"powered by"
シップ"powered by"
大人の教養として、身につけておくべき知識が書かれたシリーズの第2巻。 AI、お金、民族意識、地政学、ポピュリズム、憲法改正の6テーマに分かれて、各トピックスの歴史的背景が記載されている。 池上彰の知らないと恥をかく世界の問題を読んでいると知っている知識もそれなりにあるが、その再確認にも最適。また、もちろんはじめての知識も多数ある。 おわりに、で書かれている、教養と膨大な知識は、違ったものであり、雑多な知識の山だけでは、人間としてどう生きるべきかを考えるには不十分、との指摘は、なるほど、と感じる。
0投稿日: 2019.04.30 たなたな"powered by"
たなたな"powered by"
良い年コいてろくに新聞もニュースも見ておらず、世情に疎いので、毎度池上さんの本にはお世話になってます。 AI、ビッグデータ、仮装通貨等々、耳にはするけど、どういうもので、社会にどういう影響を持つなのなの?よく分からない…というものごとについて、分かりやすく説明されています。何にも知らなくても読み進められるのが、ありがたい。恥ずかしい話だが。 著者も本書の中で繰り返し、サブタイトルにもなづている、私たちが今どこにいるのか?ということを考えるうえで、役立つ本だと思います。 多面的なものの見方を知らず、人間が失敗してきたことは過去の歴史の示すとおり。人間の失敗も含めて多面的なものの見方を身につけることは、再びの悲劇を避けるためにも大事なことではないでしょうか。
1投稿日: 2019.04.29 まいる"powered by"
まいる"powered by"
私の前から思ってる課題は、すぐ忘れることです。。。本読んでもすぐ忘れちゃう。 そんなたくさんある情報の洪水の中、いったん立ち止まり考えてみよう、そう思ってこの本を手に取りました。 この本の中で私が非常に興味深かったのは仮想通貨の話。仮想通貨は確かに便利だと思います。実際、私は買い物するとき殆どクレジットカード払いだし、PayPay利用したりとキャッシュレス派です。ただ、キャッシュレスにできるのはあくまで円がその価値を保証しているからであるから。ビットコインはどうやって成り立ってるのか非常に不思議でした。池上さんの見解も仮想通貨は本来お金の役割である価値のモノサシとしては弱いと述べています。 確かに最近、ポイントを運用する楽天とか出てきて仮想通貨が非常に出回ってきてなんでもありな世界になってきました。 でも現金であれ、仮想通貨であれ、本質として皆「お金」と思うからお金である共同の幻想ということを認識し、振り回されないように自分を戒めていきたいです。
0投稿日: 2019.04.29 DaiSugi"powered by"
DaiSugi"powered by"
毎度のことながら分かりやすい内容。 AIとビッグデータ、キャッシュレス社会と仮想通貨、 想像の共同体、地政学、ポピュリズム、日本国憲法 の6つの事柄について書かれているが、 そのどれについても最後は1人1人が 全てを知った上でどうやっていくかを 考えて生きていかなければならない。
0投稿日: 2019.04.20 匿名希望"powered by"
匿名希望"powered by"
AIとビッグデータ。 地政学 マネー ポピュリズム 日本国憲法 AIの話にダンブラウンのオリジンの話が出てきました。最近、読んだばかりでしたので、親近感が湧きました。小説では万能なAIが登場しましたが、現実はそこまでではない。しかし、特化型AIは目覚ましく発展して、一部のひとの仕事がなくなりつつある。 トランプ大統領とユダヤ教。そして中東情勢に触れ、大国の思惑や身勝手さ。ポピュリズムの怖さ。また日本国憲法が決して、アメリカから一方的に押し付けられたものではないことが、発見でした。 一方的な見方は偏見を生む。だからこそ、知識や教養を身に付けて、バランス感覚を磨くことって大切だと感じました。
2投稿日: 2019.04.17
