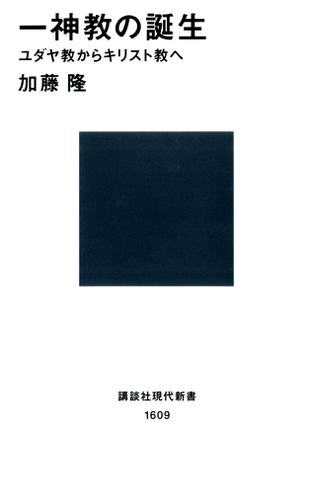
総合評価
(18件)| 1 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一神教における神と人の関係性について。キリスト教はユダヤ教からの分派から生じた世界宗教ではあるけど、決して旧来のユダヤ教から正しい位置にあるわけではない。キリスト教は、イエスが告知した「神の支配」の現実が事実である可能性に賭けている(ユダヤ教はそれを傍観している状態)。イエスが伝えてきた神の支配が「全てのもの」に関わるという性質が、イエスの死後に出来たエルサレム初期共同体によって「一部の」人びとの生活スタイルに改変されることで、「教会」の成立へと向かった。この聖俗を切り分ける「人による人の支配」こそが、世俗の支配者による「支配の仕事」を大幅に減らし、ヘレニズム時代以降の西洋社会を安定させるに至った。 教会のいう「神の支配」とは、「教会の支配」というべきか、「分け隔てしない」ところの神が自分を受け入れない者について「分け隔て」してしまっているのだ。
0投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログここまで突き詰められることで、教会へのもやもやした気持ちが晴れます。 だからといって、不信仰になるわけでもなく。 不思議な宗教です。
0投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ仏教に続いて、ユダヤ教からキリスト教へとつながる一神教がどのように成立していったのかを解明する一冊を読了。 私のような無縁の者にはわかりかねますが、唯一の神を信じるはずの一神教が、成立当初は御利益宗教だったという指摘が何とも皮肉に思えます。
0投稿日: 2018.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2002年刊行。著者は千葉大学文学部教授。 ユダヤ教→キリスト教の成立史を、前史に遡り、また事実に即して本書は解説する。人による支配の全う、という極めて合目的的理由に基づいてこれら一神教が成立していったという点は納得のところ。 ただ、西洋近代的思考、科学的探究思考が生まれた土壌としてのキリスト教は、ほとんど解説していないので、個人的な興味とは外れた点もある。
0投稿日: 2017.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ[1から]大部の日本人にとってはなかなかピンと来ない一神教の考え方。その中でもユダヤ教とキリスト教に焦点を当てながら、一神教がどのように生まれてきたのか、そしてその一神教という考え方そのものがどのように変容してきたのかを考察する作品です。著者は、ストラスブール大学で博士課程を修められている教授、加藤隆。 歴史的な流れに沿いながら、一神教の考え方の変遷を丁寧に追っているため、読みながら「あ、なるほど」と思わせてくれることがしばしば。その字面的にもどこか「確固とした」ものを思い浮かべていたのですが、一神教それ故に神との関係・在り方が多様に考えられるところが非常に興味深かったです。「神学は難解では......」と思われている方にもオススメできるわかりやすさも高ポイント。 ユダヤ教やキリスト教に関する基礎的な知識を本書で身につけることができるのも良い点かと。冒頭、そして本のタイトルと内容そのものに少し齟齬があるようにも感じましたが、大枠で「一神教とは何ぞや?」ということを知りたい人には十二分に有意義な一冊だと思います。 〜キリスト教は、イエスが告知した「神の支配」の現実が事実である可能性に賭けている流れである。これに対して、ユダヤ教は契約という唯一の関係によってヤーヴェとの繋がりを確保しながら、キリスト教の賭けが成功にいたるかどうかを見守っている流れである。〜 (語弊があるかもしれませんが)神学は本当に頭の体操になります☆5つ
0投稿日: 2015.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ民族宗教だったユダヤ教からどのようにして世界宗教であるキリスト教が生まれたのか。その過程は想像以上にある意味で打算的で、差別的ですらあり、絶対的な「神」がそこに存在してとは到底思えない、恐ろしく人間的なものだった。 この本の論理が全てではないとは思うけれど、冷静かつ客観的に捉えられた、ユダヤ教とキリスト教の関係は興味深い。 そしていまは「科学」が宗教的人のあり方を担っている部分がある 消化不良なのは、ユダヤ教の神である「ヤーヴェ」がキリスト教にどのように取り込まれていったのかが触れられはしたものの語り切られていないところ。
0投稿日: 2014.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教からキリスト教が発生した背景、3つの一神教の神は同じなのか、違うのか?などを考察する。私としては古代イスラエル宗教の成立についての無神論的立場からの記載、イエス・キリストの復活について「神格化」としてわずか触れられず、しかも復活が大きな意味がないように書かれていることについて正しいキリスト教理解とは思えないとストレスが残る。残念ながらこれが一般的な聖書の読み方なのだろう。通常は民族の滅亡とともに、民族の神も存在理由を喪うが、北イスラエル王国の滅亡と南ユダ王国がその後も150年ほど続いたことが、神を義とする古代イスラエル宗教の誕生につながったとの理解は面白く感じたが・・・。
0投稿日: 2014.06.06☆☆☆☆☆
キリスト教護教論の立場から議論を展開する学者ではない人の著作である。古代エジプトのような周辺の国々が多神教であるなかでどうして古代イスラエルが一神教の立場をとったのかは興味深い問題である。この人の議論の展開にがんばってついて行って何かを学びたい。
1投稿日: 2014.02.06☆☆☆☆☆
ユダヤ教とそこから派生したキリスト教が一神教という周りの世界とまったく異なる立場をとったのはどういう背景があったのかはこの分野に関心のある者には誰しも気になることである。 この趣旨の本はほかにも荒井章三著にもある。それもこれもなかなか難しい論議だが力作でいい参考書になると思う。
0投稿日: 2014.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ実はタイトルに若干問題があるのだが、「一神教」というものの副題にあるように扱っているのはユダヤ教とキリスト教である。 そこを含んでしまえば、ストラスブール大で神学博士をとったという著者の記述は入門者向けに分かりやすく好ましいものである。 聖書に触れる際の参考になる一冊。
0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は神学者だから、という言い方が適切かどうかわからないが、宗教の前提となる部分は文字通り前提として捉えていて、あえて踏みこまない。 ところで論理とは、もともとはロゴスであって、ロゴスとは神の言葉であり、世界を構成する論理とイエス・キリストの言葉そのもの。だから論理とは「神との論争の理」なのだよね。しかるに内容は極めて論理的といえるのだ。 もし細かいところに興味が湧けば、神学者ではなく橋爪大三郎のような社会学者による宗教解説本を読めばいいということです。 この本からは宗教史とりわけキリスト教会史について学ぶところが多かった。63点。
0投稿日: 2013.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教がどうやって一神教になっていったのか。歴史的な危機意識を神学的展開で乗り越えようとする試み。その行き着く先にイエスの動く神。そして救う神がいる。しかし神が部分的にしか介入しない現実において、教会の指導者たち人による人の支配が行われている。緻密な論理展開が面白かった。
0投稿日: 2012.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ユダヤ教:民族主義。 キリスト教:普遍主義。 分け隔てしない神を受け入れるか受け入れないかで、人間の側に分け隔てが生じる。 ヤーヴェを崇拝していたのに北のユダ王国が滅びたことをどう解釈するか。 →人間の側に過失ないし故意(罪)があったとする。 第3章、「神殿と律法の意義」で述べられている説は興味深いな。 半分くらいしかわかってないけど。 神の前での自己正当化。 4章、神殿主義と律法主義 なんか煙に巻かれてるような感じが…ケムマキ シナゴーグ=ユダヤ版寺子屋 サドカイ(神殿)、ファリサイ(律法)、エッセネ(荒野) 5章 神の支配という「情報」が社会に及ぼす影響。 キリスト教:神の支配に賭けるギャンブラー。 ユダヤ教:ヤーヴェとの契約を維持しつつ、キリスト教の賭けを静観。 6,7章 人による人の支配。 人間が信じるかどうかによって、神の態度を左右できるのではない。 普遍主義を標榜しても結局人を頂点としたヒエラルヒーになるのか。 富の享受に夢中になり、聖の領域のことを考えなくなる→世俗化。 部分的でしかないものを絶対化するのが狂信。 2012.02.12 1回目読了。
0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本格的な民族宗教としてのヤーヴェ崇拝は「出エジプト」と「カナンへ定着」の出来事によって定着し、崇拝の成立の決め手は神の恵みの有無である。 こうした構造は基本的に御利益宗教的なものである。ここでは神が人へ与える恵みの記憶と期待が、人がヤーヴェとの関係を維持する根本的な動機であり、神は基本的に人の要求に答える存在である。 多神教的傾向が顕著になったのは、ソロモンの時代であり、安定した生活の追求のためにヤーヴェ以外の神の崇拝が平気で行われることになった。このとき崇拝の対象となったヤーヴェ以外の神々で代表的なのは、バアルである。こうしたバアル崇拝に対し、北王国で活動したエリヤやアモスはヤーヴェだけを崇拝するようにと警告を発した。エリヤの後を継いだのがエリシャで、バアル礼拝を根絶して、ヤハウェの礼拝を守ることに専念した。 またヤーヴェだけを崇拝するヤーヴェ主義という流れも生じてくるが、御利益宗教的な態度が根本的にあるので、多神教的傾向は解決されなかった。 しかしこの問題が一挙に解決する事件が前八世紀後半におけるアッシリアによる北王国の滅亡であり、北王国最後の王がホセアである。戦争の敗北や民族の滅亡という事態が生じるということは、神が民を守らず、恵みや救いをもたらさなかったということである。このことは神が当てにならず、駄目な神であるということを表し、その神は見捨てられ、崇拝するものがいなくなるというのが当然であった。 だから、北王国の滅亡によってヤーヴェが見捨てられても当然であったが、このときは理屈通りには事は動かなかった。それは北王国は滅んでも南王国が残っていたからだ。ユダヤ人たちの中には、ヤーヴェを見限った者も少なくなかったかもしれないが、南王国では北王国よりもヤーヴェ崇拝が強いところで、ヤーヴェ崇拝を簡単に捨てられなかった。だが、北王国という一つの国が滅んだということは、ごまかしようのない大きな事実で、駄目な神ということになったヤーヴェ、こんな神は崇拝できないというのは常識的な判断である。 しかしヤーヴェ崇拝は捨てられない。こうした緊張の中で神学的に大きな展開が生じた。具体的には、「契約の概念」を神と民の関係にあてはめて、「民」が「罪」の状態にあると考えることである。つまり神が沈黙したのは神が駄目な神だからではなく、ヤーヴェ以外の神を崇拝し、神の前でふさわしい態度をとっていなかったからであるという考えだ。 これにより神が「義」とされた。この結果、罪の状態である民にとって、神の前での義の実現が最大の課題となった。また、民に対する神の優位が決定的になり、御利益宗教的な態度が不可能になって一神教的態度が成立した。 今回は御利益宗教的なヤーヴェ崇拝が、一神教態度に変わっていく状況を概観した。この二つの違いに注目すると、一般的な日本人の無宗教的態度が浮かび上がってくる。 日本人はよく無宗教であるといわれるが、実際はそうではない。御利益宗教的態度を持っているのだ。だからこそ初詣に行き、安産や受験のお守りなどを保持したりするのだ。これは神よりも人間が優位になっているということでもあり、神は恵みを与えてくれるという考えに基づいている。 クリスマスもある意味人間の優位が表れているのではないか。もちろん現在の日本のクリスマスの現状は、商業的な傾向が強いが、元々はキリスト教徒の宗教的行事をここまで変質できるということは、神や宗教よりも人間がまず最初にあり、人間が楽しめるのならば、クリスマスをどのように「利用」しても構わないのではないかという日本人の価値観が読み取れる。
0投稿日: 2011.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] ユダヤ教とキリスト教の神は違うのか? 歴史から人と神の関係を新しく問い直す。 [ 目次 ] 第1章 キリスト教の問題 第2章 一神教の誕生 第3章 神殿と律法の意義 第4章 神殿主義と律法主義 第5章 洗礼者ヨハネとイエス 第6章 イエスの神格化と教会の成立 第7章 キリスト教と近代 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ例えば、何かを信仰していて、にもかかわらず辛い思いをしたとしよう。 「一生懸命祈ってたのにこんなことになるなんて、祈りになんか意味無いんじゃないの?神様」 これは誰もが考えると思う。だけど、その時エラい人たちはこうきり返した。 「その信仰はちょっとズレてて、さらに、たまにサボったりもしてたでしょ?だから神様は何もしてくれなかったんだよ。ウン、そういうことにしよう。」 これは神様のコメントではなく、宗教的にエラい人のコメント。 つまりみんなは神様の存在を揺らぐことの無い大前提として、その他のつじつまを必死でその大前提に合わせようとしている。この感覚は信仰心が乏しい自分(おそらく多くの日本人も)には理解できない。信仰が精神に癒着している。 信仰心には全く関心はないけど、キリストのこととかユダヤのこととか色々わかって面白い。そして、当たり前のことだけど神様って人間が勝手に作り出したモノだから、誰かのさじ加減1つで何とでもなるんだけど、その神様の存在についてとってもロジカルに解釈しているところが面白い。現実を見ようとしない人みたい。 取り合えず、イエスは神じゃない。そして、一般ピープルは宗教を心で感じるけど、エラい人は宗教を頭で考えている。
0投稿日: 2010.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ実はタイトルに若干問題があるのだが、「一神教」というものの副題にあるように扱っているのはユダヤ教とキリスト教である。 そこを含んでしまえば、ストラスブール大で神学博士をとったという著者の記述は入門者向けに分かりやすく好ましいものである。 聖書に触れる際の参考になる一冊。
0投稿日: 2008.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログユダヤ教からキリスト教への発展史概説。 一神教の成立が「王国の滅亡から民族を救わなかった頼りない神を棄てないための理由付け」としか書かれていなくて、その部分を知りたいものにとってはいまひとつな内容。
0投稿日: 2007.11.21
