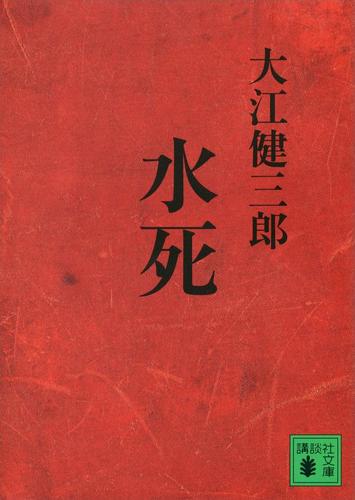
総合評価
(10件)| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ私事ではあるが、買ったすぐ後に父親が亡くなったこともあってずっと手をつけられなかった本であり、数年ぶりにやっと読み終えることができた。主人公の父の死はテーマのひとつではあるが、意外と話は四方八方に広がっていて一口には要約できない。このもやもやまとまったものを紐解くのが再読時の楽しみなんだろうと思う。静かな、ゆったりした中に、緊張感が微妙にありつつも飄々としたこのかんじは、大江の後期作特有のものだと思った。日々少しづつ読むにもいいと思う。
0投稿日: 2023.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の作品をある程度読んだ人間以外門前払い、というところに目を瞑り評価すれば、本人が描けるレベルを遥かに超えた自己批判・批評が面白い。 『死んだ犬』のくだりなど、一部最盛期を彷彿とさせる箇所もあり、後期には無かったパワーの燃焼を感じた。
3投稿日: 2022.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ天皇主義の戯画を演じて死んだ三島由紀夫に対し 戦後民主主義の戯画を引き受けて生きる大江健三郎は 三島の死をトリックスターのそれと決めつけ 影響力を無効化するために 天皇との和解を目論んだのだと思う 「あいまいな日本の私」とは、まさに天皇のことでもあるわけだ それはもちろん逆説的に不敬だった とはいえ、天皇との和解 小説を使ってのことにせよ さすがの大江も、そんなご都合主義をやらかすほど 恥知らずにはなれなかった それはあるいは、障害持ちの息子という心残りを置いた 老年の弱気なんだろう そこでかわりに、三島のホモソーシャル志向を叩くべく持ち出したのが メイトリアークという概念だった 天皇の家系をつないでいるのも、結局は産む存在としての女である それを視野に入れない三島の思想は、尻切れトンボで未来がない そういう考え方はしかし 女性の権利がうたわれる時代において 即「おもねり」と化す危険性をはらんだものであろう そして実際のところ三島由紀夫は 子らに対する圧制者としての母たちと、常に向き合う存在でもあった ただし、以上のことはすべて僕の妄想であって 「水死」という小説には三島のみの字も出てこないのであるが 序盤で問題にされる 「みずから我が涙をぬぐいたまう日」に関しては 三島の切腹を受けて執筆されたものという見方が一般的のようだ ノーベル賞作家の長江古義人は 長年の懸案だった「水死小説」への着手にあたり 地元・愛媛県の劇団員に頼まれて ワークショップを並行することになる 「水死小説」…実家近くの川で溺れ死んだ父親の名誉回復を 長江は、それによって果たそうとしたものであった しかしその試みは早々に頓挫してしまう アテにしていた当時の資料が、ぜんぶ空振りだったから そしてさらに気落ちする暇もなく 老齢の長江にとって、あまりに厳しい家庭の危機が訪れるのだが この窮地を救ったのは、劇団員ウナイコとのつながりだった 孤立した「リア王」のように 放り出される寸前の長江が救い出されたのは ウナイコと、長江の妹アサがコミットメントしてくれたおかげだ ただし それは要するに、ノーベル賞作家の威光を争奪する劇団内の対立で ウナイコが主導権を握ったということでもある 彼女はその威をかりて 高級官僚だった伯父への、ある復讐を実行しようと目論んでいた
0投稿日: 2018.12.11大江健三郎最後の仕事
と何度となく言われている宣伝文句ですが、実際に最後になる作品ももうそろそろでしょう。 大江の作品はとにかくジェネレーションギャップが概ね多くの領域を占めています。江戸期と維新、維新と国家神道普及後、戦前と前後…。 ウナイコの過激な新劇も”国家は強姦する、国家は堕胎する”というセリフをわざわざ解説しているにも関わらず、反対論者の理解を得られないし、さらに、大江の投射人物である長江の方でも、危機感を抱きながら見ているというシーンを挿入し、大江健三郎というノーベル賞作家の名を使った国家を非難するプロパガンダには容易には協力できないということを表してもいます。 これは、戦後民主主義のかつての社会主義勢力全盛で、大江文学の全盛時代とは明らかに異なるのだ、というメッセージを読者に発信しないではいられなかった大江健三郎の苦悩でもあるでしょう。 さて、反戦運動を行う大江が、最後の最後で銃撃を用いるのは自己矛盾のように見えますが、しょせん、自由というものは個人を守る力なしには成り立ちえないという現実があるからこれは仕方がないことでしょう。銃なくしては、作中のウナイコに襲い掛かる純然たる暴力に一片の反抗も許されることはないのだから…。実際、そのことを分かっている右翼からすると自己矛盾極まりないという感覚でしょうね。 作中の”父”の鞄に何も入ってはいなかったように、大江の”鞄”にももう何も入ってはいないのかもしれませんね。”父”がムラの伝統に拘って将校の支持を失ったという表現は案外、大江の心情の深いところを表現しているのかもしれません。 最晩年の仕事を見るに至って、結局、大江健三郎の仕事は”死者の奢り”に永久に取りつかれた作家の生きざまを徹底的に描いたというそれだけのものかもしれないと感じる部分もあります。実際、作家は”処女作”を超え、その先に至る展望を見ることが至上の目的でもあるのでしょうが…。 大江文学の集大成に星5つ。
0投稿日: 2018.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語が何一つ解決せず、むしろ混乱の極みのようにして終結する。さまざまな挿話が立ち起こっては消えて、のようなまま、パタンと終わる。 読後、取り残されたような気分になり、混乱したが、しばらくして気づいた。 物語に決着はつかないのだということに。 人生の決着が全てついて、終わりを迎えるなんていうことはなく、むしろ混沌としたまま、曖昧なそれなりの良い意味での諦めをもって収束させるしかないのだ。 キーワードのように鳴り響く、These fragments I have shored against my ruins という引用が示すように、何も完結させられないまま、なんとかして最後までやり抜いていくということなのだろう。 大江氏の人生をかけた物語りは、まだまだ続くのだ。氏の作品で何度も繰り返されるように、その物語を受け取った新しい世代が、脈々とモノ語りを続けていくのだ。 (ということで、大江作品をあまり読んでいない方には、絶対にオススメできない)
0投稿日: 2014.10.26大江健三郎の作品が好きな人にとっては、☆5つです
平成になってからの大江健三郎の作品というと、『燃えあがる緑の木』や『宙返り』などの対策が思い浮かびますが、これらのエッセンスである神話的手法がふんだんに盛り込まれた作品になっています。 演劇「死んだ犬を投げる」とギュンターグラスの小説、夏目漱石『心』、作中映画「メイイスケ母出陣」。 メイスケ母とウナイコ。 フレイザー『金枝篇』と長江氏の父。 などなど。 過去と現在、物語と現在の対比から、小説の深みが増していきます。 ただし、いかんせん、その構造を読み解くには体力がいります。正直、一回読んで、メモを作成し、もう一度読み直すと物語の深みが分るかもしれません。
0投稿日: 2013.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ大江作品は数作しか読んでないが、彼の作品とは相性が悪いようだ。文章じたい、読み手に対して優しくない。内容も私的すぎて、特にファンでもない私は読んでいて辛かった。長年読んでいるファンだったら楽しめただろう。
0投稿日: 2013.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
もちろんいつまでも自己批評的であったり留保を付け続ける必要はないんだとは思うんだけれど、「母を愛していたのだ」「父を愛していたのだ」のくだりには本気でびっくりした。愛している、なんて言葉、今までに出て来たことなんて一度もなかったように思うのだけれど。 それに、そんなこと、大抵の作品を読んだからとっくの昔に知ってるし、本人こそそういう言葉によって認識していなかったのかもしれないけれど、そういう簡単に言葉に出来ないもの、をこそ、彼は今まで悪文と呼ばれながらも書いて来たのではないか…?最後の小説(かもしれない)という段階で、やっと使った、ということも出来るけれど…。 『こころ』に関する「教育」のくだりは、つまり個人的なできごとを真摯に伝えることによって、他人に何を与えうるのか?そんなこと勝手な個人的表現でないのか?という大江健三郎自身の長年の問題にも触れるようであるけれど、はっきりと答えは示されていないし、示されうるとも思わないけれど、全体的になにか弱って来ている感触がするのが辛くて、これがもし彼のレイトワークならぬラストワークになってしまうのだとしたら、私は悲しい。
0投稿日: 2013.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読みかけて途中で挫折した大江健三郎の本が沢山ある。この本を最後まで読みきったということは、年をとってあらゆることに興味を持つようになり、多少とも読解力がついた証左である。 国語が極端に苦手な子供に少しでも分けてやりたい。 大江健三郎の作品は確かに読みづらい。私小説的であり、背景にあるものの説明は全くない。 この小説も水死という題名で終戦直後に亡くなった実父の謎をたどろうとしたのだが、早い時点で諦め、ウナイコという演劇女優や自分の周辺を取り巻く話が脈絡もなく、展開し、どうなることだろうと読み進めていくが、最後に衝撃的な事件が起きて、何とか小説的な幕引きとなる。 この分かりにくい、途中で投げ出したくなる小説を読みきったことで、もう一度作者の他の作品にも再挑戦してみようかと自分を奮い立たせる役には立ったのだろう。
0投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読みにくくてなかなか読み進められなかったが、二日目には慣れることができた。とは言っても、なかなかさらりとは読めない文章で、苦戦させられた。 意外性があって面白い。それに、ウナイコとリッチャンのキャラクター性が良い。でも、最後に何を伝えたかったのかが分からない。長江先生の意思が受け継がれている、ということ?急に監禁されてしまうという展開にちょっと着いていけなかった。 ウナイコのように自分を表現するようなことをしてみたいと思った。何があっても自分が伝えたいことを人々に伝えようと思う意思の強さと熱意に憧れた。
0投稿日: 2013.01.15
