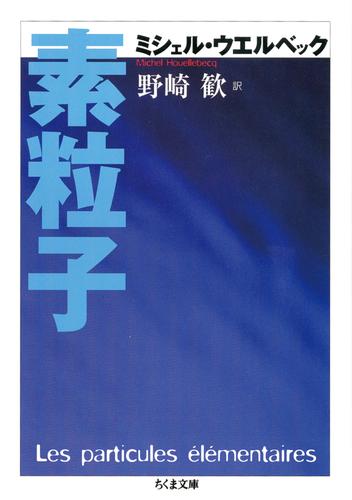
総合評価
(39件)| 7 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わったというか途中で挫折。 海外文学かつ、苦手なな理系要素、さらにストーリー的にもあまり興味持てず、読み進めるのがしんどくなって諦めました。
0投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ中年の危機を描いた小説と言われて読んだが、そんなスケールの本じゃないだろ。あるいは文明としての西洋文明が壮年期を終える苦しみを描いているとは言えるのかもしれない。読んでいて苦々しい思いになりつつ読むのをやめられず登場人物がただ愛おしい。
1投稿日: 2024.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ危険な本 問題作と紹介されていた やるだけの表現されているが、なんともエロさや色気を 全く感じない、どこでセックスしたという表示だけ。 内容も全体としては、精神病的なこだわりがあると感じる。中間部分で、オルダス・ハックスリー の書評があったり、共産主義的な、思考の断片があったり、 最終部では哲学的と感じる表現もある。 ヒッピー様なところがウケるのかもしれない。
0投稿日: 2024.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読むのに時間がかかった。 ジェルジンスキという分子生物学者とブリュノという高校教師の異母兄弟のちいさいころからの話。 1900年代から2200年代の社会にまで及ぶ。 性的な表現や常識から逸脱していると思われるこういの連続で発売されて避難や攻撃をうけたのも頷ける。 しかし、いかに道徳的に生きても死んでしまえはなんにもならないなと感じた。ミシェルは、白いカナリアがダストシュートに投げ込んだ。どんな形であれ我々も白いカナリアなんだろう。
0投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人に薦められて手に取る。恐らく自分では選ばない内容。 最初は性的なものも含む衝撃的な描写と、物理学や哲学の難解な文章に頭が混乱しながら、また辟易しながら、何度も挫折し、少しずつ読み進めた。だが次第に登場人物たちの絶望的な哀しみに寄り添うようになり、最後にはページを捲る手がとまらなくなった。なんとも不思議な、ジェットコースターみたいな小説。面白かった。 でもどうかな、やっぱり好き嫌いがはっきりとわかれる小説なんだろうな。
1投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログスーパー面白かった!強烈!読んでると鬱々としてくるのに読むのを止められない不思議な魅力を感じるところから少しずつのめり込み、下劣な話や最低な思考がガンガン出てきて不快になりつつも文体の魅力に引き込まれて読む手を止められなくなり、仕舞には愛おしくなって夢中になり、ラストで二人の兄弟の半生と語られた会話とが全て集約されたSF展開に衝撃を受けた。興奮、感動した。構造も面白い。何度も戻って読み返したりするのは久しぶりだった。何日か共に生きたような長編の醍醐味もあり余韻が凄い。心に残ってる。 ディストピア小説を読みたくて「ある島の可能性」を読もうとしたら先に読んだ方がとおすすめされた経緯なんだけど、何て的確な紹介だったのかと驚いた。 管理社会が生み出される前段階を読めたような、ディストピア小説はだいたい管理社会が成立した後の話なので普通じゃ読めない部分を見れたような興奮があった。いや、SF小説で似た方向のオチになるやつがあるので珍しくないのかもしれないけど理論的に構築されてるところは新鮮だと感じた。 ディストピア小説を漁っていて今のところ「すばらしい新世界」が一番好きなんだけど、ハクスリーの名前が出てきたと思ったら「すばらしい新世界」について兄弟でそれぞれ意見を交わしてて嬉しい驚きがあった。しかもそれも他の思想や討論と同様、オチへ繋がる要素の一つにもなっていて刺激的だった。またいつか読み返したい。素晴らしい傑作だった。
0投稿日: 2024.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「滅ぼす」を読了後、他のウエルベック作品にも触れようと決意。 50年代末のフランスに生まれた異父兄弟が対照的な人生を歩む。高校で国語教師を務める兄ブリュノは、悲惨な幼少期が災いしてかセックスに溺れる日々を送る。対して天才科学者の弟ミシェルの私生活は清純そのもので、ノーベル賞も狙えるほど研究に精魂を込めている。 アメリカから持ち込まれたヒッピー文化やヌーディストビーチ、乱行専門の風俗店に代表される退廃。現代物理学や遺伝子学といった人類知能の限りを尽くした最先端のテクノロジー。人間の生を語るうえで文字通り両極に位置するこれらの世界、そして双方を代表する2人の生き様を通して、現代を生きる人類とその未来を見つめる作品。 読み終わったのち、タイトルの意味が(ほんのりと)分かる。生物としてのhuman beingが行き着く先とは。
1投稿日: 2023.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの小説は天才的な科学者と典型的な文系人間の兄弟を両輪として展開する。1960年代より文化面で進行した個人主義と性の解放によって訪れたのは、人間の分離と欲望の無制限な増大だった。その社会を間近で観察し続けたミシェルは個人性を排除した新人類を生み出した。それは人類の緩やかな絶滅をも意味していた。 行きすぎた個人主義の他から逸脱したいという欲求から生まれたセックス至上主義、エロチック=広告社会に対するアンチテーゼであり、現代社会への諦めを感じる。そこでは歴史上類を見ない規模で不均衡がばら撒かれる。エヴァの人類補完計画にも通ずる部分がある。みんな一個になっちゃえばいいじゃん。 ミシェルとブリュノの半生を概観しつつ現代社会の限界を描き出す。個人主義と家庭の矛盾、性的解放と暴力etc。全体的に女性を主体として語ることには消極的である。 ミシェルの作り出した新人類の社会は彼自身が批判したハクスリーのユートピア社会の問題を克服できているのだろうか?遺伝子コードが同じで増殖に生殖が必要ないだけで個人性を超えることはできるのかは疑問に感じた。ウェルベックは新人類の登場した世界をユートピアとディストピアどちらとして描いているのだろうか。ハッとさせられる一節がたくさんある小説だが、その中でも以下の二つの引用には作者の人間に対する愛憎入り乱れる感情が現れていると思う。 P106 一九七四年七月の一夜、こうした状況のもと、アナバルは自分の<個的存在>について苦悶に満ちた決定的意識に到達したのだった。動物については身体的苦痛という形で啓示される個的存在が、人間社会においてその完全なる意識に到達するのはひとえに<嘘>を通してであり、嘘と個的存在とは実際上かさなり合う。 P126 人類についていくらかなりと網羅的に検証しようというのであれば、必ずやこの種の現象に注意を向けなければならない。歴史上、こうした人間もまた確かに存在した。一生のあいだ、自分の身を捨てて愛情だけのために働きづめに働いた人たち。献身と愛の精神から、文字どおり他人にわが命を捧げ、それにもかかわらず自分を犠牲にしたなどとは思わず、実際のところ献身と愛の精神ゆえに他人にわが命を捧げる以外の生き方を考えたこともない人たち。現実には、そうした人たちは女性であるのが普通だった。
0投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ"「唯物主義と近代的科学を生み出した形而上学的変動は、二つの大きな結果をもたらした。合理主義と個人主義だ。ハックスレ―の過ちは、それら二つの結果のあいだの力関係を測りそこねたことにある。とりわけ、死の意識が強まることによって個人主義が高まることを過小評価したのは彼の過ちだった。個人主義からは自由や自己意識、そして他人に差をつけ、他人に対し優位に立つ必要性が生じる。『最良の世界』に描かれたような合理的社会においては、闘いは緩和されるかもしれない。空間支配のメタファーである経済的競争は、経済の流れがコントロールされる豊かな社会ではもはや存在理由を持たない。生殖という面からの、時間支配のメタファーである性的競争は、セックスと生殖の分割が完全に実現された社会ではもはや存在理由を持たない。しかしハックスレ―は個人主義のことを考えに入れるのを忘れている。セックスは、ひとたび生殖から切り離されたなら、快楽原則としてではなくナルシシズム的な差異化の原理として存続するということが彼には理解できなかった。富への欲望に関しても同じことさ。スウェーデン流社会民主主義モデルが、ついに自由主義モデルを凌駕できなかったのはなぜなのか? それが性的満足の領域においては試みられることさせなかったのはなぜなのか? 近代科学によって引き起こされた形而上学的変動が、個人主義化、虚栄心、憎しみ、そして欲望をもたらしたからさ。欲望というのはそれ自体――快楽とは反対に――苦しみや憎しみ、不幸の源なんだ。これはあらゆる哲学者たちが――仏教徒やキリスト教徒だけではなく、その名に値する哲学者たちはみな――知っていたことであり、説いたところでもあった。ユートピア主義者たち――プラトンからフーリエ、ハックスレ―に到る――の解決法は、欲望と、それにまつわる苦しみを消すために、欲望を直ちに満たす方法を組織することだった。その反対に、ぼくらが暮らすエロチック=広告社会はいまだかつてない規模で欲望を組織し、肥大させながら、その満足に関しては個人的領域にとどめている。社会が機能し、競争が継続するためには、欲望が増大し広がって人々の暮らしを食い荒らす必要があるんだ。」" ISBN4-480-83189-4 P.174 鼻面をひきまわされる、耳をひっぱられ否応なしにつれまわされる。この小説のはじめの印象はそんなふうだった。 なにを見せられているのか、どこへ連れて行かれるのか、さっぱりわからない。90年代の映画風。はっきり言えば『パルプ・フィクション』や『トレイン・スポッティング』、『ファイト・クラブ』のようである。クール。フランスのいじめスゲー。 気づけば、森山塔作品にも似た読み味になっている。なんだこれは。まったくもってわけがわからない。だが、読むのをやめようとは思わない。 この物語がいかにして『素粒子』へとたどり着くのか、楽しみでならない。 文学を語れるほど読みこなしていないが、本作品は文学であろうと思う。経験から、文学とはどちらかというとウェットなものという印象が強いが、本作品は非常にドライである。痛ましいほどに超越的である。 エピローグ。これ以前は文学だった。 エピローグの10ページ程度でSFになる。サイエンス・フィクションではなく、サイエンス・ファンタジー。なんでこのオチ? いかなる差別をも存在しない未来への憧憬か。
0投稿日: 2022.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログブリュノとミシェル、両方ミシェルウェルベックが実際に辿ってきた人生をかなり濃く反映したキャラクターなんだな。 自由が、かえって男を生きづらくさせた。西欧社会の転換が生んだ翳りを、生々しく露悪的に捉える。自らの人生において、あらゆる面で強烈なコンプレックスを抱くブリュノ、なりふり構わず性に乱れる姿は滑稽だし彼の過去を踏まえると物悲しさすら漂う。でも後半吹っ切れたか振り切れたかしてる。より彼に対する切なさが増幅しちゃう。 根底にウェルベック自身の痛烈な自己批判があるんだろう。社会を世界をシニカルに捉えているのに、その眼差しは自身の振る舞いにすら向けられている。
0投稿日: 2022.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ終焉に向かう人類。それぞに「愛」の意味を探して苦悩する二人の兄弟。 ストーリーが面白いので、序盤はどんどん読み進められました。途中から哲学や物理の考察が多くなり、どっちも疎い僕は読むのがキツかったですが、最後で納得!めちゃくちゃ深い伏線。 読み終えてみると、かなり面白い作品!
0投稿日: 2022.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ『闘争領域の拡大』に次ぐウエルベックの二作目。フランスでベストセラーになったらしい。 ウエルベックは博識な作家だが、本書もごたぶんにもれず数学、分子生物学、はては哲学まで盛り込まれていた。ド文系な自分にはさっぱり理解できなかった箇所も多かった。難しすぎる小説ははっきり言って苦手だ。 性欲に囚われた国語教師の兄ブリュノと、天才分子生物学者である弟ミシェル。この異父兄弟を主人公としてその一生が描かれる。前半の幼少期の話は好きだったが、後半になるにつれわけがわからなくなり、あまり物語に入ってゆけなくなった。 ブリュノは性欲をこじらせたまま大人になり、ニューエイジ風のキャンプに参加したり、乱交専門のナイトクラブに参加したりと性欲を満たす機会を日夜探している。小説全体を通しても彼の異常な性欲が際立つ内容で、彼があの手この手を使って一物をしごく姿が印象的だった。ブリュノが描き出しているのは『闘争領域の拡大』でも描かれていたような、典型的なルーザー。ウエルベック的な主人公といえる。だけどそこまでの性に対する倒錯した欲望は私は持ち合わせないので、読んでてふーんそうですかというような感じになった。あと時折ミシェルとブリュノの会話があったが、これもなにかぎこちなく、風景描写も取って付けたような感じで、いかにも小説としての体を整えるためという感じがした。 弟ミシェルは兄ブリュノとは対照的で天才なのだが、無性欲、不感症で、そのこと自体についても本人は無関心だ。興味があるのは彼の学術分野のことだけ。ミシェルにもブリュノにも共通しているのは二人とも無目的に生きていることだろうか。誰にも生きる意味などわからないものだろうが、素粒子に登場する人物たちは皆さまよい、傷つき、他者を理解しようとするも満たされることがない。 それにしても作家によって小説ってこんなに違う顔を見せるんだなと感心する。村上春樹からは温かみ、ジョン・アーヴィングからは力強さを感じるが、ウエルベックに関して言えば、鋭いカミソリのような感じを受ける。時代を抉り取って描写する鋭さとでも言ったらいいだろうか。ウエルベックの小説は難しいが狙いがはっきりしているように感じた。
8投稿日: 2021.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログフランス近代の変遷とともにあった異父兄弟の人生は背中合わせで、同じ光景を見ることはない。 体を燃やす孤独、雪のように降り積もっていく孤独。欲望も快楽も幸福も愛も、個人主義がもたらした孤独を前にしては人はゆっくり狂いゆくばかり。 人は滅んでいくのだろう、無抵抗に、音もなく。 兄の人生は「これが延々と続くのか…」と思う描写ばっかりでそりゃ地獄だわと思うし弟の人生も自分では解決の術もわからない孤独に厚く包まれていてそれもまた内側から凍っていく絶望がただただ冷たい。エピローグのまとめ方はウェルベックの才能に唸るけれど、やっぱり何か怖いんだよねこの人は… 明確に反出生主義の流れを汲んだ小説だと思う。べネターの誕生害悪論が近いところにある気がする(べネターちゃんと読んでないが)けどその思想を人間ふたりの誕生から終焉まで、そしてさらに続く長いスパンの小説に落とし込むのはすごい。 でも怖いんだけどね根本的に!何かが!それがウェルベック!
1投稿日: 2021.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログミシェルウェルベック 「 素粒子 」 新しい人間学。形而上学(多数の人が共有する世界観)の変異から「人間とは何か」を考察している ショッキングなエピローグ。素粒子レベルまで物質化した人間像。性別と死がない新人類。未来の新人種が三人称的に語る構成。 面白いけど 性描写がしつこい。 祖母の遺骸や恋人との再会のシーンは、人間とは何か 考えさせられた 人間とは何か *心の内に〜善と愛を信じることをやめない *生きることは 他人の眼差しがあって初めて可能になる〜遺骸となっても 生きていた頃を想像できる *お互い敬意と憐みを抱くのが人間らしい関係 時代背景 近代科学が キリスト教道徳を一掃し、男女の違いが 個人主義、虚栄心、苦しみ、憎しみなど不幸の源となっている アナベルとの再会。心地よさ、暖かさに包まれて〜世界の始まりにいた〜時間の根が生えてくる場所を見た〜あらゆるものの内に終末を見た 空間に関する新しい哲学原理 空間は自身が精神的に作り上げたもの〜その空間内で、人間は生き、死ぬことを学ぶ。精神的空間の中で別れ、遠さ、苦しみが作り出される
2投稿日: 2020.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校教師の兄と科学者の弟、異父兄弟がその身を滅ぼしていく過程が描かれています 20世紀にかけて欧米で起こった社会制度、家族制度の変化、性の自由化の流れがわかり易く描写されています。 下ネタだらけなので苦手な人は読まない方がいいです
1投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ原書名:Les particules elementaires 第1部 失われた王国 第2部 奇妙な瞬間 第3部 感情の無限 著者:ミシェル・ウエルベック(Houellebecq, Michel, 1958-、フランス・レユニオン、小説家) 訳者:野崎歓(1959-、新潟県、フランス文学)
0投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の掌の上できれいに転がされた感じがする。一本の小説の中で何回、不幸と一瞬届きそうになる幸福の間を行ったり来たりしただろうか。これでもかというくらい振り回され、同情を誘い、もはや「素粒子」というタイトルが匂わすSF的結末への期待をも忘れて、途方もなく哀愁漂うなけなしの性愛物語として十分満足だ、と観念しかけた頃、ついに結末がやってくる。そのカタルシスたるや、圧巻である。一切の苦悩から解放されたときのような浄福を自分は味わった。自由と進歩主義に対するにべもない唾棄には思わず笑ってしまったが、このとき、登場人物たちに対する自分の数々の共感と同情も一緒に笑い飛ばされてしまった。それがまた爽快。ウェルベックの最高傑作と呼ばれるのも納得。作者の思想に同意しない人でも楽しめると思う、というかそれを狙いに行ってるだろうな。
4投稿日: 2018.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を観た時に、原作を読みたいと思ってそのままにしてたんだけど、無性に今、読みたくて仕方なくなったので借りてきた。
0投稿日: 2017.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間存在の孤独についての物語が、どこまでも個人的なエピソードを通じて、しかし普遍的な確信をもって語られる。 小説の主軸になるのはふたりの異父兄弟。兄は女にもてず、不惑を超えても性的な彷徨を続けている文学教師。弟は、相手が男であれ女であれ、他者と人間関係を築き難い天才科学者。 西欧文明の終焉を背景に、兄弟と彼らを取り巻く人間たちを透かして、孤独の絶対性が描かれる。 ラストで明かされる物語構造と人間存在への視点は超越的で、冷徹でありながら甘美だ。それはニーチェの超人思想を思い出させる。人間は生まれながらに重荷を背負ったものであり、人間の先に続いて現れるもの(があるとして)への架け橋でしかない、と。つまりは超人的な存在を仮定して初めて、人間は人間を肯定できるのかもしれない。 超人が存在せず、人間が人間でしかない現実においても、ひとは生きていくしかない。孤独と死とともに時間に押し流され、どこかにある愛を信じながら。 読後の呆然とした余韻の中で、そんなことを思わされた。
0投稿日: 2017.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「服従」が面白かったので、著者の代表作を読もうと思って購入。性格もキャリアも全く異なる異父兄弟の半生を中心に、家族や夫婦、親子、友人との関係を生々しく描いている。美貌、健康、学歴、財産、政治信条、友情、愛情、幸せなど、どれ一つ確固たるものはなく、得たと思えば去っていくし、またやってくる。外から来るものにしがみつくのではなく、中から信念を持って信じられ続けるものを持つことが重要だと再認識。これが難しいのだけれど。
0投稿日: 2017.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ『服従』が面白かったので遡ってきた。 セックスと老化に翻弄されることから逃れられない人間の孤独と絶望。若い時に読んでもピンとこなかったであろう中年の悲哀と渇望。 予想外のオチに回収される。
0投稿日: 2015.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログどちらかと言えば苦手な作家。処分する前にもう一度読もうと悪あがき。過激な性、暴力描写に、やはり遅々として進まず… しかしながら半ば自伝的本作では、人間の脆い精神構造を暴き出す傍ら、ウェルベック自身の思想が見え隠れして面白いのも事実である。影響を受けやすい私は、近々必ずやハクスレーを読み返すであろうと予測(おそらく的中)。 kinoppyでは電子書籍版が出ていないのか… ひとまずは本棚に戻す。
0投稿日: 2015.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の中で描かれているのは、単なる中年男の孤独だろうか。そうは思えない。 誰もが心の何処かで持っている寂寥感や人恋しさが根底にあって、その上で満たされない気持ちをどうするか? という問いが含まれているように思う。
0投稿日: 2015.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログミシェルは分子生物学者、ブリュノは高校の文学教師で、二人は異父兄弟だ。現在40代となった二人は同じように愛を求めている。ミシェルは休職し思索にふけり、ブリュノは失われし青春を求めてセックスに狂っている。人生に対する埋めがたい空虚さを人はどうして埋めたらよいのか。主に二人の男の人生を描いているだけだが、性別、遺伝子、セックス、幸福、資本主義、宗教、種族といった観点について、社会を再構成していくための方法を模索している。最終的には壮大なSF作品たる結びで終わる。 ヒッピーってそんなに重要なのだろうか。 海外の人ってそんなに乱交ばかりやっているのか。
0投稿日: 2015.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すごい本だけど刺戟的に過ぎる部分もあり、感想としてはめちゃくちゃだったといった感じ。ラストはちょっと賛同しかねる。 しかし、人間への根本的な愛を感じる一作である。
0投稿日: 2015.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログテーマは『ある島の可能性』とほぼ同じ、というより、あちらが、この『素粒子』の続編みたいなものらしい。 若い時分に読んだらそれこそ死にたくなるような気分にさせられたかも。なんともやるせない小説。 女たちが次々自殺するがそれもご都合主義ではなく、切実さとリアリティを持って感じられた。 非モテ系の話と聞いていたけれど、作家のポートレイトを見る限りでは意外にも美男子(私がそう感じるだけ⁉︎) 訳者あとがきによると、主人公のひとりブリュノの人生は、ほぼ作家の人生と重なるそうだ。数度にわたる精神科入院など、驚いた。 ほぼデビュー作であるこの作品は、なんというか、怒りや絶望、作家の痛みが直に伝わってくるようで、読んでいて辛かった。『素粒子』の成功である程度余裕を持って書かれた『ある島の可能性』はこちらより完成度も高いと思うし、楽しんで読めたのだけど。
1投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ静と動、性と死が激しい物語。 対局的に位置する二人の兄弟の虚しさが上手く描かれている。取り分け、時間の流れ(若さ)への恐怖は読者をも病む。 あからさまな性の表現が多く、それ自体はいいが、もう少しミシェル側のストーリーが欲しかった。 なにかしら残ってしまった自分のしこりが、上手く解決できず、戸惑っている。
0投稿日: 2014.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014年6月の課題本です。 http://www.nekomachi-club.com/side/12885
0投稿日: 2014.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むのが超辛かった 現代社会の構造、生殖、生物の細胞遺伝子レベルまで一つ一つ丁寧に確認するとそこには悲しみが徹底的に染み渡っていて、でもそれを確認できたら、なぜか私は安心した。 いや、安心したのはやっと読み終わったからか… でも早朝の湖畔を散歩しているような気持ちになった。
0投稿日: 2014.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
久し振りの現代フランス文学。読メ友のfishdeleuzeさんお薦め。一見したところ文学作品には見えないタイトルなので、自分で手に取ることはなかっただろうと思う。なお、タイトルは原題の直訳。ブリュノもミシェルも親に捨てられ、また子どもとの縁も薄い。常に勃起し、女を求め続けるブリュノ。一方のミシェルは、ほとんど性的な関心を持つことがない。1960年代のヒッピーからニューエイジを経て、性と社会や人間性の解放が謳われるが、ここに描かれた主人公たちの人生と共に、それはむしろ愛の不毛を確かめただけであるかのようだ。
0投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ相対性理論と量子力学による現代科学のパラダイム・シフトは20世紀を物質主義的価値観に塗り替えた。それは宗教的抑圧からの解放に繋がることでサド侯爵的性の快楽と同調し、しかしながらも性の自由は競争原理を呼び寄せる事で逆説的に性の抑圧へと結び付く。性への強迫観念に囚われたブリュノと禁欲的な生物学者ミシェルという異父兄弟の生涯を濃厚な性描写と情報量で描きながら、人生に対するやり切れない諦観を滲み出させている。ニューエイジの怨霊を駆逐し、ハックスリーの亡霊を21世紀に呼び寄せる本書は、打ちひしがれる様な凄い本。
4投稿日: 2013.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ相反する貞淑と自由恋愛の概念、オクシデントへの僕らの眼差しは依然として、性に対しては十分に自由な選択を彼らは行っているに違いないというものだといえるが、本書を通してみると、月並みな表現であるがなにもかもいいことづくめではないようだ。 「恋愛先進国」(こういってよければ、そして現代において恋愛とはすなわち性行為と結婚を後に控えた個人の一大スペクタクルである)フランス作家界の旗手ウェルベックの最高傑作と謳われる今作、一般的には個人的な問題として片付けられて来たセクシュアリティを、遺伝子と先端科学というフィルターを通して、社会変革プログラムの超えるべき壁として呈示する。 日本においても、高度経済成長を境に進む都市への人口流入、それによってもたられた「核家族」という家族構成の最小単位と、凄まじい移り変わりの中に僕らの”性”こういってよければ”生”は置かれてきたといえる。人間を取り巻く環境が人間を作り出すという「唯物史観」的な観点にたてば、観念的な異性関係とは、正しい性関係・夫婦関係とは、などという論の立て方は、厳格なカトリックがその信徒に教会を通して指導してきた方針と同様にお笑いぐさである。 しかし、ポストモダン的・脱構築的手法がすべてを解体し、白日の下に曝したとき、僕らがこれまで信じて来た”性関係”とは空無であったという”衝撃的”な事実に未だ耐えられない”ピュア”な僕たちというのもまた事実である。論理だけで生きていくことはできない。いかに馬鹿な決まりであれ、文化というのは撞着語法的なものなのである。そこに”ある”と強く信じることにによって何かが見たされている空無、それが文化の本質である。 ラカンのテーゼに従えば、「異性関係は存在しない」。ここでいう異性は、広く他者ということもできるし、言葉通りの異性でも言える。僕らは性交を行うとき、相手の性器と自分の性器をこすりあわせてマスターベーションをしているのである。平たく言えばこういうことだ。それは、とりもなおさず他者表象や他者とのコミュニケーションの地平を揺るがす、断絶である。 そういった、不通・不全のなかで、僕らの性関係、言い換えるなら遺伝子にインプリントされた醜いプログラム”再生産”をどう扱うのか、唯物的に歪められてきた性の変遷に終わりはあるのか、日本においては現代美術家の中原浩大がその作品『デート・マシン』で表現した”再生産過程の現時点におけるスペクタクル的表象”をどう乗り越えていくことができるのか、性の商品化の動きと、それらと切り離せない、”性の実験”ともいえる西洋のニューカルチャーの歴史的記述と、それらに対する辛辣な批判と幻滅、そしてそれの悲しい残滓をあけすけに記述してゆく。 弁証法的な解決を著者自身ももはや望めない世界に対して、SF的な解決を用意するあたり、個人的には非常に面白いが、ここでは善し悪しが別れるところであろう。
0投稿日: 2013.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ一度読んでそのままだったが、最近思い出し再読。 著者の主観が非常に強く偏見に満ちた書き方をしているので、感情移入しないで見世物として読むことを推薦します。 母親の愛を知らずに惨めな人生をおくる兄と、遺伝子物理学の天才である異父兄弟の弟のそれぞれの生き様が描かれている。 性に振り回され滑稽な悲劇ばかりで彼らの相方も皆不幸せな生き様ばかり。こっけいな行動は身にしみる箇所があって苦みばしった笑いしかでてこない。 そんな描写が延々と続くのですが、哀愁ただよう表現とポエジー溢れる文章が心地良い。 くだくだしい部分が多々ありますが好きな人にはたまらないところがある作品です。
0投稿日: 2012.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログフランスで有名なこの人、私の本好き友人に聞いてもその意見は「素晴らしい」か「糞」かの真っ二つに分かれるのが笑えます。地名やら商品名やら企業名やらをとにかくディテールに渡って細かく書いていってキャラクターを描写するというのは私にはすごく面白いと思うけど、根底に流れる、決して消えない、主人公の(ということはあるいは作者の?)徹底的な悪意に満ちたモノの見方にはかなり疲れます。 人物から流行現象まで様々な対象物に対して敢えて客観的・統計的な描写が並びますが、時にそれが大いに主観が入った幼稚な攻撃に形を変えたりもします。とはいえ、主人公(他の作品にも常にこのタイプは出てくる)の毒を含んだ呟きはたまに的を得ていて、どきっとさせられるのです。「人は他人との関わり合いのなかで、自意識を持つ。まさにその自意識こそが、他人との関係を我慢できないものにする」。 全編通してとかく女性への攻撃が多いのは典型的なコンプレックスの吐き出しでしょうか。それとも作為的にあそこまで意地悪な表現を取っているのか?もっと奥が深いのか?? と思わせられ、ページが進んで行きます・・・。 読後感は悪いのに、何故かはまる。
2投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ難解な内容。終始ストーリーの方向性が見えない。全体的に叙事的かつ客観的描写が多い。感情論に頼らない文体は孤独な、あるいはシニカルなニュアンスを強めると同時に人類の本来の姿・性質(動物性)を想起させる。観念論や唯物論、更にはヒューマニズムの歴史に関する言及が多く、「今後人類の思想はどう展開してゆくか」といった壮大なテーマを含んでいるよう感じた。 その答えは十人十色。 いろんな読み方があります。とにかく近代西洋史や思想史に興味がある方はきっとインスパイアされるだろう問題作だと思います。物語として読むより思想本として読むことをおすすめします。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物学から始まって自然科学、原子論、哲学に至るまで、とにかく難しい。 結論として、たぶん、唯物論を語っているんだと思う。そこには当然「愛」と「死」というテーマも絡んでくる。 私は唯物論的に広く大きく物事を捉えられるタイプの人間じゃないから、分かるけど共感はない。 Amazonのレビューで、「好き嫌いがはっきり分かれる作品。冷静・分析タイプに向いている」と書いている人がいたけれどまさにその通りだと思う。 難しいとか共感はないとか言ったけれど、新しい発見というか新しい思考というかいつもの自分にないものを得るという意味で興味深かったし作品として面白かった。びっくりする結末だし、話の構成も展開も手法も素晴しいと思う。 読み終わった時には「なるほどすごい作品だなぁ」と感嘆せずにはいられなくなる。 ただ、物語の中盤は無駄にエロチックな描写が多いし、作品全体のトーンが暗いから(哀しい暗さではなく狂っていたり歪んでいたりする根の暗い不健全さのような暗さ)残虐な描写は吐き気がするくらい気分が悪いし、削除してもいい箇所も多くあるように思う。
0投稿日: 2010.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ珍しく現代文学を読んだのだが、これが非常に面白かった。 この作品は前々から評判だったのでずっと気になっていた。 98年にフランスで刊行されるやかなりスキャンダラスな反響があったそうだ。 読了後は「恐ろしい小説と出会ってしまった」という気分で満たされた。 正直なところ、赤裸々な性描写やいくつもの固有名詞からは村上春樹的な部分を感じた。 ただこの小説は明らかに非リア充で非スノッブ向け(主人公がまさに非リア充)。 欧米のマッチョ信仰的な恋愛観からはかけ離れたものとなっている。 なので個人的には感情移入がしやすかった。 個人的には性描写は特に必要なく、素人童貞でも良いと思ったくらいなのだが、小説全体の反左翼的な主張を考えれば不可欠だったような気もする。 その辺は評価が分かれるところだろう。 「素粒子」は数多の文学作品に見受けられる生への虚無感がテーマとなっている。 その虚無感をどうするのか。 それは衝撃的かつ突飛なラストに集約されている。 この手のオチは特定のジャンルでは珍しくもないかもしれないが、そこまでに至る精緻な筆力はさすが。 フランスで大反響を呼び、世界中で翻訳されたのも納得。 賛否あろうが個人的には大いに賛同したい。 ただし人には大っぴらに勧められない問題作なので星は4つとしたい。 物理学や生化学の知識があればもっと深く読み込めると思うが、なくても全然大丈夫。
0投稿日: 2010.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ邦題「素粒子」。フランスで最も物議を醸す作家、ミシェル・ウェルベック。初めて読んだ。入り込むまでに時間がかかるのは、その作家の世界観を知らないせい。入り込んでからはのめり込むように読み耽った。これほど悲しい物語を読んだのは久しぶりかもしれない。ガツンとくる物言いと悲しきストーリー展開。読んでいて、こんなに悲しい最後が待ち受けているとは思わなかった。最後だけが悲しいわけではない。後半は常に悲しい。怠惰。頽廃。擦り減っていく感触。現代性をここまで確実に捉えている作品て、そうないと思う。この人はすごい。。。なんといってもアナベルに心捉えられてしょうがなかった。(07/8/20)
0投稿日: 2007.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ(記憶では)兄弟がいて、兄は不細工で性欲ありありで、機会に恵まれない人。弟は天才科学者で性欲無い人。この兄弟の性的遍歴と、一族の歴史に20世紀思想史の偉人たちが絡んで、加えて量子力学の発展史も絡んで・・・・・ポストモダン全否定して・・・・・ニューエイジ称揚して・・・・・みたいな。端折りすぎですが(笑 なにせ凄い小説です。やばい文学です。 なんせ、ひたすら性的描写と思想史エピソードがくんずほぐれつです!!頭悪い紹介ですみません(´_`ヽ) 最近ちくま文庫に入ったみたいなんで、よろしければどうぞ。 作者は、ラヴクラフト論でデビューしたという変人じゃなくてユニークな方。残念ながら、ラヴクラフト論翻訳されてませんが。 「素粒子」の後、タイの買春ツアーに参加するビジネスマンの小説(悪趣味ですねぇ)が、翻訳出てたような気もします。グ愚って下さい、手抜きです。 「素粒子」の凄い?ところは、とにかく性をえげつなくというか、苦渋に満ちたものに描くところです。人間の苦悩のすべては性に起因するといわんばかりに。というか、ずばりそう言ってます!!初期のオーケン(ノーベル賞の方)なんかにも近いかなぁ?どうだろ? 個人的見解ですが・・・・・ フランス文学好きな人、 ラヴクラフト好きな人←関係ありません、 SF好き!!な人、 20世紀思想史に興味ある人、 性嫌悪症な人、 生物嫌いな人、 食物連鎖と生殖連鎖が愚劣だと思う、「はにや」な人 科学の力で人間をなんとか出来ないかと思う人、 思想はともかくヴィトゲンシュタインの生き様に惹かれる人、 生きるのってかったるい・・・・な人、 性行為の機会ありません・・・・な人、 もう、はなから興味ありません・・・・な人、 なんでみんなそんな事に・・・・・みたいな人、 にはお勧めです!!なんか書いてて疑問に思えてきましたけど・・・・・。 ・・・・・・このリストは・・・・・自分の事か?・・・・・(×_×*) エピローグで、体に電気走って・・・・感激して涙出そうになった私は・・・・・世間的にはアレですね(笑 あんまり詳細書きたくないのだな、この原作については。とにかく読んでみろって!!強気に押す!! なんでこんな小説・・・・・と思われても、私は責任持ちませんが。 私は脳天直撃でしたがねヽ(T_T )ノ
0投稿日: 2006.07.28
