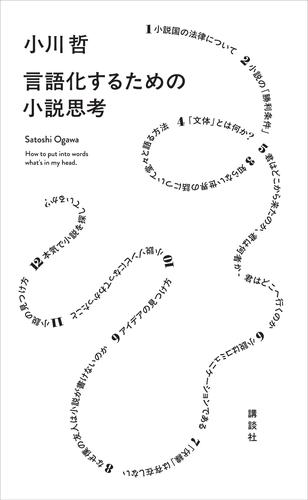
総合評価
(18件)| 8 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ芸術創作系の中で、最も知りたかったことが書かれてしまっている名著。 後半で端的に述べられる、表現活動とは何か?と、それに則った小説の技法は、全クリエイター必読かつ即実践すべき内容の嵐(まったくの異分野な私も、今日から早速活用させて頂いている)。 それにしても、著者は何者なのか。小説家の書いた本でありながら、「面白い」の古今東西を専門研究する分析哲学者なんでは?と思えるほど、様々な視点から、小説、いや商業クリエイティブも含むあらゆる表現サービスの所要を解体的に露わにして、その本質を浮かび上がらせてくる。 全くの異分野の人間だが、「ユーザーとは何か?面白いとは何か?」を日々探求しているという意味で同業者な小川さんから、いろいろな教えをこうべく、語らってみたい。それぐらい魅力的な一冊だった。ご馳走様でした。
0投稿日: 2025.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ推理小説などを読む時、どこから考えてるんだろうと不思議でしたが人によるとはいえ作家さんたちがこんな風に考えて作品を作っているんだということがわかり、面白かった。 そして相当頭がいいんだということも。 商業作家として作品を生み出し続ける為には小川さんのように読者と作家の距離感を考えながら描かなきゃいけないのかと。 大変なお仕事ですね…。 と同時に、私たちの感想も作者の意図しない捉え方をされているかもしれない…という誤読の答え合わせをするためにも大事なんだと気付かされました。 これからはありきたりな感想じゃなく、私が感じた、作者に届ける感想、次の読者に向けた感想を書くことを頑張ってみようと思う。
7投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説家による小説の書き方教本。実例多くて分かりやすい。書く方はめんどくさかったやろうなぁ。特に巻末の「エデンの園」はオモロい。
0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書ノート: その文章、「自分のため」に書いていませんか? 「伝える」ではない、「伝わる」言葉を、文章を生み出すために、小説家はいつも何を考えているのかーー? 『ゲームの王国』『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』 祝デビュー10周年! 時代を席巻する直木賞作家・小川哲が、「執筆時の思考の過程(=企業秘密)」をおしみなく開陳! どうやって自分の脳内にあるものを言語化するかを言語化した、目からウロコの思考術! ☆小説の改稿をめぐる短編「エデンの東」も収録! ☆手に取りやすい新書サイズで刊行! 小説ーーそれは、作者と読者のコミュニケーション。 誰が読むのかを理解すること。相手があなたのことを知らないという前提に立つこと。 抽象化と個別化、情報の順番、「どこに連れていくか」を明らかにする……etc. 小説家が実践する、「技術」ではない、「考え方」の解体新書。
0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほどあの小説たちはこのように生まれるのですね。 センスだけにあらず、読み手を考慮した緻密な計算がある。 昔、ビートたけしがお笑いについてまじめな話をしていたのを思い出します。 巻末に、それまで論じたことわかりやすく説明するかのごとくの小説も掲載されているのがいいですね。
16投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分にある「これは気に入らない」という小説法というのが小説の良し悪しを決定す。 自分自身の体験を抽象化し、他のものに当てはめて具体化する。p38 私の体験、経験を抽象化し、別のものと共通している所を探して想像する。 違っている所は……。(実際調べたり、想像するのかな。) 普遍的な構造は抽象化された部分だろうね。 違いは表面上のものに過ぎないかな? 情報の順番 心情から始めるか、具体から始めるか、結論を先にいうか……。 情報量の差をうまく使う。 (小)心情や行動原理を説明すると、その人物との一体感が生まれてサスペンス的要素が生まれる。 (大)先に結論を言ってから理由を説明するのは、だんだん情報量の差が縮まっていく構造になっている。 どこへ向かっていくのかを冒頭で示している小説が傾向として売れている。p66 「小説とは、内輪であれば内輪であるほど面白い」 どれだけ多くの前提条件を読者と共有できるか。 「顔の見えない読者」をどうやって想像するか。 どうすれば「私に向けられた話だ」と思ってもらえるか。p74 小説は「伏線と出来事」の連続である。 必要なことだけ話す。 「象徴的で影響力の大きな出来事(伏線)」 小説には意味のある文章しか書かれてない……と 主張、設定は後から考えるべき 小説を通じて書いてみたいこと、考えてみたいことを書く。 答えより、問いを設定。p95 物語とは偶然の出来事に耐えられなくなった人間が作り出した虚構…… 陰謀論は必然性(安定、分からないものの理解)を求める人間の心理に基づいている。 想像から出発して、事実と違くてもそのままにしておく。 事後修正、事後修正で小説を作っていった結果、それがアイデアになる。 自分の価値観を捨てれば、様々なものが許容できる。視点が広がる。p118 日常に潜む「小説」 日常での疑問とか自分の感情の変動とか、そういったものに敏感になるってことだね。疑え!(問を出す) 動機づけは後から。行動を先に。(実際の人間もこうだろ)p138
0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ全ブクロガーにおすすめしたい! いや、ごめん言い過ぎたかも 小川哲さん好きな人におすすめしたい! これだと狭くしすぎか あ、なんか小川哲さんファンなんかそんないねーよみたいな言い方になってしまった そんな意図はない ちなみにわいは小川哲さんコンプリーターなのでね かなりのファンです 本書は小川哲さんが「面白い小説とは何か」という考察のぐるぐるを詳らかにしていく ファン心理として頭の中を覗けるのは嬉しい なのでファンの人は必読 ファンでない人の扱いがムズい ん〜そうね〜 もうあれ、勝手にすればいい(投げた!) 読むも読まぬも勝手にすればいい いやでもなんか分かった気になれるよ これ読んでおくといっぱし感出せるよ この伝わらない感じは、この本の中身が全く活かされていないことこの上ない
75投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『直木賞作家・小川哲の小説論』 SF・歴史・エンタメと幅広いジャンルの作品を執筆する直木賞作家・小川哲。本書は一般的な「小説の書き方」の本ではない。小川氏が小説を書く上で大切にしている“ポリシー”や“哲学”といった小説論を包み隠さず綴り、一冊の読み物として集約した作品である。 まず、作家が小説を書く上で頭の中で考えていることを作品にして商業出版すること自体が少ない。それは、真似できるかどうかは別にして、作家にとって開示したくないスキルの核となる部分だからだ。小説家を志望する人にとって、このノウハウは垂涎の的である。創作活動のヒントがゴロゴロと転がっている。小説家志望ではない私のような読書家にとっても、稀有な作品としてとても楽しめた。 一般的な小説の書き方ハウツー本ではないとはいえ、本書は小川氏の金言にあふれている。「読みやすさとは視点人物と読者の情報量の差を最小化すること」、「実際の会話の劣化版になってはいけない」、「小説は作者が何を表現したかではなく読者が何を受け取ったかによって価値が決まる」、「書き手のために存在している文章を徹底的に削る」などなど。こういった感覚を言語化できる表現力が凄まじい。 小川氏は他書でも「自分は小説家にしかなれなかった」というような発言をよくしている。『君が手にするはずだった黄金について』は、まさしくこの“謙遜”をエンタメに昇華した作品だ。しかし、この何気ない日常から小説を探し、文章で表現するという作業はとてつもなく労力を必要とするはずだ。 本書の巻末に収録された短編「エデンの東」は、こちらも“読者にとっての読みやすさ”を皮肉たっぷりにエンタメに昇華した作品である。石川能登地震のチャリティ作品「あえのがたり」ですでに読んでいたが、本書を読んだ後では意味合いが変わってくる。資格も入社試験もない小説家という仕事。たしかに自分で名乗ることでしか表現できない特殊な職業だ。でも、言語化という作業を呼吸をするようにできる小説家・小川哲を、私はやはり尊敬している。
13投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ君のクイズを読んでずっと気になってた小川哲さんの本。著者の言うとおり、「小説の書き方」ではないけど、ものすごく鮮明に小説家頭の中を見せてもらってる感覚になって、驚きと感動と尊敬とが入り混じる本でした。 本を書く時にそこまで考えてるのかという発見はもちろんたくさんあったけど、今後私が本を読む上でもっと楽しめるわ〜と思える考え方をたくさん手に入れた気がする。 小川さんが好きな人も、小説家を目指す人も、小説が好きな人も、誰が読んでも面白い一冊でした!!! --- 非常に世評が高いけれど、どうも自分には合わない小説があるー読書を続けていれば、誰しも一度ならず経験したことがあると思う。そういうときは、自分の小説法と著者の(加えて、その著者のことが好きな読者の)小説法が違っていることが多い。 ---
12投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
直木賞受賞以降であるが、近年、著者作品は比較的読んでいるほうだ。 なので、本書の主張は、わりとストンと腹落ちする。とにかく、よく考え、試行錯誤をして作品を生み出している作家さんだということはよくわかる。作品を読んでいてもそう思うが、それを「言語化」して述べてくれているので尚のこと。 (この「言語化」という表現は、昨今の流行なので、売らんが為の策略が透けてみえて、どうかと思うが) 本書は、世にあまた存在する小説の書き方指南書とは一線を画す。お作法、文章術ではなく、タイトルにあるように、いかに思考し、小説のタネを見つけ、それを作品として昇華させるかの端緒が語られている。 いわゆるお作法的なことは、「法律」と称し、なかば揶揄しているところも面白い。 「全体の傾向として「わかりやすい物語を書く」ことを重視する人はやはり多くて、ストーリーと設定に関する法律が数多く定められている。」 曰く、「ご都合主義」関連法、クリシェ使用罪といった書き方で、それを以って、作品の批評、読後感を語るのは本質ではない、ということだ。 作る側もそれに囚われることもないというか、法律に触れないようにすること、つまり、作者都合の展開の回避、常套句の濫用などを戒めて書くのは基本中の基本ということの裏返しでもあろうか。 出版社の営業担当が腕まくりをして売りたい、と思う本はいかなるものか、「答え」ではなく「問い」が重要と、大切な教えが並ぶ。読み手を意識し「情報の順番」を考えるという教えには、大いに目を開かされた気分だ。 「「作者が何を表現したか」ではなく「読者が何を受け取ったか」によって価値が決まる。」 御意!!
2投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の頭の中をのぞいているような感覚と、学生時代に現代文で先生が言っていた内容の答え合わせみたいな感覚になる。 小説家って感覚で書いてると思っていたけど、全員がそういう訳ではないってこと。日々技を自分のものにし、表現方法を模索している。 音楽家と似ている。 読書に慣れていない人にも読みやすい本と思った。だけど、偏見の例として出てきた検見川サンダルの苦学生のくだりはちょっと無理あると思った。
0投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説とは何であって、小説家は何を考えているのか。著者の体験や思考を通じながら小説の面白さとは何かの真髄に迫ってゆく。各所での著者の文学談義に表れていた読者として一流の面が存分に出ており、小説を書きたいと思っている人も、小説を読むのが大好きという人も万人におすすめできる一冊。
1投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読んでみて序盤から驚きの連続でした。 本当に1番最初ですが、「小説法」。 だから自分と他者が面白いという本は違うのか……!と心底驚きました。 私の小説法を考えてみると ・共感できる登場人物がいる ・オチがある ・世界観が作り込まれている ・救いがあること ・生理的に嫌悪感を抱くシーンがないこと ・やたらめったら登場人物を増やさない (これはいわゆるモブキャラなのに名前がついている状態のこと。人物相関図にも載らないような関係性で作中数度でるかでないかなのに、名前がついててややこしい。人物相関図を見ても載っていなくて誰だっけ?な人がいないこと) でした。 何度も賞を受賞されるような作家で、 この作品いいよ!とおすすめされて読んでも自分の心に響かない理由が言語化されてこういうことか……と心底納得しているところです。 小説を書く人も読む人も、1度読むの自分の小説法に気づいて今後の読書ライフが快適になるなと思いました。 他にも「言語化するための小説思考」を読み、それを踏まえて最後、「エデンの東」を読む。 すると、ああそういうことか…!わかりやすさ、読者のため、はこういうことか、と心の底から理解できました。 改めて、読者をもてなすために試行錯誤して小説を書いてくださっている作家の皆様に感謝したいです。
2投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「偶然目の前に転がってきたアイデアをしっかり摘みあげる能力」サラッと書かれているけど、これが難しいんだよね。 まずは、自分が何を書きたいのか、何を考えたいのか、考えてみたい。
1投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭の良いひとだ 小川哲は就職したことのない人間らしい。それも就職や人間づきあひがいやで、小説のことばかり考へつづけてきたらしいのだ。 わかる。 正直『地図と拳』は、ほぼ帝京大学の澁谷氏の助けを借りてゐるので、その点は感心しない。 しかしこの本は面白い。 文体とは情報の順序である――思いっきし単純化していへばさういふことを主張したり、目から鱗が落ちた。 読者と作者の齟齬をどうやって埋めようかと考へつづけて、辿りついた答へらしい。 もちろん主張はそれだけでなくて、どれもありきたりの創作本とは違った切り口なのがよくて、作者の頭の良さがうかがへるのだ。
0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ小説の書き方を考える本でありながら、それを突き詰め、ついに小説という側面から見たコミュニケーション一般への見つめ直しに(勝手に)波及していく。面白い小説の話が、面白いとは何か?に変わる。だからこの本は創作論であり、それどころではない。
3投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり小川さんは面白いです。小川さんの頭の中をのぞいている感じで、こういうことを考えて日々創作しているんだと興味深かったです。9.アイデアの見つけ方の美容院と便所スリッパのくだりは思わず笑いました。ご本人も、東大卒、とにかく頭のいい人なんだなという感じで、話も面白いし、若干こじらせてもいるし、これからも小川さんの作品には注目したいと思います。楽しかった!
2投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログユートロニカ、君のクイズの二作における作風の振れ幅に驚き、著者自体への関心から本書を手に取った。 読むほどに、小説家とはこう思考するのかという興奮があり、その卓越した論理展開を追体験していると錯覚させる。 最終盤にこれまで展開した技法を作品として結晶させる構成が、とても瀟洒で知的。 未読の「火星の女王」にも期待が高まった。
9投稿日: 2025.10.24
