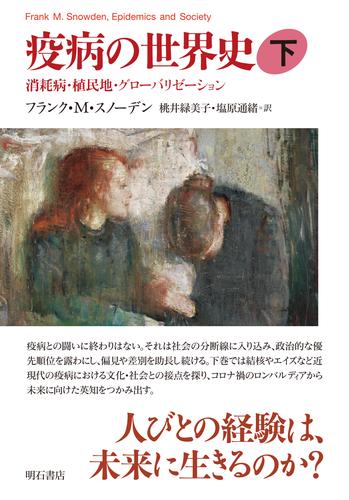
総合評価
(2件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018年に上梓、この版にはCOVIDの経験が追加されている。 人間は過去の経験に学ぶこともあるし、学ばない事もあるけれど、螺旋状に進歩してきたのでは(歴史は螺旋状に進むと言ったのはE.H.カーだったか⁇)。 英国ビクトリア朝のあのゴタゴタしたインテリアが流行遅れになったのは、衛生観念の発達からだ、と言うのは面白かった(どうやって掃除していたのか、いつも不思議だった)。 エビデンスに基づかない、風評で政策決定する政治家がいつの時代にも登場するのも面白い。
0投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
p.183 マラリア マラリアは、人間と環境との結びつき、人間と人間との結びつきを含めた全体を、最も色濃く反映した感染症なのである。運動の当事者たちは、その結論に基づいて、貧困、環境悪化、栄養不良、貧しい住環境、非識字、無知、難病の発生、不適切な濃厚など、これら全てがマラリアの要因なのだと主張した。最初の特効薬としてキニーネが無料で配布されたのも、住宅環境や住宅事情や賃金や識字率の向上、十分な栄養、国の道徳的な関与を背景にしてのことだった。これらの要因は、キニーネそのものと同じ位重要な抗マラリア剤だった。マラリアは、強力な科学技術的ツールの適用とともに減少したが、社会主義が広まるにつれても減少した。しかし、どれほど強力な科学技術があったとしても、疑問は残る。その科学技術を配備するのにふさわしい状況とはいかなるものか。マラリア撲滅運動の創始者の1人であったアンジェロ・チェッリはこの疑問に対しいつの時代にも通用するモットーで答えている。「何かをするのは良いが、他のことをおろそかにするな」。チェッリが示唆するように、有効なマラリア根絶計画たるものは多面的な目覚めを喚起すべきである、というのがサルデーニャの教訓なのかもしれない。関係各所の協力、富裕層の道義心、住民が自分で自分の健康守れるだけの教育、医療へのアクセス、効果すぎない治療、環境衛生、そして基礎科学研究にからもたらされるツールそのどれもが必要なのだ。チェリーのモットーからは、サルデーニャのもう一つの教訓をうかがえる。マラリア制圧は「応急処置」に頼るのではなく、長期的な寛容を基盤にする必要があると言うことだ。サルデーニャのでのマラリア根絶は、半世紀に及ぶ運動を経て初めて果たされたのである。そしてもう1点、サルデーニャの成功は、国際支援の重要性を例証してもいる。サルデーニャが根絶と言う最終目標達成するにあたっては、アメリカの財政的、技術的な支援が欠かせなかった。そして病気と言うものは世界全体にとって重要な、世界命にも関わる利害関係が絡んだ国際問題なのであると言う明確な認識も欠かせなかった。マラリアもまた、あらゆる疾病と同様に、国家の危機ではなく人類の危機なのである。このように、根絶の複雑さに関しての重苦しい共感は数数あれど、やはりサルデーニャ計画は、病気の根絶によっていかに地域の潜在的な資源を活用できるようになり、根絶するまでの努力が 報われることになるかを示す、希望に溢れた実例だ。戦後のサルデーニャの発展は、もはやマラリアが生産性を阻害し、教育を制限し、資源を浪費し、貧困を強要することがなくなったからこそのものである。今日のサルデーニャは、マラリアがお米された時に初めて得られる社会的、経済的、文化的な可能性をまざまざと例証している。 ポリオ:急性灰白髄炎ー糞口経路・接触感染 GPEIの歴史を明らかに、天然痘との比較で生じた無批判な楽観が、見当違いであったことを実証している。天然痘は、攻撃されると弱いと言う点において例外的であったのだ。天然痘には病原保有体動物がなく、交差免疫の問題を突きつける血清型の多様さもなかった。病状は派手で、すぐにそれと見分けがついた。病気に勝って生存できれば、強固で持続的な免疫がついた。そして交易に使われたワクチンは、1回の投与で効果があって、ワクチン関係の疫病を解き放つ恐れは一切なかった。それに比べて、ポリオははるかに手強い敵であり、撲滅主義者の最初の展望がいかに幻であったかを思い出させてくれる。病気に対する最終的な勝利は、稀な成功として言われるべきものであり、段階を踏んでいけば当然のように病原体のいない楽園につくわけではない。ポリオの制服は、すぐそこまで迫っていながらなかなかたどり着けない目標だが、もしそれが果たされたとしても、根絶が叶った人の感染症のようやく2例目にすぎない。このキャンペーンの最終結果がどうなるかは現時点ではどちらとも言えないが、いずれにしても、この過程で見えてきた様々な困難が明らかに教えてくれることがある。感染症根絶するためには、適切なツール、大々的な資金調達、念入りな入念な計画、持続的な努力と、そして何より幸運が必要なのである。 HIV/エイズ ・ アフリカでは、エイズは主に異性間性交を通じて感染する一般市民の病気になった。一方、先進世界では、男性同性愛者、静脈注射薬物の常習者、少数民族など、社会的・経済的に阻害された人々の間に犠牲者が出る「集中型」の感染症になっていった。 ・ 南アフリカの統計局の2011年の判定では、世帯が「生存に必要な最低限の金額」を稼ぎ出せないことが貧困の水準とされている。言い換えれば、貧困が最低基準、すなわち生命維持レベルで定義されていると言うことだ。この指標は「食料貧困線」と言って、1日のエネルギー摂取量2100キロカロリー分の食料を購入できる一線を指す。この基準だと、人口の21.7%換算すれば約1200万人が、健康を維持するのに必要な栄養所要量を達成できていない。必然的に、6歳未満の子供の23%は栄養不足が原因で発育不全に陥っており、特に農村部ではその割合が突出していた。2011年の調査では、アフリカの黒人の半数以上が、1日に必要な摂取量を満たすだけの十分な食料は得られていないと感じていた。結論として、「アパルトヘイトにおける人種間不平等」は、同じように深刻な「市場の不平等」にとって変わられたに過ぎなかった。 ・ HIV/エイズの流行が広がり始めた1980年代以降、アパルトヘイトに支配され、次いで市場に支配された南アフリカは、一貫して、病気が広まるための必須前提条件栄養不良と、それによる免疫低下を提供してきたのだ。しかも変更の影響はそればかりではない。南アフリカのHIV/エイズ罹患者は、HIV陽性の状態からエイズ発症までの進行が、広く急速にならざるを得なかった。それというのも、後レトロウィルス療法を受けられるだけの金銭的余裕がなかったからである。HIV/エイズと貧困は、それぞれが違いの原因であり、結果であると 言う悪循環に陥っている。これは一部では「貧困とエイズのサイクル」とも呼ばれている。 ・アフリカでは政権によってエイズ蔓延が隠蔽され、そのことが垂直感染やさらなる蔓延を引き起こした。また、抗レトロウイルス薬の配布を拒否したことで、急激な病状悪化が防げなかったことも敗因の一つだ。 ・ マイアミ、フォートローダーデール、ジャクソンビル、オーランドといったフロリダ州の各都市の状況は、エイズ撲滅キャンペーンの当事者に、今のアメリカのエイズ流行を加速させている要因を全てまとめて突きつけている。絶えず入ってくる多数の移民。医療を受ける機会を限られているために後レトロウィルス療法の成功もほとんど望めない、相当数に上るアフリカ系アメリカ人の集団。売春ツアー産業の隆盛。深刻な数のホームレス。格差の蔓延と都市部の分厚い底辺層。最も高リスクの集団に診断を受けさせず、したがってHIV感染の有無を知ることもできなくさせている、広く浸透 したスティグマ。HIV/エイズへの「援助疲れ」に陥って、他の健康問題を優先する州議会。深刻なヘロイン中毒の問題。そしてCDCの言葉を借りれば、「同性愛嫌悪、トランスジェンダー間を人種差別主義、および育成的な話題を公の場で議論することへの全般的な不快感が蔓延している」バイブルベルト(キリスト教篤信地帯)文化。これを書いている現在、ドナルド・トランプ政権のもとで連邦政府はリーダーシップを取ろうともせず、問題を対処問題に対処するための戦略を練ることも、HIV/エイズ 撲滅の既存プログラムに資金を提供することも断っている。 p.286 これらと腸チフスに対応する防御としては、下水道や排水溝が整備され、砂のろ過、水の塩素殺菌も行われた。ペストには、防疫戦、検疫、隔離の対策が取られ、天然痘には予防対策としてワクチン接種がなされた。そしてマラリアに対しては世界初の「特効薬(マジックブリット)」、キニーネが処方された。一方で、食品の取り扱いにも進歩があって、低温殺菌、滅菌のための缶詰処理、海産物養殖場の衛生管理など が普及した結果、ウシ型結核菌やボツリヌス菌感染など、食品由来の様々な病気も防がれるようになった。したがって、すでに20世紀初頭には過去にもともと恐れられていた疫病の多くが激減したが、それはもともと科学が適用した結果と言うよりも、経験上の知識が生かされた結果だった。だが、まもなくそこに新しい強力な武器を追加したのが科学だった。ルイ・パスツールとロベルト・コッホが確立した生物医学的な疫病モデルは、かつてないレベルの理解を促し、次々に科学の発見と、新しい副次的の専門分野(微生物学、免疫学、寄生虫学、熱帯医学)を生み出した。一方、ペニシリンとストレプトマイシンによって抗生物質時代が到来し、梅毒、ブドウ球菌連感染症、結核が治療できるようになった。ワクチンの開発も、天然痘、百日咳、ジフテリア、破傷風、風疹、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、ポリオの発生率を劇的に低下させた。そしてDDTはマラリアのマラリア原虫を始めとする 昆虫媒介の病原体を今にも一掃できそうに見えていた。こうして1950年代には、過去に蔓延していた感染症の多くに対する有効な手段が科学的発見によってもたらされていた。これほどの劇的な発展から考えて、今後も伝染病は1つずつ根絶されて、いずれ消滅点に達すると期待するのが妥当だろうと、多くの人が結論づけた。実際、世界規模での天然痘撲滅運動は、まさにそうした例を、提供した。WHOは1980年に天然痘が史上初めて、人間の意図的な行動によって根絶されたと発表したのである。感染症の制服という信条を力説した人々は、微生物の世界をほぼ静的な、あるいはそうでなくとも非常にゆっくりとしか進化しない世界だとみなしていた。そのため、いくら既存の感染症に勝利を収めていても、まだ人類が経験したことのない、免疫を働かせられない新規の病気が出てくるかもしれないと言う懸念はほとんど持たなかった。歴史に対する健忘症に陥って、西洋では過去500年、新しい病気が周期的に出現して大惨事をもたらしてきたことを都合よく無視した。しかし実際、例えば1347年にはペストが、1490年代には梅毒が、1830年にはこれらが、1918年から1919年にかけてはスペイン風邪が発生していたのである。 ・「病原菌の普遍性」ー現在ある病気が今後も出てくる病気であるーと言う考え方は、1969年に世界中で採用された国際保健規則の土台にまでなっており、この規則によって「通報」が必須と定められた病気は、19世紀の3大疫病であるペスト、黄熱、コレラしかなかった。通報とは、ある病気が診断されたときに国内外の公衆衛生の関係各所に報告することを求める法規則である。その通報対象に、既知の3つの病気しか含められていなかったと言うことは、もしも未知の、しかし感染力の強い致死的な病原体が新たに出現したときにどういう行動を求められるかを、この規則は何も考えていなかったと言うことだ。微生物世界は不変であると言う確信が、撲滅主義者の展望を支えていた信条のひとつだったとすれば、進化に関するもう一つの誤った考えも、やはり大きな役割を果たしていた。それは、自然は基本的に善である、なぜなら自然選択の圧力により、あらゆる伝染病は時間とともに弱毒化するからである、と言う定説だった。原則として過度に致死性の高い感染症は、宿主を早々に殺すことによって自ら伝播経路を断つことになる。したがって長期的に見れば、その感染症は片利共生と平衡 に向かっていくはずだ、と勝利はは主張した。新たな疫病がたまたま強毒だったとしても、それは一時的な不適応であるから、いずれ穏やかなものに進化して、最終的には治療の容易な小児疾病になる。良い例が、大痘瘡から小痘瘡に進化した天然痘や、16世紀の劇病型の「大痘」から今日の遅効性の疾患に変容した梅毒や、古典型から遥かに穏やかなエルトール型に変容したコレラである、と言うわけだった。 p.289 人類は健康と疫病に疾病に関して3つの近代性の時代を経てきた。その最初の時代曰く「疫病と飢餓の時代」が具体的にどの時代にあたるかをオムランは明確に示していないが、ともあれ、それが西洋では18世紀まで続き、マルサス主義で言うところの積極的な人口抑制因、すなわち疫病と飢餓と戦争を特徴としていた事は明らかである。続く「パンデミックの後退の時代」は、18世紀半ばから始まって、西洋の先進諸国では20世紀初頭まで、非西洋諸国ではその後まで続いた。この期間に、感染症による死亡率は次第に減少した。そこで先頭を切っていたのは結核であったとみられる。そして最後に、西洋では第一次世界大戦後、それ以外では第二次世界大戦後に、人類は「変性疾患と人為的な疾患の時代」に入った。疾病の時間的発展の初期段階では、社会的、経済的な条件が健康状態と感染リスクを左右するので支配的な役割を果たしていたのに対し、この最終段階では、医療技術と科学が手綱を握った。その影響下で、感染症に よる死亡数と、罹患数は次第に減少し、かわって別の死因が増えてくるようになった。それが心血管疾患や、がん、糖尿病、代謝性疾患などの変性疾患と、職業病や環境などの人為的な疾患、および事故である。1979年に合衆国医務総監ジュリアス・B・リッチモンドが言ったように、「健康転換」理論の観点で見れば、感染症は、後にそれに取って代わる変性疾患の「前身」に過ぎず、この入れ替わりは一方方向しか進まない単純プロセスの結果にとして生じると考えられる。 p.293 科学者・代議士・公衆衛生界の声に加えて、マスメディアも、この予想外の新たな危険を大々的に取り上げ始めた。特に1990年代に世界中の関心を集めた3つの出来事により、その教訓が深々と理解されてからは、歩道もいっそう熱を帯びた。第一の事件は、南米途中でですアジアこれらの大規模な流行が始まったことだった。これは1990一年にペルーで始まり、急速に大陸全体に広まって、最終的に16の国で400,000人の患者と4000人の死者が報告された。アメリカ大陸ではもう1世紀もの間これらが発生していなかったから、この歓迎されざる客の到来は、公衆衛生の進歩 の脆さを全世界に再認識させた。これらは糞便による食品と水の汚染を通じて伝播するので、いわば「ピンクの温度計」であり、社会の怠慢と標準以下の生活水準の絶対的な指標である。したがって20世紀末の西洋でこれらのアウトブレークが起こったと言う事実は衝撃をもたらし、自分たちがいかに脆弱であるかを突如として気づかされた。 p.306 抗微生物薬の開発が停滞する一方で、微生物は耐性を広範に進化させてきた。結果として、今や世界はポスト抗生物質時代に入ろうとしている。新たに薬剤耐性を持って出現した微生物株の中でも、とりわけ厄介者の一例が、あらゆる合成抗マラリア薬に耐性を持つマラリア原虫であり、ペニシリンとメチシリンの両方に耐性を持つ黄色ブドウ球菌(MRSA」)であり、結核の第一選択薬に耐性を持つ菌株(MDR-TB= 多剤耐性結核菌)や第二選択薬にも耐性を持つ菌株(XDR-TB=超多剤耐性結核菌)である。抗微生物薬体制は世界的な危機を生み出しかねず、多くの科学者は、今後現行のどの療法でも効かないHIVや結核菌や、黄色ブドウ球菌やマラリア原虫の変種が出てくると予想している。抗微生物薬耐性の発現は、ある意味では、ダーウィン的進化の単純な帰結である。感染できることがわかっているウィルスは何万種とあり、細菌だと30万株に上る。そしてその多くは、人間の1世代の間に何十億回と複製し、進化していく。このような状況下では、進化圧は長期的にどうしても人間に不利に働く。しかも、人間が過剰な行動をとることで、この過程は劇的に早まる。農家は作物に殺虫剤を、過剰に抗生物質を噴射する.。また、畜産農家では鶏や豚や牛の病気を予防し、成長を促進し、生産性を上げるために、資料に治療用以下の要領で抗生物質を添加する。実際、抗微生物薬の世界生産高の全トン数の半分を当て農業で使われているのだ。 ・SARSは中国で発生したが、隠蔽とごまかしの方針を貫いた。 p.320 全世界での衛星防衛はSARSの脅威をしのいだが、これを機に、深刻な疑念も浮上した。2002年11月から2003年3月までの中国の隠蔽方針は、世界の健康を危険に晒したと同時に、対応ネットワークに一つでも穴があれば国際緊急対応システムが土台から崩れかねないことを明らかにしたのである。11月広東省でSARSが発生し、次いで北京に広がってからの4ヶ月間、中国当局は隠蔽とごまかしの方針を貫いた。だが、中国と香港、台湾とのー貿易、投資、家族の絆、観光を通じてのー密接なつながりからして、新しい病気の存在を外の世界に知られないようにしておくのも不可能だった。特にインターネットとソーシャルメディアの時代、しかもちょうど2月の旧正月で、中国の国内旅行のピークの時期だったとなれば、完全な報道管制を敷くのも難しかった。とは言え一党支配国家の中国には、自国民に対しても外界に対しても、支配と統御のイメージを元として打ち直さなければならない事情があった。さらに共産党は、情報が行き届きすぎると自国の現実(生活水準の低さ、医療制度の不備、公共衛生上の緊急事態に対する備えの欠如)が露呈してしまうことを恐れてもいた。こうした理由から、温家宝首相率いる政権は2003年3月まで、正確でタイムリーな情報を求める国際的な圧力に抵抗し続けた。そして危機の規模を最小限に評価して、公開する数字を操作し、望ましくない知らせは報道させず、WHOのチームが国内の感染地域に立ち入ることも拒否した。しかし3月にWHOが内部告発者の役割を引き受けて、もっと持っていた断片的な情報を公表すると、ようやく中国は方針を転換した。4月17日、政治局は一転して、SARSの症例を速やかに報告することを約束し、WHOに広東省と北京への立ち入りを許可し、呉儀副大統領の指揮のもとにSARS対策本部を設置した。同時に党の機関紙の人民日報は中国の備えが不十分だったことを認め、中国CDCの所長も謝罪した。 p.368 エボラが流行できた最後の要因は、医療を取り巻く環境がグローバル化している時代にも、未だ国境に期待する幻想が浸透していたことだった。「遠く離れた」マノ川流域で疫病が噴出した時も、先進国はのんびりと、アフリカでの病気のせいで人道的に心配される程度の問題で、全世界の人間の命が直接的にさらされるなどと言う悲観的な見通しを持たせるものではないと思い込んでいた。しかし疫病は、人間が人間として生きている限り避けられないものであり、しかも現代においては、膨大な人口、活気ある都市、そして都市間を迅速に結ぶ輸送手段といった条件が、ある国に起こった感染症のあらゆる国への伝播をいつでも現実にできるのである。 西アフリカの公衆衛生の大失敗の原因は、健康な洗える政策決定を人類全体の持続可能な幸福の観点から下さずに、個々の国家の持続不可能な利益の観点から下してしまったことにある。これから人類が疫病と言う脅威から生き残るには、国際主義者の視点を持って、誰もが避けがたく相互に結びついているんだと認識することが必要だ。 p.371 疫病は、環境劣化、人口過剰、貧困などによって生じた系列に沿って広まっていく。したがって、もしも壊滅的な疫病を発生させたくないないのなら、公衆衛生が犠牲にされる可能性を十分に考慮した経済的判断下すことが必須になるし、同時にその判断を下した当人に、充分予期しうる健康への影響についての責任をきっちりとってもらわなくてはならないだろう。古代ローマのキケロによる格言に、「民の安寧が至高の法であらねばならない」と言うのがあるが、この「民の安寧」は「公衆衛生」とも読み替えられる。古いながらも、 今もって妥当な教えである。そして当然ながら、この「至高の法」は、市場の方より上に置かれなくてはならないのである。 p.399 高齢者のいないイタリアはどうなるのだろう。知恵の保持者であり、第二次世界大戦の生き残りであり、語り部であり、父母であり祖父母である世代がいなくなったら、この国はどうなるのであろう。私たちの先達が一人一人なくなっていく。…数が多すぎて埋葬しきれない棺が、ミラノの記念墓地に、あちこちの教会に、軍の車両に、道端に並んでいる。…そこには私たちの先達が立ち横たわり、灰に帰されるのを待っている。火葬場の日は止まることなく、1日24時間、煙を吐いている。パチパチと音を立てながら、 骨を、レース襟を、口髭を、記憶を、焼き尽くしていく。棺の中で、私の出身者出身地の件だが、消毒液のたっぷり染み込んだ米そうなのまとっている。この人たちがいなくなったら、私たちはどうなるのだろう。 p.404 第二の不安は、COVID-19の長期的な後遺症に十分な注意が払われているのだろうかと言うことである。この後遺症には、身体的なものも精神的なものもあると考えられるはず。まず身体的には、実際に、一部の患者が回復後も長期にわたって経過観察と治療を必要としていることが明らかになっている。特に重症者の場合は、疲労感や、肺、心臓、腎臓、血管、脳といった主要機関への思い損傷が症状としてしつこく残ることがわかっている。そして身体に害を及ぼす疾病の後には、概して第二の疾病が続く。長期の不安、失業、社会的孤立、亡くなった友人や家族を持っての悲嘆等によって 引き起こされる、精神的な不調がそれである。身体的な病が見えてからも、感情面や心理面での深刻な打撃はなかなか癒されないものなのである。 p.405 第二章以降は、慎重に選んだ感染症のそれぞれを上ごとに詳しく検討していく。まずその病気の疫学(病因、発病の機序、感染経路、症状、治療法など)が紹介され、その後に考察する社会への影響がなぜ生じたのかが深く理解できるようになっている。一口に社会への影響といっても、その範囲は政治、市民生活、宗教、文化と、多方面にわたる。例えば中世ヨーロッパを恐怖に陥れたペストは、検疫や隔離といった現在も有効な基本的対策の数々が考案されたきっかけになったほか、人々の死生観にも多大な影響及ぼし、ぺストを主題にした文学作品や絵画を数多く残した。また、黄熱、赤痢、発疹チフスはフランス皇帝ナポレオンの領土拡張の夢を打ち砕いて歴史を大きく変え、これらの流行は公衆衛生の発達を促した。そして20世紀半ばからは、世界的な保健機関が設立されて感染症撲滅するための大々的な取り組みが進められるようになった。それと並行して、本書の何章かは感染症に関する医療・医学の歴史と、病気とは何かと言う概念の変遷を主題にしている。最初の「科学的な医学」である古代ギリシャのヒポクラテスによる体液理論から話を進め、顕微鏡や実験技術の革新を経て、目に見えない病原体の正体が科学者の不断の努力により解明されていく過程を追う。世界はいままさに新型コロナウィルス感染症の惨禍に巻き込まれている。「今や世界は感染症を地球上から一掃する手段を持っている」と宣言された20世紀の不遜の時代を通り過ぎて、人間は過去の間経験から何を学んだのだろうか。この新しいウィルスに世界で2億人を超える人が感染してしまったのはなぜだろう?社会の健忘症が第一の原因だと著者は嘆く。「微生物が闘いを仕掛けてくるたびに、 その後しばらくは、国内的にも国際的にも洗えるレベルで狂ったように活発的な動きが起こる。しかしやがては、すべては忘却されて終わりとなる」。つまり、喉元を熱さが過ぎた後の忘れっぽさだ。わが国では昨年2月に、乗客に感染者がいたことが発覚したダイヤモンドプリンセス号が横浜港沖で検疫を受けると言う騒ぎがあり、そこからコロナ禍が始まった。感染者数の増減や緊急事態宣言のことばかりが取りざたされるように思う見える昨今、あらゆる初動に反省すべき点があった事はもう忘れられているのではないか。そして狂騒の最中に、誰かに罪を擦り付けたいと言う人間の本性が今度のもまたあらわになり、マスクをするしないで暴力が振るわれたり、感染者が中傷されたりする。現在の疫病はまさに「本番前リハーサル」だと言える。このパンデミックを乗り越え、次に備えるにあたっては、今一度、歴史の教訓を学ぶ必要があるだろう。そしてその教訓には、医学的な面(発病の機序等)と社会学的な面(発病の環境要因、患者への差別偏見、生贄探しなど)がある。前者については明らかに時代を経るごとに進歩しているが、後者については人間の本性が邪魔をしてなかなか変わる気配がない。それこそが未来に向けての教訓なのかもしれない。物理学者で文筆家の寺田寅彦は、「ものを怖がらなすぎたり、怖がりすぎたりするのは優しいが、正当に怖がる事はなかなか難しい」と述べた。それでも禍に対して冷静に向き合おうと努めることができるのではないだろうか。 【各疾病が取り上げられた作品】 ・エイズ in Africa:『黒死病ーアフリカにおけるエイズ』 ※レイプに関して:『レイプー南アフリカの悪夢』(書籍)、ケープ・オブ・レイプ』(映画) ・エイズ in US『そしてエイズは蔓延した』『神の復讐のあとでーエイズ、性、アメリカの宗教』 ・『感染症と不平等ー現代の疫病』 ・映画『アウトブレイク』、『エピデミックー伝染病』、『コンテイジョン』 ・本『ホットゾーン』『カミング・プレイグー迫りくる病原体の恐怖』『エボラー殺人ウイルスが初めて人類を襲った日』
0投稿日: 2022.06.19
