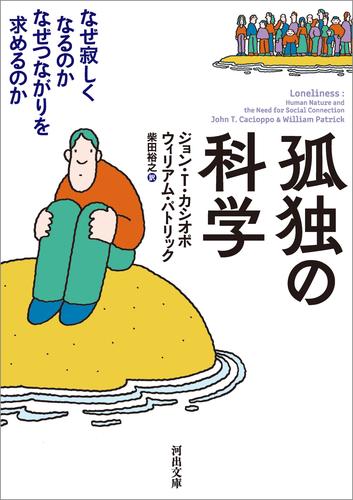
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
孤独感のみならず、脳科学本としても立派な1冊である。いや、というより、孤独感を語る上で脳科学や生理現象への言及は避けては通れないのであろう。 人間の脳は、3つの層に分けられる。 1つ目の層は、最初に爬虫類に現れたことから"爬虫類脳(脳幹)"と呼ばれる。これは心拍、呼吸、消化など、生物の生存に欠かせない機能を司っており、人間の脳幹でさえ爬虫類にとって重要と思われるメッセージしか扱わない。 その外側にある層は、人間が誕生するより遥か昔に進化した"旧哺乳類脳(大脳辺縁系)"である。これは情動を司り、行動の柔軟性や文脈に基づく制御の能力を増すことで個体の適応性を高めた。 更にその外側にある層は、"新哺乳類脳(皮質)"であり、これにより数や言語を操作できるようになった。人間の脳は、①爬虫類にまで遡る動物的な脳幹、②情動を司る辺縁系、③理性的な皮質の三位一体であり、これによって、実際に思っていることと取る行動とが異なったり(ツンデレ)、欲求と制御の葛藤が生じたりする(食べたいけど、太るから我慢する)のである。 孤独感の経験は、空腹感の経験の同じ次元の現象であり、孤独感が進化したからこそ人類はここまで生きながらえてきたのである。 サバンナの時代には、1人でいることは一寸先の生死を分かつ問題であり、神経系も闘争的反応を示すことが個体の生存確率を高めた。しかし問題は、その神経系の闘争的反応が、現代の慢性的なストレス(孤立)に対して同様になされているということだ。これが孤立を不健康・不適応との関連を説明する要因の1つである。 宗教などの信念体系は、少なくともそれを信じる人たちにおいては明確な生理的効果を与えることも否定できない。 類人猿の精巣の大きさは競争相手のオス(つまりライバル)の数に比例する。ラットは、人間の嗅覚の閾値よりも低い濃度で空中を漂うフェロモンにより生殖周期が一致していく(人間においても、寮で一緒に暮らす仲間たちの月経周期がどんどん一致していくという研究結果がある)。同調した生殖周期における適切な時期に生まれたラットの生存率は80〜90%であり、外れたラットの生存率は30%であった。 これらのことから、社会的な面(つながり)と生理的な面(生理現象や身体的反応)は、長方形の縦と横のように、切っても切り離せない関係にあると言える。孤独感がもたらす痛みや、他者とのつながりから得られる高揚感は、ともに極めて生理的なものである。
1投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ孤独は身体的な痛みと同様の生物学的シグナルである 資料では、孤独感は身体的な痛みと同様に、危険を回避するために進化した生物学的なシグナルであると論じられています。「人間は身体的な痛みを感じるおかげで身体的な危険を避けることができる。社会的な痛み、すなわち孤独感も同じような理由で進化した。この痛みを感じるおかげで、孤独なままになる危険が避けられたのだ。」と述べられています。 fMRIを用いた研究では、社会的拒絶(孤立)を経験した際に活性化する脳の領域(脊側前帯状皮質)が、身体的な痛みに対する情動反応のシグナルも受け取っていることが示されています。「機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使うと、私たちが拒絶を経験したときに活性化する脳の情動領域(脊側前帯状皮質)は、じつは身体的な痛みに対する情動反応のシグナルも受け取っているのだ」という事実は、孤独が身体的な痛みとハードウェアを共有していることを示唆しています。 人間は社会的な生物であり、つながりを求めるのは進化に根ざした本能である 資料は、人間が極度に協力的なホモ・サピエンスとして社会の中で生き残ってきたことを強調しています。「人間であるということ/極度に協力的なホモ・サピエンス/社会の中で生き残る」という章立ては、この基本的な性質を示しています。 群れから孤立すること、特に幼い頃に引き離されることは、途方もない危険を孕んでいたため、どの動物も孤立を避け、仲間との近接を維持する本能的傾向を持っていることが言及されています。「群れから孤立すること、とりわけ、幼いころに、親から引き離されることは、途方もない危険を孕んでいる。したがって、どの動物も孤立を避け、仲間との近接を維持する本能的傾向を抱くようになったとしても、驚くことがあろうか」というポール・ビュールの言葉が引用されています。 社会的なつながりを求める衝動は深く根ざしており、孤立感は本能的な恐怖として体に感じられると述べられています。「社会的なつながりを求める私たちの衝動はとても根が深いので、孤立感を抱いていると明晰な判断がしだいにできなくなるとともに、知性を含むおもなたかの神経経路が混乱し、これまで何万年ももの長きにわたって人類の大脳皮質の拡大と、その学者が見る見取りは、強化したのちのは、しだいに複雑化しすぎ、また、孤独感は社会的なつながりを取り戻すきっかけとなり、社会的なシグナルに対する私たちのレセプターの感度を上げる。 孤独は認知や行動に影響を与え、負のフィードバックループを生み出す可能性がある 孤独感は注意力を奪い、自己制御を困難にする可能性があります。「孤独感は注意力を奪う」という章立てはその影響を示しています。 孤独な人は、社会的な手がかりに対してことさらに注意が向く傾向があることが実験で示されています。「人は孤独を感じると、社会的な手がかりにことさら注意が向く。」これは、飢餓のとき、食べ物に関する手がかりに注意が向くのと同じだとしています。 孤独感は、社会的な認知を歪め、ネガティブな解釈を強化し、社会的な孤立を深める可能性があります。資料では、孤立感によって本来の社会的な機能が発揮しづらくなる場合があることが指摘されています。「問題が生じるのは、孤独感のせいで本来の社会的な機能を発揮しづらくなった場合なのだ。」 また、孤独な人は、交流の後にネガティブな印象を持つ傾向があり、特にビデオ録画を見た後に顕著であることが実験で示されています。「孤独な人は、孤独ではない人に比べて、紹介された情報の多くを記憶した。…孤立感が活性化すると、なかなかそれを拭い去れない理由が見えてくる。心を閉ざす、減退する、バージョンをそっくり改める、理想の伴侶に出会う、といったことだけではだめなのだ。」これは、孤独感が定着しやすい性質を持っていることを示唆しています。 社会的なつながりは健康、富、幸福と関連が深い 資料は、社会的なつながりが健康、富、幸福の基本的な原理であることを示唆しています。「健康、富、幸福」という言葉が繰り返し登場し、これらの要素と社会的なつながりの関連性が強調されています。 「孤独と健康 ー 五つの因果の経路」の章では、孤独が心臓血管系に負担を与え、高血圧や心臓発作のリスクを高める可能性が論じられています。「ストレスが続けば、体中の磨耗がひどくなるだけだ。」という言葉は、孤独による慢性的なストレスが身体に与える悪影響を示唆しています。 ホワイトホール研究の例が挙げられ、社会的な階層が健康状態と死亡率に影響を与えていることが示されています。「どの職階の役人も、一段上の職階の人より健康状態が悪くて死亡率が高かった」という事実は、社会的なつながりや階層が健康に与える影響の重要性を示唆しています。 幸福な結婚生活を送っている人は、感情的知能が高い傾向があり、社会的なつながりが幸福と関連していることが示されています。「幸せな結婚生活を送っている人は、たいてい幸せな結婚生活を送っており、情動的知能が高いが、彼らは必ずしもリーダーやスターではない。」という記述は、人間関係の質が幸福に影響することを示唆しています。 社会的なつながりを築く・改善するための戦略 社会的なつながりを築くためには、小さな一歩を踏み出すことが重要であると提言されています。「自転車に乗る/因果関係/フィードバックする/孤独の治療法?/物事の受け止め方を改める/変化を強める/社会的なつながりに向けて、『EASE』(ゆっくり事を進めること)」という章立ては、具体的な戦略を示唆しています。 慈善活動など、ある程度安全な環境で社会的な交流を行うことが、ポジティブな反応を引き出す確率を高めるのに役立つ可能性が示唆されています。「実験範囲を慈善活動という、いくぶんかなりと安全な範囲にとどめたほうがいいかもしれない。」というアドバイスが提示されています。 相手の欲求と気分を配慮し、丁寧な態度で接することが、人間関係を築く上で重要であると強調されています。「相手を尊重する態度が相まって、彼を動かし、自分の人生を垣間見させる気にさせた。」というエピソードは、このような態度が人々の心を動かす力を持つことを示しています。 自己のネガティブな社会的な認知パターンを修正し、現実を正しく認識しようと努力することが重要ですが、これは孤独が強い場合には困難になる可能性があることが示されています。「物事の考え方は自らどうにでもできるものであり、だからこそ私たちは、社会的な認知を武器にして社会的な経験の主導権を回復することができる。」しかし、「実験結果は、孤立感が活性化すると、なかなかそれを拭い去れない理由が見えてくる。」という記述は、その難しさを示唆しています。 技術と社会的なつながりの未来 オンラインコミュニティやメタバースといった技術が、社会的なつながりの新たな形を提供していることが紹介されています。「セカンドライフ」「ゼアー」「アクティブワールド」といったオンラインコミュニティが例として挙げられています。 これらの仮想空間では、ユーザーがアバターを介して交流し、現実世界と同様の様々な活動を行うことができますが、これらは厳密にはゲームではないと説明されています。「これらの『メタバース』、すなわち、コンピューターの創造したメタユニバースは、厳密にはゲームではない。」 一部の科学技術崇拝者は、コンピューターを介した社会的な出会いが現実世界のコミュニティーの衰退によって残された隙間を埋めるだろうと考えていることが示されています。「多くの科学技術崇拝者は、コンピューターを介する社会的な出会いが現実世界でのコミュニティーの衰退によって残された隙間を埋めるだろう、と言う。」という記述は、技術が人間関係を代替しうるという見方を示しています。 しかし、資料では、オンライン上の交流だけでは現実世界での深い社会的なつながりの代わりにはならない可能性が示唆されています。「現実世界の人間関係の深いつながりが、電子的手段による『弱いつながり』に代替されつつあるという洞察が、その背景にある。」という記述は、技術が提供するつながりの限界を示唆しています。
1投稿日: 2025.05.13
