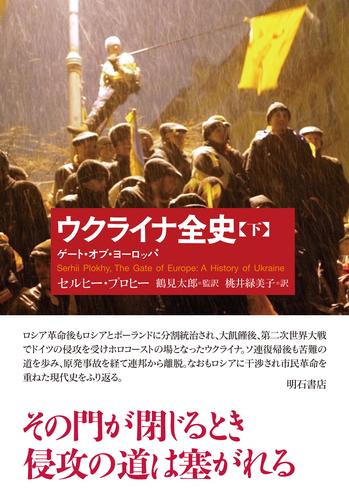
総合評価
(4件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログその門が閉じるとき侵攻の道は塞がれる。ロシア革命後もロシアとポーランドに分割統治され、大飢饉後、第二次世界大戦でドイツの侵攻を受けホロコーストの場となったウクライナ。ソ連復帰後も苦難の道を歩み、原発事故を経て連邦から離脱。なおもロシアに干渉され市民革命を重ねた現代史をふり返る。(e-hon)
0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年7⽉12⽇のウラジーミル・プーチン「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」(⼭形浩⽣ 訳/以下「プーチン論文」という。)に抗して読んだ。/ (1)《ロシア⼈とウクライナ⼈は⼀つの⺠なのだと述べた》(プーチン論文)/ プーチン論文では、ホロドモールについて、次のようにふれている。/ 《1930年代初期の集産化と飢餓という共通の悲劇はウクライナ人の虐殺として描かれる。4》/ 《4 訳注:いわゆるホロドモールのこと。⼤規模不作による飢饉で⾷料徴発と「富農」弾圧が⾏われたときにはウクライナが特に標的とされ、農業の基盤そのものが破壊された。飢餓の推定死者数も圧倒的にウクライナ⼈の⽐率が多い (諸説あるがおおむねウクライナ 500 万⼈、その他 200 万⼈)。》/ それに対して、この部分に関する本書の記述を見てみよう。/ 【一九三二年十二月、スターリンはカガノヴィチと首相の(略)モロトフをウクライナに行かせ、非現実的な穀物徴発割当の達成を強行させた。ウクライナの党幹部はモスクワの全権委員に指導され、(略)飢えに苦しみながら多くが死にかけている農民からむしり取れるだけむしり取った。当局は割当を達成できなかった村に対して、マッチや灯油などの生活必需物資の供給を絶ち、穀物のほか家畜や食糧になりうるあらゆるものを没収して罰した。 ─中略─ ウクライナでは一九三二年から一九三四年のこの飢饉で四〇〇万人以上が餓死した。 ─中略─ ウクライナの大飢饉(ウクライナ語で「ホロドモール」と呼ばれる)は、ウクライナとその国民に対する計画的なジェノサイドだったのだろうか。二〇〇六年十一月にウクライナ議会はそうであると認定した。世界中の多くの議会と政府が同様に決議したが、ロシア政府はウクライナの主張を切りくずすための国際キャンペーンを開始した。 ─中略─ それでも一九三二年から一九三三年の大飢饉の重要な事実と解釈の一部については、広く合意されつつある。公的政策が引き起こした人為的な現象だったことで学者の意見はほぼ一致しているのである。】/ このように、ホロドモールの歴史が存在し、それに対してソ連の後継国家であるロシアが、正当な位置付けも、何らの謝罪も賠償も行なっていないという事実そのものが、(1)のプーチン論文の論旨の欺瞞性を明らかにしている。/ (2)《ロシアはこれまでも、そして今後も、決して「反ウクライナ」にはならな い。》(プーチン論文)/ 以下の二つの点から、プーチンの論旨が単なるプロパガンダ以上のものを出ないことは明らかである。/ ◯2014年:ロシア、クリミア半島を併合、ドンバスに軍隊を送り、戦争を開始。2024年:ロシア、ウクライナに侵攻。/ ◯ ロシアのウクライナ侵攻における戦争犯罪: 〔2022年にロシアによるウクライナ侵攻が始まって以来、ロシア連邦軍と当局による民間人を対象とした多くの意図的な攻撃、民間人の虐殺(大量虐殺)、ウクライナ人女性と子供に対する拷問と強姦、生身及び遺体の切断、ウクライナ人捕虜の殺害、人口密集地での無差別攻撃が行われた。 ─中略─ 2023年3月、国際刑事裁判所(ICC)は、ウクライナ侵攻中の子供の誘拐という戦争犯罪への関与の疑いで、(略)ウラジーミル・プーチンとロシア連邦児童権利委員会委員(略)であるマリア・リヴォワ=ベロワに対して逮捕状を発行した。〕 (Wikipediaより。)/ 以下に、主なもののみを掲げる。 ・禁止兵器の使用: ウクライナ政府によると、侵攻開始から2023年12月までに化学兵器を465回使用。/ ・拉致と国外移送: ウクライナ当局によると、ロシア軍は侵攻開始から現在までの間に12万1000人以上のウクライナ人の子供を誘拐し、ロシア東部の州に強制移送させた。 ウクライナの人権団体は、約8万4,000人の子供を含む40万2,000人以上のウクライナ人がロシアに強制移送されたと発表した。その後、被移送者数は70万人以上とされた。/ ・民間人への攻撃(ブチャなどにおける虐殺。) ・民間人への拷問 ・性暴力 ・捕虜の虐待 ・強制徴兵 ・ジェノサイド: ウクライナ、カナダ、ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、チェコ共和国、アイルランドの議会は、この侵略はジェノサイドであると宣言した。/ もちろん、今後もプーチン・ロシアやそれに加担する者たちによって、彼らの「大ロシアと小ロシアの物語」は生産され続けるだろう。 だからこそ、僕はもっとウクライナの歴史と物語が読みたい! 「ブラッド・ランド」の血泥の中から花ひらいた美しき蓮の花、ウクライナよ、永遠なれ!
2投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ民族主義的ロマンに頼らないウクライナ証明の試みの書。感動するなって方が無理。人物で言うならペトリューラ、バンデラ、フルシチョフの評価が現代の、この本ならではのものに感じた。それだけに監訳者も書いている通りホロコーストについての記述はずるいと思った。 上巻にはなかった参考文献、索引、年表、人名録がついていた。地図はないが、地域毎に切り分けた語りをしない為に敢えて入れてないのかも?そんなわけで、ウクライナを知るための1冊目としては向かないので注意。
0投稿日: 2024.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「全史」と銘打った、ウクライナの歴史に纏わる本で、「上巻」の続きとなる「下巻」である。 「ウクライナの歴史」を古い時代から説き起こし、この上巻では20世紀初め頃に至る迄が綴られた「上巻」に対し、この「下巻」はそれ以降なので、扱われている期間は短い。しかしながら、本のボリュームは上下共に似たような分量になっている。 「下巻」については、20世紀初め頃の革命や内戦という様相から、戦間期や第2次大戦の頃、その後の様々なこと、更に「ウクライナ」の独立、最近の情勢と、非常に密度が濃い感じに纏まっている。概ね2020年頃迄の事柄が綴られる。 「下巻」の末尾には、「上巻」の部分も含めて、ウクライナの歴史に纏わる人名録、主な出来事の年表、加えて参考文献リストが添えられてはいる。が、そういうモノを頻繁に参照するような煩わしい読み方は無用だ。物語風で読み易くなっているとも思う。ウクライナで学位を得て研究教育活動に従事し、現在は米国で活動している「ウクライナ史」研究者が、「ウクライナについていろいろなことを広く知らせたい」という強い思いも込めて綴ったのだと想像する。 20世紀に入って以降も、「ウクライナ」は幾つかの国々に分かれていて、第2次大戦やその後の経過で概ね現在の版図で「ソ連の中の共和国」となり、1950年代に経済上の理由でクリミアがロシア連邦からウクライナに移管ということで現在の版図が確定している。そして1991年にその版図で「独立国」となって行くのだ。 「ソ連の歴史」というような観点、または「欧州に於ける第2次大戦期の経過」というようなことで、ウクライナの事柄には少しは触れているが、本書のように詳しく説かれている、同時に読み易いモノは類例を知らない。読み応えが在る。 そして「ウクライナの社会」の変遷というようなことも、広く深く語られていると思う。ソ連体制になってから第2次大戦へ向かって行く間の「人為的な飢饉」と呼ばれるような件も含めて経済への言及も幅広い。 ソ連時代の様々な経過の後の、「独立」への経過も詳しい。多様な要素を内包する欧州の国であろうとした訳だ。 やがて初代大統領が去らざるを得なくなった後の、政権の変遷や出来事に関しても詳しく、同時に判り易く纏まっている。 総じて「下巻」は「ウクライナ現代史」という感で、場合によってはこの「下巻」を読むと現在に至る様々な事柄を網羅することも出来なくはない。と言っても、もと古い時期の諸事項との関連も在るので、「上巻」に在るようなことも知るべきではあるが。 そして本書が綴られている時点で「第1次ロシア・ウクライナ戦争」と呼ぶべき状況に入ってしまっているが、「ロシア側で唱えている事柄」に関連した「ウクライナ側の観方」というようなことが或る程度整理されている感だ。 複雑な生い立ちを負い、文化的なモザイクという情況でスタートした「ウクライナ」ということが、本書を読むとよく判る。現在となっては、個々人の文化的出自や母語が如何であれ、「とりあえず“ウクライナ国民”」という、多数派と見受けられるウクライナに住む人達のアイデンティティは動き難いのだと思う。そこに「歴史」として考えて「如何?」ということ迄持ち出して、軍事行動に迄及んでしまう理屈というのは何なのか?そういう「考える材料」を多く提供してくれる本書である。 本書が登場した後、彼の地では「第2次ロシア・ウクライナ戦争」と呼ぶべき状況に突入してしまい、既に3年目というようになってしまい、事態の収束が読めないようになっている。何を如何言おうと、大規模な軍事行動というような動きは、生命を擦り減らし、社会の中の余りにも多くのモノを損なうばかりである。何とかならないものかと祈るばかりではあるが、それはそれとして「如何いう経過で最近の様子なのか、古い時代に遡って知ってみよう」という程度のことは出来る筈だ。そして本書はそういう「知ってみよう」に好適だと思う。 偶々眼に留めて入手し、紐解き始めた本書であるが出会えて善かった。モノも知らずに声が大きそうな方に与して、何やら大きな声を出してみれば好い訳でもないと思う。静観して、本を読んで学ぶというようなことも必要なのだと思う。ロシアとウクライナとの問題に関し、ウクライナの側に纏わる様々な情報が詰まった本書は必読かもしれない。殊に「ウクライナ現代史」という様相の「下巻」は価値が高いと観る。御薦めだ。
4投稿日: 2024.08.14
