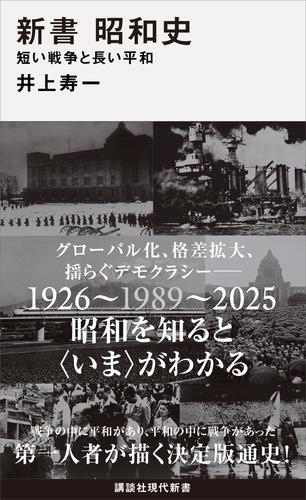
総合評価
(7件)| 2 | ||
| 0 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和を学ぶ上では他の本が適当かもしれない。 基礎的な部分を補うものが必要。 何を伝えたいのかがいまいちわからなかった。 テーマがぶれている気がする。
0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年は昭和100年だそうで、昭和史が本屋の棚を賑わしている。 やはり二次大戦前の事はあまり知らないので、もう少し掘り下げてほしかった。戦後のことは「ああ、あれにはそういう意味があったのか」という記載もあり、面白かったけれど、やっぱり全体を新書一冊にまとめるのは無理があるなあ。
0投稿日: 2025.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和100年となる2025年を区切りとして、過去100年を振り返る。正直なところ敗戦までの20年は今さらながらという気がして、あまり興味が持てず、読み流してしまった。一方、戦後80年の歴史は、私が、そして日本人が意識している以上に戦争の過去を引きずり続けていることを痛感し、納得する思いがした。52年の講和・独立、60年安保も、64年五輪も、70年万博、72年の日中国交回復も。昭和天皇の退位問題については、52年の講和条約の時点で「おことば」を語り、退位する可能性があったが、その見送りになったとの背景は全く知らなかった! 60年安保に際して同志社大学2年だった保阪正康は「社会主義革命を目指していた」と語っているということも初耳で、興味深かった。
0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和元年〜令和7年までの100年間の歴史が、ノンフィクションの群像劇として、一冊の新書にまとめられている。「日本国民必読の書」と言っても、言い過ぎではないだろう。面白かった。
1投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> 第1章 平和のなかの戦争の予兆 1926~1929 第2章 非常時小康 1930~1936 第3章 戦争をめぐる理想と現実 1937~1940 第4章 戦争と平和の間 1941~1944 第5章 国際冷戦と国内冷戦 1945~1952 第6章 高度経済成長下の戦争 1953~1970 第7章 ヴァーチャルな戦争 1971~1989 第8章 終らない戦争 1990~2025 <内容> 著者の歴史叙述は、事実だけを述べるのではなく、あとがきで言うところの「群像劇」である。小説や雑誌記事や伝記での発言などを積み重ねて歴史を見ていく手法だ。そこから単なる事実からは見えてこない背景や大衆が見えてくる。現代史を語っているからこそかも知れないが、この本からいくつか知った事があった。
1投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ啓光図書室の貸出状況が確認できます 図書館OPACへ⇒https://opac.lib.setsunan.ac.jp/iwjs0021op2/BB50393457 他校地の本の取り寄せも可能です
0投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「昭和史」というような題名の本は、何やら難しそうと手に取らないという人も少なくないかもしれない。が、本書はそういうように敬遠する必然性は全く無い。普通の小説やエッセイのような感覚でドンドン読み進められる。そうした意味で素晴らしい一冊だ。 2025年が「昭和100年」で「戦後80年」ということを踏まえて、「この100年?」というようなことを想い、考える材料を提供しようというのが本書だ。 「昭和」と一口に言っても、「昭和XX年」と明確に言い得る期間だけでも1920年代から1980年代までの60年間余りに及び、色々な要素が在る。加えて、「昭和XX年」の出来事や、「昭和」の或る時期の動きが極々最近迄の様々な事柄に繋がっているというのも多い。本書はそういう問題意識で、1926年頃から2025年に至る迄の「昭和100年」を通史的に論じようとしている。 本書では「グローバリゼーション」、「格差」、「デモクラシー」、「戦争と平和」というような4つの柱を想定し、過去100年の各時期に関して、こうした柱に関連する話題を、様々な人達が遺した証言等を一定の基礎に据えながら論じている。 世界の国々との関係が築かれ、それが進展する「グローバリゼーション」というのは昭和期以降に拡大する。世界の国々や地域間での、また国内の社会の中での「格差」というようなことも、昭和期以降には様々な変化が在る。選挙とその結果というような「デモクラシー」ということに関して、昭和期以降には様々な話題が在り得る。そして実際に軍事行動に携わる、携わらないの区別と無関係に「戦争と平和」というような課題は在り得る。 こうした4つの柱という問題意識の下、種々の“証言”を拾い集めながら論じると、「100年間に国、社会、人々が辿った経過」というようなことを通史的に網羅出来ようというものである。 本書で引かれた種々の“証言”、更に本書そのものを材料とし、過去の世界に踏み入ることを試みて、自分自身の人生等に照らしながら考え、自分自身の言葉でその考えを整理してみるというようなことが「知って学んでみる歴史」ということに他ならないのであろう。本書の冒頭部に挙っている「目指すこと」に通じる話しだが、本書はその「目指すこと」を実現出来ていると観る。 極々個人的な内容にもなる。自身の場合、興味を持って歴史関係の本を読む、テレビニュースや新聞や雑誌で社会の動きに纏わることを知ろうとするということをするようになったのは、恐らく1979年や1980年頃、小学校の高学年であった頃以降であると思う。とすると、本書に在る1979年頃から2025年に至る迄の色々な事項は「自身の人生の記憶に重なる」ということにもなる。 こういうのは読者各々によって些かの差異は在ろうが、多くの読者が共有し得る感覚のように思う。本書は「昭和史」と称して最近100年間程度の通史を打ち出しているが、結局は「あなたの人生の背景」を問うようなことになっているのかもしれない。 本書は、非常に読み易いと同時に、非常に読み応えが在ると思う。2025年が「昭和100年」で「戦後80年」ということことで、歴史への問題意識が少し高まっているかもしれない中、広く御薦め出来る一冊だ。
6投稿日: 2025.05.16
