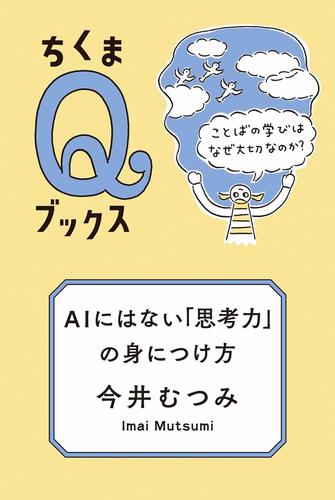
総合評価
(35件)| 8 | ||
| 16 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ・相互排他の推論 「Aではないから、Bだ」と考える。→アブダクション推論 ・アナロジーの推論 「関係の同じ」を見つけ出す。→アブダクション推論 ・帰納推論 数ある事例を参考にして考える。 ◆思考をコントロールする能力実行機能 もうひとつ、「考える力」に含まれる大事な能力に、「思考をコントロールする力」があります。これは「実行機能」と呼ばれるものです。「思考のコントロール」には次のようなステップが必要です。 1 | 必要な情報に注意を向け、情報を取り入れる。 2 | 複数の情報を一時的な記憶の貯蔵庫にためておき、取り出せるようにする。 3 | 不必要な情報に注意が向かないようにする。 詰め込んだ知識も、取り出さなければ意味がない 「考える力」というのは、「知識を使って、推論し、問題を解決する力」であるといえます。問題の解決には、推論が必要です。推論をするためには、脳に記憶されている必要な知識に素早くアクセスして取り出す「情報処理能力」と、必要な知識や情報に注目し、不必要な情報へ注目しないように思考をコントロールする「実行機能」が欠かせません。この2つの力に支えられてはじめて、推論が可能になり問題解決ができるのです。 …大事なのは、抽象的な意味のことばを「死んだ知識」としてたくさん持つことではありません。今持っている知識と結びつけることができることばをたくさん持ち、「生きた知識」にすることです。 AIの特徴は、「意味を理解しないこと」。そしてこのような「直観を持たないこと」です。そしてそれはそのまま、人間の考える力との違いになります。 人間は学びの過程で、考え、間違え、それを自ら修正することで、技を身につけると同時に、直観を磨きます。 人間は学びの過程で、考え、間違え、それを自ら修正することで、技を身につけると同時に、直観を磨きます。この直観こそが、この先みなさんが学ぶうえで非常に大切なものです。 もし無自覚なまま、考えることを放棄して生成AIを活用すれば、みなさんの知性に大きなダメージを及ぼしかねません。なぜなら私たちの学びにとって必要不可欠な「意味」 を見つけ、「直観」を育む機会がその分だけ減ってしまうからです。うどんの達人が、うどんをこねる機械を使いだしたら、自ら微調整をしながらうどんをこねることはできなくなってしまうでしょう。 小さいころから生成AIに頼り、生成AIに「答えを教えてもらう」ことに慣れてしまうと、本来人間が持っていた「意味の理解」が失われ、「直観」を働かせて新しい知識を創造していくことができなくなる。私はそのことを懸念しています。 赤ちゃんはことばを学ぶとき、未知の音を外界の対象に結びつけて意味を探し、身体に落とし込みます。そこから推論をして、自分の力で知識の体系をつくり上げていきます。 その過程で、たくさんの間違いを繰り返しながら、ことばの枠や知識を修正していきます。 このような試行錯誤を繰り返すことで、ことばや知識が、いつどのように使えるのかが感覚的にわかってくるのです。そしてそれは「生きた知識」となります。このことは1、2 章でくわしく述べてきた通りです。 一方AIは、「すでに存在している知識を再生産する」ことしかできません。それどころか、AIを使った要約的文章が大量に生成され、それが学習データに使われていくことを考えると、ChatGPTがつくる文章は出回っている文章の縮小再生産になっていく可能性があります。もし、人間がそれを「正しい」と信じ規範とするようになったら、創造的な発展はなくなっていくでしょう。 もちろん「AIを使うな」と言っているわけではありません。むしろ、うまく使う練習をすることが大事です。ChatGPTが間違った答えを返すことを経験し、うのみにしてはいけないと納得すること。その上で、どのように使ったら便利で、どのように使ったら良くない結果をもたらすかを考え続け、試行錯誤することです。 そしてそれ以上に求められることは、学校で学ぶ抽象的な概念を、どれだけ生活の経験に結びつけられるかどうかです。ランナーが抽象的な「速さ」という概念を身体で感じ取りその意味を把握しているように、日々の体験を抽象的な概念に結びつけていくことです。 これが、「記号接地」するということです。この記号接地の学びを通じて、ことばの意味を獲得し、学びの直観を得ることができるようになるからです。 このように考えていくと、私たち人間に残された道は、熟練のうどん職人のように身体や経験を通じて学び、直観力を磨いていくしかないように思えるのです。 そのためには、「間違う」ことも大事です。 アブダクション推論のことをお話ししましたね (60ページ)。アブダクション推論は、 知識を拡張させ、発展させる推論です。しかし、誤った推論も生みます。人間は多くの誤った推論をするのに、なぜ、文明を進化させ、芸術や科学を進化させてくることができたのでしょうか? それは、誤りを修正する能力があるからです。 そして誤りの修正をするのもまた、アブダクション推論です。人間は失敗から多くを学ぶことができる生き物です。実際、「学習科学」の研究では、まだ習っていない問題を、 自分の持っている知識でなんとか考え間違ったときのほうが、難なく解答したときよりも、 学びが深まり定着するということがわかっています。 生成AIを使い、簡単に答えを出してしまうことを「あたりまえ」と思ってしまうと、 「直観」が育たないだけでなく、自分で難しい問題を考え、チャレンジして失敗をすることを避けるようになるでしょう。「早く答えを出して宿題を終わらせられたらラッキー」と思うようになるかもしれません。そのような勉強法では、知識を「記号接地」することはできません。結局、どうしてそういう答えになるのか、その意味がわからないからです。 手早く答えを出すことばかりがうまくなっても、学びは深まりません。 みなさんが将来扱う問題は、答えが簡単に決まる問題だけということはまずありません。 世の中の仕組みも、技術も、ますます複雑になっていき、答えが単純には決まらない問題が多くなるはずです。そういう状況で活躍できる人は、抽象的な概念を自分に接地させ、 身体の一部にすることができる人です。つまり「生きた知識」を、身体や経験を通じて学ぶことで自ら作ることができる人なのです。
0投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BD09366550
0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ中高生に向けて書かれた本 「母語でも第二言語でも思考できない子どもの増加」が気になった 「抽象的な言葉」を「生きた知識」にすること 勉強になった
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AIを日常的にたくさん使うようになった、現在。 人間はAIに頼りすぎて、人間ならではの推論の力、言葉の力、直感、根拠に基づいて発言力などが衰えていく。 この本では、上記の力の具体的な使われ方や鍛え方などが書かれている。 Googleなどの検索エンジンでは、検索したら、「AIによる回答」が出てくる。みんなそこで、AIの回答を読んで納得してそれ以上深く調べないが、AIは、根拠に基づいた情報を言うこともなく、また間違った情報を回答として言っている場合も、大いにある。 本当に正しいかどうか、その都度思考しながら、適度にAIを使う必要がある。 考える力などを鍛えるためには読書が最適だと書いてあり、確かに、なるほどと思った。 しかし、内容が少し難しいところもあった。ページ数をへらして、分かりやすい内容にすると良いと思った。
1投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中高生向けなのでサクサク読める。AIの時代において「考える力」の大切さ。そもそも人は、幼いころから「推論する」ことによってことばを獲得してきている。ところが生成AIなどの外部装置に頼ることで、その「考える力」が失われるのではないかということ。「直観」を磨くことが大切。生成AIは教育の場にもどんどん取り入れられているけれど、その付き合い方については一度整理しておきたいなぁ。
0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を読んで、Chat-GPを使う時に、これも教えましょうか?と言うような展開になる事が多いけれど、何の抵抗も無く、お願いしますと、利用していた事に気がついた。 おっと、危ない。 これは思考が奪われていることを発見したよ。自分で考えること、直感力が大切だ。頼りきらないこと。読書が一番だね。
0投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ3章まではこれまでの著作で読んだ記憶があって、スムーズに読めた。『第4章AI時代の「考える力」』が初めて触れる知見だった。 特に、『記号接地問題』は初耳だった。ChatGPTを使ったときに感じるグルグル感…あれは確かにメリーゴーラウンドだ‼︎ AIをどのように使っていくのか、AIの時代にひとはなにをするのか、考えていくひとつの大きなヒントを得た。
0投稿日: 2025.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は著者の新書等で書かれていること。表現を平易にして、ポイントを絞って文量も少なめ。中学校1年生の次男がサクッと読める文量。彼の中に何かしら得るものがあったことを期待したい。
0投稿日: 2025.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログAIの時代に何を学ぶべきか、それは「思考力」である。 思考力を鍛えるためにどの科目を学ぶべきか、それは「国語」である。 なぜなら、国語はすべての科目を学ぶのに必要となるからであり、ことばを知っていると、思考が楽になるからである。 そのことを、私たちがどのようにして母国語を学んできたか、子どもたちの「アブダクション」を見てゆくことで明らかにしてくれる。 いわゆる『ヤングアダルト』と呼ばれるジャンルであり、新書に比べるとかなり易しく書かれており、正直物足りない。 しかし、このような本を読むと、今井先生ほどの知性が、中高生に対してどのように語るか、言い換えれば、中高生の知性をどのレベルに設定しているかを学ぶことができる。そして、自分が子どもや部下に語るときのヒントを得ることができる。 小学校高学年から中学生に読んでほしい本。 あと、小さい子をもつお母さんにも。 以下、少しだけ抜粋。 【はじめに】 では、思考力を使って問題解決ができる「名探偵」になるために、私たちは何を学べばいあのでしょうか。(略)正解は、国語です。 「なぜ国語?」 確かにそう思う気持ちもわかります。 数学や英語のほうがなんとなく、問題解決の役に立ちそうですよね。でも、私たちは何を学ぶにも「ことば」を使います。「ことばの力」がなくては、数学の問題もうまく解くことはできません。ちなみに、みなさんが数学の文章問題が苦手なのは、「数学の理解ではなく、問題文の理解が不十分だから」ということが調査で明らかになっています。 「すべての科目で使うもの」。それが国語で身につける「ことばの力」なのです。 p88 グローバルな社会になり、世界的に問題になっているのが「母語でも第二言語でも思考できない子ども」の増加です。(略) 日常会話が何か国語でできても、それだけで深い思考はできません。一つの言語で構わないので、抽象的なことばを操ることができるようにすることが大切です。 もしみなさんが、日本で育ち日本語を母語としているのであれば、日本語で抽象的な概念を扱い、思考を深めることができるまでしっかりと国語の勉強をすることです。外国語は、国語の能力の伸びに寄りそうように伸びていきます。小さい頃から英語を習っていなくても、まったく心配ありません。
9投稿日: 2025.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ語彙の獲得の上で、「推論」が大切である。 中学生でも理解できるよう、これ以上なくわかりやすく記述されている。
0投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ中高生向けのシリーズながらのおかげで分かりやすい、かつとても示唆に富む良書だ。 基本は言語の意味と、人間が言語を獲得する過程を説明してくれるものだが、言語を獲得するのと併せて思考力も獲得しているのだと分かる。 AIの仕組みも説明し、だからこそ思考し類推していくことが大切だと説く。おっしゃる通りだ。
0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間が言葉を駆使していろいろな推論をする能力は、AIにはないことを強調しており非常に頼もしい提言だと感じた. 小生をAIを活用しているが、自分の得意分野での彼らの回答はまずますではあるが、合格点ぎりぎりのレベルだと思っている.未知の分野では彼らの答えが妥当かどうか判断するのは難しいだろう.その観点から「記号接地問題」が紹介されていたのは非常に適切だと感じた.‘’記号から記号へ漂流し、一度も地面に降りることができずに回り続けなければならないメリーゴーランドのようだ‘’はよく吟味された文言だと思った.
0投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ☑問題解決に必要な「推論の力」 1.アダプション推論:仮設を立てる 2.自分で使ってみる 3.修正する ☑知識を素早く取り出す力→情報処理能力 ☑思考をコントロールする力→実行機能
0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ発見したことをすぐに別のシーンで応用する。 例えば「食べ物にかけておいしくするモノ→しょうゆ」からコンデンスミルクのことを「苺のしょうゆ」と言う。 子供は時に大人でも気付かない「モノとモノの間の『抽象的な関係性』に気付くことができる。例えば言い間違い「歯で唇を踏んだ」噛むも踏むも「上からものに力を加える」ところが共通している。分析力! 子供は2歳にして語彙がどのような関係からできているか分析し、新しいことばがどこに収まるのかを考えている。新しいことばを覚える時、その見分けかたも一緒に探り出している。例えば「羊」を覚えると「ワンワン」の範囲が狭まる。 前後左右で伝える「自己中心枠」と「モノ中心枠」同じパーキングの「前向き駐車で」という指示でも人によって「前向きの枠」が違うのである人は「通路が前」ある人は「自分の進行方向が前」と考えて逆の現象になっている。 「ことばの力」は「考える力=思考力」に関わっている。 「考える力」は言葉の学習を通して成長していきます。言葉の力と考える力は皆さんの右足と左足のような関係です。歩く時右足が前に出れば自然と左足も前に出ます。言葉の力が伸びれば、考える力も同時に伸びていきます。そして、考える力が伸びれば、言葉の力もおのずと伸びていくのです。 思考力とは問題を解決しようとする力。推論力。暗記しただけの知識は「死んだ知識」。必要な時にすぐ取り出せて、他の知識と組み合わせて新たな知識を生むことができる知識を「生きた知識」とする。 推論の中には、①相互排他の推論、②アナロジー「類推」の推論、③帰納推論があり、それぞれを組み合わせながら目の前にある言葉を推測していく。 相互排他の推論も、アナロジーの推論も「アブダクション推論」に含まれる。「仮説形成推論」の事。目に見えないメカニズム(構造)を発見すること。 情報処理能力 自己をコントロールする能力(実行機能) も合わせて重要。
0投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の他の書籍と、伝えるメッセージは変わらない。 ただ本書は子ども向けに書かれており、復習にちょうど良かったです。 p95 にある「ことばのセンス」を上げるためのコツが、個人的には収穫でした。 - ことばは、そのことばと関連することばと一緒に覚える。 - ことばの意味は、「点」ではなく、広がりがある「面」として捉える。 - 抽象的なことばの意味をしっかり本質まで理解する。 心に刻みたい。
0投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を学ぶのがそもそも好きな私にとってはスッと入ってきやすい内容だった。けれども抽象的なことばを語彙として増やしていくことで「思考力」も伸びていくというところが、子ども向けの本ながらも大人にも響く部分だった。 ことばを理解するときに点じゃなくて面で理解していくこと、似た言葉をセットで調べる、覚えることでさらに理解が深まるというのは外国語学習なら当たり前にできるのに、日本語だと途端にやっていないのはなぜだ? アブダクション推論:仮説を立てたり違う分野の知識を組み合わせたりして目には見えない現象を推論すること(仮説だからもちろん答えは一つではなく、間違うことだってある) ex)・AではないからBだ(相互排他の推論) ・関係の同じを見つけ出す(アナロジーの推論) ××数ある事例を参考にして考える(帰納推論) ChatGPTの利用が台頭する中で、経験に基づく直観、推論、記号接地(ここでは身体感覚や経験とことばを接地させる。抽象的な概念を自分に接地させ、身体の一部にする→生きた知識を身体や経験を通じて学ぶことで自ら作ることができる人に。)は人間ならではのものとして意識していきたい。 ※生きた知識:ただ抽象的なことばを覚えるのではなく、今持っている知識と結びつけ知識とする あと、知らない分野についてChatGPTに聞くのはダメだ、気をつけよう。
0投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログベストセラーになった新書も面白かったけど、それをさらに噛み砕いたかの内容の本書も、やはり興味深い。AIがトライした試験結果を見ると、まず国語の読解力ありき、ってのが可視化されてますわな。
0投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ『学力喪失』が面白かったので他の今井むつみ著作を、と。内容は、AIをフックにそれを学童向けにまとめ直している感じでした。ただ外国語習得のくだりで出てきた「日常会話レベルしか話せないバイリンガル問題」は目から鱗だった。どちらの言語でもいいから抽象的なことばで思考できることが大事。日本語が母語なら国語が大事! 抽象的な言語を広げていくには図書館便利! ようするに、国語ばりばりなら外国語習得遅いことはないと。英語勉強しなおしたいと思っていたタイミングだったから背中押してもらえた。
0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
はじめに 学校の勉強はムダではありません 「考える力」つまり「思考力」を身につけること 「すべての科目で使うもの」はそれは「国語力」です 「ことばの力」と「思考力」で、問題を解決する 第1章あなたはことばを、どう覚えてきたか ・「自分で発見して考えて学ぶ」 第2章問題解決に必要な「推論の力」 ・「ことばの力」は「考える力=思考力」と関わり合う ・知識を素早く取り出す力ー「情報処理能力」 ・思考をコントロールする能力ー実行機能 ・詰め込んだ知識も、取り出さなければ意味がない ・「考える力」というのは「知識を使って、推論し、問題を解決する力」 第3章学校で必要になる「ことばの力」 第4章AI時代の「考える力」 ・AIの特徴は、「意味を理解しないこと」。「直感を持たないこと」 ・本当の意味で新しい知識を創造することはできないのが、人間とAIの違い ・人間は学びの過程で、考え、間違え、それを自ら修正することで、技を身につけると同時に、直感を磨きます。 おわりに ・ぜひ次の本へと手を差し伸ばしていただきたいと思います。なぜなら本は、ことばを増やし、生きた知識をつくるための一番手軽なツールだからです。 次に読んでほしい本 ・今井むつみ「ことばの発達の謎を解く」 ・大津由紀雄編「ことばの宇宙への旅立ち〈3〉 ・池上嘉彦「ふしぎなことば ことばのふしぎーことばってナァニ?」 ・川添愛「世にもあいまいなことばの秘密」 ほんとうにことばの力は基本的にいちばん大切な力だと思います。 ことばの力と考える力思考力で、問題を解決する 勉強していくうえでも、距離を取っていくうえでも、人や、社会とコミュニケーションをしていくうえでも、仕事をしていくうえでも
11投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ主要テーマ 本書の主要テーマは以下の通りです。 AIにはない「思考力」とは何か: AIの能力と人間の思考力の違いを明確にし、人間が持つべき独自の思考力の本質を探ります。 思考力とことばの密接な関係: ことばの理解と使用が、思考力の育成に不可欠であることを、様々な認知発達の事例や実験結果を基に説明します。 問題解決に必要な「推論の力」: 問題解決能力は思考力の重要な要素であり、推論(相互排他、アナロジー、アブダクション)がいかに働くかを解説します。 ことばを「生きた知識」にする方法: 単なる暗記ではない、状況に応じて柔軟に使える「生きた知識」としてのことばを習得するためのヒントを提供します。 AI時代の「考える力」: AIが進化する現代において、人間に求められる思考力とは何か、AIとの向き合い方を考察します。 最も重要なアイデアや事実 以下に、本書の重要なアイデアや事実を引用を交えながらまとめます。 1. AIにはない「思考力」とことばの重要性 現代社会の変化の激しさから、「今、学校で暗記した知識が、身につけた技術が、社会に出たときには「時代遅れ」になっているかもしれません」と述べ、知識や技術の陳腐化の可能性を指摘しています。 そのような時代において重要なのは「考える力」であり、「ヒントは、『すべての科目で使うもの』を学ぶ科目です。正解は、国語です」と、国語学習の重要性を強調しています。なぜなら、「私たちは何を学ぶにも『ことば』を使います。『ことばの力』がなくては、数学の問題もうまく読めません」からです。 「思考力というのはこのように、問題解決の力につながっていきます。問題解決の力をつけることができれば、社会がどんなに変わっても、未来がどうなるかわからなくても、なんとかその場で対応することができるようになるはずです。そういう人が、これからの社会で『よりよく生きていく』ことができるのです」と、思考力が社会適応能力に繋がることを示唆しています。 2. ことばの獲得と推論 3歳の子どもがイチゴを食べる際に「イチゴのしょうゆをちょうだい」と言った例を挙げ、「『食べ物にかけておいしくするもの』が欲しい。でもその名前は知らない。そこで思いついたのが、『食べ物にかけておいしくするもの』、『しょうゆ』です」と、子どもが持っている知識を基に推論し、言葉を創造的に使用する様子を示しています。この経験を通して「コンデンスミルク」という新しい言葉を覚えた可能性にも触れています。 「名探偵」の例を挙げ、「どんな事件でも、手持ちの知識や情報は限られます。手持ちの知識や情報を使って、未知の事態に対応できるかどうか。そこが名探偵になれるかどうかの分かれ道です」と述べ、限られた情報から推論する能力の重要性を強調しています。 推論には「相互排他の推論」「アナロジーの推論」「アブダクション推論」の3種類があることを解説し、具体的な例を挙げて説明しています。例えば、見慣れない動物のぬいぐるみに「ネケ」という名前が与えられた実験を通して、子どもが「形」を手がかりに「ネケ」を推論する様子を紹介しています。 3. ことばの意味の広がりと抽象化 「『ウサギ』という言葉の意味は?」という問いを投げかけ、赤ちゃんが様々なウサギ(色、大きさ、耳の形など)を見て「ウサギ」と認識していく過程を通して、言葉が指し示す範囲を学習していく様子を説明しています。 2歳の子どもが語彙の間に「含む-含まれる」という「縦の関係」や「AであるならBではない」という「横の関係」を見出していることを、実験を通して示しています。例として、「ポチ」は「しばいぬ」に含まれ、「しばいぬ」は「イヌ」に含まれるといった階層構造を理解していく過程を解説しています。 「大きいネズミと小さいゾウ?」という問いを通して、「大きい」「小さい」といった言葉が、常に比較対象との「関係」によって意味を持つ抽象的な言葉であることを説明しています。 小学校3年生から4年生頃に学習内容が難しく感じられる「9歳の壁」と呼ばれる現象に触れ、「この頃の時期、いろいろな教科で抽象度の高い内容が出てくるようになるため」と、抽象的な言葉の理解が重要になる時期であることを指摘しています。 4. AI時代の思考力 2024年の東大入試問題をChatGPTが解いた結果を紹介し、一定の解答能力を示す一方で、数学の問題において基本的な概念を誤解している例を挙げています。「分母が小さいと分数の値は大きくなるため、3分の1の方が大きいということになります」というChatGPTの誤った回答を示し、「流暢性バイアス」によって、辻褄の合わない文章でも信じてしまう人間の傾向に警鐘を鳴らしています。 うどん作りの達人の例を挙げ、毎日微妙に異なる気温や湿度に合わせて塩と水の分量を調整する経験的な「直観」の重要性を強調しています。「この『直観』こそ、中学・高校数学を学習していくために欠かせない要素だといえます」と述べ、AIにはない人間ならではの直観力の重要性を指摘しています。 生成AIの利用は便利である一方、「意味」を見つけ、「直観」を育む機会を奪う可能性があると警鐘を鳴らしています。「小さい頃から生成AIに頼り、生成AIに『答えを教えてもらう』ことに慣れてしまうと、それは自分で考えないということだからです」と述べ、思考力の低下を懸念しています。 「効率的に知識を身につける」という考え方に対し、スティーブン・スローマン教授の記憶容量に関する研究を引用し、人間の情報処理能力には限界があるため、「本当に大切な情報――つまり情報の本質――を知り、必要な情報を選び取らなければなりません」と、情報の質と本質を見抜く力の重要性を説いています。 人工知能研究者の間で有名な「記号接地問題」を紹介し、AIは言葉を記号として処理するだけで、人間のように身体感覚や経験と結びつけて意味を理解しているわけではないと指摘しています。「身体感覚に『接地していない』状態にある」AIの限界を示唆しています。 5. ことばの学びを通して思考力を高める 言葉の学習は、未知の音を外界の対象に結びつけて意味を探り、身体に落とし込むプロセスであり、その過程での試行錯誤を通して、言葉の枠や知識を修正していくと説明しています。 抽象的な言葉を習得するためには、学校の図書室や地域の図書館を活用し、読書を通して「点」の知識を「面」へと広げていくことが重要だと述べています。 言葉の曖昧さを認識し、どのように表現を工夫すれば分かりやすく伝わるかを考えることが、コミュニケーション能力を高める上で重要であることを示唆しています。 まとめ 本書は、AIが進化する現代において、人間が持つべき本質的な「思考力」を養うためには、「ことばの学び」が不可欠であることを、認知心理学の知見に基づいて多角的に論じています。単なる知識の暗記ではなく、言葉の意味を深く理解し、様々な文脈で柔軟に活用する力、そして限られた情報から推論し、問題解決に繋げる力こそが、これからの社会で「よりよく生きていく」ために重要であると結論づけています。AIを道具として活用する時代だからこそ、人間ならではの思考力を磨くために、私たちは言葉と真摯に向き合う必要があることを示唆する内容となっています。
0投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルから内容を想像して借りたら全然違う内容だった。なんと、認知心理学からの考察だった。薄い本だし、せっかくなので読んだ。 以前AIがらみで私も経験したことがある内容に触れられていた。それは、AIが生成した文章に「AだからBだ」という文が含まれていたが、「AだからBだ」とはならない内容だったという話だ。どうしてこういうことが起きるのか。本書ではAIの仕組みにほんのちょっと触れた後、「AIは意味を理解していない」、「人間の直感のようなものがない」などという表現を使って話をすすめている。
1投稿日: 2025.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井むつみ「AIにはない「思考力」の身につけ方」読了。ゆる言語学ラジオのYouTubeで先生の事を知り比較的とっつきやすそうな本書を読んでみた。人が言語を獲得する過程で少ない情報から推論等を駆使するのはよくできてるなと思った。言葉を知ることはその範囲を知ること。それを繰り返していくことで自分の世界をより明確化できる。言葉に愛着が湧いた。最近はAIも推論がもてはやされている。奥が深いな。
6投稿日: 2025.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のなかで大事に思っていた考える力、何となく抽象的で言語化しづらかった部分について、すごくわかりやすく表現されている本だった! 4章のうち3章は、人間が言語を習得する流れについて整理しているようだったので本題は4章目なのだなと思ったのだけれど、 今の時代、たまに現れる、AIを使いこなしていることにアドバンテージを見出す人に読ませたい。
1投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「言語の本質」、「学力喪失」などの著者が中高生向けにリライトしたもの。 大変わかりやすく、アブダクション推論(仮説を組み立てる)や記号接地について書かれている。 また、「情報処理能力」などは上記の本ではあまり触れられていなかったと思うので、「情報」と「知識」の違いも曖昧な自分にとって、ちょうど良く整理してくれたと思う。 言葉の力、抽象的な言葉を知ることが学校の勉強には不可欠である。 また、情報処理能力や実行能力といった言葉を使う中で育てられる力も大切だ。 この本を高校生みんなが読んで理解できたら…学力低下の問題など雲散霧消してしまうだろうに。
0投稿日: 2025.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ今井むつみ先生のご著書では、「学力喪失」が大好きだったので、この本も読んでみました。 正直、「学力喪失」を先に読んでいたわたしとしては、少し物足りなく感じました。 そもそもこちらは10代の読者に向けて書かれたそうなので、AIとのお付き合いを避けては通れないこれからの時代に向けて、10代の読者にはすてきなエールになりそうだなと感じました。
0投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ思考するとは何か? 人工知能が発達してきている今、改めて人間の思考力の大切さを説いた本。幼児が言葉を習得する過程を例に、知識を得るための思考とは何かを解説している。 考えるためには言葉が必要、という部分にとても納得した。
0投稿日: 2025.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読みやすくかつ理論的に、思考力とはどういう要素でできているか、なぜAIに頼ることが危険なのかを順番に教えてくれる本。 中学生に読んでほしいが、保護者としても出会えて良かった。 スマホで情報の波に飲まれる人たち、AIに頼る子どもたちを前に、ただ「見過ぎちゃだめ」とか「AIは間違ってることもあるよ」と漠然とした批判では次世代をつくる子どもたちに説明不足。言語学からみて、情報を選び取る力のこと、AIの答えの作り方と人の思考による答えの違い、育むべき直観の大切さを系統立てて知ると、漠然とした思いが整理される。 この本では、抽象的な概念を自分のものにするには日々の経験と結びつけること「記号接地」についても説明される。ここで知った考え方を日常と結びつけて自分のものにしていきたい。
0投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了後、「え、名著では?」とうっかり声に出してしまった。かなり分かりやすく簡単に書かれているが、内容は優しくない。AIと人間の違いは思考力の有無だが、その思考力とは何か?を限りなく言語化した本。図書館で借りたが、買う価値あり。
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログちくまQシリーズは大好きで何冊か読んだが、本書が1番自分にとって“questしたい!”という内容だった。敬愛する佐藤雅彦さんの“疑問に思ったことを知るための探求”のような考え方、また先日news23で観たイチローさんの、高校野球部がデータに頼った練習をしていることへの懸念とリンクする部分が多くあって、脳内を突風が吹き抜けた感覚がした。子どもたちだけじゃなく教育に携わる人への必読書だとおもう。知らないことを知るためにchatGPTにお任せ、はだめですよみなさん。だいじな脳を殺さないで。
2投稿日: 2025.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ地に足のついた推論をする力こそ、AI全盛となるであろうこれからに役立つ力となる。考える力とは推論をする力である。 そのためには単語はグループで覚えて、意味を面で捉える、そして身体に結びつく記号接地した、ことばこそが生きた知識(直観)となる。 答えがない問題に取り組むこれからの世代には、直観を磨くことが求められる。
0投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ12歳から15歳を対象とした「ちくまQブックス」シリーズの一冊。これまでの著者の本の中では1番簡単で、丁寧で、読みやすい。しかし、書いてある内容は認知心理学から見た言葉の獲得の話で、決して内容的に簡単なものではない。他の本と比べて、抽象的で複雑なところを端折ってあるので、そこは注意が必要だが、初学者にはちょうど良い本。 アブダクションや接地問題に触れつつ、生成AIに思考を委ねないようにと言うメッセージは大学生にこそ伝わってほしい。
0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉をおぼえるという題材に、人間の考える能力について説明があります。面白い。 そのうえで、AIとの対比もあります。AIについては、現状のできることについて語られている印象で、普遍的なことは書かれていない?(でもAIの普遍的な部分なんて今わかるわけもない) 教養本として大人も読む価値あります。今井さんと「なぜ人間は直感的にAIが人間に置き換わる、人間を超えると感じているのか?」などお話してみたいです
0投稿日: 2024.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
物事を学習していく基本スタンスが書いてある。 現時点での知識・考え方との違いを楽しむ。 計算とかは特に、「計算機でやった方が確実じゃん。」と思って考えることを放棄してた。。。 いくら便利な装置があるからといって、100%それに頼ったら自分の力が衰えるんだろうなと思った。 便利な世の中だからこそ、「自分の頭でしっかり考えて判断していく」意思が必要だなと思った。 便利な世の中だからこそ、とんでもない間違えを起こさないようにするには簡単だけど、間違えを恐れるより自分で考えて決断して、経験値を積みながら物事を学習していくことを最優先していきたいなと思った。 メモ ・名詞を使えるようになりには、それに隣接する物事を理解する必要がある。(緑・紺・水色を理解すると青という言葉が理解できる) ・新しい言葉を自分の中の言葉と結び付けると「理解」ができる(記号接地) ・外国語を覚えるためには、暗記するのではなく似た単語と一緒に覚える。 日本語との違いを探求して楽しむ。
3投稿日: 2024.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ10代向けですが、わかりやすく大人でも参考になりました。 (小中の保護者の方におすすめかもしれませんが、同著者の他の著書を読んでいる場合は重複する部分があるかもしれません。) 身体的感覚を伴う記号接地から生まれる直感力、を磨くことが大切と感じました。
2投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ10代のためのノンフィクションシリーズ「ちくまQブックス」ひさびさの新刊(第三期、10月に三冊でて、今月また二冊)。 第1章 あなたはことばを、どう覚えてきたのか 第2章 問題解決に必要な「推論の力」 第3章 学校で必要になる「ことばの力」 第4章 AI時代の「考える力」 『親子で育てる ことば力と思考力』(筑摩書房、2020年、既読)の1〜3章を土台に十代の読者向け&最新の知見を加筆+4章を書き下ろし。 自分(赤ちゃん・子ども)がことばをどう覚えてきたのかそのしくみをふりかえり、未知のどんな問題に出会っても解決の道をさぐれるような思考力を支える要素や、言葉の感覚や能力をみがく必要性とその方法をわかりやすく説く。情報を見比べて選ぶ余地のあった検索エンジンと比べた生成AIの危険性にふれ、生成AIと同じ土俵で勝負するような方法(計算に基づいて大量に集積された知識の要約や整理はできても、直観的な思考ができない)とは別の学び方、流暢性バイアスに負けないような思考力がこれからは必要だとよく理解できる。 巻末の芋づるリスト(次に読んでほしい本)は私もイチオシのことば関連本4冊。 中高生向けの1〜2時間の講演を聴く感覚で読み切れるので、話題の新書(「言語の本質」や「学力喪失」)はちょっとハードル高かったり忙しくて積みっぱなしだったり、という大人にもおすすめ。
1投稿日: 2024.11.08
