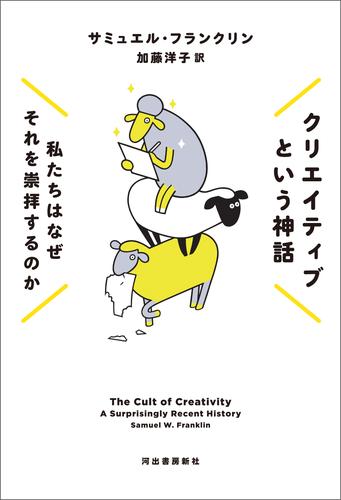
総合評価
(4件)| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「クリエイティブ」という言葉が日本人が使いまくるようになったのはいつぐらいからだったろう?と思ったことがあります。同じような「デザイン」という言葉が1960年の東京オリンピックのちょっと前から社会に登場し、それ以前は「図案」とか「意匠」とか言われていたことを知った時、では「クリエイティブ」はどうだろう?と調べてみたくなったのです。でも「デザイン」より漠然としていて意味が広くて緩く融通無碍に使われている、この言葉のことを歴史的にも社会的にも探索するのはなかなかの困難さを感じていました。「クリエイティブ」というヨコ文字と「創造性」という日本語の関係性にも難しさの原因はあるのではないか?とかとも思っています。ところがこの本の書名を見て同じようなことにモヤモヤを感じている人が世界にもいると感じ、即買い!です。ほぼ著者の問題意識には共感です。日本とアメリカの違いは関係なく「私たちはそれをなぜ崇拝するのか」です。ただアメリカを舞台に考察することによって資本主義をプラグマチックに駆動する能力としての「クリエイティブ」へのアプローチの歴史がダイナミックに浮かび上がっていると思いました。自分が「クリエイティブ」という言葉の拡がりを大きく感じたリチャード・フロリダの『クリエイティブ資本論』やIDEOについても言及されていて、ちょっとピリッとしました。問題意識に共感しつつ、語られる事実に驚愕しつつ、その主張には困惑しつつ満喫しました。「クリエイティブであるためにはどうすればいいのか?」はあったけど「クリエイティブってなんで大切と思われているのか?」は知る限り唯一無二の本でした。多分、次の起点になる本。
1投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は、創造性とは何か?をテーマとして追いかけている。AI時代における創造性とは?そして、農業においての創造性とは?といっても、なかなか創造性のあるアイデアは浮かばない。ちょうど、おもしろい本があったので読んだ。 本を読みながら感じたのは、著者はとても忙しい人だ。じっくり論考するより、人の意見を散りばめながら、「八艘跳び」のように展開していく。そのため、注意散漫な印象になり、本質が見えてこない。著者は何が言いたいのかが隠されてしまう。 著者は、「創造性の崇拝(The Cult of Creativity)」という大胆な原書のタイトルにもなっている。この表現は、クリエイティビティが単なる能力ではなく、宗教的なカルト信仰の対象のように扱われている現状を指摘する。簡単に言えば、クリエイティブという言葉を使えば、容認される状況を問題にする。 著者は本書の冒頭に「わたしは大人になるまで、自分は創造的だと信じて疑わなかったし、それはよいことだと思っていた。わたしが育った一九八〇年代は、創造性がもてはやされる時代だった。」さらに「アメリカから工場は消え失せ、ホワイトカラーの頭脳労働はコンピュータによって自動化され、脱工業化〝無重力〟経済の原材料となるのは、鉄鋼と石炭ではなくアイディアだ。」という。 そして「ますます複雑化する世界では、長きにわたり屋根裏部屋やボヘミアン・カフェに閉じ込められていた創造的人間たちが、ついに輝かしい未来のリーダーとなるのである。資格をとるならMBA(経営管理修士)よりMFA(美術学修士)」という。なんとなく、クリエイティブという言葉の意味をふんわりと表現する。 「2010年の世論調査で、1500人のCEO(最高経営責任者)が、〝リーダーに求められるもっとも重要な資質〟として挙げたのは、清廉潔白さやグローバルな思考よりも創造性だった。」という。創造性は、経営にも必要とされた。 21世紀型スキル・パートナーシップは、創造性を〝4つのC〟のひとつと位置づけた。その4つは、クリエイティブ、コミュニケーション、コラボレーション、クリティカル・シンキングである。 アメリカにおいて、creativityという言葉が普通に使われるようになったのは、20世紀の半ばからだ。creativityが最初に活字になったのは1875年のことで、第二次世界大戦が終結した直後から、創造性は一気に多用されるようになった。まさに創造性のビッグバンであると著者はいう。そして、なぜ創造性がもてはやされるようになったかを本書で考察する。 本書で挙げている創造性の天才は、アインシュタイン、エジソン、ゴッホ、ジョブスである。しかし、クリエイティビティは先天的な才能や神秘的なひらめきではなく、政治や資本主義の要請によって形成され社会に定着した「神話」であると主張している。 クリエイティブであることを実体以上に過大評価しており、ことさら創造性(創造的思考)という言葉で表さなくても、アイデアは生まれるし、なにより、新しければよいというものでもないという。 IQテスト、ブレインストーミング、自己実現ブームといった時代の流れの中で、社会的な目的のために都合よく用いられてきたという。経済の活性化、個人の自己実現、教育改革など、あらゆる問題の解決策としてクリエイティビティが崇められる過程を分析している。 著者は、クリエイティブは「能力」や「才能」といった個人的な特性として捉えられがちであるが、フランクリンはこれを神話として捉え、個人に帰属する本質的なものではないと主張している。誰でもクリエイティブであるとしている。 著者は、現代社会が「クリエイティブ」という言葉を過度に神聖視し、まるで特別な個人だけが持つ稀有な能力であるかのように扱っていると見ている。 その結果、私たちはクリエイティブな「才能」を持つ者を崇拝し、そうでない者を軽視する傾向にあると指摘している。むしろ、クリエイティブとは、特定の状況や環境、あるいは集団的なプロセスの中で生まれるものであり、決して個人の専売特許ではない、という見方が示されている。 著者がクリエイティブを過大評価し、幻想とみなす理由にはいくつかの点が挙げられる。 第一に、市場原理への組み込みである。現代社会において、クリエイティブは経済的価値やイノベーションの源泉として過度に期待されている。企業はクリエイティブな人材を求め、個人もそれを求められるが、著者はこれが現実離れした幻想を生んでいると指摘する。 第二に、個人の負担増である。クリエイティブであることが個人の責任とされることで、常に新しいアイデアや自己表現のプレッシャーがかかり、ストレスや燃え尽きの原因となる。これにより、クリエイティブな活動自体が苦痛となる恐れもある。 第三に、「クリエイティブ」という言葉による労働の隠蔽がある。地道な努力や試行錯誤、協力といった作業は見えにくくなり、閃きや天賦の才が生むものだけが強調される傾向が指摘されている。 最後に、不平等の助長も問題である。クリエイティブな人とそうでない人の区別が社会的な階層や不平等を拡大し、一部のエリートだけが賞賛される一方で、多くは「クリエイティブでない」と位置付けられることの危険性がある。 著者は、リチャード・フロリダの「クリエイティブ・クラス」論と創造都市について以下のように評価している。まず、フロリダは『クリエイティブ・クラスの世紀』等で、都市の経済成長と競争力向上には、多様な文化施設やエンターテイメント、オープンな環境を整備し、高度なスキルを持つ「クリエイティブ・クラス」を惹きつけることが重要と提唱した。フロリダは都会で成功するための要素を3Tと呼んだ。テクノロジー、才能、それにゲイやレズビアンを受け入れる寛容さ(トレランス)だ。フロリダの理論は世界中の都市に採用され、「創造都市」の概念を広めたという。 一方、著者は、これに対して批判的な視点を持つ。第一に、「クリエイティブ」が都市開発や経済競争のための道具として商品化されている点を指摘し、クリエイティブな活動や人材が単なる都市ブランドや不動産価値向上の手段に利用されていると考える。第二に、「クリエイティブ・クラス」のみに焦点を当てることで、それ以外の労働者や住民が排除され、格差やジェントリフィケーションをもたらしている点を批判している。著者は、「クリエイティブ」が社会の分断を深め、一部のエリート層だけを優遇するイデオロギーに過ぎないと見なしている。 そういう意味では、佐々木雅幸の「創造都市論」はフロリダの提起とは違っている。都市の創造性は、特定の「クラス」に限定されるものではなく、多様な人々が文化活動を通じて互いに関わり合い、新しい価値や意味を「共創」するプロセスから生まれるとしている。都市は、文化を通じて市民の参加を促し、地域の固有の資源や歴史、コミュニティの力を引き出すことで、内発的な発展を目指すべきである。 文化は経済的ツールに留まらず、都市のアイデンティティ形成、住民のWell-being(幸福)、社会包摂、持続可能な発展に貢献するものであると捉える。 具体的には、アートプロジェクト、市民活動、地域のお祭り、伝統文化の継承、地域資源を活かした取り組みなど、多様な文化活動を通じた地域活性化を重視する。残念ながら、本書には、この佐々木雅幸の創造都市論の考察はない。 著者は「クリエイティブ」を否定しているわけではない。むしろ、それは人間の活動にとって重要であると認識しつつも、現代社会がそれをどう捉え、利用しているかに警鐘を鳴らしていると考えられる。 著者が理想とする「クリエイティブ」のあり方は、現実的に捉えることにある。すなわち、「クリエイティブ」を特別な能力や才能と崇拝するのではなく、日常的な営みとし、問題解決や工夫、新しい組み合わせの発見といった誰にでも起こり得るプロセスとして理解すべきである。 次に、結果だけでなく、その背後のプロセスに注目することも重要だという。地道な探求や試行錯誤、失敗、他者との協働といった一連の過程に価値を置くべきである。 さらに、「クリエイティブ」が個人を苦しめる幻想ではなく、探究心や遊び心などの人間本来の側面から自然に生まれるものであるとの認識も重要である。こうした考えは、プレッシャーや期待から解放され、より自由で主体的な関わりを促す。最後に、「クリエイティブ」を神聖視する神話を解き放ち、その社会的構築性や光と影の側面を直視することも求められる。幻想を排し、健全な創造活動を促進する社会を目指すべきだ。 著者は、我々が「クリエイティブ」の魔法から覚め、実態を冷静に見つめることで、より本質的で人間らしい創造性を育むことができると提言している。
5投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
クリエイティブに批判的な本かと思いましたが そんなこともなくというような印象。 結局何が言いたいのかよくわからないです。 翻訳も教科書的なもので、難解な文章に 歯止めが効かない状態。 なので、読むのにかなり体力が必要。 ※僕の知能が低い可能性もあり
0投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ創造性という曖昧なキーワードが雇う側にも雇われる側にも、売る側にも買う側にも便利な概念となり定着していった歴史を追うことができた。就職前後から頭の中にあった「創造的なことがしたい」というのが実は作られた概念であり、後付けで何とでも言えるなとも感じ、ちょっと解放されてよかった。
1投稿日: 2024.12.30
