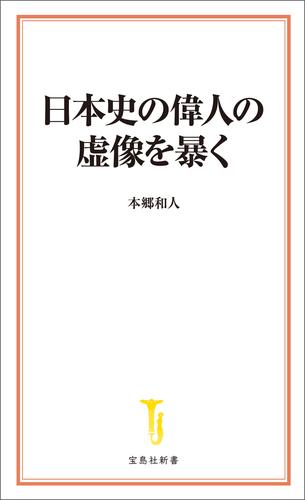
総合評価
(6件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 2 |
なかなか面白く読めた
それぞれ日本史上で英雄とされる人物たちを取り上げてその人物の実像に迫ってみる、という趣旨だが、歴史学者と在野の歴史研究家、歴史作家は同じ資料を前にしてもそれに向き合う姿勢が少しずつ違うので出す結論に差が出る。 学者は資料に書いてある事を字句の通りに読み解き結論を出すものだが、研究家はその行間にあるものを読み取ろうとするし、作家は更に面白くするために想像を膨らませる。 織田信長はその素材としては最も取り上げやすい人物だろう、日本史上のみならず世界的に見ても偉大な天才という意見があるかと思えば結果的に非凡な事をしたがよくよくみれば常識的な選択の積み重ねだという意見もある。 全体を通して感じたのは視点を変えてみる、資料をちゃんと読み解く事の重要性だろうか。 歴史を学ぶ人には通り一辺倒な解釈をしないで複数の資料を検証する姿勢が大事という歴史研究の基本を説いている訳だ。
0投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史上の偉人・英雄として描かれてきた人物たちの実像とは。 14人の本当の姿を史料から探って綴る、歴史エッセイ。 ・はじめに 第1章 藤原道長の虚像 第2章 源義経の虚像 第3章 源頼朝の虚像 第4章 北条時宗の虚像 第5章 足利尊氏の虚像 第6章 武田信玄の虚像 第7章 上杉謙信の虚像 第8章 織田信長の虚像 第9章 赤穂浪士の虚像 第10章 坂本龍馬と新撰組の虚像 第11章 西郷隆盛と大久保利通の虚像 ヤンキーの猪武者・源義経は掟破りでやり過ぎ。 武士の、武士による、武士の政権を鎌倉に樹立した、 源頼朝だが、でも京都。京都生まれで京都育ちの抱える揺れ。 「救国の英雄」北条時宗は外交下手の鎌倉幕府トップ。 偶然でモンゴル軍を退けたけど、御恩と奉公の関係は崩壊へ。 優柔不断ではなく、やるべきときにきちんと行動した足利尊氏。 出身地ガチャが明暗を分けた、武田信玄、上杉謙信、織田信長。 上洛は手段、天下布武こそが目的だった、織田信長。 ダメな殿様と有能な筆頭家老。喧嘩両成敗の道理で、 高く評価されてしまった、赤穂事件。 実体がよくわからないからの虚像の坂本龍馬と新撰組。 テロも戦いも辞さない西郷と大久保の本性は手紙の中に。 様々なメディアで描かれた歴史上の人物たちは、想像の産物。 史料自体が少ないから、想像の余地はかなりあります。 だから、古来からの伝説や伝聞、作品等に盛られたり、 こうだったかもな話が入ったりして虚像が出来上がってしまう。 また、書き手の創造の妙が愉しめるから、 虚像であれ、歴史小説に惹かれ読んでしまうんだけどね。 でも史料では実体はこうなんだよと、歴史学者の著者は 史料を正しく読み解き、史実を導き出し、考察しています。 まぁ、それでも確実ではないし、 かなり主観が入っているのが気になるところ。
12投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本郷和人先生の主張は史料を恣意的に解釈し現代的価値観の過剰投影により、説得力を欠く、彼の解釈が史料や歴史的文脈を無視して、過度に主観的である 第1章 藤原道長の虚像、道長を「政治的特徴のない貴族」と断じ、恋愛関係による地位争いに終始したと主張・・・平安貴族社会の複雑な権力構造を単純化しすぎ第2章 源義経の虚像、義経は「武士に不人気だった」の主張は、『平家物語』や『吾妻鏡』の記述を斜めに解釈し、義経の戦功(屋島、壇ノ浦)が同時代史料で称賛されている 第3章 平清盛の虚像、清盛を「革新的すぎて孤立した」と描くが、平治の乱迄の清盛は慎重に両張りしている 第4章 上杉謙信の虚像、謙信を「仁のための戦いは幻想」と断じるが、『北越軍談』や謙信の書状は、地域統治や同盟維持のための戦略的行動を意味しないか?史料の多面性を無視しすぎ 第5章 足利尊氏の虚像、尊氏の行動を「複雑すぎる」とし、源氏や天皇との関係を混乱の元と批判・・・究極の立場に追い込まれ反射的・場当たり的行動をそのように言われてもw 『太平記』や『梅松論』は尊氏の政治的柔軟性を示し、室町幕府の基盤形成に不可欠人物だった 第8章 織田信長の虚像、信長を「天下統一を最初から目指した」とする主張は全面的に否定したい、初期の信長は領地経営に重点を置き、将軍家の自立を望んでいたと思う
1投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ割とよく知られているような情報を根拠にして、歴史上の有名人を強引に低く評価しているだけのような印象を受ける。 裏表紙には、「人気の東大教授が綴る歴史エッセイ」と書いてあるので、あんまり真剣に読むべき本ではないというのが出版社の立場なのかもしれない。そう思って読めば、それなりに楽しめる。
0投稿日: 2025.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私の分類上、星★1つにしていますが、内容が悪かったわけではありません。 2024年3月31日に定年退職したとき、部屋の中に散らかっている本を見て、1年以内(2025.3.31)までに全て処理することを心に決めました。段ボール箱3つと、スーツケースに入った本達です。読み終えてポストイットが貼ってあるものは完全にレビューまで書き終えましたが、読みかけ本の処理に困りました。 半分以上読んでいるものは、読み終えてレビューを書きましたが、それ以下のものは処理に困っている状態でした。興味があって購入し、読み始めたもの、読んだらきっと良いポイントがあるのは分かっていますが、これから読みたい本も出版されるし、目の状態もあまり良くないので、部屋を整理するためにも、今日(2025.2.3)から私の61歳の誕生日(3.31)までに、全ての本を片付けたく思い、このような結果となりました。 2025年2月3日作成
0投稿日: 2025.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史学は残された文献を調査し、当時の社会的背景を加味した上で、何があったか推察する学問である。当たり前ではあるが、過去にその場を見た人間が居ないような古い時代まで、遡れば遡るほど、推察の広さも深度も大きくなる。残された文献が、当時の公的な文書であったり、客観的な意見を述べられるような立場の人間が描いた物であれば、信憑性もある程度は確保され、歴史的な価値も認められるであろうが、個人の日記や歌に込められた気持ちなどからは、果たしてそれが事実であったのかどうかは判らない部分も多いだろう。だが、極論を言えば、全てが過去の事、たとえ関係者が生きている数年前、数日前のことであれ、過去は過去だから、それをどの様に解釈し文書に残したかは、記載者にすべて委ねられる。描いた人間の心理や価値観が大きく影響するだろう。分かりやすい例で言えば、対立した両者のうち、負けた側は勝った側の事を酷く扱うだろうし、その逆は自分たちの行為を美談化して(盛って)正当化する様なものだ。「歴史は勝者が作る」という言葉が示す様に、勝てば如何様にでも歴史を描くことができる。今流れているニュースでさえも、どの様に伝えるか、見た側がどう解釈するかは人それぞれである。何を起点に、どこを始まりとして考察するかで、大分その歴史の解釈は変わる物であり、答えが一つではない、という歴史の面白さでもある。 本書は私の好きな歴史家の1人である本郷和人氏が描いたものだが、その推察の柔軟性を活かして、これまでの定説とされた歴史を「虚像」として、次々と新説を述べていくものである。だが、氏も言う様にそれが全て正しい事実かと言えば、そうでなく、あくまで推察の一つに過ぎない。だがそれが読者にとっては、第一級の研究者が述べることだから、説得力があって面白いのである。全く読んだ自分の仕事の状況、最近読んだ著書、昨日見たニュースなど、場合によっては体調までもが、解釈に影響するとさえ思える様な、歴史の奥深さと言うものを感じさせてくれる一冊である。教科書として習った事よりも、自分の知識の深さや考察力が、どこまで行っても確実な正解が無い、解答への近道である(遠回りにも感じるが)。だがこれ程までに、回り道が楽しい学問もない。どんな答えを導いても、他人から誹謗中傷されるいわれはないし、異を唱えるなら自分で考えろ、という最終兵器をいつでも使える。 本書では歴史があまり得意ではない方でも読める様に、坂本龍馬や織田信長、菅原道真など、日本の歴史上で偉大な功績を残した人々にフォーカスし、誰もが読みやすい内容となっている。こうした書籍をきっかけに、歴史の深い闇、迷路に突入し、自分なりの出口(ゴール)を描いてみては如何だろうか。終わりの無い暇つぶしといえばそれまでだが、誰1人として正確に説明する事が不可能な究極の想像の世界にダイブできる。
7投稿日: 2024.12.15
