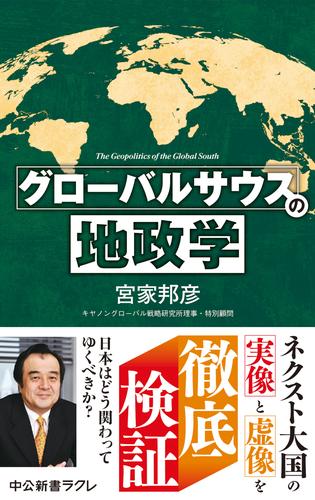
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバルサウスは一枚岩ではなく、経済発展段階、政治体制、文化的・宗教的背景において多様性を持つ。 重要なのは正しい答えを見つけることではなく、正しい問いを探すことであるというドラッカーの言葉を引用し、グローバルサウスを一括りに論じることの危険性を示唆。 著者は、グローバルサウス諸国を所得水準や民主主義指数などに基づき類型化を試みている。 BRICSのような枠組みにおいても、参加国の思惑は一枚岩ではないことを指摘。 2. グローバルサウスの地政学 冷戦後の「ポーラーシフト」として、国際社会の軸が南北に移動しつつあるという認識を示す。「変化の中心は覇権を争う米国と中国だけではない」と強調。 ウクライナ戦争におけるグローバルサウス諸国の多様な反応(国連決議における棄権や反対など)を例に、欧米中心の国際秩序に対するグローバルサウスの複雑な立ち位置を分析。 「国連総会ではこれら3国を含む『グローバルサウス』諸国の多くが賛成に回り、結果的には [賛成:141 反対:7 棄権:35] という圧倒的多数で決議は採択された。」 「前回(国連総会決議 Es-11/1)の総会決議に比べ、反対が19カ国、棄権が20カ国増えていることだ。」 パレスチナ問題の歴史的経緯を振り返り、グローバルサウスにおける反欧米・反イスラエルの感情の根深さを解説。「20世紀初頭イギリスのとんでもない『三枚舌外交』が生んだ悲劇である。」 3. パンデミックとグローバルサウス 米中露などが展開した「ワクチン外交」を分析し、グローバルサウスに対する影響力拡大の意図を指摘。 中国が自国製ワクチンを「世界の公共財にする」と表明したことの戦略的意味合いを考察。 インドが中国に対抗する意図を持ってワクチン外交を展開した事例を紹介。 日本が自国開発ワクチンを持たず、米国製ワクチンの確保を優先した結果、ワクチン外交で立ち遅れたことを指摘。 4. 文化とグローバルサウス ハンチントンの「文明の衝突」論を再考し、グローバルサウスの文化的・宗教的な多様性を無視できないと主張。「文明は歴史、言語、文化、伝統、そして最も重要である宗教によって互いに区別される。」 イスラム協力機構(OIC)やバチカンの影響力を分析し、グローバルサウスにおける宗教の重要性を強調。 中国におけるウイグル族の人権問題などを例に、文化・宗教的対立が国際政治に与える影響を示唆。 5. 日本の対グローバルサウス政策 経団連が発表した「グローバルサウスとの連携強化に関する政策提言」を紹介し、日本経済界の関心の高まりを指摘。 「グローバルサウス諸国は、(筆者注・歴史・文化的背景は多様だが)西側にはない天然資源や人口増加を背景として、近年経済力を向上させるとともに、今後長期にわたり経済的プレゼンスを高めると予測される。」 日本のODA(政府開発援助)の変遷を概観し、従来の理想主義的な姿勢から、より国益を重視する戦略的な活用へと変化していることを説明。 2003年のODA大綱改定で「我が国の国益の確保にとって不可欠」と明記された点を重視。 2023年に導入された新たな無償資金協力の枠組み「政府安全保障能力強化支援(OSA)」に言及。 中国の援助が、被援助国の経済・民生向上よりも、資源確保や政治的影響力拡大を優先する傾向があると指摘。「中国の『債務の罠』と呼ばれる手法が問題となっている。」 グローバルサウス諸国との連携において、日本の強み(質の高い技術、信頼性など)を活かすべきと提言。 6. 主要国のグローバルサウス戦略 中国: 経済力と軍事力を背景に、グローバルサウスへの影響力拡大を積極的に推進。「就治の正統性」を強調し、反米の姿勢を鮮明にしている。 ロシア: 反米・反西側の立場を共有するグローバルサウス諸国との関係強化を図る。ウクライナ戦争におけるグローバルサウスの反応を注視。 インド: グローバルサウスの「代表」としての自負を持ち、民主主義を標榜しつつ、米中いずれにも偏らない独自の外交を展開。Q u A Dなどを通じた西側との連携も模索。 ブラジル: 反欧米・反植民地の意識を持ち、グローバルサウスとの連携を重視する一方、国内政治の不安定さが外交に影響を与える可能性。 南アフリカ: BRICSへの参加などを通じてグローバルサウスとの連携を強化するが、国内の経済問題や政治情勢が課題。 サウジアラビア: 経済的利益の拡大を目指し、グローバルサウス外交を展開。「二聖モスクの守護者」としての宗教的役割も考慮。 UAE: 経済的な多角化を図り、米中露などの主要国間の政治経済的競争の狭間で微妙なバランスを保つ外交を展開。 トルコ: 東西の狭間でアイデンティティの模索を続け、EU加盟交渉の難航などから、グローバルサウスとの連携を模索する傾向。 イラン: 歴史的に欧米の植民地支配の経験がなく、独自の立場を維持。核開発問題などを背景に国際的な孤立を深める中で、グローバルサウスとの連携を模索。 エジプト: アラブ・アフリカにおける地域大国としての地位を維持しようとするが、経済的な脆弱性や食料安全保障の問題を抱える。パレスチナ問題への関与は深い。 インドネシア: 多様な民族・宗教を抱える民主主義国家として、グローバルサウスにおける独自の地位を築こうとしている。 7. 「ネクスト大国」の可能性と類型化 著者は、2050年の「ネクスト大国」候補として、インド型(インド、インドネシア)、中国型を挙げている。 その他、ロシア型、ブラジル型、トルコ型、エジプト型、サウジアラビア型にグローバルサウス主要国を類型化し、それぞれの特徴と限界を分析。 北朝鮮を特異な例として言及。「『生き残り』を図ることで頭がいっぱいであり、『グローバルサウス』内で指導的地位を担う余裕はないだろう。」 8. 日本が取るべき対グローバルサウス戦略 従来の援助中心の姿勢から脱却し、国益に資する戦略的な連携を構築する必要性を強調。 「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化」「貿易投資関係の強化」「重要鉱物等のサプライチェーン構築」などを通じた経済的強靭性の強化を提言。 ODAの効果的・戦略的な活用、日本企業の現地展開の加速、産業協力の強化などを具体策として提示。 グローバルサウスへの関与においては、「説得力のあるナラティブを効果的に発信する」ことの重要性を指摘。 インド型に対しては、同盟国化を安易に期待せず、中立を維持させることが重要であるとし、Q u A Dのような緩やかな対話の枠組みを推進すべきと主張。 中国型に対しては、グローバルサウスを徹底的に利用しようとする意図を持つため、警戒が必要と論じる。 ロシア型に対しては、経済的支援を重視する傾向を利用し、中国との連携を弱めるよう働きかけるべきと示唆。
0投稿日: 2025.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログそろそろこの手の勉強もしなければと思ったところで買ってみた! 筆者の考えが率直に書かれており、よかった!
0投稿日: 2024.12.12
