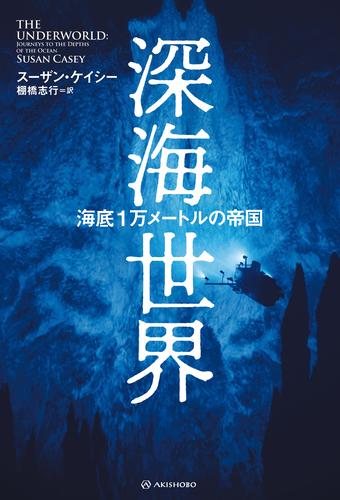
総合評価
(6件)| 4 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ深海への人類の挑戦を本人の体験をもとに書かれた著作で、実際に深海に行った筆者が書いたものである。 生きて帰ってこれないかもしれないという恐怖や実際に観た深海の感動が伝わってくる本。 では自分も行ってみたいかと考えるとそれはまた別の話でちょっと厳しいかも。。。という感想です。
0投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ深海をどう定義するのかはいろいろな意見があるようですが、本書では太陽光が届かなくなる200mよりも深い海域を深海と扱っています。その定義に従えば、地球表面の65%が深海域となるとのこと。本書は、深海へ挑んだいくつかのプロジェクトを通じて、深海域がいかに生物種に富んだ世界であるか、また将来に向けての問題点などを扱っています。 本書にもある通り、宇宙へ到達した人間は数百人レベルなのに対し、最も深いマリアナ海溝チャレンジャー海淵(水深は10900m程度)に到達したのはわずか数人です。そのハードルは1平方センチあたり1トンを超える水圧はもちろんですが、何より深海底には地図がないのでGPSが使えません。音波で測位するにも水温や水流による誤差も発生します。実は宇宙よりも到達困難なフロンティアとも言えるのが超深海帯です。超深海帯はこれまで暗黒の、生物が生息できない”死の世界”であると思われてきました。ところが、潜水艇やロボットによる調査によって、数多くの微生物をはじめクラゲや魚類など豊かな生物圏が構成されていることが判ってきています。潜水艇に同乗した著者自身の体験や、潜水艇で数多くの調査を実施した科学者による色鮮やかで豊かな描写が、そのイメージを変えてくれます。 一方、マンガン団塊など豊富な地下資源の埋蔵場所として深海域が注目を浴びており、資源の高騰にともなって深海域からの鉱物資源の開発が進められています。深海域は太陽光も届かず、生命活動は非常に穏やかなので一旦破壊された環境や生物圏は回復が非常に難しく、海洋生物学者は深海域の開発は取り返しのつかない事態を招くと反対している現状が紹介されています。 宇宙を扱った書籍が数多く出版されているのに対し、海洋、特に深海域を扱った書籍は少なく、現在の深海域開発の実情を分かりやすく、生き生きと伝える内容の濃い稀有なノンフィクションでした。
4投稿日: 2025.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・深海(水深200メートル以下)は海洋空間の95%を占めるが、今でも海底の8割は鮮明な詳細図が作製されていない。 ・世界で一番深い海淵はマリアナ海溝のチャレンジャー海淵 ・トンガ海溝のホライゾン海淵は「生命がない。冷たい。…私がそこにいることを望んでいな」いところだった。
0投稿日: 2024.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ海愛、深海愛に満ちた一冊。 海大好きジャーナリストが、とうとう実際に潜航艇で深海に行ってしまう。 その行程と、深海愛が素晴らしく溢れ出ている。 欧米系のこの手の本の煩わしい冗長な描写は確かに鼻をつくのだが、まし。 何より、この、深海自体が素晴らしい。 本の構成としては、ただの日記と言って仕舞えばそんな気がする。 リスク描写は最小限だし。舞い上がってる感は一杯。閉所、暗いところが苦手な人には向いてない。 また、口絵というか、その深海の写真が素晴らしい。 その一方で。 ここが掘り出すべき宝箱にしか見えない人達がいて、やばいのも事実 目の前にある自然は、征服すべきので、そこから得られる富は、あなたのものだ的なやばい動きもある。 海はなんでも受け入れてくれる、という思想でもないだろうが、廃棄したゴミが山ほど溜まっていて、代謝の緩やかな深海ではそれが、どれだけのダメージか。 つまるところ、人間浅知恵でいじってはいけないものが世の中にはいくらでもある。その謙虚さを失った時に、どんなしっぺ返しがあるか。 これまで何度も、いくらでも後悔して来たことをまた繰り返すのか。 深海は、それを突きつけてくれる。 まだ、宇宙へ拡大した方がましなんだろう。結局は。 その一方で、世界レベルのバカな金持ちが、無理矢理にでもどれだけの扉をこじ開けて来てくれたのか。 色々考える本。
1投稿日: 2024.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ16世紀の海図から最新の研究成果まで、深海についての知見を物語のように面白くっ綴ったサイエンスノンフィクションである。何よりもわくわくするのは、著者自身が足を運んで、時には深海へもぐり、その驚異と感動を伝えてくれることである。要するに、体を張っているのだ。だからこそ、書かれていることが単なる知識でなく、血肉のような喜びや恐れとして感じられる。深海は孤独で静かである一方、生き物に満ちにぎやかである。そんな深海に、人間は容赦なく開発の手を伸ばそうとしている。私たちは、深海についてほとんど何も知らない。そのことをあらためて教えてくれるとともに、深海を知りたくてたまらなくさせる本である。
1投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の深海探査情報はジェイムズ・キャメロンの個人的探査艇建造時点から更新されていないかった!宇宙開発関係のニュースはどこかの社長がロケットに乗ります含めてどんどん発信されてくるのに海中の探査のニュースは全然出ない。この本も本屋さんをぶらぶらしていて偶然見つけたもの。ネットでもリコメンドで上がってこないしどういう情報を分析してるんだろうね?こうして自分の関心領域も、意識しないと変なバイアスがかかったものだけが流れてきて影響を受けていることがよくわかった。 深海探査すごい進化してるぞ。本は付箋だらけ。深海探査は国家プロジェクトとしてやっているのかと思いきや、金持ち企業家が各分野のプロを集めた個人的プロジェクトによって推進されているのも驚き。一周回ってもはベルヌのSFやスペオペの世界になってる! もはや有人潜水艇のデザインもランチパックを立てたみたいな格好!ダイオウイカを見つけた時の透明アクリル球体の船体にも驚いたけどこれはすごいね。カーボンを取り込んだ植物プランクトンを深海域からのプランクトンが夜間に取り込んで深海に溜め込んでいくサイクルがあるとか、気候は海から始まっていることがよくわかる。 ショックだったのは深海域を資源開発のために切り売りする国際機関があるとか、その資源開発開発会社の科学顧問として伝説のアルヴィン号の唯一無二の女性パイロットだったバン・ドーバーがついてめちゃめちゃな開発に関与していたということ(昔彼女の本読んですごい感動したのになぁ)。中国の深海探査挺は中であたたかい食事まで取れるデカさなんていう情報は誰も流さない。欲とエゴと政治にまみれた科学探査の世界の情報は流れてくる情報を漫然と受け取るだけでは正しい姿は見えない。もっと積極的に取りに行かないといけなのね。恐ろしくも面白い世の中になったものだ。
16投稿日: 2024.07.26
