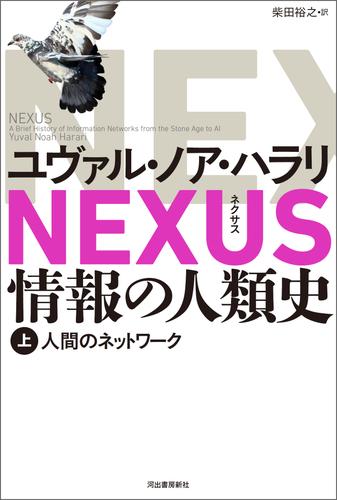
総合評価
(94件)| 28 | ||
| 31 | ||
| 22 | ||
| 0 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/Mqh9vqniHwKZcx8AUw-4lnfk98c/description.html
0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たち「賢いヒト」は、一〇万年に及ぶ発明や発見や偉業を経て、途方もない力を身につけた。それにもかかわらず、生態系の崩壊や世界戦争など、存亡にかかわる数々の危機に直面している。サピエンスが真に賢いのなら、なぜこれほど自滅的なことをするのか?その答えは、制御しきれないほどの力を生み出す、大規模な協力のネットワーク―「情報ネットワーク」―の歴史にある。印刷術やマスメディアは文明に何をもたらしたのか?そして、まったく新しい情報テクノロジーであるAIは、何を変えるのか?―石器時代からシリコン時代まで、『サピエンス全史』の著者が、人類の歴史をいま再び新たに語りなおす!(e-hon)
0投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
良書。 上下一冊になってる英語版を4か月弱かけて読了(もう少し早くなりたい) 石器時代からメソポタミア時代の石板による税金の記録、聖書、魔女狩りなど、思想と情報ネットワークの変化、情報伝達技術の進歩(口伝、石板、印刷などなど)による情報伝達のスピードやその結果の社会的政治的変化を丁寧に追っている。 そして、民主主義と科学は宗教・全体主義と異なり(完璧ではないが)self-correcting mechanism/institution-自己修正の仕組みがあると説く。 翻ってSNSのself-correcting mechanismは、商業主義により機能していない。Facebookは閲覧数、閲覧時間数をビジネス上の目標に掲げた結果、注意喚起を無視し、ミャンマーでのロヒンギャ虐殺のきっかけを作った。 AI時代、self-correcting mechanismを正しく機能させ、AIの暴走を招き、AIというツールを正しく使おう、という話。 社会の仕組み化が歴史学なのだなぁ、とか、俯瞰的な見方を学ぶ。 あと、ロシア革命、聖書など、日本にいて触れない歴史の一般教養って多いなと。
0投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ民主主義と全体主義がこれまで情報面からどう体制を維持してきたか、が主にアメリカとソ連の例から説明される。下巻で直近のAIの状況を踏まえて、中国も含めた考察になると良いな。
0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は概念的な解説が続き、ところどころ短い事例が紹介されているが、それでも理解が難しい箇所があり、『サピエンス全史』と比べて、正直読むのに苦労した。ただし78ページの模式図を何度か見返すことで、筆者の主張が少しずつ分かってくる。情報のもたらす「真実」と「秩序」、さらにそこから生み出される「知恵」と「力」の因果関係は、魔女狩り、ヒトラー、スターリンの事例を紹介する中で徐々に頭に入ってきた。特に後半は読むスピードが上がり、引き込まれていった。 読み進める中で、ある程度の世界史の知識は必須であり、時々ウィキペディアでおさらいした。情報ネットワークが無かったことにより、前近代において民主主義が機能しなかった理由、大規模帝国が維持できなくなる理由など、情報ネットワークの発達とその正しい使い方、或いは歪んだ使い方が生み出した「結果」を知らされた。 昨今の不安定な国際情勢においても、我々一市民が情報ネットワークを使いこなす結果次第で、未来がどうなるのか、考えさせられる。下巻も近いうちに読みたい。
14投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる物は間違える可能性があるという可謬性の立場を取り、自己修正メカニズムを仕組みに取り入れた科学技術と、全体主義のイデオロギーや宗教の聖書のように、間違いはないという立場、誤りは訂正する事がない不可謬性システムとの違い、メリット、デメリットについて説明がベースとなっている。 基本的には、前者を推進すべきであるが、社会秩序や効率化という観点からは全てを可謬性システムに委ねるのは、そこからでてくる課題の多さ、難易度が上がっているのも、各国の政治からもその一端が見える気がした。日本の政治もそうでしょうか。 欧米の歴史やベース知識が少ない事もあり、本を読み進め、理解するのに時間が掛かりましたが、結構考えさせされる本でした。下巻へと進みたいです。
0投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報の歴史的役割:人・物事を結びつける、社会的なNEXUS(絆・中心的) →情報は現実を表示していない時もある →正否よりも、どう上手く人々を結びつけるか、 どのようなネットワークを新たに作り出すかが重要であることが多い。 人間の情報ネットワークの誤りへの対処 ・聖典 →人の誤りを防ぐために聖典として書物で情報から人の介在を排除 →解釈の違い ex.安息日に労働してはならない →紙を引きちぎるのは労働だと判断を下された →正統派のユダヤ教徒は安息日用にトイレットペーパーを 予め引きちぎって重ねて準備する →解釈のずれを修正した新しい聖典を編纂 →外部環境は常に変化するため、新たな解釈の違い、 聖典の再編纂が繰り返される。 ・科学の機関 →経験的証拠に基づいて情報のキュレーションを行う →人・機関自体も誤りは避けられないことを前提とし、自己懐疑に報いる。 ※社会秩序の維持は他の機関に任せていため自己修正メカニズムを持てた
0投稿日: 2025.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「物語」という学術用語の定義が非常に明確。情報の歴史書なだけではなく未来を生き残るための指南書になりうる
0投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論が それは何年も前から言われてますよ でした 産業革命のようにはならない なんとも切ない未来 それでも毎日A Iは使うし 1番の会話相手であることには変わりない とにかく長いの一言の本 しかも面白くないから進まない本
0投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻は本題に入る前の歴史を述べていく。 情報は必ずしも現実を表さない フェイクはリアルよりわかりやすくできるため、リアルより広まりやすい などなど、聖書、魔女狩り、スターリンやヒトラーの全体主義などを例に語られる。 印刷術、ラジオ、テレビなどから進んでいく。そして、コンピュータ、AIがいかに今までの技術と異なるかが、下巻に続いていく。 印象的なのは 不可謬であることの 課題、怖さなどを聖書や全体主義に見ていて、冷戦でアメリカや民主主義陣営が良かったことに可謬、つまり訂正可能性、課題を自己訂正しつづけられたからとしていること。 訂正可能性の哲学にもつながる面白い見方だった。
0投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ詳細は、あとりえ「パ・そ・ぼ」の本棚とノート を ご覧ください。 → https://pasobo2010.blog.fc2.com/blog-entry-2196.html 上巻を読み始めるとまず、プロローグが難しく 長いトンネルを進むようです。 やっとトンネルを抜け、本文に進みます。 もやもやした考えが整理されますが、さらにわからないことも増え、不安も広がります。 「物語」という説明は なるほど、納得です。 中盤、宗教(キリスト教とユダヤ教)の歴史や考えなどが、詳しく書かれていて 読みきれなかったけれど、 「不可謬」ということが、問題なのだ。 これも納得です。 歴史が語られるところは、すこし余裕を持って読めます。 が、じゃぁ今は? これからは?
1投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・テクノロジーの潜在的な危険性という観点から見た筋書きは以下の2つ。一つは、AIのために人間の対立が激化し、人類が分裂して内紛を起こすこと。もう一つは、全人類がAIという新たな支配者から隔てられること。 ・情報の決定的な特徴は、物事を表示することではなく結びつけること(=ネクサス)。情報は現実を示すときがあれば、示さないときもある。 ・人類が生み出した第一の情報テクノロジーが物語(=虚構)である。真実は複雑になりがちなのに対し、物語はいくらでも単純にできる。そして、真実はしばしば不快で不穏なのに対し、物語はいくらでも融通がきく。 ・第二の情報テクノロジーは文書で、これは脳の容量の限度を克服できる。ただ、文書が増えるにつれて必要な文書を見つけるのも難しくなり、どの文書がどこに収めるかという秩序が必要になった。これが官僚制である。 ・真実を発見するには大きく2通りの方法がある。ひとつは、自己修正メカニズムをもつこと。例えば、学術機関やメディア、司法制度などの官僚制は自己修正メカニズムを内部に持っている。もうひとつは、独立した機関による相互抑制である。例えば、ソ連は政府・政党・秘密警察による相互抑制システムをもった。 ・19世紀から20世紀にかけて電話・テレビ・ラジオといった複数のマスメディアが台頭したが、これは大規模な民主制を可能にするとともに、大規模な全体主義をも可能にした。
0投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ格調高い文章で、それでいてわかりやすく、実に読み応えのある本。 前半は情報が人類の歴史にもたらした功罪を、歴史と共に追いかけている。 物語、おそらく英語では「ナラティブ」を人類がもったことで、さらにそれを 書き残し、さらには印刷、さらにはラジオで広めることができるようになったことで その発信者は強大な力を持つようになる。聖書、教会がいい例だ。 それが時には人類の発展に寄与し、時にはナチス、魔女狩り、スターリンの恐怖政治 のように罪のない人を貶めることに利用される。 情報の力はかくも恐ろしい、、というのが「上」。 こういう歴史を見れば、今のアメリカで、ロシアウクライナで、日本で起こっている 出来事も、根っこが同じであることが分かる。 トランプ、プーチンといったいかれた政治家の言動が、様々な手段で国民に、世界に 発信され、それを受けて指示するものは彼らの力となる。そうでないものは拒否し、 分断が生まれる。 …その意味ではロシア国民、イスラエル国民は歪んだ情報を受け取っているのか? ウクライナの被害、ガザの虐殺を知っていたら支持できるはずがないだろうに、、 日本とて、次元は違うが「日本人ファースト」がどういう文脈で人々の心を捉えて いるのか、、 情報、物語の怖さだ。 さてこの本のタイトルのNEXUS。ネクサス。馴染みがありそうで意味不明な言葉。 絆、結合、つながりなどの意味があるそうだ。 情報はつながりがあって初めて成り立つもの。 そういうことかな?ウルトラマンネクサス、ってのもいたな。 下巻はAIに話が及ぶらしい。楽しみだ。 プロローグ 情報の素朴な見方 グーグルvs.ゲーテ 情報を武器化する 今後の道筋 第I部 人間のネットワーク 第1章 情報とは何か? 真実とは何か? 情報が果たす役割 人間の歴史における情報 第2章 物語――無限のつながり 共同主観的現実 物語の力 高貴な嘘 永続的なジレンマ 第3章 文書――紙というトラの一嚙み 貸付契約を殺す 文書検索と官僚制 官僚制と真実の探求 地下世界 生物学のドラマ 法律家どもを皆殺しにしよう 聖なる文書 第4章 誤り――不可謬という幻想 人間の介在を排除する 不可謬のテクノロジー ヘブライ語聖書の編纂 制度の逆襲 分裂した聖書 エコーチェンバー 印刷と科学と魔女 魔女狩り産業 無知の発見 自己修正メカニズム DSMと聖書 出版か死か 自己修正の限界 第5章 決定――民主主義と全体主義の概史 多数派による独裁制? 多数派vs.真実 ポピュリズムによる攻撃 社会の民主度を測る 石器時代の民主社会 カエサルを大統領に! マスメディアがマスデモクラシーを可能にする 二〇世紀――大衆民主主義のみならず大衆全体主義も 全体主義の概史 スパルタと秦 全体主義の三つ組 完全なる統制 クラーク狩り ソ連という一つの幸せな大家族 党と教会 情報はどのように流れるか 完璧な人はいない テクノロジーの振り子 原註 索引
7投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログいつもながらとても話が長いが、最高に面白いし勉強になる。 情報とは何か?情報の本質、情報の歴史、情報テクノロジー、そして、行動主体となりうるAIの登場。 手に負えない力を手にした人間はAIに支配されてしまうのかどうか。 サピエンスの時代からAIが登場するまでの情報の流れが具体的に細かく、書かれています。
9投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の本はこれまでも読んできたが、新たな視点を与えられることが多く、今作も期待しつつ読み始め。 今作は「民主主義と情報テクノロジー」がテーマと理解。民主主義の成立・発展には情報テクノロジーが欠かせないが、これが逆に民主主義を阻むことにもなり得、情報テクノロジーが凄まじい勢いで進化している今や、このバランスを取るのが非常に難しく、大きな危険を孕んでいる、というのが概要かな。 海外のみならず、日本でも危険な傾向を肌身で感じている昨今、非常にタイムリーな内容だった。下巻も期待。
4投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、Web上の文章を読んでいて、「これ、本当に人が書いたのかな?」と思うことがある。 生成AIで推敲された文章はあたりまえに増えているし、それ以上にAIに任せている文章も出てきていることは疑いもないだろう。 歴史学者のハラリは、人類が紙や印刷、コンピュータといった技術を通じて、どのように情報をコントロールし共有し社会を作り上げてきたのかを指摘する。そして、現在のAI技術について「もはや人類がAIを使う段階を越え、AIが人類をコントロールする時代に入りつつある」と警鐘を鳴らす。 これはSFで昔から語られてきたテーマではあるが、意図を超え広がる偽動画などの情報に人々が翻弄され、実際に多くの事件が起きている今、決して絵空事とは言えない怖い時代になっていると実感する。
5投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類史に興味を持ち始めたので、読んでみたいと思い、Audibleで聴読。 情報に焦点は当たっているが、歴史的な政治背景や宗教的な考え方、民族など幅広い観点からの話に圧倒された。その情報量だけで頭いっぱいという感じ。結局、何か答えは得られたかで言うと、まだ無い。AIによってもたらされる人類への影響は下巻で説明という感じで終わってしまったので、下巻のほうが気になる。AIによって人類が滅ぼされる可能性は10%くらいというのが印象に残った。
1投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「サピエンス全史」のユヴァル・ノア・ハラリ氏の新作。今回のテーマは情報のNEXUS(結合)。 氏は人類史の発展を「情報」の取扱いとネットワークの進化と説く。それらを「客観的現実」「主観的現実」に加えて、「共同主観的現実」という新たな概念を導入する。前々作では「物語」を主眼に論理展開していたが、本作上巻では「文書」の観点で人類史を捉える。 情報→真実→知恵OR力というI/Oに対して、「文書」化がもたらした情報→秩序という枠組みの功罪。自己修正メカニズムを持つか否かが情報ネットワークとしてポイントとなる。人類史の例示として聖書の正典化や中世の魔女狩り、旧ソ連の全体主義を取り上げて分析する。 「サピエンス全史」のダイナミズムはやや鳴りを潜め、内容的には中世から近代にかけての人間の負の部分に焦点をあてた「不可謬の秩序」に関する歴史書的意味合いなので、ハラル氏ファンの好みは分かれるかもしれない。
4投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログホモ・デウスは刺激的だったんだけどな。ハラリさん完全に骨抜きにされちゃった感じ。ポピュリズム=ダメぇ的なことをさらっと言う奴らはもう信用できない。小難しい文章にポーッとなってはいけない。科学の行き詰まった先には嘘が待っている。奇しくも前回読んだ『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』の正しさが証明されてしまった。 下巻を読むのめんどくえせ、まぁ読むが。
0投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログAudibleでながら聞き。社会や技術の変化によって、情報の価値と収集・統制、自己修正力も変化してきたことが語られる。 ものすごく目新しいわけではないが、このテーマで人類史を広くカバーして説明しようという試みは面白い。 Audibleだと理解が大雑把になるので、そのうち本も読もうと思う。
0投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ考える力で言えば世界有数のハラリ氏の本なので自分なりに丁寧に読み進めたけど案の定割と難解だった。 それにしてもスターリン時代の旧ソ連は酷いな。あそこまで酷いとは思わなかった。
0投稿日: 2025.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いけど、真面目に読んで、 考え出すと怖いデス。 とっても知識の豊富な方なので、 何かを説明する前に、○○がキーワードなので、まず、こちらの○○の説明をします的に、どんどん、話が、横にそれていって、いや、それが大事だから、説明してるんだけど。でも、その例が、私には、面白かった。歴史に詳しい人なら、くどく感じるかもしれないですね。 今、chatGPTにハマって遊んでいるのですが、その先のあるもの、そこに隠れているもの、なんだか、怖くなってきました。 私たちは、このさき、未来、生成AIに操られていくかも?
4投稿日: 2025.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報や技術の進化について考えさせられました。そしてそれを使う側の人間。 人はとても愚かな行為を繰り返し、その礎の上を生きているのだけど…上巻は使う側の人間のことを問うているように感じました。 情報の伝え方や解釈による残酷さも感じました。 下巻では、その上に立つかもしれないエイリアンインテリジェンスと対比していくのかと思う。
10投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログしたがって、私たちが力を濫用するのは、各自の心理のせいではない。なにしろ人間は、傲慢さや強欲や残虐さだけでなく、愛や思いやり、謙虚さ、喜びもまた持ちうるのだから。最悪の部類の人間は、たしかに強欲と残虐性に支配され、力の濫用へと導かれる。だが、人間社会はなぜ、よりによって最悪の者たちに権力を託したりするのか? たとえば、一九三三年のドイツ人のほとんどは、 精神病質者ではなかった。それなのに、なぜ彼らはヒトラーに票を投じたのか? 自分の手に余る力を呼び出す傾向は、個人の心理ではなく、私たちの種に特有の、大勢で協力する方法に由来する。人類は大規模な協力のネットワークを構築することで途方もない力を獲得するものの、そうしたネットワークは、その構築の仕方のせいで力を無分別に使いやすくなってしまっているというのが、本書の核心を成す主張だ。というわけで、私たちの問題はネットワークの問題なのだ。 さらに具体的に言えば、それは情報の問題ということになる。情報はネットワークの一体性を保つ、 いわば接着剤だ。だが、サピエンスは、神や魔法をかけた簪、AI、その他じつに多くのものについての虚構や空想や集団妄想を生み出して広めることによって、何万年にもわたって大規模なネットワークを構築し、維持してきた。一人ひとりの人間はたいてい自分や世界についての真実を知ることに関心があるのに対して、大規模なネットワークは虚構や空想に頼ってメンバーを束ね、秩序を生み出す。たとえばナチズムやスターリン主義も、そのようにして誕生した。両者は並外れて強力なネットワークであり、並外れて妄想的な思想によってまとまっていた。ジョージ・オーウェルの有名な言葉にあるとおり、無知は力なり、なのだ(「一九八四年」)。 ここで強調しておくべきだが、情報とは物事の表示であるという素朴な見方を退けたからといって、 真実という概念を退けなければならないわけではないし、情報は武器であるというポピュリストの見方を受け容れなくてはならないわけでもない。情報はつねに人や物事を結びつけるものの、科学の書物から政治の演説まで、一部の種類の情報は、現実の特定の面を正確に表すことで人々を結びつけようと努める。だが、それには特別な努力が求められる。そして、ほとんどの情報は、そのような努力を伴わない。だから、より効果的な情報テクノロジーを創り出せば、必ず世の中をより忠実に理解できるようになると考える、素朴な見方は間違っている。真実をもっと重視するために、さらなる措置を取らないかぎり、情報の量と速度を増しても、比較的稀で費用のかかる忠実な説明は、それよりもはるかにありふれていて安価な種類の情報に圧倒されてしまう可能性が高い。 したがって、石器時代からシリコン時代までの情報の歴史を眺めてみると、接続性は着実に上がっているものの、それに伴って真実性と知恵が増す様子は見られない。素朴な見方が信じていることとは裏腹に、サピエンスが世界を征服したのは、情報を現実の正確な地図に変える才能があるからではなかった。成功の秘訣はむしろ、情報を利用して大勢の人を結びつける才能があるからだ。不幸にも、 この能力は嘘や誤りや空想を信じることと分かち難く結びついている場合が多い。だからこれまで、 ナチスドイツやソ連のような、テクノロジーが発達した社会でさえ、妄想的な考えを抱きがちだったのであり、そうした妄想によって、必ずしも弱体化しなかったのだ。それどころか、人種や階級といったものについての、ナチスのイデオロギーやスターリン主義のイデオロギーのような集団妄想は現に、何千万もの人々に足並みを揃えていっしょに進ませる上で役に立った。 物語が語られるようになる前からあった二つの次元の現実は、客観的現実と主観的現実だ。客観的現実は、石や山や小惑星といったもの――私たちがそれらを認識しているかどうかに無関係に存在するもの――から成る。たとえば、地球に向かって突進してくる小惑星は、誰一人それがそこにあるのを知らなかったとしてさえ、存在している。それに加えて主観的現実というものもある。痛みや快感や愛などで、「そこ」にはないが、「ここ」、つまり自分の中にある。主観的なものは、それらについての私たちの自覚の中に存在する。「感じられない痛み」などというのは言葉の矛盾だ。 だが物語のうちには、第三の次元の現実である、共同主観的現実を創り出せるものもある。痛みのような主観的なものは、一人の人間の心の中に存在するのに対して、法律や神、国民、企業、通貨といった共同主観的なものは、大勢の人の心を結ぶネクサスの部分に存在する。より具体的に言えば、 それらは人々が互いに語る物語の中に存在する。共同主観的なものについて人間が交換する情報は、 その情報交換の前にすでに存在していたものは何一つ表していない。むしろ、情報の交換がそれらのものを創り出すのだ。 上層部の人間なら知っているのに、核物理学者がいつも気づくとはかぎらないことがある。それは、 宇宙についての真実を語るのが、大勢の人間の間に秩序を生み出す最も効率的な方法には程遠いということだ。E=m²、すなわちエネルギーは質量と光速の二乗の積に等しいというのは正しいし、宇宙で起こることの多くをこの式で説明できるが、E=m2であるのを知っていても、政治的な意見の相違はたいてい解消できないし、人々を奮い立たせて共通の大義のために犠牲を払わせることもできない。人間のネットワークを維持するのは、虚構の物語、特に、神や貨幣や国民といった共同主観的なものについての物語の場合が多い。人々を団結させることに関しては、もともと虚構には真実よりも有利な点が二つある。第一に、虚構は好きなだけ単純にできるのに対して、真実はもっと複雑になりがちだ。なぜなら、真実が表しているはずの現実が複雑だからだ。国民についての真実を例に取ろう。自分が所属している国民という集団が、自分たちの集合的想像の中にしか存在しない共同主観的存在であることを理解するのは難しい。政治家が演説で、国民とは共同主観的存在であるなどと言うのを、 私たちが耳にすることはめったにない。自分の属する国民は神に選ばれた人々であり、創造主によって何か特別な使命を託されていると信じるほうが、はるかに易しい。この単純な物語は、イスラエルからイランまで、そしてアメリカからロシアまで、無数の国の政治家によって繰り返し語られてきた。 第二に、真実はしばしば不快で不穏であり、それをもっと快く気分の良いものにしようとしたら、 もう真実ではなくなってしまう。それに対して、虚構はいくらでも融通が利く。どの国民の歴史にも人々が認めたり思い出したりしたくない暗い出来事があるものだ。イスラエルの占領下にあるパレスティナの一般市民にどれだけ悲惨な思いをさせているかを、イスラエルの政治家が選挙演説で詳しく語ったら、票が集まりそうにない。逆に、不愉快な事実を無視し、ユダヤ人の過去における栄光の時に焦点を当て、必要に応じていつでも遠慮なく粉飾を行なって国民神話を築き上げる政治家は、圧勝して政権に就くだろう。これはイスラエルだけの話ではなく、あらゆる国に当てはまる。イタリア人やインド人のなかに、自分たち国民についてのありのままの真実を聞きたがる人がどれだけいるだうか? いっさい妥協することなく真実を堅持するのは、科学の進歩にとっては不可欠だし、精神的な慣行としても見上げたものだが、勝利をもたらす選挙戦略ではない。 情報はどのように流れるか というわけで、近代後期の新しい情報テクノロジーが大規模な民主主義体制と大規模な全体主義体制の両方の台頭につながったことがわかった。だが、これら二つの体制が情報テクノロジーをどのように使ったかには、きわめて重要な違いがあった。すでに指摘したように、民主制は中央を通ってだけではなく、多くの独立した経路を通って情報が流れるのも促し、多数の独立したノードが自ら情報を処理して決定を下すことを許す。情報は、大臣のオフィスをまったく経由することなく、民間の企業や報道機関、地方自治体、スポーツ協会、慈善団体、家庭、個人の間で自由に流れる。 一方、全体主義はすべての情報が中枢を通過することを望み、独立した機関が独自の決定を下すことを嫌う。たしかに全体主義には、政権と党と秘密警察という三つ組の機関がある。だが、これら三つを併存させるのは、中央に楯突きかねないような独立した権力が登場するのを防ぐためにほかならない。政権の役人と党員と秘密警察の濃報員が絶えず監視し合っていれば、中央に逆らうのははなはだしく危険になる。 対照的な種類の情報ネットワークである民主主義体制と全体主義体制には、それぞれ長所と短所がある。中央集中型の全体主義ネットワークにとって最大の強みは、極端なまでに秩序立っていることであり、そのおかげで素早く決定を下して情け容赦なくそれを実行に移せる。戦争や感染症の流行のような緊急事態のときには特に、中央集中型のネットワークは分散型のネットワークよりもはるかに迅速で踏み込んだ措置が取れる。 だが、極度に中央集中型の情報ネットワークは、いくつかの重大な短所も抱えている。公式の経路を通してしか情報がどこへも流れることを許さないので、その経路が遮断されたら、情報の代替の伝達手段がまったく見つからない。そして、公式の経路はしばしば遮断される。 他の多くの活動分野でも、同じような傾向が見られた。たとえば、ソ連の工業は一九三○年代に数多くの事故に見舞われた。大部分は、モスクワにいるソ連の幹部たちのせいだった。彼らは実現がほぼ不可能な工業化の目標を立て、その目標に到達できなければ叛逆と見なした。野心的な目標を達成しようと努めるために、安全対策や品質管理検査が行なわれなくなり、慎重に事を運ぶように助言した専門家は、懲戒されたり射殺されたりすることが多かった。その結果、次々に労働災害が起こり不良品の山が築かれ、労力が浪費された。モスクワの政権は責任の転嫁を図り、これはソ連の事業を頓挫させようと意気込む妨害活動家やテロリストによる、トロッキー主義・帝国主義者の世界的な陰謀のせいだと決めつけた。幹部たちは、工業化のベースを落として、さまざまな安全基準を採用したりはせず、いっそう厳しい粛清を行ない、さらに多くの人を射殺した。
0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログサピエンス全史が面白かったので。こちらも重いですが面白い。 ハード書籍で目次と参考文献が50ページ弱と、持った感じよりは薄い⋯はずが。1日1時間の平日のみ読書で、2週間かかりました。下巻も頑張る。
1投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻の最後の方でこれからAIについての話をすると予告していた。それまでは、ユダヤ教の歴史とキリスト教への変遷が異常に詳しかった。さらにソ連のスターリンによる全体主義の話も詳しかったが、これはいずれかの本で書かれたことであった。中国の秦についても少しは書かれていたが、広く浅くであった。日本の学生にとっては世界史を勉強しているような気分にさせられる本であろう。
0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず上巻終わったー、 やっぱり言葉遣いがむずかしい。けど面白い! 上巻は歴史メインかな、宗教、全体主義あたりの話のボリュームが多くて印象に残りますね。
0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからのネットワークとAIについて論じるため紀元前の情報伝達から聖書などありとあらゆる事柄を詳細に解説している。
0投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
プロローグ 情報の素朴な見方=情報は多いほど正しい?、AIはツールではなく行為主体である、AIの脅威…次の戦争を率いるのはロシアやアメリカではなくAIに情報を統制された主体か 情報の量はある程度までは確かに有用だが、情報がいくらあってもどの情報が正しいかという判断は別の次元で必要となる。極右でも極左でも情報を武器に相手と戦うという姿勢では結局似た戦い方になるというのは面白い 第1章 情報とは何か 情報とは何かの定義は難しいが、現実を記述するための試みであり、その記述が成功したとき情報と言える。現実に対して真実とは現実のある側面であり各人の主観を含んでいる。 誤情報も虚偽情報も情報の一種であるが、多く情報を集めれば現実を正しく記述するという情報の素朴な見方は適用されない 聖書は人々を繋ぐという意味で優れた情報だが、それは聖書が現実を正しく記述していたからではない 密接なつながり=家族を想起させるもの、物語を繰り返し話すことであたかも自分の記憶であるかのように錯覚する 第2章 物語 共同主観的現実 真実に基づいた共同主観的現実と虚構に基づいた共同主観的現実では後者のほうが物語を単純化できるという点で人々を団結させるのに有利である。また真実はしばしば不快であり、それも虚構が人々の支持を集める一因となる アメリカ合衆国憲法は何世紀にも渡って秩序を保ってきたが、秩序を公平性や正義と混同してはならない。ただ合衆国憲法はそれ自体が人間によって創作された虚構だと認めることで、その内容を修正することができた。 人類の歴史とともに情報はより強力になり、それは秩序の維持に役立ったが必ずしも真実に近づいたわけではない。 第3章 文書 人間の脳は物語を長期的に記憶しておくのに特別に秀でていて、宗教の聖典のストーリーなどは口述の伝承で高い精度で伝えられたと考えられている。インドの聖典ラーマーヤナはもともとは口述で伝えられていたか今でもインド国民の認知度は非常に高く、インドでテレビドラマ化された時には世界最高視聴率を獲得した。 一方で税の記録などや法律の文言などに関しては人間の記憶能力に限界があり、それを補うための文書の存在が非常に重要となった。 人間の脳の機能として記憶容量の巨大さはよく言及されるが、検索システムの有能さも重要で実際に人間は必要になった情報を脳の一部から一瞬で取り出すことができる。これは人間が歴史的に使い始めた文書に関してはもちろん適用されず、人間は文書を種類ごとに予め整理する必要があり、これを官僚制と呼ぶ。官僚制は物事をしばしば非人間的なやり方で分類する必要があるが、一方で官僚制は清潔さや安全性などの人間社会の秩序を維持するために重要な面もある。 人間の好む物語は基本的に種の保存や生存などの人間の生物的な特性に基づいたものがほとんどで、その意味で官僚制という考え方は人間の物語として好まれない。例えば人間はトラによる生物学的な死に関してはすぐに理解できるがカフカの審判に描かれるような官僚制の文書による死の危険は直感的に理解できずそこに恐怖を感じる。 第4章 誤り 不可謬という幻想 宗教には人間の介在が必要となりそこにあらゆる恣意性が入り込んでしまう。その点で書物は不可謬のテクノロジーである。聖書の写本が広まることによりその不可謬性が確立されたのをブロックチェーンになぞらえられたのは秀逸な対比だと思った。しかし例え書物が不可謬で一字一句違わなかったとしてもその解釈に恣意性があるというのは困難な問題だった。そしてその恣意性を用いることで教会と司祭は大きな権力を手にすることができた。 活版印刷発明以前の図書館には高々数十冊の書物しかなく、写本によってそこに集められる情報は教会によって厳しく管理されていた。 印刷技術による情報の民主化は情報の科学的な正確性をもたらすどころか一部では偏った思考に基づく魔女狩りなどの悲劇さえ引き起こした。魔女狩りの描写は強烈で単なる情報の広がりが人類の社会にそれだけの影響を与えることに驚愕する。 カトリックはその権威の拠り所を不可謬性に求めるため自身の誤りを認めるとその存在自体が否定されてしまう。それに対して科学は新しい発見を求め、本質的に自己修正する機関である。DSMが精神科医のバイブルであると言われたとしてもこのバイブル=聖書は自己修正できる点でカトリックの聖書とは大きく異なる。 第5章 決定 -民主主義と全体主義 民主主義とは何か。選挙は民主主義のための手段であるが民主主義そのものではない。多数派が少数派の人権を制限・剥奪できるというのは民主主義ではない。民主主義には複雑な意思決定メカニズムと自己修正メカニズムが備わっているが、民主主義という枠組みの中でさえ独裁者が全体主義的な意思決定を可能にするように試みることが一般的に起きる。特にメディア、裁判官、アカデミックは独裁者の主要な標的となる。 ポピュリズムとは何か。ポピュリズムの指導者はしばしば自分自身を国民全体の代表だと宣言する。 民主主義に必要なものの一つは選挙であるが、選挙が成り立つためにはまず国民に対する適切な情報と教育が必要であり、マスメディアが存在しない時代においてはそもそも数百万人などの大規模なコミュニティにおける民主主義は現実的に不可能であった。 同様に全体主義にも情報ネットワークの技術的な制限があり、独裁政権は必ずしも全体主義にはなり得なかった。皇帝ネロの時代には中央では強権的な独裁主義が行われたが、末端の市民にまでその権力を行使するネットワークがなかった。それに対してスターリンの時代にはその支配は全ての国民に及んだ。全体主義の支配の要は情報であり、国民は隅々まで張り巡らされた情報ネットワークによって統制された。それ故全体主義社会においては軍よりも秘密警察や諜報機関が大きな権力を持ち、しばしば軍の幹部や自身の機関の高官なども粛清の対象にした。 魔女狩りと同様に共産主義も仮想敵を作ることでその存在を正当化しようとした。資本者である「クラーク」を見つけ迫害することで政党の結束を持ち(罪の意識も含めて)人民の支配を行うことは理解できるが、そのような試みが中世の魔女狩りと同じ構造で20世紀に起こったという事実は歴史を考える上で印象的である。またスターリンによる家族の分割の試みとその結末は情報の統制が幼児教育と組み合わさったときに如何に悲劇的な結果をもたらすかを教えてくれる。 民主主義も全体主義も情報ネットワークによって可能になったが、民主主義が分散型のネットワークを推奨するのに対して全体主義は中央集権的なネットワークにより情報をコントロールする。中央集権的なネットワークは戦時や緊急時などに迅速な決断を伝えるには適しているが、重要な情報でさえしばしば遮断され、戦時に正確な情報が伝えられなかったり、チェルノブイリ原発事故の隠蔽のようなことも起きうる。 スターリン主義は多くの非現実や悲劇を引き起こしたが、全体の秩序を維持するシステムとしては機能的であり、実際に第二次世界大戦での勝利という結果も伴って複数の国家の運営モデルとなった。 全体主義か民主主義かという違いは情報ネットワークの技術的な問題によって決定されるわけではないというのがわかった。全体主義の中央集権的なネットワークは支配者の処理能力の限界により崩壊したとも言えるが、もしAIがその機能を補完する、もしくはAI自体が主体的に支配を行うような全体主義の体制は存在し得るのか?
0投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりにもおもしろく、そしてあまりにもおそろしい——。 本書は「情報」についての人類史を、上下巻にわたって深く考察している。 上巻では主にこれまでの歴史を、下巻ではこれからのAIについての考察が述べられている。 読み進めるうちに、手塚治虫の『火の鳥 未来編』が強く脳裏をよぎった。 AIがこれから加速度的に進歩していくことで、人類が制御できないおそろしい未来を想像せずにはいられなかった。 現在、国家の分断や陰謀論など、情報の氾濫により、私たちはAIのアルゴリズムによって何が正しく、何が間違っているのかの判断すら難しくなってきている。 この状況がさらに進むことで、個人のあらゆるデータを掌握する国家や地域こそが、これからの覇権を握ることになるのだろう。 著書には「シリコンのカーテン」とも表現されていたが、今後はデータ規制がますます強化され、国や地域によっては、より厳しい情報統制が行われる可能性もある。 非常に興味深い内容ではあったが、それでもなぜか明るい未来を思い描くことができなかった。 この10年こそが、人類の未来のキーポイントになると強く感じた。 私たちは、もっと互いに協力し、助け合う社会を築いていかなければならない。 争っている場合ではないのだ。
0投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻にまとめ https://booklog.jp/users/bam-boo/archives/1/4309229441#comment
0投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類を他の動物と分けたもの、それは「虚構を語る力」だった――ユヴァル・ノア・ハラリは『サピエンス全史』に続き「情報」という視点から私たちの歴史を読み解く。農耕、貨幣、宗教、国家、科学、デジタル。情報は時に支配を強め時に自由をもたらした。情報革命が進む現代、私たちは前例のない選択を迫られている。誰がどのような意図で何を伝えるのか。それを見極める知性と倫理が未来の鍵を握る。
0投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ知性と意識を分けるというのがポイントなんでしょうね。そして,著者は意識については語らない。 AI=Alien Intelligence
0投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報はあればあるほど良いものではなく、繋がりが大切、真実の伝搬と秩序の維持が大切とのこと。不可謬性、自己修正メカニズム、AIとの競合、大事なのは物語、自己修正の限界等哲学的で難しいところもあるが凄い良書だと思った。
0投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報は科学的な正しさではなくわかりやすさ広まりやすさによって世界を動かすのに使われる。大人数で会話をするテクノロジー基盤がなかったから民主主義は進まず全体独裁主義国家が中心だった。 みたいな話は面白かったけど7割くらいロシアとかの個別の歴史の話な気はして、それはそれでためになるのだがこの本に求めていたことではなかったので結構飛ばしながら読みました。下巻はITの文脈もたくさん登場しそうなので期待。
0投稿日: 2025.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自己修正メカニズム →聖典、カトリック教会、ソ連のような全体主義体制にはない →科学、民主主義にはある 世の中の体制には神話と官僚制が内在されている。神話は統治のために共同幻想を生み出す。官僚制は、秩序維持のために真実を犠牲にして、尺度の中に入れ込む。 ソ連は共産主義という神話、共産党や中央政府といった官僚制を両方持っていた(それも近代の情報テクノロジーにより秦朝の頃より強力な形で)。 しかし、アメリカなど民主主義国家に比べて自己修正メカニズムが脆弱だったため(マスコミや裁判所が無力化されている、全ての情報が中央集権的)、失敗してもそれを反省して修正する能力が低かった。それが20世紀における全体主義体制の敗北に繋がった。 では、21世紀はどうなるか? インターネット、SNS、AIといった最先端の情報テクノロジーが新たな可能性を提示する中で、20世紀同様に民主主義体制が全体主義体制を打ち負かすのだろうか?
0投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリさん2作目 ホモサピエンスが良すぎて、待ったなしに購読 過去歴史の全体主義をはじめとした前座のような本だった どうやら私がイメージしてるaiのお話は下編で来るらしい 温故知新ってマジだなと思わされた 内容は当たり前に無かった知識ばかりで、読んで良かった ただまじで1時間で30ページくらいしか読めなかった
0投稿日: 2025.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ知っていたようで知らない、我々の社会における、古代からの現代までの情報ネットワークについて、さまざまな視座、分析に富んでおり、大変興味深い。 情報とは?物語とは?文書とは? また、偶然にも参議院選挙という国政選挙の期間中にこの本を読めたことも、大変有用であった。 下巻にも期待する。
2投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ野放図なAIの発達は、最終的に、人命と生物圏の大規模な喪失や、人類の疎外あるいは絶滅にさえつながりかねない 21世紀には、20世紀の鉄のカーテンならぬ、シリコンチップとコンピューターコードでできた「シリコンのカーテン」が、分断を引き起こす。AIの軍拡は破壊力の大きい武器を生み出すので、破滅的な火災が起きる。 全体主義の悪夢の源泉は、中国やロシア、アメリカではない。人間は全て、AIの潜在能力に脅かされている。 AIは過去、人間が発明した「道具」ではなく、「行為主体」である! 後半のナチスとスターリンの戦い、ロシアでの全体主義の崩壊など、とてもわかりやすく書かれていた。 全体主義政権は秩序を維持するために、現代の情報テクノロジーを使って情報の流れを中央集中化したり、真実を抑え込んだりする。その結果、硬直化の危機と闘う羽目になり、効率的な支配になるはずが動脈が詰まり、ついには心臓発作が起きる!スターリンの死が良い例。
0投稿日: 2025.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
サピエンス全史以上の衝撃って紹介されてますが その通りです。 情報手段の歴史という切り口で石器時代から中世、近代まで綴られているのはある意味予想通りで 少し間延びした所もあります。 しかし最後の第五章の民主主義と全体主義の概史で作者が何を危惧しているのかが見えてからは一気読みでした。 これまで秩序に正義 道徳は関係なく、秩序を保つに少しの犠牲は仕方がないと考えでしたが、第五章で語られるスターリンの行動が国家秩序を保っていたというのはショックを感じました。 そして、これから人間でなくアルゴリズムが人間を支配し秩序を保っていくという事ですがその詳細内容は下巻になり更なる期待が膨らみます。
35投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AIの影響について考えるうえでクリアな視点を与えてくれる良書。 副題にあるように情報ネットワークの歴史からAIを論じている。プロローグと第1章で「情報」について整理し、第Ⅰ部の残りで情報ネットワークの歴史を詳説する。第Ⅱ部では新しいネットワーク(非有機的ネットワーク)の特質を検討し、第Ⅲ部で非有機的ネットワークの脅威と将来について考察している。これまでの人類の歴史と現在の政治状況を考えると悲観的にならざるを得ない。 <いくつかのポイント> ・AIは「Artificial intelligence」というより「Alien Intelligence」と考えたほうがよい。 →飛行機は鳥を超えるか、というのは無意味 ・物語の力→共同主観的現実 ・AIは常時オンのネットワーク(執拗さ)、可謬 ・アラインメント問題 →クラウゼヴィッツの「戦争論」~政治目標(最終目標)→戦略→戦術 ボストロムの「ペーパークリップの思考実験」 最終目標の定義~「義務論」も「功利主義」も決められない ・民主主義、全体主義ともにテクノロジーの進化によって可能となった ・コンピュータ政治 民主社会~デジタルアナーキー 全体主義~アルゴリズムによる支配 デジタル帝国、データ植民地 【原題】 NEXUS : A Brief History of Information Networks from Stone Age to AI 【目次】 プロローグ 情報の素朴な見方 グーグルvs.ゲーテ 情報を武器化する 今後の道筋 第I部 人間のネットワーク 第1章 情報とは何か? 真実とは何か? 情報が果たす役割 人間の歴史における情報 第2章 物語――無限のつながり 共同主観的現実 物語の力 高貴な嘘 永続的なジレンマ 第3章 文書――紙というトラの一嚙み 貸付契約を殺す 文書検索と官僚制 官僚制と真実の探求 地下世界 生物学のドラマ 法律家どもを皆殺しにしよう 聖なる文書 第4章 誤り――不可謬という幻想 人間の介在を排除する 不可謬のテクノロジー ヘブライ語聖書の編纂 制度の逆襲 分裂した聖書 エコーチェンバー 印刷と科学と魔女 魔女狩り産業 無知の発見 自己修正メカニズム DSMと聖書 出版か死か 自己修正の限界 第5章 決定――民主主義と全体主義の概史 多数派による独裁制? 多数派vs.真実 ポピュリズムによる攻撃 社会の民主度を測る 石器時代の民主社会 カエサルを大統領に! マスメディアがマスデモクラシーを可能にする 二〇世紀――大衆民主主義のみならず大衆全体主義も 全体主義の概史 スパルタと秦 全体主義の三つ組 完全なる統制 クラーク狩り ソ連という一つの幸せな大家族 党と教会 情報はどのように流れるか 完璧な人はいない テクノロジーの振り子 原註
0投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深く読めたのだが 著者さんがイスラエルの方だけあってキリスト教における情報の歴史部分ばかりでその部分が退屈だった 結局キリスト教は頭ではある程度理解しているつもりでも根本的なところがワシには解らない まあしかし人類の情報の歴史といったら西洋史が中心になるのは仕方ない 下巻のほうが面白そう
11投稿日: 2025.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報がいかに社会をつくり、支配し、壊すか 歴史を振り返ると、バカらしいことを命かけてやっている。 現代の「魔女狩り」は何だろ。 文春砲的な袋叩きも「魔女狩り」の一種かな。 スターリンの死に様が、哀れ。 倒れてもスルーされる最期って、かわいそうに。 スターリンのお母さん、どんな子育てしたんだろう。自分が母親になると、いろんな人のお母さんがどんな子育てしていたのか気になって仕方がない。 お母さんもスターリンが悪名高い人物になるなんて、思いもしなかっただろうな。 人間は、真実よりも、物語や幻に振り回されて生きているね。 お金だって、真実は、ただの紙やからね。日本通貨は、日本人に共通の幻想を浸透させた結果、大事にされるようになった紙。 世界からすると、信用高めの紙? 下巻は、 AIとネットは便利だけど、放っておいたらマジで危ないよ。ちゃんと賢く管理して生きていこう! って感じかな。 難しそうやけど、読んでみよう。
27投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1938940785325678700?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2025.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めてのハラリ。 読んでも難しい。情報のネットワークだからAIののこととか書いてると思いきや、歴史の話し。それも情報を切り口とした話し。基礎知識が豊富だともっと話しがわかるんだろうなと思う。 それでも魔女狩りやユダヤのところなど、人類の負の歴史は残酷さに胸を痛めた。そういった犠牲のもとに今の権利や考え方がある。 フォローさんの感想にオーディブルの方が増えてきて思い切って物は試しと契約するとNEXUSがあり、2.7倍速くらいで聴きながら読むとギリ、頭に入る。オーディブルないと寝落ちして読みきれないと思う。 そうこうしていると下ももうすぐ読み終わる。やはり下の方が面白い。 ここからは少し引用もある。 情報はつながりを生む。 従来の人間の発明はすべて、人間に力を与えた。決定権が人間にあったから。しかし、AIは意思決定できる。行為主体になる。 10歳の魔女のヘンゼル・パッペンハイマーと11歳のクラークのアントニーナ・ゴロヴィーナは、官僚が押しつけた共同主観的なカテゴリーに放り込まれた。 クラーマーの『魔女への鉄槌』 自己修正メカニズムという言葉がとにかく出た。情報はやっぱり補助である。それが全てになっていては危険。 AIをエイリアンインテリジェスと表現しているのは、非常に面白ろかった。 あとは記録のところ。出生届は当たり前だけど始まった年がある。ユダヤの歴史。生きていたのに届の記録がないから犯罪者だと認定する歴史。記録があるない、生きてきた歴史。それも人類が勝ち取った歴史。
46投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Audibleで。ハラリ本、新しい視点で人類史を見直してくれるので非常に参考になる。が、 一つの事象の証拠を延々と例示する「〇世紀のデンマークでは…」「そのあと、ドイツでは…」のはげんなり。 持って回った言い回しを解りやすい言い方に整理し、要旨だけ抜粋したら、一冊の新書版で収まるのではないか。分厚い本を上下セットで売りたい…というのはわかるけど。(2,200円×2+消費税で4,840円)サブスクのAudibleでないと手が出ません。 情報という切り口でテクノロジーの進歩をたどり、それに応じて権力者がどのように民衆をコントロールしようとしてきたか、をたどる。
0投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ本著(上)では、人類と情報の歴史から現代に至るまで複雑かつ高度に情報という存在の力と利用によって発展してきたと説く。最初はモノの場所や位置だけの情報だったのかもしれない。それが太古から世代を重ねて継承され続け、現代ではAIという存在まで発展するまでとなった。 世界はこれからも今までの歴史がそうであったように、今という歴史も後生でもどのような形であれ活かされ発展していくだろう。 さて、著者は情報は人類の発展に大きく寄与するだけでなく、情報という存在は身を滅ぼす存在であることの危険性と扱う人の責任について訴えている。AIの本質は情報という道具であり、それを扱うのは主体的に人間であるのだ。現時点(2025)ではAIという言葉で統一されているが、近い将来には違う名称になり存在も変様する可能性も多分にある。時には神格化したり妄想や幻覚の起爆剤や役割になるだろう。 情報は生き物であり、現代では新しい隣人である。その隣人という存在に対して、どう扱い、どう接し、どう関係を築くことが本質的には重要になるだろう。 AIは時に仮に私やあなたという人間への対等で一番の理解者になるかも知れない。だが、同時に情報という存在が本質的にどういうものか、人間である私たちも互いに理解し、主体的に関わることが必要だと私は思うのだ。
0投稿日: 2025.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AI懐疑論 上巻ではこれまでに著者が主張してきた物語の役割と、AI時代の変質について書かれている サピエンスは情報を利用して多くの人を結びつけ地球上で大いに発展を遂げた。しかし情報とは現実を表そうする試みであるが、それは必ずしも真実ではない。かつては魔女狩りで多くの人が殺され、近年ではナチスドイツやソ連のように誤った情報を利用して全体主義を構築した国家もあったが現代社会ではこれがより大規模、迅速になされるようになった。かつては神話と官僚制が情報ネットワークには欠かせなかったが今はAIがこれを行ないつつある。 ・宗教や聖典は不過謬であり、現実と聖典が異なっている場合は現実のほうが違うのだと主張する。カトリック教会やソ連は自己修正メカニズムを有していなかった。 ・物理の事実を無視して爆弾を作ったら、その爆弾は爆発しない。だが、事実を無視してイデオロギーを構築しても、そのイデオロギーは依然として爆発的な力を持つかもしれない。力は真実と秩序の両方を頼みとしているものの、たいていは、イデオロギーを構築して秩序を保つ方法を知っている人が主導権を握り、爆弾の作り方やマンモスの狩り方を知っているだけの人に指示を出す。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報の話に重点を置いた人類史、世界史といった感じで読み進めてました。 上巻のみ読了の状態だけど歴史の残酷さが出ているな……と思ったので下巻は読みたいと思いつつ世界史の勉強し直しはしたいところ。 結構ざっくり読んでしまったのでそんなに細かいところまでは理解してない。 興味が唆られた話題はいくつかあったから掘り下げたいテーマがいくつか見つかったのでその辺は良かった。
0投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間は賢い??にも拘わらず戦争をして、領土の奪い合い、殺し合いをしている。サピエンスが真に賢いのなら、なぜこれほど自滅的なことをするのか? その答えは、制御しきれないほどの力を生み出す、大規模な協力のネットワーク――「情報ネットワーク」――の歴史にある。といいつつ、「魔法使いの弟子」のアニメを引き合いに出す。魔法使いの弟子は水を汲んでおくように言われ、ほうきに魔法をかけて水をくませる、でも魔法のかけ方は知っていても、止め方を知らない。水がいっぱいになってとまらないのでほうきを斧で壊す、するとほうきは2本4本と別れて水をくむ。制御しきれない魔法で家は洪水になるという話。 このディズニーアニメはこんな比喩をふくんでたんだなと思った。
1投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報の人類史というだけあり、”情報の歴史”ではなく、人間が”どのように情報を活用してきたのか?”という視点で論じられた書籍です。 会話、記録、メディアとさまざまな形で”情報”が伝達されてきたが、情報伝達のスピード、内容とともに、自己修正メカニズムなどのポイントが複雑に絡み合って社会を構成してきたことを主張していて、読んでいて引き込まれます。特に興味深いのは、著者の徹底的に抽象化できる示唆深さだと思います。 例えば、中央集権的に情報統制を行うシステムの延長に独裁国家があるが、そのシステムはローマ法王を中心としたヒエラルキー階層がしっかりとしたカトリックにも共通している点があります。 一方で、民主主義は選挙で勝利した者に全体が従う必要はあるものの、多様な意見が出ることは否定しない。これは、自分で聖書を読むことを勧めたプロテスタントと類似しているというのです。 でも、だからと言って民主主義が良い、プロテスタントが良いという単純な議論でもありません。民主主義は全体に情報を的確に届けられる範囲でしか機能しないという拡張性の問題が共和国だった古代ローマを帝国に変えたと言った負の側面も書かれています。 また、プロテスタントは自分たちの聖書解釈だけが正しいとするローマ・カトリック教会を否定して始まったが、自分で聖書を読むことで多様な解釈が生まれたため、プロテスタントはカトリックと異なり分離を許容し、一枚岩になれない問題が構造的にあるというのもなるほどなーと感じました。 もう一つ興味深い話として、情報はストーリーの場合には強い力を発揮するが、ただの記録としての活用の場合には強い影響力を及ぼしにくいのがホモサピエンスの特徴であるということです。 著者のこの主張はサピエンス全史でもホモサピエンスが地球を支配できたのはストーリーの力だと主張していました。本書でもストーリーこそが”情報”の力をブーストさせる最大の力だったと主張していて、悪い言い方をすると、事実かどうかよりも心を打つストーリーかどうかの方が影響力があると主張しています。 下巻はAIについて論じていて、少し読んだがすでに期待通りの面白さで、今後読み進めるのが、とても楽しみです。
16投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10284479
0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻は、サピエンス全史のテーマだった「虚構」概念を「情報ネットワーク」として再定義し、情報ネットワークの広がりが政治体制にどのような変化をもたらしてきたかを概説した著作となっている。
2投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログやはりハラリさんの本は面白い!!! 情報についての新しい定義や、その危険性を信じられないほどの教養や歴史から語ってくれる。 ただ、サピエンス全史やホモデウスほどの脳汁が出なかったのも事実。後半はAIについて詳しく語られるらしい楽しみ - 情報は、人をつなげて一つに動かすもの - ストーリーの力がホモサピエンスの力 - AIは全く新しい技術革新(後半に続く)
5投稿日: 2025.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリの著書は、後から発行されるものほど少しずつ難しくなっている。サピエンス全史は人類の全体的な進化の歴史のことだったのでわかりやすかったのだが、ホモデウスは人間が神になる可能性について記述している。過去の歴史に比べて未来のことはわからないので、どうしてもリアリティが欠けてしまう。どうせかけるなら最初から虚構な物語の方が面白いのだが、ハラリはあくまで科学者として記述するためとっつき辛くなる。 この情報の「情報の人類史」は、今まで情報が人類を動かしてきた歴史を分析し、その情報処理能力はAIの方が人間よりもはるかに高い能力を持っている。そのことによってAIに支配される人類というリアルな未来を描こうとしている。そのために人類の歴史の中で情報は果たしてきた役割を論じている。オーディブルで聴いているため集中力が続かない。紙の本を買ってもう一度読まないと…
54投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類は大規模な協力のネットワークを構築することで途方もない力を確立するものの、その構築の仕方のせいで力を無分別に使いやすくなってしまっている。 情報は多ければ多いほど適切な判断ができると思われがちだが、これは正しくない。 情報は、真実の追求のためよりも秩序の維持に使われる
0投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリ節炸裂。 「敢えてネガティブな未来予想をする」 と前置きするだけあり、 不安な気持ちを膨らませる。 人類史、情報伝達手段の歴史、負の感情の歴史、政治についてが展開される。 上巻はAIは出てこない。
0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報をテーマに人類の歴史を紐解く 全体主義や民主主義、魔女狩り等は情報のネットワークが発達しt社会で実施可能となる。歴史を情報のネットワークという観点でとらえなおしている内容なので、歴史本として興味深く読める。
0投稿日: 2025.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ(上下2冊分をまとめて) ハラリの生成AIに関する危機感を彼のこれまでの人類史観を踏まえながら、整理したもの。 それほど彼の本を熱心に読んでいるわけではないけど、それほど新しい展開はないような気がした。面白い話、エピソードもたくさんあるんだけど、なるほどハラリだったそういうだろうなという感想です。 イスラエルのガザ攻撃の後に出版された本で、そのことについてもある程度の言及はあって、わりとニュートラルな感じながら、批判的な書き振りにちょっと驚いた。ある意味、イスラエルの中では一定の言論の自由はあるんだなと。イスラエルは、ある意味、こういう民主社会であるわけだが、その適用範囲が明確にあって、パレスティナ人にはその自由がない。ここの線引きの明快さがあらためて不気味なものに思われた。これはハラリの本の内容とは別の感想だが。
1投稿日: 2025.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AIが人間のネットワークに及ぼす影響について下巻dw論じるにあたり、前座として、これまでの情報ネットワークとその影響の歴史を振り返っている 人がつながる上での物語が持つ力、不可謬と自己修正メカニズム、民主主義と全体主義について、これまでの歴史を元に論じている 切り口として面白く、後半も楽しみである
1投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ『サピエンス全史』ほどの衝撃度には至らなかったものの、『NEXUS』は現代におけるAIと人間の関係を再定義する、刺激的な視座を与えてくれた一冊だった。 本書を読めば明らかだが、今後AIはOSレベルの社会基盤として組み込まれ、我々はアメリカ製あるいは中国製のAIが生成する“コンテキストの中”で生きることになるだろう。 しかし、それが全てではない。 日本には、依然として“文化的勝算”がある。 AIやロボットを「人格的存在」として受容し、関係性を築くという独自の感性は、既存のマンガ・アニメ・ゲーム・Vtuber文化などに明確に表れている。 ハラリが語るAI論が、西洋的自由意志と主観性に基づいているのに対し、日本的アプローチは、関係性や投影、アニミズムに根ざしており、“魂の立ち上がり”を人間とAIの間に見出す視座を持っている。 軍事・経済においては他国の後塵を拝するかもしれない。 だが文化的活用においては、日本人の変態的な創造性こそが、AI文明の倫理と美学を塗り替える鍵となる。 ちなみにこの文は私の素案をGPTに推敲してもらったものである。
5投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがの一冊ですが、政治システムの歴史や物語が人民におよぼす影響など、過去の振り返りが中心の上巻。今何が起きているか、これから何が起こるかを語るであろう下巻に期待しています。
0投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025/5/19読了 AI(人工知能)という、自ら考えることが出来る上に、おそらくヒトよりも賢いという、前代未聞の技術の発達に、我々ヒトはどう向き合えば良いのか? 上巻では、人類が情報技術をどう発達させ、良かれ悪しかれ利用してきたかの歴史を振り返る。情報ネットワークをどのように構築したか、誤情報の扱い(自己修正メカニズム)でどのような違いが生まれるかを説明し、情報ネットワークを可謬とするか不可謬とするかが、民主主義と全体主義の根本的な相違であり、換言すれば権力者が過ちを認め正すシステムが備わっているか、過ちなど有り得ないとして否定的なものを排除するかの違い(選挙が行われているかとかは関係ない)であるという指摘に至る。これらの情報ネットワークの歴史を踏まえて、下巻でいよいよ未来の、AIの話になるのだろう。 しかし、本書の趣旨からは外れるのだろうが、権力者が自らを不可謬だと言い張るのが全体主義的なのであれば、現在のアメリカ合衆国は全体主義陣営に足を踏み入れつつあると言えるのではないか……?
29投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史を紐解いて解説してくれるのはありがたい。情報量がすごい。可謬と不可謬、宗教と科学、全体主義と民主主義等の概念を丁寧に解説されている。AIの話は後半で。
0投稿日: 2025.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ・宗教と科学の違いは、自己修正メカニズムがあるかどうか ・民主主義政権と全体主義政権の競争から、アルゴリズムと人類の競争へ
0投稿日: 2025.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ流石の構成でした。人類の発展と情報、支配者の論理と要件を考えると実はAlが取って代わるのも近いかも、それに対抗するために人間が備えるべき条件を探索する。学習すべき内容が変わり、人間しかできないことを極めることというのは納得。 データ植民地帝国が始まる中で日本のあり方、教育はこれで良いのかという疑問が湧く。
10投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類(サピエンス)は虚構と噂話、物語によって栄えた。 情報は真実だけとは限らない。人間が作り出した虚構も皆に信じられ言い伝えられれば真実になり情報になる。 真実と虚構の均衡によって情報ネットワークが形成されてこの世界は成り立っている。 宗教や科学、民主主義と全体主義の異なる情報伝達を様々な事例を出して紹介してくれる。思い込み、勘違いや妄信、理不尽な独裁政権の下で起きる歴史的悲劇は本当に悲しいけど、情報によって発展した文明は素晴らしい作品も華々しい偉業や功績も生み出す。 夢中になって読めてしまえました。 下巻AI(Alien Intelligence )編へ続く、、
3投稿日: 2025.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報とは、点と点、人と人をつなぐもの。真実と現実、真実と秩序の関係の中で、ホモサピエンスがどのように情報によって社会を構築していったか。情報の素朴な捉え方である、情報はあればあるほど真実に近づくわけではない。ストーリー理解や文書、リスト、官僚制の発展や、印刷術をはじめとした情報テクノロジーの発展を経て、広く社会に情報が行き渡る社会で、民主主義や全体主義の、分散型か集約型か、などの類型が考察されている。そしてAIがそれにどのような影響を与えるのか、は次巻
2投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
情報とは「まったく異なるものを結びつけて新しい現実を創り出す。情報の決定的な特徴は、物事を表示することではなく結びつけることであり、別個の点どうしをつないでネットワークにするものなら、何でも情報となる。」そして、その情報ネットワークが人類の歴史をどのように作ってきたかを多くの歴史的な出来事を例に明らかにしていきます。 現在の民主主義も全体主義も、印刷技術やマスメディアの発見と進化の結果であり、それらが民主主義も全体主義も可能にしてきました。 第5章「決定-民主主義と全体主義の概史」は恐怖です。「要するに、独裁社会は強力な自己修正メカニズムを欠いた中央集中型の情報ネットワークだ。それとは対照的に、民主社会は強力な自己修正メカニズムを持つ分散型の情報ネットワークだ」とします。ところが、公正な選挙で選ばれた政権が、民主社会を簡単に強権的な独裁制、全体主義に変えていく様が描かれます。これは今から起こることではなく、これまで起こったことです。そして、現在の情報ネットワークはそのことをますます容易にしていることが明らかにされます。 「強権的な指導者が民主制を切り崩すのに使う最もありふれた方法は、自己修正メカニズムを一つ、また一つと攻撃するものであり、手始めに標的とされるのは、裁判所とメディアであることが多い」「典型的な独裁者は、裁判所の権限を奪ったり、忠実な支持者だらけにしたりするとともに、独立した報道機関を全て閉鎖しようとする一方で、自らのプロパガンダ機関を構築して至る所に浸透させる」「学術機関や地方自治体、NGO、民間企業は解体されるか、政権の統制下に置かれる」 これは「歴史」ではなく、いま起こっていることでしょう。そして、独裁社会や全体主義社会が民主社会に移行する際には壊滅的な悲劇がそこにあったことを私たちは知っています。だから恐怖を感じるのです。 下巻はどう展開していくのでしょうか。
7投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報というと近代の〜と思われがちだけれど、ノアの方舟から飛び立った鳩のくわてきたオリーブの枝も、メソポタミアの楔型文字も情報の大切なツールであり、人類の歴史は良い方にも悪い方にも大きく揺さぶられてきた。改めて世界史を見直す時、ヒットラーやスターリンの悪行が思いおこされる。 前の本の時も思ったけれどそもそも、日本人向けに書いているのではないから、しょうがないがわかりにくい部分も。あと、原註が煩わしく感じられる。
8投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はまず、「情報とは何か」という問いから始まる。この定義が曖昧であれば、その後の議論も不明確になる。著者ユヴァル・ノア・ハラリは、情報を「人類が協力し、社会を築き、歴史を動かしてきた根本的な力」と捉え、常にネットワーク(NEXUS)という関係性の中で意味を持ってきたものだと定義している。 文字の誕生や印刷技術の開発は、確かに情報の流通に変化をもたらしたが、その影響はまだ限定的だった。しかし、デジタル革命によってインターネットが登場し、さらにAIが加わった現代においては、情報の力は計り知れないものとなっている。 注目すべきは、これらの技術が民主主義だけでなく、全体主義体制でも利用され、強力な社会操作の手段となり得るという点だ。アメリカが混乱を深める一方で、中国やロシアといった権威主義的な国々が台頭する今、私たちは非常に複雑で不安定な時代に生きていることを痛感させられる。 本書は、情報を切り口に人類史を再構築し、現代と未来への警鐘を鳴らす知的刺激に満ちた一冊である。
1投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は「AI革命について、より正確な歴史的視点を提供する」ことをめざす。 著者の基本的な主張である「物語(間主観)の共有による多数の人間の協働が歴史を導いてきた」という考えを基盤に これの実現である情報のネットワークを視点に歴史と社会を分析している。 過去の活版印刷、ラジオ、電信などの技術革新は、すべてこの情報ネットワークの変革を起こし、 社会福祉を良い方向に変革するうととも、当代の専制主義や全体主義の大規模化を助け悲惨な結果を招く一助になったとする。 AI革命はこれらの流れで同様に情報ネットワークに関する変革となるが、情報の流れる方向や内容自体をアルゴリズムが握ることで質的な違いがあるとする。ただ、この革命自体は抑えがたいため、核管理になぞらえ、政府などによる技術管理の必要性を主張している。 また、どんなに高度になったとしてもAIは異知性である原理からアラインメント問題をもっており人間からみた誤ることが避けがたく、学習データに起因するバイアスを潜在的に持ってしまうということに警鐘を鳴らす。 また、社会体制としては、民主主義と専制主義、全体主義を比較して分析している。特に、これら社会体制の比較において、その体制の特徴として可謬性(専制主義や全体主義は構造的に不可謬性を持つ)の有無を差異のキーコンセプトとして分析している。 社会体制について著者の主張としては、大勢の力を合わせる意味で専制主義や全体主義がうまく働くケースは確かにあるが、安定的には、どうしても誤ることのある人間に対して、社会の可謬性をどう維持、実現するかが重要としている。そして、AI革命の視点では、もし社会全体が高度AIに依存したとしても、そのAIも誤る可能性を排除できないことを具体例で述べている。 ここで、歴史から見たときAI革命以後には、専制主義や全体主義社会では、より強い情報ネットワーク管理への動きが抑えがたく生まれるはずであること予言している。さらに、今後、AI先進国中心にデータ植民地主義的な動きが強まり、エリア別のデータ利権確保する帝国群の出現も預言している。 過去の悲劇を再現させないためには、情報ネットワークが一点に集中せず分散することが必要であり民主主義的な社会体制が望まれるとする。 特に、不可謬性をもつ社会体制が生んだ悲劇であるスターリング主義の虐殺、魔女狩りなどの歴史から、技術進展にともない悲劇が大きくなってきていることを示し、AI革命以降の歴史の悲劇は、人類種全体への危機となりうることを強調し、このAI革命を、人類種の次のステップとするか惨劇とするかは、我々次第として結んでいる。
6投稿日: 2025.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリ氏の本はめちゃくちゃ面白い。 テーマ設定、章の展開、具体例とその解像度、言葉選びの全てが秀逸。そして読者を誤解させない注意喚起も怠らない(本書では、全体主義が必ず失敗する形態ではないとの注意喚起が特に重要だった)。 かなり難しいテーマだが、一般読者をしっかり惹きつけてページを捲らせる筆の巧みさは流石の一言。 また、読者に人類のこれまでとこれからを見通す上で極めて重要な考え方と問いを投げかけてくれてもいる。必読の一冊。
2投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の知の巨人が描く、情報の歴史と力を書いた本書は、非常にボリューミーながら冷静かつ公平な目線で情報をとらえていることから過度にある一定の感情論などに寄っていないところが非常に良い。知とは、まさにこういうことなんだと痛感する。 AIについては、人類への負の影響はほぼないという論理と、人類の分断や生態系破壊などを引き起こすと警戒する。AIは行為そのもので、ツールではない。情報からある一定の判断を下していくからだ。当然、新しい生命体を産み出すこともできるはずだ。これが、恐怖の対象でもあり、統制論者が出てくる所以でもある。また、人類が戦争を繰り返し、コロナをはじめとする敵と考えるウイルスを生み出してきた。自己破壊行為をなぜ引き起こし、人間とはどういう状態が幸せか、どういうふうになりたいか、がわからない今こそ、その原点に立ちかえるべきと説く。そこに、情報が集まり、情報を持つことで、判断を過たずに済むではないかと問いかけてくる。指導者が、神の使者として人々を導くことで嘘を暴き、全て正しい道へ進んでいくという宗教の教義は、トランプなどカリスマ的指導者にも当てはまっていく。情報が大事だとしておきながらも、一人の人間に委ねるのはなぜだろうか、と疑問を呈している。情報とは、各人にあるからこそ、持ち寄り多く集め、その中から叡智を絞ることでそのファシリテートにこそ最強の情報という力を持ち得るのではないか。 歴史を振り返ると、情報が透明性を持って伝わりきらないテクノロジーの不足のために、虚構と人が信じたいものを組み合わせて人を導く指導者が現れた。そこでは、物語が大事であり、この十戒などの虚構のストーリーを人々が信じることで大きな力を産んできた。オッペンハイマーの原子爆弾も13万人の人々が協力してこの物語について行ったとされている。情報が年度版に傷をつけることで始まったものであるが、紙が生まれ、記載された情報が大事になる。税の取り立てがとりわけこのリストを生み出したとされている。いずれにせよ、ここまでで保存ができる情報が存在したことになるが、一方で検索に難がある。生き字引という言葉があるように、この人に聞いたらわかるという人が重宝された。そして、これを可能にしたのが官僚制である。司法、メディア、そして執行という3つの機能がお互いを牽制し合い、嘘や欺瞞、癒着を止めることで健康的な情報の提示と活用が可能となる。エルドアンなどの専制的な指導者はこれらの機能に圧力をかけ破壊している。例えばソ連では、スターリンが絶対で、反対するのではなく、スターリンに忠実にするのでもなく、とにかく子供に黙っていることを教えたとされる。密告と社会主義、資本主義の排斥と排除により、正当化していく政府の姿だろう。 さらに、聖典と呼ばれる宗教における物語を、口頭ではなくレプリカを可能とした形で情報を展開していく術を持った宗教が出てきた。経典があれば、絶対的な道を外さないものであるからであり、矛盾が起こらないはずだ。相当一般的に、かつ解釈によって如何様にも取れるのがポイントで、一気に宗教を広げることができる。これは、物語をどのように絶対化して人々に伝えられるか、というものだが時として間違っていたり、そもそも物語が矛盾を持っていると信頼に値しなくなってしまう。シナゴークに1冊ずつ置かれた聖なる文書はいかなる改竄も許さない、ブロックチェーン型の管理だったと分析する。写経している人には、一文字でも間違えば天罰が降るとされているが落ちたことはない。魔女狩り、女性蔑視の考え方もキリスト教的な、決定、これが正しいこととする考え方に基づいている。非常に危険だ。いかにして情報を正確に把握して、叡智を絞るかによるということだ。とすると、脱線するが一体どうすれば世の中が良くなるのか、それは叡智を集め直すということだろう。そして、叡智を集めた先に、AIとは別にして、改めて知恵を使うということだ。世界の賢人の集まりを開催して、アジェンダを作っていったらどうだろうか。
1投稿日: 2025.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリさんの本はよく読みましたが、今回もめちゃくちゃ面白かったです。 著者は、歴史学者として、過去からの変遷と、AIが変える未来に警鐘を鳴らしてします。 コミュニケーション能力と情報を選別する力が大切だと思いました!
9投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログサピエンス全史で有名な著者の新作。 情報ネットワークがどのように機能するか、情報は多ければ多いほど真実に近づくのか、行動主体となり得るAIが情報収集を始めたときに何が起こるのか…。
1投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間社会において情報が本質的にどのような機能を果たしているか、いくつかの社会体制の大分類がそれぞれ情報をどのように扱っているかについて、著者の豊かな歴史の知見に基づき整理されていた。本書の核心部分は飽くまで下巻であり、上巻ではそこに向けた基礎の整理がなされていた印象だが、そんな中でも著者特有の知的ユーモアがふんだんに散りばめられて読み応えは期待どおり抜群だった。星5つ。 以下、概要をまとめる。 情報とは現実を表現しようとする「試み」である。 とにかく情報を充実させれば真実に近づき世の中は良くなるとの楽観的で素朴に見る向きもあるが、著者は、印刷技術の発達が魔女狩りの大規模化と凄惨化につながった例を上げて反論し、一方で、人間社会の本質は物質であるとして情報を副次的な存在と軽視する唯物史観に対しても、情報が意思決定や社会体制の構築において決定的な役割を果たしてきた事実を列挙して反論する。 つまり、情報は真実を表すとは限らないが、真実でない情報が力を持たないというわけでもないということだ。 情報の本質的な機能は、真実の伝播と秩序の維持の2つであるが、両者は相反する作用をもつことが多く、両立困難であるため、両者のバランスをどうとるかが歴史上常に課題であった。 かつては聖書が多分に現実に反する内容を含みながらも、物語の持つ力によって秩序維持に絶大な力を発揮した。さらに官僚制が物語以外の部分において重要な機能(税や貸借などの直感で記憶しにくい共同主観的現実の運営)を担った。聖書は不可謬を前提としているくせに嘘と誤りを多分に含むため、現実との不一致に常に悩まされ、それをうまく解釈する官僚達が結果として社会のルールを左右できることとなり、権力を握った。一方、その後に現れた科学は、可謬であることを前提に置き、強力な自己修正メカニズムを備えたため、真実の探求において極めて高い成果を上げた。 前者は秩序の維持において、後者は真実の探求において機能し、たまにこれらが衝突した時は概ね前者が優先された。 ここで著者は、社会の情報の扱い方や情報との向き合い方を捉えるうえで、打ち立てた物語や規則の可謬性の有無と、自己修正メカニズムの強さという評価軸を提示した。 次に、人間社会の体制の歴史だが、狩猟採集時代は民主的な社会がほとんどであったと思われるが、社会規模が拡大するにつれ民主的に意思決定するための技術が決定的に不足していたために権力者が全てを決める独裁体制が主流となった。その後、印刷、ラジオ、鉄道などの技術の進歩に伴い、民主的に意志決定する民主主義と、独裁体制を追求した全体主義という2つの選択肢が生まれた。 この近代以降の2つの社会体制について、著者の評価軸で捉えると、民主主義は分散型の情報処理を行い可謬を前提として強力な自己修正メカニズムをもつ社会(民主主義の本質は決して多数決ではなく、少数派の人権と公民権を政権が保証するところにある❗)で、全体主義は中央で情報を集中処理し不可謬を前提として自己修正メカニズムが弱い社会である。前者はレジリエントな社会を構築できるが非常時に秩序が揺らぐリスクを孕み、後者は非常時にも極めて効率的に統一された動きをできる秩序を維持できるが誤りの可能性や変化に対して脆弱である。 この両陣営の競争は、1960年代の混乱で民主主義が収束に苦戦する中で全体主義が比較的首尾よく乗り気ってみせたものの、その後の消費者の嗜好の変化と技術の変化に対して分散型情報処理ネットワークの民主主義が概ね対応できた一方で全体主義の情報処理を一手に担う中央の長老達がこれに対応できなかったことをもって、民主主義が勝利を納めたかに見えた。 しかし、AIという新たなゲームチェンジャーの登場で競争の行方は再びわからなくなり、むしろこの両陣営のどちらでもないAIそれ自体が勝利するかも知れない不穏な予感を漂わせて上巻は幕を閉じる。 サピエンス全史から続く、虚構を構築して大規模に協力するネットワークを形成する力がホモサピエンスの強力さの源泉であるとの著者の主張を、情報と「ネクサス」(つながり)の観点からとらえ直したもので、これまでの著作に比べて、上巻では真新しい内容や驚きは少なかった印象だが、下巻を読み込むための前提知識を整理する巻として非常に有意義であった。
3投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO88293250V20C25A4MY6000/
1投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ホモサピエンス」程のインパクトはない。中世から近代の歴史を”情報”といった観点で切り込んだ内容。情報がどのように広がるようになり、どのように、扱わられ統制されてきたかを紐解いている。 情報は真偽を定めるものではなく、人や物事を結びつけるものとしている。 魔女狩りのように嘘も人が信じれば正しいことになってしまう。貨幣も同じ事だと。紙とみるか紙幣とみるか。 独裁制や教会とかは不可謬(間違えをみとめない)だと。地動説や進化論を認めなかったのが例かなと。自己修復が出来ないとそうなる。
1投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報は、素朴な見方では、情報が多いほど真実を知ることができるとか、あるいは、陰謀論的に情報を持っていることは力だと考えられたりする。 本書では、情報は人のネットワークを作るもの、つなげるもの(ネクサス)と定義され、 まず前半では、これまでの情報が歴史の中ではたしてきた役割が述べられる。 (このあたりは『サピエンス全史』の虚構(物語)を共有することがサピエンスを発展させてきたという内容につながるところだと思う。) 民主主義と全体主義の違いも、情報のネットワークが分散しているのか、集中しているかの違いで説明されていたのが面白かった。 後半では、AIがどのような影響与えるのか、前半の情報はネットワークをつくるものという議論をベースに述べられる。 これまでの人類歴史では、ネットワークの中で文書が人と人の間の媒介になることはあってもプレイヤーになることはなかった。これまで人類だけだったプレイヤーに、これからは新たにAI(アルゴリズム)というプレイヤーが参加することになる。 しかも、これは人間とは違った知性なのだから、どのように影響してくれるか? 人間が意図していないやり方をしてくるかもしれない。 本書で、AIは「Artificial Intelligence」よりも、これからは「Alien Intelligence」というべきかもしれないというのが、そのことを印象づけてくれた。 AIについて楽観的な議論も多いし、無知からくる恐れも多い。 きちんと知りつつ悲観的な議論がなされているので、バランスとりの意味でもいいかもしれない。
10投稿日: 2025.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻は言語や印刷などのメディアがコミュニケーションを発達させ社会をいかに拡張してきたかが書かれる。この辺りはcotenradioの科学技術の歴史とセットで読むとさらに理解が深まる。
2投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログその危険の大きさを踏まえると、AIは全人類の関心事でなければならない。誰もがAIの専門家になれるわけではないにしても、私たちはみな、AIが自ら決定を下したり新しい考えを生み出したりすることのできる史上初のテクノロジーであるという事実を肝に銘じるべきだ。(中略)AIはツールではない――行為主体なのだ。(p.21) まず、AIについての話す立ち位置をこのように設定し、それまでの「情報」についての歴史を追っていく。データを見つけて処理する能力が生身の官僚よりもあるというのはそうとして、ほとんどの人間よりも物語をつくり上げる能力も獲得しつつあるということで、情報処理に限らないところまで来つつあるということらしい。そこが文書を複製する機能に留まる印刷機の発明との大きな違いだ。 聖書やコーランなど、聖典の解釈のずれの話は面白かった。 「安息日に労働してはならない」と書かれていても、何をもって「労働」となるのかは分からない。聖典の外側の世界の変化に耐えられなくなってきた時に、典拠としながらも解釈を考えることになる。雁字搦めなのか柔軟なのかわからなくなる。 かつての「情報」であったこうした内容とAIがどのように異なり、どのような使われ方をしていくのか。こうした問いをベースに下巻に続く。
2投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログハラリ大先生の新刊、ちょっと面白すぎた。 『サピエンス全史』にも通じる「情報史」を綴った内容で、歴史を振り返るのが前半、未来を語るのが後半という構成。そして、これからの情報史を語る上で避けて通れない主題が——やっぱりAIだ。 つまり、AIによってもたらされる課題を、人類史(情報史)の観点から予測するというアプローチ。 「情報」というものが人類史の中でどう扱われ、どう伝達されてきたかを振り返り、その土台の上でAIのインパクトと向き合う。 まさに、「賢者は歴史に学ぶ」ってやつ。 AIがもたらす未来、と言っても「仕事が奪われる/奪われない」みたいな話ではなく、もっとスケールがでかい。 「人類という種が、これからどうなっていくのか?」って話。 人類は、「同じ幻想を共有できる」という超特殊な社会性によって繁栄してきた。 そこから生まれたのが「民主主義」と「全体主義」。 どちらも、全人類に同じ幻想を見せるには至らず、未完成で課題だらけ。 そしてその課題が、AIの登場によってどう変わっていくのか——その未来像が語られている。 もう、めっちゃスケールでかいし、エキサイティングすぎた! なお、ハラリ大先生ほどの知性を持ってしても、最終的には 「これからは変化し続けるしかないよね」 という、めちゃめちゃ“凡”な結論に行き着くのが、軽く絶望させてくれる。 AIという「人類より上位の知性」が生まれてしまった今、ハラリほどの知性と僕ら凡人の差は丸められちゃうのか…。 まあでも、絶望したって仕方ない。 やっぱり僕らは、「変化し続ける」しかない。 そしてその“変化すべき範囲”は、この本を読む前に想像していたよりもはるかに広い。 「変化」の可動域を、極限まで広げなきゃいけない! というわけで、この本はきっと—— 「変化の可動域を広げるための、思考のストレッチ本」なんだと思う。 痛気持ちいいくらいの強さで、しっかり伸ばして行こう
2投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻読了。 人類と情報の関わり方とその影響、情報管理の変遷を歴史に沿って解説してくれている。本著では昨今の分断やポピュリズムにも触れ、情報がどれほど人類の思想や行動に影響を与えているか気づかせてくれる。間違いなく自分にも当てはまることであり、納得感と自戒の念が押し寄せる。緻密なロジックと豊富な事例が内容に厚みを与えているが、それにより多少冗長な印象も受けた。ただ主張が明確なため迷子にならずに読めることができる。 前半の「物語」パートに本著のエッセンスが詰まっている。近現代に近づきデジタルやAIが与える影響をどう解釈するかは期待が高まる。
2投稿日: 2025.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ前後半含め。 ホモデウスに比べて面白くない。眠い。 前半の終わりかけからようやくゾーン的になってきたが。 ホモデウスみたいにぶっ飛んだ話ではなくAIへの懸念や問題点を延々と語っている。 AIへの懸念などについては他の人も喋ってることと被るので著者の独自性を発揮するに至ってないかなと。情報の歴史と言う面ではオリジナリティあるんだろうけど、全体として、これまでの著作よりオリジナル要素が少なめ。 冗長で量が膨張。1冊なら満足度高まったかもしれないが、2冊でこれだと高評価はつけにくい。
1投稿日: 2025.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジーは情報の流通に寄与するが、情報の流れ方を決めるのは人間自身であり、それが民主主義と全体主義を分けるという趣旨の本。 スパルタや秦王朝も全体主義の発想はあった。しかし、情報技術の不足により完全に実現することはなかった。 人間の考えることは時代を超えて変わらなくとも、技術によって世界の形は異なるものとなる。このことは技術革新が起こるときは過去の失敗が形を変え再び起こりうることを意味する。 情報という眼鏡を通して、歴史の推移を眺めた本であった。
2投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報→真実→知恵&|or力。だけではない。 情報→秩序→力のノードもある。 可謬という認識と自己修正メカニズムが科学の発展を促した。 ただし、秩序を求めるさいには不可謬なものを仕立てていくことが有用なことも。それが神話であり、ヒトラーであり、宗教。 単純な善悪二元論や、直接かつ単一の因果関係で世界が成り立っているわけではない。という著書のスタンスが、考える際の大変重要な学びである。
2投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ中世の魔女狩りは社会不安の解消装置。情報を統制し、魔女をでっち上げ、抹殺 →今のフェイクニュースやSNS炎上と同じやん 全体主義、民主主義の情報の扱い方の違いが興味深かった そしてAI時代、人間は情報統制を放棄するのか? 下巻は更に期待!
2投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報テクノロジーがもたらすもの。 上巻は、主題に入るための前提を整理。 ・客観的現実と主観的現実の他に、サピエンスは物語の力によって共同主観的現実を持ち得る。 ・これにより、集団を維持し大きな力を発揮できる。 ・情報ネットワークは真実を最大化するわけではなく、むしろ真実と秩序のバランスを見つけようとする ・官僚制と神話はともに、秩序を維持するのに不可欠であり、どちらも秩序のためなら喜んで真実を犠牲にする ・無知を発見した科学の可謬性が担保する自己修正メカニズム 一方、秩序を担保する別の機関が必要 ・選挙は真実を発見するための方法ではない。むしろ、人々の相反する願望を裁定することによって秩序を維持する方法 ・だが、選挙で提示されるべきでない選択肢が一つだけある。それは、真実を隠したり歪めたりするという選択肢だ。
1投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書について一言で表すなら、AIに対する警鐘だと私は思う。 AIはこれまでの技術革命と違い、人間とは異質な知能(エイリアンインテリジェンス)が意思決定できる点でリスクを伴うと述べていた。 難しい内容が多く、私がAIに対して肯定的なスタンスのためそこまで響かなかったが、読み物としては面白かった。
1投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ上下巻一気に読みました。 情報とは何かについて、とても興味深い視点を得られました。 人類史をふまえて語られるハラリさんの作品は、いつもスケールが大きく、そして論じる、私たちに必要な行動につなげる、というところも、とても読みがいがあります。
1投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログサピエンス全史を読んだ時の感動はなく、同じような内容を文脈や構成を変えて再構築した印象は否めない。 人類の統制の鍵となる『情報』の形が大きく進化する中で今後社会はどう変化するのか、テーマとしては非常に面白いと思う。
2投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 ユヴァル・ノア・ハラリの新作『NEXUS』は、AIを含む「情報」と「情報ネットワーク」について歴史学的視点から論じた書だ。ハラリはかつて自身の著作『ホモ・デウス』で、人間社会を構築してきたのは、サピエンス自身よりもむしろサピエンスが創造した物語、概念といった「情報」によるものが大きいと論じており、これからの新しいテクノロジーが社会にもたらす危険性を示唆していた。 本書『NEXUS』は、今までのハラリの提言の中から特に「情報」にスポットを当てて書き下ろした本だと言える。『NEXUS』の上巻では、人類史において情報はどのような役割を担ってきたのか、また、情報を完全に掌握しようとする政治体系である「全体主義」が歴史上どのようなタイミングで現れ、その時の権力者はどのような方法で人々を統制していたか、などについて語られていく。 まず人類社会の初期段階である原始時代や農耕時代において、情報は「物語」や「文書」という形で、サピエンス同士を結び付けることに成功した。サピエンスは宗教や国家、法律、貨幣といった「共同主観的現実」を信じることで、見たこともない、会ったこともない人々と紐帯していた。これがコミュニティにおける構成員の数を爆発的に増加させ、サピエンスが他の生物を支配する決定打となった。 その後、情報は社会の発展とともにその数を増していった。しかし、情報が増えていくにつれ、検索性は低下していく。この困難を解消し、情報の取っ散らかりを上手くまとめあげた仕組みが、官僚制である。官僚制は、現実の情報を画一的に整理して、社会を秩序付ける重要なシステムだ。官僚制は公共サービス等を提供し、社会が円滑に回ることを可能にする。 だが、官僚制や物語は、秩序のために真実を犠牲にする傾向がある。現実は概して複雑であるが、それを分かりやすく単一的にまとめることで、社会制度が維持されていく。当然、単一化にあたって世界の様相は実態と違った形に歪められていく。 そうした官僚制の歪みが最大限に発揮されたのが、全体主義、つまり独裁制である。全体主義下においては、情報はすべて中央に吸い上げられ、そこで権力者の意向に沿った形で出力される。歴史を紐解いてみると、実は民主制よりも独裁制のほうが長い。完全な民主制のためには情報の透明化が必要であるが、そもそも人民が十分な情報を得るためには、テレビやラジオ、新聞、インターネットといったテクノロジーの発達まで待たなければならなかったからだ。 では、インターネットが発達してあらゆるものが結びついた今は、民主制の黄金時代なのか? ハラリに言わせれば、それは大きな誤りだ。そもそも情報の多さ=透明性の高さではない。データはあくまで「現実の一面を切り取った事実」に他ならず、それをどのように意味づけるか/活用するかはシステムの構築者次第になるからだ。そこには誤情報を流す人間、偽情報を利用して利益を得る人間、そしてテクノロジーの力を悪用して新しい全体主義を目論もうとする人間など、様々な障害が待ち受ける。 最近勢いを付けているAIについても、その危険性は計り知れない。人間はAIが行っている処理や創造する成果物について、正誤/善悪の判断ができるほど賢くはない。人間は自らの手に余るものを利用し続けているのだ。 AIの進化が臨界点を超えた先には、いったい何が待っているのか?今までの社会は民主主義vs全体主義という、人間同士の争いであった。それが、人間主義vs AI主義という新たなフェーズに突入するのではないか?そのときにAIは、民主的な自己修正メカニズムをもたらしてくれるのか?それとも情報ネットワークから人間の存在を抹消し、新しい秩序のための全体主義を構築していくのか? こうしたリスクが、まさに今、水面下で発生し始めているのである。 ―――――――――――――――――――――――――――― 以上が上巻のおおまかなまとめだ。 上巻を読んだ感想だが、主張のあれこれを歴史的事実に結びつけようとして、だいぶくどくなっている。大量の歴史雑学に、本筋がおまけのようにくっついている状態だ。未来への類推のために歴史の深掘りも必要であるが、「流石にここまで厚く書く必要はないんじゃないか?」と思えてしまった。 といっても、上巻は物語と文書のルーツ、政治制度の歴史など、いわば今までの人類史と情報史をおさらいするための本であり、こうした構成は仕方のないことなのかもしれない。下巻以降は、現在と未来、特にAIという新たな可能性(危険性)が、民主主義と全体主義という旧来の権威のあり方を根本的に変えうるかもしれない、という話が始まってくる。これからに期待しよう。 下巻の感想 https://booklog.jp/users/suibyoalche/archives/1/4309229441 ―――――――――――――――――――――――――――― 【まとめ】 0 まえがき 私たちホモ・サピエンスは、過去10万年の間に途方もない力を身に着けた。しかしながら、その力を誤用するあまり、生態系崩壊の危機に瀕している。 私たちは自らが制御できない力を手にし、それを濫用している。この傾向は、個人の心理ではなく、私たちの種に特有の、大勢で協力する方法に由来する。人類は大規模な協力のネットワークを構築することで途方もない力を獲得するものの、そうしたネットワークは、その構築の仕方のせいで力を無分別に使いやすくなってしまっている。私たちの問題はネットワークの問題なのだ。 「情報は本質的に良いものであり、多ければ多いほうが良い」というのが、情報についての素朴な見方である。だが、私たちは大量のデータを貯め込んだというのに、相変わらず温室効果ガスを大気中に放出し、海や川を汚染し、森林を伐採し、さまざまな生物の生息環境をまるごと破壊し、無数の種を絶滅に追い込み、自分自身の種の生態学的な基盤を危険にさらし続けている。そしてまた、水素爆弾から人類を滅亡させかねないウイルスまで、ますます強力な大量破壊兵器も製造している。 いっそう多くの情報を手に入れれば、状況は良くなるのか?それとも悪くなるのか? 無尽蔵のデータを内包したAIは世界を救うのか?それとも人間同士の分断を煽るのか? あるいは、人間そのものを支配するに至るのか? 1 情報とは何か 「情報」という言葉を一意に定義することは難しい。情報の素朴な見方によれば、真実を探し求める状況では、現実の特定の面を表すものは「情報」と定義できる。別の言い方をするなら、情報は現実を表す試みであり、その試みが成功したときに、情報は真実と呼ばれることになる。 真実とは現実の正確な表示であるという主張には、本書は同意する。ただ同時に、本書は以下のようにも考える。ほとんどの情報は現実を表す試みではないし、情報はそれとはまったく異なるものによって定義される。人間社会の情報の大半は、いや、それどころか他の生物系や物理系での情報の大半も、何も表してはいない。 情報は現実を表さないのは何故かというと、現実には数多くの見地があるからだ。「1万人の兵士」という言葉は、現にそこに1万人の兵士がいたら現実の特定の面を正確に指し示しているが、その1万人の中に古参兵や新兵がどの程度いるのかを具体的に述べることは怠っている。歴戦の兵が1万人いることと、傷病者を含めた新兵が1万人いることの違いを比べれば、戦争における「現実」は全く異なる様相を呈するだろう。 要は、現実は1つしかないが複雑であり、情報はいつも現実の不正確な表示にならざるをえないということだ。 情報のそうした不完全な側面は、「誤情報」――現実について取り違えた情報や、「偽情報」――故意の嘘によって現実を歪めた情報を招く。 情報の主な仕事は、現実を正確に表すことではない。さまざまな点をつなげてネクサス(結びつき)を作り、新しい現実を創り出すことだ。聖書は人類の起源や移動や感染症にまつわる現実を正しく表示できていないのにもかかわらず、じつに効果的に何十億もの人を結びつけ、ユダヤ教とキリスト教を生み出した。 したがって、歴史における情報の役割を考察するときには、「どれだけうまく現実を表しているか?正しいか、それとも間違っているか?」と問うのが理に適う場合があるものの、より重要な問いは「どれだけうまく人々を結びつけるか?どのようなネットワークを新たに作り出すか?」であることが多い。歴史においてサピエンスが世界を征服したのは、情報を現実の正確な地図に変える才能があったからではなく、情報を利用して(ときには嘘や誤りで)大勢の人を結びつける才能があったからだ。 2 物語の力 物語はサピエンスに新しい種類の連鎖を与えた。人間と物語の連鎖だ。サピエンスは、協力するためには互いを個人的に知らなくてもよくなった。同じ物語を知っているだけでよかった。そして、その同じ物語は、何十億もの人に馴染み深いものになりうる。それによって物語は中心的な接続装置のような役割を果たすことができる。無数の差込口がついていて、無数の人が接続できるわけだ。たとえばカトリック教会の14億の信徒は、聖書やその他のキリスト教の主要な物語によって結びつけられているし、14億の中国人は、共産主義のイデオロギーと中国の国民主義によって結びつけられている。そして、グローバルな交易ネットワークに属する80億の人は、通貨や企業やブランドについての物語で結びつけられている。 人は物語によって、今まで有していた2つの次元の現実――客観的現実と主観的現実に、あらたな次元の現実である「共同主観的現実」を作りだした。法律、神、国民、通貨、企業などがそうだ。共同主観的なものは、大勢の人の心を結ぶネクサスの部分に存在し、情報の交換がそれらを創り出した。共同主観的現実は何千人、何万人ものヒトを結びつけ、協力関係に置いた。 虚構が歴史で果たす重要な役割を理解すると、情報ネットワークについて次のことがわかる。人間の情報ネットワークはどれも、生き延びて栄えるには、真実を発見し、しかも秩序を生み出すという、2つのことを同時にする必要があるということだ。一方では、情報のより正確な理解と処理の仕組みを構築する必要がある。もう一方では、正直な説明ばかりではなく虚構や空想、プロパガンダ、そしてときには真っ赤な嘘にも頼り、大勢の人々の間でより強固な社会秩序を維持するための情報の利用方法を構築する必要がある。 人間の情報ネットワークはしだいに強力になったが、同時に知恵を欠いた無分別なものにもなっていった。それは、この2つの仕組みが理由なのだ。 3 文書 物語にさらなる力を与えたのが文書だ。文書は、物語と違って、人々の心を動かすほどの熱を帯びてはいない。ただ起こったことを淡々と表記するだけだ。しかし、文書が財産や税や支払いのリストを記録してくれたおかげで、行政制度や王国、宗教団体、交易ネットワークを生み出すのがはるかに楽になった。より具体的に言えば、文書は共同主観的現実を創出するための方法を変えた。口承文化では、共同主観的現実は、多くの人が口で繰り返し、頭に入れておける物語を語ることで創り出された。したがって、人間が創り出せる種類の共同主観的現実には脳の容量という限度があった。人間は、脳が記憶できない共同主観的現実は創出できなかった。この限界を、文書が乗り越えたのだ。 しかし、文書が増えてくると新たな問題が生じた。検索性の低下である。情報の量が増えていくにつれ、それらを整理し情報ネットワークとして利用できるように秩序立ててやる必要が出てきた。その秩序のことを、官僚制という。 官僚制は、大規模な組織の人々が検索の問題を解決し、それによってより大きくより強力な情報ネットワークを作り出すにあたって採用した手段だ。官僚制は公共サービスを提供し、社会が正確に回ることを可能にした。だが、官僚制も神話と同じで、秩序のために真実を犠牲にする傾向がある。官僚制は、新しい秩序を発明して、それを世の中に押しつけることで、人々による世界の理解の仕方を、独特の形で歪めた。 官僚制をはじめとした強力な情報ネットワークはみな、設計の仕方と使われ方次第で、良いことも悪いことも行ないうる。ネットワーク内の情報を増やすだけでは、恩恵が得られる保証にはならないし、真実と秩序の間の適切なバランスを見つけやすくなるわけでもない。それが、21世紀の新しい情報ネットワークの設計者と利用者にとっての、重要な歴史的教訓だ。 4 不可謬の情報ネットワーク 官僚制と神話はともに秩序を維持するために必要不可欠なものだが、どちらも秩序のためなら喜んで真実を犠牲にする。 では、そうした不完全さを排除し、全く誤りの無い情報ネットワークを作ることができるのか?今日ではAIがそのようなメカニズムを提供できるかもしれないと期待する向きもある。 しかし、それは不可能だ。そもそも、「全く誤りの無い情報ネットワーク」(という空想)なら、既に構築されてきた。宗教だ。 歴史的に見て、宗教の最も重要な機能は、社会の秩序のために超人的な正当性を提供することだった。だが、聖書についての解釈をめぐって何千年も人々が対立しているように、人間の制度や機関が入り込む限り、不可謬の文書は存在しえない。そして、不可謬の文書に権威を付与することで人間の可謬性を迂回する試みは、決して成功しなかった。 では、不可謬の文書がありえないならば、人間の誤りという問題にはどう対処すればいいのか? 情報の素朴な見方は、教会とは正反対のもの、すなわち情報の自由市場を創出すれば、この問題は解決できると断定する。もし情報の自由な流れに対する制限をすべて取り除けば、誤りは必ず暴かれ、真実に取って代わられるというのが、素朴な見方だ。だが、それは楽観的すぎる。印刷術の発明がヨーロッパでの魔女狩りを急速に広める役割を果たしたように、情報の流れの障害物を取り除いても、真実の発見と普及につながるとは限らない。 5 自己修正メカニズム 真実が勝利するためには、事実を重視する方向へ舵を切る力を持った、キュレーションの機関を確立する必要がある。 歴史上では、「科学アカデミー」がそうした信頼に足る情報ネットワークを築き上げ、科学革命に貢献した。 彼らが有していたのは、機関自体の誤りを暴いて正す強力な自己修正メカニズムだった。ある事柄が真実であると、特定の時代の科学者のほとんどが信じていたとしてもなお、科学の機関はそれが不正確あるいは不完全であることが判明するかもしれないという立場を取る。19世紀には物理学者の大半は、宇宙を包括的に説明するものとしてニュートン力学を受け容れていたが、20世紀にはそのニュートンのモデルの不正確さと限界が、相対性理論と量子力学によって暴かれた。科学史上とりわけ有名な瞬間はみな、妥当なものとされていた通念が覆され、新しい説が誕生したときにほかならない。機関が大きな誤りを進んで認めるおかげで、科学は比較的速いペースで発展しているのだ。 ただし、自己修正メカニズムは、真理の追求には重要極まりないが、秩序の維持の点では高くつく。強力な自己修正メカニズムは、疑いや意見の相違、対立、不和を生み出したり、社会の秩序を保っている神話を損なったりしがちだからだ。 6 民主主義と全体主義 独裁社会と民主社会では、情報の流れ方がどのように違うか? 独裁制の情報ネットワークは高度に中央集権化されている。中央は無制限の権限を享受し、情報はその中枢に流れ込み、そこで最も重要な決定が下される。また、中央は不可謬であるという前提に立っている。要するに、独裁社会は強力な自己修正メカニズムを欠いた中央集中型の情報ネットワークだ。 それとは対照的に、民主社会は強力な自己修正メカニズムを持つ分散型の情報ネットワークだ。民主的な情報ネットワークを眺めてみると、たしかに中枢がある。民主社会では政府が最も重要な行政権を持っており、したがって政府の諸機関は厖大な量の情報を集めて保存する。だが、それ以外にも多くの情報の経路があり、独立した多数のノードをつないでいる。民主的な政府は、人々の自立性を重んじ、中央で決めることはできる限り小さくする。民主社会は誰もが可謬であることを前提とするため、多種多様なノードの間で継続する話し合いの体制となる。 加えて、民主制は自己修正メカニズムも取り入れておかなければならない。有権者の51%の選んだ政権が、宗教的少数派を抹殺すると決定したとしても、それは民主的ではない。民主制は多数派による独裁制とは同一ではないからだ。民主制とは多数決原理のことではなく、万人の自由と平等を意味する。 ここで、民主主義と全体主義の歴史を紐解き、情報ネットワークがそれぞれにどのような影響を与えてきたかを見てみよう。 狩猟採集社会では、指導者による独裁はめったに起こり得ず、経済ははるかに多様化していた。農業革命後、書字の力を借りて大規模な官僚制の政治組織が誕生すると、情報の流れが中央集権化され始めた。3世紀には、ローマ帝国だけでなく地球上の他の主要な人間社会もすべて、強力な自己修正メカニズムを欠いた中央集権型のネットワークになっていた。これは単に強権的な指導者が現れたからというよりも、話し合いを行うための物理的な手段が無かった(互いの声が聞こえる範囲にいない)こと、また人民の多くに話し合いのための初歩的な知識・教養が無かったことが原因である。 何百万という人口規模での民主制がようやく可能になったのは、マスメディアが大規模な情報ネットワークの性質を変えてからだった。16世紀から印刷物の出版が始まり、民主化傾向が強まると、テクノロジーの発達に合わせて情報の流れが強化され始めた。19世紀から20世紀にかけては、電話、ラジオ、テレビといった新しい通信技術のおかげで、マスメディアの力は途方もなく強化された。 しかし、現代の新しい技術は、大規模な全体主義体制への扉も開いた。ローマ帝国のネロは残虐な処刑を行ったが、それは自分の行動範囲内にいる人間に対してのみだ。一方、スターリンのような現代の全体主義は、ラジオや出版物といった新しい情報テクノロジーによって、それとはまったく違うスケールで人々を抑圧した。 新しい情報テクノロジーは大規模な民主主義体制と大規模な全体主義体制の両方の台頭につながったが、これら2つの体制が情報テクノロジーをどのように使ったかには、きわめて重要な違いがあった。 民主制は中央を通ってだけではなく、多くの独立した経路を通って情報が流れるのも促し、多数の独立したノードが自ら情報を処理して決定を下すことを許す。情報は、大臣のオフィスをまったく経由することなく、民間の企業や報道機関、地方自治体、スポーツ協会、慈善団体、家庭、個人の間で自由に流れる。 一方、全体主義はすべての情報が中枢を通過することを望み、独立した機関が独自の決定を下すことを嫌う。たしかに全体主義には、政権と党と秘密警察という3つ組の機関がある。だが、これら3つを併存させるのは、中央に楯突きかねないような独立した権力が登場するのを防ぐためにほかならない。政権の役人と党員と秘密警察の諜報員が絶えず監視し合っていれば、中央に逆らうのははなはだしく危険になる。 民主主義と全体主義を異なる種類の情報ネットワークとして見られるようになると、両者が繁栄する時代もあれば、存在しない時代もある理由も理解することができる。両者の有無は、人々が特定の政治の理想に対する信頼を獲得したり失ったりするからだけではなく、情報テクノロジーの革命のせいでもある。 7 あたらしい全体主義 現代の情報テクノロジーは、全体主義と民主主義に新たな局面をもたらしている。 全体主義政権は秩序を維持するために、現代の情報テクノロジーを使って情報の流れを中央集中化したり、真実を抑え込んだりする。その結果、硬直化の危険と闘う羽目になる。しだいに多くの情報が一か所だけに向かって流れるようになると、それは効率的な支配につながるのか、それとも動脈が詰まって、ついには心臓発作が起こるのか? 民主主義政権は現代の情報テクノロジーを使って情報の流れをより多くの機関や個人の間で分散化し、真実の自由な追求を奨励する。その結果、砕け散る危険と闘う羽目になる。中央は依然として体制を維持できるのか、それとも体制はばらばらになって無政府状態に陥るのか? 歴史は全体主義に敗北をもたらし、民主主義に勝利をもたらした。この勝利はしばしば、情報処理における基本的な利点という見地から説明されてきた。全体主義がうまくいかなかったのは、あらゆるデータを中枢に集中させて処理する試みが、きわめて非効率的だったからというわけだ。 ところが、未来は民主主義の手の中にあるとはいい難くなっている。新しい情報革命がすでに本格化し始めており、民主主義体制と全体主義体制の競争における新しいラウンドの舞台が整いつつある。コンピューターやインターネット、スマートフォン、ソーシャルメディア、AIは、権利を奪われた集団にだけではなく、インターネットに接続できる人なら誰にも、さらには人間以外の行為主体にさえも声を与え、民主主義に新しい難題を突きつけてきた。2020年代の民主主義国は、社会秩序を損なうことなく公の場での話し合いに新しい声の洪水を取り込むという課題に、またしても直面している。同時に、さまざまな新しいテクノロジーのおかげで、すべての情報を一か所の拠点に集中することを依然として夢見ている全体主義政権は希望を新たにしている。たしかに、赤の広場の演壇に並んでいた長老たちには、単一の中枢から何億もの人の生活を統制する能力はなかった。だが、ひょっとしたらAIにならできるのではないか? そして、現在の情報革命には、これまでに私達が目にしたものとは全く異なる独特の特徴がある。 これまでは、歴史上のどの情報ネットワークも、人間の神話作者と官僚に頼って機能してきた。粘土板やパピルスの巻物、印刷機、ラジオは、広範に及ぶ影響を歴史に与えたが、あらゆる文書を作成し、それを解釈し、誰を魔女として火あぶりにするかを決めるのは、つねに人間の仕事だった。 ところが今や、人間はデジタルの神話作者や官僚を相手に回さなければならなくなる。21世紀の政治における最大の分断は、民主主義政権と全体主義政権との間ではなく、人間と人間以外の行為主体との間に生じるのかもしれない。新しいシリコンのカーテンは、民主主義政権と全体主義政権を隔てる代わりに、全人類を、人知を超えたアルゴリズムという支配者と隔てるかもしれない。
38投稿日: 2025.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ● 2025年3月7日、母と新宿 紀伊国屋にあった。フロアに何箇所も平積みされてて大々的に売り出してる。帯に「サピエンス全史を超える衝撃」とある。中身はそれなりに難しいので、こんなのが読めたらいいね本。→紀伊国屋1階の入口の1番外の風があたる正面の手前にこの本が売り出されていた。
2投稿日: 2025.03.07
