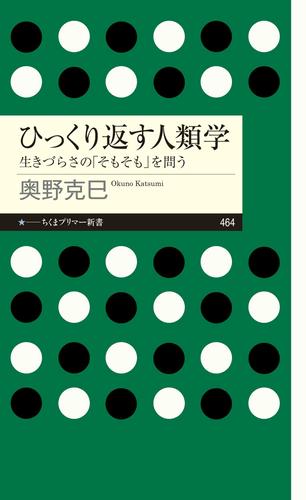
総合評価
(16件)| 1 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん。 問いに対して先住民の生活を見ることがどのように作用しているかわからずモヤモヤ。 狩猟採集や集団的共同生活の暮らしぶりは興味深かったが、その視点を用いたところで、諸々の社会問題の解決には向かない気がした。 ひっくり返すといっても、文化や社会システムは、不可逆的に成り立つものと思われるので、原始的に立ち返るのは不可能に思える。 このルポルタージュを見なくても、問題が多発してることでそもそもの価値観に疑問を持つことは出来るし、原住民たちの生活や慣習を活かすことの現実味がない。 ただ、既に行われていそうだけど、「行動(見て真似する)から習得する」方法は教育現場での取り入れることができそうだし、「権力を持たない、集中がない行動様式」は小さい共同体ではある程度実現可能だと感じた。 私たちの社会の在り方の否定したい場合に、先住民の社会を肯定することで、現代社会を否定できるというのは違う気がした。そのような単純な様式に当てはまらないから、作者の主張(これ自体も断定的に見られない)がどれも逸れているような感じがした。 校正ミスがいくつか見られ、読み間違えそうになる箇所もありその点も残念。 新書なのに、命題に対して、ただ事柄を述べているような整理されてないと感じる文章の形態も好きではなかった。
0投稿日: 2025.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ解決なんて絶対無理だと思うような社会問題も、「そもそも…」と考えると、思いもしない糸口が見えてきそうな…。本作は、文化人類学のケースや考え方に焦点をあてた内容であるものの、一般的な考え方にも当てはめられそうで勉強になった。
0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://claude.ai/public/artifacts/41d83529-a073-4d1c-bf89-00bbaa19a13e
0投稿日: 2025.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な民族誌の事例を基に、我々の「当たり前」をひっくり返し、物事の「そもそも」を問い直す人類学の思考法を通して、学校教育、貧富の格差や権力、心の病や死、自然と人間との関係といった身近でありながら重大なトピックを「ひっくり返して」考え、生きづらさの「処方箋」を探る。 民族により「当たり前」は異なっており、フィールドワークにより紡ぎ出された民族誌の知見により、自分たちの社会の「当たり前」がひっくり返され、物事の根源に立ち戻った本質的な議論につなげることができるという人類学の魅力は、よく理解できた。 「教える」という概念がないヘヤー・インディアンやプナン、貧富の格差がないプナンやサン・ブッシュマン、カリスのサラババ(唇の過ち)、死者を忘却化するプナン、川に人格を認めるマオリなど、紹介されている民族誌の事例も、とても興味深かった。 ただ、それぞれの民族の前提条件等(紹介されている多くの民族は狩猟採集社会であるなど)を無視して、資本主義が発達した現代日本社会の参考とすることができるのかなど、全体を通して、いろいろ疑念や違和感も拭えず、ちょっとすっきりしない読後感だった。
0投稿日: 2025.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ学ぶとは何なのか、貧富の格差や権力の集中はどうして起こるのか、心の病はどうして起きるのか、人の死にどう向き合うべきなのか、人と自然はどう関わるべきなのか.何とも捉えどころのない質問に、ある程度的確な答えを提示する内容の本だ.現代社会でよく見られる問題ばかりだが、著者は狩猟民族のプナンやその他の原始民族へのフィールドワークから答えを導き出そうと思索している.学びという概念がない、ありがとうという言葉がない、権力者が存在しない、死を忘却して関知しない、人間と自然を別のものと捉えない.これらの状況が存在することは本書を読むまで気がつかなかったが、人類の祖先に近い生活を未だに営んでいる狩猟民族にその原点があることは、考えさせられることだと感じた.
1投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下、引用。 「そもそも論」は、与えられた目の前の問題の解決にあたるのではなく、話を蒸し返すため、場の空気を読まない議論として、煙たがられる傾向があります。この話にはそもそも無理があるのではないかと述べながら、ちゃぶ台をひっくり返すように考えていくと、議論は前に進むどころか、停滞してしまうのです。本書『ひっくり返す人類学』では、人類学で、ちゃぶ台返しをしてきたことになります。 実は人類学は、「そもそも論」がとても得意なのです。 ティム・インゴルドは、人類学が一般にそうした特異な傾向を持つ学問であるため、人類学の研究者は、様々な問題に関する公的な議論にしだいに呼ばれなくなったのだと指摘しています。公的なディベートでは、人類学者は、 質問者を非難し、その暗黙の前提を明るみに出し、こうした前提をもたない他者ならば、その問いを異なるしかたで提示すると述べることだろう。簡単な答えなどない。 人類学は、あなたが知りたいと思っていることを言ってはくれない。つまり人類学は、あなたがすでに分かっていると思っていることの基礎をぐらつかせる。人類学の研究者たちには、以前より賢明ではあるが、スタート時点よりも知識の量が少なくなっているという結果で終わってしまうかもしれない。(『人類学とは何か』奥野克巳・宮崎幸子訳 亜紀書房、二〇二〇年) 「そもそも論」は、人々がすでに分かっていると思っていることの基礎をぐらつかせます。そして、目の前に与えられた問題に対して議論を進め、知識を増やすのに貢献するのではなく、知識の量はむしろ議論のスタート時点より少なくなってしまうかもしれないのです。それは一見、停滞しているかのように見えるかもしれませんが、目の前の問いの存在意義や必要性を疑う点で、人類学を通じて、私たちは「より賢明」になることができるのです。 ビジネスコンサルタントの細谷功が、『考える練習帳』(ダイヤモンド社、二〇一七年) と題する本の中で示している身近な事例から、「そもそも論」とは何かに関してもう少し探ってみましょう。たとえば、職場のモチベーションを上げるために、あれやこれやと新しい働き方を考えている場面で、「そもそも論」者であれば、新しい働き方がそもそもなぜ必要なのだろうかと考えます。そもそも、いったい何が問題なのかという問いへと立ち返るのです。 そうすることで、より上位の大きな問いにたどり着くことが可能になります。問題そのものを定義し直すことで、「長期的視野に立って仕事に取り組むにはどうすればいいのか」とか、「上司と部下の齟齬をなくすにはどうすればいいのか」という新たな問いを持ち出して、本質的な議論へと階段を一段上がるのです。 こういった思考法こそが、「そもそも論」です。人類学は目の前に与えられた問題をひっくり返してみることに長けています。なぜなら、インゴルドが言うように、目の前にある問題に対して、それが今とここから遠く離れた場所で、我々と同じ前提を共有することがない他者たちが、異なるしかたで問いを立てていることを知っているからです。 では、なぜ今「そもそも論」が必要なのでしょうか? それは、世界が臨界点に達しており、私たちにはもはや、この崖っぷちの世界だけしかないからです。 森は開発によって荒廃させられ、鉱業は大地をすっかり掘り返してしまっています。 化石燃料の燃焼は、気候に甚大な影響を及ぼしています。生きていくのに必要なモノの不足が、大量虐殺に至る衝突をもたらしています。グローバルな生産、分配と消費のシステムは少数者に富をもたらす一方、多くの人たちを慢性的な貧困や不安に追いやっています。 人類にとってこうした未曽有の危機的状況の中で、生が今後も続いていくためには、 私たちはいったいどうすればいいのでしょうか? 答えはどこかに転がっているのではなく、探し出さなければなりません。身の周りにある哲学や科学を追及してみても、 「問題解決型」の思考法だけでは答を見つけることはできないでしょう。危機が困難であればあるほど、目の前にある問題をいったんひっくり返してみるような、アクロバチックな思考法を手がかりにするしかありません。 その時に威力を発揮するのが、私たちのやり方や考え方をいったん括弧に括って、どこそこではこうである、あちらではそうなっているという別の可能性にあたりながら、私たちが依拠している前提それ自体をひっくり返す人類学です。人類学とともに、いっ たん私たちの目の前にある問題をひっくり返してみて、解くべき問題がそもそも的を射たものなのか、そもそも限られた状況の中で、私たちが問題を解こうとしているだけなのではないかということから考え直してみるのです。 読者のみなさんが今後、人類学とともに、ひっくり返す思考法を身につけて、私たちの目の前に横たわる数々の困難にチャレンジしていくことを願っています。
0投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類学に学生時代ふんわりとしか触れてこなかった身からすると、とても読みやすく、面白かった!ちくまプリマー新書、やはり良い。 単純に「同じ地球上でこんなにも異なる文化が育まれているんだ」という驚きと、「いま自分が抱えているモヤモヤはこの社会に特有の文化的葛藤なのか」という気づきとそこから抜け出すきっかけを授けてくれる、そんな側面を持つ学問が人類学なんだなあと勉強になった。 当たり前を疑う、前提を見つめ直す、という行為は、当たり前や前提が異なる「なにか」をヒントにすると少し難易度が下がるというか、やりやすくなる。そのためにも、未知のものを知る、触れてみる、できるなら体験する、ということは重要なんだなー。きっと。 •サカナやトリにとっては、「自然」は抗うべき対象ではなく、一体化するものです。他方で、船や飛行機にとって「自然」環境は、克服すべき問題なのです。 •知識は私たちの心を安定させ、不安を振り払ってくれる。知恵はぐらつかせ、不安にする。知識は武装し、統制する。知恵は武装解除し、降参する。 •学ぶとは「知識」を身に付けるだけでなく、「知恵」を重んじることであり、「知識」に「知恵」を調和させることです。 大切にしていきたい言葉も沢山あった!
3投稿日: 2025.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ●教育・学びには、教える人と教わる人という二つの立場があることを当たり前に受け止めているが、広い世界、そういう前提がない社会もある。それらの例を持ち出しながら、どこそこではこうであるという別の可能性にあたりながら、私たちが依拠している前提それ自体をひっくり返すという思考法を示すのが本書である。
1投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本で暮らす中で「当たり前」だと考えられていることが、別の国・地域ではまったく違っている例が示されており、読みながら自分の中の「そもそも」を問い直していける、おもしろい内容でした。
1投稿日: 2024.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類学は「そもそも論」が得意. 遠く離れた場所では我々と同じ前提を共有することがない他者が存在し, 彼らは異なるアプローチでその問題に対処している. それらを知ることで, 「すでに分かっていると思っていること」の基礎を崩し, より上位の大きな問いにたどり着くことが可能となる.
0投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ【学校について】 人から教わるという発想がなく、人がやっているのを見て学ぶ社会がある。 彼らは学校を必要と感じていなくて、授業に参加してもずっと座っているだけだと感じるし、宿題を忘れたら怒られ、いじめに遭うこともあり、次第に学校に行かなくなるが、困らない。 この話は大人になった今、すごく納得できる。 どれだけ英語の文法を勉強しても、ネイティブスピーカーと話すことに不慣れで抵抗があると使い物にならないし、逆に文法はめちゃくちゃでも話すことに慣れていて、意思疎通ができている人が周りにいて、「学校の勉強って何だったんだろう…」と思うことが多い。 社会に出て求められるのは、知識ではなく考え実践する力なのに、(少なくとも私が経験した日本の)学校教育は、勉強の進め方までも事細かに指示されて、「先生に従う=いい子」という感じ。 大勢の子どもが一度に学ぶにはある程度しくみを画一化することが必要だけど、それが主体性を奪っているのかなと思う。 座学には限度があって、体験、実践することが大きな学びに繋がると思ってはいるものの、学校に行かないことは大ごとな環境に生きているから、実際にそう感じて「学校に行かない」を実践できる人たちを少し羨ましく思った。 【心の病】 全体的に、フィールドワーク先の人たちは「個」を意識していない。(それに加えて常に集団で生活していることで悩みを抱えることもなさそう) 逆に、今の世の中では良くも悪くも「個」を大切にしていて、大家族も少なく1人の時間が多い人が増えていたり、多様性が認められるようになってきたことで「自分らしさ」も求められるようになり、それがストレスに繋がっているのではと感じた。 【自然と人間】 自然と人間は切り離されていて、人が自然を支配するような感覚は、紀元前のギリシア哲学にまで遡る。 動物実験をしたり食べたりすることに対して「かわいそう」と感じる感覚を、人間に近い動物から広げていこうという考え(哺乳類→鳥→虫みたいに)はなるほどと思った。 普段から、人間は他の動物のことを考えずに利己的だと思ったり、地球環境の保護を積極的に行う動きがあるものの、そもそも自然界に人間がいなければ生態系は保たれていたのでは?1番要らない生き物って人間だよな…と思いながら生きているので、このテーマに関する世の中に存在する意見を知ることができてよかった。 〈全体を通して〉 「そもそも」について考えることはできても、世の中のしくみや価値観が出来上がっている中で、それを実践することはとても難しい。 ただ、世の中を変えることは難しくても、ふとした時にこの本で知った価値観を思い出して、今の自分の置かれた状況を客観視して、少しでも楽に生きられたらと思う。
12投稿日: 2024.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログちくまプリマー新書であるため、内容は整理整頓され、わかりやすい。 本書の目的は、世の中に蠢く様々な問題に対して、他民族の視点から見つめ、考え直すことだ。それはある意味マルチバース的な視点なのかもしれない。 我々に必要な、ありとあらゆるレンズを手に入れる方法を、人類学を通してキッカケをくれる一冊である。
0投稿日: 2024.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログシンプルながら唆られる装丁。 同筆者の『はじめての人類学』では歴史的な流れを主要な人類学者を押さえながら紹介していったのに対して 「ひっくり返す」という概念を我々の固定化された思考に比して提示しながら、人類学と社会との関係において不可分と思えるような形で、この学問の意義と存在感が示されている。 外界から覗くそういったダイナミズムは、研究者自身にも見いだせる。
0投稿日: 2024.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとほんとにひっくり返ったかもしれない。「子どもたちは学びたがっている」「人はもともと好奇心旺盛である」というようなことが自明でないとすると、私がいままで考えてきたこと、言ってきたことのおおもと、土台がくずれることになる。そもそも、「教える」「教わる」というようなことばがないという。ふん?でも、もともと技は「教える」ものではなく「盗む」ものという言い方もできるし、見よう見まねで「覚える」ということでいいのか。いまあるような形での学校、その学校で教わるような知識、それは必要なくとも、生きていく術は必要だし、それは自然に、それこそ見よう見まねで覚えていると言えるのか。好奇心がないとはどこにも書いてなかったように思うし。鶴を折ってあげたら、他に何ができるかと聞いてきたともいうし(「教えて」とは言わなかったとしても)、それに、「学ぶ」ということばがないとは書かれていなかったはず。「学ぶ」が「まねぶ」から来ているとするなら、まねて覚えていくというのでいいのか。ちょっと、勝手に納得している。それから「ありがとう」ということばもないという。それは良いことだと思う。「分け与える」ということが「有難い」ことではないということだから、それは大変良い習慣なわけだ。それから生や死について、心の病について。卑猥語などを無意識に言ってしまうというのはトゥレット症と言われるものに近いのだろうか。興味深い。そして、もう一つ、山や川に法人格を与えるということ。それはもともと神話の中などではあったことなのだろうけれど、いまのこの世の中で法的に人格を認めるというのは日本ではありえることなのだろうか。でも、その後ろで人間が訴えを起こしたりするわけだから、それってどうなんだろうと思ってしまう。とは言え、法的にそれを認める国があるというのは望ましいことのように感じる。まあとにかく、まだまだ世の中知らないことはいっぱいあるわけだ。「子どもの文化人類学」も読まないといけない。
0投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前に、原ひろ子「子どもの文化人類学」(ちくま学芸文庫)の解説を書いている人類学者で、「ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと」(新潮文庫)は積んである。まずはこちらでお近づきになろうか。 タイトルをみてもわかるように、人類学のフィールドワーク(現地社会に中長期滞在して、その社会の一員として暮らしながら直接観察したり話を聞いたりする調査方法)で得られた体験を通して、現在の日本で普通に暮らす私たちが内在化している「常識」を問い直す一助となる一冊。わがやの当たり前、学校の当たり前、日本社会の当たり前、ネットで繋がった世界の当たり前は必ずしも人間全体の当たり前ではないことを少数民族の社会や文化から知ると、ほんとうにコロンブスの卵のようにおどろかされる。この本では学校や教育、貧富の格差や権力、心の病や死、自然と人間について、それぞれさまざまな人類学の知見を元に、わたしたちがとらわれがちな「そもそも」を疑ってみせる。そんなところからひっくり返されたら途方に暮れてしまいそうだが、そこから考え始めてこそみつかる希望もあると思えた。 第一章の学校と教育の話の中には、原ひろ子の著書にあるヘヤーインディアンの話もたくさん引かれていた。この章がおもしろかったら、「子どもの文化人類学」もぜひ芋づる式に読むといいと思う。学芸文庫といっても、とても読みやすくておすすめ。 私にとっては、この著者の調査したボルネオ島の狩猟民プナンの話がどれも興味深く、次は積んである新潮文庫を掘り出して読まなければと思っている。
4投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1824036699258929246?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
1投稿日: 2024.08.15
