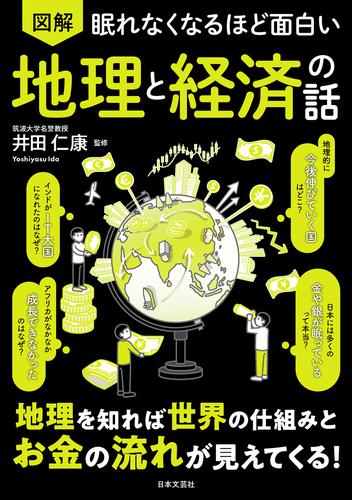
総合評価
(5件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10297984
0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルにある「眠れなくなるほど面白い」は明らかに大袈裟な釣り文句。 経済とお金に絡むさまざまな事象をイラストや図解を使い、1項目につき2頁で、わかりやすく面白く紹介する。 ただ、著者は投資コンサルタントであり、書かれている内容に深みはなく、ゴシップ的な記述も多い。 その中で、覚えておいてもいいかなと思うものを列挙しておく。 ①元本が何年で2倍になるかは、複利の場合は72を年利で、単利の場合は100を年利で割るとわかる ②取引に関係のない人たちにメリットをもたらすのが「外部経済」、反対にデメリットを与えるのが「外部不経済」 ③「合成の誤謬」とは、個々人の行動が理にかなった合理的に正しいものであっても、それが全体に行き渡ると望ましい結果とならないこと。例えば、コロナ禍のマスク買い占めがマスク価格高騰を招いた。 ④賃貸住宅では、プロパンガス業者が導配管の工事費用、各室の給湯器費用などを大家に対して無料にし、その分を各室の毎月のLPガス代に反映させるため、ガス料金が高くなる
0投稿日: 2025.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ眠れなくなるほどではありませんでしたが、一人の社会人として、知っておいた方がいい情報が沢山あり、良い学びを得ることができました。 投資をしている身として、今後どこが伸びていくのかを知ることができてよかったです。 今経済はアメリカの時代ですが、今後は東南アジアやインドが伸びてくるそうです。
52投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ地政学のようなテーマで、連続的に世界なり日本なりを俯瞰していく内容かと思ったが、世界と日本国内の区別なく、その地域地域にスポットライト当てて事例を取り上げていくスタイルで、地政学を掘り下げるというよりは、地理的な雑学本という感じであった。知識として意外と思うものもあり、負荷をかけずに流し読みするのに適した本だと感じた。
13投稿日: 2024.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍で私の仕事スタイルも変化しましたが、高校での指導要領も変わったようですね。地理総合、歴史総合という科目が必修になり、私が学習した数十年前とは学ぶ内容も変化してきているようです。そんな状況を踏まえて、今では「地理」そのものを学ぶのではなくて、他の科目、この本においては「経済」と絡めて学ぶようになってきているようです。 社会人になり、テストのための勉強から、自分の興味を深めるための勉強(読書)をしている私にとっては、今回読んだ本は興味深かったです。本の表紙に書いてあるように「地理を知れば世界の仕組みとお金の流れが見えてくる!」とありますが、様々な事件・戦争が起きる背景には各国の置かれている「地理」が少なからず関わっていることが少しずつ理解できたと思います。 以下は気になったポイントです。 ・アメリカが世界トップの経済大国なのは、地理的に最強(グレートプレーンズ、プレーリーが農業に適した肥沃な土地)である、さらに鉄鉱石、石炭、石灰岩といった天然資源に恵まれている。五大湖から大西洋に注ぐ運河が造られて水運も発達した。(p14)2020年には、NAFTAに代わって、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が発効、自由貿易の文言が外されて、保護貿易色の強い協定になった(p15) ・BRICSは、2024年には、エジプト・エチオピア・イラン・アラブ首長国連邦が加盟して、9カ国の巨大経済圏となった。世界GDPの28%、原油生産量の44%を占める(p18) ・インドがIT大国になれたのは、経済自由化、人口増加、アメリカ西海岸との時差が12時間半、英語が準公用語、新しい職種なので仮想カーストでも能力次第で出世ができる点にある(p21) ・アラブ首長国連邦は7つの首長国が集まっている、面積の大半は「アブダビ」である。人口1000万人のうちUAE国籍を持つ住民は1−2割程度、ほとんどが外国籍の特殊な人口構成を持っている(p34) ・スマホやPC,家電などの廃棄物に含まれるレアメタル=都市鉱山、日本における埋蔵量は、金で6800トン、銀で6万トンと言われている。世界埋蔵量と比較すると、金が16%、銀が22%である(p44) ・東京都心から1700キロ離れている「沖ノ鳥島」が失われると、この島を根拠とした排他的経済水域が失われ、その広さは40万キロ平方で、日本の領土を上回る(p46) ・ラクダは背中のコブに蓄えられた脂肪を、食事を摂れないときのエネルギー源にする。この時に、代車水という水分も作られて、水分の補給が可能である。体質的に、体に長く水分を蓄えられるようになっている(p64) ・現在日本で稼働中の主な油田・ガス田として、新潟に2箇所、北海道に1箇所のガス田、秋田県の八橋油田がある(p75) ・19世紀初頭の文化・文政期には、江戸では下り醤油(薄口)に代わって、地回り醤油(濃口)が主流となり、蕎麦つゆ、寿司のつけ醤油に使われ、今につながる江戸の味のベースとなった(p99) ・江戸時代までは、お茶といえば「宇治茶=京都」であったが、明治時代になって静岡県の生産量が一番になった。徳川慶喜と一緒に移り住んだ旧幕臣が、手に職を持っていなかった中で、旧幕臣の勝海舟の進言により、お茶の栽培が始まった、日本一位の製茶地帯となる牧之原台地もこの時期に開拓された(p100) ・創業者である豊田喜一郎の名は、本来「トヨダ」で10画だが、「トヨタ」だと、8画となり、末広がりで縁起が良いとされるので、社名はあえてこちらを選んだ(p103) 2024年6月24日読破 2024年6月25日作成
0投稿日: 2024.06.25
