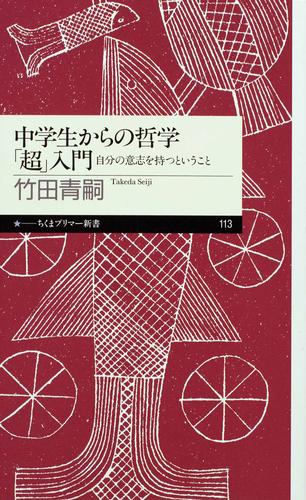
総合評価
(52件)| 10 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恥ずかしながら哲学について全く知らない状態で、題名に惹かれて読むことにしました。 難しい内容も多いが、使われている言葉はわかりやすかったです。哲学の面白さ、宗教との比較、自己の意思を持つことの大切さ、ハッとさせられることばかりでした。流し読みしてしまったところもあるので何度も読み直したいです。ただ結構気合がいるので、他の入門書をいくつか読んでいこうと思います。笑
0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学について著者の経験なども踏まえざっくりと、専門分野は少し深く書かれた著作です。全体的に平易な文体で書かれており読みやすいものの、中盤の一部は専門的で少し難しい場面もありました。ただ全体を通して論旨が明確でありとても読みやすかったです。
0投稿日: 2024.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
哲学について触れようとすると、いわゆる哲学史から入ることになりがちであるが、そういった小難しいことは抜きに「現象学」の専門家としての立場から分かりやすく伝えてくれる1冊。また、著者が哲学の世界に入ったキッカケなども書いてあり、著者への親近感をもてる。私個人としては3枚目の世界を再構築していくという一節にとても共感した。
0投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生からとなっているが、大人にも読みごたえがある内容。 宗教も哲学を「真理や普遍性を追求するゲーム」、「世界説明の方法」との例え、社会を勉強するための例として「大貧民ゲーム」を「論より資本主義」「論より格差」であるとし「自由の相互承認」という理念でなりたっているという。人間関係の基本原理は「承認ゲーム」でその人の生の欲望と自己ルールによって規定されるとし、現代の欲望の時代に向き合うには、自分の意志を持つことの重要性を様々な例を用いてわかりやすく説明。 きょうだいと親との三角関係で家庭内の承認のたたかいにより「よいーわるい」の自己ルールがねじれてしまい、他者への自己防衛と攻撃性と高める可能性、友だちとの関係の中で承認を作る努力をすべきと助言。 「自由恋愛、自由職業、社会的承認」がかつての自由の象徴、一般欲望とすると八割の人が不幸になってしまう。自分の「自由の条件を作り直す」ことが大事なテーマと締めくくっている。
7投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生からのなのに難解で大変でした。おそらくこの分野の読書量が足りず、頭ん中が耕せてないのですね。だから今はどんどん読むのみです。 それでも哲学を宗教や経済を絡ませて多方面から語られていたので、興味は刺激されました。面白い感覚です。
0投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに中学生とありますが、実際は過去の哲学者の概要とともに自分が哲学にどう向き合うべきか?が深く書かれています。 ある程度難解でしたがこれから本格的な哲学書を読むのにまずは手馴しになります。
1投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・教養を養う一環で読んだ本。哲学系の本は難しいことが多いが、だいぶ読みやすく書かれており、最後まで興味を持って読むことができた(ただ、中学生にはちょっと難しい印象) ・資本主義の本質とはなにかを大貧民ゲームを通じて子ども達に問うた話など、純粋に興味深い話も多かった
0投稿日: 2022.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ一部中学生では難しそうな記述が見られたが、中々面白い本であった。特に、「幸福とは何か」に関する箇所は納得度が高かった。
0投稿日: 2022.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
哲学者の竹田青嗣が、中学生向けに哲学を説いた本。 この本を読んで初めてフッサールの現象学が、「正しさ」=「自己了解」であると言っていることを理解した。「正しさ」は「正しいか間違っているか」ではない、というのは面白い。 改めて「現象学」によって「相対主義批判」ができるというのも発見。勝手な推測だが、相対主義を乗り越えて肯定的世界観をもちたいという著者の動機がいつも見え隠れするのは、やはり著者が在日韓国人であるということが大きいのではないか。複数文化を経験し、価値を相対化する必要性を感じることを契機に、彼の哲学が構築されて来たように思えてならない。自分が帰国子女である点と重なるため、なおそう感じる。 それにしても、「正しさ」が自己了解であり、その自己了解の根源が他者との調整可能性であるという考えは、自分にとって極めてしっくりくる。同様に、「本質」が「真理」のようなものではなく「相互承認に耐えうる原理」であるというのは、目ウロコ。確かに了解しやすい。別の見方をすると、確証バイアスがなぜ悪い話ではないのか、というのを、科学ではなく、哲学的にサポートできるということといえまいか。確証バイアスが、他者と調整可能な自己了解に基づく限りは、それは正しいと言えるからである。 してみると、著者の言うようにポストモダンが現象学を誤解していると言うのがなぜかを深掘りすると理解が進むはず。なぜなら、現象学は、おそらく相対主義(の苦しさ)をよく知っていて、嫌いな者が、打ち立てたい考え方だからである。逆にいえば、相対主義を平気で標榜できるのは、本人自身は、相対主義の苦しさを味わったことがない、ということなのではないか?いやもしかすると、ポストモダンは、相対主義を標榜しながら、本当の相対主義にあるわけではないのかもしれない。
1投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教と哲学の違いが面白い 宗教は物語で、哲学は概念なんだそう。 私はキリスト教の学校に通っていましたが、聖書のストーリーとか物語。 元々は異端だったけれども主流となり政治と合わさって権威のゲームになっていくと。 宗教や世界史はあまり詳しくはないけど、わかる。 https://jinseilog.com/introduction-to-philosophy/
0投稿日: 2021.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学はどの本を呼んでも何だかいまいちよくわからなかったが、さすがに中学生向け(?)の哲学「超」入門なら少しはわかるかもしれないと思い読んでみた。結果、ほぼすべてにおいてなるほどと思える素晴らしい内容だった。 自分とは何か?世界とは何か?哲学とは何か?宗教と哲学との違いは何か?社会とは何か?幸福とは何か? といったことがらについて、著者の生い立ちからはじまり、地に足をつけてわかりやすく書いている。(…といっても中学生にはかなり難しいと思うが) その中で著者が最も伝えたいことは「自分の意志をもつこと」で、それは、自分の幸福の条件を、才能や運に委ねるのではなく、自分で自分の「自由の条件」を考えて作り直すということだ。 私たちは知らず知らずのうちに、自分ではなく他人が欲しがるものを高い価値があると思いこんでしまうが、それを手にすることができるのは実際は2割くらいしかいない。幸せになるには、他人の欲するものを欲する「一般欲望」ではなく、「自分の意志を持つこと」が必要。そしてそれによってはじめて生きる意味を見いだすことができる。 とても勉強になった。よくわからなかった哲学が少しだけ身近になった。今後の探求の大きな手がかりになりそうだ。
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【2回目】8/23から全5回にかけて実施した、オンライン読書会で講読したテキスト。ここでも「これは自力での達成だ」と思っていたことを何点も見かけることとなって、びっくりさせられた。自分を「よく」知るということは、自分の欲望のあり様を知ろうとすることに他ならないのだと、改めて感じ入った。特定に個々人の内側で、哲学的思考が芽生え、成長していく様を、ご自身の経験に即して語られているところは、とてもよかったと思った。
1投稿日: 2021.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログYさんからのオススメで読んでみた。 超入門ということで、作者の実体験を交えて読みやすい文体で書かれていた。 色んなエッセンスが詰まっていたが、 一般欲望から「自分だけの欲望=意志」を持つことが幸せにつながるというのが自分の心に1番刺さった。 自己認識と、自分ルール作りに努めたい。 また世界史講義録(金剛先生) という素敵な歴史サイトも教えてもらった。 http://timeway.vivian.jp/kougi-1.html めちゃワクワクので少しずつ読んでいくことにする。 #エッセンス - 宗教は物語で世界を説明する - 哲学は、概念と原理を使う - 壊れた世界も自己修復する力がある - 本質は、正しさではなく、他者と調整可能かどうか - 社会的ルールと自己ルールの二つが存在する - ガウェインの結婚: 自分の意志を持つこと
0投稿日: 2021.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生向けなので、なるべく平易な言い回しで哲学を語っている。ただ、決め打ちが多く、参考文献や引用文献の記載が巻末にないので調べるのが面倒(笑) 宗教、経済などからの視点を変えた論旨は興味を持たせるが...。純粋に哲学だけで勝負しても良かったのでは?
9投稿日: 2020.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ自由を得るために必要なことは何か? 自由とはどいうものなのか?知ることから始まる。 歴史の過程から、今では経済的な背景 自由恋愛 職業の自由 社会的承認 ガウェインの結婚
0投稿日: 2020.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の本質を考える方法が、哲学。人間は何のために生まれてきたのか、この問題が永遠にわからないたむ、ずっと考え続けることになる。だから、自分の意志が大事。
0投稿日: 2019.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生が理解できる哲学の本だと思って読み始めたが時間がかかったぁ(汗) 現代社会においては、自由すぎて何が「自由」なのか、豊すぎてどこに生きる意味があるのかも、うまくみえない。その環境で「自分の意思をもつこと」ことが、現代社会に生きる私たちにとっての最大のテーマなのだと。
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学、宗教、科学の違いと価値、自分とは何者か、生きる意味、ルールとは何かなど、自ら思考することの大切さを説いた本。中学生向けに書かれていて平易な言葉で説明されていて、なんとなく分かっていたつもりになっていた事柄が、よりよく理解できたと思う。資本主義、宗教、科学のバランスが、最近なぜ崩れつつあるかということも、本書の説明で納得。「欲望はいつも必ず向こうからやってくる」「宗教最大のライバルは資本主義」「一般欲望だけでなく、固有欲望を持つことのススメ」
0投稿日: 2018.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログとっつきにくい哲学をわかりやすく書いた本。著者によれば哲学も宗教の科学の違いは世界の説明の方式。その中で哲学は人々の異なる信念や価値観の中から共通項を取り出すような考えだと述べる。違う言葉でいえば、自己を押し付けるのではなく自己と他者と相互承認のうえに哲学は成り立つ。 自分自身について自分で深く考える方法が哲学のエッセンスとも説く。各々は・・したい や ・・になりたい といった欲望を持つが、それは各々の自己ルールによって規定されている。自分の欲望や自己ルールを省みることが自分の意志を持つということである。
0投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ語り口は軽妙だけれど、本当に理解するのには、ある程度の哲学的な問題意識と素養が必要。 フーコーやレヴィナス、分析哲学への批判は、なるほどと思える。哲学と宗教の違い、科学との親近性も面白い。 アーサー王伝説から自分の意志を持つことの重要性、そして最後のファンタジーと論としては面白いが、どこまでアクチュアルたりうるか疑問だ。 ・人間は希望や目標が強く明確になるほど、意味と価値の秩序がしっかりし、そのことが時間のリアリティをますます濃くする。 ・宗教には「ここに何かほんとうのものがある」という人々の信憑を土台にした「真理を求めるゲーム」という性格がある。哲学は、むしろ「普遍性を求めるゲーム」。 ・宗教は、それが大きくなればなるほど、できるだけ重々しい「権威」づけを行い、この権威をみんなで厳かに守る「権威のゲーム」になる傾向をもっている。 ・ルソー:財の蓄積のないところでは、戦争の理由がないはずだ
0投稿日: 2016.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がどのようにして哲学の道に入っていくことになったのかを振り返りつつ、著者自身の哲学をわかりやすい言葉で語っています。 著者は、現象学を独自に受け継いだ「欲望論」ないし「エロス論」と呼ばれる立場を標榜しています。本書の後半では欲望論の観点から、われわれがこの社会のなかで「幸福」を追求することの意味について解き明かそうとしています。とくに、自己自身の欲望のあり方と社会のルールを編みなおしていく可能性を示すことに、著者の努力が傾けられているように思います。 ただ個人的には、著者やその盟友の西研らが、ここで語られているような考え方を「元気の出る思想」として提出していることには、おめでたさを感じてしまいます。むしろそのような仕方で自己と社会に関する理解を編みなおしていかなければならないことに倦怠感を覚えてしまいますし、それが現代思想の流行を支えた心情的な背景になっていたような気がするのですが。 ところで、著者は『現代思想の冒険』や『言語的思考へ』(ともにちくま学芸文庫)などでくり返し現代思想への批判をおこなっていますが、本書でも随所に現代思想に対する不満が述べられています。ただ、個人的には著者の現代思想批判には納得できないところがあると感じています。本書ではレヴィナスやその影響のもとにある他者論について、「まずいちばん注意すべきは、哲学的な装いをとっているものの、この「他者」の考えの核にあるのは、不遇な立場にある他者へ憐憫、道場、そして利他的なものを生活の基本にしようという、古くからの人間観だということです」と述べ、またそうした他者論を一種の「ロマン的思想」と特徴づけています。しかし、レヴィナスをはじめとする現代思想の他者論は、まさにそうした他者の理解を批判するというモティーフをもっていたのではなかったかと思います。 おそらく著者自身も、その程度のことは十分に承知しているはずです。そのうえで、著者自身の欲望論の観点から、現代思想の他者論を導いている「本質」を観取した結果、それは一種のロマン主義にほかならないと結論づけているのだろうと思われます。
0投稿日: 2016.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かり易く、読みやすく、面白い内容だと思います が、この内容が中学生から読めるかというと。。。 そんな中学生がいたら驚異的だと思いました。 息子が読めたらかっこいいなあと思いますが。 フッサールやハイデッカーの現象学の立場から 近代以前の神学・近代哲学・ポストモダン・現代哲学 までの流れや、宗教と科学と哲学の整理。 自己欲望と自己ルール、一般欲望。 自分の意思を持つことの重要性。他者とのかかわり 、形而上学の扱い。。。 それぞれ分かり易く書かれてあります。ただ、大人が 読んでも何度も読み返すか、そういう話に接し 続けないとなかなか腹には落ちないのではと思います。
0投稿日: 2015.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学とはなにか、を平易な言葉で(あるていど主観的なきもするが)書いてくれている 面白いなと思うことがいくつかあった ・哲学は、全員の共通の理解に迫る学問である。心理を追い求めるのは、下からあたものを掘り進めて見つける作業をさすが、哲学の場合は全員で田を耕し、最も全員の了解を得ることができる答えをさがすことである ・宗教と哲学の違い 宗教は物語的。教祖の言葉を神格化していく。多様性に対し排他的にならざるを得ないため、共生が最大の課題である。永続性を持たせるためには、つねに時の人の解釈が必要であり、結果的に権力との接続が深い。哲学と科学は、誰でも他人の提唱をきにせず、思ったことを論じていい自由がある。科学は、そのなかでも、自分としては「なぜ」を追求していく学問だと思う。とくに自然科学的な要素になっていくが、どちらかというと仮設を立証し、真理に近づくことを最大の目標としている。哲学は、「そもそもなにか?」を、世界の人間全員が共通して理解・共有し、納得できる定義、表現を探す作業に近い。哲学と科学は、エビデンスの有無、主観的であっていいという違いが最も大きいだけで、根本的には同じだと思う ・いろいろな経験から、自分なりの答えを見つけているところは、とても共感できる。結局、七めんどくさい事を言っているけれど、いたってシンプルで、自分が思っているようなことをいっているなと思う ・社会の本質はルールである。面白いなと思う。 社会の重要な点は、全員が暗黙のうちにルールを共有していることにある。ルールを承服するには、個人が納得する必要がある。その根本には、個人は自由であると互いに認め合う(決して縛られていない)ということ重要だと。うーん、おもしろい。智生や将生にも、早くそのルールの意味と、自分たちが自由であることを納得させる必要があるなとおもう。
0投稿日: 2015.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ6 はじめの信念はそのまま信じるな 自分の感情の中に、絶対的にそうだと思えること、確信をもてないこと、その中間地点の境界線 失恋などの大きな感情のゆらぎ、挫折の後に哲学について考えるということ。青年期の独自の経験。 宗教と哲学。自我の不安。決定的な答えを出せないということ。権威のゲーム。⚪︎⚪︎の本質とは何か。1番大事な点は何か。 自由の相互承認。 人を殺してはいけない理由。相互承認の理由。道徳の理由。人間的に生きるための根拠を自ら投げ捨てるを罪と罰。 自分の生への意志を持つこと。一般欲望とは別の自分固有の生の欲望を見出す。
0投稿日: 2015.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
以下、心に留った点 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 誰でも自分の心を内省して、ここまでは確実、それ以上確実なことが言えないという分岐点がある。誰でもそれを意識できるし、言うことができるという点に、「現象学」の確信がある。 あるところから先は、決して確実なことがいえない…懐疑論、相対主義 確実なことが言える…真理主義や客観科学主義 現象学は正しい認識という問題をどの程度確信と納得の状態があるか、という枠組みに置き換えた 事実を知るということと納得する自己了解するというのは本質が違う 人間や社会の問題では、何が「真理」か誰が「真理」を持っているか、と考えてはいけない。たくさんの人間がそれぞれ自分の確信をもち、その確信を交換し合っている。そういった多様な確信が、どのような条件があればうまく交換され、共有されるのか、ということをはっきりさせることが認識問題の本質である ヘーゲルの「不幸の意識」理想には憧れるけど、自分は到底そこまではいけない。それで引き裂かれて挫折がおこる。 =世界が壊れる経験 そこからの世界の自己修復 人間は希望や目標が明確になるほど、意味と価値の秩序がしっかりとして、そのことが時間のリアリティをますます濃くする 竹田さんの「欲望論」 事物の存在の性格や意味が、それに向き合う人間(主体)との関係によって変化することを、関係が相対的だという。 欲望がなければ、世界の意味の秩序は形成されない。ただしまた、世界の秩序が形成されてはじめて、われわれは自分の欲望ののなんであるかを知る=欲望相関性 2章 宗教も哲学も「世界説明の方法」 宗教 人間は自我に存在の不安をもつ。それを克服するためにあらわれた 物語がある。教祖がいて、「真理」に近づく真理のゲーム 共同体の知恵。人間の生活が多様になることであまりうまく働かな くなってきた。 弱点 激しい競争と権威のゲームへの推移 哲学 タレス 世界の森羅万象は「水」「アルケー=原理・起源」 原理を提出する言語ゲーム 方法の特質は概念を使うこと、原理を置くこと、再出発(幾度でも 新しい原理を提示できること) これによってより「共通了解」に近い原理(キーワード)を推し進 めていく 弱点 難しくなっていく 懐疑主義(相対主義)物事は見方を変えるとなんとでもいえ る。確実なことなど何もない 神の問題を通さなくても人間の問題を考えることができるようになった。(例えば、社会や人間欲望や実存)それが哲学において「神が死んだ」という意味 自由の相互承認による宗教の受け入れ合う世界 本質=イデア 「真理」とは違う。それぞれのものごとにあるもの 一番大事なポイントをなんと言えばいいか ※ アルケオロジー=考古学=起源の学 アナクシマンドロス 無限なものトアペイロン アナクシメネス 空気プネウマ イオニア自然学派 詭弁論 ヘラクレイトス 「人は同じ川に二度は入れない」 エレアのゼノン 「アキレスは亀を追い越せない」 無限は何よりも大きいということではない 第3章 ルール なぜ人を殺してはいけないか 社会のルール 自分の自由を投げ捨てる行為だから(相互承認がなければ 確保されない) 道徳的側面 見つからなければOK?自分は全うな人間だと自分自身に言 えなくなる 自己とは何か?実存哲学 キルケゴール、ニーチェ、ハイデガー そしてヘーゲル 自己価値の欲望 自己のルールの束 他者との承認ゲーム。どのような承認ゲームを作ろうとするかは、その人の生への欲望にかかっている。それは、自己ルールによって決まる。 ※ 母親からいわれるよいわるいが最初のルール。ということは、親のもつ教育の責任はとてもとても大きい 第4章 根本原因と派生原因。 資本主義社会が悪いのではない 資本主義社会は持続的に生産を拡大させる経済のシステムであり、それは同時にすべての人間に「自由」を解放する近代社会と切り離せない社会 無限競争にならないウィンウィンゲームにいかにしていくか 一般欲望 たくさん愛されたい、評価されたい、人の上に立ちたい、偉くなりたい… 競争の中で実現される欲望である以上、ほとんどの人は挫折する そこで必要なのが「自分の意思を持つこと」ではないか? =自分の幸福の条件を、才能や運にゆだねるのではなく、自分でよくつかみ直すこと、言い換えれば、自分で自分の「自由の条件」を考え、作り直すこと ある欲望が本当に自分を生かすような欲望であるかを自ら考え直すことには重要な意味がある 自分の感情は本当の自分ではないそれはファンタジーだ ※ 金岡新さん ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生からの、というタイトルだけど、中学生、読むのかなあ。 哲学はなんぞやを知るのに、非常に役立った。宗教と哲学の違いとか、わかりやすい。下手にニーチェとかから入んないほうがいいな。 1章は著者の体験談で、主観ありまくりで、失敗したかなあと思ったけど、あきらめないでよかった。
0投稿日: 2014.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間社会は自己ルールに基づいた個と他者との承認ゲームである。自己ルールは自身の生い立ちや欲望と深くかかわっており、欲望の実現のためには他者との承認ゲームを勝ち進んでいかねばならない。資本主義では”金”がゲームの勝敗を握っており、欲望のまま金儲け一辺倒に走ると、ゼロサムゲームへと発展。8割が負け組みとなる世界を創ってしまう。そもそも欲望を作り出す自己ルールは家族や社会が作り出すものであり、我々がもっと豊かな価値観を目指した場合にはWinWinゲームが出来るのではないか。そのような提言を感じました。
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学はなんぞやからはじまり、哲学と宗教の違いなど、哲学書を読む前に全体を俯瞰するにはもってこいの本です。 歴代の哲学者や哲学の歴史など、流れが分かった上で詳細な内容に入っていくべきと再認識。 ちくまープリマー新書、なかなかやりますね!中学生が読んで理解できるかは不明というとかなりマイノリティーになると思います。 哲学とは、ものごとについて「自分で考える方法」である。 哲学の方法の本質は、物語ではなく概念を用い、さまざまなことがらについて「原理」を少しずつ推し進めて、多くの人間が納得できる「共通理解」を作り上げてゆく方法である。 哲学は、答えがでない問題をどこまでも考える学問だというイメージがあるが、それは形而上学にはまりこんでいたときの哲学であって、現在はそんなことなないらしい。(カントが形而上学を終わらせたとか) 形而上学とは、形として見えるものの向こう側にある、見えない世界についての知識、学という意味。 プラトン、カント、ニーチェ、ハイデガー読んでみたいと思いました。 この著者 竹田 青嗣さん、かんなり分かりやすい☆この人の本にはまりそうです。 「とことん壊れる経験がないと、世界はふかまらない」
0投稿日: 2013.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログヘーゲルの人間社会観に基づく自由主義的社会理論や、資本主義の洞察など、竹田青嗣の哲学が平易な言葉で語られている。 中学生には分からないかもしれないが、高校生や大学生の哲学入門としては良書だと思う。
0投稿日: 2013.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ頭のよさそうな文章で、ときどきはっとさせられるフレーズがあり、興味深かったです。みなさんのレビューにあるとおり、中学生には難しいです。高校卒業したあたりでぜひ読んでおきたい本。
0投稿日: 2012.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が哲学に入った動機が、人生での挫折体験や、失恋のショックなどの、等身大の体験であったことにとても共感できて、すんなり中身を読み進めていけた。面白かったし、分かり易かったです、
0投稿日: 2012.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中学生の頃に疑問に思うこと・・・「なぜ、勉強しなければならないの?」 大人達の答えは、常に説得力がない・・・良い高校、良い大学に進学し、 良い職業に就くため、そして高い収入を得ることで、幸せになるために・・・ 中学生は、疑問に思う・・・「それが本当に幸せになる手段なの?」 この本には、こう書いてある。 「勉強するのは、まさに『生き方を選ぶ自由』をえるためだと。 私たちがより良く生きるためには、考える力が必要だ。この本には、 私たちが考える力を身につけるために必要な思考のテーブルがある。 私が、中学生だった頃に出会いたかった素晴らしい内容がある。 でも、かつて中学生だった私のようなオジサンにもおススメです。
0投稿日: 2012.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログまえがきには本の構成が簡潔にまとめられていました。 後半は例などを用いて説明されていたので読みやすかったと思います。 ただ"中学生からの~"と言うには、前半は少し難しいかも。
0投稿日: 2012.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
中学生には多分難しい。 けど読めないことはない。 社会とは相互承認で作られている。 犯罪的な裏取引も、そこにお互いが認めたルールがあるから成り立つ。 (悪の組織もルールを守っているから成り立つなんて…) 子供時代は親や周りのごく親しい人との間だけで、自分のルールを作っていく。 大学や社会に出て、自分と異なるルールを持つ相手と出会い、衝撃を受け、お互いのルールを少しずつ変えていきながら社会を作っていく。 (衝撃を受け、自己ルールが崩れて組み立てなおしになる人も多いそう。私自身もいままさにそういう状況だったので染み入った。) 幸せの話、みんなが求めているものを人間は欲しくなるけれど、みんなが求めているものは手に入りにくい。 (可愛いくて若い女の子に愛されたい!大金持ちになってみんなに尊敬されたい!) 本当に自分が欲しい物を突き詰めていくと、幸せは意外と手に入りやすくなる。 (本当は愛されたいだけ。なら美人じゃなくても、自分自身を理解してくれて愛してくれる人でいい。 尊敬されたいだけ。ならお金持ちにならなくても心がけ一つで立派な人間になれるかもしれない)
0投稿日: 2012.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすく書かれているのはわかるが、それでも理解しきれなかった。もう少し読解力をつけてまた読み直したい。
0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学の入門にはまさに最適な一冊と思える。 哲学的ものの考え方、どんな人がどんな考え方をしたのか、 この著者の哲学感などが分かる。 ただ、中学生には難しいんじゃないかなあ。
0投稿日: 2011.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあることはかなり難しいかも。宗教は「権威」のゲームになっていく傾向がある、哲学はどんどん難しくなっていく傾向がある、というのはいい対比だと思う。
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 自分とは何か。 なぜ宗教は生まれたのか。 人を殺してはいけない理由は何か。 何となく幸福じゃないと感じるのはなぜなのか…。 読めば聡明になる、悩みや疑問に対する哲学的考え方。 [ 目次 ] 1 自分とは何者か(神経症-私はなぜ哲学者になったか 欲望論哲学の出発点) 2 世界はどうなっているか(宗教のテーブルと哲学のテーブル 哲学のテーマ-「神」と「形而上学」について 宗教と哲学の弱点) 3 なぜルールがあるのか(大貧民ゲームで近代社会を体験する) 4 幸福とは何か(ガウェインの結婚-「自分の意志を持つこと」) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
1投稿日: 2011.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めの章は読むのが非常に苦痛だったが、宗教の辺りから何とか楽しめるようになった。 何も知らない苦手分野については、解説書を良く読むのだけど、この本はそういう類ではなく、あくまでも「入門」ということなのだと納得。
0投稿日: 2011.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自己ルール」を再確認し「一般欲望」を吟味することが自分の意志を持つことにつながる. →世間で言われる成功なんてほんの一握りしかできないんだからそれを追い求めてもよっぽど才能ない限り心体おかしくなるだけ. 自分の中で折り合いをつけることが大事.
0投稿日: 2011.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「一般欲望」とはべつに、自分はこのように生きよう、このような生き方をしたいという、自分固有の生の目標を見出すべき。 「自分の意志をもつこと」こそは、現代社会に生きるわれわれにとって、最も大事なテーマ。
0投稿日: 2011.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、いわゆる過去のビッグネームの思想を紹介するような哲学書ではなくて、著者が哲学するようになったきっかけ、哲学に興味を持つようになったきっかけが核となっている。本のタイトルにもあるように、まさに「自分の意思を持つということ」について書いてあると思ってもらって構わない。 目次 Ⅰ.自分とは何者か Ⅱ.世界はどうなっているか Ⅲ.なぜルールがあるのか Ⅳ.幸福とは何か 哲学・思想関係の本としては、他のものよりもとても読みやすい。さらに、文章量も少ないので、サクっと読める。ただ、中学生には難しいかなと思う。
0投稿日: 2011.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011/01/17読了 中学生向きではない。読むのにもセンスがいる。ただ、哲学書としてはいいほうじゃないかな。敷居は低くなったように感じるが。
0投稿日: 2011.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ己の知性は中学生以下と自覚して購入。案の定、ほぼストレスなく読了した。気になった箇所⇒世の中に、はっきりした答えを見出せる問いと、問うても決着の出ない問いがあるということ、このことが「原理」として腑に落ちていることは、どれだけ人間を聡明にするか解りません。これを理解できないかぎり、人は、いつまでも一方で極端な「真理」を信奉したり、一方で、世の中の真実は誰にも分からないといった懐疑論を振り回すのです。いわば「形而上学」とその反動形成で、表裏一体のものです。
0投稿日: 2010.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の方が逃げな感じがしたけど概ね分かりやすい 答が絶対でない問いの部分については理解できなかった というより完璧に反論できる気がする
0投稿日: 2010.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生向けに書かれた本であるが、正直半分も頭に入ったか疑問である。 しばらく時間を置いて再読したい本である。
0投稿日: 2010.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題は「中学生からの~」とあるが大人が読んでも全く差し支えはない内容。哲学を勉強することの切っ掛けになりそうな本。
0投稿日: 2010.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はわかりやすい。現代人の考えや悩みに沿った哲学の考え方が紹介されていて、読んでいてスッと頭に入ってくる。オススメ!
0投稿日: 2010.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ一枚目・二枚目・三枚目の世界像、不幸の意識、宗教と哲学の違い、現象学など目から鱗の内容が沢山あった。 タイトルは中学生からとなっているがこの本は2枚目の世界像が形成される時期の人が素晴らしいものに見える2枚目の世界像をさらに壊した先にあるのが本当の世界像だと言うことに気づかせるためにも、大学生くらいの人が読んだ方がいいんじゃないかと思った。あと、そもそも中学生には内容が少し難しい気もする。なんてかいたら今の中学生に怒られるのだろうか。
0投稿日: 2010.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分とは何か。なぜ宗教は生まれたのか。人を殺してはいけない理由は何か。何となく幸福じゃないと感じるのはなぜなのか…。読めば聡明になる、悩みや疑問に対する哲学的考え方。
0投稿日: 2009.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログひとつの ものごとの かんがえかたに ついて ていあん した ほん。 なんだ そんなこと か と おもうひと あれば こんなかんがえかたも あるのか と おもうひとも いるはず。 おすすめ。
0投稿日: 2009.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本だけではなく、竹田青嗣さんの本はとても読みやすい。中学生からとなっているが、内容的には大学生ぐらいの悩み始めた世代が対象かなという感じ。
0投稿日: 2009.07.14
