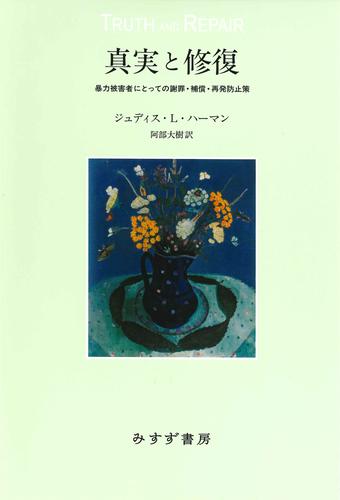
総合評価
(7件)| 4 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ性被害や児童虐待など、被害を受けた人を前に中立的姿勢はありえないことを痛感し、メンタルの治療というよりは、社会の中で性被害をきちんと認知し、修復してゆくプロセスが重要だという言葉は、第三者もコミュニティの一員として傍観者ではいられないことにハッとさせられました。
0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
被害者の視点から被害者の回復のために、社会は何ができるかを書いた本。ここ最近で一番納得する内容が多く、一気に読み進められた。最近、性被害のニュースが多く流れるようになってから、性加害者には厳罰化したほうがよい、という意見をXでよく見かけるようになった。もちろん、憤りがあることはもっともで、でも、そこには被害者の視点が入っていないような気がして、ずっと違和感があった。ハーマンも、被害者よりも周囲の人間のほうが、厳罰化を求めると書いていて、こういうことかと。でも被害者が何を求めるかを聞き取って、それを実践していくことが被害者の方の回復に役立つのだ。それが場合によっては厳罰なのかもしれないし、修復的司法なのかもしれない。ただ、一番中心に置くべき、被害者の方の声を皆がもっと真摯に聞いて社会が何ができるのかを考え、実践することが大事だと思う。皆の思うような怒りを勝手に被害者も感じていると誤解してはならない。もっと事態は複雑だ。だって、多くの加害者は被害者と顔見知りで同じコミュニティに属していることが多いのだから。被害者が加害者に怒りだけではない、いろいろな感情を感じて当然だし、周囲の人が傍観したり、加害者よりになることへの憤りもきちんと考えてほしい。 加害者をただ糾弾したり閉じ込めておくだけでは、見ないことにしているのと同じで、社会は何も変わらない。状況に怒って、すっきりしたことにしていないか。組織や周囲がもっと変わる必要がある。読みながらそんなことを思ったのと、ハーマンのずっと被害者の方への優しいまなざしがある著作で、それが胸に来た。2023年の著作をすぐさま翻訳してくださったことにも感謝。
1投稿日: 2024.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ医学とか心理臨床を超えてコミュニティや法整備などの問題も大きいよなぁと改めて思った。日本語訳はこなれていて読みやすい。また繰り返して読むべき価値のある本だと思う。
0投稿日: 2024.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん・・・。 なんかこう、基本的には、今の男性支配社会システムの中で、どう道徳のコミュニティを広げていくか、という話だった。 言わんとしていることは理解するのだけど、それって奴隷が御主人様におこぼれを乞うのとどう違うの?と思った。 例えばどんなに性売買のシステムが改善されても、女性が人身売買させられていることの根本は変わらない。 男性支配社会システムがいかに愚かであるか、その解体が必要で、その方法はおこぼれを乞うことではない、という作品が読みたかった。
0投稿日: 2024.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ『心的外傷と回復』がなかなか読めないでいてもどかしく思っていたところ、図書館の新刊コーナーで本書を見つけ、とにもかくにも借りてきた。 仕事柄、暴力被害者への対応をすることはよくあるのだけれど、頭では理解しつつ、こうしてはっきりと言語にしてもらえるとその意味するところがよくわかる。 修復的司法についても丁寧にわかりやすく触れられていて、改めて理解を深めることができた気がする。 暴力を手放すとは、暴力被害からの回復とは、そのための手立てとは。 結局のところ、どれだけ当事者が回復したところで、再発防止がなされなければ本当の意味での回復とは言えず、被害者加害者だけへの対策では足りないということだ。 暴力被害の解決には、社会の在り方そのものを問いただすことを通してしか繋がらない。 やっぱり、早く『心的外傷と回復』も読まないとな。
5投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ出版社(みすず書房)のページ https://www.msz.co.jp/book/detail/09690/ 内容、目次、著訳者紹介、書評情報 書評 「今週の本棚」20240429「毎日新聞」斎藤環による書評 https://mainichi.jp/articles/20240427/ddm/015/070/017000c 「まわりのひと」変える使命感 20240507「東京新聞」河原理子による https://www.tokyo-np.co.jp/article/325116 斎藤環による書評 20240526「ALL REVIEWS」掲載 https://allreviews.jp/review/6711
0投稿日: 2024.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
些細なことかもしれないが、ハーマンは本書の原書で性的暴行の虚偽告発はまれであると、2010年の研究を引いて次のように書いている。 "... false accusation, but in the matter of sexual assault, such complaints are rare, and concern about them in vastly overblown in the public imagination." (仮訳)「しかし、性的暴行の問題では、そのような訴えはまれであり、そのような訴えに対する懸念は、世間一般に大きく誇張されている。」 根拠にしている2010年の研究は次のもの。 Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C., & Cote, A. M. (2010). False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases. Violence Against Women, 16, 1318–1334. ところが性的暴行の虚偽告発についての研究は上の2010年の研究以降も積み上がって、2019年の本 "Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention"の次の章にまとめられている。 Understanding False Allegations of Sexual Assault William T. O’Donohue この本では上の2010年の研究について次のようにコメントされている。 "Nonetheless, the methodology used in this study has the fewest limitations of the literature reviewed in this chapter and yet yielded similar false allegations rates to previous studies. However, a significant percentage—nearly 14% were not coded in this study and 45% did not proceed forensically. If any substantial subsample of these were actually false then the rate of false allegations would be significantly higher. Taking these unknown cases out of the equation results in a false allegation rate of 14.3% (8/56)." 「それにもかかわらず、本研究で使用された方法は、本章で検討した文献の中で最も制約が少なく、しかも先行研究と同程度の誤判定率をもたらした。しかし、かなりの割合(14%近く)が本研究でコード化されず、45%が法医学的手続きに進まなかった。もし、このうちのかなりのサンプルが実際に虚偽であったとすれば、虚偽の申し立て率は著しく高くなるであろう。これらの不明事例を方程式から除外すると、虚偽の申し立て率は14.3%(8/56)となる。」 ハーマンの"Truth and Repair: How Trauma Survivors Envision Justice"が2023年刊行なので、性的暴行の虚偽告発については2019年刊行の"Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention"も参照できたはずだが、それをやらずに新しい知見を見なくなったのであれば、研究者の振る舞いとしては残念な気がする。
1投稿日: 2024.02.24
