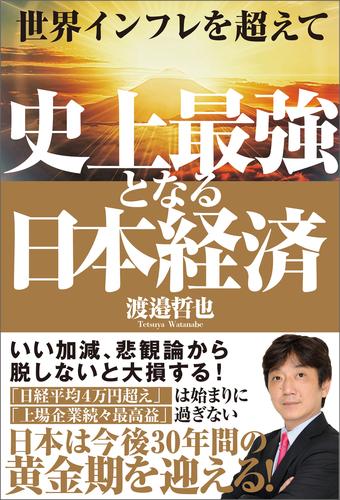
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ私事ですが社会人になったのが平成元年、その年末にバブルのピーク(日経平均最高)を迎え、年号が変わった2年に不況が起きてきたように(昭和2年、大正2年、恐らく明治2年)ほぼ社会人生活を続けた35年間は不況の日本で暮らしてきました。 インフレは子供の頃の微かな記憶はありますが、30年以上も同じような生活をしていると、いざインフレが来てもどう過ごしていけば良いのでしょうか。その間に日本のGDPは中国やドイツに抜かれて、私の生きている間に、インドやインドネシア等にも抜かれていくと予想されています。 日本の将来を憂う本は本は沢山出ていて簡単に手に取れそうですが、その反対の内容である本書のタイトルには惹かれるものがあり読むことにしました。この30年間足踏みしていたから、これから30年はその揺り戻しで成長する、という単純な話では無いとは思いますが、デフレ化の資産運用は「とにかくお金を稼いで現金を大切にすべし」だったと思います。散々失敗してきたからこそ私が学んだ教訓ですが、これからのインフレ時代は「お金の価値が下がっていく時代」なので、本気で資産運用を考える必要があると思います。 この本を参考にして人生の後半戦の中観以降を自分らしく過ごすための指針がこの本から読み取れたので嬉しく思いました。 以下は気になったポイントです。 ・日本は賃金がなかなか上がらない状況が続いている、しかし今こうした状況が大きく変わろうとしている。その大きな原因となったのが、米中対立やロシアのウクライナ侵攻から始まった東西の新冷戦、そして新型コロナの流行である。国家間の対立は再び国境に壁をつくり、さらにコロナによって、人・モノ・カネの流れは強制的に遮断されてしまった。やがてそれらは再開されたが、この間、生産拠点を中国から自国に移すなどのサプライチェーンの再構成が進み、東西の新たな冷戦はますます強化するようになった。これによりインフレが世界を覆っている、グローバリズムによるデフレの時代から、新冷戦のインフレへの時代へと巻き戻しが起こっている(p4) ・いまだに景気対策のために「国債を刷ってお金をばらまけ」という人がいるが、それはデフレ時の策であり、需要が供給を上回っている状態でそれを行えば、さらにインフレを促進する。景気がよくなるのではなく、単にインフレになるだけ(p20) ・なぜ日本だけが30年もデフレになったのか、1)バブルが崩壊した時期、冷戦終結・グローバリズム(低価格・低賃金競争)開始の時期が重なった、2)消費税の導入と税率引き上げ、3)日本人口が人口ボーナス(人口増加による経済拡大)の時期から、人口オーナス(減少による経済縮小)へと転換した、4)阪神大震災、東日本大震災により円需要の高まりから円高、それにより輸出競争力が低下し海外に生産拠点を移しデフレ化が促進した(p31) ・現在の冷戦環境(2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻、アメリカによる中国デッカプリング(外し)、23年10月のハマスのイスラエル攻撃によるグローバリズムの終焉)(p39)は、日本にとって決して悪いものではない。日本を経済成長に導いたのは、前回の冷戦で、日本が世界で最も輝く時代が続いた(p41) ・物価下落が継続的に起こるデフレスパイラルにより、日本の産業を破壊し商店街を壊し、人々を貧しくした。ダイエー、長崎屋、ニチイ、マルエツ、ダイイチ、サティなど、かつては大量にあったスーパーマーケットのグループも、吸収合併を経て、今では、イオンとイトーヨーカドーの2大グループにほぼ集約された(p53) ・新たな冷戦により、日本を長期のデフレに追い込んできたグローバリズム、中国、脱原発からの脱却が進みつつある。日本を弱体化させてきた元凶を排除することは、すなわち、かつて世界最強と言われた日本経済を取り戻すことでもある(p97) ・日本のメディアは円安の悪影響ばかりを宣伝するが、円の下落は実はプラスの側面の方が強かった。国際競争力が回復して輸出に大きなプラス効果が出た。2023年6月の貿易収支は、23カ月ぶりに黒字を計上した、輸出も半期で最高額を記録した(p62) ・長期のデフレは日本企業の体質を非常に強くした、2022年世界のインフレ率(8.8%)に対して、日本は2.3%、各国が高いインフレ率に苦しむ中、日本は低いインフレ率に抑えることができあた。企業の体力強化により、マイルドなインフレに転換できた、これから問題となるのが賃金上昇である(p64) ・帝国データバンクが2022年12月に行った企業動向調査によれば、海外展開している4社に1社が国内回帰、国産品への切り替えを実施、検討していると回答した。エプソン、アイリスオーヤマ、ワールド、JVCケンウッド、製造大手も製造拠点の日本回帰を発表している(p69) ・現在光ファイバによる高速通信が行われているが、有線であるが故に、最寄りの基地局から利用者の建物までを結ぶ通信回線の最後の部分(ラスト1マイル)をどのように接続するか、それにかかるコストが大きな問題となっている、これを解決するには、ワイヤレス化が必須である。そこで、光信号を使った革新的な半導体により、処理速度を上げて、なおかつ消費電力も大幅カットするのが、IWON構想である。これまでのサーバクライアントの形も大きく変わり、自動車の自動運転も通信ネットワークを中心としたものが可能となる。また、電波による電力送信ができれば、携帯電話の充電が不要になり、電力消費が100分の1になる(p84) ・これまで半導体製造装置は、基盤に光で回路を焼き付け、フッ化水素でエッチングを行う露光方式であった、これはオランダASMLが特許を抑えている。これに対して、キャノンの開発した、ナノインプリント方式(ハンコを押すように半導体回路を作る)は、特許をキャノンが抑えて、コストはASML方式より1桁安い、半導体の分野で日本が再びトップを独創する日も遠くない(p87)オンリーワン技術をどうやって温存し、海外流出を守るか、日本だけでできない部分については、アメリカはじめ西側陣営と協力していくことで進めている(p95) ・欧州では電気代の高騰でEVに対する逆風が強まっている、さらに様々な問題点も明らかになりつつある。中国や欧州がEV 開発に注力している理由の1つは、日本のピストンリングを使った、エンジンやタービン技術に対抗できないから(p96)ガソリン車をEV に変えるには、電池の材料であるニッケルが地球3回分必要、ボディは電池が重いので、アルミダイキャスト(鋳造)となる、大きな欠点として溶接できないので、破損時にはユニット全交換となり修理代がかかる、700万円のEV に修理代が500万円というケースもある(p98)電池の寿命は8年間(テスラ)で保証しているが、それ以降は実費交換になり、300万円近くコストがかかる、中古車市場でも4年以上使用した車両はほとんど売れないだろう(p99) ・アメリカのハーツレンタカーは、2024年1月所有するEV 2万台を売却し、ガソリン車に切り替える決定をした、その理由として、修理コストの高さとレンタカーとしての人気低迷を挙げている。欧州でもEU は2035年んびガソリンを使うエンジン車を禁止して全てEVにするという方針を、わずか1年で転換しエンジン車も容認することを決定している、太陽パネルも廃棄時に有害物質が生じる問題もあり環境のためになるのか疑問の声が出ている(p100) ・石炭の利点は、保管が簡単だということ、液化天然ガスは揮発していくので備蓄は60日程度、石炭は180日以上ある(p113) ・2023年11−12月にかけて、COP28(アラブ首長国)が開かれた合意文書では、草案の「化石燃料の段階的廃止」は削除され「化石燃料の段階的削減」にトーンダウンした(p115)議長国の先端技術相は、気温上昇を1.5度に抑えるという目標のために化石燃料の段階的廃止を求めることは「科学的根拠はない」と発言した(p123) ・アメリカでは2023年3月、グリーン(環境)投資に注力し、エコに関連した債権の60℃を扱っていたシリコンバレー銀行が破綻した。これも中間選挙で共和党が下院の過半数を取ったことが大きな原因となっている。下院は予算の優越権を持っている(p117) ・自民党内で脱原発・再生可能エネルギーを推進してきたのは、2016年に発足した再エネ議連(菅元首相、二階元幹事長、小泉元環境大臣)で、従来の電気事業連合会体制に関わることができなかった議員たちであった、岸田政権により、菅グループと二階派が党内野党化して、2023年9月に再エネ議連の秋元議員が収賄容疑で捕まって力を失った。23年3月には、岸田首相、麻生副総裁、森山選挙対策委員長が主体となって「国産再エネ議連」が設立されて、エネルギー政策においては、原発議連・再エネ議連・国産再エネ議連という、3巴の戦いになり、再エネ議連が弱体化しているのが2024年初頭の状況である(p121) ・中国の地方政府の債務は公式発表で35兆元(700兆円)だが、地方融資平台の債務は公式統計に含まれず、こうした簿外債務のIMFによる推計は66兆元(1320兆円)であり、全体では2600兆円と見積もられている(p134)中国の不動産価格は適正価格の3−5倍、人口の2−3倍住宅が余っている状態では、現在の価格の6分の1ー10分の1まで下落が続くことになる。日本のバブル時は、年収倍率の18倍まで上梓したが、バブル崩壊により3分の1に下落した。(p138)中国では、不動産デベロッパーの破綻を認めないので潰れないで残っている。裁判所が破産を認めないので会社は潰れていない(p141) ・中国の現状はどのような形で解決するか、1)市場原理に従って完全にバブルを崩壊させ、国民全体がダメージを受けながら再建に向かっていく(かつての日本)、2)資本主義経済を諦めて再び共産主義に戻っていく、全てを国有化して完全な統制経済となる。西側諸国と同じ市場で共存できないので、デカップリング(切り離し)が進んでいく、現在の習近平政権が行なっているのは、完全に後者であり「現代の文化大革命」の状況になっている(p153) ・2019年イタリアを一帯一路に加盟させて、G7で唯一の加盟国になり、ベネチア港を一対一路の終着点にすることを目論んでいた、しかし2022年の総選挙で、悟空のメローニ首相が選出されて政権交代が起きた。2023年12月に一帯一路を正式に離脱を表明した。さらに、紅海とバブ・マンデブ海峡封鎖の影響(シルクロードにおけるチョークポイント)が深刻化することで、海の一対一路は破綻することになる(p168) ・中国との関係を見直す国が増えつつある、特に中国の「借金の罠」に苦しめられている国は西側陣営につくことによって、債務の8割をチャラにしてもらえる魅力は大きいだろう。2023年11月には、アルゼンチンで反中右派のミレイ大統領が誕生、2024年1月にBRICSに加盟予定であったが、参加取り止めを明言している(p172)23年8月には、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国が加盟することに合意したが、候補だったインドネシアは加盟を辞退(p178) ・ロシアがウクライナ信仰をした理由として、東部4州を支配下におくことでクリミア半島(黒海艦隊・セバストポリ、軍艦の建造基地)までの陸路を確保したかったから、そこから国会に出て、トルコのボスポラス海峡を経て、地中海、アラビア海、インド洋に出ていくが、トルコはボスポラス海峡を制限したので、ロシアにとっては黒海が完全に機能不全になった(p186)さらにスウェーデンがNATOに入ると、バルト海のロシア艦隊は完全に機能不全になる、バルチック艦隊の司令部は、ポーランドの真北にあるカリーニングランドにあるから、すると、結果的に日本真北の、ウラジオストック・ナホトカに多くの軍艦を集中させることになる(p189) ・サウジアラビアなど、多くのアラブ諸国がスンニ派である一方、シーア派の中核をなすのがイランであり、中東各地にシーア派は点在する、問題となっているのは、シーア派の武装組織である、イエメンのフーシ、レバノンのヒズボラ、ガザのハマス、その背後にはイスラム革命防衛隊(イラン国軍)がいる。このため、イスラエルは多面線を迫られ、ガザ地区・レバノン・シリア・ユダヤサマリア地区(ヨルダン川西岸)・イラク・イエメン・イラン、の7方面戦争の様相を示している、イランを除けば一種のゲリラ部隊で、正規軍相手の戦いにならない、ある意味、ベトナム戦争と同じで泥沼化する(p193) 2024年7月23日読破 2024年7月26日作成
0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界は複雑になっている。 ウクライナ問題、古くからあるパレスチナ問題、同じ国とは思えないくらい分裂しているアメリカ、経済はどうなっているのかよくわからない中国など。 そんな中でも日経平均株価は、上昇を続けている。 先週の金曜日に、バブル期に記録した3万8915円まであと少しのところまで達したが、下げて終了した。 以前、週刊東洋経済の記事で、中国は世界の知見を学んでいるというようなことを書いている人がいた。 それなのに不動産問題で多額の債務を抱えていると言われている。 「クマのプーさん」と揶揄されるあの最高指導者の権力維持のために、個人崇拝を進めたり、自分の都合の良い人材(人罪といったほうがいいか)を登用したり、「巨大な北朝鮮」を目指しているのかと思ってしまう。 中国人の不動産投資に対する熱狂ぶりには目が丸くなる。 日本はお人好しなので、技術を提供していてオウンゴールを連発している。著者が例に挙げている日本の新幹線技術がいつの間にか中国産に化けている。 米中対立で日本は「漁夫の利」を得る絶好のチャンスが到来している。 熊本や北海道で、半導体工場の建設や計画により、特に熊本で、アゲアゲになっているとメディアが取り上げている。 EVは環境によくこれからの時代をリードするかのような幻想をメディアは垂れ流している。 ところが寒い地域ではEVは役に立たず、しかも電池の寿命は短いなど裏の顔が露呈して、EVに依存から方針転換する国や会社も現れた。 ハイブリッド車で定評のあるトヨタ自動車が見直されて、このところ株価がアゲアゲフェスになっている。 財務省が増税病にかかり、アゲアゲムードに冷水を浴びせるようなことをしなければ、日本経済に明るい未来が見えてくるかもしれないなあと思った。
0投稿日: 2024.02.18
