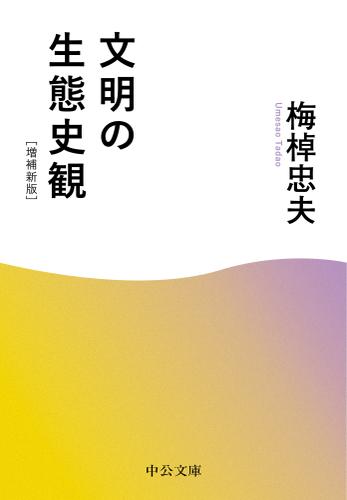
総合評価
(6件)| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ比較文明学者(敢えてこう呼ぶ)の梅棹忠夫博士による表題作を含む十二の論考。彼の主張でユニークなのはユーラシア大陸を間の「乾燥地帯」で第一地域と第二地域に分け、封建主義から自己発展的という意味合いに置いて日本文明と西欧文明を同一視する「平行進化説」という考え方である。 また、本書ではその思想の変遷や深化が彼自身のフィールドワークを通して高度化していくのが読み取れる点が興味深い。インドを西洋でもなく東洋でもなく「中洋」と称するに至る体験は随筆としても面白い。 世界の文明を構造で捉える説はフランシス・フクヤマ氏やフランシス・フクヤマ氏など幾つかあり、現代となっては梅棹氏の説はややシンプル過ぎるきらいはあるが、日本初の小論として切り口の鋭い分析として教養になる一冊。
1投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【全体の主張】 人類の文明の発展には「生態(自然環境)」と「社会構造」の相互作用がある。 特に、ユーラシア大陸を東西に分けて、「東の世界」と「西の世界」の違いを軸に文明の成り立ちを分析します。 ⸻ 【文明の分類】 梅棹は、ユーラシア大陸を中心に世界を以下の2つに分けて考えます。 1. 第一地域(西ユーラシア) •中心:ヨーロッパ・中東 •特徴:牧畜を基盤とした移動型の生活文化 → 激しい宗教対立(例:キリスト教 vs イスラム教) •文明:発展は早かったが、宗教や階級社会に縛られがち 2. 第二地域(東ユーラシア) •中心:日本・中国・東南アジア •特徴:稲作を基盤とした定住型文化 → 比較的平和で柔軟な文化(例:仏教受容) •文明:発展は遅れたが、近代化に成功しやすい素地がある ⸻ 【文明発展の2段階モデル】 文明の発展は以下のように進むと説きます。 1.第一段階:文字文明の確立(古代) •文書による記録、法制度、国家の成立 2.第二段階:情報文明の確立(近代) •印刷技術、通信、教育普及 → 知識社会・民主主義の土台に → 日本は、この**「第二段階への飛躍」に成功した例外的な文明**である、と位置づけられています。 ⸻ 【日本文明の特異性】 •西洋を模倣したわけではなく、独自の価値観と文化で近代化を達成した •明治維新〜高度成長期の近代化は、**「東の文明が西を追い越す転換点」**になりうる ⸻ 【本書の意義】 •近代西洋中心の「世界史観」や「進化論的歴史観」を批判 •日本を含むアジアの文明に新しい誇りと視座を与える •現代のSDGsやポスト成長社会を考える上でも示唆に富む
0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ考察の対象をアジア、欧州、北アフリカに限定し、西欧と日本の東西両端を第一地域、それ以外を第二地域として世界史を説明した本です。 第二地域は、文明の発祥地だが、常に乾燥地帯の遊牧民からの侵攻を受けて発展が阻害されるが、第一地域は、優れた文明が伝播する程度に第二地域に隣接する一方で、遊牧民の侵攻から逃れられる程度に第二地域から離れているため、発展した。。大まかにまとめるとこんな感じの理論と理解しています。さらに、広大な第二世界をインド、中国、ロシア、イスラム•地中海、東南アジア、東欧に区分して、それぞれの特徴を論じています。 元々、この本を読む前に著者の「文明の生態史観」という考えを知り、それを詳しく知りたいと本書を読みましたが、全体的にエッセイ的なテイストであまり体系的に生態史観が説明されておらず、少し物足りませんでした。 理論そのものについては、数十年前の日本でやりがちだった、西欧文明に羨望を抱く一方で他のアジア諸国を下に見て、「日本はアジアの中でも特別で西欧に近い」という論理になっていないか注意しながら読んでいましたが、そういう理論ではなく、新しい観点から世界史の整理を試みた理論だと思います。ただ、「インドや東南アジアって破壊的な影響を遊牧民から受けたっけ」など、理論の骨子となる部分に疑問がありますし、いくら何でも第一地域と第二地域の二元論で語るのは大雑把すぎる気もします。 正確かどうか、或いは有用かどうかは私の知識では分かりませんが、総じて言うと、非常に面白い考え方だと思いますし、何より著者自身が考えてこうした新しい視点を考案できるのはすごいと思います。
5投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本と西ヨーロッパを第一地域、それ以外の旧世界を第二地域とする考え方、また第一地域において早く近代化が進んだ背景は興味深かった。一方で、その内容はYouTubeである程度知っており、それ以外ど新たにおっ!と思う内容に出会えなかったのが残念。また読み返したい
0投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ実は先に「文明の生態史観はいま」の方を途中まで読んでいたが、これは対談であってやはり先に「文明の生態史観」を読まないと分からないと思った。それでこの本を読み出したのだが、全く今読んでも現在を体現しているように感じる。それは最近読んだ「地球史マップ」というビジュアルな分厚い本と、もう一つ、「小麦の地政学」。その中に先生の言われている楕円形の地図がでている。 「ひずみなき世界の姿を」で全地球的な課題について比較文明論を考えることはできるはずだ、と先生は言われている。 50年経ってこれほど繋がったこの本と地球史マップ はありえない、と感動した。 第1地域と第2地域の知識人における政治的意識と政治的実戦のあたりも大変興味をもった。 最後の比較宗教論は難しいかったけれども免疫との展開の仕方には、こんな方法もあるのかと目から鱗だ。 実際に世界を歩いて生活や環境を見てきた人には敵わない。大いに世界を歩いて観ることと今の若い人にこの本を勧めたい。
0投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ東西の対立的座標軸で捉えられてきた世界史に生態学の視点を導入した比較文明論の名著。著者の到達点を示す「海と日本文明」を増補。〈解説〉谷 泰
0投稿日: 2023.11.13
