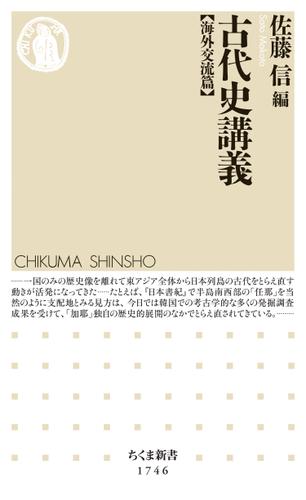
総合評価
(4件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本古代史の最新研究成果を総覧する入門書シリーズの一冊。邪馬台国から平安初期までを対象とした十五講を通読することで、日本の古代国家成立過程が国際環境との相互関係にどう規定されていたかが良く分かる内容だった。
0投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『古代史講義』にも色々あって、今回は「海外交流篇」 中学生の時に任那日本府はなかった(泊勝美)を読み 驚いた記憶がある、以来肯定否定の繰り返しで時々は 確認したくなるとともに、実態は兎も角遥か古代から 半島と人も文化・製品も交流があるのが当時の社会だ なとおもいがとぶ (倭の五王の上奏文で将軍号を授けられているので、 なんらかの武力的優位がある関係があったと思ってい る・・・知らんけど) だから「第4講 加耶と倭」で「任那日本府が特定の 問題のために派遣された使節云々・・・」は不承知だ
0投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> 第1章 「魏志倭人伝」と邪馬台国 第2章 倭の五王とワカタケル大王 第3章 筑紫君磐井と東アジア 第4章 加耶と倭 第5章 百済と倭 第6章 高句麗と倭・日本 第7章 新羅と倭・日本 第8章 仏教の伝来と飛鳥寺創建 第9章 遣隋使と倭 第10章 白村江の戦いと倭 第11章 渡来人と列島の日本 第12章 奈良時代の遣唐使 第13章 鑑真の来日 第14章 渤海と日本 第15章 鴻臚館と交易 <内容> 古代史講義シリーズの第5弾。昭和史シリーズとともに一番熱心?。それだけ研究が深化しているのだろう。確かに、授業で教えていることにカビが生えかかっていることを実感した。また渤海の話や鴻臚館の話は余り知らなかったところなので、面白かった。
0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史学の最新の研究成果と研究動向を提供することを目指す、ちくま新書の「〇〇史講義」シリーズ。本書は、『古代史講義』の海外交流篇。 「はじめに」でも言及されているが、自分の学生時代には、半島南西部に任那日本府というものがあり、562年(任那でころぶ)に滅んだと学んだ記憶がある。本書全体を通読して、東アジア全体から日本列島の古代をとらえ直さなければならないのだなと痛感した。 興味深かったのは、まず「第4講 加耶と倭」。日本書紀の記事の史料批判、そして任那日本府が特定の問題のために派遣された使節であったことなど、最新の研究成果に触れることができた。また、第5講以下では、百済、高句麗、新羅の三国との、数世紀にわたるパワーゲーム的な関係を深く学ぶことができた。 そのほかの各講により、中国・朝鮮半島から渡来した人や鉄器その他の物、また仏教、漢字等の文化など、様々な文物の交流の様相について最新の知見に触れることができる。
1投稿日: 2023.09.13
