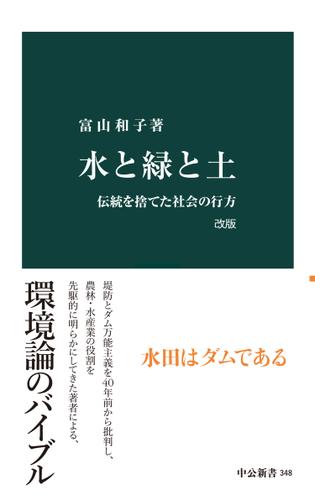
総合評価
(6件)| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ有吉佐和子の「複合汚染」の中で紹介があったので読んでみた。今につながる問題。 日本人も明治維新以前は、先人の経験の積み重ねにより、人々は自然に対する深い叡智を持ち、謙虚に自然と向き合っていた。が、明治維新以降、短絡的な目的志向が効率的・科学的、先進的と勘違いされ、また自然と切り離される人々が増え、水も緑もも土も、結果的にどんどん狙いとは反対の方向に向かってしまっている。もとに戻すのは事実上ほぼ不可能。人間が地球を破壊している。気づき始めている人はいるが、その対処方法はまたまた近視眼的なものになってしまうのだろうか。恐ろしいことだ。
0投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1974年に初版発行の名著。自然を機械的に捉えるべきでないこと、土地利用の多様性が持続可能性を高めること、伝統を捉え直すことが科学であるなど、現代においてなお響く指摘が多い。刺激を受けた。
0投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然界の「分業化」に警鐘を鳴らした日本環境論の古典。本書は1990年の時点で28版を重ね(初版は1974年)、2010年には新版が出るなど、長年にわたって読み継がれてきた本である。 著者の主張を要約すると、本来は水(河川)と緑(森林)と土(土壌)は一体のものであり、長い年月をかけて相互補完的な関係を築き上げてきたという。しかし、高度成長期の都市開発が、自然界を「分業化」させてしまい、その結果、より多くの環境問題を引き起こすことになった。例えば、治水事業として各地に築かれた「堤防」は、水と緑・土の繋がりを断ち切ってしまったため、これまで森林や土壌が吸収していた水や土砂が全て河川に閉じ込められ、より大規模な水害を引き起こすことになったと著者は批判する。また、ようやく取り組まれ始めた自然保護政策も、その「分業化」を前提にしている点では変わらず、効果は限定的であるとも述べている。 本書は、こうした都市開発による自然破壊をただ糾弾するのではなく、そうした開発を是とする人々の「思想」にまで遡って分析を行っている点が興味深い。現代の日本が抱える環境問題の”原点”を学ぶ上で、非常に参考になる一冊である。
0投稿日: 2019.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログかつて自然を愛し自然に対応して生きる民族であった日本人が,なぜ現在のように自然を破壊するようになったか。この本は1974年に書かれたものだけれど,現在の日本に通ずるところは沢山あると思う。日本の国土に住んでいる人達皆に読んでもらいたい。
0投稿日: 2012.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] [ 目次 ] [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「私はこの国土で行われてきた破壊の事業のあとをたどりながら、そのどこに誤算があり、誤算はどのようにして生まれたか、その秘密を探って行きたいと思う。」という序章のとおり、水を、農地を、国土を“破壊”したこの国の業績をたどっている。 2010年7月刊ではあるが、1974年発行の改訂版なので、事例としては昭和のものが紹介されている。しかし恐ろしいことに、その問題は今日でも同じ軌跡をたどっていることが見て取れる。
0投稿日: 2010.09.14
