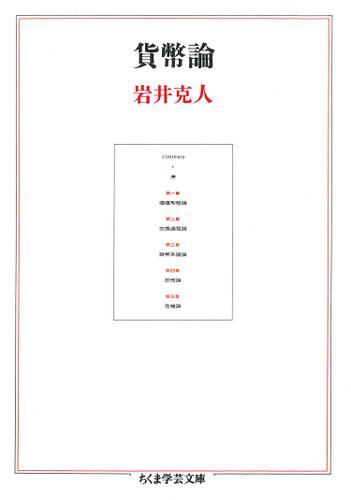
総合評価
(31件)| 5 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣とは何か? この問いの深淵さ、「意地の悪さ」に初めて気がついたのはマルクスだ。 マルクスは貨幣を「形而上学的な奇妙さに満ち満ちたもの」と呼んでいる。 貨幣を当たり前だと思わずに、そこに形而上学を見出したことこそマルクスの天才だ。 貨幣を形而上学的謎として解くためには、マルクスの「資本論」、特にその「価値形態論」を抜きにしては、アプローチする出来ない。 と、言うことで、岩井克人は、マルクスの「資本論」を自家薬籠中のものとして、縦横に活用する。 本書は、岩井克人によるマルクス「資本論」の独創的読解だ。 さわりの一章だけをざっと見るとこんな感じだ。 第一章 価値形態論 資本論の要である「価値形態論」と「交換過程論」から貨幣登場のメカニズムを炙り出す。 貨幣は貨幣として流通してしているから貨幣なのだ。 このトートロジーこそが謎の根源だ。 神の成立と同じメカニズムに基づく社会現象だ。 したがって、マルクスの「価値形態論」は、貨幣論に留まらず、神の発生論でもあり、更には、言語の発生論、国家の発生論でもあるのだ。 経済学、宗教岳、言語学、政治学の根幹に存在する形而上学的謎を、トートロジーとして「価値形態論」として抉り出して見せたのだ。 そして、価値形態が生まれてくる(つまり、貨幣が、神が、言語が、国家が生まれてくる)メカニズムを「交換過程」と言う動的な相で捉えてみせるのだ。 そして、貨幣が神となった特殊な資本主義社会的は、トートロジーの行き着く先、ハイパー•インフレーションという危機を招くと予言する。 トートロジーには実体はない。 実体の無い虚空から生じた「剰余価値」は、実体のなかった虚空の宇宙に生じた物質のようだ。 この「奇跡」が、実体があるかのように振る舞う貨幣を生み出した。 他人が貨幣として受け取るから、他人が貨幣として信ずるから、貨幣として機能するのだ。 そして、剰余価値は剰余価値を生み出し続けて、巨大な価値のハイパー•インフレーションを作り出すのだ。 こうして、貨幣商品説も貨幣法制説も葬り去る。 本書を十分に理解するためには、難しいマルクス「資本論」を理解しておくことが望ましい。 そのための最良のガイドが、柄谷行人の「マルクスその可能性の中心」だ。 第二章 交換過程論 第三章 貨幣系譜論 第四章 恐慌論 第五章 危機論 と続く。
1投稿日: 2024.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログある人が「貨幣に対する理解に役立った」と言っていたのを聞き、読んでみましたが、個人的には、あまり得るものがありませんでした。 「貨幣が貨幣であるのは、人々がそれを貨幣とみなしているからである」というトートロジー的な説明をひたすら繰り返しているだけに見え、果たして200ページも使う必要があったのか、謎です。 50ページもあれば、十分な内容な気がします。 ページ数が膨らんだのは、雑誌の連載だったのが原因ではないかと。 雑誌の連載であれば、やたらと同じような内容が出てくるのも納得。 貨幣の出現や歴史について知りたくて読んだのですが、その点においては得るものがなかったので、他の本にあたってみます。 投稿に関しては利用規約およびプライバシーポリシーをご確認ください。利用規約の禁止事項や免責事項
0投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩井克人の文章は比較的わかりやすいというのが従来の印象だが、この『貨幣論』は難しくて理解の突破口となる「引っかかるところ」がないまま最後まで読み進んだ。マルクス理論独特の難解で抽象度の高い論理展開で、纏めるのには相当大変だろうが諦めずに、ここから再々度の読み込みでなんとか整理してみる。この作者をしてもこれ程の表現にならざるを得ないのは、マクロ経済学における「貨幣」というものが簡単に説明できるような単純なものではないということなのであろう。同時に本質的なものであると思う。 貨幣形態・価値形態論と交換過程論・価値・商品価値・価値実態論・等価労働交換・交換価値・価格・貨幣起源の商品説と法制説・労働価値説・恐慌論・ハイパーインフレ・・・。 これらの概念定義と論理的な組み合わせによる貨幣の解明がこの論考のテーマである。
0投稿日: 2024.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログマルクス『資本論』(主に第一巻と第三巻)をベースに、著者が貨幣の本質に迫るのが本書の内容である。貨幣とは何かという問いに対して、「単純な価値形態」、「全体的な価値形態」、「一般的な価値形態」、「マルクスの貨幣形態」、「貨幣形態」と順に追っていくうちに著者はある結論を下す。それは「貨幣とは貨幣である」というトートロジーである。つまり貨幣には本質的なものはなく、貨幣について考えれば考えるほど、ますますその存在理由がわからなくなるという。経済学を専門とする著者がこのような奇妙な結論を導いたことから、貨幣が単なるモノとは異なる独自の性質を帯びていることが読み取れる。 また、第五章危機論で言及されたハイパーインフレーションの話も興味深かった。この辺りは、現在基軸通貨であるドルの行方を予測するうえでも非常に参考となるだろう。冒頭で挙げたように、本書はマルクス『資本論』を基に展開されるが、事前に読まなくても、読み進められる。その意味で『資本論』で語られた資本主義の分析の要点をこの本を読み通すことで学べるのではないだろうか。
1投稿日: 2023.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「われわれは今では価値の実体を知っている。それは労働である。われわれは価値の大きさの尺度を知っている。それは労働時間である。」 難しくて一回読んだだけではわからない。マルクスの貨幣論を修正しているようなんだけど、元のマルクスの貨幣論がわかってないから、どう修正したのかも当然わからない。でも恐慌が貨幣の存在によって起こるというのはわかった。 貨幣も商品であり、投入された労働量によって価値が規定されている、そんなことをマルクスは論じてるらしいけど、本当なのかはよくわからない。 それに対して、岩井先生は、貨幣の価値は「貨幣に価値があるのは、皆が価値があると信じているからである、なぜ皆は価値があると信じているかは、皆が価値があると信じているからである」という循環論法によって規定されていると言ってるように思う。 因果がそれ以上遡行しない地点として、因果の道の終着点としての循環論法で、線が円環に閉じているようなイメージか。 岩井先生の考えは、他の研究者からマルクスを誤読しているという批判もちらほら見かけた。マルクスの思想は、いまだ統一見解がされていないのかもしれない。
0投稿日: 2022.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
貨幣とは、自らが他の商品に直接的に交換可能性を与えると同時に、他の商品も貨幣に直接の交換可能性を与えるという位置に存在しているものである。 何がどういう経緯で商品から貨幣に変わるのかは、説明できない奇跡だと言う。マルクスは、恐慌(商品世界全体で起きる需要不足)こそ資本主義の本質的な危機であるとした。しかし、筆者はそれを否定する。資本主義にとって本当に危機的な事象とは、無限先の未来まで誰かが自分の貨幣を受け取ってくれ、そして受け取った人も他の誰かが貨幣を受け取ってくれるだろうという期待が持たれなくなってしまうことだという。すなわち、ハイパーインフレである。ある財の需要が過剰になると、売り手は価格を上げる。しかしながら、物価上昇は全ての財で起こっているのだから、買い手側からすれば今財を買っておかなければ買うのはどんどん難しくなる。これがハイパーインフレをもたらすのだ。
0投稿日: 2022.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログAudibleでランニングしながら聴取。学生の頃読んで以来30年ぶりの再読(というか再聴)。当時は四苦八苦して読んだ記憶があるが、今聴くと重要部分の繰り返しが多く、聞き逃しても筋が追えるため「ながら聴き」には意外に適している(書き下ろしでなく「批評空間」への連載だったことが影響していると推察)。 なんといっても本書の肝は、マルクス「資本論」他における価値形態論・労働価値論に潜む矛盾を「論理循環」の形で可視化させたことにあるだろう。価値形態論を突き詰めてゆくと実は論理循環が含まれており、そこではマルクス自身が信奉して止まなかった労働価値論の項が消去されてしまうことが示される。そしてこの論理循環は他に依拠するところのない、著者自身の言葉を借りれば「宙吊り」の構造を持っており、さればこそ、自律的に存立する強固さと、いったんその根拠を疑い出せば霧散してしまう脆弱さを併せ持っている。本書では著者一流のレトリックを用いて、資本主義における貨幣経済がこの「奇跡」の上に成立していることが明快に記述されている。「本物」と「代用物」という記号論的二項対立を、この連環構造の中に解消させてゆく著者の鮮やかな技量は今でも色褪せておらず、見事というしかない。 そしてもちろん、「恐慌ではなくハイパーインフレーションこそが、貨幣の存立基盤を突き崩し商品世界を解体する実存的危機である」という主張を含む本書は、実際に世界的インフレが進展しつつあるこの2022年にこそ特段の関心を持って読み返されなければならないと思う。
2投稿日: 2022.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣について近代経済学の立場から考察した著作。 著者はマルクスの価値形態論を批判的に検討していきながら貨幣の本質に迫ろうとする。 しかしその批判が成功しているかというとそうも言えない。 まず、第一に著者はマルクスの価値形態論の弁証法的展開を、時間的展開と誤解している。弁証法とはあくまでも概念の時間的発展であり、歴史の実際の時間的な発展ではない。それはいわば構造に関することであり、歴史に関することではない。マルクスが価値形態論で示しているのは、資本主義社会が成立しているある一時点における貨幣の論理的成立根拠である。それは資本主義社会の貨幣を考察するときに、貨幣形態からさかのぼって、一般的価値形態と全体的価値形態をたどり、単純な価値形態へと到達するのである。建物がどのように建設されたかは建設された建物が自重をどう支えているかという構造力学とは関係がない。 第二に、著者は労働価値説を批判することで、価値形態論を批判しているが、労働価値説と価値形態論は独立している。異なる労働は比較できない。マルクスが言うように、まず交換が成立し、そのことから逆にそれら両商品を生み出す異なる労働の価値が等しいと置かれるのだ。労働価値説は労働こそが価値であるという。それは価値とは何かと人々が自分で考えたときに導き出される結果なのであり、その意味で、前に書いたことと同様、構造にかかわることである。人々はそう意識はしないが、労働を価値として商品の価値を測っているのである。そもそも価値とは何らかの実体があるものではありえない。一種の信念・信仰である。兌換紙幣は金との交換を保証しているがそれは金が世界通貨だからだ。しかし金になぜ価値があるのかと言われると誰も明確には答えられない。端的に言えば他人が価値があると信じているから価値がある。紙幣が金と結び付けられてもそのことで価値の根源がはっきりするわけではない。だから著者が価値形態論への脱構築の試みの果てに、貨幣の根源に空虚を見出したのは当然のことである。 それでは価値形態論と労働価値説の関係をどう考えればよいか。 私自身は価値形態論を以下のように考えている。資本論の価値形態論は、商品世界を価値交換のネットワークとして描き出している。商品交換から価値を抽象物として取り出すことでそのことに成功している。マルクスが賢いのはすべてを労働価値という抽象価値に還元して考えたことだ。これを労働価値というのは仮の名称だと考えればよく、お望みならリンゴ価値だの貨幣価値だの呼んでいい。つまりある種の交換体系が成立しているのは、その抽象的価値が共通しているから、と「仮定」した。これは価値が現実に実体として存在している必要はなく、交換がそのように行われるということを意味しているに過ぎない。商品相互のある一定の量的交換関係が成立している社会体系では、ある一種の商品を選び出してその量によって、多種の商品の価値を測ることができる。その一種の商品を物差しとして使うわけだ。 そのように考えれば、具体的物体として存在する資本財を抽象的価値に還元して考えることができる。価値形態論では労働や貨幣が絶対的地位に置かれているのではなく、その地位が相対的であることを表しているのだ。つまり労働の代わりに価値をリンゴの個数で測ったり、貨幣量で測ったりしてよいのである。価値が任意の財の量であらわされるとすると、労働力商品の位置づけが重要になる。資本主義社会では、労働(労働量)を時間決めで売るわけではなく、労働力商品を売るのである。ところが、労働こそが価値の尺度なのだ! ここに資本主義社会成立の秘密がある。 マルクスはこの特殊な商品の価値を、その再生産に必要な価値の量によって定義する したがっていわゆる「搾取」と言われるものは、この労働力商品が現実に労働によって生み出した価値と、「資本価値の補填+労働力商品の価値」の差額のことだ。 重要なことはそのような一定の価値交換体系のあるところでは、利潤は労働の搾取によってしか生じえないということだ。労働価値説をとろうがとるまいが、そのことに変わりはない。それが価値形態論から帰結されることだ。(労働価値説を仮定しないマルクスの基本定理の証明はhttps://youtu.be/whTf28oaqHU) というわけで、著者は価値形態論の批判に成功しているとは言えない。魅力的な代替案は提示されておらず、常識的な近代経済学の立場に回帰し、「貨幣は神秘である、貨幣の成立は奇跡である」と問題を棚上げにしているだけのように見える。これなら価値形態論のほうがおもしろいし、説得力がある。 それでも貨幣の本質を考えさせるという意味では刺激的な本である。 著者は貨幣価値には根拠がないとするから、貨幣が商品よりも相対的に価値を上げるデフレーションよりも、貨幣が商品よりも相対的に価値を下げるインフレーションのほうを、資本主義にとって大きな危機であるとする。確かに資本主義というのはいわば貨幣信仰の宗教とも言えて、その成立基盤はあんがい危ういもので、無根拠があらわにされたときあっけなく崩れてしまうものかもしれない。
0投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白かった。貨幣の本質がよく分かった。 危機論における、ハイパーインフレで貨幣(→商品社会→資本主義社会)が機能しなくなると言う主張に関しては、論理的にはありうるだろうけど、実際的にはそんなこと起きるのか、非常に疑問であり消化不良を感じた。 ・全ての貨幣が一度に機能不全に陥ることなど起きるのか? (基軸通貨の死亡 = 貨幣の死亡とは個人的には思えない) ・貨幣が死んでも、「人間の本質」によって、貨幣は新たに創りなおされる のではないかと思う。特に後者に関して述べたい。 個人的に「貨幣とは、貨幣として使われるからこそ、貨幣なのであり、貨幣とは、流通するからこそ、価値を持つ。」と言う貨幣の本質には同意するし、貨幣は使われなくなったら (貨幣が下支えしている商品社会や資本主義社会もろとも)消滅する、と言うロジックにも同意している。 一方で、上記の「貨幣」や「貨幣の本質」を下支えしているものに「人間は交換する(したがる)動物である」と言う本質が存在するはずである。従って、仮にハイパーインフレで貨幣が死んでも(死にかけても)、この人間の本質によって、また新たに貨幣が創られるのではないかと思う。 ▶︎ 読書の目的: お金(貨幣)の成り立ちを知りたい → 貨幣の誕生は「奇跡」的な出来事。貨幣はいかにして生まれたか?という質問に対しては「貨幣商品説」「貨幣法制説」の2つの論争(前者:元々、様々な商品に交換することができる/みんなが欲しがる商品(家畜など)が貨幣として流通し始めたという説・後者:時の政府や権力者の命によって、貨幣として使われるものを生み出したという説)が存在するが、筆者はこのどちらも否定する。貨幣は、貨幣として使われるからこそ、貨幣なのであり、貨幣は、流通するからこそ、価値を持つ。この無限の「循環」こそが貨幣の本質であるので、「広い交換可能性を持っていたから(→)貨幣になった(貨幣商品説)」も「為政者が決めたから(→)貨幣になった」のでもなく、「貨幣だから(→)貨幣」なのである。 ▶︎ 概要 本書は、マルクスの思想を土台として、貨幣とは何かを考察する本である。本書の大きなポイントは2つあり、 ① 貨幣の本質 貨幣とは、貨幣として使われるからこそ、貨幣なのであり、貨幣とは、流通するからこそ、価値を持つ。 ② 資本主義の危機 貨幣の存在は、商品世界の存立の土台であり、資本主義社会の存続の土台でもある。上記に挙げた貨幣の本質を鑑みると、貨幣は、使われなくなると、貨幣では無くなり、流通しなくなると、価値がなくなる。つまり、貨幣の使用・流通が止まると、貨幣自体やそれが持つ価値が消失する。それはつまり、貨幣を土台とする商品社会や資本主義社会の危機を意味する。これまでの経済学では、資本主義の危機を需要不足/供給過多(流動性選好の増加)による恐慌に見てきたが、本当の危機は、需要過多/供給不足(流動性選好の減少・ハイパーインフレーション)にある。前者の恐慌の場合は、物価・需要の低下という負のスパイラルが、労働者の賃金の「下方への粘着性」(制度や人情などにより、人間の人件費はなかなか下げられないし、クビも切りにくい)によって、ある程度抑制される(ストッパーが存在する)が、後者のハイパーインフレの場合は、論理上はストッパーが存在しないため、貨幣が死ぬ(つまり商品世界と資本主義を破壊する可能性)がある。
0投稿日: 2021.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣が貨幣として通用するとは。 貨幣それ自身に価値かあるわけではなく、商品流通のための潤滑剤的役割。 しかし、人々が貨幣を主人公に祭り上げたとき、インフレが起こり、更に貨幣に熱狂し、最高潮に達したとき、ハッと我に帰る。これは、なんなのか。ハイパーインフレーションか目前だ。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣と哲学。一見無関係のようにも思われる両者だが、決してそうではないことを本書によって思い知らされた。 貨幣とは何か。その起源がそもそもはっきりしないことを明示した上で、岩井はまず貨幣そのものには価値がないことを確認する。確かに貨幣をいくら貯め込んだところで、使わないことには意味がない。貨幣は使うことによって、すなわち交換することによって初めて価値を付与される。ではなぜ何の価値もないはずの貨幣が交換されるのか? なぜわれわれは何の価値もない貨幣を受け取るのか? 岩井は答える。われわれが貨幣を受け取るのは、将来それを(商品と引き換えに)受け取ってくれる他者が必ずあらわれるはずだと信じているからだ。すなわち貨幣の根拠は未来への信憑にある。逆に言えば未来への信憑にしかない。しかしその信憑はそれほど絶対的なものだろうか。 商品には価値があり、貨幣には価値がない。貨幣の価値は、商品と交換できるという限りにおいての、いわばヴァーチャルな価値でしかない。そのことに人々が気づき、貨幣を捨て商品を取るという選択がいっせいになされたならば、すなわち貨幣信仰が崩壊し、貨幣の価値が限りなくゼロに近づいたとき、いかなる事態を招来するだろうか。 世界的な不景気が叫ばれて久しい。しかしだれもがお金を使おうとしない現状は、貨幣信仰が安泰であること以外の何物でもない。本当にこわいのはその逆のケースなのだと岩井は説く。「貨幣と商品の関係は言語と事物の関係にほぼ等しい」というあとがきも含め、哲学的刺激に満ちた貨幣論の名著である。
0投稿日: 2019.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩井克人『貨幣論』。マルクスの『資本論』への批評を足掛りにして、貨幣とは何なのかを考察する。貨幣について、またそこから、売買することについて、とても多くの洞察を示唆してくれた。経済の高度な概念はでてこないので、経済ってよくわからないけど、お金について考えてみたいひとに超おすすめ。 読んでて気になった点として、1)芝居がかった大仰な言い回しが多いのでたまーに鼻につく、2)最初はがっつり『資本論』そのほかマルクスの引用がたくさんでてくるので貨幣の本なのか不安になる、というところか。ぼくは、後半の恐慌論・危機論あたりの理解が甘い気がするので、また読み返したいところ。
0投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ北さんからの推薦本。 推薦されなければ読まなかったはず。 経済学に全く疎いにも関わらず、意外にも面白い。 結局、「貨幣とは何か?」の問いの答えは「貨幣とは貨幣として使われるものである」 「商品」でもなければ、何者かによって恣意的要因でもたらされた「制度」でもない。 循環論法によって自然発生的に存在したもの。いわゆる「奇蹟」である。 作者が述べている、貨幣であるための存在規定「未来永劫貨幣として信用される日々」が、覆る日(最後の審判)が訪れて、資本主義の終焉が訪れることはあり得るのだろうか? 本書が書き上げられてから24年。 今ではあり得ないことではないきがしてならない。 それにしても、商品世界に対する貨幣とは、人間世界に対する言語である。 との考察は非常に面白く、分かりやすい。
0投稿日: 2017.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.はじめに 貨幣論という書名は実に親切で、きっと貨幣について論じたものであろうことは容易に想像がつく。 強いて難癖をつけるとして、貨幣というやや畏まった表現だが、言わずもがな要はカネである。 著者はその「カネの正体とは何ぞや?」という問題を論じた挙句、「いくらカネとは何ぞやと考えたところで何も出てきやしないのだ」という結論に達する。 そして、そのカネのカネたる所以(つまり、何も出てきやしなかったというオチ)こそは、資本主義にとっての危機とは何であるかを教えてくれる。 すなわち、資本主義にとっての危機とは、マルクスの言うような恐慌(過剰生産ないし需要不足)ではなくて、レーニンの言うような貨幣の堕落(ハイパー・インフレーション)であると岩井克人は結論づけるのである。 それはなぜだろうか。むろん著者にはその立証責任があるし、現に本書にてそれを果たそうとしている。 2.理論家が理論を徹底できなかったワケ。そして、貨幣とは 著者はマルクスの価値形態論をマルクス以上に徹底させることによって、貨幣が商品世界において決定的な役割を演じていることを論証してみせる。 ここで一つの疑問が生まれる。 それは、「なぜマルクスは、価値形態論を著者ほどには徹底させることができなかったのか」という点である。 その回答は、「もし価値形態論を徹底させてしまったならば(つまり、著者と同様の思考過程を歩んだとすれば)、マルクスは彼の信奉するもう一つの理論、労働価値説を放棄することになりかねなかったから」である。 マルクスの価値形態論においては、貨幣商品の原材料の採掘に投下された労働時間が貨幣商品の価値量を規定しているという形で、労働価値説が堅持されている(と少なくともマルクス自身は考えている)。 けれども、岩井克人の貨幣に対する認識においては、労働価値説は棄却されている。 貨幣とは、人々がそれを貨幣として信ずるがゆえに貨幣なのである、と。 この貨幣なる代物は、一般的等価物として、商品に交換可能性を与えることにより、商品によって交換可能性を与えられ、また、商品から交換可能性を与えられることにより、商品に交換可能性を与えている。 貨幣の上のような性質こそは、商品世界すなわち商品の膨大なる集合としての資本主義社会がこの地上に成立することを可能としている。 また、交換過程論に視点を移せば、商品所有者にとって、貨幣こそは「欲望の二重の一致」を回避するモノであって、これがあるからこそ我々は交換の困難に苦しむことがない。 (もしあなたが貨幣のない社会において、本一冊を持っていて、靴一足が欲しいという場合、あなたは靴一足を所持しており、かつ本を欲している相手を探しださなければならない。しかし、貨幣のある社会においては、あなたがたとえば10,000円を持っていれば、靴屋は貴方に靴を売ることを渋りはしない) 貨幣が商品世界に占めている役割は、それが古典派経済学者によって媒介物に過ぎぬと言われたのに比して、あまりに大きいのである。 3.貨幣の崩壊への道 恐慌というのは、確かに歴史の示すとおり、資本主義にとって試練だった。 けれども、試練はやはり試練である。 それに直面することにより、資本主義は弱体化したというよりは、むしろより強靭になっていく(少なくとも、マルクスを理論的基礎に持つ社会主義よりは長生きしているわけだ)。 なぜか? なぜ、マルクスにとって資本主義の危機であったはずの恐慌が、かえって資本主義を強化しているのか。 それは、恐慌という状態が、商品よりも貨幣を選ぶ状態であり、したがってそれは商品世界を成立させている貨幣に対する信仰告白が蔓延している状態だからである。 ケインズの表現を借りれば、貨幣には流動性があると言われる。 この流動性は、「誰でもいつでも受け取ってくれる」という信用があるということであり、 他の商品にはほとんど認められない貨幣に固有の性質である(これに対して、商品なり製品を人々が実際に購入するためには、それこそ「命がけの跳躍」を必要としているため、その処分は[購入に比して]容易なことではない)。 それ自体の商品価値をほとんど有しない貨幣に対して(中央銀行が発行する不換紙幣をまともに原価計算してその額面通りの価値を有すると誰が算出できるだろうか)、かような価値を認めるところに、貨幣の貨幣たるゆえん、神秘とか奇跡とか言われるところのモノがある。 ということは、恐慌において相対的に貨幣(それは商品世界で重要な役割を担っている)が重んじられているということは、それは本当の意味での資本主義社会における危機とは言えないのではないか。 ということは、である。 もしその流動性に対する信仰が途絶えたとき、したがって人々が貨幣の流動性を疑ってかかり、貨幣ではなくて個別の商品に逃げ込んだとき、商品世界はどのようになってしまうのだろうか。 貨幣より商品が選ばれる世界、その窮極的な形として、ハイパー・インフレーションが生じた場合、もはや貨幣を貨幣たらしめる根拠を捨て去ったあとに残るモノは、個別バラバラな商品と、それ自体さして価値を有しないかつて貨幣だったモノ-したがって今やそれはやはり個別バラバラな商品の一つ-である。 「価値の体系としての商品世界が、たんなるモノの寄せ集めでしかない状態へとひきもどされてしま」い、「『巨大な商品の集まり』としての資本主義社会の解体」を生むという点で、ハイパー・インフレーションは、資本主義社会にとってより本質的な危機なのである。 4.貨幣形態論 しかし、私はどうにもこの論に与することができない。 私は、人々はたとえ貨幣を手放すとしても、流動性までは手放さないのではないかと思う。 (果たして人々は二重の欲望の一致を要する社会に耐えられるだろうか?) 貨幣は、時代に応じて、貝殻であったり、君主の刻印が押された鋳貨であったり、あるいは中央銀行の発行する兌換紙幣次いで不換紙幣とその形をかえてきた。 けれども、そこで共通するのは、いずれの貨幣も流動性の機能を果たしてきたという事実である。 マルクスにおいて労働価値説という実体に対して価値形態論という現象形態があるように、流動性という実体に対して貨幣という現象形態が変遷し続ける。 貨幣は人々が貨幣であるとみなすから貨幣であるというのであれば、その物質的素材や名称は理論的には不問のはずである。 であれば、人々は現行貨幣が著しく減価してそれが商品世界の存立構造を解体する前に、流動性の所在を移転するのが筋合いではないか。 人々は次なる貨幣を「奇跡」(これは奇跡という呼称に反し、人類史上幾度となく繰り返されてきた)によって生み出すのではないか。 いや、奇跡という言い回しこそ、岩井が資本主義の不安定性を強調するために用いた表現ではないか。 なぜならばこの奇跡が実際にどれほど奇跡的であるかについて、あれほど価値形態論をマルクス以上に論理的な形で展開した岩井が、マルクス以上の修辞法すらも(したがって当然ながら、論理的にも)披露できていないのだから。 また、貨幣価値の減価を防ぐ実際的な方法として、ハイエクの「貨幣発行自由化論」も検討すべき事項ではないか(私はまだ貨幣論集を読んでいる途中だけれども)。 実際、ビットコインはまさに民間による貨幣発行の典型である。 もし貨幣発行主体がシニョレッジを貪るため貨幣を多量に発行した場合、貨幣多量発行に伴う貨幣減価が生じ、貨幣利用者としては、他の価値ある貨幣へ乗り換えるというビジョンである。 これをうけて貨幣発行主体としては、貨幣価値が過度に減価しないように、価値が安定化するように努めるインセンティブがあるという次第である。 貨幣間競争、これは一国一貨幣というアタリマエに囚われた私たちには盲点である。 実際、貨幣を中央銀行のみが発行している事態を独占供給と理解する人はあまりいない(銀行券に類似した物を発行すれば通貨偽造罪に問われるということもあってか、現代の社会通念において、別種の貨幣を創造する意欲なり発想を持つことは、たとえ貨幣発行業に参入するために要する費用を無視したとしても、難しいことである)。 競争原理という資本主義社会におけるアタリマエが貨幣においては十分には機能していないのである。 資本主義社会が本来的に不安定なものである、とは岩井の主張するところであるが、しかし、資本主義社会は未だその本来的な姿を明らかにしていないのではないか。 (そして貨幣を巡るこのような見方は、資本主義を純粋な形で炙り出したマルクスにおいても果たして展開されていただろうか) シニョレッジ、この君主権力の名残を玉座から引きずり下ろすことが、資本主義に期待された一仕事なのではないかと私は思う。 歴史上、資本主義が貨幣による試練を受けることはあったが、貨幣が資本主義による試練を受けたことはなく、そしてそれは未来に起こりうる出来事なのである。
0投稿日: 2017.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ繰り返しの中で 貨幣は死を迎える。 それは資本主義の死。 貨幣論の本質は、 資本主義の危機は 恐慌ではなく、 ハイパーインフレーションだということだ。 マルクスの貨幣論に始まり、 貨幣について、論じられた本書は 膨大な繰り返しをあえて使う。 それは貨幣のあり方に似て。 貨幣を語ることは、 現在、唯一の体制である資本主義を語ることで 貨幣の危機は、資本主義の危機だ。 単一の価値となりつつある貨幣は だからこそ、ハイパーインフレーションによって その価値を失う、という危機をもつ。 貨幣は言語である、という指摘も印象的だった。
0投稿日: 2017.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の考察は、マルクスの『資本論』における労働価値説と価値形態論との関係をめぐる考察から始められます。著者によれば、マルクスは労働価値を超歴史的な「実体」として理解する一方、超歴史的な価値の「実体」がどのようにして交換価値という「形態」を取るようになるかという問題について考察をおこなっているとされます。この両者の関係には、労働価値説を前提として商品世界の貨幣形態を導く一方で、商品世界のか兵形態を通して労働価値説を実証するという循環論法に陥っているという批判がなされますが、著者はこれを「生きられた循環論法」として捉えることによって、貨幣についてさらに深い洞察を展開しようと試みます。 貨幣は、みずからの存在根拠をみずからで作り出すという無限の「循環論法」によって、絶え間なく自己を吊り支えていると著者は考えています。こうした観点から、貨幣の外部に、それを基礎づける何らかの根拠を想定する貨幣の起源に関する説を論駁します。たとえば、貨幣商品説は人間の主観的な欲望によって貨幣を根拠づけ、貨幣法制説は高官家庭の外部に存在する人為的な権威によって貨幣を根拠づけます。しかし著者によれば、貨幣はいったんその循環論法が作動し始めてしまえば、その存在に関して実体的な根拠を必要とすることなく流通します。こうして著者は、「貨幣とは何か?」という問いに対して、「貨幣とは貨幣として使われるものである」と答えるほかないと言います。さらに著者は、こうした貨幣の流通が交換可能性を未来へと繰り延べることによって成立しているという議論へと踏み込んでいます。他方で著者は、貨幣の運動が実体的な根拠を持たないということから、ヴィクセルの『利子と物価』における不均衡累積過程に関する議論を参照しつつ、ハイパー・インフレーションのような危機に陥る可能性の存在を論じています。 なお、本書の「後記」には、本書の貨幣論が後記ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論と対応していることを指摘していますが、この問題をめぐっては、柄谷行人の『マルクスその可能性の中心』や、『内省と遡行』に収められた論文「言語・数・貨幣」で、これと同じ趣意の議論が展開されています。
0投稿日: 2016.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだかとっても当たり前のことをわざわざ小難しく言っているだけのような気がする。 それにしてもマルクス経済学といった学問でもなんでもないものがどうして流行ったのか理解できない。
0投稿日: 2016.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログマルクスを主に引用し、貨幣の循環論法を基本線として話しが進められる。恐慌論、危機論ともに貨幣の循環論法に起因している。思想をめぐるというもので確たる結論が用意されてるわけではないが、とても読み応えがある。
0投稿日: 2016.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログマルクスの考えに沿って貨幣の本質を問い直す。 前半部分はマルクスの思考方法が抽象的で理解が難しかった。 貨幣は貨幣とされるから貨幣になる、それはそうなのだけれど、マルクスに限らず昔の哲学者は本質論を展開して物事を捉えきれてないような気がする。貨幣を論じているのに、信用創造や金融機関のバランスシートを語らないのでは、議論の幅に限界が生じるのは当然だろう。
0投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣は貨幣として使われると貨幣になるというトートロジーこそが貨幣の本質であるという本。要素ではなく関係性に注目するのは論理哲学や構造主義っぽい感じもする。
0投稿日: 2014.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前読んだ『二十一世紀の資本主義論』は「貨幣」存在の独特さを描出してとても面白かったのだが、今回の本は少し様子が違っている。やはり貨幣なるものの存在を浮き彫りにしようとするのだが、そのために、何故かひたすらマルクスを精読・分析し続ける。そして、マルクスの「可能性」として、じぶんの貨幣論に通じる要素を引っ張り出そうというわけだ。 しかし柄谷行人といい、この人といい、何故そんなに無理してマルクスを救済しようとするのだろう?「マルクスの可能性」と言うが、結局はマルクスは古典派経済学の労働価値論(「価値は商品生産の労働時間によって決定される」)を抜け出すことができず、それを超えた理論を決して明言できなかった。マルクスが決して明言しなかったことを「可能性」などとして引きずり出そうなどという試みは、もはやマルクスを逸脱することになるのではないだろうか? そこまでしてもマルクスにこだわり続けるというのは不可解だし、無理に思える。 本書を読んでいてその点が非常に気になったものの、著者の貨幣論はやはり興味深い。 「貨幣が貨幣であるのは、それが貨幣であるからなのである。」(P70) 「貨幣という存在は、みずからの存在の根拠をみずからでつくりだしている存在である。」(P104) 意味内容を持たない、完全に非-意味である貨幣というシニフィアン。それの自己組織化運動である、社会関係のなかでの経済システム。 私はウェーベルンなどが切り開いた、情動/意味作用と断絶したある種の音楽を、このような「貨幣」性と考えてみる。貨幣としての音が、人間主体の意味体系とは別のところで、自己組織化運動を繰り広げる・・・。 こういう夢想を惹起してくれた岩井克人さんに感謝している。
0投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこの人、ポール・サミュエルソンから指導を受けたそうだ。 資本主義がどうしたとか資本論がどうしたとか、左翼の残党と本出したりしてるのでマル経の人かと勘違いしていたよ。 Wikipediaによれば・・・ 当初は新古典派経済学の研究で評価されたけど、不均衡動学に関する研究において新古典派批判に転じた、とのこと。
0投稿日: 2013.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「貨幣とは何か?」について丁寧に論じて謎を解いてくれます。面白いです。経済学の知識が無い私でも、「ヴェニスの商人の資本論」を読んだ直後だったのでそう難なく読むことが出来ました。 著者の岩井さんによれば貨幣について本質的に考えることによって、資本主義の本当の危機がデフレスパイラルのような恐慌ではなくて、世界的なハイパーインフレであるということが結論づけられています。 マスクスさんに興味があった折に、古典派経済学や新古典派経済学ともからめてマルクスさんの貨幣論を丁寧に説明してくれている本書を読めてラッキーでした。 本書の内容とは直接関係ないのですが、最後の文章を読み終わった時に感じたのは、人類が自然に手を加えてこれまで無限に作り出してきたあらゆるものが貨幣に姿を変えた途端にその額面だけが残存し、廃棄物として捨て去られた物やサービスのようにもう消えて無くなってしまっているものも、貨幣の額面としては勘定に入っているのかなぁ〜という感慨でした。 もしそうだとしたら、貨幣というものが存在し得た太古の昔から現在に至るまでの人の営みが全て現存する貨幣の額面として刻み込まれていて、それは現に動いている物やサービスをはるかに超える額になっているのじゃないかと。そんな膨大な幽霊みたいな実体の無いものを含み混んだマネーが世界中の金融市場を飛び回っているのじゃないかというような気がして、「幽霊の正体見たり枯れ尾花…」って感じでなんだかお金も大したもんではないのかもなぁ〜と思いました。まぁ…たぶん間違った想像なんでしょうけど… ですがまぁ、そういうふうに思うことができてしまうと、確かにお金が無ければ資本主義経済社会では非常に生きづらいけれども、かなり相当に不便であるというだけで、絶対に生きられないわけでもないという気もします。やはり、生きるということはその時その時の生き物の営みそのものという風にとらえることが出来れば、生存の象徴である「富」の概念も変化して観念的、機械的で冷たいお金じゃない、もう少し人間的な手触りのよいものに変わっていくのじゃないかなぁと感じました。 そして、岩井さんによるとハイパーインフレによって引きおこされる資本主義経済の危機の本質はお金がお金として受け取ってもらえない状況なんだそうです。お金をお金として受け取らない人をこの本では「異邦人」と名付けています。変化した「富」の概念を採用する「異邦人」さんたちがたくさん増えれば、資本主義経済によるいろんな問題も解決の糸口が見えてくるのじゃないかと…
0投稿日: 2012.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本人はなぜ株で損をするのか?」で紹介されていたので読まなくてはと思い購入。文庫本になってから13刷。この程度の厚さだと気楽に読む気になる。
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろな批判のある書物のようですが、貨幣というものの不可思議さがわかっておもしろい。ので読むの二回目。 ここにあるの、構造主義的な考え方なんですね。貨幣を貨幣で買うことというのは無いわけではないですが、そういうときって、貨幣に何を見いだしてるのでしょうか。貨幣が商品としての価値を持った瞬間貨幣は貨幣でなくなると言うのは今までなかった視点だったので、新鮮でした。
0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからはわからないかもしれないがマル経の本。しかし侮る事なかれ、面白い上にきちんと議論が成り立っている。教科書というよりかはその他の空き時間に。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半部要約 マルクスの価値形態論を徹底するとマルクスの意図を越えて、「貨幣が貨幣として流通しているのは、貨幣が貨幣として流通しているからである」という循環論法に行き着く。貨幣の起源は貨幣商品説や貨幣法制説といった物語によっては語り得ず、貨幣はその存在そのものが「神秘」である。 後半 資本主義の本当の危機はマルクスの言うように「恐慌」=人々が商品よりも流動性を持つ貨幣を望むために商品を売ることが困難になる事態ではなく、「ハイパー・インフレ」=人々が貨幣からの逃走を始めること。 すなわち、貨幣を貨幣たらしめる神秘が消滅すること。
0投稿日: 2011.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログネットの人気者、池田信夫は宇野弘蔵のパクリというが(彼が繰り返しことあるごとに、パクリパクリと言うのは、何か個人的な感情が絡んでいる用に思える)、私のような宇野世代ではない人たちにとって、焼き増しだとしても分かりやすい言語で資本主義や最も基本的でありながら「つかみどころのない」エンティティの一つである貨幣の話をしてもらえるのはありがたい。間違いなく、一読の価値あり。経済・経営に関するブログなんかをやっている人には、ここら辺は押さえておいて欲しい。 岩井氏の有名な原著論文はこちらhttp://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m27/index.htm
0投稿日: 2011.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ貨幣とは何かを問い貨幣の不安定さを指摘。そこから生まれる恐慌の危険性を述べるとともに逆説的にそこには資本主義の繁栄が保障されてる。資本主義を崩壊に導くのはインフレーション。労働ではなく貨幣の根本に剰余価値は存在しているみたいな流れ。
0投稿日: 2011.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ書かれている内容については、学者の中では批判のでるところだそうです。が、左脳刺激にはもってこいです。
0投稿日: 2010.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「BOOK」データベースより 資本主義の逆説とは貨幣のなかにある!『資本論』を丹念に読み解き、その価値形態論を徹底化することによって貨幣の本質を抉り出して、「貨幣とは何か」という命題に最終解答を与えようとする。貨幣商品説と貨幣法制説の対立を止揚し、貨幣の謎をめぐってたたかわされてきた悠久千年の争いに明快な決着をつける。
0投稿日: 2004.11.22
