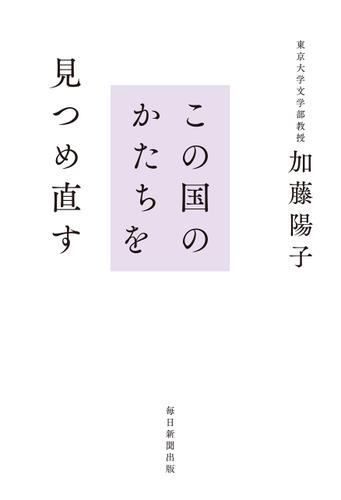
総合評価
(11件)| 2 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ全部は読んでないんですが。 加藤陽子氏は(私が言うのもなんだけど)信頼に足る著者だと思うのだけど、この本は新聞のコラムを集めたもののせいか、どうも厳密さに欠けるというか、なんか議論が雑だなあという印象が強い。 たとえば、東日本大震災についての文章をまとめた第2章の「大震災、国の記録 政治家の気迫伝わるか」と題されたコラムのなかの (以下引用)まず気づいたのは、会議ごとに冒頭でなされる菅直人首相(以下、肩書はすべて当時)の発言が軽いということだ。善意と熱意に満ちてはいるが、全閣僚を率いて議論を導き、政治的決断を行う首相の役割を果たす者がほかならぬ自分だとの自覚が、その言葉からはうかがえないのだ。(引用おわり) こんな大雑把な印象だけで話をされてもなあ、という感じ。震災当時にアンチ民主党メディアがよく言ってた「リーダーたるもの、自分があっちこっち行こうとしないでデンと構えているべき」みたいなしょうもない精神論と変わんないような気がするんだけど。 そのほか、菅内閣による日本学術会議の任命拒否問題にしても(その件自体にかんしては政権の横暴だと私も思いますが)、加藤氏はそれが慣例でないという事実にのみ基づいて批判している(ように見える)のが、なんというかあんまり本質的でないなあと思う。 蒙を啓かされたのが「個人が尊重されるかどうか 国民世論のありかに信頼」という文章の次の部分。 (以下引用)夫婦別姓論者が、なぜあれほど別姓を嫌がるのか。その理由の一つは、歴史的な経緯から説明可能です。明治政府が大日本帝国憲法と皇室典範を起草するにあたっては、女帝を容認した案も途中まで準備されていました。実質的に憲法を書いたといえる内閣法制局長の井上毅が、女帝による皇位継承は、天皇の姓が変わること(易姓)を意味するとして強く反対し、結局、明治憲法は女帝を認めず、男系による皇位継承を決定しました。この、姓が変わっては万世一系という観念が崩れるとの無意識ゆえの呪縛こそが、別姓を望む他者の選択をも制限すべきだとの意識を支えているように思います。家族制度が崩壊するという理由づけも、「別姓を認めればこの国のかたちが変わる」という、意識せざる危機意識ゆえと見えます。(引用おわり) 「思います」「見えます」と言っていることからべつに定説ではないのだろうけど、説得的な理屈だと思った。しかし姓が変わるといっても皇族に姓なんかないじゃん、とも思うんだけど。本当にそんなしょうもない理由で別姓が認められないのだとすればは非合理もはなはだしいけど、逆に非合理だから(理屈の問題じゃないから)こそ反対の立場も強固なんだろうなあ。バカバカしい。
0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎日新聞に連載された短文を集めた。 「時代の風」2010.4~ 「加藤陽子の近代史の扉」2020.4~ (月1連載) 「今週の本棚」毎日新聞での書評 毎日新聞インタビュー 歴史事象を参考にして今とこれからを見つめる。 日本学術会議の事も書いてある。数えるとインタビューも含め6本。 〇2021.4.7「政治の姿勢を歴史に刻むため「実」より「名」を取る。説明なしの任命拒否。その事実と経緯を後世に残すために 2020年6月に拒否された6人のうち5人が、2021.4月に学術会議の「連携会員」「特任連携会員」として活動に参加することになった。だが、加藤陽子氏一人だけは、任命拒否問題が解決していないまま「特任連携会員」になるつもりはないと返答。なぜ希望しなかったのかコメントを寄せた。 『特任連携会員としてお務めを果たそうとするお考えを持つ方が現れるのは本当によく理解できます。 ただ、幸いに歴史系で任命されなかったのは当方一人であり、また多くの歴史系の会員が奮闘されている現状にかんがみ、やはり当方としては、今回の菅内閣の、充分な説明なしの任命拒否、また一度下した決定をいかなる理由があっても覆そうとしない態度に対し、その事実と経緯を歴史に刻むために「実」を取ることはせず、「名」を取りたいと思った次第です。』 毎日新聞デジタルインタビュー2021.3.12 1960生まれ。東大入学は1979年。その当時、体育も男子学生と一緒、着替えの女子の部屋も無かった、と。研究者になってからは、もちろん、グロテスクなまでのハラスメントを多数経験してきています。中でも忘れられないのは、1984年、修士論文を書き終わり発表した後の懇親会。一回り上の男性研究者から、どうせ女子は就職できないから、僕と一緒にアメリカに行こう、と言われたこと。好意を持っているようだが、研究者として対等に見ていない。・・5年後どちらも実現させました。・・ある意味、この言葉ゆえ奮起したが、その時はその場の雰囲気をこわさない程度にしか言い返せなかった自分への怒りもあり、怒りのエネルギーは全く減る気配がないです。 2021.7.30第1刷 2021.10.30第6刷 図書館
6投稿日: 2025.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、加藤陽子さんの発言などに関心をもっていて、初めて著書を読んでみた。ざっくり読んでしまって、専門の近代日本史などに関する鋭い言及などは消化不足でごめんなさい。 冒頭のほうのインタビュー記事を起こしたところがよかった。「そもそも何の落ち度もない個人が、一方的に著しく時間と手間を強いられる制度の方が問題なので、悪い制度には誠実に対応しすぎないことが肝心」(p.37)というのは自分にとって至言。最近意地を張るかのように遵法精神旺盛なときがあったりするので、もっと都合よく生きないといかんなあ。
2投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの方の「歴史観」歴史へのスタンスは素晴らしい 権力に対峙し軸がブレない だから政府は恐れ、学術会議から外したと理解できる 実力を認識している 1.危機の指導者 長期的戦略思考力とは 対米戦争で長期化は回避と理解はしているが、具体策ないまま開戦 最悪 ロジスティクスの算段が出来る指導者の不在 2.戦後の「天皇退位規定」天皇の戦争責任論 一般人として極東軍事裁判 3.危機対応 平時も戦時も基本は同じ「構想手法」(下平拓哉防衛省) ①現状の把握 ②問題の析出 ③解決策の案出 4.現代資本主義経済体制の閉塞 水野和夫氏 1971 ニクソン・ショック 1973 オイルショック 5.必要な政治改革=参議院改革 衆議院に対して強すぎる
1投稿日: 2023.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は鋭く、嘆きたくなる時勢について語れど、あくまで冷静で知的な文章が心地よい。 「国家の再生が必要となる時、ひとは国家の来歴を求め、自らの父祖の歴史をたぐり寄せる。だが、そうする時、自らの国家が他国との間でつむいだ歴史に潤色を加えようとするのは無意味だ。嘘をつくには相手がいるが、他国は国家の嘘につきあってはくれない」
1投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書は趣味、気楽なものがいい。 でも、たまにはと、この本を手に取った。 (著者は、政府に任命拒否された日本学術会議の新会員候補の一人。 歴史学の手法で首相官邸側の思惑を解き明かす時評を含む反骨の論評集。) 出版社より 老化の進む脳には厳しくて、メモを取りながら読んだ。 歴史学って 興味深いなあ。 真理に向かうための誠実で真摯な研究。 その一端をのぞかせてもらった。 記録を大切にしない風土の根幹には政治の不在がある。 そして、あとがきで著者は言う。 真実の歴史を「言葉」から探ること、本書ではこれを目指した、と。 ≪ 国家とは 危機の時代に 問い直す ≫
18投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史学は何をする学問か…「歴史の闇に埋没した『作者の問い』を発掘すること」…歴史上一定の時代に現れたり創られたりした制度・組織・論理が、なぜその時代に現れるのかを考える態度…制度や組織を創り出した「作者」の思索の跡をたどるのが歴史学の役割…(p28) 歴史の真実は、人間の行動の記録として残された事実だけで成り立っているのではなく、人間が書いたり発したりした「言葉」に現れた知性の営みの中にもあると先哲は教えてくれている。真実の歴史を「言葉」から探ること、本書ではこれを目指した。(p280 おわりに)
4投稿日: 2022.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ東大教授加藤陽子氏のコラム&エッセー集。日本学術会議の6人除外当事者であり、事件についても詳しく語られている。
1投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ各一章を読んだあと ふーん なるほど そういう視点のとらえ方があったか と 思わせてもらえる一冊 考えながら 行きつ戻りつしながら 読ませてもらいました 新年早々に 心地よい刺激をもらえました もし、未読の方にお勧めするなら p169~ ー井上ひさしが追い続けた「かけがえなさ秘めた笑い」 の一章から を挙げたい
4投稿日: 2022.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年一番のインテリジェンスな本だった。内田樹を初めて読んだ時の衝撃を思い出した。 『難しいことをやさしく、やさしいことを深く、深いことを愉快に、愉快なことをまじめに』
1投稿日: 2021.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ近代歴史学者の著者による評論集。第一章:国家に問う、第二章:震災の教訓、第三章:「公共の守護者」としての天皇像、第四章:戦争の記憶、第五章:世界の中の日本、歴史の本棚。文書を大切にしない国は歴史をも大切にしない。中国には史官という役目の官僚がいたのに。今の日本には、後から批判される可能性がある都合の悪い文書はみんな破棄する悪弊を官僚が持っているのか…。
1投稿日: 2021.11.16
