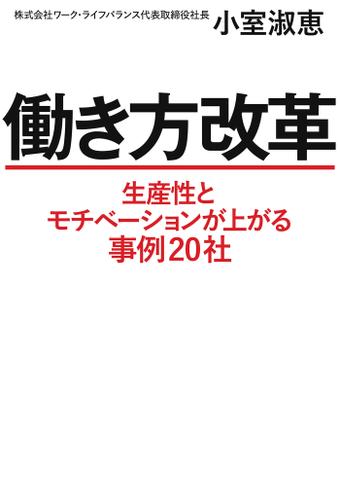
総合評価
(16件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業が働き方改革に成功した実例やどうやって企業風土や経営層の考えが変わっていったかがの具体事例が多く掲載されている。 どこの企業も一様に、朝メールやカエル会議という、株式会社ワーク・ライフバランス社伝統の手法を取り入れ、同社のコンサルが入っている。どちらかというと、企業の部長職以上のトップマネジメント向けの一冊ではある。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ※以前に読んだ本の登録 ざっくりメモ 働き方改革に取り組む企業事例が載っており参考になる本。 業務過多や長時間労働といった問題には、その業務内容自体だけを改善するだけでなく、働く従業員の働く環境、メンタルの改善をすることが重要である。関係の質を高めることが、思考の質を変え、行動の質を変え、結果の質を変える。心理的安全性を作ることも大事。
0投稿日: 2023.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。 朝メールは、組織でやらなくても個人的には採用できたらと思いました。働く時間も大切だけど、内容のマッチングも課題かもしれない。やりがいを感じることができれば、集中して効率的に仕事できるので、時間の問題も自ずと解決されそう。
0投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方改革が成功した企業事例を紹介した本。どの企業にも共通してそうなのは、無駄をどのように削減できるかが、またオープンな議論ができているかがポイントだと思った。
0投稿日: 2021.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フライヤー2019/05/12 09:38 ・人口ボーナス期とオーナス期 →ボーナス期とオーナス期は働き方が違う ←経済が発展する道筋が逆 -ボーナス期:若者多く,人数増えることがプラスになる ←社会保障費そんなにかからない ← 勝利の方程式だ:早く、安く、大量に生産 →労働時間と成果が直結しているからである。(1)なるべく男性ばかりで、(2)長時間働かせ、(3)同じ条件の人材ばかりを揃えた組織が勝つ。社会全体としては、夫婦が性別で役割分担をするのが理に適っている。 -オーナス期:労働人口減って,高齢者増える ←1990年代半ばからなってる ← (1)なるべく男女ともに、(2)短時間で働かせ、(3)違う条件の人材を登用する組織が勝つ。労働力が不足するので、男女どちらからも選ばれる組織が有利 ・最初は5~10人編成のチームを3~6つ選抜し、そのトライアルチームを8カ月間走らせる。 ←全社一斉は現場や他から不満でる → 働き方を変えられない真の理由とその対策が徐々に見えてくる ・ステップ0:ゴールイメージの決定 →働き方改革で何を目指したいのかをメンバー全員で話し合い、共有するのである。 → 課題の方が多く出たとしても、かならずポジティブな言葉に置き換える ・こうしたステップは、ともすれば「タイムマネジメント力の強化」手法に見えるかもしれない。だがその本質は「関係の質」を上げること →関係の質向上→思考の質→行動の質→結果の質の向上 ←結果の質から入ると反発,やらされ感出てバットサイクル
0投稿日: 2021.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ休暇取得率100% フレックス制度 リモートワーク 仕事見直し 属人化業務の廃止 IT投資 突発業務を無くす
0投稿日: 2020.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方改革はどこから手を付けるのが良いのか、それには多くの事例があるのが良いと考え読んでみました。 事例20社について、会社紹介と働き方改革の背景、その取り組みや成功の秘訣2〜4つ、といった内容なので、カタログのようで響きませんでした。 せっかくこれだけの事例を集めたのだから、取り組みや秘訣をマトリクス的に整理して、全体を俯瞰したり、比較出来ると良いのに、と感じます。 うーん、比較してみるか? どの業界も苦労してること、 どの業界でも働き方改革は可能であること、 具体的手順(ゴール設定、朝メール夜メール、カエル会議、改革施策の実行)、 経営層が本気で取り組まないと形骸化すること、 反対意見へのQA集、 は参考になると思いました。
0投稿日: 2020.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
メディアでも有名な著者。 日本での人口ボーナス期は終了、人口オーナス期における人材確保と人生の充実のために、働き方改革が必要だと。 具体的手順として、朝メール、夕メール(時間管理と業務の見える化)、カエル会議(やり方と人生を変える、早く帰る)、8か月の継続など提案。 警察や県庁でも実施例あり。 もっと働きたいという若手が望むのは仕事ではなく成長だという質疑への答えなど、よく考えられている。 ほうれんそうのおひたし。 報連相は有名だが、おひたしは、怒らない、否定しない、助ける、指示する。とか。
0投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ小室さんは講演を聞いたこともありますが、今回は沢山の成功事例が載っているということで読みました。 成功事例の中の苦労話にもう少しフィーチャーしてもらえれば良かったかなと思いました。 少し成功事例が遠い話に聴こえてしまいました。
0投稿日: 2019.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の中で最も悪い見本となっているのが私であるが、働き方改革をしたいと思ってはいる。しかし、どこからか救世主が現れて何とかして欲しいとも思っている。 当事者意識はなく、本心では望んでないのかもしれない。 お金をひたすら稼ぐことしか自分の価値を表現することが出来ないからというのが、正直なところ。家族の中でも一番立場弱く、価値を感じられる場所は私生活にはないのだから。
0投稿日: 2018.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方改革について、目的、進め方及び具体的な手段を前段で述べ、後段はそれらを基にした取組例を大まかにまとめる構成となっています。働き方改革というと、ともすれば「残業時間削減」という安易な言葉に置き換えられがちですが、「締め付け感」を従業員に与えず、コミュニケーションを促進することで従業員満足度を向上させるとともに、少ない時間で効率よく成果を挙げるための解説がなされている良書でした。そして特に、長時間労働や非効率な業務の震源地は官公庁、自治体及び教育現場にあることを指摘されている点が秀逸でした。
1投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方改革と一言でいっても大きくわけると以下の3つがあると思います。 ① 長時間労働の是正(残業の削減) ② 非正規と正社員の格差是正 ③ 高齢者等の雇用促進(雇用の吸収力アップ) この中でも①に焦点を当てて書かれた本でした。 職場の残業を減らしたく読んでみました。まずは「なぜ長時間労働を是正しなければいけないか」に関して。マクロな視点で見た時に、日本は人口オーナス期に突入しているので、そもそも生産性を上げないといけないという話。単純な残業カットではなく、生産性を高めることで、結果として長時間労働減らすという考え方に納得。 また次に、実際に残業削減に成功した豊富な事例が、詳細に記載されていてすぐに実践したくなるような内容でした。鍵は、朝時点の予定業務が、定時時点でどうなっているかというギャップのチェック。まずは残業が出ないように業務量と納期を調整することが大事だけれど、確かにそれでも残業が出てしまうのが、その日の業務が予定通りにいかなかったから。その要因が何かを紐解いて解消するのが効果的だとこれも納得。 小室さんの活動で凄いと思わされるのは、自身の活動を公(政府・日本)の意義に変えたこと。きっかけは小池さんからの電話で議会に呼ばれた事だったらしいが、そこから数々の議員勉強会に参加して長時間労働の是正を「政府・日本における価値」に置き換えてプレゼンして、安倍首相含む政府の考え方を変えさせたことが凄い。 ●人口オーナス期でGDPを高めるには、土台となる労働力人口の確保と、その労働生産性を高める事が不可欠。 ⑴ 少子高齢化により労働力人口が落ちている中で、 1. 現在の労働力確保のために、女性や高齢者などの雇用促進が必要(雇用の吸収力アップ) 2. 未来の労働力確保のために、長時間労働の是正による男性の育児参加ができる環境作りが必要 →特に2。男性の育児参加の時間数と2人目の出生有無には相関があるデータを示せたことが大きい。これまで少子化対策は女性に対するアプローチが大半だったが、男性の長時間労働是正が少子化対策になることが初めて(政府の中で)繋がって国策に落ちて一気に進んだ。 →少子化対策は遅れれば遅れるほど、高齢化が進むため取り戻せない。中国ではオーナス期に入った瞬間に一人っ子政策を解除して、食い止めている。日本は20年遅い状況。 ⑵ 人口ボーナス期での成功モデル=労働集約型による海外需要の大量受注(働けば働くほど儲かる)は、人口オーナス期においては機能しない。いかに生産性を高めて空いた時間を活かせるかが大事(結局、時間に頼った働き方だと、男性の長時間労働化が進み、少子化が進み、未来の労働力が確保できないため) このロジックを整理して、プレゼンして結果、法改正までこぎつけたんだから。凄い。
0投稿日: 2018.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の小池さんは一時期よくビジネス系の雑誌に出ていたが、安倍首相にあって説明する様になったとは、読んでいて驚いた。 自分の会社も働き方改革を進めようとしている。去年事務所移転を機にフリーアドレスになって、働き方も少しずつ変わってきているし、テレワークもしやすい環境になってきていると思う。そして、自分の部署は比較的対応している方だ。 しかし海外のオフィスで働く人と密接に関わっているのでよくわかるが、まだまだやれる事、できていない事が数多くあると感じる。
0投稿日: 2018.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の本で読んだことがあった話が、単語と登場したためちゃんとインプットされる。「人口ボーナス期」に対する「人口オーナス期」。欧米と違って、労働時間を減らそうにも一筋縄ではいかない日本は、とりあえず、朝方勤務をしっかり残業としてカウントする、というあたりから取り組むのは良いことだと思う(うらやましい)。たぶん、社員に自由度をもたせるという意味はあると思う(始業を早められるフレックスってだけで目新しいものではないけれど、やれるかどうかは会社次第)。公的機関が「働き方改革」と行うのはたしかにインパクトがあるし、それが警察となればさらにインパクトは大きい(愛知県警察)。おもてなしとかサービス精神とか(間違った解釈の)「お客様は神様」とか、日本は社会全体の過剰さを意識してセーブする時期に来ているのだと思う。
0投稿日: 2018.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人事担当として働き方改革が何かを勉強するために読んでみた。働き方改革でいえば、著者の本が一番だろう。なんせ、安倍総理に提言したのが著者なのだから。 どんな職場でも、働き方改革はできる。問題は、いかに職員が納得して改革をすすめられるか。担当者としては、改革の重要性をきちんと理解していかなければならないし、職員が腹落ちできなければならない。そのうえで、職員自ら考えたプランで行わなければ、一過性で終わってしまう。 警察や内閣府など営利団体ではないところでも、行っている事例が多数載っていて、すごく参考になった。
0投稿日: 2018.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ残業時間25%減、売上5億円アップの会社も!長時間労働を見直したことで、飛躍的に業績を上げた企業の具体的事例とノウハウを紹介。
0投稿日: 2018.03.23
