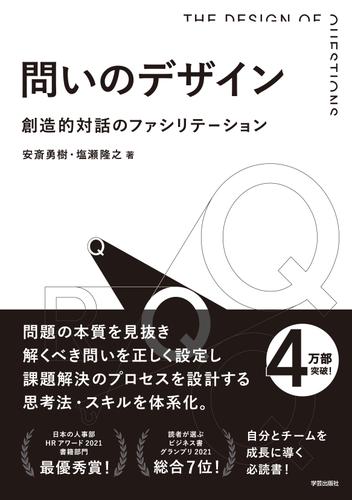
総合評価
(79件)| 31 | ||
| 28 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/dLEGXSaSWIW3P8PGAmENbMiirso/description.html
0投稿日: 2025.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の講演を聞いて,興味を持った。問い方や,それを含むファシリテーションについて,非常に具体的・実践的に書かれていて,「技」を身に付けたい人にお勧め。ただ情報量が多いので,一読しただけでは技は身に付かず,実践と学習を繰り返す必要はあると感じた (悪いことではない)
0投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/dLEGXSaSWIW3P8PGAmENbMiirso/description.html
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログめっちゃおもしろい。 ファシリテーション、マネジメント、キャリア教育などを専門とする2人の大学教授による共著。片割れの安藤氏はコンサルティングファームの経営者でもある。 それぞれが実際に企業や自治体などから依頼を受けて行ったファシリテーションの事例も豊富に掲載されている。 なによりもまず、言葉の定義や、伝えるべきことの構造などを筆者らが丁寧に検討し組み上げた本であることがわかる。それが好印象だった。参考文献の分量やその密度もさすが大学教授やなぁといった感じ。よく耳にする本から、普通の人は知らないであろう論文までさまざま。 そして、とにかく実践的な書物である。 何か目の前に問題があるとき、まずそれをどのように捉えるか、どのように問い直すことができるか、答えに向かうためにどんなステップを必要とするか、などなど、実践的かつ具体に沿って手順と例が紹介される。 現場で数々の問題解決のサポートを行ってきた著者たちだからこそ書ける、リアルで納得感のある視点がいくつも登場する。 問題解決のためには、まず正しく問いを立てなければならない。目先のファシリテーション技術に頼るだけではダメで、根本の問題認識、課題設定が重要である。あらためて問い直したとき、もしかしたら元々認識していた問題とは別角度の問題に気がつくかもしれない。 では具体的にどんな事例があり、どんな問いを立てるべきか?それらを具に、順を追って解説してくれる。 だから、別にファシリテーションをしたいとか何かに実際困っている、という人でなくても、読み物としておもしろく読めるだろう。
1投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ前段は学術的な印象で、話としては分かるが、自身の経験や課題意識が余程ないと活用が難しい印象を受けていた。 一気に引き込まれたのは最終章の事例集。著者は必ずしも商品開発や観光の専門家ではないはずなのだが、ファシリテーションの力でまとめ上げていった様子が感じられ、その威力を強く感じた。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションが上手な人は、仕事が上手な人だと思う。周りの人を幸せにしながら仕事をすることができる人だと思う。
1投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログうまく整理されていると思うけど、哲学思考とかリフレーミングとかドラスティックな問いの変換はなかなか難しそうだ。
0投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチングを学ぶものとして、大変刺激のある本でした。 特に“問いのデザイン”を活用した実例は、コレステロールで錆びついた血管をドクドクさせました。
3投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ元々安齋勇樹さんの講演動画はYouTubeで何回も繰り返し観ており、その流れで書籍を購入しました。定期的に読み返したい内容だったので購入して正解でした。 これからの時代・ビジネスシーンにおいて「問い」が持つ役割、「問い」をデザインする方法と期待する効果がたっぷり語られていますが、めちゃくちゃ腹落ちしました。 この考え方を持って、早めにチームを率いることができれば、、、と思わずにはいられませんでしたが、明日からでも実践できるテクニックも沢山あるのでオススメです。
0投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファシリテーションする際に振り返りたい内容。時間制約と成果を安易に出すためにかなり誘導していたから終わったあとの成果に繋がらなかったのではと反省させられる。 京急の事例は痛いほどよくわかる。いいアイデアが出てきたときに、どのタイミングで会社としてのやる意義と利益に繋がるかを検討すればいいのか、「第三の道」の問いをプロセスに入れたい。
0投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ20240813029 「答え」を急ぐよりも問題の本質を捉え現状を打破する「問い」をデザインし対話の場をつくる。 考え方の整理に役立った。
0投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログなにかをより良くしよう、問題解決しようとしたときに「どうすれば⚪︎⚪︎か?」という問いを立てるが、そもそも問いの立て方が間違っているといくら話し合っても解決しない。 でも当事者たちは問題がそこではないということに気づかないまま解決に向けて話し合いを重ね、お手上げになることが往々にしてあるようだ。 そこで筆者のようなファシリテーターが必要となる。 ファシリテーターは企業の会議などの場で中立的な役割を果たし、課題解決のために皆の意見を集約してよりよい方向へ導く役割の人だ。 ファシリテイトするときには、まずは参加者の固定観念に揺さぶりをかけ、本当に皆が問いとすべきこと(考えるべきこと)は何なのかをともに模索するところから始まる。 固定観念に揺さぶりをかけるテクニックとして面白かったのは「9点問題」。ご存知ない方は是非やってみていただきたい。 また、どんな問いが良い問いと言えるのかについては箇条書きで具体例が書かれていたのでとても参考になった。 そのほか、ファシリテーターがリフレーミング(参加者の対話によって場に立ち現れた意味を、別の認識の枠組みから捉え直すことで意味づけを変える)する際のテクニックなど、課題解決に向けてのノウハウが盛りだくさん! 後半は筆者が企業、地域、学校の課題を解決した事例も載っており、全体を通してとても勉強になる本だった。
16投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションの説明を読むのは難しい。なぜなら、ファシリテーションには「空気」があるからだ。 「その場はあたたかい雰囲気でした」と説明されても、その雰囲気は頭ではわかるが、でもそれは、その場の雰囲気を理解したことにはならない。 同様に、ファシリテーションを説明されても、頭では理解できるが、ファシリテーションの実際を理解したことにはならない。ファシリテーションの説明を読む難しさはそこにある。 しかしそれは、著者らの説明不足、言語化不足ということを意味しない。むしろ、説明や言語化は充分である可能性もある(「可能性もある」という但し書きは、ファシリテーションの実際を私が理解できていないので、説明・言語化が充分かどうかを正しく判断できないことによる)。たとえば、旅行ガイドには旅のおすすめを充分に書いてある。旅先で、「あ、ここ旅行ガイドに書いてなかったぞ」と思っても、詳しく旅行ガイドを読んでみると実際は書いてあったりする。自分が読めてなかっただけなのである。 その意味で言えば、本書はファシリテーションの旅行ガイドである。本書を読んで、ファシリテーションという旅に出て、旅の中でふたたび本書を参照する。そしてまた、ファシリテーションという旅を続ける。そういう往還を通してはじめて、本書の意義がわかる。本書を片手にファシリテーションをするとき、本書の魅力が最大限に発揮されるのであろう。
1投稿日: 2024.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ上司がファシリテーションを勉強せいと、会社で購入した本。 タイトル通り「問いとは何か」「問題とは何か」「課題とは何か」を通して「創造的対話」を重要視し、ファシリテーション能力を向上させていこうとする本になっている。 社会人向けセミナーを受けているような感覚だ。プレゼンテーションスライドのような、数点に要約したまとめが随所に登場する。ノートにまとめたくなる構成だ。 タイトルの「問いのデザイン」は理解できるが…、上司の思惑「この本を読んで、ファシリテーション能力を向上する」は、これを読んですぐに上達しそうにはないかな。
0投稿日: 2024.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこれって本当に難しい。けど、すごく面白い。問いのデザインの仕方でゴールも辿る道も異なる。対象が誰かでも変わってくる。だから、絶対的な問いってないだろうし、全員で創り上げていくもの。それをファシリテートできる人って憧れる。
1投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ問いの建て方を軸にプロジェクト(対話)のプロセスを語っている。問の重要性といった部分はほとんど割かれることなく、プロセスが厚めで思っていたの内容とは少しちがった。要は、相手も自分も衝動を駆り立てられるような問いを立てられるかを意識する必要がある。簡単に言うと相手にビジョンを与えられるような、能動的だったり自分事になるような問い方をしていけばよいかと。
0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯目的 仕事で会議体の取りまとめを行う機会が増えてきたため、ファシリテーションのスキルを身につけたいため ◯感想 問いの基本性質をインプットした上で、問いのデザインの基本フレームを学ぶことができた。 特に問題の本質を捉え、解くべき課題を定める「課題のデザイン」に関してはワークショップだけではなく、通常のアイデア創出系の会議体や商談内でのヒアリングフェーズにも応用できると感じた。 問題に対峙した時の思考法は正解のない問題に対峙した際の思考法として癖づけしていきたい。
0投稿日: 2024.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログPart1 問いのデザインの全体像、とPart2 課題のデザイン までは自分の物事の考え方を再整理するのにとても役立った。それ以降は実際に問題解決するためのワークショップのファシリ術なのだけど、ここまでファシリできたら凄いだろうな。 場づくりは重要。
0投稿日: 2024.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題と課題の違いを再整理するために購入。ワークショップの進め方、ファシリテーションの重要性についても学べた。挿絵や表があって、とても読みやすかった。教科書として手元に置いておきたい一冊。
0投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ問いの考え方としては仕事じゃなくて普段の私生活にも活かせると思った ひねった考え方、目的意識が大事だなと ワークショップでファシリエイトできるほどのプロになりたいものだ
1投稿日: 2023.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の太さには現れない骨太な内容でした。 問とは何か、ワークショップと問というある種の参加者とファシリテーター(伴走者)との両方の立場で語られていて深い。すぐには使いこなせないがいずれは…!
0投稿日: 2023.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事の中でワークショップをすることがある者です。 これまで経験して得てきたワークショップのコツのようなものが整理され言語化されているので、再現性が高まりそうでありがたい。 その上で、抜けていた準備や、視点などの、確認と補足になった。
0投稿日: 2023.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 多人数での生産性を最大にするにはファシリテーターが必要。求められる素質は的確に問いを投げかけること。創造性は人の間に生まれる。
0投稿日: 2023.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログワークショップにおいて、議論を活性化させ、より生産的な場にするための手法をまとめた本。大切なことは、課題の質・ワークショップの進め方・思考法と環境の整備だと思う。 ワークショップの進め方がどんなに良くても、課題の質が悪いと良い結論を得ることはできない。逆に、課題の質が良ければ、議論が活発になるそうだ。勝負は戦う前にすでに決まっているのである。 ワークショップの進め方は、イントロダクション→知る活動→創る活動→まとめの順序で行うのが一般的である。イントロダクションでは、掴みとして無関係な話題を出すのではなく、簡単なものでいいからテーマに沿った話題をすることが大事である。その後の、知る活動や創る活動に気持ちや考えが入りやすくなる。 思考法は、最も大切なことだと考える。課題のデザインからメイン活動まで幅広く活用することができるからである。個人的には、天邪鬼思考、道具思考、哲学的思考が大事だと感じた。他にも、時間軸や社会レベル・個人レベルの影響の大きさ、課題の細分化など多様な考え方が記載されている。 本書の土台は、課題を様々な視点から見ることで、そのための方法が網羅されている。日常から勉強、仕事まで応用できる。
0投稿日: 2023.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本はめちゃくちゃよかった!「問い」をデザインすることは、会議やワークショップの場だけでなく、仕事を進めること、友達と楽しむこと、いつでも発生する対話をどう創造的なもの、ワクワクするものにしていけるかということで、そういう視点で見ると応用力のとても広い1冊だなと思います。あ、こういうアプローチもあったのか、と昔の会話を思い出すことや、今度こういう引き出しを使ってみようと思えるアイデアがたくさん出てきて、久しぶりにメモを取りまくりました。ためになる本を読むと、たくさん本が読みたくなりますね。
1投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的にわかりやすく、とても読みやすかったです。目標のリフレーミングは様々なシーンで役立ちそうです。 最後に実例があったのも、著者自身も悩みながら問いを研ぎ澄ませていることがわかり、問いをデザインすることの奥深さを感じることができてよかったです。
0投稿日: 2023.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ創造的な対話を進めるためにどう進行していくべきかをまとめた本。 問いに関する基本的性質から、問題の本質の捉え方、課題の定義の仕方、その上でのワークショップの進め方など著者の経験に基づきまとめられており秀悦である。ただ、1回読んだだけで理解出来る内容ではなく、何度も読んで実践を積み重ねることでようやく身について行く内容。経験を重ねてこの本の内容を身につけていけたい。
0投稿日: 2022.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ会議、打ち合わせを調整したものの意見の出ない場に虚しさを感じることも多く、ファシリテーションがうまくなりたいと常日頃思っているので、参考にしたいと思い、借りた。体系的に整理されていて、参加者が自分事として取り組めるように場を調整する手段などとても参考になるが、ワークショップのファシリテーションと会議、打ち合わせののファシリテーションは違うのでそこは混同しないようにしたいと思う。
0投稿日: 2022.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、問いを作ったりファシリテーターとして場を運営したりする人にとって、まず読むべき教科書だと感じました。文章は平易で図解を掲載している部分も多いため、大変読みやすかったです。図書館から借りて読みましたが、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。本書を読み込んで、日々の問いづくりや授業展開に活かしていきたいと思います。
0投稿日: 2022.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ問がなぜ必要か。 どのような効果があるのか。 何をすればよいのか。 がポイントごとにわかりやすく表現されている。 ワークショップデザインをされる方、 ファシリテーションをされる方はご覧になるとためになると思う。
1投稿日: 2022.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログゼミでワークショップを企画する際に参考にした。1から丁寧にわかりやすく書かれてあり、大変助かった。 依頼者がどのように目標を認識しているのか、課題は自分本位ではなくメンバーに共通することなど、クライエント/当事者重視で進めることを忘れずに、次も機会あれば活かしたい 「workshop」は「工房」である、ということが印象的だった ファシリテーション、対話、ワークショップなどに興味ある人は1冊もっていていい!!
0投稿日: 2022.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体と抽象で議論を捉える。 因果を構造化して、それに対して本当か?どうして?それだけ?と天邪鬼思考をしたり、素朴思考をしたりして投げかける。 議論のスタートが鍵。まずは答えやすい具体的な問いから始めて、足場づくりをする。 問いをイメージするときは、個人⇆組織と過去⇆未来の二軸によるマトリクスで整理する。 例えば個人×過去の象限は「経験」という具体を問うものであり、組織×未来の象限は「ビジョン」を問うものになる。 他にも良い目標の設定方法など、為になる記載が豊富にあった。良書!
0投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと仕事で必要になりそうだったので、 ざざーっと必要なところを拾い読みしたのですが、 そんな適当な読み方にもかかわらず、 この本は結構なスゴ本だというのが読んでいてヒシヒシと感じます。 残念なのは、ちょっと堅苦しそうなタイトルで、 中々読者が読もうという気にならないところ。 タイトルの設定が間違っているわけではないのですが、 もっと多くの人に読んでもらってもよい本だと思いますし、 とっつきにくそうなタイトルですが、予想外に読みやすくもあります。 個人的にドキっとさせられたのが、 「問題と課題の違いは何でしょうか?」というもの。 そんなの考えたことなかった…。 というより、同じと思っていたんですけど。。 著者の理解では、問題と課題の定義は、以下とのこと。 問題:何かしらの目標があり、それに対して動機づけられているが、到達の方法や道筋がわからない、こころみてもうまくいかない状況のこと 課題:関係者の間で「解決すべきだ」と前向きに合意された問題のこと なるほど、著者の理解では、問題のサークルの中の一部が課題なわけですね。 結構分かりやすい。。 ファシリテーションに限らず、良質の「問い」を見つけることは、 全てのビジネスパーソンにとってとても重要なので、 多くの人の読んでもらいたいスゴ本です。 自分もちゃんと読み直します…。
4投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログp219 答えは持ち合わせていないが、答えに辿り着くプロセスには責任を持っている。そのようなスタンスを場に共有することは、場をホールドすることにもつながるでしょう。 自分の意見も持ちながら、自信を持って伴走するための根拠が示されている。コンサルティングにも、子育てにも通じるスタンスで、迷いがちな領域と思う。 タイトル通り、問いに特化しており、コーチングの概念は問いの中のごく一部として捉えられている。答えが示されているわけではなく、この本自体が問いのような作りと感じた。
0投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で困りごとの相談を受けると、「いやほんとの課題はそこじゃないんじゃない?」と感じる事がある。対話を深める中でうまく軌道修正できる場合もそうでない場合もあって、それを上手に整理する人になりたいと思って手に取ってみた。リサーチドリブンイノベーションという同じ筆者の本が面白かったからというのもある。ただ話すだけではなく良い問いを投げかけて一緒に考えるのが大事、そしてその良い問いを作る方法も詳しく書いてあり早速仕事で活かしていきたいと思った。
0投稿日: 2022.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログちょうど仕事でファシリテーションを担うことになり四苦八苦しているところ、この本に出会ったが、マインドセットからノウハウまでとても参考になった
0投稿日: 2022.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 2. 3.問いかけの作法よりも理論っぽい説明が多く、読むことに多少苦労した印象を持ちました。しかし、書いてある内容は、とても大切なものばかりです。「問い」とは自分だけではなく、相手に対してプラスな影響を与えていくことが本当の役割なのだと思いました。自分自身では気づかないことを問いによって固定観念を外してあげることや視点を増やしてあげることは他者だからこそできることです。 これから気を付けていきたいことは「尋問にならないこと」です。つまり、自分が聞きたいことだけ言って終わることから卒業することです。自分が聞きたいことがあるのはもちろんですが、いかに相手の気持ちを深堀り、整理しながら自分の聞きたいことを導き出すことも大事です。対話を重ね、本書の言う「創造的会話」を実現し、仕事やプライベートをさらに楽しくしていきたいと思いました。
5投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・問は、集団のコミュニケーションを誘発し、関係性を再構築できる。 問は、創造的対話を生むトリガーとなる。 ・他社との対話の中で、どちらかが正しいことに躍起になるのではなく、そこから新しい認識を学ぶという視点を大事にしたい。 ・日常生活や業務の中でも意識したいなと思ったのは、認識が間違っている相手に対しての働きかけの仕方。⇒関係者の中のコミュニケーションの合意としてできた認識を、外部の人が一気に覆すことはできない。それが彼らにとっての現実だから。認識を再構成させるためには、当事者自身も彼らの中に入って対話し、「現実を再構成」させる。その中で、彼らに考えさせる問いをなげかけることが大事。 学び: ■新しい関係性を構築するステップ ①溝に気づく(違和感を感じたら、個々人の暗黙の前提が違うことによるGapがあるこを認知する。) ②溝の向こうを眺める(どういった認識をもっているかを想像する) ③溝の渡り橋を設計する ④溝に橋を架ける
1投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログコーチ、ファシリテーター、マネジメントなどに関心のある方におすすめです。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )
0投稿日: 2022.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「問いの作法」から先に読んだのもあってこちらの方にあまりインパクトを感じなかった。ファシリテーションの話が中心ですが、「問い」に関する内容は「問いの作法」とあまり変わっていないようです。(当たり前か)
0投稿日: 2022.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書会で読んだ一冊。問いとは何か、優れた問いを投げかけることによってどんな変化が起こるのか。ワークショップの場の設計の仕方など、実践的な部分までカバーしてあり面白かった。 ワークショップにおける『参加者の経験をデザインする』という視点が自分的に刺さった。
0投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ漠然と「問い」の力を強化できればと思い読み始めたが、「創造的対話のファシリテーション」の副題どおり、ワークショップのデザインについても多く語られていた。ちょうどグループワーク中で、色々取り入れられそうな要素があったので実践していきたい。ワークショップの実例紹介が大変参考になり、興味深かった。
0投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々なワークショップを手掛けているミミクリデザインCEOの安斎氏と京都大学の塩瀬氏の、ワークショップデザインの極意が示された一冊。 根底にある思想は「いろんな問題に対する答えを出すときに重要なのは、認識の固定化と関係性の固定化を揺さぶること」と述べており、そのためにワークショップでは「問いのデザイン」が重要となるというのが出発点となる。 本の流れは問いのデザインの全体像を説明し、具体的な手法として本当に解くべき課題の設定方法、ワークショップのプロセスのデザイン、ファシリテーターに必要なコアスキルを述べてから、最後に実際の事例の紹介をして締めくくっている。 実際にファシリテーターを体験したことがあれば、実感としてよくわかる部分が多いと感じる。問いの種類や深さの説明のところは秀逸なので、非常に役に立った。 ワークショップを企画・立案する立場にある人には必読書ではないだろうか。
0投稿日: 2022.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ何をするにもそもそも「問い」がイマイチだとそれなりの答えやディスカッションしか出ないよね、という事はみんな知るのが大事だとわかるわかる系
0投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテーションで「問い」を投げかける本質的な意味を考えるヒントをくれる書籍である。議論を通して、新しいことを生み出したい方は読むと議論の進め方や考え方が参考になる本。
0投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会構成主義の誕生から何十年経つと思うけど、 こうして生き生きと、経営や生活の場でワークショップという形で活かされるようになったのは、ファシリテーターや研究者の方々の地道な実践の積み重ね、知的努力と創意工夫の賜物と思います。凝縮された問いのノウハウ本でした。 問いのデザインというタイトルそのままに中心部は問いをどのように設定し落とし込み表現するかが説明されています。足がかりを重点に、創発的学びを生み出す問いの作り方を自分自身の研修の場面に置き換えて考察する機会となりました。 この先欲しい知見として、トップダウン思考の古い組織に、創発的学びの場の必要性や効果をどう理解してもらうか?研修のあり方は組織体質が滲み出る。場の設定のための設定が本当にむつかしい。
0投稿日: 2022.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ちょっとした論文を読んでいる気分 49 問題とは 何かしらの目標があり、それに対して動機づけられているが、到達方法の道筋がわからない、試みてもうまく行かない状況のこと 78課題とは 解決すべきだと前向きに合意された問題のこと。
0投稿日: 2021.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 課題解決のための「問題提起」を導き出す方法論。 アート思考などで“直感”を鍛え、隠された問題点を導き出すというアプローチではなく、物事の本質を導き出す、ある意味哲学的対話のような手段だった。 テーゼ → アンチテーゼ → ジンテーゼといった風に。 固定化された「認識」と「関係性」によって、「変わりたくても変われない」閉塞感を打破する、新しいアイデアを導き出すための「問い」を発見するために必要なことは、対話だった。 対話によって、個人の認識は揺さぶられ、変化を求められ、変容していく。 それは冲方丁『ばいばい、アース』( https://booklog.jp/item/1/4044729034 ほか )の懐疑者・アドニスの存在が主人公や世界の在り方に変化を促すのと同じ。 コミュニケーションの中で「対話」によって自由な雰囲気の中で相互理解を深めてゆく。そのプロセスこそが、“問いのデザイン”だった。 問題を問い直す考え方の指南、妨げになる考え方(空気?)を説明。 「問い」を導き出すための対話をうながす手段としてのワークショップの仕方――デザイン――についても解説。 武田砂鉄『紋切型社会――言葉で固まる現代を解きほぐす』( https://booklog.jp/item/1/4255008345 )にも通じる。 flier紹介。( https://www.flierinc.com/summary/2357 )
1投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
問いは非常に大事な思考の起点であり、タイトルに強く惹かれて読書。 本質的な思考法・切り口を伝えてくれる良著 メモ ・認識と関係性の固定化の病い 認識が当たり前となり固定化 変化の足枷に コミュニティにおいて暗黙で関係性固定化 ズレが固定化してしまうこと。 ・問いのデザイン 2段階 1.問題の本質をとらえて、解くべき課題を定める (課題のデザイン) 2.問いを投げかけ、創造的対話を促進する (プロセスのデザイン) ☆問いの基本性質 問いの設定により導かれる答えは変わりうる 問いは思考と感情を刺激する(問いによって過去未来、低い浅い、思考が変わる。伴って印象感情も変わる) 問いは集団のコミュニケーションを誘発する 対話を通して問いに向き合う過程で個人の認識は内省される 対話を通して問いに向き合う過程で集団の関係性は再構築される 問いは創造的対話のトリガーになる(角度を変えた具体化を進めた、背反的要素を含んだ問いにすることで深い議論につながりうる) 問いは創造的対話を通して新たな別の問いを生み出す ・問いから生まれるコミュニケーション4つ 討論 どちらが正しいかを決める 議論 合意形成意思決定のための納得解を決める 対話 自由な雰囲気の中新たな意味づけをつくる 雑談 自由な雰囲気の中気軽な挨拶や情報交換 ・対話は決着をつける必要はなく、異なる価値観に触れ、自分自身の前提をメタ認知しながらお互いに素朴な疑問を投げかけたり、違う角度から意見を述べたりしながら共通の意味を探っていく ・問いを通じた探求サイクル 問いの生成と共有 →思考と感情の刺激 →創造的対話の促進 →認識と関係性の変化 →解の発見・洞察 →問いの生成と共有 ・問いとは人々が創造的対話を通して認識と関係性のを編み直すための媒体 ・課題設定の罠 自分本位 自己目的化(トレンドからの設定) ネガティヴ・他責 優等生 壮大 ☆問題を捉える思考法 素朴思考 率直にわからないことをベースに 天邪鬼思考 批判的に盲点や裏側を考える 道具思考 関連知識・FW活用を考える 構造化思考 構成要素の関係性を分析整理 哲学的思考 本質を考える。そもそも論。◯らしさとは。 ・課題を定義する手順 要件の確認→目標の精緻化→阻害要因の検討→目標の再設定→課題の定義 ・目標精緻化ポイント 期間で短期中期長期にブレイクダウン 優先順位づけ 目標性質で成果目標・プロセス目標・ビジョンの3種類に整理 ・目標の阻害要因 そもそも対話の機会がない 当事者の固定観念が強固 意見が分かれ合意形成できない 目標が自分ごとになっていない 創造性や知識が不足している ・リフレーミングのテクニック 利他的に考える。 大義を問い直す 前向きに捉える 規範外にはみだす 小さく分割する 動詞に言い換える 言葉を定義する 主体を変える 時間尺度を変える 第3の道を探る ・ワークショップの定義 普段とは異なる視点から発想する対話による学びと創造の方法 ・ワークショップの四つのエッセンス 非日常性、協同性、民主性、実験性 ・ワークショップの問いのデザインの手順 課題解決に必要な経験のプロセスを検討 経験に対応した問いのセットを作成 足場の問いを組み合わせてプログラム構成 ・問いの制約設定 価値基準を示す形容詞を付加(快適な、豊かななど) ポジティブとネガティヴを示す(魅力、課題) 時期や期間を指定 想定外の制約をつける(想像してなかった切り口) アウトプット形式に制約(三つの条件は? 起承転結で表すと?など) ・足場の問いのテクニック 点数化 グラフ化 ものさしづくり(評価軸の議論へ) 架空設定 もし〰なら? そもそも 喩える ・
2投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いというか勉強になる! この本で社外内で人と話す機会を、より有意義かつ優れた時間にできるようになった。 これが自然にできるようになれば、恐らく今の何倍も人が集まる人間になれると思った。 これは、人と人が新たに何かを創り出したり、問題を解決する基礎的な考え方です。 これが出来る人間が1人、2人と増えていったら、間違いなくその一つの組織は異次元に大きくなるでしょう。 上の人間はこれで地位をキープでき、下の人間はこれで上に上がれる。
0投稿日: 2021.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読み終わった。ゆっくりと慌てずに少しづつ時間をかけて読了した。安西先生のワークショップに以前参加したことがあって、更にファシリテータとしての力を身に着けようと当時を思い出しながら読み進めていったのだが、まだまだ、消化しきれていない。 もう2,3回ぐらい読み返すだろう。
0投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ■問いの基本性質 ①問いの設定によって、導かれる答えは変わりうる ②問いは、思考と感情を刺激する ③問いは、集団のコミュニケーションを誘発する ④対話を通して問いに向き合う過程で、個人の認識は内省される ⑤対話を通して問いに向き合う過程で、集団の関係性は再構築される ⑥問いは、創造的対話のトリガーになる ⑦問いは、創造的対話を通して、新たな別の問いを生みだす ■問題を捉える思考法 ①素朴思考 ②天邪鬼思考 ③道具思考 ④構造化思考 ⑤哲学的思考 ■リフレーミングのテクニック ①利他的に考える ②大義を問い直す ③前向きに捉える ④規範外にはみだす ⑤小さく分割する ⑥動詞に言い換える ⑦言葉を定義する ⑧主体を変える ⑨時間尺度を変える ⑩第三の道を探る
1投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ問いの作り方に加え、場の回し方や企画の立て方、進行方法や心構えまで、今悩んでいたことを学ぶことができた。 理論だけではダメだとわかってはいるが、ポイントを言葉にして書いてくださっているので、自分の足りない点を振り返ったり知ったりすることができる。 話し合いにおける考え方のヒントなども得られた。 中堅として研修を回すことになった人や、教育関係者、新しいものを創り出そうとしている人にすすめたい。
0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ問題の捉え方や、課題の設定をする時に合理的な方法が学べる本。 特に問題の捉え方で勉強になったのは、「天邪鬼的思考」 当たり前に思うことや、常識も一度天邪鬼になってあえて否定して考えてみることで新しい考えが浮かんでくることがある!
0投稿日: 2021.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ問いの深さを考えさせられる、おすすめの一冊 問いによって人の思考と感情は刺激されます。 良質な問いによって、対話を生み出し、課題解決に導くことも可能です より良い問いがないか、常に考えていきたいと思います
0投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログワークショップデザイン・ファシリテーション論を研究している方の著書とあって、興味深い内容だった。個人的には資生堂の事例が面白かった。
0投稿日: 2021.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ良質の問いを立てて、有意義なワークショップのファシリテーションを行うための良書。問いの立て方のみならず、ワークショップの持つ一つの特徴として、非日常性がある点に納得した。
0投稿日: 2021.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ先入観や固定観念を壊すために必要な問いの立て方について解説された一冊です。「問い」と「対話」を戦略的にデザインする方法について、理解が深まります。
0投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めてファシリテーションに興味を持ってから早や8年。改めてファシリテーションの難しさにぶつかって本書を手に取った。 良い。 参加者の言葉をどう引き出すか、が今の課題で。 ドンピシャの本だった。 どうやって問いを組み立てるか その概念を読んでいるうちに、今、自分が企画しているワークショップの改良点が浮かんできた。 自己採点で私のファシリテーターの点数は10000点満点中3000点くらい。(要するに100点中30点) 経験は何度かあるけれど、苦手意識克服できずにやってきた。 今度は少しステップアップできそう。 そう思わせてくれる本でした。
0投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ【工学部図書館リクエスト購入図書】 ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30825755
0投稿日: 2021.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ思考の質や深さ幅といったものは、問いの質や深さ幅の影響を大きく受けるので、問い自体を良いものにしていくのが大事だよというのを網羅的に整理してくれる良い本です。 例えば ・どんな食べ物が好きか? ・好きな食べ物を今すぐ食べられるとしたら何がいい? ・今日の夕食好きなものなんでも食べていいとしたらなに食べる? ・3大ずっと食べていられるほど好きなものランキングを教えて と“好きな食べ物”を考えるのにも問いの立て方でまったく思考プロセスが変わってしまう。 issue drivenや論点思考など思考法について書かれている本をたくさん読んでいる人には馴染みの深い話がたくさん登場します。 加えてその中でのファシリテーターの役割、タイプ別の振る舞い方や、場の状態に合わせたアプローチなどもまとめられているので、会社組織などでイベントやワークショップを考えたり進行する人にとっては実践的な内容になっています。 目新しさのようなものは無いですが、タイトルの通り問いのデザインの仕方とファシリの仕方について過不足なく書かれている本なので使いやすい。
0投稿日: 2021.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ【橋口】 正しく問いを立てることで、相手から必要な情報を引き出しやすくなり、活発なコミュニケーションを生み出すきっかけにもなると思いました。どういう問いの因数で、構造的に文脈を組み立てていくのかそのワークフローやヒントがこの本に書かれているため、汎用性の高い書籍といえます。
3投稿日: 2021.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事でもそれ以外の活動でも、あらゆる場面で課題設定、問いの立て方が重要だなと感じる一方で、その手順を詳しく書いたもの、特にビジネス以外の場面でも使えるように一般化したものってありそうであんまりなかったように思う。本書はそこをど真ん中から向き合って丁寧に言語化されているところが素晴らしいと感じた。 自分の問いのデザイン力、今は40点くらいかな…必要なときに都度読み返しつつ、少しずつでも上げていきたい。
1投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に星10くらいの良書。 対話における四象限のそれぞれの側から問いを形成し、場における最良をデザインする手法としてのファシリテーション。 対話とはなにか、実践手法をHOWTOする理論も実践もある素晴らしい本。
1投稿日: 2021.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログファシリテートの本とはいえ、普段のコミュニケーションの中で使えるhowtoばかり。 言葉の紡ぎ方によってそのさきのものは変わりうることがよくわかる。同じ意味のことでも、ニュアンスが違えばそれを聞いた人の感情や思考は変わりうる。 好奇心とか、深い思考って人間誰もが持っていて、興味をもった大将に対してはinterestingと感じることができる。それを創発できることはとても楽しいことだし、そのヒントがたくさん詰まっている。
2投稿日: 2021.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近注目されている「問い」。まさに「イシュー」そのものだ。 本書ではワークショップの方法まで落とし込んであり、ファシリテーターの腕も含めて、全体のスキルを向上することが大事と説く。 最大の目的は結果であり「優れた答え」を出すことにある。 そうなると、全体のワークショップのクオリティを上げていく必要性があるのは当然という訳だ。 そしてその中でも一番最初の大事なポイントが「問い」そのものなのである。 優れた問いを出すことが、優れた答えを出すと言っても過言ではない。 「問いを極める」 ここまで意識して会議などを仕切ったことがあるだろうか。 定例化している会社の会議体はもちろん、何か案件について深い議論をしたい時にもそこまで徹底した「問い」を意識したことはないはずだ。 だからこそ著者にはひっきりなしに依頼が舞い込む訳だが、やはり普段考えないような問いを見つけ、その答えを探していくというのは、どうにも非日常的過ぎる。 普段の日常の生活の中では、その枠を飛び出すことが案外ハードルが高いということなのだ。 そこは著者も語っている。ワークショップという非日常をどうやって運営するか。 その為のノウハウや心構え、準備の方法などが本書では記載されている。 しかしながら相当な訓練が必要な気がする。 本書を読んだだけで会得したと思うのは大間違いだ。 特に優れた問いを作る部分は、相当に経験がモノを言うと思う。 だからこそ、その境地にまで至れば、結構強い。 なぜならかなり優れた答えを出せる可能性が高まるからだ。 今の世の中は本当に複雑化してしまっていて、何が正しい答えかを導き出すことが困難だ。 会社の中の人で、特に年配者に多いが、今までのノウハウが活きないために、思考停止に陥ってしまって問題を先送りしている人もいるくらいだ。 誰も正解が分からない中で、何らかの答えを出して前に進まなければいけない。 その為の第一歩が「優れた問いを見つける」ことなのだ。 「問い」を「どうデザインするか?」 これは、イシューがデザインできるものだということを示唆する。 デザインとは、もちろんセンスが大きな要因だが、実はセオリーとかルールがあったりする。 それらを理解し、+αのセンスを磨くことで、優れた問いを生み出せるという訳だ。 この辺は、素朴な疑問(シンプルさ)、天邪鬼的思考(クリティカルシンキングだ)などを例示しているが、他の書でもよく言われていることだ。 これからを生き抜くためには、本当に必要なスキルかもしれない。 「優れた問いを見つける」 意識していきたいと思う。 (2021/1/10)
1投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読んだワークショップ、ファシリテーション関連の中では、一番良いです。 普段自分のやっていることと、頭の中が整理されました。 問いと対話のデザインの方法、問題の本質の見抜き方、問いの考え方、深化のさせ方、ワークショップの組み立て方、ファシリテーションのスキルなど、構造的に、整理されて書かれています。 ファシリテーターの習熟度や芸風の整理は、なるほどと思いました。 お勧めです!
1投稿日: 2021.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログつむ読2021 No.2 [2021.1.2](300p,5h) 『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』 解決策の発想までを効率的に導いてくれる本質的な問いを立て、ファシリテーションによりそれの解決策を実現するために必要な“視点”“マインド”“プロセス”が記されている。 “視点”については、テクニック的に利用することもできるほど分析されているため、就活生などにもお勧めしたい(というより、自分が読みたかった)内容。 個人的トピックである“制約”についても因数分解されており、とても参考になる。
1投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人々の関係性の中に知が宿り、意味が形成されて、アイディアが発露してゆく。そのための問いの立て方と対話のあり方についてまとめられており、とても面白かった。ワークショップに限らず、日々の仕事やちょっとした対話でも活かしてみたいと思える考え方が多かった。
2投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログワークショップを作る人、オンライン会議などを仕切るリーダのための本である。実践者にとっても他の一流の実践者の思考法が学べるという意味でも価値がある。 オンライン会議が当たり前になった昨今、ファシリテーション、ファシリテーターという呼び方も一気に浸透してきた。一方で、会議術の本は数多あれど当然だが対面前提のプロセス解説がほとんどなので役に立たなくなりつつある。オンライン会議は企業や個人の環境に依拠してしまうため標準的なものを提示しにくいということもある。 この書籍では「問い」がいかにファシリテーションにとって大事かという本質を具体的な事例や学習等に関する理論に基づき解説している。かつ筆者自身の「素朴思考」「天の邪鬼思考」等のコアスキルがどう「問い」と結び付けられるか開陳されている。こういう内容は弟子になる、団体に所属するなどで受け継がれるところだとは思うが書籍で得られるというのはなんともお得な話である。 グラフィックレコーディングを仕事にしている小生であるが一緒に仕事をしたいと思っている方の一人である。
2投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに実践的な内容を本で公開してしまっていいのだろうか、、、不確実な世界を生き抜くために必要な問いを立てるスキルは万人に必須なので、この本も万人に必須だと思います
2投稿日: 2020.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
○購入のきっかけ 山口周さん著「ニュータイプの時代」で、これからは課題解決能力ではなく問題発見・設定力が必要になる時代、とありとても納得したので、問いの立て方とその後の解決プロセスについて、知識を深めてみたいと思い手に取った。(amazonでは電子版がなく、止む無く久しぶりに紙を購入) ○読後の感想 様々な文献、筆者らが実際に行なったファシリテーションの経験を説明しつつ、問いを立てることの意味や立て方のフレームワーク、問いの良し悪し、ファシリテーションの実務などについて筆者の考えが非常によく纏まっており、とても知識が深まった。 ファシリテーションの知見は、日頃の仕事における問題発見・解決に応用出来ることを確信した。 (失礼ながら)「ファシリテーション」が職業として成立するということが、この本を読んで初めて理解できた。 読みはじめは、ひとつひとつの説明が丁寧過ぎて冗長に感じたが、自分が理解したい箇所や理解が足りないであろう箇所だけは丁寧に読み、その他は筆者の言いたいことは何かを考えながらある程度サッサっと読む位が自分には丁度良く、ペースが分かれば文章の長さはそれほど気にならなくなった。 最後の章で、企業・団体でのファシリテーション事例が纏めて紹介されているが、(当たり前だが)ファシリテーションが実際にどういう形で活かされるのかが具体的にイメージ出来るように書いてあり、とても有用だった。 他の書籍では、ネットで調べたらすぐ分かるor中身の浅い情報に留まっている事例紹介が多く、全く用を為さないのでいつもはほぼ読まないが、この本は違った! ○読後の目標 問いのフレームワークや、問いの良し悪しに関する目を自分のものにして、日々の仕事や生活に活かす! そのために本の内容を定期的に見返す。 ○本の内容 *ネタバレ* *問いが変われば、答えも変わる 未来のトイレを考えるとき、「もっと清潔で快適にするには?」と考えるのか、「場所に捉われないトイレのあり方とは?」と考えるかによって、導かれる答えは大きく異なる。問いの中身によって、刺激される思考と感情が異なる。 *問いは、集団のコミュニケーションを創発する 人は問いに対峙すると、思考の「種」が生まれる。その種が場に共有されたとき、討論・議論・対話・雑談のコミュニケーションが生まれる。議論は結論を導くこと、対話は相互の理解を深めることがゴール。 *対話を通じて個人の認識は内省され、また共通の意味づけわ探るなかで集団の関係性が編み直される。 *新しい関係性を構築する4つのステップ ①溝に気づく②溝の向こうを眺める③溝の渡り橋を設計する④溝に橋を架ける *抽象と具体の往復で対話の解像度は上がる *問いを介して人々が認識と関係性を編み直していくサイクルを経て、集団によって問題が解決され、持続的に学ぶことができる。 *人の固定観念の強さを示す「9つの●」の問題 →当事者の認識によって、問題の解釈は変化する。 *課題設定の罠 ①自分本位②自己目的化③ネガティブ・他責④優等生(すぎて問いが深まらず、解決の糸口が見つけにくい)⑤壮大 *問題を捉える思考法を使い、本質観取する! ①素朴思考②天邪鬼思考③道具思考(他者の視点、知識、記号やツールなどを利用して思考を進める・深める)④構造化思考⑤哲学的思考(〇〇とは何か?を突き詰める) *課題を定義する手順 ①要件の確認(依頼主の要望、理想的な目標状態、問題状況に関する制約、関係者の情報、使える資源、予算と期間)②目標の精緻化(ステップ分け、優先順位付け、成果目標・プロセスを通じて達成したい目標・ビジョン策定③阻害要因の検討(そもそも対話機会がない、当事者の固定観念が強固、意見が分かれて合意形成できない、目標が自分ごとになっていない、知識や創造性が不足)④目標の再設定・リフレーミング⑤課題の定義(①効果性②社会的意義③内発的動機、の観点で課題設定する) *ワークショップはただの研修ではない!ワークショップとは経験のプロセスをデザインすること。 非日常性、協同性、民主性、実験性を喚起し、問いの解決の糸口になるような場を作り出すもの。ブレストからアイデアが生まれないのは、問いや、問いかけ方が配慮されていないから対話が深まらないため。問いが重要。 *ワークショッププログラムの基本構造 ①参加者の興味を惹く導入と②知る活動で新たな視点や知識を仕込み、③創る活動と④まとめを通じて意味をつくりだし日常に持ち帰る *ワークショップの問いのデザインの手順 ①課題解決に必要な経験のプロセスを検討する 定義した課題を解決にあたって必要な経験をいくつかのブロックに分割する ②経験に対応した問いのセットを作成する ③足場の問いを組み合わせてプログラムを構成する *問いの作成のポイント ①何を探索するかを決めて問いを立てる(知識、情報、価値観/俯瞰的・個人的、過去・未来などの視座も含む) ②制約を設定する 何でも良いので自由に、はダメ。認識や関係性を揺さぶり、参加者の思考と対話を方向づけることを意識させるために制約が必要(価値基準を示す形容詞をつける、ポジネガを示す、時期・時間を指定する、想定外の制約をつける(自動運転社会において「歩行者」が求めるもの等)、アウトプットの形式に制約をつける(紙、起承転結、身体で表現等) ③表現を検討する *足場の問いは重要。問いを効果的にワークさせるための「問いを活かす問い」。足場かけが上手くいかないとファシリテーションやワークショップは上手くいかない。 例:「居心地の良い図書館を考えて、レゴでミニチュアを作ってください」→あなたにとって居心地の良い場、場の印象をオノマトペで表すと?、良い図書館の条件、図書館の具体的な仕様、ミニチュアをつくる、という形で観点を分けたりして思考の偏りや検討の順序をより良い方向へ導くとよい。 *アイスブレイクこそ問いが肝心 *ファシリテーションのコアスキル ①説明力②場の観察力③即興力④情報収集力⑤リフレーミング力(参加者の癖を見抜き、視点の偏りの無い対話になるよう、一度立ち現れた意味を、別の認識の枠組みから捉え直すこと)⑥場のホールド力(場が傾かないよう、押し付けや誘導をさせないよう、参加者のエネルギーが120%発揮されることにコミットする)
3投稿日: 2020.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校、起業、地域など様々なところにある課題。課題を解決するためにファシリテーションの経験豊富な著者が「問いのデザイン」と呼ぶ手法を解説している図書。 問題の本質を見直し、全員が解決すべきと納得した課題を見つけ出す「課題のデザイン」、どのような道順で課題を考えていくのかの「プロセスのデザイン」の2段階に分けて「問いのデザイン」を考えていく。読んでいてとても面白かった。 ワークショップのプログラム構造は①導入②知る活動(情報収集)③創る活動④まとめ、が基本で職場の会議などでも同じ流れ。具体的経験から抽象的な意味を見出す要素を抽出し、また具体的な項目を考えるというファシリテーションが有効。この2点まずは面白かったので個人的に意識したい。 上手に実践できたらいいなぁ…
1投稿日: 2020.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ【星:3.5】 課題解決、そのためのワークショップ、ワークショップのファシリティテーションにおける「問い」の重要性などを説明した本。 なかなか良い本だとは思うのだが、「問い」の話が半分で、もう半分が普通にファシリテーション技術の説明という形で、本の中心テーマが「問い」と「ファシリテーション技術」に分裂してしまっており、内容に今一歩まとまりを感じられなかった。 自分が「問い」の立て方に興味をもって読み始めたというのもあるのだが、タイトル通りもっと「問い」を本の内容の中心に添えてほしかった。
1投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「問いの立て方」について学びたくて手に取りました。 問いを立てることによって、 固定化された認知と関係性に揺さぶりをかける。 そして改めて考える機会を設ける。 「問い」と「対話の場」の合わせ技の紹介で、参考になりました。 いろんな場で使えそうです。 終盤の事例紹介、同じ問いへの答えを30日だしつづける、というのがすごくおもしろそうだなと思いました。 問いを立てる際の視点の持ち方、コツや工夫が紹介されていて、とても参考になりました。 自分なりにまとめ直して、いつでも振り返ることができるようにコンパクトにして持ち歩きたい内容の一冊でした。
1投稿日: 2020.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ対話がイノベーションを生むと解釈 対話は討論、議論、雑談とは違う これができたら強そう http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761527433/ 作者のnoteが分かりやすい https://note.com/yuki_anzai/m/mfeba7f9b202c
1投稿日: 2020.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ形骸的なブレストから脱却せよ。 そのためには、ワークショップにおけるファシリテーターの役割が重要になってくる。 (ファシリテーションの辞書代わり) ワークショップがメインスコープでありながら、一般的なファシリテーターにも本質的に必要とされる要素が詰まった教科書である。小手先の会話技術だけでなく、課代設定→問いの分解および投げかけなどの、ファシリテーターの思考レベルと参加者とのコミュニケーションレベルまで手本にできる。 ワークショップ内にも、知る→(考える)→創る→まとめの各フェーズがあり、それぞれの行程でどのように参加者と伴走すべきかが分かる。 (立場や前提を揺さぶる問い、抽象⇔具体のサポート)
2投稿日: 2020.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログワークショップ実践者のための指南書。 私自身、ワークショップをするわけではないので、全てをそのまま参考にするというわけではないが、仕事、ボランティアの課題解決、研修、打合せで、日常生活の会話で参考にしたいところがたくさんあった。 タイトルにもなってる問いのデザイン、問いが本当に大事。すごくページを割かれてるので、ポイントを参考にしながら、課題解決のときに、本当にそれが向き合うべき問いかを見直すのに使いたい。日常生活の中でも、いつもの会話にちょっと視点を変えたり刺激を与える問いをするヒントになりそう。 ワークショップ実践者でないので、他の本の方がストレートに学べるのかもしれない。ただ、ワークショップというなんとなく知ってるけど身近でないものから学んでいくというのが、新鮮で楽しかった。また、実践と理論を行き来しながら進んでいくリズムも心地よかった。
2投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ意味と仕様は同時に考えられない、あるいは考えようとしたときの難易度の高さは相当なもの。ダブルダイヤモンドの構造で複雑さを下げる作戦は一つ。
2投稿日: 2020.06.07
