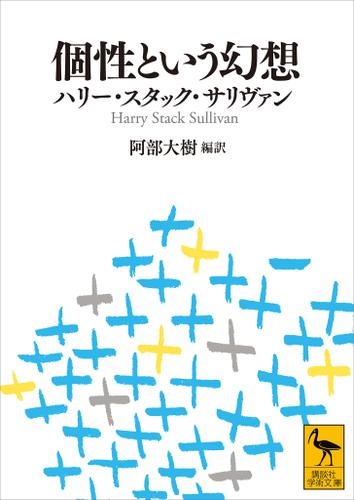
総合評価
(5件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ中井久夫を通して間接的にしか知らなかったサリヴァン自身の著作を初めて読んだ。なのに中井久夫訳ではなく阿部大樹さんの訳でなのだが。中井の訳本や原著はいずれ手に取りたい。 本書は阿部さんによる日本オリジナルの論集。サリヴァンが臨床から離れて以降の論文が収録されている。戦争や従軍する人々の士気、国民の戦意について触れられているのが時代を感じさせ、そこには正直あんまり気持ちがのれないのだが、最後の方にまとめられているので、サリヴァンの基本的な考え方を踏まえながら読むと、そういう論考を書かざるを得なかった事情や、その原稿の裏側で実際にサリヴァンが見据えていた未来も見えてくる気がする。「すなわち精神科医が第一に取り組むべきは、人間に備わった可能性が濫費されている現状に対して、そのような問題が二度と生じないように社会体制を変更することである」(p57)。サリヴァンの眼は徹頭徹尾、個人ではなく、社会・世界を捉えようとしている。遺された論考は、差別と自国民ファーストが横行する現代に活動する我々医療職にとっても参考になる。
2投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカで1940年代末まで活躍した精神科医、ハリー・スタック・サリヴァンの講演や論考をまとめたもの。 サリヴァンは、臨床の方面では統合失調症患者の寛解率7割という数字を残しました。他方、社会的分野や政治的分野では、まず徴兵検査の整備があげられます。精神面の検査を通った者でも、軍に従事していると必ず精神に失調をきたす者がいることをマクロにもミクロにもとらえていますし、かたや徴兵検査で合格しなかった者に対しても、そういった人たちへの大衆の偏見を正すためにどうするかを考えました。次に、現在の精神科医療の診断・統計マニュアルとして用いられるDSM(たびたび更新されて、現在はDSM-5にバージョンがアップされています)の原型となる「徴兵選抜局医事通信1号」を作り、DSM的なものの必要性を訴えました。 他、秘書に語った話として、サリヴァン自身が以前統合失調症を発症していて寛解した身であるというものもあります。また、別の本でちらっと読んだ逸話としては、患者への共感力がずばぬけていて、動物とも共感できるといった伝説的なものがあります。 そんなサリヴァンの常套句として伝わるのが「私たちは誰でも、まずシンプルに人間であって、それ以外のものではない」。どことなく相田みつをの「人間だもの」を想い起こさせます。 サリヴァンが考えたのは、人間の精神を形づくるのは「場」だということでした。そして、「場」とは「対人の場」であり、人間同士の相互関係によって、人間の精神、いわば個性は作られていくとしました。なので、個性というものは、個それのみで培われていくものではないとする。だから、本書のタイトルになっている「個性という幻想」という見抜きにたどり着くのでした。そして、幻想とは、役に立たないものであるでしょう。 サリヴァンが言うに、不安という概念は、あらゆる物事を知るため決定的に重要です、だそうです。不安は間違いを正す機会から目を背けさせるものです(p101)、とも言っています。 不安はいつも必ず、(人生早期の)多数の不承認に晒された体験に根ざしています(p101)、と。ここでいう不承認とは、これはだめだ等と叱られる否定の体験のことです。ここから考えたのですが、他者に高い要求を設定して、あれはだめこれもだめと怒ってばかりの人は、おそらく幼児期に自分が体験したことを他者に経験させたいのでしょう。 __________ 不安はむしろ、選択的不注意となることの方がずっと多いようです。これ(=選択的不注意)は私の造語ですけれども。気づいても当然良さそうでありながら、特に自分に羞恥心を催させるようなものだけがすっぽりと見過ごされれている状態を指します。現状に頑なに留まるために生じるものですが、そうなると有能な精神科医も、聖職者も、あるいはその他の専門家もお手上げになってしまいます。(p102) _________ →この選択的不注意は、僕の身近な人によく生じています。なんで、そんなことに気付かないの、気づかないフリをしているの? と疑問に思っていたことですが、こういったメカニズムがあったのだなあ、と勉強になりました。たしかに、不安が強い。不安障害と言われてますし。 そして、不安が怒りをもたらすことも解説されています。不安を感じたときに、それに怒りを持つことは想像に難くありませんが、怒りは「自分から見た自分」を「他人から見た自分」に強く結びつけるもので、不安に比べればずっと御しやすいそうです。不安は自分の権力を否定し脅威感を植え付けてくるのですから、とさらに解説がなされ、怒りの感情は周りの人々を怯えさせ、私たちが自尊感情にダメージを受けたことを束の間、覆い隠します、と結ばれていました(p103あたり) とまれ、そういう人たちが自分と同じような問題を抱えた人たち(次世代)を再生産してしまう。そして、それゆえにみんな、母性を渇望するわけです。自分を治したいっていう無意識の欲求みたいなものがありますから、じゃあ自分には何が必要なのかと求めたくなるものが、母性ではないでしょうか。 話は変わりますが、「それは言うべきでない」みたいな社会規範的というか道徳的というか、不文律の禁忌ってありますよね。そういった「禁忌を破るなよ」っていう圧力って、これまで同調圧力に似ているなあと思っていました。でも、こういうのは「モーレス」っていうようです。ちゃんと名付けられていました。(p150あたり) 話題はまた次に移ります。サリヴァンによれば、「幼少期に取り残した体験、その残渣が現在に霞をかけて、観察を曇らせる」(p153)のだと。これはあれですね、洞察力の強弱って人によりけりだけれど、その秘密について述べていると思うんです。つまり、内省が深くて広い人ほど、洞察力を発揮できるのではないか、と(でも、ここでいう「観察」はその人からの「観察」なのか、その人への「観察」なのかを考えないといけないなあとあとで気づきました。精神科医の言葉だけに)。 次は「昇華」について学べる箇所を。連続引用していきます。 __________ さて、この昇華なる概念がが化学から精神医学へと借入されて、人間の低次の同期が魔術のごとく高次のものへと持ち上がる現象を指すために使われるようになりました。(p92) 昇華というのはよくできたもので、もとの動機があまりに激烈でさえなければ、大抵うまくいきます。私たちは知らないままに社会に受け入れられるように成形されていくものですが、文化の丸暗記がその最も一般的な方策であって、精神医学に見られる昇華はその一特殊例に過ぎません。丸暗記することで、この手元にあるものを満足させ、それでいながら社会に認められたパターンに従うようになるのです(p93) もし「どうやって昇華するか」を誰かに教えたとすると、その人物は昇華ができなくなるものです。(p94) (かつて論じた通り、シンタクシス的な経験である「意思決定」や「意識される思考」は昇華と異なる。) (中略) その定義からして、二歳児に起こるのであろうと五二歳の男性に起きるのであろうと、昇華とはやはり非作為である。昇華は他人にコミュニケートできるような思考の産物ではなく、むしろ(不安を解消するために)パラタクシス的な状態で参照プロセスが起動されたことの結果である。(p250) どのような社会体制のなか生きていようとも一定の昇華をすることは必要で、またそのためには十分な休息ないし睡眠が求められる。(p264) __________ →昇華することとは、うちに溜まったものがすごく意味のあるものへと変化して救われるという体験とも言えるでしょう。そしてそれは、人からやり方を教えてもらうと、とたんにそのやり方ではできなくなるものだと述べられていますね。これは、このあいだ『ほぼ日』で読んだ糸井重里さんと東浩紀さんの対談のなかで語られていた「ジャンル自体が生まれたばかりのときはすごく名作が出るけど、産業として大きくなると駄作ばかりになる」に対応する概念ではないでしょうか。誰かが独力でやり遂げた昇華(作品)は、作為的じゃなかったからこそ傑作だったのであって、その方法論が記述され、それをもとに計算して作られるとそれは昇華まではいかない、ということになります。そして、昇華のためには休息と睡眠が必要だとあります。たとえばクリエイターはフリーランスの人が多いでしょうし、フリーランスゆえ報酬が買い叩かれてしまうために睡眠時間や休息時間を削ってまで創作するという悪習があるように思いますが、それだと傑作は生まれにくいということです。これは体制側の問題であって、クリエイターは被害を受けていると言えるんじゃないですか。 というところですが、以下からは気になった箇所の引用に僕のコメントを加えて書いていきます。 __________ 周りを見下げることで得られる一過性の安全保障感を決して見くびってはいけませんよ。そこに浸っていると自分が立ち往生していることに気付けなくなります。(p43) __________ →これ、個人としてもそうですが、人からも言われることってありますよね、「○○さんたちに比べたらまだあなたはいいほうだよ」というように。これが一過性の安全保障感を与えられた状況であって、それを真に受けているとそこで思考停止して立ち止まってしまいます。また、だから「我慢しなさい」と他者から我慢を強いられることでもありませんし。 __________ さて、文化に満たされることによってヒトが人間になると言いました。社会化されることによって、と言い換えても構いません。気を付けていただきたいのですが、ヒトに文化がピン付けされれば人間になる、などと考えないでください。文化とはどこかに貼りつけておけるようなものではなく、一度文化が備わったなら、それまでにあった性質は消えてなくなります。「社会化された人格」が動物に着せかけられるのではなく、その内側から成長していくものがあって、人間となるのです。(p94) __________ →前に考えたことがあるんですが、それが次のようなものでした。「1800年くらい前には、占いで政治を行っていた。卑弥呼の時代。たとえば、その頃生まれた赤ちゃんを現代に連れてくることが出来たら、彼なり彼女なりは立派に現代人に成長するんでしょう。逆に、現代に生まれた赤ちゃんを卑弥呼の時代に連れて行けば、それはもう立派な古代人に成長することでしょう。人間は歴史を重ねて、「現代」という波を作ってきて、それに乗っかって生きている。人間もすごいけど、人間をどう作り上げてしまうかは波にかかっているんじゃないか」。なんだか近いなあ、似ているなあと思って読んでいました。 __________ すなわち、生化学的世界があらゆる生物にとって必須であるように、文化、社会体制、あるいは言語や定式化された概念などが含まれる環境が人間にとっては必要不可欠なのです。そうであるからこそ、孤立しているとか、空想してばかりで実のある交流を失っていると、それまで高度に社会的だった人物であったとしても堕落してしまいます。(p94) __________ →「貧すれば鈍する」という言葉があります。これって上記引用のことを言っているのかもしれないですね。 __________ 自分ではどうにもできない、前進できる可能性が一切ない局面に置かれると、人間は虚脱します。他者からの敵意が原因と分かれば虚脱はさらに深刻になります。自分を嫌悪している集団がいる、どうなっても構わないと思われている、そういう人たちに命運を握られている――そんな状況です。(p202) さてここからは逆のパターンを考えてみます。普通であれば虚脱に陥るような環境にもかかわらず、なぜだか元気にやれているというケースです。(中略)一般に、状況について自覚的であるか否かに違いがあるようです。自覚的であるなら、先に述べたような相互作用に足を引っ張られることがあったとしても、自分に何ができるかを確認することが可能で、つまり落ち着きを取り戻すことができます。(p203) __________ →たとえば五月病なんかもそうなのではないかと思いますし、会社を3か月とか半年で辞めた人たちの内面で生じていることにはこういうことがあるのかもしれません。僕も最初の会社勤めのとき、入社段階からまったく仕事を与えられず、というハラスメントを経験しました。何もするな、と言われて、事務職なのに電話もとってはいけない。虚脱へとおいやる方法です。そうではなかったとしても、どうやったら前進できるのかわからず、自分でもどうしていいかわからなくなると、その人は虚脱するということでしょう。そして、それを防ぐには、状況や環境がどういうものかを言葉で把握すること、つまり自覚です。でも、状況や環境の複雑なところまで見えてしまうと、それを言葉にするのもアップアップになって、最後にはキャパオーバーとなってリタイアしてしまうことも考えられます。僕は先ほど挙げた会社勤めでは、こういったケースに陥ってリタイアしました。まあ、僕個人の内部の話であって、外側の動きや思惑やこちらをどう思っていたかのほんとうのところはわかりませんが。 __________ 個別具体的な出来事を扱わないままに生まれついた幻想などばかり論じることは、人類を分断し、むしろ国家間の緊張を大きくするだけである。(p253) __________ →アーリア人至上主義だとか優性思想だとかについて言っているわけです。サリヴァンは精神科医として人間をみながら、対人関係にこそ精神医学で考えるものがあるとしてそこに社会との相互関係もみています。ですから、精神疾患の苦しみを減らしていくには、国のあり方、社会のあり方を大きく変えていかねばならない、と考えました。時代的にいって、相当ラディカルだと思います。でも、そこに人間社会を向上させたいというような強い気概が見受けられます。人間の精神や発達は生まれつきよりも、出生後の相互関係から生まれるとここでもこの引用部分のあとに述べていました。
18投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい、サリヴァン。 この人を今こそ読むべき。 アメリカにおけるトランプの邁進とそれに追随する人々や彼らの暴走を一挙に体現した連邦議事堂事件以降の現代において、サリヴァンの訴える対人関係において構築される人間精神の在り方を思考することは、今こそアクチュアルで実利的な効果を上げる。 ゆるゆるふわふわな日本においてフロイト的な精神分析が広まらなかった一方で、サリヴァンの方法論こそが特に重要かもしれない。 会社や学校のせいでメンタルやられる人多いし、周りの人の顔を伺う癖が強い日本人には効くんじゃないかしら。
0投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて、読みました。 歯ごたえがあり、読み終えるのに時間がかかった。 「個性は、各個人が先天的に持っているのではなく、生まれた時からの対人関係から作られる。」ということらしい。確かに対人関係の歴史は、その人だけのものだ。個人的には、物理的文化的環境も関係があると思うが。 時代背景として、世界大戦があり、兵の徴用検査に積極的に協力する所など、少し考えさせられた。
0投稿日: 2022.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 人間が持つ集団としての性質。どこまでを一つの集団と定義するのか。思想は優生思想につながる可能性がある。虚心坦懐に論理を見つめる。
0投稿日: 2022.10.14
