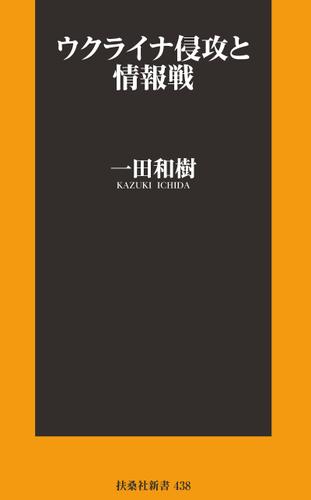
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこの書籍「ウクライナ侵攻と情報戦」は、一田和樹氏によって執筆された、2022年のウクライナ侵攻を情報戦の視点から包括的に分析した専門書です。本書の中核テーマは、現代の軍事行動が物理的な戦闘だけでなく、情報空間における戦いと密接に連動していること、そして欧米メディアの報道では見えにくい「グローバルサウス」(アフリカ、アジア、中南米諸国)における異なる視点の存在です。これらの非西洋諸国では、ロシアの行動が必ずしも侵攻や戦争として認識されておらず、反欧米感情や歴史的背景により中立的立場を取る傾向があると指摘されています。 ロシアの情報操作戦略については、世界トップレベルのネット世論操作大国として詳細に分析されています。主要なツールとして、RT(ロシア・トゥデイ)やスプートニクといったプロパガンダメディア、自動化されたボットや人間操作のトロールアカウント、フロント企業を通じたプロキシ活動、SNS上での隠れた政治広告などが挙げられています。特に注目すべきは、QAnonなどの陰謀論コミュニティとの連携、反体制派・極右・反ワクチン派などの敵対国内グループへの支援、そして「バイオラボ」陰謀論のようなグローバルサウス向けの特別なナラティブの展開です。これらの手法により、ロシアは相手国の分断と混乱を促進し、サイバー空間の「非対称性」を活用した戦略的優位の確立を図っています。 ビッグテック企業(グーグル、フェイスブック、ツイッターなど)は、「無自覚な権力者」として情報戦の重要な舞台となっています。これらの企業は、ロシアの国営メディアアカウントの制限やブロックなどの対策を講じましたが、その効果は限定的でした。特に問題視されているのは、これらの企業が偽情報や陰謀論を流布するサイトに広告を配信し、多額の広告収入を得ていたことです。一方で、ファクトチェック機関は資金不足や倫理的課題に直面しており、情報空間のモデレーションには構造的な限界があることが明らかになっています。ロシアは新たなアカウントの開設やインフルエンサーの活用により、プラットフォームの制限措置に適応し続けています。 本書は、世界的な民主主義の衰退と「デジタル権威主義」の台頭という重要な文脈でウクライナ侵攻を位置づけています。V-Dem研究所の調査を引用し、世界各国で民主主義体制から権威主義またはハイブリッド体制への移行が進んでいることを示しています。ロシアのSORMや中国の社会信用システムに代表されるように、権威主義国家はデジタル監視技術と情報統制システムを駆使して国民管理を強化しています。これらの国々は「民主主義の顔をした権威主義」として、表面的には民主的な制度を維持しつつ、実質的な権力集中を進めているのが特徴です。 米国の政策変更と影響力低下も民主主義衰退の重要な要因として分析されています。2000年代以降、米国が世界の民主主義を主導する役割が弱まり、中国の経済的台頭が民主主義モデルへの代替案を提供する状況が生まれています。国内的には政治的二極化、エリートによる情報操作、経済格差の拡大、SNSによるフェイクニュースや陰謀論の拡散といった課題が民主主義の機能不全を招いており、これらの問題が相互に作用して民主主義の脆弱性を高めています。 最終的に、本書はウクライナ侵攻を新しい国際秩序への転換点として捉えています。情報戦が軍事力と同等の重要性を持つ時代において、タリバンのアフガニスタンでの成功例に見られるように、SNSを「武器化」した情報戦略が軍事的劣勢を覆す可能性を示しています。従来の欧米中心の国際秩序が揺らぎ、多様な視点と多極化が進む「グラデーションの世界」への移行が進んでおり、もはや単純な「民主主義 vs 権威主義」の二元論では現実を捉えきれない複雑な時代に突入していることを強調しています。この分析は、情報戦の専門的理解と客観的分析の重要性を訴える著者の警鐘として位置づけられています。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の頭が悪くてあまり理解できず… いかに自分がグローバルノースに染まっていることか。 ロシアが情報戦に長けていることは分かった。
0投稿日: 2023.06.04
