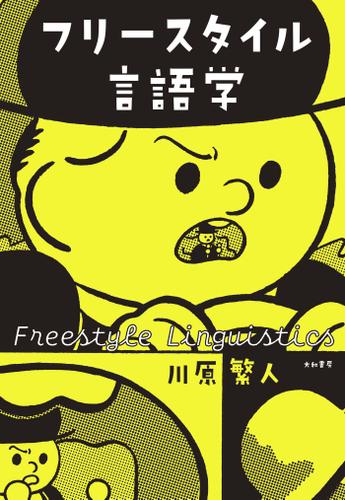
総合評価
(40件)| 16 | ||
| 13 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ専門分野を広く世の中に広めたい、という筆者の熱量がビンビン伝わる本。おそらく音声言語学の分野の最先端にいるはずなのに、驕らず、専門的な言葉も噛み砕いてとにかく知ってほしい、面白いでしょ?っていう熱い思いが詰め込まれている。 もともと、日本語ラップの韻に興味があって図書館で予約したが、そのほかの研究についてもめっちゃ面白かった(ピカチュウ、プリキュア、ドラクエの呪文、略語など)し、家族や学生との関わり、そして研究を通して社会へどう貢献できるか、など研究者のリアルが伝わってくる部分も興味深かった。 特にポケモン。濁音が物理的に大きく感じるイメージが、発音時の口腔内の状況とリンクしてるってところがほえーってなった。知的好奇心が高い方にはぜひ読んでほしい本です。
9投稿日: 2025.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学自体は、文学部で講義をとっていたため表面上は知っていたが、これほど身近で、これほど奥深いものだとは思わなかった。著者は言語学が何に役に立つかという世間からの目に今も苦しんでいると書いていたが、本文にも記されているように医療の面でも重要視されているし、なによりほぼ無知といって差し支えない私を言語学の虜にしてくれた。前野ウルド浩太郎さんや川原さんのような面白い若手の研究者の方がいるおかげで僕のような無学な人間は世界の一端に触れることができる。ありがたい限りである。 この書籍の構成は本当によくできている。序盤にメイド喫茶やプリキュア、ポケモンにドラクエといったサブカルチャーを取り上げながらサブリミナル的に言語学用語を差し挟み、こちらの興がのってきた頃に連濁や構造の違いなどといった専門的な内容を少しづつ取り上げ、後半からはがっつりアクセントやイントネーション、外来語に母音をつける時の法則性などより深いところに入りこんでいくようになっている。不思議なことに、前半にある程度専門用語を学べたおかげで後半の見慣れない単語群が苦もなく読める。しかも理解できて、楽しい。まんまとしてやられたなという気分になるのだが、心はウキウキとしてしまっている。もうこれを読んだ私の認識は拡張されており、普段何気なく聞いているような会話の中にすら新しい世界があるのではないかと思うようになってしまった。おかげで日常を過ごすことがより楽しくなった。こういったところでも著者に感謝の言葉を述べたい。 また、Jラップについての記事はとても興味深いものがあった。韻の踏み方について、日本人ラッパーが単語全体で韻を踏んでいたとは...。考えたこともなかった。この方面の著者の書籍も探し出して読んでみたいと思った。
9投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://opac.shigakukan.ac.jp/opac/volume/519942
0投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ異常なまでの文のうまさ。アカデミアの著書でこんなに一般書として楽しく読める本は他にない気がする。 楽しく気軽に読めるので、誰にでも薦められる良書でした。
4投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログp98 プリキュアの名前の文責めちゃくちゃおもしろい。ブートストラップサンプリング。「プリキュアで学ぶブートストラップ法」。 p114 エントロピー(乱雑さの尺度)=部屋の散らかり具合=予測可能性。 ラーメン屋の「しゃいませー」はエントロピーが低い。いらっしゃいませと言ってるだろうと予想できる。 p220 にせだぬきじる にせたぬきじる 連濁前に最初から濁音がついてたら濁らない。つまりたぬきじるだとだぬきじるにはならない。たぬきはだぬきになる。 p236 頭が赤い魚を食べる猫(中村明裕) p320 ALSとマイボイス p333 コロナデマ翻訳
0投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも文系理系と分けるのも好きではないが、いわゆる文系分野の研究者が理系的思考で研究している。 言語学の面白さを語った本かと思いきや、そればかりでなく、感動の涙も流れた。著者の人間味溢れる内容で、どんな経験も無駄にはならない、何が研究と繋がるかわからなく、自分で選り好みせずに果敢に外界に携わっていくべきだと思える。
0投稿日: 2025.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の本は以前途中で読むのもやめてしまったことがあった。 というのも、著者の専門は言語学の中でも音声学であり、その本では音象徴を扱っていたからだ。 私はあまりその分野に興味がなかったのと、学問的にもあまり魅かれなかったからだ。 (音象徴って何となく、こじつけな感じがするからだ) しかし、本書は音の分野だけでなく、言語学にまつわる話もありで面白かった。 学者である著者が、自身の研究が世の役に立っているのかということを気にするということを知り、学者も普通の人なんだなと妙に親近感が湧いた。 全体的に読みやすく、言語学について何も知らなくても楽しめると思う。
0投稿日: 2024.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語ラップなどを題材にしたユニークな研究が注目されている言語学者による、言語学エッセイ。 言語学、その中でも特に音声学を専門に研究している言語学者・川原繁人さんの言語学・科学エッセイ本です。 言語学・音声学って何? どんなことやってるの? 何か役にたつの? といまいちピンとこない人にこそ読んでほしい。 ドラクエの呪文、ポケモンの進化前と進化後の名前の変化、メイド喫茶のメイドさんや、プリキュアの名前の分析、日本語ラップの韻の踏み方などとっつきやすい題材から言語学とはどのような学問かを分かりやすく、かつ楽しく説明してくれます。 日本語話者だと普段何気なく使っている母音と子音。「にせたぬきじる」と「にせだぬきじる」の使い分け。「頭が赤い魚を食べる猫」という表現は何種類の解釈が可能かなど、改めて説明されると感服するような事ばかり。 個人的に一点だけ腑に落ちないのが、「日本語の音には必ず母音が隠れている」という話に関係して。日本語は基本母音と子音が一塊になっている……はわかる。日本語は子音だけで音を発する事はあまりしない……も分かる。外国語(例えば英語)には、子音だけの単語が存在する……のも感覚ではわかるんですが、じゃあいざそれを自分で発音しようとなると、母音を入れずに発音するって未だにどういうことかよく分かってません。母音がない音って何……母音がない音を聞き取るとか、入れずに発音するって難易度高くないですか?? どうやら日本人は子音が続く単語に母音を脳内補完しがちらしく、川原先生曰く他の著作でも触れているそうなので、そのうち別の本も読んでみたいです。 また、自分の研究をどう社会へ還元するかというお話の中での、ALS患者さんたちの為の音声読み上げソフトの改善に関わった話、コロナ禍での少数言語話者に正しい情報を伝えるための活動など、自分のもてる知識や人脈を活用して奔走する姿には感動しました。 学者さんというと、どうしても特定のコミュニティの中でひたすら研究をしている姿を想像しがちですが、対外的なアグレッシブさのようなものも必要なのだなと改めて実感できたような気がします。 普段触れる事のない学問の世界に触れられる、興味深い1冊でした。
19投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ直接的な感想にはならない抽象的な視点になるが、自分が楽しく学び続けることは尊さを教えてもらった。 特別支援教育に携わる者として、最終章のマイボイスの取り組みは、胸にくるものがあった。 学問として何の意味があるがわからないものも、いつかは人の役立つ時が来るという、人生の伏線回収的な部分を見させてもらった。 自分も言語学の勉強を少しずつ始めているが、今学んでいることが将来受け持つ子どもたちに、生かされることを切に願う。 川原先生は音声学の先生であられるが、専門性だけでなく生き方からも学ばせてもらった。 関係ないが、やはりいい大学にはいい先生がいると再確認した。
1投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ川原繁人先生の面白言語学の集約本。親しみやすいけれど中身はガチ成分も多め? 川原先生を初めて知ったのはYouTubeの「ゆる言語学ラジオ」という番組。なので、本で触れられた研究内容はそこそこ知っていた。それでも楽しめた。 研究内容も面白いが「言語学」といういわゆる「役に立たない」学問をやることに対する、先生の熱い思いに触れられるのが醍醐味
0投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログバーリートゥード言語学を読んでかなり面白かった印象があるうちに、この本を本屋で見かけたんだけど、大分時間が経ってから読むことになってしまった。バーリーを読んだ時の読後感は残念ながら得られなかったんだけど、この言語学者である著者が本当に真摯に楽しんで、役に立とうと苦しんで、この本を書いた、書いた元になる活動をしていることは伝わった。 学術的な箇所はあまり腑に落ちず、ちょっと読み飛ばしてしまったのを見ても、自分にはちょっと面白く思えないのかもしれないな、言語学は…
1投稿日: 2024.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学と書いてあるから難しい話かと思ったら、くだけた内容で面白かった。最初はメイドの話などが出てきてつかみにくかったが、途中出典に麻雀実況の日吉さんの名前が出てきてから一気に親近感がわき読み進めた。 ドラクエの呪文やポケモンの進化の音について考えたことなかったけど、そう言われてみればなんか強そうになってると思った。
6投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに「言語学」というワードが入っており、難しい本かなっと思い、読んでみましたが、とてもわかりやすく解説されており、楽しく読むことができました。言葉について専門的に学んでいない人にも優しく教えてくれる本だなと思いました。 タイトルに引かれた方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか??
8投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学時代に音声学の授業を取っていたものの、内容に特段興味を持てなかったのだが、、早くこの本に出会えていれば、もう少し音声学へ興味を持てたかなと思う。 普段意識することは無くとも、言われてみれば確かに!となる(例えば音象徴の下り等)こと満載。 そして、自分の仕事が社会の為になっているのだろうか?という問いは、学者以外にも通ずるものがあると思う。自分の仕事に誇りを持ち、懸命に働こうと思わせてくれる。
0投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の言語学愛が全ページから溢れていて読み応えがあった。言葉のアクセントが次に続く言葉で変化する法則とか、つい声に出してしまった。言葉って面白い。
1投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学、とくに音声学の面白いところが全部詰まったような本でした。 学問について語ってはいるものの、肩肘を張らずに楽しんで読めるのでおすすめです。 言語学をあまり知らない自分のパートナーにも、「ポケモンとかプリキュアの名付けが面白いんよ」と言ってつい話してしまいました。本当なら押し付けて読ませたい。 特に、最後の章に書いてあったALS患者の母が娘たちに残したい自分の声の話では、自分がその母と同じ歳で子どもがいるのもあり感極まってしまいました。 川原先生の授業を受けているような気持ちで読めますが、実際に授業を受けたらもっと楽しいんだろうな〜とハードルをあげてみる(笑)
1投稿日: 2023.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログポケモンやプリキュアの命名法則など身近な例をもとに、本格的な音声学の研究について知ることができた。一見役に立たなそうな音声学が、イントネーションやアクセントが重要な歌手やコロナの正しい情報を色んな言語で伝える時など、様々なところで貢献しているのが分かり、面白かった。 連濁のルール(ライマンの法則)など、普通に学術的な知識がすっと入ってくるし、「にせたぬきじる」「にせだぬきじる」の違いなど説明も分かりやすかった。
0投稿日: 2023.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
たとえば、日本語学の素養がある読者が読んだ場合には、そんなにびっくりすることはない気がする。題材は目新しいものが含まれているが、内容は啓蒙的。 触れられて語られていない内容にこそ、マニアの興味は向くのかもしれない。
0投稿日: 2023.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ外来語は「連濁」にならない(狸汁はたぬきじる、だが、たぬきスープはたぬきズープ、にはならない)。 bach、salad、など、日本語で語尾の子音を発音するときは前の母音に引っ張られる。 ハッシュドポテトではなくハッシュトゥ。ボンバーマンではなくボマーマン。等、言語学に基づくトリビアと、そこに体系があることへのワクワク感に引っ張られる。 必要以上の著者の承認欲求アピールや、「痛い」感じが全体を読みづらくしている感はアリ。
2投稿日: 2023.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の時から翻訳家になりたかったり、センター試験の勉強で発音記号の面白さに気付いてしまい「言語」にはたぶんずっと興味はあった。 大学では「純ジャパ」ながら言語学のゼミに入り、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を学び、スペイン語もど初心者だったのにバスク語の研究を齧った。そして難しすぎてほんとに齧って終わった。(ごめんなさい) でも、言葉は面白いと思っている。社会人になって、仕事の都合上、中国語を学ぶ機会があったのがとても面白かった。が、頭でわかっていても思った通りの発音が出来ない言語だった。同じ漢字なのに英語より難しいのなんで…と泣いた。 初めて韓国に降り立ったのは仁川空港でのトランジット。なぜ、隣の国の言葉なのに全く分からないのか驚いた。(欧州に行けば仏だろうと西だろうとアルファベットで単語も似ていてなんとなく分かる) そして数年前からK-Pop界に足を踏み入れ、ハングルを勉強してみようかな(の状態が3年超続いている)となったんだけど、古に学んだ発音記号の知識はめちゃくちゃ役立っている。 と、前置きが長くなったけれど。 何故この本を読みたいリストに入れていたのかは分からない。どこで出会ったのか。 ナムペン(BTSのRMのファンのこと)、ラプラペン(BTSのラップメンバーのファンのこと)を拗らせすぎて、ラップの研究をしようと思っていたのか。 実態として世界の共通語となっている英語を母語としない私たちは、母語と英語をミックスして使うことが当たり前になっていて、似た発音、異なる発音をうまく使い分けている。それは韓国も同じ。 東方神起やBIGBANGからK-popは聴いていたがバンタンに出会い歌詞の哲学性やラップの面白さにドツボにハマった。沼である、沼。初見でカッコイイ。(怒られるかもだけどビジュがというよりはオーラがカッケー!という感じ)気になるから歌詞の和訳を調べると、え、めちゃくちゃ深い。哲学的。政治的。社会的。 そして韓国語のオトの面白さ。韻の面白さ。日本語ともラテン語源とも違う独特の音。日本語と共通の単語や発音。悲しい歴史も含めて、あらためて言語に興味を持った。 奇しくも私も幼児の成長も近くで見ている。言葉を学ぶ過程。家で使わない乱暴な言葉(ため息)にいつの間にか直っていた言い間違い。(ピリリ=テレビ等)いつの間にか彼の頭に装備された平仮名やカタカナという文字。発音。教えていないのに音の持つイメージ。(自作恐竜の名前になぜ濁音がたくさん入るのか、とかね) なんとなく、肌で感じていた音のもつイメージを言語学なんだけど身近な事例や90年代を生きた世代に嬉しいアーティスト(zeebraとか)を用いて分かりやすく解説してくれる、興味深い一冊でした。 「言葉」を持つ唯一の生物としてのミステリーを 「人間「 × ×のせい」って思いがちだけど、ラップはそんな思いを「 × ×のおかげ」に変える力を持っている」このフレーズは私がラップを好きな理由を纏めてくれている気がする。そう、ラップはその人の人生そのもの。 ぜひBTSのリリックの巧妙さを著者には見て、分析頂きたいと思った。
0投稿日: 2023.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の魅力は、言語学を筆者がなによりも愛していて楽しんで執筆している様子が伝わってくるところである。 ポケモン・プリキュア・ラップなど、身近なものを話題にしてわかりやすく言語学のおもしろさを教えてくれる1冊。 以前から少し興味があったが、言語学に触れたのは初めてだった。最初は堅苦しい感じじゃないといいなーと思っていた。しかし、その不安はインパクトのある題名、それと蛍光黄色の派手な装丁が吹き飛ばしてくれた。中身も題名・装丁に負けず親しみやすい感じで、どんどん読めて面白かった。 マイボイスの話であまり考えてこなかった声の大切さにも気づけ、とても感動した。
1投稿日: 2023.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログFreestyle Linguistics https://www.daiwashobo.co.jp/book/b602398.html
0投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ才気走った言語学者の自分語り。けれん味たっぷりだが嫌味がない、というか、嫌味にならないよう工夫して書いている。(その「配慮してますよ」感もにじみ出ているが)。言語学の面白さ・大切さを、軽い語り口でしっかり届けようという著者の目論見は見事に達成されている。すごいなと思う。
0投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと読みたいとは思っていて、 図書館で見つけて即借り。 想像以上におもしろかった! 最後あんなに泣かされるとは思わなかった!! 世界中で数多くの研究者が、自分の研究分野をどう社会に活かすか、悩んだり、奔走したりする姿が、川原先生のお仕事を通して初めて具体的に知ることができた。 研究者という職に就く人たちへの印象も大きく変わった。 川原先生が、本当に言語学が好きで、若い人にもわかりやすく伝えたい、学問が楽しいと感じてほしいと思っていて、自分の研究にも誇りを持って臨まれている。そんな様子が文字からひしひしと伝わってくる。 ものづくりでもエンタメでも、あらゆる分野に共通するけど、そんな人たちを見ると心が浄化されるようで気持ちがいいし、自分もそうなりたいと意欲が湧いてくる。 先生は特に、偉い先生なのに偉そうじゃなくて(笑)、実績をみると(研究とか学問とかぜんぜん深く知らないけど)言語学の世界では雲の上のような存在なんだろうな〜というのがわかる。 でも大学生に講義したり、入門としての易しい本を執筆したりしてくれるあたり、私たちの目線まで階段を降りてきてくれるような、そんなありがたい存在だな〜とも思う。 まさに私みたいな、言語学に興味はあるけど難しそうでとっつきにくいな〜と思っているような人にちょうどよい一冊。笑 内容としては、言語学の深く広い世界のほんの上澄みかもしれないけど、充分に驚きと発見をたくさん楽しめた。 ラップや歌、アニメのキャラクターへの名付けの側面から紐解かれることばの謎も、ちょっと難しかったけど、次々繰り出される日本語の発見パンチにページをめくる手が止まらなかった笑 あと共感したのが、日本語は難しくはあっても決して特殊な言語ではないということ。どんな言葉も平等に大切ですばらしい。英語のほか中国語や韓国語にも触れる機会があって、それぞれに発音の特徴やことばの歴史をたどることに楽しみを見出しているところなので、先生と同じように感じていることが嬉しかった。 外国語を勉強する時も、「できない=恥ずかしい」ではなく「できない=可愛い」のマインドを持っていきたい。 言語や部族名など、白人目線からの蔑称が歴史的に残ってしまっているものを改名していく動きにも、言語学が大きく関わってくると知ったことが驚きともに納得感があった。それも言語学の担う大事な仕事なんだ。 少数言語話者がコロナ禍で感じた不安を払拭しようと動いたり、難病の方を声を残すためにマイボイスを作ったり。 言語学の分野がいろんな方向から社会とつながっていく様子が手に取るようにわかってワクワクした。 読み終わる頃には、すこしの興味はもっと大きく膨らんで、「もっと知りたい!」の種を見つけられる意義深い1冊だった。 先生の授業、1回受けてみたかったな!!
3投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学、音声学、音響学に興味を持ちにくい言語聴覚士とその学生にオススメ。学生の頃に読めば講義を興味持って聞けたのにと思う。
0投稿日: 2023.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋でたまたま目に入り購入。 自分自身、日本語ラップやアニメが好きなので興味を持った。 生まれてからずっと使い続けて来た日本語の深さに触れることができた。 新たに知ることができたこと。 メイド名研究の項で、音声学には共鳴音と阻害音という区別があるという事。濁音が付くのが阻害音、つかないのが共鳴音という事らしい。 確かに、昔からレナとかリナとかナナとかはギャルっぽいとか源氏名っぽい名前だな、って思ってた事が言語化されて長年の疑問が溶けた。そうか、そういう名前は共鳴音という濁音がつかない文字で構成されていたんだな。 阻害音が入る名前はどこか和風なイメージがぼんやりあったのもそういうところだ。 ポケモンの名前の研究では進化するほど濁音が増えていく法則なども納得。 このような、日常にあるありふれた固有名詞が持つイメージが言語化されて解説される爽快感があった。 そういった事以外だと、後半にあるALSの方用のマイボイスというサービスの開発に携わった話はウルっと来た。 もし自分の大切な人が声を出せなくなったら、など今までは考えた事は無かった。 言語学というものが社会の役に立つのか、と著者の川原先生は苦悩したこともあったらしい。 この開発への参加を通しての貢献、ほかの学生ボランティアの人生に影響を与えた事など、川原先生の奥さんが言った「あなたの研究を通して学生さんたちに面白いと思わせたら、それは立派な社会貢献なんじゃない?学問の楽しさを伝えるのも大事な仕事よ」という言葉に集約されているように思えた。 この言葉は自分に取ってもとても励みになった。自身の仕事に置き換えて考えてみようと思う。 言語学という分野について何一つ興味が無かった自分にも楽しく読めた1冊。 普段の生活の中で飛び込んでくる言葉や文字の聞こえ方と見え方が今後は変わると思う。
0投稿日: 2023.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「はじめに」で著者が書いている通り、言語学について真面目に扱いつつも具体的なエピソードが交えられておりとても面白い。 共鳴音と阻害音を伝えるために「女性の写真では共鳴音を含む名前がより魅力的とされ、男性の写真では阻害音を含む名前がより魅力的とされる傾向にある」という論文から、メイドには「萌えタイプ」と「ツンタイプ」の2タイプがいると仮定して「萌え」=「女性的」=「共鳴音」、「ツン」=「男性的」=「阻害音」を検証しようとする発想がすごい。 著者の義母の使う好きな方言ランキングで、「んだっちゃ」をあげ、それが同意を表していること、さらにそれに似て非なる『うる星やつら』のラムちゃんの「だっちゃ」が「私はラムちゃんだよ」の役割語(類義語として「ござる」「んじゃ」)であることも書いている。普段何気なく使う言葉の中でも、「役割語」という概念があったりと、言語学という世界が広がっているのだと知って楽しくなった。 言葉が与えるイメージが学術的に証明されていたが、そもそもそういう証明をしようという発想がすごい。 山寺宏一さんの声が科学的に検証されていたのもおもしろかった。 そして、言語学がおもしろいというだけではなく、ALSになった患者に対して自身の声を録音した音声ソフトを作成する活動を行ったり、コロナにおいて正しい情報をどんな言語を使う人に対しても伝えられるような活動を行ったりと、役に立つ学問であることもしっかりと伝えていた本だった。 ぜひ著者の授業を受講してみたいし、普段の言葉も大切に疑問を持ちながら使っていきたい。
1投稿日: 2022.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ一冊の情報量、凄すぎる…。母音3要素・構音点・共鳴vs阻害音や両唇破裂音における音象徴・音声の3尺度・呼吸法・方言と鼻濁音・エントロピー・連濁・無声化・文の構造 などなど。 楽しく読みました。感想は、音声学って学生時代から好きだったけど、この本は今まで読んだ本の中でも面白い。身近なテーマで入門にとても良いと思います。ライトに書かれているけど、用語の難しさはあります。けれど、言語学(正しくは音声学)に興味のある人が読むから大丈夫、多分。 言語学界隈で人気の川原先生の本。良い研究者はユニークな実験をされているのね…そしてそれを思いつく事がすごい。こんなに有名な先生でも世の中の役に立っているのか悩むなんて驚きです。研究が臨床現場のエビデンス検討や効率化を支えてくださってます。世の中の役に立っています。研究者の皆さん、ありがとうございます。
0投稿日: 2022.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学の中でも「音声学」に着目した一冊。著者はポケモン言語学で有名な方。メイド喫茶、ドラクエ、フリースタイルとポップな題材を絡めて音声学の事例を紹介しているので入門書にうってつけだろう。半エッセー本でもあり、著者の、言葉を楽しもうとする姿勢がとても良かった。
0投稿日: 2022.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログゆる言語学ラジオきっかけで言語学に興味が出てきたおり、図書館で表紙を見て読んでみた。 著者の専門分野は音にあるみたいで、日常に近い事例で音声学について色んな興味深い事例あり。日本語は意識して使ってないけど、なるほどとか言われてみれば、みたいな法則など、面白い。
0投稿日: 2022.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
もともと興味のある分野だったということもあるが、内容は間違いなく面白かった。唯一のネックだった文体の寒さというか痛さは、後半に行くにつれて減じていったので一安心。 漢字1字の2字の読みに見られる子音や母音の限定とか、促音化する語しない語の違いとか、どれも面白くてとても覚えきれないので、手元に置いていつでも参照できるようにしたい。
0投稿日: 2022.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書といい川添愛さんといい 一般向け教養書が面白くなければ言語学者じゃない という変な誤解を生みそう
0投稿日: 2022.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ書評で知り、装丁が気になって読んでみた。 近々に読んだ『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 』と同じ著者と読み始めてから気付いた。万人向けでどちらか読むなら本書、子育てに興味があるなら後者をおすすめ。 言葉遊びが気になったり、好きな方にはうってつけで、そうでない人には気になるきっかけになると思う。
1投稿日: 2022.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言語学ってなに?ってレベルだったけど、学問の本らしからぬハジけた装丁(うまい)と、ドラクエやポケモンなどの文字列にまんまと惹かれて読んでみた。 そして期待通り、わかりやすく楽しく言語学・音声学を学べた! 一緒に法則を発見しながら読んでいけて、面白さがちょっとわかった。入門としてとてもすてきな本。 普段意識していなくても、自分もみんなも当たり前に身につけている言語や音声の法則がこんなにあるんだなあ。英語圏の人が英語の構造をそんな理解せずに使っているという感覚が謎だったけど、日本語でも同じことが起きてて理解できた。「にせたぬきじる」も、当たり前に「にせたぬき」+「しる」だと分かる。 連濁とライマンの法則は特に面白くてお気に入り。日本語は「っ」+「濁音」が嫌い、ひとつの単語にふたつの濁音が入ることを嫌う、本当だ! ハ行はもともとパ行だったという話も、清音(無声音)と濁音(有声音)の比較を見て納得!t・d、k・g、s・zの関係性と、h・bの関係性は違って、同じなのはp・b。とっても面白い。 ドラクエの新しくできた呪文いまいちどれが一番強いのかわからんなーとストレスを感じてたのは、これまでの法則に当てはまらないからだったんだな。子どもながらに無意識に法則を理解していたらしい。ポケモン名とかは意識的にわかってたけど。 人の名前が本人や周囲に与える印象や影響についても考えていたのだけど、音声学的にも裏付けがあるということで、今後名付けの際には両唇音だ濁点だとか考えながら決めたいと思う! 学問的にも勉強になったのだけど、著者さんの視点や生き方からも学べるところが多かった。 “言語学者は、特別な理由がない限り、言語に対して「かくあるべし」という言い方をするのを好まず、「あーこういうことが起きたんだー。どうしてそうなるんだろー」と観察と分析に心血を注ぐ生き物なのだ。” (p.168) とか、“「できない=恥ずかしい」ではなくて、「できない=可愛い」の方が強いんじゃないかな” (p.174) 、東京方言を標準語を呼ばないし訛りは素敵だとか、物事を見る時の柔軟で優しい視点、とても素敵だと思った。見習って、「間違いだ!直せ!」ではなく「かわいいな」「おもしろいな」と思う心で生きたい。 それに、とても楽しそうに生きているなという印象を受けた。日常の中でも研究の中でもおもしろいものを見つける態勢ができている。わくわくして、自分の足で動いて、自分の頭で考えて、人に感謝して、人の役に立つことを考えて。もちろん楽しいだけではないけれど、楽しむ姿勢が素晴らしい。自分が持っている限られた時間も、こういう風に使っていけたらいいよな。 あと、山寺宏一さん、すごいとは思っていたけど言語学的観点から見ると益々すごすぎて大尊敬!ジム・キャリーの吹替の時は英語訛りになってる、かまめしどんの時は母音も子音も宮城方言で素敵な鼻濁音、銭形警部の時はアメリカ人声優のように声帯だけでなく披裂軟骨も振動させている、とか何⁉︎ 神にもほどがあるよね‼︎
3投稿日: 2022.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ川添愛とはまた違って、音声学からアプローチする言語学の啓蒙書。アニメのキャラ名が半濁音を多用する訳は日本人には感覚的に自明であるが、学問的に追求、理論化して英語圏の研究者にも評価されるということなどを解説する。自画自賛をやたら連発する語り口には反発を覚えながらも、意義ある研究成果であることには異議は唱えられないところ。
0投稿日: 2022.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ色々発見もあるし、研究(自由研究)ってこうやると楽しいなー、あと趣味でも身近なところからモノを考えるのは、人生を楽しくするなあ。読み返したいところがたくさんあるのでKindleでも買おうかな。
0投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすく取っつきやすく面白い。 エルデシュ数とベーコン数おもしろい。 ポール・エルデシュが気になって調べた。Wikipediaでポール・エルデシュを見つけ、語彙や署名のところがスゴイ面白かった。
1投稿日: 2022.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「あ」は「い」より大きいを書いた方の最新刊。 自身や家族への思いもあり、言語学の興味がそそられる話が満載。また読もう。
3投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログで可愛い表紙と言語学という面白そうな内容に惹かれて購入。 身の回りにある固有名詞から感じる印象と、発声するときの口の動きや音の法則性が関係していることが面白かった。 それを分析するためにメイド喫茶に通ったりラッパーの人と話したり、ポケモン名やドラクエの呪文を分析したり、いろんな分野の中にある言語を観察していくので分かりやすかった。 運動不足から始めたヨガのなかで呼吸と言語につながりがあると発見するのも、普段からアンテナ張るってこういうことなんだな〜と感心したし楽しそうなので真似したいと思った。 メイド喫茶行ってみたい。
0投稿日: 2022.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学者、川原繁人の言語学の入門書というかエッセイ? 言語学というと世代的にソシュールやチョムスキーが思い浮かぶのだが、著者である川原繁人は言語学でも専門は音声学や音韻論で内容もそちらに寄ったもの。プリキュアやポケモン、あるいはメイド喫茶のメイドの名前や日本語ラップなどキャッチーな題材を判りやすく言語学的な問題として読み解いていく。 考えてみれば当たり前だが多くの言語は発話される以上、人間の口や舌、喉などの身体的な構造上の制約を受けざるを得ないのだな。 他の本も読みたくなった。
1投稿日: 2022.06.03
