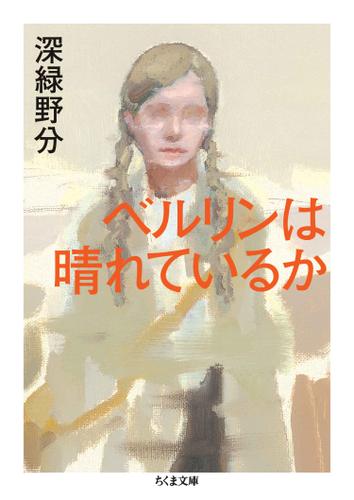
総合評価
(97件)| 23 | ||
| 42 | ||
| 17 | ||
| 4 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ良かった。日本の小説でここまでドイツの戦時中のことの物語が読めるのも凄い。 そしてこれこそ、再読したくなるミステリー(私はこの小説、ミステリーとはあまり思っていない)だ。 ジギは憎めないやつだな。 ダニーもいい人だ。 ギゼラのことを庇ってあげるように教えてくれたお父さんの話かたはとても好きだった。 この小説は素晴らしいと思う。 ドイツの歴史を知りたくなる小説でもあった。
1投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあるのは文字だけのはずなのに、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、そして味覚までもがとてもリアルに感じられる作品。情景描写はもちろん、音、その場の空気の表現まで細かくて本当に戦後のベルリンにいるような感覚になった。特にすごいのが、食事の表現。戦前の温かい家族の食卓も、夏至の日のアイスクリームも勿論だが、特に驚いたのは戦後のそれ。作者はワニ肉とかカエルのスープを食べたことがあるのか?と思った。 文章自体はそれほど難しくないので中学生でも読みやすいです。(少々大人向けの表現はありますが。)
1投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ敗戦直後のベルリン。孤児のアウグステ・ニッケルはアメリカ軍の管理地区のレストランで働き糊口を得ていた。 ある日の夜、帰宅後に米兵が現れ、ソ連軍管理地区のNKVDに引き渡される。 どうやら昔の知人が毒殺し、殺人の疑いをかけられたようだ。 疑いをはらすことはできたが、ナチスの残党がテロを企画しているという話もあり、ベルリン公開後ポツダムで三巨頭の階段も迫る中、殺された知人の息子を探すことを命じられ、ユダヤ人と一緒に探しに行くことになる。 サスペンスというジャンルのようだが、読んだ感想はサスペンスではなさそう。
1投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ濃い、濃い、濃い。あなたは戦争を経験したドイツ人ですか?ってくらいにみっちりと戦前、戦中、戦後のドイツが描かれている。2箇所の誤植(文字化け)もご愛嬌。これはたまらん本です。
3投稿日: 2025.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦直後の分割統治されたベルリン。一つの死を解く道程と過去の回想が交互に現れる。語り口は素直で読みやすく、衣食住や町並みや会話や空気の匂い、圧力や苦痛や死までが等身大で入ってくる。だからこそ、タイトルとラストが、眩く、目に沁みる。 読みながら同じ時期に、ポッドキャスト「COTEN RADIO」の「オスカー・シンドラー」のシリーズを聴いていた。アウグステとカフカ、レオン少年とシンドラー、ルートとマリア。創作と現実を往来しながら同じ時空に存在していた人たちの関係性、意志や行動に思いを馳せる、それも物語の解像度を高めるのに役立ったと思う。
3投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ国家が、名も無き大衆が、冷静に考えれば違和感のある方へ、道義的ではない方へと歩み始めた時。暴走しだした時。 あなたは、私は、それを止めるべく動けるか。 それとも日常に埋もれて、考えることを放棄するか。力なき一市民にできることなどないと、我が身を守るだけか。 Noと言える人、立ち向かえる人が多数派になったとき、きっとようやく人類世界から虐殺や戦争がなくなるのだろう。 いや、どうだろうな。結局のところ、変えられるのは自分の言動だけで、ひとたび何かを強く思い込んだ他人を説得することは、同じ風土の中に暮らしている人同士でさえこんなに難しいのに、そんな日は来るのか。来て欲しいのだけど、正義はそれぞれにあって、だからこそ人間は、たとえ善人でも残酷になることがある。 ならばせめて、お前は何を選択し、どう振る舞うのかと、自問自答を放棄しないべきか。 戦争を決断する時、負けた場合を考えないやつらに、舵取りを任せてはいけない。どんな時でも、最もひどく犠牲になるのは、私たち庶民なのだ。民主主義に生きるなら、私たちは考え、主張することを放棄してはいけない。 他人に刃を向けるとき、その刃がいつか自分に向くかもしれないことを、忘れてはいけない。なぜ人はいつも自分は迫害できる側だと思ってしまうのだろう。 そんなことを思った、考えた作品だった。 ナチスが政権をとる前夜から、戦中、降伏後のドイツを舞台に、それぞれの情勢下に生きる人々が克明に描かれる。大きな政治や軍事の話ではない。日々を生きる一人一人の姿だ。監視され、密告され、飢え、連行され、殺されていくユダヤ人。反ナチズムの人たち。"アーリア人"でない民族。社会の役に立たないと決めつけられた人々。 違和感を感じつつ、ナチズムの過激化をついに止められなかったドイツ人。そして爆撃に脅え、飢え、過激に批判され、陵辱されていくドイツ人。 膨大な資料を元に、史実に誠実に、敬意をもって書かれた作品であることが分かる。 簡単に善悪を語らない点も素晴らしいと思った。 深緑さん、お見事でした。
2投稿日: 2025.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり期待して読んだのだが、あまり引き込まれなかった。ベルリンやその周辺の地名がたくさん出てくるが、土地勘がないため上手くイメージできなかったのが原因かもしれない。文体もちょっと苦手かも。 ナチスによる差別や迫害の描写には心が痛んだ。
0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ第2次世界大戦終戦直後のドイツの話。戦中の様子が幕間として描かれ、ドイツ市民の困窮ぶりやユダヤ人、障害を持つ人への差別が詳細に書かれていて読んでて胸が痛くなる。 主人公の芯の強さが周りの人をも正しい道へと導いた気がした。
1投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめて、戦時中のドイツを題材にした物語を読んだ。 最初は少し時間がかかったが、ベルリンの街、その当時の空気感がとてもイメージしやすく、途中からは一気に読み進められた。 話は重いけれど、読み終わったあとは満足感があった。
1投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログきちんと取材されているんだろうなと感じる。戦火の中とあと。ナチスドイツの前と後。キャラも魅力的。とても面白かった。
1投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめは暗く辛い戦争の話が続きますが後半の展開は目まぐるしく変わり続きが気になりました。 第二次世界大戦の詳しい描写に辛い気持ちになりましたが、戦争と人間の愚かさを教えてもらいました。 もっと世界史を勉強しなくてはとういう気持ちになりました。
0投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「同志少女よ、敵を撃て」を読み、同じ時代のドイツ側の物語を読みたいと思い手に取った。 ベルリンが舞台。ドイツが降伏して間もない頃と、ドイツがナチスに傾倒してやがて破滅に向かう1928年から1945年までを交互に描く。 とにかく重い。普通の人たちがじわじわとナチスの考えに染まり、熱狂し、やがては優生思想や民族排除を何とも思わなくなる様がリアルで怖い。 更に敗戦国の悲惨な現実も描かれている。 ナチスを誰も止められなかったのかと非難するのは簡単だが、いざその状況になったら、不可抗力な気もする。日々高まる生活への不満の中、あの男がじわじわと力をつけてきた。気がつかないうちに思想を植え付けられ、あるいは抗えば処刑される状況で何ができるだろう。今でも有り得る話で遠い昔の出来事で片付けてはいけない。 作中のベルリンの街の解像度が高い。よくこれだけ再現できるものだと思ったら、巻末に多数の参考文献が。当時を忠実に再現しながらミステリのエンタメ性もあり、面白かった。特に後半は一気読み。 なぜ戦争が起こるのか、その時国民は何をしていたのか、今だからこそ読んでおきたい一冊。
4投稿日: 2024.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
起承転転承結みたいな感じ?笑 期間を開けて読んでしまって、話が抜けかけた。戦争描写、心理描写が本当に美しい。 個人的理解としては、ユダヤ人や障がい者が犯罪者として迫害されてるとき、本当に犯罪者だったのはアーリア人、ドイツ人だったってことだよね。人種なんて不確定なもので、人を決めることはできない。結局のところ、何人だろうが極悪人はいるし、聖人はいる。 物語的驚かされる起承転結ではなかったけど、、導入が好きだったかな。読み終わった時、見返したらあの導入は必要だったのかは疑問だけど笑 あと、アウグステのお父さんのギゼラの薔薇の話は涙無しに読めなかったわ。刺さった。 第二次世界大戦後のドイツが分割されるまでの歴史をほとんど理解していなかったから、それまでの混乱について勉強になった。 どこの国も、戦後に抱える問題は似たものがあるよね。誰に支配されたとか、どんなものが足りなかったとかじゃないものが。 戦争というものが生み出す、言葉で書き表せない残酷さを、体験していないのに、本や映像から知ることができるって今生きてる人の特権だよね。
1投稿日: 2024.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦で敗戦後間もないドイツでの物語 幕間として、主人公視点で戦前、戦中、そして物語の冒頭に繋がるまでが断片的に描かれる 以下、公式のあらすじ --------------------- 戦争が終わった。 瓦礫の街で彼女の目に映る空は何色か ヒトラー亡き後、焦土と化したベルリンでひとりの男が死んだ 孤独な少女の旅路の果てに明かされる真実とは―― 読後、きっとこのタイトルに心が震える。 1945年7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4ヵ国統治下におかれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立しつつある状況下で、ドイツ人少女アウグステの恩人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた毒により不審な死を遂げる。米国の兵員食堂で働くアウグステは疑いの目を向けられつつ、彼の甥に訃報を伝えるべく旅立つ。しかしなぜか陽気な泥棒を道連れにする羽目になり――ふたりはそれぞれの思惑を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。 --------------------- 日本での戦争に関する様々なエピソードは好むと好まざるに係わらず子供の頃から知る機会はあったわけだけれども 同盟国であったドイツの状況に関しては、ナチスの行ったユダヤ人の虐殺をしってはいても具体的にどんな状況だったのはは詳しく知ろうとしなければ知る機会がない この物語がどこまで事実に基づいているのかは不確かだけど 巻末の参考資料を読めばその確からしさがわかるのだと思う アーリア人から見た戦争とはどんなものだったのか 戦時中に自ら積極的に行った事ではなかったとしても、「戦争だったから仕方がない」のか 戦後に断罪される「善良な市民」と、その「責任」 指導者を選んだ責任 そうせざるを得なかった社会の風潮 そして自己を納得させるための理屈 いくら抗おうとしても、個では難しかったのかもしれないけど 迎合していた大多数はどのようにすればよかったのか ユダヤ人を「移住」させていたというけれども、善良な市民はどこまで真実を知っていたのか 優生思想に基づく差別や断種 人は自分が差別されない立場であれば、差別とは思わないのかもしれない 戦後の分割統治された混沌とした社会 日本もアメリカ、ソ連、中国で分割統治されていたらどうなったのだろうか 結果論ではnあるけれども、アメリカ単独というのはマシな選択だったのだろうなぁ 主な登場人物 アウグステ・ニッケル デートレフ・ニッケル マリア・ニッケル イーダ クリストフ・ローレンツ フレデリカ・ローレンツ ファイビッシュ・カフカ (ジギスムント・グラス) ドブリキン大尉 べスパールイ軍曹 エーリヒ・フォルスト それぞれの信念や思惑 物語が進むにつれて読者がわかってくる事情 最後はまさかそんな展開になるとは全く予想していなかったなぁ ストーリーよりも、ナチス・ドイツという国の出来事が衝撃的だった
4投稿日: 2024.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログアウグステの生き様に色々と考えさせられました、戦争後を舞台としていますが、回想シーンでは戦時中の悲惨な様子もありありと描かれており胸が痛くなるようなシーンも多かったです。結末には色々と驚かされました。 文章構成が難しい本だったのでなかなか読み終わるのに時間を要しましたが、読んでおいて良かったと感じます
1投稿日: 2024.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか進まず?という展開がある。最後にジギの手紙という形で「もやもや」がスッキリする。途中なんとなくアウグステが歯磨き粉に毒を入れたのはわかってしまう。戦争前後のドイツの混乱した世の中を感じとれたのは良かった。最初から読み返したいけど既に延滞なのでまたの機会にする。
1投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ1945年7月ベルリン…敗戦直後のこの国にはソ連・イギリス・アメリカ・フランスと色々な戦勝国が入り乱れ… … … て、ごめんなさい。難しいことは分かりません^^; その分からないながらの感想をぜひ!m(__)m とにかく、敗戦後のこの地に力強く生きる17歳の少女がとあるきっかけで、ある人の訃報を1人の少年に伝えに行く物語。 これ、たった2日間なのにP523。 こりゃ時間かかるな。と思いつつ…ま、まとまった休みも利用しつつではありましたが、あっという間でした。 あれ?これって著者さん日本人だったんだ⁈と後になってから驚いたのは…そう、この物語に日本人は出てこなかったから…ですね。 確かにテーマは重たいし、目を背けてはならないこと。 ただ、悲しいことだけではないし光は見える。 光が見えるからこそ感動あります。 この本に出会えてよかった^ ^ この時間ありがとうございました♪
1投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ初深緑。決して楽しい物語だったとは言えない——ただロシア・ウクライナ戦争が起きている今、読むべきタイミングであることは間違いない…。これに近しいことが今現在行われていると——私(たち)に何が出来るだろうか…。主人公・アウグステの恩人を殺したのは一体誰なのか・・この謎を解き明かす、本編と幕間の構成も見事だった。 彼女の未来に幸あれ。と願わずにはいられない——タイトルの意味をよーく考えてみたい一作でした。
3投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦のドイツで、少女が人を探す。ソ連、アメリカ、ユダヤ人など当時の情景がわかるが、自分には合わせて内容。
0投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『戦場のコックたち』で、ミステリ要素が戦時中というシチュエーションに対して少し浮いていると感じた部分が、本作では両者の融合率がぐんと上がっている。 旅の目的上、クリストフに毒入り歯磨き粉を渡したのは誰なのか?という謎を避けて通れないところ。また、膨大な資料や取材から成る、圧巻の情景描写にさりげなく忍び込まされたヒントがその一因なのかな、と感じた。 幕間も、序盤は戦争によって変化していくベルリンを描くためのパートなのかなと思っていた。その実、アウグステの動機をこれでもかと納得させられることになるとは。 読んでいて辛い描写が山積みだが、アウグステ以外の登場人物も一人一人の造形が深く、引き込まれた。
1投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログほんと救いがなくてヘビーな内容だったけど、なぜ?と疑問がいっぱいあったので、ラストが気になり最後まで読めた。 人間の生への貪欲さ、強さ、目を背けたくなるような残虐さ。 戦争になれば、普通の人もこうまでなれるんだろうか? ウクライナ、キーウも出てくるし、今も戦争してる地域ではこのようなことが行われてるのかもしれないと思うと、胸が痛むけど、私に何ができる? ナチの支配下にあったドイツの人たちもあの状況にあって何ができた? 虚無感に襲われる。
3投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かった 久しぶりに時間のかかる一冊 文庫本の文字の小ささに辟易したし 話も辛かった 事細かに、実際こんなことがあったのだろうという そんな事柄が書かれていたせいもある 生まれた国や時代に感謝しないと
1投稿日: 2024.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦直後のドイツ・ベルリンを舞台にしたあるドイツ人少女が主人公のミステリー。 合間にある戦時中のストーリーも合わさり、かなり読むのが辛く、途中で何度も挫折しそうになりました。 ただただ苦しかった。 以前訪れたダッハウ強制収容所を思い出し、つらすぎました。
0投稿日: 2024.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代背景があんまり理解できないまま読んだせいなのか入り込めなかった。 ミステリーというよりも、ロードノベルというべきなのか。 戦時下の生活や、敗戦国のたどる状況などの悲惨さはリアルな描写です。これを書くには相当な当時の国家関係や市井を理解していないと書けないだろうなと想像しました。
2投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は数年前までベルリンに住んでいたので、舞台の地理的感覚がよくわかって読みやすかったが、そうでない人は相当頻繁に地図の頁を振り返る必要があるのではないだろうか。また、あまり日本人に馴染みのないドイツ語をそのままカタカナで表記しているところも多く、読みやすさよりも異国情緒を大事にしているように感じたが、それでいて登場人物の言動や描写が現代的過ぎて白けてしまう場面も… ストーリーはまあ、あっと驚くラストってほどでもなく、伏線回収も好みが分かれるところかも。ただ、戦時中〜連合国占領直後のベルリンの混乱ぶりは臨場感たっぷりに描かれており、「日本は鬼畜イワンどもに占領されなくて良かった」とつくづく感じさせられました。
1投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ同著者作の、『戦場のコックたち』を読んで自分好みの文章を書く人だと思い、同年代の設定の話であるこの作品も面白いだろうと考えてこの作品も読んでみたがあまり面白みを感じられなかった。 第二次世界大戦中後のドイツの薄暗さ、饐えたにおいのする生っぽさを強く感じられる文章ではあったが、その演出がくどく没入感が得られなかった。 ドイツ人の戦後に晒される加害性は、日本人のそれと同様であり、歴史を見つめる上で無視して生きることは不可能なのだと強く思う。
0投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦降伏直後のベルリンが舞台。戦争で両親を亡くした17歳の少女が恩人の訃報を伝えに行方知れずの甥っ子を探す話。 混乱の極みにあるベルリンで強かに生きる子どもたちや勝者として振る舞う連合軍。一筋縄では行かない捜索の行程で助けられたり裏切られたりしなぎら目的を果たすが、意外な結末にたどり着く。 戦争終結直後のベルリンがありありと目に浮かび、かなりしんどい気持ちになる。 ナチスのホロコーストや空襲による無差別攻撃など、人を殺すことに対して何の呵責も持たない状況と、戦後の1人の人間の死が対比されているように感じられ、改めて死の重さってのは状況に応じて変わることにげんなりした。 最後の最後に種明かしがあるが、主人公の思うところは十分理解できたとは言い難い。が、それなりにさっぱりした読後感。
1投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログもうあまり覚えてないけど、ドイツ語学科だから読んでみないとと思って買ったことは覚えている。 戦後の生々しい感じとかが描かれていて重い感じだったなあ。戦争もうしてほしくないって思った。 色々ナチスのこと勉強してきたけどあまりにも残酷だし、悲しいよね。もう2度とこんなことしないでほしい。
0投稿日: 2024.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ心とカラダ 頭が 元気でないと 読めない 。モノクロ映画のように 場面が展開して 勝手なイメージが膨らみすぎて 悲惨とか 残忍とか そんな言葉じゃすまない世界にひきずりこまれてしまったから。アウグステは悪くない。あなたは 賢くて利口な子。 私たちはみんな、走って、走って、息が切れ心臓が止まるまで走って、戦争を駆け抜けた。 〜この一文が全てだとおもう。
8投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ敗戦直後の混乱に揺れるベルリンに生きる人々の様子がよく描かれてお歴史・文化を学ぶ上でも興味を惹くだけでなく、ミステリとしても読み応えのある良書。
2投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦の頃のドイツ。本編では戦後になっていたのでホッとしていたけど、幕間ではガッツリと戦中。なかなかにしんどかった。「同志少女よ敵を撃て」がソ連側の話だったので、本書と対になっていて面白い(ソ連軍の女性狙撃手の話です) 遠い国、過去の出来事をまるで自分が体験したかのように感じられ、世界が広がった。やっぱり読書っていいな〜
1投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むのが辛くなります。 全くの真実ではないのでしょうが、ナチス支配下と戦後の人びとの生活が、映像で見えてくるぐらいにリアルで、辛い。 戦争?生活の苦しさ?民族の違い?何が原因で、人は人を排除していくのだろうと、考えてしまいました。
0投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたまこの作者のことを知り、なにか著作を読んでみようと、図書館でこの本を借りてみた。 けっこうな厚さで驚いたが、さくさくと読み進むことができた。 数年前、日本語で読める稀有な当時の一次史料である『雪あかり日記、せせらぎ日記』(ドイツに赴任中の建築家・谷口吉生による当時のベルリンやナチスの様子が描かれる日記)、および、『あのころはフリードリヒがいた』、『波紋』でナチス・ドイツとその周辺については知識が深まったところだったので、わりとスムーズに読めた。 (映画ではジョジョラビット、帰ってきたヒトラーを見た) 話は暗いけど、史実はもっとダークだろう。 謝辞を読んで、豪華な名前に目がくらんだ。 ドイツ翻訳家の酒寄さん(解説も書いてらした)、設定考証の白土さん、今やお名前を見ない日はないくらいのロシア通の小泉悠さん、大砲とスタンプの速水螺旋人さん…うーん、売れっ子たちが犇めいていた。 さすがの取材力である。 それにしても、なんでこの小説はこんなに長いんだろう。 話はけっこうシンプルなのになあ。 読みどころはどちらかといえば、過去を埋める幕間のシーン。 中盤、主人公とハンスとの「復讐したい相手への処置」の会話はなかなかに重い。 最後まで読んだらまた出だしを確認したくなる本だ。
4投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツ側の開戦前から敗戦までのリアルな描写がわかりやすく描かれていた ささやかな幸福を見なおす良い機会を得た
0投稿日: 2023.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台は第二次世界大戦後のドイツ。 戦争直後の日本ならともかく、ドイツを舞台とした小説は読んだことがなかったから、新鮮だった。……とは言い、内容は凄く重い。気軽に読むものではない。だがその分、当時の情勢、空気感にリアリティを感じる。 犯人は全く予測がついていない人で、意外だった。動機や犯行の手法自体は読んでて理解は出来るが、ミステリー特有の読了後のスッキリ感・爽快感はあまりない。やるせなさが残る。
0投稿日: 2023.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ第9回Twitter文学賞(国内編) 2019年本屋大賞第3位 このミステリーがすごい! 2019年版第2位 ナチス時代から一転、第二次世界大戦後の敗戦国となったドイツでは、米ソ英仏の4カ国統治下におかれながらどのように人々が過ごしていたのか、壮大なスケールで描かれた歴史ミステリーです。 ミステリーの要素よりも、徹頭徹尾リアリティのある描写が当時の映像をイメージさせ、何度もやるせない想いに駆られながらも作者の手腕に感服しました。 馴染みのない名前だらけ、旅の途中で色んな出会いもあり、登場人物も多いので何度も人物紹介ページと照らし合わせながら読み進め、ページ数も多いのでかなり時間がかかって読了しました。 壮大な物語を読み終えた後は、歴史の一時代を読み終えた充足感があり、この小説と出会えて良かったなと思いました。
10投稿日: 2023.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を見てるみたいだった。 辛い描写も多かったけれど、まるでその場の空気を感じられたような気がしました。 面白かった。
0投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読んでる途中、終わるな終わるなと思いながら読んでた キャラクター性とリアリティのバランスが良い感じがして、登場人物全員が好きになれそう 終わり方もえ!?となるほど…が共存する感じで、もう一回読み直したくなった
0投稿日: 2023.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争によって狂った心、目を覚ました猛獣の存在を自身の内側に感じながら、それと葛藤する自分。何が正義で何が悪なのか。登場人物の心象が緻密にそして生々しく描かれており、映像を見ているかのような錯覚さえ覚えた。 1939年、アウグステが中等教育のときの回想にて、迫害を受けていた隣人のイツァークの言葉「どれだけ締め上げられようと人の心は自由なんだよ」がひどく心に響いた。 中盤以降、心身ともに傷を負った登場人物たちの一つ一つ行動が物語の最終章へ収縮していく。読み進めるにつれ、引き込まれていき、「ベルリンは晴れているか」という題意を考えさせられた。
1投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代背景や当時の生活が資料に基づいて描かれていることがわかり、あの時代にドイツで生きていた人々のリアルな生活が想像できた。 ただ、読み物として没入しづらく、最後までいまいちストーリーを楽しめなかった。
2投稿日: 2023.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
過去と現在を交差させながら、陰影に富んだ主人公の心情描写と、克明な戦時下のベルリンの描写が際立つ物語でした。 戦況が悪化するにつれ、暗殺を恐れて民衆の前に姿を見せなくなるヒトラーに対する反感や、収容所送りにされていくユダヤ人や移民を、自分たちの都合の良いように解釈して、見ないふりをし、ついには歯止めのきかない崖っぷちに立たされていたドイツ国民。その流れもわかりやすく、ドイツの雰囲気を残しながら読みやすい文章でした。 最後、腑に落ちないのは、クリストフが自殺をしたこと。 子供を毒でじわじわ弱らせ殺すのが好きというのは、戦争とは関係のない、特殊な性癖によるものだと思うけれど、そんなサイコパスが、主人公から責められて何故自殺を図るのか?戦後の混乱する闇市の中でも次の獲物を物色するような人間が、主人公に見破られ、指摘されたくらいで自殺するほど自責の念にかられるだろうか。 ただ、クリストフが自殺だったからこそ、爽やかな読後感が味わえるのかもしれない。
2投稿日: 2023.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争直後のベルリンの状況を調べられたとは思う。 調べたことすべて盛り込みたい気持ちは分かるが、最後の意外な結末を迎える劇的な伏線にはならなかった。 逆になかった方が良い。 なぜエーリッヒが映画の撮影所が固まってある場所にいるのか、その必要性がいまいち分からない。 なぜカフカがDPキャンプに、米軍の軍曹が出て来る必要性が分からない。 それよりは、彼らを真実を導き出すための伏線にすれば良かった。 孤児窃盗団のエピソードは、本筋と微妙にズレている。
1投稿日: 2023.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログまるで翻訳の本を読んでいるかのような硬派な文章でした。そうゆう文章の方が私は好きですが、展開がゆっくり進むので読んでて少し飽きてしまいました。しかし、まるで戦後のドイツにいるかのような細い描写は素晴らしいと思います。肝心の結末は、尻切れトンボで終わった感があり、なんとなく消化不良でした。
2投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ総統の自死、戦勝国による侵略、敗戦。何もかもが傷ついた街で少女と泥棒は何を見るのか。1945年7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4カ国統治下におかれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立しつつある状況下で、ドイツ人少女アウグステの恩人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた毒により不審な死を遂げる。米国の兵員食堂で働くアウグステは疑いの目を向けられつつ、彼の甥に訃報を伝えるべく旅出つ。しかしなぜか陽気な泥棒を道連れにする羽目になり・・・ふたりはそれぞれの思惑を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。 現代の日本人が書いたとは思えないリアルな戦後ドイツの民衆が描かれて、著者が取材などいったいどれほどの努力をしてこの綿密な世界観を作り上げているのか怖くなるほど。最初はカフカの背景が気になったけれど、序盤から問いかけられている通り、アウグステがエーリヒを探す本当の理由は最後に明かされます。結構びっくりしたけど、結局ローレンツの真意は何だったのかな・・・ともやもやしてしまった。フレデリカも気づかないってそんなことあるのかな。背景の作り込みがすごい分、本筋がいまいち納得できなくて少し消化不良。アメリカやソ連に支配される中で日々を懸命に生きる一般市民のつらさや混乱、その中でも何とか立ち上がろうとする姿は尊いし、逆にユダヤ人に限らず同性愛者など何かを標的にして「正しさ」を決めつける世の中にしてはいけないと、今の時代だからこそ肝に銘じる必要があると感じました。
0投稿日: 2023.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログまるで少し前の時代の硬派な翻訳本を読んでいるような圧倒的な臨場感がありながら、登場人物の内面やキャラが丁寧に描かれ、ある意味突飛ともいえるプロットも、違和感なく入ってくる。ミステリーというにはある程度予想できる展開ではあるが、そうした犯人あてなどどうでもよくなるほど、主人公から目が離せなく引き込まれる。 これこそ作家の力量に圧倒される作品に出合えた幸せを感じられるものであった。 PS p278、477の多分「掴」が?となっていたのは誤字だろうか?
0投稿日: 2023.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
描写とかすごくリアルでエピソードもかなりキツくてこれがリアルなんだなとかんじました 描写とかはすっと入ってくるものばかりで難しい内容だけど文体とかははいってきやすかったです
0投稿日: 2023.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦後、ドイツ。 潜伏先で世話になったおじさんの死の謎。ユダヤ人のフリした男とのロードムービー。 驚きはないが、戦後ドイツの生活がありありと描かれている。幕間のヒトラー政権になってからの悲惨な運命を辿る国とそこに生きる人の生活が生々しくてよかった。 日本人が出てこないのも珍しいよね。
0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリはもちろんのこと、戦時中、戦後のドイツのことが詳しく書かれていて、とても良かった。 何年も前だけれど、アウシュビッツ強制収容所を見学したときのことを思い出した。 国のせい、戦争のせいにすることは誰でもできるけど、その道を進む政治家を選ぶのは国民である自分たちなのだと言われたこと。
0投稿日: 2023.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ドイツの終戦辺りの様子が詳細に把握出来た気がする。幕間という形で主人公の背景を描写するのも新しくて面白かった。 確かにこの流れで行くと犯人は決まっちゃうよな〜… アウグステは強く生きたなあ
0投稿日: 2023.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦が終わった年の七月、ベルリン。 アメリカ軍の兵員食堂で働くドイツ人少女、17歳のアウグステ・ニッケルの目線を通して見る戦後のドイツを舞台にした、本編は二日間だけの物語だ。ある人物に会うために危険を犯してポツダム会談の前日にハーバルスベルグへと向かう道中の事件の数々。 そこに「幕間」と題して、アウグステの誕生から、本編の数日前までが交互に書かれる凝った編成の本だ。 幕間が、本編の種明かしのように構成され、また、アウグステという少女が、1928年のヴァイマル政権下のドイツにて生を受けてからの、壮絶な17年を追体験するように読ませることで、よりその目線をドイツからのものに寄せる。 これを読む前に、「戦争は女の顔をしていない」を読んでいたので、私の目線はソ連側、戦勝国側寄りで、尚且つ歴史の大筋に於いてのナチス・ドイツの蛮行、あの地獄を全否定する目線からやはり入っていくことになるので、そういう意味でも面白い追体験だった。 ミステリー作品であり、ネタバレ要素が入るといけないので詳しい筋には触れずに、感じたまま書く。 幼い頃のアウグステの、隣人のユダヤ人家族への普遍的な親しみとか、同じジートルング(集合住宅)に住むダウン症の少女への、複雑だけど根本的に温かい思いとか、父親(共産主義者)の思想とか、そういったものが、国民社会主義ドイツ労働者党、つまりはナチスが台頭していくにつれ、破壊されていく様。 ジワジワと日常に侵食していく主義思想。「まだ、大丈夫。」 「まさかあのような思想が」 思っているうちにするするとそれが正しいことになっていき、どんどん適応していくドイツ。純正なアーリア人以外、何かしらの不具、思想の違い。少しのズレも許さない国家によって消されていく人々。 アウグステ達家族も、思想の違いをひた隠しにして、息を潜めるように生きていた。 「全部、ナチと戦争が悪いんです。全部。」 自分に言い聞かせるように呟くアウグステ。 大きな歴史から見たら、その中にドイツ人全体が含まれるように見てしまう人は多いだろうし、実際に戦ったり、征服されたりした国の人、迫害を受けた人からしたら尚更だろう。 アウグステが反ナチで、母からはぐれたポーランドの少女を匿い、父と母を祖国に殺され、終戦間際にはベルリンに上陸してきたソ連兵に陵辱されていたとしても、だ。 「あなたも苦しんだのでしょう。しかし忘れないで頂きたいのは、これはあなた方ドイツ人がはじめた戦争だということです。善きドイツ人?ただの民間人?関係ありません。まだ、まさかこんな事態になるとは予想しなかった、と言いますか? 自分の国が悪に暴走するのを止められなかったのは、あなた方全員の責任です。」 NKVDの大尉が冷たく言い放つ。 このお互いの感情に、どうやって折り合いをつけるんだろう。この巨大で決定的な断絶に。 善くありたいと思う気持ちに嘘はない。けれど、人が人を喰らうような極限の状況で、それを保つことが誰に出来ようかと思う。ああ、夜と霧のV.Eフランクルなら違うだろうか。 私達は殆どがただの人なんだという思いと、ただの人が戦争を始めるんだという事実。 二日間の旅の道中に出会う様々なルーツの「生き延びた」人々との交流には、暗さもあるが、生き延びたが故の貪欲さ、明るさもあって、全編にうっすらと光が見えるのだ、そこの書き方が素晴らしいと思ったし、だからこそ読み進められたんだと思う。読み終えたとき、タイトルの意味も深く伝わる。 著者はこれを書くにあたって、実際にベルリンに足を運び、膨大な資料に触れている。責任をもって書いたのがよく伝わってくる、調べながらじっくり読む本だ。読んだ後と前では景色の変わる力を持った本。 あー、善く生きるってどういうことなんだろう。昔はみんな赤ちゃんで、子供で、多分みんな等しく尊かったはずなんだろう。瞬間瞬間の正しさを選んで、間違えて、次があるって思っていたら次が来なくて。。これからもずっと、死ぬときまで考え続けるんだろう。 ケストナーの「エーミールと探偵たち」も読まねば。アウグステの、絶望の中の光となった本。 読み終えてからすぐに一ページに戻りたくなる小説は絶品、その定説(自分の)通りの傑作でした。
1投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者を好きになるきっかけになった作品。 ベルリンでの状況を細かくストーリーに落とし込んで、ミステリー要素もあって現在と過去で交互に話が進んでいく展開もすごかった。
6投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ衝撃的な印象を受ける小説だった。大戦中のドイツが舞台を主人公のアウグステの目を通して、様々な状況が見えるような描写で作者はドイツ人と思った。 大混乱の中を生き抜くアウグステの生き方も彼女を取り巻き人々も個性的な魅力的な人達でミステリーと歴史が融合されたような読み応えのある小説でした。作者が若手の日本人とは驚いたが巻末の参考文献を見て小説家の努力と熱意を強く感じた。
1投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ少しずつ崩壊していった日常と第二次世界大戦後のドイツの様子の対比が見事でやりきれなさを感じながらも一気に読み終えた。特に終盤が素晴らしかった! 『戦場のコックたち』に引き続き、「手紙」というアイテムの使い方があまりにも完璧すぎる。 子供の目線に立ってナチスドイツや第二次世界大戦を見つめるとここまで景色が違うのかと驚いた。 今なら『ジョジョラビット』の終盤、ソ連の兵士が登場した展開を観て胸を撫で下ろすことなんてしないだろう。 明日も同じような朝を迎えられるなんて言い切れない。 保証はない。 そんな世界を私達は生きている。 それを強く強く噛み締めながら眠りたい。 良い小説だった。
0投稿日: 2023.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーが面白く、登場キャラクターそれぞれに魅力が詰まっているのはもちろんだが、私が一番この作品で惹かれたのは表現の仕方だった。 同作者の『オーブランの少女』を読んだ時にも感じたが、この作者の言い回しはとてもおしゃれでわくわくすると改めて感じた。 物語にはあまり関係ない、ただの事実の描写なのにとても魅力的な表現がたくさんあった。
0投稿日: 2023.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恩人のクリストフが毒入りの歯磨き粉で死亡した。疑いをかけられた主人公であるアウグステが、その時に知ったクリストフ・フレデリカ夫妻の甥っ子エーリヒ。彼にクリストフが死亡したことを伝えるために旅に出ることに。 その旅には、元俳優であるジギや孤児の子達が同行したり、ソ連の秘密組織が絡んできたりと面白かった。また、第二次世界大戦後のドイツを舞台にしているが、翻訳小説かと思うくらいに描写が生々しかった。旅の中で孤児の話や被災した動物園の話など戦時、戦後の悲惨な状況などが描かれていた。 真犯人が、主人公であったことには驚いた。流石に、それはないかな、と思っていたので。エーリヒが、クリストフの快楽殺人の餌食にならなくて済んだという安堵を知らせたいがために、長旅を買ってでたいうのや、主人公が、クリストフを殺害したいと思うまでの動機がイマイチわからなかった。家族同然と思っていたイーダが殺害されたからか?それとも、イーダを引き金として家族が戦争に殺されてしまったことへの贖罪だろうか。そこのところももう少し描いてくれると尚良かったと思った。
3投稿日: 2023.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023-3 ナチスとかユダヤ人とかぼんやりとイメージがあったものが自分がその場にいたように(ユダヤ人は主人公と隣人で仲が良かった)突然経験してこの世にこんな恐ろしい事があったのかと愕然とした。とても長い話だけどそのボリュームの分胸にずしっとくる小説だった。
0投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログあの戦争のさなか、そして戦後にドイツで暮らすというのがどういうことだったのか、リアルに感じることができた。ベルリンをさまようロードムービーのような作品だけれど、その中で様々な立場の人物から戦争が語られる。声をあげることが犯罪になってしまったときに沈黙するのは仕方ないのではないか、と思ってしまう自分がいて、ではいったいどの時点で止められるのか、答えがないことを考えてしまう。
1投稿日: 2022.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログナチスドイツの敗戦後のベルリンを舞台に、ある男の不審死により疑われた少女の旅を描くミステリー。 戦争の情景が思い浮かんでくる様な、密度の濃い作品。 誰も浮かばれない戦争の苦しさがリアルに表現されている。 普通に面白かった面白かったが、リアル感を出す為にあえて原語に忠実なカタカナ書きがされていて、それがちょっと読みづらく、長いと感じてしまった。
0投稿日: 2022.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文庫化を待っていた作品。 戦争という重いテーマを根幹にしながら、ときに軽やかに、そして最後はこれからへの希望を感じさせてくれた作品。『ベルリンは晴れているか』というタイトルは秀逸だな、と。実際に、“晴れている”のかどうかは分からないけど、その先は読者に委ねられているのかなと。 戦争作品の中で、ヒトラーに虐げられるユダヤの人たちの物語には何度か触れたことがあるが、その当時のドイツ人、にスポットを当てた作品は始めて。そのなかで、当時の政治状況やヒトラーという人物の禍々しいカリスマ性、群集心理、こういったものに囲まれたときに、はたして、あの時代、ドイツとう国に自分がいたとして、ナチスに傾倒しない、と言い切れる自信は無いと感じた。だからといって、致し方なかったという暴論ではなくて。人間1人1人は弱くて矛盾だらけでちっぽけな存在、ということの再確認。 一方、終戦後の暮らしは厳しいものの、要所要所でふとした瞬間の自然描写が多く語られていて、人の残虐さや愚かさとは無縁の、自然の力の逞しさのようなものを感じた。 ここからはネタバレですが、アウグステの最後の台詞。いわゆるドンデン返し。これは全然思いもしなかった。伏線はずっと張られていたのだけど。いろんなことが、実は1本の線(1人の殺人者)で結ばれていた、両親の死もエーリヒに会いに行くこともその大きな流れにあったものだった。 色々な要素が絶妙に組み合わされていて、考えさせられる作品でした。
1投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログベルリンを舞台にしたロードムービー的ミステリー。目的地までたいした距離でもないのに、とにかく予想外の出来事が次々に起きる。 ナチスドイツから連合軍支配下に移った直後のベルリンを背景とするがゆえに登場人物も悉くその背景を背負っている。 印象に残るのはブリギッテ2世。ほんの一瞬しか出てこないが、強烈な印書を残す。当時のベルリンでその後どのように生き抜いていったのだろう。
1投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦前後のドイツの様子とそこに暮らす人々の、リアルで精緻な描写が圧巻。 ミステリに分類されているが、推理を楽しむというより、目をみはるほど豊かな表現を味わうだけでも価値がある。
1投稿日: 2022.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1945年7月。 敗戦国ドイツのベルリン郊外にあるポツダムで、イギリス、アメリカ、ソ連の首脳が集まり、ドイツの占領統治などについて話し合ったポツダム会議が行われるそばで、ひとりのドイツ人少女が恩人の死を伝えるために彼の甥を探していた。 1945年7月時点のベルリンの様子が、主人公のアウグステの目を通じて語られるが、そこは弱肉強食の世界。 少し前まで傲岸不遜にふるまっていたナチスたちが今度は迫害され、ソ連の占領地区、アメリカの占領地区に分断されたベルリンでは、日々減少していく配給品の不足を埋めるために、ある者は媚び、ある者は地下に潜り、ある者は怯えながらその日を暮らしていた。 ドイツ人の音楽家が、青酸入りのアメリカ製歯磨きを使い殺されたのはソ連の占領地区でのこと。 彼はアウグステの恩人だった。 アメリカ兵のための食堂で働いていたアウグステは歯磨きを入手することが可能だったことから、殺人の疑いをかけられたが、釈放の条件として彼の甥であるエーリヒを探すことになる。 同行するのは陽気な詐欺師。 概ね日本人ばかりのところへアメリカ人だけが占領軍として滞在した敗戦直後の日本と違い、ドイツ人、ユダヤ人、ドイツが占領した地区から連れてきた外国人、ナチが迫害していたツィゴイナーなどが、それぞれに傷を負いながら生き延びようと足掻く。 アウグステが知り合った人たちの中には、ユダヤ人にしか見えない生粋のアーリア人(そのためユダヤ人からもドイツ人からも忌み嫌われている)や、性的マイノリティのため親に捨てられ矯正施設に入れられたドイツ人、強姦されたショックで麻薬中毒になった少女など想像を絶する若者たちが多くいる。 そんな現在の間に挟み込まれる、生まれてから現在までのアウグスタについて三人称で語られる幕間がある。 第一次大戦の敗戦後、辛く苦しい生活に追われるドイツが、いつしかナチスに傾倒し、さらに息苦しい世の中になっていく様子がここで書かれている。 アウグスタの父はドイツ共産党の支持者だったが、ナチスが力をつけるにつれて、油断すれば命の危険にさらされるようになっていく。 ヒトラーとスターリンが手を組んだ時から、共産党を脱退しても、決してナチに忠誠を誓おうとしない彼は、秘密警察に目を付けられていたと思う。 そんな夫を支え、娘を大切に慈しんで育てた母は、夫が死刑になった後、自殺する。 それが娘を救う道であると信じ。 善きドイツ人であったアウグスタの一家がこのような目に遭ったのは、ポーランド難民の盲目の少女を匿ったことからだ。 優勢思想をその信条に盛り込んでいたナチスが、アウグスタの身近に住んでいたダウン症の女性を、ユダヤ人の幼馴染みをどうしたのかをアウグスタは知っている。 そして彼らを助けるための手を差し出せなかったことが、ずっと彼女の負い目となっていた。 だから、盲目の少女(イーダ)を救いたかった。 そのことが彼女の運命を大きく変えてしまうことを知らずに。 ノンフィクションのように容赦なく書かれる敗戦国ドイツ。 しかしこれ、ミステリだったんだな、と最後まで読んで思い出す。 400ページ辺りの衝撃の発言で、時々チクチクと感じていた違和感の正体を知ることになる。 あのときああしていれば…という岐路は、人生の中に何度もある。 しかしアウグスタの岐路は、なんという人生に導いていったのか。 最後に、幼いころ父に買ってもらった英語版のケストナーの本が彼女の光となる。 ケストナーってところがまた、良かったな。 そしてそれを守り抜いてくれたホルンと名前を騙らないお洒落な女性。 いざという時、わたしは彼らのように行動できるだろうか。 ”自由だ。 もうどこにでも行ける。なんでも読める。どんな言語でも―― 失ったと思っていた光が、ふいにアウグステの心に差した。そしてその光は、今のアウグステには白く、眩しすぎた。”
3投稿日: 2022.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「戦場のコックたち」を読んでから、次はこの本が文庫になるのを待っていた。 「戦場の…」では「史上最大の作戦」や「遠すぎた橋」「バルジ大作戦」を思い出したけど、「ベルリンは晴れているか」と言われて「パリは燃えているか」を思い起こした。 その語感からだけではなく、西部戦線における大きな節目であったレジスタンス蜂起の物語はこの本に描かれた1年後のドイツの姿に繋がっているように思える。 ドイツが敗戦し米英仏ソの4ヵ国統治下に置かれた1945年7月のベルリン。ドイツ人少女アウグステの恩人にあたる男が、歯磨き粉に含まれた毒によって不審な死を遂げる。 恩人殺害の疑いをかけられたアウグステはソ連NKVD(内務人民委員部)に引き渡され、無実を証明するのであれば恩人の甥にあたる男を探せと命じられて、ユダヤ人の元俳優カフカを道連れにしてポツダム近郊(バーベルスベルク)へと向かう…という出だし。 このバーベルスベルクへの旅、戦後の混乱した街の状況に加えポツダムで米英ソの巨頭会談が行われることもあって色んな困難があり、ベルリン市内を行きつ戻りつ。 米英ソそれぞれの国柄が出た異なる統治の雰囲気や終戦後の街の様子、二人が出会う人々の複雑な心情が手に取るように伝わり、カフカや浮浪児のヴァルターとハンスが語る自身の物語には戦争の罪深さが滲み出る。 『憎らしい相手に会ったらどうする?』と問われたハンスが『僕は臆病だし、正義って何なのかわからなくなった。だからあの人たちが、もうとっくに死んでて、復讐しなくてすめばいいなって思うよ』と答えるところには泣ける。 ただ、展開がちょっと忙しく、二人が窮地に陥ると必ずNKVDが現れるところやミステリー仕立ての真相にはやや違和感。 寧ろ私には、アウグステがここに至った経緯が語られる“幕間”と称されたパートの印象が強烈に残った。 開戦前夜から戦争中の、ヒトラーの台頭とその非人道的な所業、それを目の前で見せられているような作者の筆致は息苦しくなる程に読むのが辛かったが、しかし、分断が進む現在の世界情勢を思うと今こそきちんと読まねばならないと思って読んだ。 そうした社会の大きなうねりが描かれる一方、あわせて個人の中での勇気の萌芽や正しいと思う行いを出来なかった時の悔恨も描かれ、正しい行いが必ずしも良い結果をもたらすわけではないという歴史上の皮肉も知った上で、それでも人としてどう行動すべきかを考えさせられるのだった。
21投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ登場人物が多過ぎ、私の読解力では状況の変化について行けなかった。 もう少し簡素化しても、充分にストーリーは面白く展開できたのではとの印象を抱いた。 物語は面白いのに、ちょっと勿体無いなと思った。
0投稿日: 2022.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦直後のベルリンを舞台とした長編小説。巻末に多数の参考文献が並べられており、当時の時代考証や生活様式の描写はかなり緻密。ナチスが強権を振るう戦中〜終戦直後の混沌渦巻く社会情勢を市井に生きる人々の視点で描くところに著者の熱量をひしひし感じる。然しながら、プロットやキャラクターの人物造詣は作り込みが浅く、物語の推進力は今ひとつ。登場人物の独白で事の顛末を語らせる手法もあまり感心は出来ない。過去作「戦場のコックたち」同様、著者が描きたいのはミステリーではなく、戦争が生み出す混沌とした社会の有り様なのだろうか。
0投稿日: 2022.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ不穏でいながら精密な描写、まさに体験したかったドイツがそこにありました。歴史物は歴史的なだけでなかなかリアリティも想像も膨らまないけれど、その舞台で起きる物語があれば入り込み易く、学びにもなり、スリリングでタフなナチス前後のドイツを体感できました。
3投稿日: 2022.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログドイツ無条件降伏から数ヶ月後が舞台。 幕間の戦前、戦中のドイツの様子に辛くなるけど非常に良いミステリでした。
0投稿日: 2022.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ3月にセレクトショップで見かけた本 もしこの本がミステリーじゃなくて戦争の惨たらしい部分だけを描きていたら、きっと読み終えられなかったと思う。 後半にいくにつれて繋がること、明らかになることが多くておもしろかった。
0投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ得た膨大な知識から必要なものだけを選んで物語を紡ぐ。すごいなぁ。これを読んで、自分は戦争について知ってるようで何も知らないんだなと感じた。
0投稿日: 2022.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ恐ろしく読了までに時間がかかってしまった。 パンドラの箱の底にあるのが希望だとしたら、読後味わっているこのある種の絶望は何だろう。 しかしその絶望感は決して言葉のままではなく、それこそが人間の生きる意味なのだと皮膚で感じている。 今この瞬間も戦争が起こっているこの世界。 余りに陰惨で卑劣で涙すら流したところで虚無感にしかならない戦争という時代を生きるということ。 私には経験がないので、所詮は絵空事でしかない。 なのにこの込み上げてくるシンパシーとは何なのだろう。 「たった」一人が殺害された事件を追う中で、一体何人の死を目にするのだろう。 時折もうこれ以上は読めないと心を砕かれそうになった。 余りにも軽すぎる命、そしてこれが現実だと突きつけられている。 大人も子供も女も男もない。みんな殺されるのだ。 人種も国も関係ない。 殺すものと殺されるもののみ、それがこの戦争だ。 なのに、私はこの本に感謝している。 アウグステには自分にも共感できる心の動きがたくさん見えたし、アウグステの決して愉快ではない道中記をなぜだろう、不謹慎なのは分かっているのにワクワクしながら読み進めてしまっていたのだ。 それはこの作者に恐ろしいほどの文才があるからだろう。
5投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次世界大戦後(日本はまだ交戦中)、世話になった知人の死をその甥に伝えるべく、占領下のベルリンを彷徨う2日間。 本編の間に「幕間」として主人公であるドイツ人の若い女性、アウグステの生い立ちが語られ、最後に、本編の冒頭につながる。 本編も幕間も、静謐な筆致で時代の空気がまざまざと描き出され、勇ましい開戦当初とすべての価値観が逆転した戦後と、いずれの局面でも抑圧される立場に置かれるアウグステの息遣いが重い。 彼女がなぜこの奇妙な旅に拘るのかが明らかになった時、戦争とは全く別の狂気の存在に暗澹となる。 もうひとつ、アウグステを追い立てるドブリギンの動機の方はあまりピンと来なかったけど。
0投稿日: 2022.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
戦後ドイツのお話。戦後といっても占領まもない頃なので、悲惨な描写が目立った。ヒロインはアーリア人の女の子なんだけど、父親は処刑、母親は自殺、友達は強制収容所送りと悲惨すぎる。ドイツは戦争を仕掛けた立場なんだけど、必ずしも経済的に楽な立場ではなかったんだと思った。 ストーリー、ヒロインは最後どうなってしまうんだろう。病院にいたみたいだったけど。結局、ヒロインが最後に何を思っていたのかわからないまま終わってしまった。あと、誤字…というか文字化けの箇所が二箇所あったんだけど、あれはわざとなんだろうか。
0投稿日: 2022.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人が書いているにもかかわらず、当時の情景が肌感覚で伝わってくる不思議な小説。特に、料理の香りや温度などの伝え方が見事。
0投稿日: 2022.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ何だろう・・・・読み終わって呆然としている。 最後のどんでん返しも衝撃だったのだが、それまでに分かってくる登場人物それぞれの背景が明らかになるにつれ、胸を衝かれるような思いをした。うまく説明できないなあ。もう一度読まなくては。
0投稿日: 2022.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画を観ているようだった。 > この国は、もうずいぶん前から、沈没しかけの船だったんだ。どこがまずかったのか、どこから終わりがはじまっていたのか、最初の穴を探し回っても、誰もがはっきり答えられない。全部が切れ目なく繋がっているからさ。 自分の心だけは自分が操縦する。 そんなメッセージを受け取った。
0投稿日: 2022.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
歴史的な背景知らないのが悪いんだけど、単なるミステリとして読むのであれば展開は想像しやすい。描写説明が結構多くてなかなか次の展開に行かず、一気に読むというよりはじっくり読む小説。
0投稿日: 2022.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログナチスが戦争に突き進んでいく、その社会の空気の変化の描写がすごいなと。もちろんミステリーのストーリーも面白いけど、やはり、時代ごとのドイツの雰囲気を読者に感じさせる描写が一番の読み応えあるところかなと思う。一つ一つのストーリー、登場人物、それら全てが、強いものではない側にいる人たちの視点で描かれていて、それがこの小説の根幹を作ってるような気がした。
2投稿日: 2022.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦中、戦後のドイツの息苦しさ、生活感を描き、ミステリーも引き込まれました。ミステリーの面白さだけでなく、戦争の悲惨さを改めて知らされました。
0投稿日: 2022.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争とはどういうものなのか、特に国の中が分断された最中の戦争、小説とはいえ、少しは感じて考えることができた気がする。そこには、民衆に対して嘘をつき、無責任な行動で自らの立場や利権を保持、拡大することだけを求め、民衆は、必死で生き延びようとする、時には近い人どうしでも裏切ったり、騙したりしながら。 主人公のアウグステが、自らの意思で養父・フレデリカが亡くなったことを伝えようと、昔に、家を出た彼の甥・エーリヒを探しに出る。第二次世界大戦で、ベルリンが陥落しドイツが敗北、直後のアメリカ、イギリス、ロシアがベルリンに入り、これからの統治を奪い合っている時だった。戦争は終わったものの混乱の中で、それぞれの登場人物が必死で生きようとしている。
2投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外を舞台にした日本人が主人公の小説は数多あるが、日本人が一切登場しない海外を舞台にした小説は稀有だろう。 著者は、1983年生まれで、舞台は1945年7月のドイツベルリン!巻末に記載された主要参考文献の数々に、この作品に対する著者の並々ならぬ思い入れが感じられる。 単行本刊行時から注目を集め、小説上の質の高さは、様々なランキングで上位を獲得し、直木賞候補になったことで折り紙付き。 主人公は、17歳の少女アウグステ。彼女が戦時中世話になった人物クリストフが毒死する。誰が彼を殺したのか?最後に明かされる真相には、意外性があり、ミステリー仕立てになっている。 物語は、クリストフの死を伝えようと、彼の甥を訪ね歩くというロードムービー的に展開される。 ソ連の軍人が重要人物として登場し、彼の部下にはウクライナ生まれも。昔日の感を感じてしまう。 書中、ソ連の軍人が語る言葉がある。 「しかし、忘れないで頂きたいのは、これはあなた方ドイツ人が始めた戦争だということです。”善きドイツ人”?ただの民間人?関係ありません。まだ『まさかこんな事態になるとは予想しなかった』と言いますか?自分の国が悪に暴走するのを止められなかったのは、あなた方全員の責任です」 この「ドイツ人」の部分を「ロシア人」に変えて、現代のロシアにそっくり差し上げたい。
6投稿日: 2022.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。第二次世界大戦敗戦後のドイツが舞台。戦争の愚かさ、恐ろしさ、様々なことを考えるきっかけになった。
0投稿日: 2022.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後のドイツが主に舞台の話で、ちょっと世界史が入っていた。 話としては読み応えがあって面白かった。ドイツを舞台にしていて、ドイツらしさがたっぷり入っているが、読みにくいということもなかった。 ただ、戦時中の描写は少し生々しくてきつい。
0投稿日: 2022.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいるさなかは気づかないけど、読み終えてから「当たり前のように読んでいたけどこの本すごくない?」と思うものに出会うことがあります。この『ベルリンは晴れているか』もそんな本でした。 話の舞台となるのは敗戦直後、アメリカやソ連の占領下に置かれたドイツ。語り手となるのは戦争時にソ連兵に襲われた暗い過去を持つ少女・アウグステ。彼女の恩人が米国製の歯磨き粉に混ぜられた毒による死を遂げ、アメリカ兵員食堂で働くアウグステはソ連の兵士から疑いの目を向けられます。 そんな中アウグステは恩人の甥に訃報を届けるため、陽気な泥棒を道連れに町を出ます。 すごいと思ったポイントは作品の密度とそして空気感。書き出しの兵員食堂の一場面から丁寧な描写ははじまりそれが作中ずっと続く。戦後ドイツの空気感、たとえば都市、米軍やソ連軍のキャンプ地、市民たちの生活、戦争の傷跡を抱えた人々…… 一場面一場面のリアルな描写が作品の密度を高め、読んでいくうちに作品の空気感が自分の中に共振していきます。 共振は戦争の不穏さや恐ろしさも切迫感を伴って伝わってきます。旅のかたわらの回想では戦争直前、そして戦中のアウグステの様子が描かれます。ナチスが権力を握り、反抗的な態度や思想は取り締まられ、障害者や同性愛者、ユダヤ人や外国人たちは連行されていく。 アウグステとその家族が徐々に追い込まれていく様子は、胸が裂けそうなほど辛く苦しい感情になりました。そして戦争の爪痕はアウグステ以外の登場人物たちからも見えてきます。登場人物ひとりひとりの苦しみや葛藤がいずれもリアルに感じられる。それはこの詳細かつリアルな描写が作品の密度を高め、空気感を作り上げていったからにほかありません。 巻末の参考文献の数を見ると、作品の圧倒的なまでの密度も思わず納得。これだけ力をこめられて作られた作品だからこそ、なじみのない国、なじみのない時代設定でも違和感なく読者を作品の世界へ引きずりこみ、そして感情を揺さぶるのです。 この作品の文庫版が発売された時期というのは、期せずしてロシアがウクライナへの侵攻を続けている時期でもあります。戦争というものはどういうものなのか。時のプロパガンダや独裁政治は何を生み、そしてどこへ行き着くのか。 密度の濃い描写から作り上げられた迫真の物語は、その回答の一端を突きつけます。力や暴力が世界を変え、プロパガンダやフェイクニュースが現実を蝕む不穏な現代において、こうした物語の重要性はこれまで以上に増していくのだろうと思いました。 第16回本屋大賞3位 2019年版このミステリーがすごい! 2位
8投稿日: 2022.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第2次世界大戦中のドイツの話。最後のどんでん返しがよい。今までにない設定でのミステリーで魅了されたが、時間の流れが前後するので、少し話の流れを把握するのに苦労した。
0投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ舞台は戦後間もないドイツ・ベルリン。 当時のベルリンはイギリス・アメリカ・ソヴィエトの三か国によって分割統治されており、どの統治下でもベルリン市民は惨めな思いを抱えて暮らしていた。 その中のアメリカ領で暮らす少女が主人公。 珍しく英語が理解できる彼女はアメリカ軍食堂で給仕として働いていたが、いきなり寝ている中をMPに叩き起こされ、なぜかソヴィエト統治区域に連れていかれる。 そこで知らされたのは、戦時中にみなしごとなった少女を匿ってくれた恩人の死であり、その死がテロによるものである可能性があるという懸念であった。。 目の前に情景が浮かんでくるほど描写がうまい。 そして飽きさせない。ちょっとハプニング起きすぎにも感じるが、当時の社会の複雑な問題をぼやかすことなく、克明に描きあげているのが凄い。 ここまでの作品をドイツ人でない人間が書けるとはと思うほどだった。
2投稿日: 2022.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第二次世界大戦後のドイツのミステリー小説。 2週間ぐらいかけて読んだ。言い回しやがわかりにくかったり過去と現在を行き来したりで若干の読みにくさ感じた。あえて日本人には理解しにくいドイツの表現を使用することで当時のリアルな空気感を重視している。 アンネの日記はユダヤ人だけど、この本の主人公はアーリヤ人。当時のユダヤ人ではない人の視点でも物語が展開される。 恐れや自分の利益のために、差別とか洗脳とか戦争とか虐殺が普通に行われていたということ、人間ほど残酷な生き物はいない。 後半に進むにつれ面白くなってくる。今読むべき一冊!
1投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ1945年7月、ドイツの敗戦で米ソ英仏の4ヵ国統治下のベルリンに住む少女。街は戦争の傷跡が生々しく、流通やライフラインは途絶えがち。統治国の軍に難題を出され、彼女はそれでも努力していく。真摯な彼女に影響を受けた人は多い。それにしてもこの真実は…… ウクライナの人たちにも平穏な時間が早く戻ってきますように 278ページの横向きの ”?” はなんだろう??
1投稿日: 2022.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔読んだ中村正軌氏の『元首の謀叛』 以来の日本人が書いた「東西時代のドイツもの」。 あれは東西の壁が崩れるころの話。 これはその前も前、第二次世界大戦後のドイツはベルリンでの連合軍統治(米ソ英仏)時代が舞台の歴史ミステリー。その後ドイツが二つにベルリンが二つになったわけだけれど。 まず評判通り、資料読みこなしの想像力と活力にあふれた本だった。 それはいいのだが、ヒロインのドイツ少女アウグステの冒険活躍を単純に楽しめないように、ミステリーの背景のドイツ敗戦処理に暗躍するソ連赤軍(秘密警察)情報局が、なんだか今現在を彷彿させるようで、ロシアのウクライナ侵攻状況を身近にしている時も時、妙な納得で読んだ。 しかしこと、ヨーロッパばかりではない。 地球上どこでも、人間が何世紀にも辿って生きていく歴史は、なんと複雑にして怪奇、縺れにねじれてほどけないのは趨勢なんだ。
6投稿日: 2022.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのミス2009年版2位。終戦前後のベルリンを舞台とした小説。一応、ミステリーっぽいけど場面場面の説明が多い。時代背景も良くわからないし、誰が何をしようとしてるのかが全く頭に入ってこない。そんな感じで読み続けるのが苦痛で一生読み終わらないではないか思った。やばかったです。なんとか20日かかって読み終わった。このミスランキングは読書マニア向けの骨太小説がたまに上位にはいってくるので、そういうのにあたると悶絶します。
1投稿日: 2022.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ミステリー小説としても面白かったが、第二次世界大戦下のベルリンを舞台とすることで、この時代の狂気を伝えようとしているように感じた。 戦後のアウグステ(主人公)の生活は、敗戦国として肩身も狭く物資も足りず大変だが、戦時下のナチスドイツの人種政策や言論統制の世界と比べると、はるかにマシだと感じる。 戦時下の悲惨さや狂気さは、戦争が進むに連れて激しくなり、「明けない夜はないが、明ける前の夜が最も暗い」という言葉が身に沁みた。
2投稿日: 2022.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦直後のドイツ、アウグステは恩人が毒入り歯磨き粉で死んだことで事件の捜査に巻き込まれる。 恩人の甥を探し、ベルリンを歩き回り、人と出会い、多数派ではなかった1人の少女の視点から、戦後と戦中のドイツの出来事と空気を描いた作品。 収録された地図を何度も見返し、アウグステの感じるにおいや温度を共有するように読んだ。 ミステリとしての面も素晴らしく、最後まで読むと、頭から読み返したくなるタイプの物語。初読時点でちゃんと違和感が散りばめられているので、とてもフェア。 いまの世界情勢下で読むことで考える事はとても多かった。ナチス政権下の主流派、中立派、反対勢力、の心の動きが摑みやすかった。 アウグステが現在に至るまでに出てくる、名前の出てこない2人の女性が印象的。喪服の女性と、洒落者の女性。 子供の視点だと名前を知らなくても人生に関わる人がいる、この描き方はとてもリアリティがあった。
2投稿日: 2022.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から気になっていたが、図書館で予約が回ってきたときは読みきれず(というかほとんど読み始められず)返却した。もう文庫化して、カバー装画もそのままでうれしい。 ドイツ敗戦後、連合国(英仏米露)が分割統治していたベルリンが舞台。
1投稿日: 2022.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋大賞入賞時から気になっていたもの。文庫化にあたり入手・読了。解説に書かれていて『なるほど』と思ったんだけど、日本読者の読み易さより、現地の空気感が重要視されていて、そのせいか、取っ掛かりにくさを感じたのは確か。でも難解というレベルではないし、読み進めるうち、自然とこの世界観に惹き込まれていくことになる。終戦後ドイツが各国に分譲統治され、どこへ向かうかという過渡期の混乱も見事に描き出されていて、戦時ものとしても秀逸。そして、舞台はベルリンだけど、大戦中激しく争ったソ連が絡んでこない訳もなく、ウクライナ出身の兵も登場。否が応でも、現在進行形の戦争を思わずにいられないけど、本作に触れ、その無道さへの反発を新たにする。戦争反対。
1投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
正しいのかはわからないが、この時代のドイツの空気感をよく表現できるなぁと思った。 基本的な筋はベルリンからバーベスベルクまでの旅程の中で様々な事件が起こるロードムービーの構成なので、付帯されているベルリン付近の地図をみながら、当時のベルリンを想像しながら読んでいると、重くて辛い内容も湿っぽくならずに読める感覚があった。 物語としてよくできていて、主人公のアウグステ目線で語られる、一見奇妙に見える他人の行動も根拠・理由があり、それは後にちゃんと明かされることになる。 そういったミステリー的要素が物語を読み進める求心力とはなるものの、しかし本当に興味深いのはそこではなく、さまざまな登場人物が語る、救われない当時の戦時下のドイツの状況ではないかと思った。当時の状況下で人はどのように思ってどのような行動をしたか。創作ではあるが、豊富な参考文献によって時代考証はされているはずなので、その記録とみても興味深く感じた。 自分がこの時代に生まれていたら、と考えずにはいられない。 2022年現在、戦争を仕掛けて世界から非難をあびているロシアに生きる人達も、戦争の賛否で分断が生まれ、それがエスカレートして弾圧につながっていったりするのだろうか。このような悲劇の時代を再来させないために、人間はどう行動すればよいのだろうか。 そういったことを考えさせられる現実感を得られた。
2投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦争とは何か人とは何かを考えさせる。 ミステリーとしての筋立てとしては唸る程ではないかもしれないが、そんな事はどうでも良いと思わせるディテールの描写力による第二次世界大戦終戦前後のベルリンの雰囲気が迫ってくる。 毎日TVでウクライナの戦争のニュースを見ているのでより具体的に戦争が迫ってくる。
1投稿日: 2022.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの時代のドイツのお話をドイツ人の視点から物語を日本人が書く、というものすごく難しいことに作者に挑戦させたのはなんだったんだろうか、そう問わざるをえない挑戦的な作品です。そしてその挑戦は成功に終わりました。ストーリー作りやキャラクター、描写なんかに、ものすごく時間をかけられたのでは、と想像します。あまりに苦しい状況の描写に、前半、若干読み進めることに苦しさを感じたりもしましたが、その丁寧な仕事に助けられて読んでいくと、後半の展開に引っ張られていきました。作者のさらなる挑戦に期待したいと思います。
4投稿日: 2022.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初から最後まで、ものすごく胸が詰まるお話でした。こういうことが昔、本当にあったんだという恐ろしさにぞっとしつつ、その最中で心と命を燃やして生きる人々の姿に、息できないような苦しさを何度も感じながら、それでも目を逸らしてはいけないと思いながら読みました。
2投稿日: 2022.03.28
