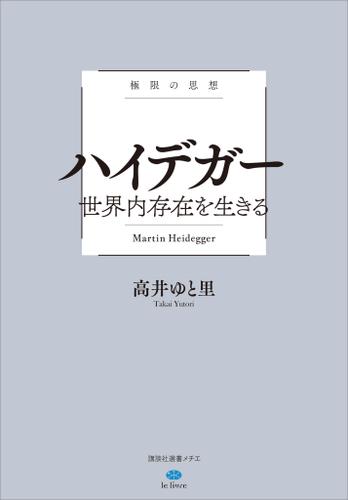
総合評価
(7件)| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は本書において、『存在と時間』を『私たちがそれぞれ「私」の生を生きているとはどのようなことか』という問いから解釈している。著者の説明は非常に丁寧であり理解しやすい。著者は『存在と時間』について『私たちが行為者として世界を生き、空間を踏破し、人々と共に生き、人生の意味を問い、自己についての物語を描き出す、そうした生き生きとした「生」についての哲学的分析が、そこにはある』、そのように語っている。 本書では、『存在と時間』は現代の小さな個人の物語に寄り添う本であるかのように語られている。他の類書が読者を『存在と時間』の時代に連れていってくれるのに対して、本書は『存在と時間』を現代に連れてきている、そういう印象がある。私は『存在と時間』の中心的モチーフについて、1927年という戦間期のドイツという時代背景もあって、『死へと先駆しつつ決意すること』において、「平凡で日常的で大衆的な在り方から脱却して、自己に固有の可能性に命を燃やせ!覚醒せよ!」という、いかにも『実存主義』な悲壮感と雄々しさを伴ったイメージを持っていた。当時のドイツで『存在と時間』が世間的な大成功を収めたことを考えても、そのイメージは間違っていないと思う(ハイデガー本人の意図とは異なる読まれ方だったとしても)。例えば他の類書では、『ひと』は「マスメディアや均一化する大衆社会への批判」をもって、『死へと先駆しつつ決意すること』は「戦争と不安の時代における若者像」をもって、具体例とすることも多い(これはこれで当時の時代背景からして正しいと思う)。対して本書では、『ひと』はマイノリティの人々への同調圧力として、『死へと先駆しつつ決意すること』はそのような人々が苦難や葛藤のなかで日々経験しているようなものとして、それぞれ例示される。著者が挙げる様々な例は、著者自身の関心に由来するものであることは間違いないが、それらは『存在と時間』の議論の内容をイメージしやすく膨らませるために効果的に使用されており、著者の思想を強引にねじ込むようなものではない。おそらく現代の読者には、「戦争と不安の時代における若者像」よりも「同調圧力に流されつつ抗って自分自身として生きようとする孤独な個人」の方が同調しやすいだろう。著者の解釈は、『存在の時間』の議論が持つ普遍的な射程の広さを示唆しているように思う。実際、本書の記述はしばしば胸を打つようなものであった。私は本書を読むまで知らなかったが、著者にはトランスジェンダーの活動家としての顔もあるようで、何かと言われがちなようである。しかし少なくとも本書における著者は、『存在と時間』の案内役として真摯であると思う。 どうしても本書で「足りない」と思ってしまう部分は、(1)「現存在の時間性」の説明がないこと(本来的時間性は「先駆-瞬視-反復」だ、というあれ)、(2)『共同存在』の『歴史性』に関連した『民族』の『運命』に関係する(今となっては)不穏な印象を伴う議論の説明がないこと、である。もっとも(2)は本書のコンセプトからしたら当然かもしれない。(1)については、ハイデガー本人の目指す『存在一般』に繋がる重要概念だとされるが、著者は『よく理解できていない』、『哲学的に成功しているようには到底思えない』と書いており自覚的に省略されている。この点は判断が分かれると思う。 『存在と時間』が未完の著作である以上、『存在の問い』あるいは『ハイデガーの思想史』を無視して、『存在と時間』を単独で理解するという本書の姿勢は判断が難しい。しかし、著者が強調するように、どういう読み方が『存在と時間』を『より網羅的に、また実り豊かに解釈できるか』というのも真だろう。だから、著者が本書の姿勢について『決してハイデガーの意図を裏切るものではない』とまで言い切る必要もなかったのではないか、そう思う。というよりも、やはりそれはハイデガーの意図とは違うと考えるのが自然だ。しかしながら、もっと率直に、「ハイデガーの意図とは違うとしても、ここには極めて重要な洞察があり、読むべき価値がある」、それが全てではないだろうか。若い著者であるので、ハイデガー業界の先生方への対抗心なのだろうか、などと少し思いもした。実際、本書は著者の読み方において素晴らしいものになっているので、ことさらハイデガー本人の意図から正当化する必要はないと思うのだ。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの思想に関しては先に読んだ飲茶の『あした死ぬ回復の王子』が物凄く分かりやすかったので、もう少し違う視点、更に原典に近い内容を読みたくて手に取った。それと、何より著者の高井ゆと里に興味があった。ノンバイナリーの哲学者である。 ハイデガーの哲学そのものは、やはり原典をきちんと読もうという結論に達した。私は物臭なので、原典の今の感性から少しズレた語感を今の感性に直して、その上で自分自身の思考に当てはめる所作を好まない。噛み砕いて解説する本があるならそれで良くて、原典を経験したマウントは、本質的にそこまで重要視しない。 ただ、本書は、高井ゆと里氏独特の感性というか、言葉遣いがあったと思う。それだけで満足である。高井ゆと里に何故惹かれたかは、自分自身の分析と共に、ゆっくり考えたい。
50投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ最上級に噛み砕いて、これほどわかりやすく『存在と時間』を解説してくれた本はない。 自分の生を日常性から一歩深い視点で見つめることができる。 初めて解説本を読んで、『存在と時間』そのものに挑んでみようと思えた。
0投稿日: 2023.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの『存在と時間』の解説書です。 『存在と時間』はかつて、既刊部分のみをもとに実存哲学の代表的な著作とみなされていましたが、その後「存在の問い」というより大きな問題設定のなかで『存在と時間』の位置づけを見なおすことの必要性が主張されるようになり、日本でも木田元が多くの著作を通じて、そうしたハイデガー解釈を啓蒙してきました。 もちろん、そのような理解が広く受け入れられたあとも、仲正昌樹の『ハイデガー哲学入門─『存在と時間』を読む』(2015年、講談社現代新書)や北川東子のハイデガー 存在の謎について考える』(2002年、NHK出版)など、あえて『存在と時間』の議論を実存哲学として紹介することで、その魅力を示そうとした著作はあります。これに対して本書では、『存在と時間』が現在われわれが手にとることのできるようなかたちで刊行されたことの意味を重視し、「存在の問い」という後年のハイデガーが手掛けることになる問題設定のなかで『存在と時間』の解釈をおこなうのではなく、『存在と時間』の内在的な解釈を通して、ハイデガーがわれわれの「生」についてどのような分析をおこなっているのかということを明らかにすることがめざされています。 その一方で、伝統的な実存哲学の概念に依拠して説明をおこなうのではなく、ドレイファスや門脇俊介といった研究者のスタンスが踏まえられているのかもしれませんが、現実のなかで実践的な活動をおこなうわれわれのありかたにそくしてハイデガーの議論を読み解く試みがなされており、新鮮な気持ちで読むことができました。
0投稿日: 2023.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がいまだに通読したことのない『存在と時間』についての読みをこの一冊で包括的に提供してくれた、(単行本ではあるが)新書的アプローチの本。注釈を中心に国内外の最新のハイデガー研究の成果が書かれており、読者としては信用がおける。 要約の仕方については論争的な部分もあることも含めて著者自身が丁寧に紹介しているが、素人目にはあまりその点はわからない。とはいえ木田元の「未完問題」アプローチがあることは知っており、それゆえ「未完のものをどう論ずるのか」という先入見が自分にも多少残存していたので、その懸念をかなり早い段階で棄却してくれた点は読み進める上でありがたかった。 ハイデガー哲学に必ずしも「(健常な)身体」概念を要請する必要はないこと、哲学における「自己物語」の話が現存在の同一性を認定する上で重要であることなど、20世紀哲学のあれこれを読みながらハイデガーをつまみ食いする上でしばしば引っかかっていたことをしっかり説明してくれたのも、よかった。 もしかして、このハイデガー本において示される自己論は、キルケゴールの実存主義哲学やメルロ=ポンティの身体コミの現象学より、プラグマティズム思想家兼社会心理学者であるジョージ・ハーバート・ミードの『行為の哲学』や、その後(主にイギリスの)質的社会心理学で展開された言説心理学(Discursive Psychology)のとる立場に近しいものとして読み直せるのではないか。そういう気づきを得させてもらった。それは著者が「ノンバイナリに気づく一人の男性」の事例について述べた時、ジェンダー論における哲学的アプローチとしてハイデガー哲学を参照したことで、より鮮明になったように思われる。
0投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「存在と時間」を実存解明の書として読むという視点が卓抜。 しかもかくまで平易に噛み砕いて解説した入門書はかつてなかったと言ってよいだろう。 ただ、分量が限られているせいか、やはり物足りなくはある。
0投稿日: 2022.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は「私たちがそれぞれ『私』の生を生きているとはどのようなことか』という問題に対する取り組みとして『存在と時間』を解釈する。 実存主義にも存在論にも還元できない、そうした『存在と時間』に固有とも言える哲学的洞察を評価する試みであることを個々に明記しておく。
0投稿日: 2022.04.11
