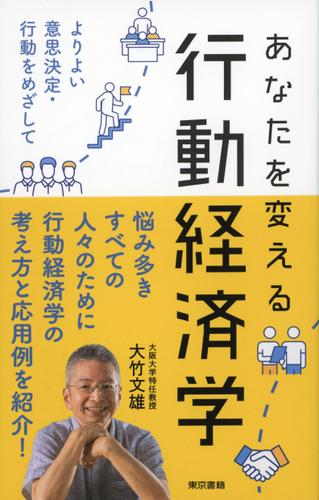
総合評価
(24件)| 3 | ||
| 7 | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本的な行動経済学。 サンクコスト、錯覚、損失を避ける、先延ばしの心理。 高校生からの質問に対し、行動経済学の観点から解説をしていく。
0投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は理屈では動かない。私たちの意思決定がいかに感情や環境に左右されるかを描き出す。「後でやろう」と先延ばしし「みんながそうしている」と流される。そんな日常の選択にこそ行動経済学の知恵は光る。罰よりも報酬、命令よりも仕組み――人を動かす鍵は意外なところにある。自分を責める前に行動を導く環境を整える。それが変化への近道なのかもしれない。
0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の行動やバイアスがわかりやすく書かれている。 実際の研究データをもとに調べられておりわかりやすかった。
9投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生に向けての連続講義からの理解しやすい行動経済学の入門書。様々な意思決定場面で合理的判断をつけていくヒントが得られる。高校生が出す身近な事例から考えの過程を追えることが、とても参考になった。
0投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学を体系的に知ることができた。先に読んだ後著の「実践行動経済学」の方が好みではあるが、こちらの実践例があってわかりやすかった。
0投稿日: 2025.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKのオイコノミアで放送した内容という感じだった。 p177の熊本の病院で行ったナッジの取り組み(日勤と夜勤の看護師のユニフォームの色を変えたところ、夜勤明けの看護師に医師が仕事を頼まなくなったので残業が減った)がとてもよいなと思った。
0投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学とは直感的意思決定が合理的な判断からズレる事。 ・サンクコスト 取り戻せないコスト ・損失回避 利得よりも喪失を回避したくなる ・現在バイアス 先延ばし ・ビア効果 みんなと同じ行動 ナッジとは、自由に行動はできるが、あなたのために望ましい選択肢を選びやすくする
1投稿日: 2024.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログサンクコスト 現在バイアス などが、高校生に行ったアンケートをもとに説明。 わかりやすいが、40代以降には質問自体がかけはなれている。 20代前半まで向け?
0投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学の類書を数冊読んだ中でダントツにわかりやすい本だった。高校生への講義がベースになっており、Q&Aも理解を深めるのに役立った。
0投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強やダイエットがなぜ続かない? 大阪大学の先生が高校生向けにおこなった行動経済学の講義を元に著した本。理論の説明と身近な行動がセットで提示されており、どのようにすればよりよく行動できるかの具体例が数多く紹介されるので、行動経済学とは何かを学ぼうとする人だけでなく、行動を変えていこうとする人にも有益だろう。
0投稿日: 2024.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【★5】【オススメ】考え方(表現)を変えるだけで、人間の行動は多少制御できる。これは他人にも使えるし、自分にも使える。大変勉強になった。
0投稿日: 2024.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学関連のを立て続けに読んだけど、とても興味深い分野だった。人は、サンクコスト(埋没費用)に振り回され、損失を極端に嫌うが、損失の基準も、参照点が異なれば、同じ内容でも損失とは思わずに行動してしまう。どこか合理的に装いながらも、不完全な状態である
0投稿日: 2023.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「行動経済学」というのを初めて知って、読んでみましたが、ちょっと難しくも感じましたが面白かったです。自分の普段の行動で、「上手く操作されていたなぁ」と思うところがありました。 ① 毎日、前日より1%でいいから成長する。すると70日後、実力は今の2倍になっている。 ② サンクコストをりかいすればあ行動を変えられる。 ③ 人は同じ金額であれば、利得よりも損失を約2.5倍大きく感じる。 ④ 人はよく分からないものに対して「何も意思決定はしない」という選択を選ぶ。 ⑤ 「純粋な利他性」は良し。しとご喜んでいる姿を見ると自分も幸せになるというもの。
0投稿日: 2023.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生相手にお話されたことがベースになっているからか、とても読みやすく、理解しやすい一冊でした。一つ一つが興味深かったので、何度も読み直しながら理解深めていきたいと感じました。
0投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログそうなんだよね。サンクコストは無視できないんだよね。人って弱いよね。と改めて実感する本。 アンカーとかナッジとか損失回避とか、実践できれば、もっと賢くなると気付かされる本。
0投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に3ヶ月前に出会ってたら、チケットは買ったけど、乗り気がしなかったフジロックには行くことはなく、安値でも売り払ったのに… と思えるような、日常においても、ビジネスにおいても目から鱗な考え方を学ぶことができた。 義務教育の必須科目にしたほうがよくないか?コレ
1投稿日: 2022.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
時間割引率が低い=将来のことを重視して考えられる。 サンクコストは忘れる。オランダ語を捨てて英語を勉強した福沢諭吉。大村益次郎は、オランダ人が翻訳したものを読めばいいと考えた。 人が来なくなった重要文化財はサンクコストか。将来盛り返すかもしれない、または外部性がある。=外部性があればサンクコストとは言えない場合がある。 人間の特性としては現在バイアスがある。現在を重要視する傾向。貯蓄目的にも表れる。 損失回避。損失のほうが痛手を感じる。プロスペクト理論。 デフォルトで意思を誘導できる。レジ袋が追加出費になるか、レジ袋代を値引きするか。損失回避との組み合わせでレジ袋の有料化はうまくいった。 デフォルトとコミットメントを組み合わせる=予定を入れておいてキャンセルを面倒にさせる。 ワクチン接種で、接種をデフォルトとすると、接種率が高くない場合無断キャンセルが多くて混乱する。 ヒューリスティックス=近道で考えようとすること。 社会規範=多くの人の行動、を参照点にするとそれに外れた行動は損失を感じる。マスク、制服の例。 相対所得仮説=周りの所得と比べて多ければうれしい。絶対額ではない。 「コミットメント、ノルムス、&カスタードクリーム」=約束、社会規範、カスタードクリーム。 自ら約束をして記入してもらうと、守りやすくなる。 この依頼のために、カスタードクリームを挙げると互恵性から、依頼を断れなくなる。 互恵性のためにはプレゼントらしく見せること。引っ越しの手伝いのお礼に、食事をごちそうするほうが、同額のお金を渡すよりも喜んでもらえる。カスタードクリームの代わりに300円だったら喜ばれない。 コミットメント=患者自身に予約の日時を記入してもらう。 限定合理性。どのくらい先を読むか。=フレーミング効果。参照点を変えると判断が変わる。 代表制ヒューリスティックとリンダ問題。 大小二つの病院の男の子の割合。 アンカリング=最初に見せた価格が参照点になる。 まったく関係のない事柄の数字でも、アンカリングになる。誕生月、学籍番号を書く、サイコロの数字、などもアンカリングになる。 ナッジは大きな金額をかけないこと。 ナッジは望ましい行動をとらせるもの、スラッジは本人には望ましくない行動をとらせるもの。 ナッジかどうか=EASTか=簡単、魅力的、社会規範を利用、互恵性に訴えている、タイミングがいい。 ナッジを選ぶには、何が原因かをよく考える。 現状維持バイアス、損失回避、各省バイアス、書記保有効果、選択過剰負荷、情報過剰負荷、投影バイアス(現在の状態が将来も続くと考えやすい) 具体的な行動であれば先延ばししずzらい。コミットメント効果で罰を決めておく。デフォルトを利用する。 看護師の残業を減らすため、日勤と夜勤のユニフォームを変えた。 外部性を減らしたり、市場競争を促進するためにナッジを導入できる。 男性の育児休暇をなぜ取らないのか聞き取りを始めると取得率が上がった。デフォルトで取得するようにした。 処方箋のジェネリック医薬品は、今は変更可がデフォルトになっている。 床に⇒を書くと、消毒する。喫煙所への⇒を床に書く。 行動経済学で最も効果があるのは社会規範。みんながやればみんながやる。 ピア効果=グループ内のメンバーの行動が影響を与えること。ピアとは、同僚のこと。同じでないと損失を感じて損失回避しようとする。 正のピア効果=周りが優秀だと自分も努力する。周りがさぼると自分もさぼる。同調しようとする動き。 負のプア効果=周りが優秀だとあきらめる。反対の動き。 水泳チームに早い選手が入ると全員が早くなる=ピア効果。 仕事をした成果が目に見えるようにしておくと意欲がわく=自分で意味のある条件を作り出す。 行動計画を立てるのは、先延ばしする現在バイアスを防ぐ効果がある。具体的な行動に分解する。 ライバルをつくる=ピア効果を狙う。コミットメントの達成には小さなご褒美をつくる。 塩分少なめ、と表示されていてもその商品を買わないが、塩分多めを表示するとそれを避けることになる。 経済学部は女子学生比率が文系の中でも低い。女性は資格が得られる学部を選ぶ傾向がある。 経済学部は何を勉強するかが分かりにくい。 経済学部の中でも経営は女子学生に人気がある。実社会で役立ちそう。
0投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学に興味があり、著者のみならず、セイラー氏やサンスティーン氏の著作も読んでいるが、専門用語がしっくり心に落ちずに、理解が不十分な部分もあった。本書は高校生向けであるため分かりやすく、また章末に高校生自体が具体例をあげたり、Q &Aコーナーで応用例を示してくれているので理解しやすい。入門書としてはお薦めである。
0投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルになぜか興味を持った。 そもそも「経済学」もよくわかっていないのに。 行動経済学が「分かっていてもできない」ことについての学問だとは、全く知らなかった。 これは楽しそう。 サンクコストは大体わかるけれど、「損失回避」の具体例や「現在バイアス」、「アンカリング」など、他にも様々な特性でボトルネックを引き起こされているようだ。 そこで、「自由に行動できるけれど、できればいい方を選びやすくさせてあげるよ」というナッジを組み込めば暮らしやすくなる。 紹介されている「コミットメント」や「デフォルト」は、他のビジネス書などで書かれている手法のもととなる考えだった。 ナッジ…とまではいかなくても、訴求力を上げるために活用できることはたくさんありそうだ。
0投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大竹氏のこの手の本を読むのは、これで3冊目。さすがに内容は重複するものが多く、これまでのおさらいのつもりで読んだ。復習した主なポイントは以下のとおり。 ・サンクコスト(埋没費用)を取り返すことにこだわると、合理的でない選択をしがち。過去にこだわらず将来について意思決定をすべき。 ・人はマイナスによるショックの方がプラスのうれしさより、その度合いが大きい。だから、できるだけ「損失回避」をしようとする。 ・先延ばししようとする「現在バイアス」に対する有効な対策は「コミットメント」 ・レジ袋の有料化は「デフォルト設定(初期設定)」と「損失回避」の組み合わせ ・合理的な推論によらずに近道の直感を用いて判断する方法が「ヒューリスティックス」 ・「社会規範」、「不平等回避」は行動経済学上の大事な概念。特に「社会規範」を使ったナッジは効果がある。 ・同僚や友人の動きと異なっていると損失を感じるのが「ピア効果」
0投稿日: 2022.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは面白い。早稲田塾の高校生向けの講義を母体とした具体例豊富な行動経済学入門。 対象が高校生ということで分かりやすいし具体例も豊富。勉強を続けるコツだったり、高校生の選んだ選択肢を解説するスタイルは実に良い。出版社が東京書籍なのも頷ける。 本書でもちょこっと言及しているが箱根駅伝の青学の目標設定も、行動経済学的には現在バイアスを減らすようにしていることが良く分かる。 筆者は新型インフルエンザ対策委員。行動経済学の視点からまん延防止の意見を出しているという。 まだまだ発展途上の行動経済学。どちらかというと現実的ではなかった経済学と人間の認知バイアスをうまく組み合わせた楽しいジャンル。その入門として最適な一冊。
0投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすい入門。ほとんどがごく実践的な話なのと、「ナッジ」にけっこうページつかってるのが特徴?賢い高校2〜3年生向けに書いてるような雰囲気があり、これで経済学部志望者を増やす計画なのではないか。
0投稿日: 2022.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の世界事情… ウクライナ侵攻問題のような危険が もし自分の身に降り掛かったとき、 自分はどんな行動をとれば どんな意思決定をすればベストなのか 参考にしたくて読みました 結果…ベストな答えはでませんでしたが より良き人生を歩む為に、現状維持バイアスやピア効果を参考にしながら 戦争の無い平和な社会を1日でも長く生きられるよう 頑張っていきたい
0投稿日: 2022.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学って初めて聞いたけど、日々の何気ない言動は潜在的にこうやって体系づけられているんだと。後半が事例も出てきて自分の言動にも応用したいと思ったが、一読だけでは頭に刻み込めていない。もう一回読み直すことにしよう。
0投稿日: 2022.02.05
