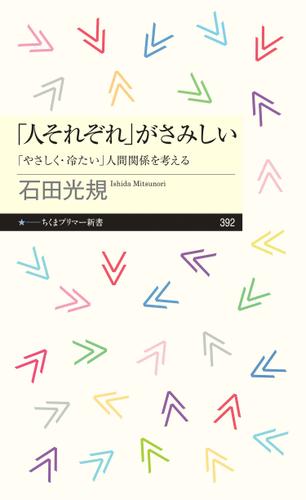
総合評価
(28件)| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023. 岩手県立大学 看護学部 看護学科 小論文 後期 2024. 北海道教育大学 前期 教育(函館校)−国際地域(地域教育) 小論文 前期 2024. 岐阜大学 後期 医-看護 小論文 後期 2024. 浜松医科大学 広域 医-医 小論文 後期
0投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ多様化が進む現代社会において、「人それぞれ」という言葉に違和感はない。しかし、自由を尊重した結果、孤独を深めている現実がある。寛容に見えて他者と一線引く都合の良い言葉でもあったからだった。 確かに、めんどくさくなって「人それぞれでいいんじゃない?」と話を終わらしたことがある...。新たな視点を与えてくれて、興味深く面白かったです! 新書は難しそうというイメージがありますが、読みやすくて良かった。
11投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「人それぞれ」というのは多様性を認める言葉である反面、対立を避けるあまり他人に対して無関心になったり無難な関係しか築けなくなってしまうことにも繋がる。 ほんとにその通り。 じゃあ深い対話を通じて自分と違う意見の人とも分かり合うためにはどうしたらいいかというと、そもそも人とのつながりに対する期待値を下げる必要があるとのこと。 ちょっと消極的なような印象もあるけど、確かに私も自分にとってプラスだと感じる人間関係だけを求め過ぎているのかもなぁと感じた。 もっと気の合う友達が欲しい、とはいえそんなに気の合う人なんてなかなか出会えない、出会えたとしても深い話ができるような関係性を築くのには時間がかかるし億劫だなぁ...。 これって裏を返せば、「信頼できる友達を時間もコストもかけずに見つけたい」ということになる。 うん、我ながらこんな考えの人とは友達になりたくないかも笑 人間関係っていうのは良い出会いもあれば嫌な思いをすることもある。 「SNSで気の合う人に出会えないかな~」なんて面倒くさがってないで、もっと足掻くべきなんだろうなぁ。
8投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人それぞれ」って言うと、多様性に理解のある寛容は人という感じがするけど、ばっさり切り捨てるような寂しさを感じることもある。 その寂しさの理由が「こういうことだったのか」とわかった気分。 一人でいるほうが気楽で、でも誰かと繋がっていないと不安で…という心理や、人それぞれと言いながらも自己主張はしづらいという現代の風潮。結局みんなどこか息苦しいのかなと思う。 人間なんて、プラスの面もマイナスの面も持ち合わせているのが当たり前で、コスパを考えることなく相手と向き合ってみることが大事だという考えには賛成。「人それぞれ」っという言葉はできるだけ使わず、面倒くさいことにも関わってみようかという気になった。
51投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論、対話が大事。それはわかるけど、どうやってしっかり対話していくので。社会学?の本でよくある、結局それでどう実践するのだというところが疑問すぎる。異質なものとの対話が大切なのはデータがなくとも真摯に生きているとわかる部分も大きい。知りたかったのはその先。まだまだ発展途上かと思う。
0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023. 岩手県立大学 看護学部 看護学科 小論文 後期 2024. 北海道教育大学 前期 教育(函館校)-国際地域(地域教育) 小論文 前期 2024. 岐阜大学 後期 医-看護 小論文 後期 2024. 浜松医科大学 広域 医-医 小論文 後期
0投稿日: 2024.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「多様性」(もしくは「キャンセル・カルチャー」)が希薄な人間関係という問題意識に繋げて批判的に論じられることが気になった。筆者のポジショナリティが隠蔽されている。 現状に息苦しさを覚える私たちは、「昔はもっと大らかだった」、「昔はもつと豪快な人がいた」などと言って、「人それぞれ」ではない社会の気楽さを懐かしみます。(126頁) ←「私たち」って誰
1投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『「人それぞれ」がさみしい』 2024年7月25日読了 わたしたちが日常よく使ってしまう「人それぞれ」という言葉について、その社会的背景や内包する意味と問題、人間関係の変化などを多角的に扱った一冊。わたしが特に面白いと思った3点を列記していきたい。 1.「人それぞれ」を可能とする社会 わたしたち人類は狩猟採集や農業などで生計をたてており、集団で生活せざるを得なかったと言えよう。「人それぞれ」が可能になったのはつい最近のことなのだ。お金を支払うことでモノが買え、サービスが受けられるようになった。そして個人が尊重される社会になった。 たしかに「個人」が誕生し、人生の選択ができるようになったのは、人類の歴史の中でもつい最近のこといえよう。わたしたちの社会が「人それぞれ」となり、個人の自由が尊重される一方で、新しい問題が表出してきているのだ。 2.人間関係の変化 かつて地縁や会社での縁で結びついていたわたしたちの人間関係は、より個人が尊重されるようになり、自分の好きなように選択できるようになった。これは地縁という面倒な結びつきから解放される一方で、友達関係がより不安定になったともいえる。しがらみが少ない分、関係性を解消することも簡単になったということだろう。 しかし、人々は人間とのつながりから逃れられない。求めてしまわざるを得ないのだ。だからこそ、この不安定な人間関係に恐れを抱いており、関係性が修復不可能になってしまうような衝突を避けるために「人それぞれ」が多用される。 3.「人それぞれ」がもたらす問題 筆者は本書のなかで「萎縮」とそれによる抑え込みが表出した「過剰さ」を問題に挙げている。 「萎縮」の例としては、パワハラやセクハラを恐れるがために、部下に注意できない上司や、コロナ禍の「自粛警察」のように過剰に迷惑を抑制しようとする監視の目を挙げている。このほか、最も厄介だと思われる例が生活保護受給者に対する批判の目である。生活保護というものが税金で成り立っているがために、その受給者を努力不足であり「迷惑」とみなす考え方だ。このように、「人それぞれ」という考え方が広まる一方で、「迷惑センサー」によって人々の行動を律している側面もある。つまり、現代においても集団的体質というのは「迷惑を過剰に排除しようとする目」として残っており、その中で「生きづらさ」を抱えるのも必然と筆者は述べる。 このようにある意味、自分の意見を強く発信しにくくなった世界の中で、人々は不満を抱え込むとともに、自分と同じ意見の他者と強くつながるようになる。これによって、対立と分断が深まるとされる。また、「それぞれの不満に蓋をすることで秩序を維持してきた「人それぞれ」の社会」において、「迷惑センサー」をより過敏にしており、秩序から外れた人々にぶつけられる過剰なまでの反応(=炎上)を引き起こしやすくなっているといえよう。 「人それぞれ」の社会とは一見自由なように見えるが、萎縮の中で不満が募り、分断や過激な反応を生み出してしまっている。その問題を少しでも和らげる解決策として、本書では「異質な他者を取り入れる」ことを提唱している。たしかにしがらみが少ないわたしたちは、自分と合わない他者と付き合わないという選択がとれるようになった。自分に好ましいと思われる他者の中で生き、「異質な他者」の存在がより薄くなっていると言えるだろう。しかし、自分に好ましい意見ばかり聞いていても、世の中の分断と対立はより一層深くなるばかりである。 筆者がより居心地がよいと説く「おたがいに迷惑をかけつつも、それを笑って受け入れられるつながり」には、全く同感するところである。互いに迷惑をかけないよう、息をひそめて本音も言えない関係性はしんどい。居心地がよい関係性を築くためにも、「目の前の人と腰を据えて付き合うことを意識し、お互いがもつ異質さを受け入れる」ようになっていきたい
0投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学入試小論文の出典として名前を見て、この手のテーマが昨年の流行であったとのことで手に取った本。 プリマー新書ということで学生向けなので、文体も優しく、すぐ読めてしまうが、なかなか現代の「息苦しさ」を絶妙に言語化してくれているように思った。それゆえにプリマー新書であることが悔やまれる。あと2、3歩踏み込んだ内容を読みたいと思った。 人それぞれ、という一見個性を尊重する社会通念は、実は形を変えているだけで集団主義的な色を非常に強く残しているというのはその通りだ。 外のコミュニティに対して「迷惑センサー」と「特権センサー」が過敏に反応し、相手を再起不能になるまでボコボコにする想像力のなさや、付き合う相手を選べるようになったが故の「キャンセル思考」「コスパ思考」によって、踏み込んだ深い関係性を築けない寂しさはとても合点がいった。 ここから先は持論だが、全ての問題の根幹にあるのは、他者に対する想像力の欠如だと思う。ただ、その想像力は思いやりから生まれるものだ。これだけ個人主義が進んでいる昨今、他人を思いやる事の美しさを語ることが難しい。何でもかんでもコスパで考えることになった今では、他者への思いやりに必要性こそなければ、関わらない「緩やかな撤退」が戦略的に効果があるからだ。 どんな世界線に進んでいくとしても、目の前の人を大切にする自分でありたいと改めて思った。
1投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代は『人それぞれ』の多様性が認められはじめて、ずいぶんと昔よりは生きやすくなっていると思う反面、他人とクイックに繋がれる希薄な人間関係にうっすらとした寂しさを感じてこの本を読みました。 ・異質な他者を取り込むには深い対話が必要 ・最適化願望をいったん脇におき、つながりへの期待値を下げ、人にはプラスの面もマイナスの面もあるというごく当たり前の事実に立ち返る必要がある ・人付き合いの基本と本質は、期待通りにいくこと、期待にそぐわないことも含めて共に過ごしていくこと 人間関係を築く際に自分に足りてないことや、これからの人付き合いに意識していきたいことが明確になった気がします。
0投稿日: 2024.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・「個を尊重する社会」というのは、一人ひとりがそれぞれに独立した意見をもち、それを率直にぶつけられる社会という意味合いもありました。誰もが、気を遣いつつも、率直に意見をぶつけ合うことで、よりよい社会を築いていく。そういった対話のある社会が目指されてきたのです。 果たしてそういった社会は実現できたのでしょうか。世の中を見渡してみると、実際に到来したのは、目の前の他者に対して意見や批判することを憚り、それぞれが自分の殻に閉じこもる社会、あるいは、検索をつうじて、互いに意見の合致している人のみが結びつき、意見の合わない人は寄せ付けない分断型の社会ではないかと思うこともあります。そこからは、個を尊重する姿勢を読み取ることはできません。
2投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「まあ、人それぞれだからね」というのは一見寛容に見えるけれども非常に冷たい対応で、それによって生じる懸念などの解説をした本。新書だし薄くてわかりやすかった。 「人それぞれ」ってのはその人を尊重するように見えて、その人自身が抱える問題をこちらに持ち込まないでくれという一種の拒否反応でもあり思考をストップさせる言葉でもある的なことが書かれていて、いやーほんとそうですよね…と反省したというか、考えたくないことが出てきたときに使ってしまいがちが頻出フレーズよな…と思った。 「人それぞれ」なのはもう存在するものとして社会に共有されたほうがいいし、大事なのはその「人それぞれ」の中身に対してどうやって行動していくかよね。 このあたりを柔軟にしていけばもっと労働に参画しやすい人たちも出てくるよね
2投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ若者あるいは中学生向けの新書である。したがって、難しくはなく、語りかけるような書き方である。 何か人付き合い、あるいは炎上してしまった人が読むと癒されるであろう。短時間で読めるので大学生にもおすすめである。
0投稿日: 2024.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちは長い年月をかけてやっとひとりになることができた。私たちが深い対話を取り戻すためには、最適化願望をいったん脇におき、つながりへの期待値を切り下げ、ただつきあうことをもっと意識した方がいい。多様性というワードの本質の誤解と似ていると思った。
0投稿日: 2023.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ超良かった。ぜひ「昔は良かったなぁ」と思っている人には読んでほしい 個人主義の弊害について書かれているが、 ネットでの過剰な「叩き」、「親ガチャ」にまで言及されており、とても読み応えがあった 気づき ・集団から離れた「人それぞれ」社会は、「つながりは自分で調達する」ことを意味する。それは「相手からも魅力的である」必要があるため、人間関係がコスパ重視になる。 ・人間関係のコスパ主義は、人間関係を狭める。 「人にはプラス、マイナスどちらもある」ということを今一度思い出すべき ・現代の「叩き」に共通するのは「異質な他者の不在」である。異質な他者をも取り込む必要性
0投稿日: 2023.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昔、クラスメイトに吐き捨てるように言われた「人それぞれだから」がずっと心の奥にわだかまっていました。それは会話を終わらせて私を遮断し、まるで「あなたみたいな人と会話はしたくないからあっちへ行ってくれ」と言われたかのような衝撃でした。 それからほどなくして、とある人の呟きで目を開かされた思いがしました。詳しく覚えていないのですが、その人は「人それぞれ、と言う人には対話の余地がない」というようなことを書いていて、当時の私は「私が抱えていたモヤモヤはこれなんだ!」と新しい発見にとても興奮したのを覚えています。 最近では、「みんなちがってみんないい」という文言のCMを見て「何か違うなあ。もともとの言葉の重みを解釈違いしているように感じる」と一人悶々としていました。 時が過ぎて現在、本書を読了後の私は、(良い意味で)更にモヤモヤの奥地に踏み込んだ心地でいます。 本書は、「人それぞれの社会」と題した現代社会における人間関係の希薄さについて述べています。「人それぞれだよね」と言って会話を終え、深く立ち入らないことは「個」を重視する現代社会ではよくある現象だとし、その社会で暮らす人々の負の側面に光を当てます。 希薄な人間関係を下支えする「過剰な気遣い」や、「コスパ」で対人関係を考える手法、「自粛警察」「親ガチャ」から「自己責任論」まで、腑に落ちることが多かったように思います。 最近読んだ『責任という虚構』(小坂井敏晶・著)の内容も思い出しつつ、多様性というのは本当に諸刃の剣なんだなということを考えました。「多様性を認める」と人々は簡単に口に出すし実行しようとするけれど、実際にはそう簡単ではないということも、きっと人々は理解していて、だからこそ深い対話を避けたいから「人それぞれ」といって切り上げようとするのだと思います。 (『責任という虚構』では、多様性を認めるということは間接的には犯罪者の存在、逸脱者の存在も認めなければ成り立たない、という旨の記述があります) 多様性を認めるということは、属する集団・宗教・政治理念にはじまり、性自認や対立意見を持つ者を受け入れる努力をし続ける、その努力に終わりはない、ということでもあります。 日本の場合、多様性を認めるとは言っても、多くはそれ以上の深い対話や意見交換などは行われないことがほとんどです。 これは政治信条に関して昔の日本人が「ノンポリです」と宣言していたことにも重なります。 日本の場合、構造をより複雑にしているのは、 ・圧倒的な格差社会 ・あらゆる平等を唱えながらも、対立者を自分より下へ追いやろうとする話者(実は平等を目指していない) といったような圧倒的な不平等・格差社会が表にありながらも、 ・「人それぞれ」(=多様性の容認)と口にしながらも、その薄膜を取り払うと存在しているムラ社会。 といった大きな矛盾を抱えていることが理由として挙げられると思います。 欧米社会では「人それぞれ」が定着して、個人主義となり、対話によっての解決が生まれているのかもしれませんが、個人的にそれは日本では難しいハードルだと感じました。 理由には、本書でも述べられている通り、現代の人々の関係は「気遣い」に下支えされた脆い構造だからというのがひとつ。もうひとつは、コミュニケーションを無駄だと感じている層が多いことが挙げられます。人とのつながりを「コスパ」で見積もる考え方や、本心を言えない友人関係からも窺える通り、日本人はもはや、我々が知らないうちにコミュニケーションを失ってしまったのではないでしょうか。 これからの日本人だけでなく、過去も我々はコミュニケーションを知らなかったかもしれない、とさえ感じました。 というのも、会社で行われる懇親会や歓送迎会などの類は上司に気遣って保たれている関係性だからです(=「人それぞれの社会」の友人関係と同じ)。 日本人は恐らく、今までも(そして多分これからも)建設的な対話や議論といった類のものはしてこなかった(し、多分これからもしない)のだろうと強く感じました。 「ネットでの対話が相手を罵り合うだけで対話とならない」という例からも、日本人の対話スタイルは十分すぎるほど説明できると思います。ネット社会、特にSNSを見ていると、人々がいかに「自分が被った被害」と「相手が努力せずに得ている権利」を比べて相手を非難しているかがわかります。対立する意見を持つ者同士は敵として憎しみ合うことが決められているかのようです。 そこに根本的解決を導く手段は用意されていないし、立場の違う者同士が落としどころを見つけるための対話など皆無です。 この状況を見ていると、「人それぞれ」というのは日本にとって、欧米を始めとした先進諸国に合わせるために唱える「スローガンのようなもの」であって、実在する日本社会は現在もムラ社会そのものなのだと思います。相手と意見が違えば、「人それぞれ」といって争いを回避するのが暗黙の了解となっているだけで、腹の中では「ありえない」と思っている(が、表現はしない)。場を乱さないことを優先しすぎた結果、脆い人間関係を心にもない気遣いで下支えしているのが人々の「人それぞれ」の本当のところです。 このような構造の中で建設的な話し合いができるわけがないのです。 余談になりますが、私が就活をしている時代には「コミュニケーション力」が過剰に求められていました。蓋を開けてみれば、コミュニケーション力とは立て板に水ですらすら話せて空気を読める人材のことで、相手の立場を理解したうえで言葉を選んだ丁寧な会話ができる、建設的な意見交換ができる人材のことではありませんでした。 このように、日本人は何かしらコミュニケーションについて誤解していると感じることが多々あります。自分たちの目指しているものが、「誤解したアメリカ」「誤解した欧米諸国」であることに未だに気づいていないのです。 本書では、特権階級の人間に対する非難めいた気持ちを感じる現象について「特権センサー」と説明したうえで、こう説明されています: 【特権センサーを軸とした議論の不毛さです。お互いに対立し合っているものどうしが、特権センサーを軸に議論すると、自らの不幸(特権のなさ)と、相手の幸せ(特権)を批判し合うものになりがちです。互いの不幸自慢や、やっかみ合いをしている間は、相手の境遇は見えてきません。】(p.145より引用) このことについては、以前読んだ『幸せになる勇気』(岸見一郎・著)を思い出しました。 カウンセリングをしていると大体突き当たる現象があって、それはクライアントの訴えが「かわいそうな私」と「ひどい相手」に始終してしまうというものだ。という内容の箇所があり、本書で取り上げられている「特権センサーを軸とした議論の不毛さ」も、この「かわいそうな私」と「ひどい相手」にぴったり重なると思います。『幸せになる勇気』では、「これからどうしたいか」という視点を持つことが大切だ、と提案されていました。 本書ではそういった対話の必要性を説きながらも、「失敗すればやり直せばいい」と背を押す言葉で締めくくられています。 しかし、個人的にはこれについても疑問で、失敗を恐れ、過剰な気遣いで下支えした人間関係の中で、軋轢を生まないようにと行動してきた結果が今のような「人それぞれの社会」であるにも関わらず、「失敗を恐れずに」話し合いなど不可能ではないかということです。 現役世代などは「対話しても無駄」とか「後味の悪い思いをするくらいだったら個々人で我慢したほうがまし」と考えるのではないかと思います。 著者は対話について、 「『それぞれ』人の意向には配慮しましょう。でも、時には深く対話しましょう」などというムシのいい言葉で、人が集まるとは思えません」(p.178) と書いていますが、「それぞれ」の事情は無視して大筋合意の方向にもっていくのが大切と考えているのでしょうか? ここのところも良く分からなかったです。 本書に「実践編」はありません。問題提起はなされますが、肝心の「解決編」にあたるところには「結論として、対話は重要だからコスパとか損得とか考えず、ただ付き合いをしてみましょう」とあるだけ。 しかし、街中を歩いてみればすぐに理解できることですが、もはや人類は電脳世界から一歩たりとも外へは出なくなってしまっています。既に時すでに遅し、です。 もう一歩踏み込んだ著者なりの打開策を提示してほしかったと感じました。 また、残念だなと思ったのが、「人それぞれの社会」とひとくくりにすることで、現代社会にある問題点を、あたかも「人それぞれ」という言葉に代表される社会(という大枠)の中だけで観測される事物・現象として取り扱ってしまったこと。「人それぞれの社会」とひとくくりにすることで、本来ならムラ社会の鉄則である「他人に迷惑をかけない」ということや、「ズル(特権悪用)は許さない」という特徴を「人それぞれの社会」として紹介してしまっています。 実際には、「人それぞれ」と言いながらまだまだムラ社会と変わっていないよ、という話を著者自身も『日本社会の集団的体質は未だに健在だと思わせられます』(p.127)と語っているにもかかわらず、あまりにも標題・「人それぞれ」という言葉に拘りすぎているように感じられました。 個人的なモヤモヤから手に取った本書でしたが、思いがけない収穫があり、結論としては読んで良かった本です。 この現状を知ったうえで、「自分はどうするのか」「周囲にどのような行動を提示するのか」が重要だと思いましたので、今後の課題としたいと思います。
0投稿日: 2022.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの著者さんの言っていることが、自分に当てはまっていた。一人でいるのが気楽で落ち着くし、人との関係は疲れるし面倒くさい。何より自分と合わない人との関係なんて、もっといやだ。だけどこの本を読んで、少し価値観を変えてもらえた。
2投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログみなさん、前回のレビューをご覧いただけただろうか。 (この切り口、気に入っている) ご覧いただいていない方のために、再度振り返ってみよう(しつこい)。 naonaonao16g、様々な顔回りの異変から親知らず(下)があったことが判明しました。 無事手術(骨を削ったのでこの言い方を選んでいる)を終え、術後も良好とのこと。 しかしである。 また耳が痛みだしたのである。歯医者さんも耳鼻科も原因不明、ということで大病院で検査。結果、CT・MRIともに耳にも脳にも異常はなし(よかった!)。 とのことでいよいよ耳の痛みに関しては原因不明なのだけれども、フェスに参加して(いや、BUMPに会って、と言い換えてもいいだろう)以降痛みが引いてきた…(!) この、時間が経ってよくなる感じはやはり親知らずが原因のようにも思えるし、フェスに行ってよくなったとするとストレスとも考えられる… 親知らず(下)を抜いたことのある方で、骨とか削ったことある方っていますか? その場合、二週間以上経っても痛みが残ってて大丈夫なもんでしょうか?誰か教えてください(泣) また自分の話が長くなってしまったけれど、ここからは作品のレビュー。 ずっと気になってた作品で、よほど気になってたのか、本棚に同じ作品が2冊。やっちまってる… 「人それぞれ」であるとか「一人を楽しむ」「一人旅」「おひとりさま」「孤独はいいこと」と言われるようになり、一人で生きていくことも多様な生き方の一つ、という現代社会。 著者の石田さんは、しかしそんな現代社会はP33「対立を回避するために、他者に対する批判や意見を憚り、気を遣い合うことに重きを置いている社会に見え」ると話す。ではなぜそんなことになってしまったのか。 それは、人や集団との関係を、自分で選べる社会になったからだ。その繋がりを「心地いい」と感じれば関係を継続するし、「居心地が悪い」と感じれば関係を切ればいい。人との繋がりが地縁ベースから感情ベースになったことで、繋がっていたい関係があった場合には「心地いい」を継続しなくちゃいけない。 でも、人と人とのコミュニケーションて常に「心地いい」わけじゃない。だからこそわたしたちは、相手に気を遣って、対立を避けて、言いたいことも言えずに、「人それぞれだしな」と、落とし込んでいる。ポイズンである。 この「人それぞれ」という言葉。P50「この言葉は、一度発せられると、互いに踏み込んでよい領域を区切ってしまいます。それに加え、それぞれが選択したことの結果を、自己責任に回収させる性質もあります」。 自己責任。この言葉は、「多様性」が産んだ負の遺産のように思う。 この言葉は「その道を選択せざるを得なかった人」にとっては呪いの言葉でしかない。でも難しいのは、ある場面においては、「自分で向き合わないといけないこと」もあるということだ。 ここで面白く且つ納得のいく調査結果を一つ。 P53「若い人たちは、『友達といるより一人が落ち着く』にも関わらず、『友達と連絡をとっていないと不安』と考えているわけです」。 若い子にとって、SNSが安心できる場所になるのも納得。繋がっている感じがするもんね。 P91「私たちは、『人それぞれ』と言いながらも、心のどこかで『望ましい結果』は共有しています。また、社会は序列に溢れており、人々の決定にはさまざまな要素が影響しています。このような社会で『人それぞれ』に選んだ結果は、けっして、平等にはなりません。にもかかわらず、私たちは、様々な決定に対して『人それぞれ』に選んだものと処理し、あまり関与しょうとしません」。 じゃあ一体どうすればいいんでしょう? その答えが具体的に描かれているのかどうかはさておき、詳細は本作を読んでいただければ… この作品、他にもハラスメントや迷惑だと感じる人へのセンサーの話にも触れていて、親しみやすく読みやすいものでした。 ※この部分はまさに、「人それぞれ」なのにも関わらず、相手を攻撃してこき下ろそうとする「異質性の排除」が行われているので「人それぞれ」が成り立ってない部分に該当する※ わたしの職場は特に、いろんな子がいて、それをまさに「人それぞれ」で「それでいーじゃん✌」としているのだけれど、やはり「選択してここに来た子」と「ここに来ざるを得なかった子」がいるわけで。そこをきちんと事情も知らずに一緒くたにして「自分のことは自分でやりなさい」っていうのも変な話。「人それぞれ」「自己責任」って言葉は簡単にコミュニケーションを終わらせて、お互い納得できてしまう。だけど、それは対応する大人の怠慢だ。基本的には自分のことではあるんだけど、声かけとか以前より気を付けていかないとな、と思ったし、ちゃんと相手の話を聴いていくことは本当に大切なのだなと思った次第。 プライベートに置き換えると、わたしはちょっと違和感あることを人に言われるとすぐに関係を切っちゃうところがあるのだけれど、これで生きやすくなる半面、簡単に人との関係を切ってしまうことになる。でもこれって難しくて、誰かが発した言葉の意味合いと、それを言われた側の言葉の受け取り方って違うから、その「違和感」の程度にもよるんだよね。何気ない言葉が相手を傷つける。でも相手にとってそれは何気なくない。ここに修復の機会であるとか、相手を知る機会があるといい。だけど、ここで相手が関係を切ってきたらそこで終わってしまう。 最近、関係を切って楽になることも増えた。同時に、だから謝る機会も減った。個人的には、会って間もない関係だったり、深くない関係ならどんどん切っていいと思う。だけど、やっぱり大切にしたい関係だったら、言葉を選びながら、ちゃんと伝えた方がいいよね。でも、わたしが大切にしたい関係だからって思って言葉を発しても、向こうは切ってくるかもしれないし、傷つけてしまうかもしれない、修復できなくなるかもしれない。そんな風にぐるぐる考え出すと「人それぞれ」ってなってしまうのもわかるよ。わたしは、もう何年もしっかり関係を築いてきて、心から何でも話せる友人じゃない限り、突っ込んだことを言えない。だって怖いもん。 最近増えてきた「多様性」の裏の顔。そこに真っ先に目をつけたのは、やはり朝井リョウさんの『正欲』だと思ってる。
62投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人それぞれ」という言葉に込められている、一見多様性を重んじているようで実は思っていることを飲み込み、大きな波を起こさないように過ごす考え方、今の社会で多くの人が知らないうちに実践している考え方や行動をわかりやすく解説してくれている。実は私も大いに思い当たるところがある。一つはこの20年ほど友人ができないこと、大学生の頃の友人とは離れていても会えばすぐに戻る感覚で今も繋がっているが、働き出してから本当の苦しみを吐露できるような友人と巡り会えない。これは青年期を過ぎた大人では仕方ないのかなと思っていたが、恐らく本書で書かれていることが本当の原因だったと思う。私も相手を尊重するという考え方のもと、自分の意見を声高に言うこともなかったし喧嘩になることもなかった。信を置く付き合いというのは互いに良いところ、悪いところを認め合って成立するものだと思うので、それをしなければ生まれない。また今の世の中、君子危うきに近寄らずでなるべく自分にとってマイナスになることは避ける傾向にある。そうなると、コスパで友人や結婚相手を選ぶと言うと露骨過ぎるが、そういうことなんだと思った。でも、本書を読んだ後、これに気づき周りの人と積極的に話すようになった。被害がない人間関係も良いものだが、やはり寂しかったのだ。
2投稿日: 2022.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人それぞれ、という言葉は、多様性を受け入れるように見えて、他者への介入を阻害する。リベラリズムに裏打ちされた個を尊重する社会は、誰と付き合うかを選べる社会。絶対にその人と付き合わなければならないという強い土台がないからこそ、人はコミュニケーションに最新の注意を払う。 1000人に1人のマイノリティの意見も、インターネットを使えばすぐに10万人の同調者を募れる。意見の合う人だけが集まる社会で対話する力が失われ、他者に冷たい分断社会が生まれていく過程が多角的に語られていた。
0投稿日: 2022.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人それぞれ」というフレーズの様々な意味を追求しているが、柔軟な思考方法でわかりやすい解説だと感じた."迷惑センサー"や"特権センサー"の議論が楽しめた.
2投稿日: 2022.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログさっくり読めて概観がわかる。 日本社会に権威が残らなすぎて、剥き出しの好き嫌いでしか人とつながれなくなりみんな臆病になった、という話だと理解した。
0投稿日: 2022.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人それぞれだからね」と話を結論づけることは思考停止に過ぎないと前から思っていて、「人それぞれ」は冷たく、突き放している言い方だよね。帯にもあるように「受け入れつつ突き放す人間関係」。なんとなくこの寂しさや息苦しさを感じている人は多いと思う。言語化されていて良かった。 「人それぞれ」の生き方がありながら、序列は存在するから息苦しいという点が腑に落ちた。格差、自己責任論と言われる今の社会で、それぞれに手は差し伸べるのではなく、手を引き合う、足を引っ掛け合うような場面が最近多いように感じる。 「みんなちがって、みんないい」には「みんな違うから、みんなそのままでいい」多様性と「みんな違って、みんな同じ扱いをうける」平等性の二面がある、という点も勉強になった。 「人それぞれ」は、各々を守る一方で自分もいつかは攻撃されうる不安があると思う。「人それぞれ」だからしょうがない?本当か? 点ではなく、面で捉えていく必要があるのではないか。 「人それぞれ」と糾弾する誰かに、自分もいつかはなるのかもしれない。その共感こそが社会をより円滑にする。著者の「異質な他者」との交流、対話にあたる部分。 しかし、最近は「異質な他者」を知る以前の問題というか、本当に自分でいっぱいいっぱい、ネットでいう「無敵の人」が増えてきた。健康的な社会であれば所得の再分配や最低限の生活保障のセーフティネットが働くんだろうけど、社会の余裕の無さ、貧困は全体に広まっていて、そのことがより「人それぞれ」の分断を生んでいるんだと思う。ぶっちゃけ、全員余裕がないよ。金銭的な余裕がないから、身体的に追い詰められて、精神的にもぎりぎりの状態になる。問題を面でどうしても捉えらなれない。主観的にしか考える余裕がない状況にいる人が多い。「人それぞれ」だからしょうがないじゃ済まないのに、「人それぞれ」だからこそ比べて蔑んだり嫉妬したりする。 「人それぞれ」が悪いことではなくて、「人それぞれに苦しいから助け合う」とか「人それぞれに頑張っているから尊重し合う」ような、肯定的な雰囲気になればいいのにな。 押し付ける思いやりよりも、一歩引いて慮る思いやりが必要だと思った。引く思いやり。過剰に反応するのではなくて、遠慮して包み込む思いやり。 格差是正については、色々と興味があるので、もう少し他の本も読みたい。
7投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人それぞれ」って多様性が叫ばれる昨今、耳触りのいい表現に聞こえるけど、人それぞれだからって言われちゃうとそれ以上何も言えなくなっちゃう。私がずっと思ってたことはこれだ!って気づきました。 人それぞれだからってのは、多様性とか異質性を受け入れてるように感じるけど、実はそうじゃなくて、それ以上そのことに深入りしないってことなのよ。つまり議論の余地もないの。これって本質的には全然受け入れたことにならないし、そのことを理解しようとする人をばっさり切り捨てるってこと。 理解できなくても、受け入れられなくても、そのことについて議論したいと思ってるのに、人それぞれだからって考えようともしないで、多様性とか言ってるのはやっぱり違うと思う。 でもみんなめんどくさいんだよね。内面に踏み込もうとして痛い目にあうくらいならはじめから距離をとろうとするのもわかるけど、それってすごくさみしいなって思う。そういう人にとって私のような人はめんどくさいんだろうな。私って友達がいないなぁって思うのはそういうことなのかも。ケンカしてでもちゃんと議論してくれる友達がいないんだなきっと。
14投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰しもが口にしたことのある、「人それぞれ」という言葉。 多様性の受け皿として、便利に使われているものの、それは対立を避けるためのものであり、極端に言えば、それは無関心なのです。 この本では、集団から個人への転換と共に訪れた、個人主義と多様性の間でどう生きるべきかを事例を用いて解説しています。 「人それぞれ」を枕詞にし、個人主義とは言いながらも、他人をまるで腫物扱いにして、無関心を正当化するのは、やはりどこか歪んでいると思います。 そして、大きな問題は、個人レベルで行われるそれらのことが、社会全体に浸透して、自己責任論が蔓延っていることだと思います。 サンデル教授が述べていた、能力主義の裏側にある自己責任論に、こうした背景もあるのではないかと、思わずにいられませんでした。 社会的な問題に対して、個人レベルでどう解決していくか、それは非常に難しいことだと思います。 しかし、だからと言って動かないのではなく、また、自分と異なる意見にフィルターをかけるのではなく、まずは興味を持つことが、あるべき多様性なのかな、と読み終えてから感じました。 「受け皿を広げよう。」
9投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ1章 「人それぞれ」が成立する社会の条件 1 「個人化」が進んだ社会 自由にいろいろなことをできるようになった社会 個人化と「人それぞれ」 2 「一人」になる条件1:物の豊かさの獲得 集団的な社会 経済成長とモノの充実 商品・サービスと社会保障にゆだねられた生活維持 3 「一人」になる条件2:個人を重視する思想 人権思想と自由主義 個性と多様性の尊重 失われた「定番のライフコース」 個人化と「人それぞれの社会」 4 「個を雌璽する社会」と「人それぞれの社会」 現代は「個を腺重する社会」なのか? 相手を否定しない技法の発達 「人それぞれ」が重宝される若者の友人関係 気を遣い合い、対立を回避しようとする社会 第2章 「人それぞれ」のなかで遠のいていく本音 1 ある会話から 2 気楽さと不安の狭間で 無理して人と付き合わなくてよい気楽さ つながりに注ぎ込む「感情」 感情に補強された不安定なつながり 3 重宝される「人それぞれ」のコミュニケーション 「人それぞれ」と解釈することで対立を回避 「多少自分の意見をまげても、友人と争うのは避けたい 4 遠のく「身近な人」たちと、漠然とした寂しさ 受け入れつつ突き放す「人それぞれ」 高まる孤立の不安 寂しい日本人 5 生身の人から幻想の友人へ ケンカをしてしまうと友情が修復できない 「友情の物語」幻想 寂しさの解消 第3章 「人それぞれ」では片付けられない問題 1 「人それぞれ」にはならない「人それぞれ」 ある親子の会話 友だちの進路の話 2 「多様な選択」の落とし穴 それぞれの選択を認める社会の受け皿 自由な選択はよいことなのか 「社会的ジレンマ」の発生 3「人それぞれの社会」のもどかしさ 自分一人だけでは叶えられない望み 対話と調整を要する時代 逃れられない他者の影響 4 「人それぞれ」が広げる社会の格差 選択の結果や条件は必ずしも平等ではない 人びとの結婚願望はあまり変わっていない 生涯未婚率に見る「人それぞれ」の結末 5 不平等を見過ごす冷たい社会 孤独・孤立を問題視するのは「余計なお世話」? 華麗な業績をあげた人が執筆する孤独・孤立推奨言説 「コスパ」化する人間関係 「人それぞれの社会」の厳しさ 第4章 萎縮を生み出す「人それぞれ」 1 ハラスメントと炎上騒動 何を言えばよいかわからない 迷惑な行為は許さない 2 「他者に危害を加えない」という理念 「人それぞれ」にはならないこと ハラスメントとダイバーシティ 3 リスク化する言葉と表現 ハラスメントの境界線 言葉のリスクの高まり 表現することの難しさ 4 リスク化に対処するふたつの方策 緩やかな撤退 結託という解放 5 「迷惑」という監視と裁き 迷惑をかけてはいけない 迷惑センサーのウチとソト 自粛警察、謝罪会見 キャンセル・カルチャーの恐怖 6 救いの声を封じ込める迷惑センサー 支援の届きにくさ 声を上げられない人たち 7 「人それぞれの社会」の集団的な体質 第5章 社会の分断と表出する負の意見 1 抑え込んできた思いのゆくえ 2 吸い寄せられる同質の意見 意見の合う人を求めて 検索される「つながり」 3 同質な集団同士が引き起こす対立・ 純化した集団 対立と分断の時代 4 過激化する主張 ヘイトの発生 多様性への不満の受け皿 5 「特権センサー」による糾弾 「特権」は許さない 特権センサーがはたらく仕組み 多様性への対抗軸として 6 秩序から外れた人びとにぶつけられる不満 不満の受け皿としての迷惑センサー•特権センサー 「テラスハウス」の事件 「上級国民」を監視する特権センサー 7 インターネットの機能的な問 「1000分の1」は低い確率ではない アルゴリズムによる多様性の排除 8 対話なき「人それぞれの社会」 「人それぞれの社会」での萎縮 規範的圧力からうまれる大きなうねり 相手の見えない「人それぞれの社会」 第6章 「異質な他者」をとりもどす 1 身近に「異質な他者」がいない社会 「異質な他者」の不在 気の合わない人とつき合わなくてよい社会 身近な人の批判的・否定的意見の封じ込め 2 他者への想像力と共感の欠如 分断され攻漿し合う集団 他者を執拗にたたく人たち 3 対話をつうじた深い理解のススメ 分断を修復する対話 友だち関係を円滑に進める対話 対話の重要性はわかっているけれど 4 異質な他者を取り込むために:住会編1 インターネット 普及の速さに注目 インターネットと砲話の普及過程 技術の影響を検証する仕組みを 5 異質な他者を取り込むために@社会編2 つながり 頑健さの保証 継続性のあるつながりにむけて 6異質な他者を取り込むために:個人編 最適化を望む人間関係 「親ガチャ」「子ガチャ」 最適化の追求と関係からの撤退 最適化からの離脱 それでもつながりにとどまる気持ちを
0投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本当に考えさせられた。「多様性」も「人それぞれ」も悪い言葉ではないが好きになれない。なぜそう感じるのか。この本を読んで納得。私は個々人の事情が違うことを受け入れるのは賛成だし、正直面倒で何ら介入せず放置することもあるが、それを一言で正当化する姿勢は味気なく虚しい。世の中には身近な人づきあいを「コスパ」で選ぶ人もいるらしいが、どこからを受け入れがたい迷惑と捉えるのか。考え出したら迷路にはまり込む。
1投稿日: 2022.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ人それぞれ、多様性の違和感の答える本 どこかで聞いたことのあるような話が多かった。あとがき直前の5ページくらい読めば終わりな印象だった。
0投稿日: 2022.01.14
