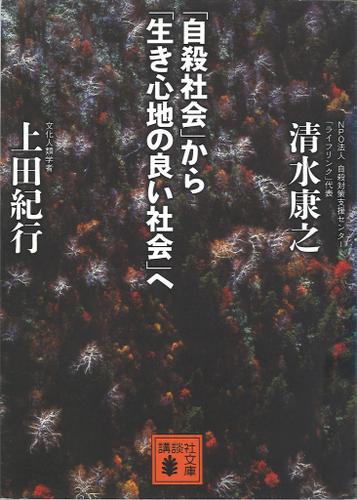
総合評価
(10件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ現実問題から背景、関連問題と多岐にわたる視点で語られ、また実施されている対策にも言及されてて内容は濃い。さて、私は、あなたは何ができますか?
0投稿日: 2023.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに自殺が多いいんだとは思わなかった。かなり目からウロコが、というビックレの話題が満載。知っておかなきゃいけないことばかり。
0投稿日: 2015.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 毎年、自殺者が3万人を超える自殺大国・日本。 2004年、NPO法人「ライフリンク」を立ち上げ、「自殺対策基本法」成立の原動力となった清水康之氏と、「生きる意味」を問い続ける文化人類学者の上田紀行氏が、「自殺社会」日本の正体と、「生き心地の良い社会」への道筋を徹底対論。 [ 目次 ] 第1章 駅の鏡から自殺を想う 第2章 悲しみは連鎖する 第3章 「ごめんね」と遺して逝く人々 第4章 いじめの構造 第5章 真の豊かさを求めて 第6章 “生き心地の良い社会”へ [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
0投稿日: 2014.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本人がP11 で言うように、自殺の問題を徹底して掘り下げた先に、この生きずらい社会の正体を明らかにすることができたなら、’自殺社会’は、’き心地の良い社会’踏み出す足掛かりになる。というように、行政に、社会にどう自分たちがかかわるかで、社会はどんどん変わると思う。
0投稿日: 2014.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログNPO法人「ライフリンク」を立ち上げ、「自殺対策基本法」成立の原動力となった清水康之氏と、「生きる意味」を問い続ける文化人類学者の上田紀行氏が、「自殺社会」日本の正体と、「生き心地の良い社会」への道筋を徹底対論。 だって
0投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ環境が人生を左右することはあると思う。けれど、どんな状況でも生き抜く人は生き抜くし、自殺する人は自殺する。これも認識と選択の問題だ。そして自殺は最悪の選択だ。遺される人にとっては。
0投稿日: 2012.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今週おすすめする一冊は、『「自殺社会」から「生き心地の良い社会」へ』。文化人類学者の上田紀行氏と、NPO法人自殺対策支援センター「ライフリンク」の代表・清水康之氏が自殺について語り合った対話の記録です。 日本では、1997年の金融危機の直後に自殺者が急増し、初めて年間3万人を超えました。以来12年間、毎年3万人以上の方が自ら命を断っています。一日に直せば80人以上。数字だけではなかなか実感がわきませんが、東京マラソンの出場者数がちょうど3万人と言われると、その数字がとたんに重みをもって迫ってきます。 でも、自殺について大っぴらに語られることはありません。自殺は忌むべきものであり、語られることのはばかられるものだからです。 自殺は、多くの場合、自殺者個人の問題として語られがちです。そして、多くの場合、それはその人の「弱さ」や「敗北」という文脈で語られてしまう。しかし、それがどれだけ自殺者の遺族達を傷つけることになるのか。身近な人の自殺を防げなかったことに対する罪悪感に加え、「自殺するような弱い人」「自殺者を出すような呪われた家族」という周囲の蔑視が遺族達を苛み続けるのです。自殺は決して終りではなく、遺族にとっては終りのない悲劇の始まりなのだということ。私達はそのことにあまりに無自覚です。 自殺を「弱さ」や「敗北」として見てしまうのは、結局、人を実績やパフォーマンス、つまり、何ができるか《doing》でしか見ていないからでしょう。しかし、《doing》で見ている限り、人は取り替え可能です。極端な話、ロボットやコンピュータでもいい。そこに人としての「かけがえのなさ」は発生しようがないのです。 どこまで行っても自らの「かけがえのなさ」を実感できることのない社会。それは、誰もがいつ自殺してもおかしくない過酷な社会です。日本は既にそういう「生きにくい」社会になってしまっている。それをもっと「生き心地の良い社会」にするには、自らの「かけがえのなさ」を実感でき、相手にも実感させてあげられるような関係、つまり《doing》の前に、その人の存在それ自体《being》を認め合えるような関係とそれを支える社会の仕組みを築くことが大事だと著者達は述べます。 著者の一人・清水氏は、自殺の番組を作ったことをきっかけにNHKを辞め、自殺対策支援のためのNPOを立ち上げた方です。この人の想いの強さと実践のあり方が素晴らしい。まだ30代ですが、どうすれば自殺に追い込む前に救うことができるかを考え抜き、効果的な打ち手のネットワークを張り巡らせていく。その周到さに、実践するとはこういうことなのかと目を見開かされる思いがしました。 自殺はもはや他人事ではありません。そして、自殺について考えることは自らのあり方をふり返るいいきっかけを与えてくれます。だからこそ、できるだけ多くの方に読んで頂きたい一冊です。 ===================================================== ▽ 心に残った文章達(本書からの引用文) ===================================================== 自殺は、「悲劇の終り」であって、その人の人生の結末として自殺がある。でも、一方では、「自殺から始まる苦しみや悲しみ」もあって、その場合の苦しみや悲しみを背負うのは、遺された家族なんです(清水) 「自殺というのは弱い人間がすることだ」 「人生から逃げたんだ」 そういうマイナスイメージでもって遺族に接してくる。子どもたちは敏感に感じるんですよね。親戚や近所や学校や、社会全体の眼差しを(清水) 自殺問題を考えることは、今生きている僕たちにとっても、まさに他人事ではないリアルな問題であって、僕たち自身が生きていて「心地よい」と感じる社会を、今後築いていくための作業でもあると思っています(清水) 「この社会全体が、いつかは底上げされて豊かになっていくんだ」という大きな流れすらも感じることができない中で、それでもすべては「自己責任だ」というふうに言われて個的な戦いを永遠に続けさせられていく。普通の人間にとってはちょっとありえないような負荷のかかりようです(上田) 今、起きているのは、適応できない人たちが追い込まれて命まで奪われて不幸になっていくのはもとより、一見適応しているように見える人たちまでもが、実はどこまで幸せを実感できているのかわからないということです。だとしたら、いったいこの社会の中で誰が得をしているんだと、大声で聞きたくなるわけです(清水) 社会から「誰でもいい」と扱われてきた結果、「誰でもいい」から殺したかった、となる。つまりそれは、現代日本のシステム化された社会の中で、それぞれの「かけがえのなさ」を実感できていないということですよね(清水) 「なぜ自殺者がこれだけ増えてしまったのか」という方向へ、見方を転換しなければならないんだと思います。 それがきっと、真の意味での「責任を背負う」ということであり、未来を作るために必要な第一歩なのだと思います。 今ある社会に対して、自分には「責任がない」と思っている限り、それは「これから先の選択をも放棄する」ということと同じですから(清水) アメリカでの高校生活を終えて日本に帰って来ると、日本の高校を中退したときには「あの子どうしちゃったの」みたいに言ってた人たちが、今度は「アメリカの学校を出てすごいわねー」と褒めてくれるようになりました(笑)。 とにかく、周囲の評価は本人に関わりなくコロコロ変わるんだということを悟った高校時代でした(清水) 家族が、親戚が、友人が、そして自分自身も、「まさか自殺するとは思わなかった」人が、いつ自殺に追い込まれるかわからない社会に僕らは生きている。 我々は、景気が悪化したくらいで、人々が死に追いやられるような脆弱な社会基盤の上に生きているということの恐ろしさを、そろそろ身にしみて痛感したほうがいいと思うんです(清水) 僕たちは、亡くなられた方の命を取り戻すことはできないけれど、遺された「声」を社会づくりに反映させることで、その存在を生かすことはできると思います。というか、生かさなければならない。 (…)徹底的に彼らの「声」から学ぶことが、僕は「生き心地の良い社会」をつくるためには欠かせない作業だと思うんです(清水) たしかに夜中に店が開いていれば便利なこともあるかもしれません。だけど、果して二十四時間ぶっ続けで店が開いている必要性がどれほどあるのか。二十四時間営業しているということは、裏を返せば、誰かの大切な人が夜中の二時、三時に働いているということですよね。でも、そうまでしてコンビニに二十四時間営業していてほしいかと言えば、僕だったら、自分の大切な人を働かせてまでコンビニに二十四時間開いていてほしいとは、とうてい思えません(清水) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[2]編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 車の中でペットボトルの水を大量にこぼしてしまい、そばにあった携帯電話が水没してしまいました。ドライヤーで乾かしてみたりと悪戦苦闘したのですが、結局、機能は回復せず。修理もできないとのことで、買い替えるほかなくなってしまいました。無念です。 考えてみると、今年は、既に同様のことを二度ほど経験しています。二度とも水没させたのは腕時計ですが、ちょっとした不注意によって浸水させ、致命的なダメージを与えてしまったという意味では、状況が似ています。今回が三度目の正直ですね。 モノの場合、いつかは壊れるものだと諦めているし、たいていのものは修理できますから、全くもって取り返しがつかないということはそれほどありません。でも、事故が起きた時には、「取り返しがつかないことをしてしまった」という気分になります。それをここ三ヶ月くらいでもう三回も繰り返している。 これはやっぱり何らかの警告だと思い直しました。「このままでは取り返しがつかないことが起きるよ」という意味での警告。 今年は数え42の本厄ですが、どうもこれまでは物が身代わりになってくれていた気がしてしょうがないです。大きな災厄がおきないうちに、警告の内容を読み解き、早めに対処したいものです。
0投稿日: 2010.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ1日に100人も自殺する社会は異常である。 人が自殺するのは、失業、生活苦、いじめ、うつ病とからしい。 人間どうせ、死ぬんだから、慌てて自殺する必要なんてない。もったいない、生きてるだけで楽しいことなんていっぱいあるのに。人生、案外楽しいのにな。死ぬなんて勿体ない。死にたくなったら、アンネの日記でも読めばよい。生きてるだけ人生って素晴らしいって思えるようになるから。
0投稿日: 2010.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本はいつから、どのようにして1日約100人の自殺者を生み出す社会になってしまったのか。自殺予防の具体的な取組の提言を含んだ対談集。巻末に相談先リストを付した点も評価したい。 隔週誌のビッグイシューで組んだ対談がもとになっているようなのだが、ビッグイシューがオリジナルで出版するのは難しかったのだろうか。一般書の出版は、ビッグイシューの知名度を高めるチャンスになると思うのだが。資金面など簡単なハナシではないのだろうな。
0投稿日: 2010.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログいまの日本の社会は年三万人、一日三百人が自殺している社会。 確かに通勤電車が人身事故でよく止まるが自殺がこんなに多いとは。 日本より経済状況が悪い国が必ずしも自殺が多いとは限らない。 日本の社会特有の問題があるらしい。 日本の学校でイジメが起きやすい構造に似ているようだ。 日本の学校は、イジメが起きやすい環境。アメリカの学校では陰湿なイジメがめったに起きないらしい。アメリカの学校は人間環境が固定されていなくて《逃げ場》が出来る。 日本の学校は人間関係が1年間クラスで固定され《逃げ場》がない。 日本の社会も《逃げ場》がないから自殺に追い込まれしまう人が多いのではないか。 この不景気で自分自身も会社に残れても辞めても地獄という状況だ。 もう右肩上がりの社会になることはないだろうから。 これまでように誰もが勝ち組を目指すというのは無理がある、ということにこの本を読んで気づいた。 勝ち組以外の方向を考えてみようと思う。 NHK社員時代の自殺遺族への取材がきっかけで自殺対策のNPO「ライフリンク」を設立した清水康之さんの行動に感心した。
0投稿日: 2010.06.12
