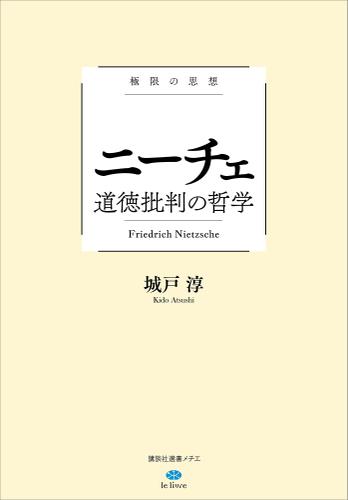
総合評価
(6件)| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログニーチェの『道徳の系譜』を読み解く上で非常に参考になった。『道徳の系譜』初読の時点では全く見えなかった景色が、この本を足がかりに見えた。ニーチェ初心者は、できれば『道徳の系譜』とこの本を交互に理解しながら読み進めるのがいいのではないと思う。 しかしこの本で解説される部分は、『道徳の系譜』の特に大事なところ、要点に絞られるので、ところどころは自分自身で、あるいは他の解説書を参考にして読まなければいけないところもある。 また、『道徳の系譜』では触れられていないニーチェの思想も四章で触れられるが、『道徳の系譜』のみの解説で良い人には二章と三章で十分だろう。 それと、著者はニーチェが専門ではなく、カント研究者らしい。しかし、『道徳の系譜』に何箇所も出てくるカントの部分の解説が欲しい人には特に参考になるだろうと思う。 また読み返して、今度は理解しきれてない部分を拾っておこうと思う。
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、ニーチェの哲学を『道徳の系譜学』を核に、初期から後期までを全体として解釈する。また著者はカント哲学の専門家でもあり、ニーチェの哲学は『カントの批判哲学の超越論的な問題設定を継承した』ものだ、という視点からも解説される。 著者は、『道徳の系譜学』の要点だけでなく、ニーチェが書かなかったこと、見落としたことまで指摘する。そしてそれは、極めて妥当であるように思えた。その際、様々な論者の異説も紹介され、それによって著者の論に説得力が増す。このような読み方は自分一人では到底無理なので大変ありがたい。『道徳の系譜学』の三つの論文は、ときに第一論文(ルサンチマン論)の読みやすさとインパクトが際立つため、そこだけが論じられることもある。しかし本書では、三つの論文の関係性も重視されており、その説明も説得的である。 最終章では『道徳の系譜学』以後のニーチェが扱われる。著者の『永遠回帰』の解釈では『歴史的自覚』が重要である。著者の解釈によると、『永遠回帰』の試練を経由した自己是認とは『生活のすべてが然るべく配置されて、最善の成り行きであると確信しているような、晴朗な精神状態のこと』である。私はここでスピノザを思い出した。次に、『永遠回帰』によって歴史が救済される可能性が示唆される。それによると、過去を継承し、未来は将に来たるべき歴史となり…ということである。ここはハイデガーの『存在と時間』みたいだ、と思った。
0投稿日: 2025.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学的歴史を相剋したものとみなすとき、それが因果的な過去や史実に限らず、「昨日何をしたか」という個人の記憶や道徳的履歴まで含めて考えるべきだと感じた。その上で、結局、一人の人生は生まれながらの初期設定も含めて〝因果“あるいは〝予定説、運命論“で描き出せるものであり、ニーチェの超人という思想は、その関係性からの思考的離脱にあるのではなかろうか。 ルターやカルヴァンの予定説は、「人間は生まれる前から救われるか否かが決まっている」という救済の選別を前提とする。が、ニーチェは人間が自己を創造しうる「自己超克」を重視。つまり、予定説が押し付ける「すでに決まった運命」や因果論には反旗を翻し、自らの運命への主体的姿勢を超人に見出した。未来を自ら書き換える存在として超人を仮定する。 そして、いわゆるフォアキャスティングでもバックキャスティングでもない、今を生きる刹那の繰り返しを「永劫回帰」とした。様々な文脈の中で自我は象られ、連関している。だが、結局はそうした外部性に関わらずに存在する個性こそが超人であり、その純粋な存在は、繰り返しても同じ。純粋な存在を重視すべきだ。 ー ニーチェはなにも、歴史的人間を忘却の力で非歴史化することを目論んでいるのではない。いいかえれば、自然の意志衝動によって人間を野生化することで、歴史病を治そうというのではない。ニーチェはむしろ「超歴史的な立場」に立つことで、歴史と非歴史をひとしく超克しようとする。超歴史的立場とは、歴史のなかに非歴史を見てとる立場である。この立場から見れば、歴史的な偉業や達成をつくりだす人間の魂や文化の活力は、歴史過程のなかで発達するのではなく、むしろそのつど完成して終局しているのであって、それゆえ同一の形が歴史と現在の生を貫いている。超歴史的立場の命題をニーチェは次のように定式化している。過去のものと現在のものは同じ一つのものであり、すなわち、あらゆる多様性にもかかわらず類型としては等しい。それは、不易の諸類型の遍在として、不変の価値と永遠に等しい意味をもつ静止した形姿である。これは後年の「永遠回帰」の萌芽となる思想であるといってよい。 ー 歴史を虚構にしないためには、歴史に対する尚古的な態度が必要である。「尚古的歴史」とは、いにしえからの文物や伝承の骨董的な保存という意味での歴史である。過去をもたない人間は、いわば根無し草のように軽薄であろう。みずからを形成してきた伝統を学び、保存し、その敬虔な雰囲気のなかで呼吸すること、その伝統に根ざして養分を受けとることが人間の成長には不可である。 正直に言うと、ニーチェが何のために永遠回帰などという、逆説的には人生が何度も生きられるような思考実験を用いたのか、分からない。一度きりの人生だと考える方が超人の前提に相応しい気がするからだ。その方が余程、大切に生きるはずではないのか。
62投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログニーチェの『道徳の系譜』を読み解くとともに、彼の道徳批判がもつ超越論的な意義を解き明かそうとする試みがおこなわれています。 ニーチェの道徳批判といえば、われわれの道徳的な心性の背後にルサンチマンが控えていることを指摘したものとして広く知られています。しかし著者は、ニーチェの道徳批判を、いわゆるモラリストたちのそれから区別しなければならないと主張します。モラリストたちは、表面上は道徳的にふるまっている人びとの心の奥底に、非道徳的な動機が存在していることを鋭く見抜きました。しかしそうした批判は、いまだ道徳そのものに対する問いなおしではありません。 著者は、「ニーチェがカントの批判哲学の超越論的な問題設定を継承したこと」を承認するという立場から、彼の道徳批判を理解しようとします。ニーチェの思想における超越論的な立場からの考察は、「系譜学」という歴史的な方法として具体化されましたが、それは「発生論の誤謬」を犯すものであってはなりません。このアポリアを切り抜けるために著者は、『道徳の系譜』の議論を読み解き、ルサンチマンにもとづく自己欺瞞に対するたえまない自己検閲をおこなうことで、道徳的な意識が成立したことを明らかにしています。 一方で、こうしたニーチェの超越論的な系譜学の立場にもとづく議論は、道徳批判をおこなうための価値基準をみずからのうちにもつことになります。このような問題に対して、ニーチェは、あたらしい価値をみずから創造する「超人」の思想を提出することでこたえようとしたのだと著者は論じています。 「あとがき」で著者は、「ニーチェの方法論的核心にはカント的な超越論哲学の伝統があるはずだ」という確信のもとで本書を執筆したと述べています。ニーチェの思想の解釈としてたいへん意欲的な試みだといってよいと思います。
1投稿日: 2023.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログカント研究者の視点が随所に光る。 キーワードは超越論的。 ニーチェの道徳批判を『道徳の系譜』に基づいて丁寧に読みほどいている。 ニーチェの問題意識がよく分かる。 最後に著者が読み解いた、個人としてだけではなく、人類としても、歴史としても、道徳を解体していく「永遠回帰」の思想は魅力的だ。
0投稿日: 2023.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログニーチェを多数読み込んでいるわけではないので、著者の言わんとするところがどこまで理解できているか心許ない。さしあたり「道徳の系譜学」を読んでから再度チャレンジしたい。
0投稿日: 2021.12.14
