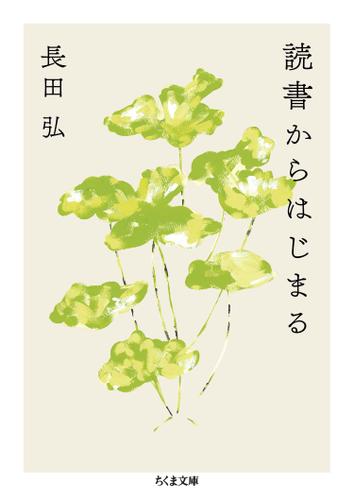
総合評価
(47件)| 15 | ||
| 14 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長田さんの詩集は好きなんだけど、意味はわかるんだけど難しくて入ってこない。 なんとか一章、また一章と読み進めました。 やはり私は本質を理解するよりも表面を理解するくらいの読書が好きなんだと思う。
0投稿日: 2025.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ本とは、人間がもっとも長く付き合ってきたメディアである。 〈再読〉 本の文化を成り立たせるのは、忘れる力。忘れるがゆえに、もう一回読むことができる。 読んでも読んでも忘れる人間のために取っておくのが、図書館である。 〈読書と友人〉 読書というのは、私を探している本に出会う経験。未知の親しい友人に出会うこと。 〈読書と椅子〉 本を読めるような椅子を見つけられるかどうかで、人生の時間の景色は違ってくる。 〈言葉〉 自分の使う言葉が自分を表す。 言葉を覚えるというのは、この世で自分は一人でないと知ること。 〈言葉と経験〉 経験を言葉にする。 言葉にできない経験は残らない。 〈育てる文化→蓄える文化→分ける文化〉 育てる文化→読書 蓄える文化→図書館 分ける文化→情報 アレクサンドリア図書館の教訓。アレクサンドリア滅亡により、図書館も灰燼に。 〈まとめ〉 上手に読むというのは、読んでよかったと、自分で自分に言える経験をすること。 自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書である。 〈私見〉 読書を、幅広い角度から分析した本。 本を友人にたとえる。図書館は本を蓄える場所。 本を読むための椅子の重要性。 読書というものを、深く考えてみたい方にはおすすめの本。
3投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分が本に感じている感覚を教えてもらった気がする。 「いい時間」、「故郷のような愛着」、「心が自由」、「自分の中に蓄える言葉」ということ。 個人的には「思い出すひと」がいるということも、本に感じる優しい感覚。
0投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ長田さんの読書へのまなざしは20年以上の時を経て、なお普遍的。 読書から何を得るのか、そもそも人はなぜ読書するのか、 様々な角度からかかれ、大切にしたいと思う言葉がちりばめられている。 p7「情報の言葉は、それによって自分の位置を知るための言葉でなく、それによってそれまで知らなかったことを知るための言葉なのです。」 p185「ひとの記憶の目安となるのは、自分の言葉を見つけたという思いがそこにのこっているような時と場所のことであり、そうして、自分の言葉をみつけるということは、自分の心のなかにもっている問題をみずからいま、ここに確かめる、確かめなおすということだからです。」
6投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ296 読書からはじまる / #読了 #図書館本 良寛さんのことば「耳を洗え」に出会う。 洗うという言葉に「心を洗う」「耳を洗う」「魂を洗う」昔の人は隠喩としも使っていた 耳をきれいにし澄ますことが大事 「心を澄ます、心を濁すのは愚か者だ」 お風呂は心の洗濯だったかな? 洗うって神聖な儀式みたい
7投稿日: 2025.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログゆっくりと噛みしめるように読んでしまう、そんな文章だった。今まで読んできた読書について書かれた本とは異なる。もっと深いところのこと。気づいていなかったことに気づかされた。 図書館で借りて読んだが、ぜひ手元に置いて何度も読みたい。次に図書館に行ったら、まず「子供の本」をチェックする。
1投稿日: 2025.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉に真摯に向き合っている著者の読書エッセイ。響く言葉がいくつもあった。 言葉というものは皆平等にもっていて、その言葉をどう結ぶか。自分はどんな言葉を抱いていて、どんな風に使えているだろうか。大事なのは意味ではなく心だなと思う。 読書を通じてどれだけ大事にしたいと思える言葉に出会えるか、それを大事にしていけるか。自分の本棚を見るとその本から受け取ったメッセージや読んだ当時の感情が思い出される。自分も案外良い読書ができているのかもと思えた。 この点電子は身体的な記憶が残りにくいから、自分の記憶として想起するのが難しそう。
1投稿日: 2025.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの方の本は2冊目。 やっぱり慈愛に溢れた方だなぁと思う。 少しずつゆっくり読んだ。 なんとなくそういう読み方がしっくりくる。
1投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ残念ですが、私には合わなかったです。 他の方の感想にもあるように、所々うなずける箇所もあるが、繰り返しが多くて…途中で諦めてしまいました。
2投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログもうすこし、著者とキャッチボールがしたかったかも。 読書というものをこれ以上単純化できないほど、易しい言葉に分解して、新たに捉え直す一冊です。「本」そのものはもちろん、「読書」という行為がなぜ自分をアゲてくれたり癒やしてくれたりするのかを分かってみたいとかねがね思っていたところ、この本に出会いました。 この本は読書に対する新たな視点に気づかせてくれます。児童書を子どもが読むものだと大人が線引してしまう「児童書を読まない大人」。膨大な量の本が眠っている図書館の存在や積ん読など「読まない本の大切さ」。どんな本を読むかは語られるが、いつどこでどんな椅子で読むかの重要さは語られないという「本と椅子の関係」など、この本が気づかせてくれた新たな価値観は今後の読書ライフに活きてくると思います。本好きであれば誰もが、本屋に入れば気分が高揚するでしょうが、まだ出会っていない素晴らしい本に出会う可能性に満ちていて、しかも出会いきれないほど多くの本が手に取られるのを待ってくれているというワクワクを感じているのでしょう。 一度読書のよろこびを知ると、その後読書をしていない時でも、この世には自分がまだ知らない、面白い価値観が山のようにあると思えるし、それだけで人生に面白さを感じることができます。いやそれは本でなくていいのかもしれない。変わらないはずの日常に、ほんのすこしだけ色がつけられるような、ちょっとだけアガるような何か。音楽でも、映画でも、料理でも、、、とにかく感受性の幅を広げてくれるもの。本は感受性の種がぎっしり埋まっています。読んで自分が感じるだけでなく、こういう感じ方もあるらしいと知ることができるだけで、心に豊かな実りが得られます。押し付けられたり、世間で正しいとされている感じ方だけでは人生は彩られません。 最初の章で「本は友人」と語られます。本ではまだ感じたことはないですが、私には「友達」に近いような「こいつとは他人ではない」と思える音楽アルバムがあります。人間ではないものに人格を感じるほど、愛着が湧き、いつもそばに感じるものが。 ハードの更新のためにソフトが短命になることへの危機感は私も共感しました。とくに現在隆盛しているネットコンテンツは、対応終了してしまえばいとも簡単に見られなくなってしまいます。その点、紙の本のいいところは、電源を必要としないところ。電源いらずでページを開くだけでアクセスできるし、紙の方が後世まで物理的に残ります。本は記録であり、それは1000年以上前の人間の考えに触れられるだけでなく、その人の周りの風景や当時の世の中のムードもふくめて教えてくれます。歴史が解き明かされていったのは、紙の本や掘られた石など、物理的な記録のおかげなのです。 この本を読んで残念に思ったところを言うなら、著者の言いたいことを捉えきれなかったという読後感です。難しい単語を使わずに易しい言葉で書かれているのはけして悪いことではないですが、「読書の本質」という言語化するのが困難なテーマに平易な文章で迫るもんだから、初期装備でラスボスと対峙するように感じ、著者ほどの言葉のプロであればそれは可能でしょうが、読者である私の理解が追いつけませんでした。著者はあえて易しい言葉で説いているのですが、意味の広い言葉で語られるため、読んでいて具体的なイメージを描きづらく、抽象的に思えます。著者が詩人ということもあり、良く言えば「詩的」ともとれるけれど、悪く言えば十分な説明がないとも思いましたし、著者とキャッチボールができていないモヤモヤを感じました。結局何が言いたいのかが分からない自分は、まさにこの本の中で批判されているような、意味の世界に囚われて「情報としての読書」をしている人間なのかもしれません。読者は「考えるな、感じろ」ってことなのかも。結局は著者の言葉に、感覚的に共鳴できる人のための本のような気がして、その輪に入れない、同調できない自分を感じつつも「まあしょうがないか」と思い本を閉じました。 余談:読んでいて「講演の書き起こしのような構成だな」と思ったら、やっぱり講演草稿でした。読むのではなく、講演として聞くと味わいが違ったのかも。
1投稿日: 2024.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ長田弘さんの詩集は大好きなものが多いのに、こちらは残念ながらあまり合わなかった。所々頷く部分はあるものの、同じ事柄を僅かな違いの言い回しで繰り返し説いていたり、過去を美化しているような、退屈に感じてしまうところが多かった。言葉を大事にしているからこその文章だと思うので、読んでよかったと言いたいところだけれど、今の自分には刺さりきらなかったというのが本音。
1投稿日: 2024.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ環境の変化で読書が心の支えになった時に読んだ。 なんか言葉の細かいニュアンスを大事にする人が書いてるんだなあって思った。すごく感覚的にいろんな物事が語られて、なぜかこわさを感じた。 129 自分が持っている時間というのは、自由になる時間というのではないのです。 そうではなくて、自分のもっている時間の井戸から、記憶の水を汲み上げるための時間が、一人の「私」という空のバケツを満たす、充実の時間であるだろうというふうに思うのです →文化を消費しまくることに私は介在しないじゃん、って思ってたけど単純にそういうことでもないらしい 136 経験を分け合う
1投稿日: 2024.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルが“読書からはじまる”だけど、読書うんぬんの話じゃないのです。 ことばと人間の話 自分の在り方の話 センテンスひとかたまり毎に、極上のチョコレートを口にしているような感じ。 同じ文章を何度も味わって堪能して そうやって少しずつ少しずつ読んで 余韻に浸って溜め息がもれる。 あぁもうすぐ読み終わっちゃうなというところで、 近くに住む天使がお手製スイーツを持ってきてくれました。 ひと休みして食す。 絶好のタイミングで絶品のチーズケーキ。 これ以上ない舞台が整ったところでいよいよ本も大詰め。 耳を澄ませるように大事に読みました。 最後の一文で、共感のあまりヘッドバンキングしてテーブルに頭ゴンゴンしているところを主人に見られ、 「何してるの?」と言われて 「あ、感動してるの」と我に返って読了。 ただただ最高。
3投稿日: 2024.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
評判が良かったので手に取ってみたが、悲しいかな、あまり合わなかった。この本と合う方はとても感銘を受けてらっしゃるので羨ましい。 私自身が短絡的すぎる人間のため、読書は楽しい暇つぶしで、本はいつもお供にして寝てても立っててもどこでも好きなように読めて良いよなーって思っていた。それ故に、そんな難しいこと言わず楽しく読書させてくれ、と反発心のようなものがおこってしまったのであった。自分自身に残念。 所々、某政治家のポエムを思い出してしまったり…ああ。
1投稿日: 2024.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本に対する心構え、立ち位置を改めされ再認識させられた本です。200頁ほどの本ですが、少し時間がたてば何度も読み返して新たな解釈、発見気づきがある本です。
2投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ本が好き 義務でも修行でもなく、ただ単に楽しい遊びだから この本は読書についてではなく、もっと根本にある言葉について、自分のありようについて考える導きのような本 「言葉というのはその言葉で伝えたいことを伝えるのではない。 むしろ、その言葉によって、その言葉によっては伝えられなかったものがある、言い表せなかったものがある、どうしてものこってしまったものがある、そういうものを同時にその言葉によって伝えようとするのです。」 この文章を読んだ時にホッとした気がして 伝えたい思いがあるのに、言葉にできなくて、言葉にしようと思いがよくわからなくなってしまう こういうことを言いたいわけじゃない... なんでみんなはきちんと伝えられるのだろう ってずっと思ってた 伝えたいことを言葉にしようとすることで、自分の中を見つめること、確かめること 言葉に言い表せない心のうちがあることを知り、それを伝えることができるのも言葉であること 言葉で尽くせぬものがあることは、ごく自然なこと 自分の言葉を持つということが、成長というのならばまだまだ成長過程 これからも楽しく本と付き合っていきたい
3投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログすべて読書からはじまる。本を読むことが、読書なのではありません。自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です。 とてもよく分かる。あー私の読書はこの一言に行き着くなあと思った。
2投稿日: 2023.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、なんだか思っていたものと、というか少し違うような気がした。うなずくところもありそうでないところもあり。
1投稿日: 2023.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直自分にはあわなかった。昔を美化しているような印象が強い。何年か経って違うタイミングで読んだらまた違うのかもしれない。
1投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ715 友人というのはその場かぎりではありません。「ずっとつづく」関係です。親しい、よく知っているという以上 に、友人というあり方の根をなすのは、「ずっとつづく」ということ。「ずっとつづく」ものが友人であり、友人た りうるということであり、「ずっとつづく」というのは、日常的にずっと連続するだけでなく、日常的にたとえ連続 していなくとも、続いているという感覚がずっとつづいている、ということです。 友人と言うと、人間のようにしか聞こえないかもしれませんが、人間だけでなく、たとえば山もそうです。 そこに山がある。その山を見て、そこにひとは、さまざまなものを見る。緑を見る。晴れたり、曇ったり、天候を 見る。過ぎてゆく季節、やってくる季節を見る。山を見ているうちに、自分の思いを見ていることに気づくことも、 きっとあります。状況、年齢、環境、その日の気分の問題まで含めて、それぞれに、さまざまに、そこにある山を見 る 本について語られる言葉のおおくには、すくなからぬ嘘があります。誰もが本についてはずいぶんと嘘をつきま す。忘れられない本があるというようなことを言います。一度読んだら忘れられない、一生心にのこる、一生もの だ、という褒め言葉をつかいます。こんないんちきな話はありません。人間は忘れます。だれだろうと、読んだ本を 片っ端から忘れてゆく。中身をぜんぶ忘れる。覚えているのはたださっきの小川のかがやきぐらいというのが、ほん とうです。読んでしばらく経ってから、これは読んだっけかなあというような本のほうが、ずっとたくさんあるはず です。 たとえば、大学に行って、大学の誇る図書館で、その蔵書をどれだけ読むでしょうか。がんばって読んだとして 一人一〇〇冊あたりも読むでしょうか。とすれば、大学が誇るすばらしいよい図書館とは、ほとんどだれも読ま ない本がたくさんある図書館のことです。実際に読むかもしれない一〇〇冊ぐらいしか本がない図書館は、図書館と はよばれません。本は非常に不思議なのです。使わない洗濯機や、使わない自動車がたくさん並んでいても、役に立 たないのです。本は別です。だれも図書館のない大学には行きたいとは思わないでしょう。しかし実際に入っても、 図書館の本をほとんど読まないで卒業するでしょう。 というのも、他人と競争する。他人と競争して、他人に勝つ。 るいは負ける。そのように勉強というものが、つねに他人を確かめ る、他人との距離を確かめるようにして行われてきたということが あります。しかし、子どもがどんどんすくなくなってゆく社会で は、他人に勝つために勉強する必要より、もっとずっと必要なのは 自分を確かにするためにする勉強であり、自分を確かめる方法とし ての勉強がいっそう求められます。
2投稿日: 2023.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書という行為が人生にもたらすものは何か。なぜ読書が必要なのか。読書の意義を説きつつも、平易な言葉で読書に対する心理的なハードルを上げることはない(寧ろ下げてるくらい)。それって結構すごいことだと思う。この一冊も僕の心に植わった木になった。きっと大きく育つだろうなって気がする。
1投稿日: 2023.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ気に入った文章の抜粋。 本は死んだすべての人の中から、自由に自分で友人を見つけることができる。何千年もの昔に友人を求めることができる。読むとは、そうした友人と遊ぶということです。 子どもには、大人には、老人にはこういう本といった壁で囲むような考え方は、わたしたちにとっての本の世界をすごく狭く小さなものにしてしまう。
6投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どんな言葉をどれだけきちんと使っているか、あるいはどれだけきちんと使えないでいるかが、それぞれを違える大事なものになってゆく」という一節に納得したり、「読書の鉄則は、ただ一つです。最初に良書ありき、ではありません。下手な鉄砲、数撃ちゃ当たる、です」という言葉に共感して思わず笑ったり。 読書を「自分を効率的に成長させてくれるもの」だと感じて、「本を読みたい」と言うひとも多いけれど、読書はむしろ効率とは程遠いものだと思う。退屈な時間、疲れる時間も多くて、それでも読み続けている内に、思わぬ発見に視界がひらけたり、いつまでも心の中に佇んで離れないひとに出逢えたりする。 「本というのは、自分で、自分の時間をちゃんと使わないと機能しないメディア」だという言葉もあった。音楽や映画は流していれば勝手に進むけれど、本は自分で読み進めない限り、開いていれば勝手に読み進めてくれることなどあり得ない(音楽や映画と同様、内容をすっ飛ばせば勝手に進ませることは可能だし、音楽や映画も流し見では内容は入ってこないので、必ずしもそうだとは思わないけれど)。 本を読んできて、内容を覚えていなくても、自分の考え方はこれまで読んできた本の欠片によって積み重ねられてきたものだなと思う。これからもマイペースに読書を続けていきたいと感じた。
3投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ本、読書、言葉と。柔らかな口調で本質をついている。本は一生を共にするもの。自分を育てるもの。師匠だったり友だったり。本って偉大だ。
1投稿日: 2023.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むということがどういうことなのかを考えるのが本書です。 「読まない本」にゆたかさがある。「たくさん読む」が正解ではない。 ことばがゆたかな人は、ゆたかである。ことばが貧しい人は、貧しい。 気になったことは以下です。 ・友人としての本。友人というのはその場かぎりではありません。「ずっとつづく」関係です。 ・どこへ行っても、みなおなじ。今はどこへ行こうと、日本のどこもおなじ表情をもつようになった。ミリオンセラーの本も、ほとんど急速に読まれなくなり、昨年のベストセラーは今年は、もう読まれないのが普通。生活のなかで考えるなら、おたがいの違いを表すものがあるとすれば、それは、「言葉」です。 ・母なるものとは自分が生まれ育った言葉のこと。 ・今の日本のなかでゆたかでないものがあります。私たちにとって今いちばんゆたかでないものは、言葉です。 ・マイ・フェア・レディという、オードリー・ヘップバーンの映画があります。映画は、とても元気がいいけれども、貧しい語彙と粗野ないいまわしと不調法な話し方しか知らない若い女性が、苦心惨憺のあげくに、みずから言葉をゆたかにしていくようになるまでを、巧みに描きます。その映画の急所は、言葉のもち方が、一人の人間を人格をつくるのだということです。 ・言葉をゆたかにするというのは、自分の言葉をちゃんともつことができるようになることです。 ・どんなに、おカネをもっていても、おカネで買えないものが、言葉です。 ・言葉の貧しい人は貧しい。言葉をゆたかにできる人はゆたかだということを、忘れないようにしたい。 ・本は年齢でよむものではない。本を読むというのが、新しいものの見方、感じ方、考え方の発見を誘われることでないなら、読書はただの情報にすぎなくなり、それぞれの胸の中にけされないものとしてのこる何かをもたらすものとしての、読書の必要は失われます。 ・人は何でできているか。人は言葉でできている。言葉は人の道具ではなく、人の素材なのだということです。 ・情報でない言葉が重要。伝わってのこるものは、その人の表情、身振り、雰囲気、気分といった、不確かな、非情報的な言葉です。 ・人の表情は、言葉のかたちをもたない言葉です。 ・良寛いわく、「耳を洗え」。耳を洗うというのは、我見をもたぬということだ。 ・民話の芯になっているのは、ひとを現在に活かすものとしての、記憶の目安です。 ・情報はふえればふえるほど、逆にコミュニケーションはすくなくなってゆく。 ・読書の核をなすのは、努力です。情報の核をなすのは享受です。読書は個別な時間をつくりだし、情報は平等な時間を分け合える平等な機会をつくりだします。簡単に言ってしまえば、読書というのは、「育てる」文化なのです。対して情報というのは本質的に、「分ける」文化です。 ・「育てる」文化の基本は個性です。「分ける」文化の基本にあるのは平等です。きわめて平等であるけれど、またきわめて画一であることも事実です。 結論 ・人は読書をする生き物です。人をして人たらしめてきたのは、そう言い切ってかまわなければ常に読書でした。 目次 はじめに 1 本はもう一人の友人 2 読書のための椅子 3 言葉を結ぶもの 4 子どもの本のちから 5 共通の大切な記憶 6 今、求められること 7 読書する生き物 8 失いたくない言葉 あとがき 解説 ISBN:9784480437426 出版社:筑摩書房 判型:文庫 ページ数:240ページ 定価:720円(本体) 発行年月日:2021年05月 発売日:2021年05月12日 国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:DSRC 国際分類コード【Thema(シーマ)】 2:VSL
16投稿日: 2022.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本への愛をとても感じる文章。本は読んでも忘れるものだけれども、それによって再読するチャンスが得られるという考え方は素敵。聖書が章や節で分けられて引用されるようになるのに1500年以上かかっているというのは知らなかったし興味深い。
1投稿日: 2022.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ池澤春菜さんの解説から引用します。 「この本はいわゆる読書論や、読書のすすめではありません。もっと根源的な、言葉について、そして自分のありようについて考える本と言えるかもしれません。古今東西の言葉を収めた『本という考え方』とどう向き合っていくか。全てのページに、一生を通じて、折に触れ思い直し、噛みしめるような宝物のような言葉が溢れています」 全くその通りだと思いました。すごく栄養価の高い食品を少量頂いたかのような気持ちになりました。 詩人、長田弘の他なる一面を改めて知り得たと思いました。今の世の中にこれ程わかりやすく、奥深い知見を広げてみせてくれる方は少ないと思います。 この本を読んだことを忘れそうになったら繰り返し読みたい本です。 以下印象深い文章を少しだけ抜粋します。 はじめにより 本というのは「本という考え方」。 本は「本という考え方」を表すものであるということ。 本は「本という考え方」をつくってきたものである。 本によって、本という一つの世界のつくり方を学ぶということ。 本の大事なありようのもう一つは、じつは「読まない本」の大切さです。 「本の文化」を深くしてきたものは、読まない本をどれだけもっているか。 読んでいない本が大事なんだという本との付き合い方がどこまでも未来にむけられた考え方としての「本という考え方」を確かにしてきた。 (以下略) ・本という文化を育ててきた人間がそこにいる。本のあるところ、つねに人間がいる。それは、友人としての本という感覚。感じ方がじつは本の文化というものをつくってきたのだということです。 ・本の文化を自分のものにできるかどうかの重要な分かれ目は、その再読のチャンスを自分のなかに、生活のなかに、日常のなかに自分の習慣としてそれをつくってゆくことができるかどうか。 ・どんなにおカネを持っていてもおカネで買えないものが言葉。 ・心はどこにもないものだから言葉でしか言えないのです。 以下、書き写していると全文書き取りになってしまうので、この辺で。 尚、この本では子どもの本についていても触れていて、子どもの本というのはじつは大人こそが読む本にほかならないと長田さんはおっしゃっています。 私はあまり読んでいない分野なので、これから少しづつ読んでいってブクログの本棚にも載せていけたらと思いました。 また、ブクログの存在は、本を友人にするにあたって大変こころ強いものだと思います。
84投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書についてというよりも本とは言葉とはといった内容。私自身本を読むことは好きだけれど同時並行が出来ない分、後回しにしてしまうことが多い。本と向き合う時間をきちんと設けたいなと改めて思った。
2投稿日: 2022.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読む意味を一緒に考え、本好きの自分を優しく肯定してくれる本です。 本に書かれている言葉によって、自分の存在を確かめたり肯定したりできる。 見たこともない世界を言葉から想像できる。 本を通して世界と、自分と静かに対話できる。 いつでもそばにある、いてくれるという心強さを感じる。 自分の言葉にできないものを、感じたり言葉にしてくれたりする。 本ってやっぱりいいな。
12投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ『すべて読書からはじまる。本を読むことが、読書なのではありません。自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です。』 めちゃくちゃ共感。 そして美しい表現の多い本でした。 本って、言葉って、日本語って素晴らしい。
8投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1年前に読んでいるのに、すっかり忘れて再読… 再読は友情の証、なんて書いてくれている、ただボケてるだけか?と思ったが、忘れたらもう一度読めばいい、それが本の文化だ、と。素晴らしい。 読んでも読んでも忘れる人のために、取っておくしかないから図書館は必要なのだ、と。 前回は読むための椅子、の話が強烈な印象に残ったが、再読では視点も変わるのか、他にも沢山良い言葉 やはりこれは本棚に残すべき一冊かと。 人びとが本を読まない時代に、人びとの間に失われるのは友人を見つける能力。 言葉は、誰にとっても同じもの、言葉は平等なものだけれども、人と人を違えるのも言葉、言葉を豊かにできる人と乏しくしてしまう人とを言葉は違えるから。 自分は言葉を、どう豊かにできるか。 器量よし、心の大きさを、心の容積を大きくしてゆけるような言葉を、どれだけ自分の中に蓄えていけるかが、これからの時代の物差しになってゆかないと、私達の時代の言葉はどんどん乏しくなってしまう。88 何事も段階的にということを前提に考えることは、何事も制限的にしかとらえることをしないという事110 絵本のような子どもの本の読み方に教えられるのは、読書というのは自分の時間ほでに入れ方なのだ、ということ122 良寛より 耳を洗うとはどうすることか 我見をもたぬということだ 162 我見によってしかこの世を見ないというのは危うい 文庫ならではの解説、池澤春菜もまたいい 幸田露伴の孫引き、 「どんな人もその気になれば友だちは見つけられる。現実生活に友だちがいない人にも、唯一友人を準備してくれるものがあるとすれば、それは書籍だ」221
6投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこころに残る文章が多く、こんなにスマートフォンのメモに打ち込んだ本はないんじゃないかな。 多感だった頃に感じていたことを言葉にしてもらった感覚。あの感覚は私一人ではなかったんだな、という安心感。一度読むだけでは味わいきれていないので、また時間をおいて読みたいと思える本だった。
3投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ【2022_02】他の方が主催される読書会でのテキストが、長田さんの『最初の質問』という絵本だった。それが縁となって手にした著作。今年はこれ1冊しか読めなかったとしても、もう後悔することはないだろうと思う。できることなら、生前にお会いして、「先生」と呼ばせていただきたかった。うまくコメントできないが、お許し願いたい。
3投稿日: 2022.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
少し難しかった。また再読したいと思う。印象に残ってるのは、読書の内容は忘れてもいい。また再読すればいい。 本は自分の心を見つめ直す場所。池澤春菜さんの解説は、読書欲を駆りたてられる。
1投稿日: 2021.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
詩人ならではの言葉の向き合い方や言い方が、正直読みにくかったです。 ただ、「面白い視点」は多かった。 「若い世代が本を読んでない」わけではなく、「若い世代が読む本を大人が読まない」のだ。 人は自分が触れてきた言葉しか表現することはできないし、自分がいいと思った言葉を使うようになる。 日常から意識をしている人とは差が出ると感じました。
3投稿日: 2021.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログスケールが違った。巷に溢れている読書術とは違い、なぜ人生に読書が必要なのか、あたたまる視点で書かれていた。 情報収集に躍起な今の時代の虚しさを、私も感じていたが、それも言葉にされていた。 読売新聞のこどもの詩のコーナーで、名前を毎日拝見していたが、本を読むのは初めてだった。 ああ、これが本当に文を書くことで食べている人の文章なのかと感銘も受けた。 情報取得のための読書には、ハッとさせられる。 寄り添ってくれるのが本だという本質を突きつけられた。
8投稿日: 2021.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログひとにとって本とは、読書とは、そして言葉とはなにか 静謐なエッセイ。 ひととしてのありようを考えさせる後半は、 何度も読み返したい素晴らしいものだった。
7投稿日: 2021.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログどの一文をとっても心に深く染み渡るような本でした。 読書に何か目的意識を持って取り組むような使命感にかられて読むことがあり、純粋に楽しむということを忘れることがありました。多くの情報を取り入れるためではなく、自身の記憶に残るような一文・一句に出会いたくて、本を読んでいたことを思い出せました。好きなフレーズに付箋を貼ったり線を引いたりして、ふと本棚から取り出して読み返したくなるような一冊との出会いを、読書は届けてくれる。そんな行為がとても貴いことに感じられる一冊でした。
4投稿日: 2021.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むということは、情報を得ることとは違うと。読書とは何かを様々な角度から語る。 『本についてのいちばん重要なことは、本は「本という考え方」をつくってきたものであるということ』と始まるこの本は、講演原稿から書き起こした平易な表現なのに、丁寧に読まないとなんだかよくわからないままに一冊が終わってしまう。終わりころの『本を読むことが、読書なのではありません。』という文を読む頃には、何となく書いてあることがわかるようになっている。これはちょっと違うなと思うところもかなり多いけど、自分にとっての読書ということが整理できたような気がする。解説は池澤春菜さん。ストレートに本好きと語る文章が気持ちよい。
4投稿日: 2021.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むのは好きだが、 私の読書はいったいどういう読書なのか。 単に情報集めに終始していないか。 ちょっとドキッとさせられました。 単なる読書論ではなく、 もっと大きなテーマが語られています。 ただ、やはり詩人の文章。 ところどころ、頭にハテナマークが浮かぶ。 このお方の文章、授業するのに苦労したことを 今、改めて思い出します。
1投稿日: 2021.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本について読む本。 情報として本を読んでいる感は確かにある。 もっと言葉を味わう読み方も身につける必要があるなぁ 育てる、蓄える、分ける この3つのキーワードで言葉を紡いでいく。 以下、印象的なシーン 1. 子どもの本というのは、子どものための本なのではありません。大人になってゆくために必要な本のこと。 →絵本でも読んでみようかな 2. 本を一冊読もうと思ったら、その本をどの椅子で読もうかと考えられるなら、良い時間をきっと手に入れられるだろうと思うのです。〜この本をどの椅子で読もうかと考えて、そこから自分のことを考えてみる。これからそういうことが、とても重要になってくると思います。 →今まで考えもしなかったなぁ。本は読んでたけどたしかにベッドで寝転んで読むか、電車の中かだったし、、、場所(椅子)ってとても大事かもしれない。 3. 本というのは、本を開いて読めばいい、読まないうちは本を読んだことにならないのだということではないのです。本は読まなくても良いのです。しかし、自分にとって本を読みたくなるような生活を、自分からたくらんでゆくことが、これからは一人一人にとってたいへん重要になってくるだろうと考えるのです。〜本屋に寄る時間や、家具屋で椅子を覗く時間を、自分の1日のなかに作るだけで、本のある人生の風景が見えて来ます。 →すごくいい。本、読書とは何かというちょっとした哲学を感じる。
2投稿日: 2021.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「すべては読書からはじまる。本を読むことが、読書なのではありません。自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です。」 これが全てだと思います。 下手な感想を書くよりも、印象に残った表現をここに残したいです。
4投稿日: 2021.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書についてのエッセイで、難解なテーマではないし、けして難しい言葉が使われている訳でもないのに、著者が語りかけてくるものをどう受け取ったら良いのか、自分がどう理解したのか、文章にすることが思いのほか難しい。 例えば、「2 読書のための椅子」の冒頭、著書は「読書のためにいちばん必要なのが何かと言えば、それは椅子です。」とある。次のパラグラフで、本を読むときに自分で自分に最初にたずねることは、その本をいつ、どこで読むか、本を読む場所と時間である、それが、その本をどんな椅子で読むか、ということです、と言う。これで分かったような気持ちになるが、また具体の椅子の話が続く。 直線的に文章が続くのではなく、ぐるっと螺旋状に回って芯に辿り着くような感じと言えば良いだろうか。 解説で解説者が具体的に紹介しているが、言葉、記憶に関して、印象的な文が随所に出てくる。読者一人一人にとって、そうした文章がおそらく見出せると思う。 一文一文をゆっくりとしたリズムで読んでいかれることを、お勧めしたい。
7投稿日: 2021.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んだら忘れられると言うのは、悪いことじゃなくて本の良いところか。前に読んだ時のことを思い出せる。過去の自分との対話ってか。 本を読む時の椅子の話。椅子じゃなくても、ここでゆっくり読むのが好き、と言える場所、そこにいられればいいって言える場所があれば人生幸せだよな。
1投稿日: 2021.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書や言葉の大切さを色々な角度から書かれている。 共感することも多く、また気付かされることも多かった一冊でした。
2投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
社会にとって「本の大事なありよう」が問われている。 言葉のちからが揺らいでいる。そんな今、発行された本。 「本を読んでも読んでも内容を忘れてしまうのはもったいない。」と思っていたけれど、「忘れるのは当たり前で、読んで忘れてもう一回読めばいい、それは絶えず新しい経験になる」と励ましてくれる本。私は大切だと思う本の友人になりたいし、友人でありたい。 あとがきより 橘曙覧の歌3つのうちの1つ たのしみは そぞろ読みゆく 文の中に 我とひとしき 人を見し時(P116) 私の本を読むスタンスはこれだと、見つけた感じです。 **************************************** めったに☆5はつけないけれどこれは文句なしで5。 惹かれたフレーズや感想、まとめなどを綴ってみました。 1.本はもう一人の友人 「本は死んだ人すべてのなかから、自由に自分で、友人を見つけることができる。(中略)読むとは、そうした友人を選ぶということです。」(P19) 2.読書のための椅子 図書館の座席指定チケットなんて素敵ですね。公共施設の平等性を考えると無理なのかなー…。 3.言葉を結ぶもの 言葉とは、その人の生き方の流儀でありマナーである。 4.子どもの本のちから 子どもの本は子どもたちのほんであって大人たちの本でもある。大人こそ読むべきもの。 5.共通の大切な記憶 読書は自分の時間の使い方の問題である。自分の時間とは、自由になる時間ではなく、記憶の水をくみ上げるための、充実の時間。 6.今、求められるとこと わたしたちは言葉とあいまいさのなかに生まれてきて、生きていく。言葉はつながり。情報は言葉ではない。 7.読書する生き物 情報の主人公は情報でありあなたでもわたしでもない。 8.失いたくない言葉 情報は「これから」を語るもの、読書は「これまで」を語る言葉。図書館は「育てる」と「分ける」を繋ぐ「蓄える」文化である。
5投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の持つ意味大切さいろんな角度から述べていて、ふに落ちることも多い。 まずハード面ということで、読書のための椅子についての考察、子供の本の持つ力など興味深く図書館の大切な存在理由にも納得しました。
3投稿日: 2021.05.24
