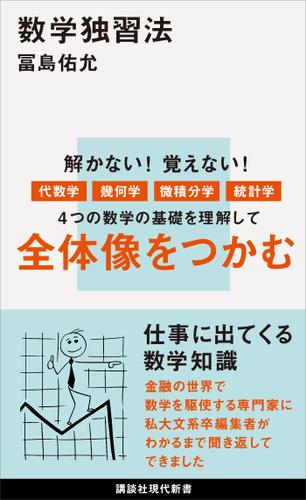
総合評価
(15件)| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログプログラミングやデータサイエンスの関連での数学を学ぶ前に読むべき本。 なんで数学が必要なの?や、数学的な考え方のイメージを掴んだ上で数学を学びに行くことで学びが最大化できる。
0投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系の私に数学を教えてくださいよりは、やや、難易度高い。が、中学、高校数学の範囲を少し越えて、ビジネスで用いられる数学を根本的なところから応用まで説明してくれ、数学的な思考方法を身につけることができる良書。 あとがきでも書かれているように、丁寧な専門用語の解説、計算より考え方の理解重視、数学なぜ学ぶのかという問いへの対応という、3点が意識されていて分かりやすく、数式の羅列ではなく読み物として数学思考を学ぶことができた。 今回この書で、 線形代数って何を指しているのか 三角関数を用いたフーリエ変換 微分方程式の意義→複雑な現象を微分で簡素化して方程式で表現解析して、積分で現実の世界に戻すことで活用するということ 統計学、特にベイズ統計学というものの概要 を把握できたことが大きな収穫であった。
10投稿日: 2024.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学四天王「代数」「幾何」「微積分」「統計」。 わからんものをx(エックス)として考える代数。 三角形から始まる幾何。 細かく切って、切ったものを積み上げて、の微積分。 膨大なデータを俯瞰して解釈する統計。
0投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ・数学の基本を専門的ではなくわかりやすい言葉を交えながら解説し、具体例を交えながら現実にどう役立てられているかが解説されている。 ・厳密な数式の解説はされないため、数学を学ぶ意義を理解する入門書として最適。数学学習の理解を深める助けになると思う。
0投稿日: 2024.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学のやり直しというか高校のころは全く勉強していなかったので、まさに今新しい勉強をしている感じです。 難しいてけど、新しく覚えるものは楽しい!
2投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学的、理系的な思考の要点は、余計なものを切り捨てて本質を浮かび上がらせるシンプルイズベスト。にある。 本書で扱うのは代数学、幾何学、微積分学、統計学。 代数学は未知の数字を文字に置き換えて、思考する学問。 幾何学の基本は三角形。 微積分学は表裏一体。 統計学はビッグデータ時代を生きるためには重要な学問。 数学は面白く、学び直したい。
0投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い! 数式を見て、何となく何をしているのかイメージできるようになるための、初学者の本。 ここから数学を勉強していきたいと思いました!
0投稿日: 2022.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学が現代社会の中で実際に使われている様が垣間見られる本。新型コロナ感染者の推移のグラフとか、自動運転技術にベイズ統計が利用されていたりとか、興味が湧く話題が多い。ただそこから先は別の本なりで勉強しなければならないので書名の「独習法」とはちょっと違う。
0投稿日: 2022.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞広告を見て本屋で買った本。面白く読めました。 「独習法」とありますが、本書は本格的に数学を習得したい人向けの本とは違います。むしろ「方程式を解いたり数理モデルを作ったりといったことは得意な人たちに任せておけば問題」ないという立場です。「数学とは何か、どう考えるのか、何の役に立つのかという『数学の俯瞰図』を頭の中に作り上げることが「本書の目的」です。 著者の冨島祐允さんは数学者というよりも証券アナリスト。数学の全体像や発想方法をいかにビジネスに活かしていくかを読者にストレスを感じさせることなく説明してくれます。 本書では数学の根幹をなす4つの分野、代数学、幾何学、微積分学、統計学を「数学四天王」と呼び、それぞれの分野が現代の話題にいかに絡んでくるかが興味深く説明されます。例えば、自動運転と統計学、宇宙ロケットの推進原理と微積分学、音楽データと三角関数などなど。 本書は数式はほとんど登場しません。登場するのは最低限の公式、対数、三角関数くらいです。微積分の説明を微分からではなく、面積を使って積分からの説明しているのはわかりやすいと思いました。 数学応用の最新のエッセンスが数時間で理解できます。お得な1冊です。
1投稿日: 2021.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたま本屋で見つけて読んだ本、なかなか面白かった。代数学、幾何学、微積分学、統計学の4つの数学の基礎を上手に説明している。難しい数式なし。 幾何学から三角関係、基本波の重ね合わせ、フーリエ変換まで続いたところが、流れるようで面白い。個人的には、微分積分は他の本で読んでいる内容と重なっていた。そして、統計学は、実例を上げながらの説明で、特にデータが蓄積されるに従って学習してアップデートされていくベイズ統計学が楽しい。 数学的な考え方が身近に感じられる、とっつきにくさが緩和される、の効果はありそう。ただ、これだけで何かができるようになる訳ではないので、あくまでも導入のための一冊。
0投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系な人向けに分かりやすく数学を解説した本で、単純な学び直しではなく、サイン・コサインがどう社会に役立っているかといった解説本。バリアフリーの例を出すところは、数学得意な人でも中々言えないんじゃないかと感じた。 …本の題名は間違っている気がしないでもない。「数学の独習の仕方」を学べる本ではないことは確か。
0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログかって「サイン・コサイン、なんになる」(受験生ブルース)と数学を呪詛した(元)学生達に対するアンサー本。幾何学の基本だという三角形が今あるiPhoneに繋がってるというのは現代テクノロジーのそこかしこに数学が活用されてるほんの一例に過ぎない。
0投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ代数学 指数関数は対数グラフで見るとわかりやすい。 対数と指数は逆の形 PHは、-log水素イオン濃度。水は0.0000001mol/Lなので、logをとると10のマイナス7乗で7になる=中性。濃度が10倍上がると1増える。 幾何学 幾何学の基礎は三角形。図形の中で三角形を探し、それと相似な三角形を考える。 フーリエ変換で波を三角関数の合成と考える。 複雑な波の周期の整数分の一の三角関数を足すと、分解できる。 データ圧縮に使われる。 微分積分 積分はグラフの面積を求めること、微分は傾きを求めること。 速さは距離を時間で微分したもの。もう一回微分すると加速度。 統計 ナイチンゲールの功績は統計学者としてのもの。 統計学は記述統計、推計統計、ベイズ統計の3つ。 記述統計は、データがある場合に分析。 推計は、データの一部から全体を推測。母平均の区間推定の公式は、標本平均±t値×標本標準偏差/サンプルサイズー1の平方根。 ベイズ統計は、試行錯誤。新しいデータが次々にやってくる場合に使える。自動運転車のAIで使える。
0投稿日: 2021.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログたしかに著者の言う様に、数学的思考は大事そうだよなと、本屋に行ってこう言う本を見かけるたびに思っていて、買って読んでみたのだが、やはりと言うかなんというか、学生時代それこそもう中二の相似とか関数くらいから苦手になってしまったそのまま、読んでいてもあまり理解できなかった。残念! それでも全く忘れていた微分積分とはなるほどこういうものなのかって触りは感動だったし、他で読もうとしてすぐ挫折した統計学の本にもう一度挑戦してみようと思えたのは少しは収穫だったと言えるのかもな。 この本については、スタンスは良いと思うので、著者の言うよりもっと数多くの世の中のこう言うことを知るために解決するために、代数や幾何学や微分積分、統計学の考え方や知識がこうやって役に立つんだよと言うことを挙げて欲しいので、改訂版として、その分分厚くなってもいいので改めて出して欲しいなと思う。
0投稿日: 2021.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ短時間でざっと数学の復習ができて良い。 複雑な要因が絡むビジネスへの応用は難しいかな? 数式で表せるぐらい、できるだけ事象を単純化する心構えを学ぶ本。
0投稿日: 2021.07.10
