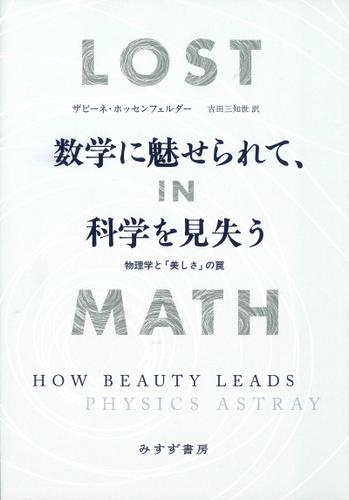
総合評価
(9件)| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ【自由研究】超ひも理論シリーズ(第三弾) 超ひも理論の最大の弱点は「検証できない」ことだそうです。(検証するには太陽系ほどの装置が必要なのだとか…) 検証できないのに「美しく」「自然」だから認められる理論が多数ある異常さに著者は警鐘を鳴らします。 反証もあります。 楕円軌道のケプラーVS円運動のガリレオ、「ビッグバン」のルメートルVS「忌まわしい」アインシュタインの例。美しくないものが勝利したことはあったのです! 考えてみると「美しさ」は人間特有の主観なのですね。(猫にE=mc²という式を見せても無視されるように…) しかし現在の物理学界は、高度になるほど検証が不可能で、理論構築のみが先行し、美しい=正しい説がはびこっているのだそうです。 そのジレンマに途中、著者大丈夫か?と思う場面は何度かありましたが、検証こそ物理学者の矜持というのは随所に感じました。 数学は理論の袋小路に陥り、物理学は死んだのでしょうか?今後AIや新たな技術革新で検証能力が向上するのでしょうか? 著者は最後に力強く宣言します。「物理学の次のブレイクスルーは、今世紀に起こるだろう」と。そして「それは美しいだろう」と。やっぱり美しいんかい! *** アインシュタインの相対性理論がブラックホールを予言したように、超ひも理論はマルチバースやホログラフィー理論を予言しています。 超ひも理論が正しいかどうかはさておき、個人的にはとても楽しい理論と感じています。(ほとんど理解できてませんが…) 世界中の学者さんが研究する次の理論が表れるのを楽しみに待ちたいと思います。 (追記) 再読記録あります。→
5投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 人は現象に法則を見つけようとする。複雑な事象を切り取り、パターンを見つけ、大きすぎる値や小さすぎる値には微調整を加える。外れ値を除外し、条件を平準化し、帰納していく。よりシンプルに。より自然に。 それは素粒子物理学の世界でも例外ではない。「真理」とはとどのつまりあらゆる事象の中心に存在する単純なパーツだ。それゆえ自然法則は無駄が無く、エレガントで、かつ美しくあるべきなのだ。 しかし、人間の感じる「美しさ」が真理と合致していると何故言えるのか?「美しい」という概念は主観的な価値観である。均質性や単純さに心地よさを覚えるのは人間の「美意識」によるものであり、物理法則とは関係ない。 本書では、「美しさ」を重視して理論を進める物理学のありかたに警鐘を鳴らす一冊だ。筆者のザビーネ・ホッセンフェルダーは現役の理論物理学者である。自身の研究分野の現況を解説したり、分野の最前線で研究を行っている同僚にインタビューを行ったりしながら、物理学界隈に蔓延する「美優先主義」を痛烈に批判する。仲間たちの研究を目の前でこき下ろすとは結構アウトローな学者だが、第一線で研究を重ねている人物だけあり、語られる内容は具体的で面白い。何より知見のある人からのダメ出しというのは痛快なものだ。 では、美意識を先行とした理論がどういう弊害を引き起こしているのか?顕著な例は「超対称性理論」をめぐる研究である。 超対称性理論は、標準模型のすべての素粒子に「対となる素粒子が存在する」と仮定する。この素粒子がもし存在すれば、現状解明ができていない不自然な(あまりに大きすぎたり小さすぎたりする)数値を自然に解明できる。例えばヒッグス粒子は量子揺らぎの影響を受けて、質量の理論値が実測値よりも10の14乗倍大きくなっている。これは決して無視できない誤差だ。だが、超対称性理論が真だとすれば、この誤差を埋め、自然な値にすることができる。 超対称性は、既存の諸理論にあまりにきれいに適合するので、多くの物理学者たちがそれは正しいに違いないと考えている。加えて、対となる素粒子には暗黒物質の候補が含まれると考えられているため解明が期待されている。 しかし、いくらLHCで量子の衝突を繰り返しても、超対称性粒子は未だ検出されていないのだ。 それは、物理学者たちが長年にわたり築き上げてきた数々の理論が葬られることを意味する。そして、物理学者たちは次のステップ、「超対称性が現れない理由」を探し始めている。つまり、理論の齟齬を埋めるための理論の齟齬を埋める理論を探しているのだ。 多くの物理学者にとって「ただランダムにそうある」という事実は耐えがたい。そのため、そこに対称性を加えたり統一を加えたりして――たとえ実験結果と大きく矛盾するとしても――理論上の均衡を図っていく。 これを受けて「じゃあ、ファクト第一主義で行こうよ」と思うかもしれないが、話はそう単純ではない。物理学の分野では、実験でたやすく証明できるほど単純な理論はもう残っていないからだ。そうなると、莫大な時間と金をかけて大規模な実験をするしかなくなるが、手あたり次第やるわけにはいかない。新しい現象を明らかにする可能性が最も高い実験はどれかを決定するには、まず理論を作らなければならない。そして、実験結果の無い理論は何に導かれるかというと、「美意識」しかない。地図無き場合に頼れるコンパスは、結局のところ「自然さ」であり、はじめに戻ってきてしまうのである。 ――――――――――――――――――――――――――――― 以上が本書の内容の一部である。 私は今まで、物理学は夢のある学問だと信じていた。宇宙の成り立ちを解き明かしていけばいずれは人類の進化につながると考えていたからだ。だが、第一人者が語る物理学の今後はなかなかに暗い。物理学のありかたを根本から見直すことになれば、今まで費やしてきた時間や、LHCをはじめとした超大型の実験器具は無駄になってしまう。 物理学の発展はどん詰まりに向かっているのか?そして美意識を重視した理論は今後も続き、それは正解へと繋がっているのか?多くの物理学者が今、この問いと向き合っている。 ――――――――――――――――――――――――――――― 【まとめ】 1 美意識によって、科学を見失う 本書は、美意識に頼った判断がいかに現在の物理学の研究を推し進めているかという物語だ。それは、教わったものをいかに使ってきたかを省みる、私自身の物語でもある。しかしそれはさらに、私と同じく、「自然法則は美しいのだと私たちは信じているが、何かを信じ込むことは、科学者がやってはならないことではないのか?」という不安と闘っている、ほかの多くの物理学者たちの物語でもある。 「物理の理論が美しいという感覚は、何かしら私たちの脳に生まれつき備わっているもので、社会的に形成される合意のようなものではないでしょう。それは心の琴線に触れるようなものです」。CERNの理論部門のリーダー、ジャン・フランチェスコ・ジュディチェは言う。 「美しい理論に出くわすと、芸術作品を前に感じるのと同じ感情的な反応が生まれるのです」 彼が言っていることがわからないわけではない。わからないのは、それがなぜ重要なのかだ。美しい作品を生み出すことは尊い手仕事だとしても、科学は芸術ではない。私たちは感情的な反応を引き起こすために理論を追究しているのではない。私たちは、観測した事実の説明を探し求めているのだ。科学は、人間の認識力の欠陥を克服し、直観の誤りを避けるための組織的な取り組みである。科学は感情を扱うものではなく、数と式、データとグラフ、事実と論理を扱うものである。 2 超対称性理論に見る、物理学の暗い未来 物理学の分野では、理論は数学でできている。理論の構築に数字を使うことで、論理的な厳密さと内部一貫性を強化することができる。要するに数学は、理論の曖昧さをなくし、結果を再現可能にするのである。 だが、物理学は数学ではない。うまくいく理論は内部一貫性があるのみならず、観測結果とも一致していなければならない。この要求が、物理を非常に難しくしている。新しい理論は、既存のすべての理論の成功をすべて包含し、さらに少し向上しなければならないのだ。 美的基準に囚われた理論の例として、「超対称性理論」を見てみよう。 超対称性理論は、標準模型のすべての素粒子に「対となる素粒子が存在する」と仮定する。この素粒子がもし存在すれば、現状解明ができていない不自然な(あまりに大きすぎたり小さすぎたりする)数値を自然に解明できる。例えばヒッグス粒子は量子揺らぎの影響を受けて、質量の理論値が実測値よりも10の14乗倍大きくなっている。これは決して無視できない誤差だ。だが、超対称性理論が真だとすれば、この誤差を埋め、自然な値にすることができる。 超対称性は、既存の諸理論にあまりにきれいに適合するので、多くの物理学者たちがそれは正しいに違いないと考えている。加えて、対素粒子には暗黒物質の候補が含まれると考えられているため、解明が期待されている。 しかし、いくらLHCで量子の衝突を繰り返しても、超対称性粒子は未だ検出されていないのだ。 それは、物理学者たちが長年にわたり築き上げてきた数々の理論が葬られることを意味する。そして、物理学者たちは次のステップ、「超対称性が現れない理由」を探し始めている。つまり、理論の齟齬を埋めるための理論の齟齬を埋める理論を探しているのだ。 ここ何年ものあいだ、LHCでは何か新しいことが起こらなければならない、さもなければ、現在存在する素粒子物理学の記述のなかで最善のもの(標準模型)が、自然ではないことになってしまう、という話が流布していた。これらの自然さを測る数式は、極端に大きい、または小さい数が含まれる理論は美しくないという考え方に基づいている。しかし、「自然さ」という美的基準を指針にすることは混乱を生むだけではないのか? 3 美的第一主義は昔から存在した 天文学者にして数学者のケプラーは、当時、惑星(水星、金星、地球、火星、木星、土星)が太陽の周りを円軌道に沿って運動しているというモデルを考えていた。それらの惑星の軌道はそれぞれ、太陽を中心とし、互いに入れ子構造になった正多面体プラトンの立体の上にあり、個々の惑星の軌道半径は対応する正多面体の位置で決まるというものだ。このモデルから得られた惑星間の距離は、観測結果とよく一致した。それはとても見栄えのよい宇宙像だった。「このような完全な創造者の作品にとって、このうえなく美しいものであることは、絶対に欠かせないことである」とケプラーは述べた。 ところが、のちにケプラーは、惑星の厳密な位置を詳細に記した多数の表が参照できたおかげで、自分のモデルは間違っていたと納得し、惑星は太陽の周りを円ではなく楕円の軌道に沿って公転しているのだと結論付けた。 彼の新しい説は、即座に非難をもって迎えられた。当時の審美的基準に合わなかったのだ。あのガリレオも、「天体には円運動のみが自然に適合し得る。それらが最善の配置で作られている宇宙の不可分な一部であるからには」とケプラーを否定している。 4 そうは言っても何を頼ればいい? 物理学者にとって対称性は、不要な繰り返しを避ける組織化原理である。パターン、類似性、秩序は、どのような種類のものでも、対称性の表れとして数学的に把握することができる。対称性の存在はつねに、冗長性を明らかにし、単純化を可能にする。つまり、対称性は、より少ないものでより多くを説明する。対称性は、強力な統一原理となり得る。なぜなら、ある場合には非常に異なって見えるものどうしが、じつは対称変換によって結びついて同じ一つの属性で括れることを示すものだからだ。 しかしながら、大量のデータを単純化するための正しい対称性を見つけるのは、往々にして簡単ではない。そして、研究対象の領域が実験による現実から離れていればいるほど、その領域の理論については、美的魅力の比重がますます高くなる。 美的基準ではなく実験結果を参照するのは確かに正しい。しかし、可能な仮説をすべて検証することは、断じて不可能だ。回数の面でも、予算の面でも。そのため、今日の科学的事業の大部分では、はじめは良い仮説を見出すことに注力する。物理学の基盤の部分で、私たちはつねに、実験による検証以外の根拠によって理論を選んできたわけだ。 それは必要なことだ。その理論が検証に値すると誰かに認めてもらえなければ話は始まらない。だが、どんな理論に取り組むかを、理論が検証される前に決めるには、どうすべきなのだろう?また、実験家たちは、どの理論が検証に値するかをいかに決めるべきなのだろう? 科学者たちが美に気を取られていなければもっと先に進んでいたかもしれないということをさておいても、物理学は変わった――そして、変わり続けている。以前は、適切ではない美的理想を修正するようデータが理論物理学者に強いるということがあったので、物理学者はなんとか失敗を乗り切ってきた。だが最近では、新しい現象を明らかにする可能性が最も高いのはどの実験かをまず理論によって決定しなければならないことがますます多くなっている。そしてそれらの実験は、数十年という時間と数十億ドルという資金がなければ実施できない。 あらゆる場所を探す余裕は私たちにはない。したがって、新しい実験がより難しくなるにつれ、理論家たちは、美しい夢を見ながら夢遊病者のように歩き回って袋小路にはまらないように、一層の注意が必要なのである。この新しい要求には新しい方法が必要だ。だが、それはどんな方法だろう?
24投稿日: 2022.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者が物理学の現状に疑義を感じ、いろんな人にインタビューしながら科学とはなんぞやと考えていく話。 「本書は、美意識に頼った判断がいかに現代の物理学の研究を推し進めているかという物語だ」と序文にある通り、いろいろな人が理論の優劣を考えるとき美しいかどうかを気にしてて、けして客観的でない”美”意識に客観的であれと考えている科学者の多くが惹かれている様が、時々挟まるとても皮肉が利いた文章で紹介されててとても面白い。基本的には実験の結果検証をすることで理論を洗練させてきたのだけれど、近年は実験するにも金も手間も時間もかかるモノばかりになり新たに生まれた理論全てを検証することなど実質的に不可能な状況なので事前に選別する何らかの手段が必要だって話もあり、かつてはそれがうまく機能してたが今はそうでもない話がありと、科学の現状と将来について期待と不安を感じる内容だった。 個人的にはところどころ「経済学批判かな?」と思える話を見かけて物理学も最先端の(検証が難しい)話になると同じようなことになってるのだなと思ったりしたのだけれど、後半に剛速球の経済学批判が入ってて大爆笑してたw
1投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ理論と実験は相互に進展していく。理論の高度化により,実験も高度化を余儀なくされたことで,理論を検証するためのデータが得られにくくなったのが現代物理学。データが得られない時に理論物理学者は理論の美を尤もらしさの基準とするようになってきたが,それは科学の方法としてどうなの?という問題提起をしているのがこの本。 ***** 物理学の分野では,理論は数学でできている。私たちは何も,微分幾何学や次数付きリー代数を知らない人を怖がらせて遠ざけるために数学を使っているのではない。私たちは,愚かだから数学を使っているのだ。数学を使っていれば,私たちは正直でいられるーー数学は,私たちは,自分自身や他の研究者に嘘をつくのを防いでくれる。数学で間違うことはあり得ても,数学で嘘をつくことはできない。 理論物理学者としての私たちの任務は,既存の観測結果を記述するため,あるいは,実験の計画の指針となる予測を得るための数学を構築することだ。理論の構築に数学を使うことで,論理的な厳密さと内部一貫性を強化することができる。要するに数学は,理論の曖昧さをなくし,結果を再現可能にするのである。(pp.10-11) 物理学では,理論はほとんどつねに,アイデアを寄せ集めてゆるく縫い合わせただけのパッチワークのようなものとして始まる。理論を構築しようとして物理学者が作り出したぐちゃぐちゃしたものを整理し,その理論全体を導出できるようなすっきり整った一連の仮説を見つける仕事は,数理物理学を専門とする仲間に委ねられることが多い。数理物理学は,物理学の一分野というよりも数学の一分野である。(p.11) 論理的一貫性はどんな科学理論にもつねに必須だが,すべての科学分野が数学的モデルを使うのに適しているわけではない。数学ほど厳密な言語を使っても,データがその厳密さに見合わないなら意味がない。そして,物理学は,あらゆる科学分野のなかで最も単純な系を対象としているため,数学的モデルを使うのに理想的なのである。 物理学では,研究の対象は再現性が高い。実験系の条件や環境を制御する方法や,精度を損なうことなく無視できる効果はどれであるかが,物理学では比較的よくわかっている。たとえば,心理学実験における結果を再現するのは難しい。なぜなら,この世に同じ人間が二人存在することはないし,人間の持っている奇妙な性質の数々のうち,どれがその実験に関係しているのかがわかっていることなどめったにないからだ。しかし,そのような問題は物理学にはない。ヘリウム原子は空腹になったりしないし,曜日による機嫌の良し悪しもない。(p.13) 手ほどきを受けたことのない人には,たくさん並ぶ方程式は近づき難く見えるかもしれない。だが方程式の扱いは,教育と習慣の問題だ。(p.13) だが,学んだこともある。それは,科学的な理論は反証可能でなければならないというカール•ポパーの説は,とうの昔に時代遅れになっていたということだ。これはわたしにはうれしい知らせだ。というのもこの哲学の説は,レトリックの手立てとして以外には科学の分野の誰によっても一度たりとも使われたとは思えなかったからだ。どんな説でも,新たに登場する証拠に合うように修正したり拡張することは可能なので,ある説を反証することはめったにできない。そのため,理論を反証するのではなく,私たちは理論を「納得し難くする」。つまり,こういうことだ。繰り返し修正された理論は,ますます難解にーー醜くとは言わないまでもーーなり,ついには科学者たちが興味を失ってしまう。だが,ある説が納得し難くなるのにどれくらいかかるのかは,ひとつの理論を,相容れない証拠に適合するように繰り返し修正することに対する,その人の許容度がどれだけかに依存する。(p.52)
1投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ美という基準の在り方について、懊悩している様子を読まされる。厳格さのイメージがあった物理学だけど、実情はそういうわけでもないみたい。
1投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。科学者による現在の科学的手法への批判、特にバイアスについて語られていた。自分のような部外者の科学解説書好きではなく、科学者に向けて書かれているのだろう。
1投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現状の物理学のコミュニティは、ある意味では不健全な状態にあると言える。検証不可能なスケールの理論は指導原理を美しさに求め、パラメータの精密な調整を嫌うかと思えば人間原理によって目を逸らし、流行りに飛びつき目先の同僚の評価を気にする。それぞれの選択は大局的に見れば本当にベストな科学的進歩の方法であるとは言い切れない。物理学者は、それぞれがもう少し広い視野で学問に臨むべきである――大まかな中身はこんなところでしょうか。 主張をつぶさに理解するのは非常に難しいと感じました。ともすれば物理学者が視野狭窄に陥った的外れな行動ばかりの人種だと勘違いされかねません。この本は単なる物理学者批判の本ではないように思えます。筆者のホッセンフェルダーも物理学者ですから、彼らに選択肢がほとんどないことを分かっています。筆者は物理学者が盲信に陥らないよう警告すべくこの本を書いたわけですが、その立場は非常に中立的です。
2投稿日: 2021.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルは科学となっているが、物理学、それもほとんど素粒子物理学についての記述である。原題はちゃんとPHYSICSとなっている。物理学の一ファンとしての感想。とくに素粒子を研究している物理学者たちはあせっているようだ。多額の税金をつぎ込んで、大型のプロジェクトで実験を進めているが、思わしい結果は出てこない。理論通りに行かない。もっとエネルギーを大きくしないといけない。もっとお金をつぎ込まないといけない。ここまで進めてきたのだ。ここで引き下がるわけにはいかない。どこかの国のスポーツの祭典と同じ構造だ。人間が抱えるさまざまなバイアス。それが必ずしも悪いとは思はないが、気をつけないといけない。「物理学は数学ではない。物理学は、自然を記述すべき数学を正しく選択する学問なのである。」本当だろうか。すでにある数学から選択するというのではなく、自然を記述するために適切な数学を作っているとは考えられないだろうか。どうして、自然は数学で記述できるのか。それは、数学をそういうふうに作り上げてきたからなのではないのか。というか、物理学と数学はそれぞれ影響し合いながら進展してきたと考えればいいのか。ところで、著者は女性のようだ。どうも私にも強いジェンダー・バイアスがはたらいているみたいだ。ずっと著者は男性と思い込んでいたので、会話文の語尾でときどき女っぽい表現があり、違和感があった(ここにもバイアスがある)。私が所属した物理学科は40名中女性3名。数学科や化学科、生物学科は3割近く女性だったと思う。うらやましかった。もっとも地質鉱物学科(略してチコウ、なんと嫌なネーミング)は0名。そんなところで勝った負けたではないのだけれど。そういえば理学部の教官に女性はいたのだろうか。一般教養の哲学と心理学とフランス語くらいは女性だったと思うが。それから、どうでもいいことだが、インタビューの記述に当たって「」が使われているが、始めの「はあるのに、終わりの」がないところが多く、なんか気になった。こういう書き方があるのだろうか。それともう一つ、ワインバーグはまだ健在だったのか(88歳のようだなあ)。久々のみすず、図書館に購入してもらいました。その後、亡くなったという新聞報道があった。残念です。
2投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ随分昔に「ストリング理論は科学か」という本を読みました。本書のテーマはこれと同じです。実験で検証できない物理学は科学ではないということです。一般相対性理論を構築したアインシュタイン、相対論的な量子力学を記述する方程式を考案したディラックは、物理学における数学的な美の重要性を強調しました。物理学は自然法則を解明する学問です。ある理論が正しいのか間違っているのかを判断するには実験するしかありません。しかし、現在の素粒子論で主流となっている超弦理論は実験による検証ができない学問です。実験による検証の代わりに使われているのが、数学的に美しいか否かという基準です。アインシュタインやディラックの時代はそれで成功したけれど、これからもそれで成功する根拠はありません。自然は「数学的な美」を選択するという考えは研究者の願望に過ぎません。というお話です。現在の一流の超弦理論研究者はこの本を読んでどんな感想を持つんだろうか。まあ読まないよね。これから理論物理を志すひとは物性や量子コンピュータのような実験で検証できる分野をおすすめします。
1投稿日: 2021.04.29
