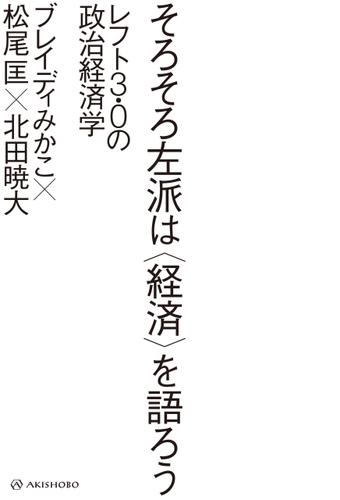
総合評価
(37件)| 9 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年か前に一部界隈で話題になっていた。なんかヒントが得られるかなと思って読んでみたが、結論から言うと全然期待外れだった。 アベノミクスの積極財政の考え方を、ヨーロッパの左派運動の政策も参考に、日本の左派も取り入れて独自の積極経済政策をもとう、という趣旨の本だが、アベノミクスの「異次元緩和」についての具体的な分析もなく、日本の財政経済の歴史的な分析もない。非常にうすっぺらな議論。経済思想の表面のうすい膜だけすくい上げて、妙に多くの修飾語をつけて文章にしたという感じ。反面教師にはなるかもしれないが。 ただ、ブレイディみかこ氏のイギリスのリアルな状況の紹介は非常に参考になった。排外主義や極右が台頭してくる社会的背景があること、それを生の対話でリアルにつかんで政策化すること(snsではなく)、愚民論は反民主主義的であること(これは北田氏)、など。
0投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ《借金を踏み倒せ!》という章にもあるように、根本的に将来世代のことを考えていない全く持ってダメなタイプの本。本書では入念に議論が重ねられた「財政出動」を結局再評価するというスタンスを取っており、左派の書物としては面白いが、主義主張としては甘受し難い。もう少し学術的な内容かと思って期待した読んだ私が馬鹿だった。「取り残されている人びとがいないように、みんなで一緒に健康的に成長しましょう」という観点からコービノミクスを評価しているが、そんな平均化された成長がダメだったことは中国やロシアの共産主義のゆく果てを見れば明らかではないか。 この本は、要するに自分たちの言葉が何から発されたものであるのか、という観点からの厳粛さがない。本書の「借金なんか踏み倒せ!」という観点から国債を発行することを推奨し、財政出動へと持っていこうとする提言は、自分のいる文化的な土壌や、読んだ書物の数々に対するリスペクトに欠けた、空虚なものに聞こえる。これでは、知識人としての尊厳はかけらもない。左派がこれでは、もはや貨幣は信頼できない。ビットコインなどの実体のない仮想通貨に、人々がすがりつく理由がよくわかる。 みんなで成長することはできないから、成長できる人から順番に成長しましょうという、鄧小平の方がずっとまともなことを言っている。少なくとも私はそう感じる。 知識人が返す当てのない借金を始めたら、要注意だということがよくわかる。とりわけ私のような奨学金債務者にとって、借金なんか踏み倒せ! なんてのは、債務のない自由な立ち位置を与えられた彼らにしかできない、羨むべきものだった。 ただし、本稿にて触れられているブレイディみかこの指摘は興味深いものがある。例えば、「EU離脱の投票で離脱派に投票した人たちは、現状をなんとかしなくてはいけないと思っていたが、決して排他的ではなかった」という点など。話者が各々の専門領域について語っている内容は面白く読める。北田さんは社会学についてはやはり詳しいし、松尾さんもマルクス経済学の人としてみると面白い発言もある。内容は全体としては同意できないけれども。
0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本で語られていることの重大さに、今更ながらに気づく、というか、刊行当時に読んでおくべきだったと強く思った。今現在も尚、不況にあえぐ日本にとって、どこか変換点だったのかがよく分かるし、左派に対して何が足りないのか、もっと言えば民主党政権時代に、何が圧倒的に欠如していたのかがよく理解できた。刊行から年数は経っているし、世界情勢は今まさに大きく変動している中、今の日本に必要な経済に対する考え方が詰まっている。左派はあまりに経済に対して無頓着であったかを自らを含めて痛感させられた。
0投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ先の選挙で国民民主が議席を伸ばした意味が分かった気がする。最近はギルティトゥアソシエーションも酷く、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いも大概にして欲しい。
0投稿日: 2024.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2018/7/11) ブレイディみかこ 松尾匡 北田暁大 左派による反緊縮政策を!がテーマの本。 保守、リベラル、右派、左派という言葉の定義が、 今の政治家の振る舞いの中で意味不明になりつつある。 保守本流を名乗る安倍政権の金融緩和政策が実はリベラル的だったりしているのがその証左。 と言って安倍さんにリベラルな気持ちなど全くなく、 ただ、国民受けする政策をして支持率を上げて、悲願の憲法改正がしたいだけ。 自民党のその他の有力者は皆財政均衡、消費税増税派。 田中角栄時代の自民党はもうないのだ。 だからこそこの本は問う。 今こそ左派は反緊縮政策を掲げ、現政権を倒せと。 政治は経済だ。 私は、今は諸悪の根源のように語られることの多いミルトン・フリードマンの理論の信仰者。 彼の理論を「新自由主義」とすることには違和感はある。 大きな政府、国民から税金を集め恣意的に使う、というやり方に反対、 というのは正論だと思う。今でも思う。 そんな大金の投資先を、正しい判断が出来る人なんていないだろうと。 その点、消費税増税はある意味大きな政府につながるわけで、 フリードマンがたたかれるのもそういうことか? ベーシックインカムはありだと思う。 よくよく考えれば、民主党の子供手当は、ある意味子供へのベーシックインカムだったのではないか。 これを国民全員に広げる。 財源は? 日銀が刷る。 それで行けるのではないか。 ハイパーインフレが怖い? 貯金している人が怖いだけ。持たない人は怖くない。 そもそも今の財政不均衡とやらも、実は不均衡ではないのだ。 金持ちの貯金が銀行を経由して国債となって日銀に買われているのだから。 貯金という生きていないお金が借金の形を取って生きるのだ。 そもそも経済でこれが正しい、なんてことはない。 昔は金本位制が正だった。今誰もそんなこと言わない。 今や国の保証さえいらない、という仮想通貨が出回っている。 要はものが、役務が動けばいいのだ。 老人が老後の心配にとっておいている金を市場にださせればいい、と「心理経済学」で 大前研一氏が言っていたが、まさにそうだ。 お金、なんてなんでもないのだ。 皆が人の役に立てば、世の中は回る。 そういう世の中を作らなきゃ。 老人が自分の財産にしがみついて若者を犠牲にする社会に未来はない。 老後の備えの財産が1800兆?国民一人当たり1500万? 信じられん。 第1章:下部構造を忘れた左翼 第2章:「古くて新しい」お金と階級の話 補論1:来るべきレフト3.0に向けて 第3章:左と右からの反緊縮の波 第4章:万国のプロレタリアートは団結せよ! 補論2:新自由主義からケインズ、そしてマルクスへ
0投稿日: 2024.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログp80 労働党の方ではブレクジットを選挙戦の争点にしなかった。むしろブレッド&バターイシュー(どうやって飯を食うか問題)と呼ばれる国内問題を争点にしました。そして、その戦略が見事にあたった p85 労働者にとっての離脱は、文化的な動機(移民への不満)よりも経済的な動機(生活への不安)が大きかった
0投稿日: 2023.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 今の野党に経済政策を仕込むより現政権に社会保障制度を手厚くさせるほうがハードル低いような気がする。保守支持層も読むべき。 2023年4月現在の物価高が始まっている環境でどこまで緩和政策が続けられるのか、緊縮が始まったタイミングが野党の攻め時。
0投稿日: 2023.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
このままの世の中でいいとは思っていない。しかし、共産主義はもちろん、社会主義も決して受け皿にはなり得ないとも感じている。なぜならば、この本の帯にあるように、左派は経済を回すことを考えの範疇に入れていないからだ。結局資本主義経済に寄生することを前提に理想論を叫んでいる。まるで社会的な中二病だ。(ついでに言うと国防においても同じことが言える) そんな「左派」が経済のことを考えたそうだ。読んでみたが、やはり堂々巡りから抜けられないようだ。本当に困ったものだ。
0投稿日: 2023.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「左派」論者3名による経済政策論かつリベラル批判の対談書。日本のリベラル派を、経済成長政策を疎かにしてきたと批判し、文化的・制度的な面での公正性を重んじるだけでなく、「明日どうやって飯を食っていくか」に直結する経済政策もちゃんと考えろと指摘している。この本を読むことで、リベラルを自称し人権を重視し・・・と考えている人が、自分の視野の狭さに気付かされるかもしれない。僕はそうだった。 対談の著者は三名。①『僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で有名なイギリス在住の文筆家、ブレイディみかこ。②マルクス経済学を専門にする立命館大学の経済学教授、松尾匡。③理論社会学でメディア史を専門にする東大大学院教授、北田暁大。戦後史、経済理論史、時事問題(ブレグジット、ギリシャ危機など)を幅広く取り上げつつ丁寧に説明しており、我々はどこからきて、今どこにいるのか、そして今後どこへゆくのかの文脈について、整理することができる。面白い。 また、この本を読んで感じたのは、経済政策を評価(立案・投票などすべて)するとき、私たちはどんな社会(国)作りがしたいのかをそもそも考える必要があるということ。 税金の使い道についても、税の累進性の政策の是非についても、結局何がしたいのかの目的に紐づけて、メリデメを評価する必要がある。 ついては、日本にそういった明確なビジョンがあるだろうかと思うと、色んな政治家がビジョンを出していることにようやく気づく。また様々な政策研究会議においてビジョンらしきものが提示されている。 「株式会社ニッポン」があるとしたら、世界市場でどんなポジションで、どういうミッション・ビジョン・バリューを持ってやっていこうとしているのか、もっと明確に理解していきたい、、、 本書が重要だと思えるのは、現実主義的な語り口だからだ。ライツ・トーク(rights talk)と呼ばれる、人権をベースとするリベラリズムの考え方(とくに、rights as a trump *人権の切り札性)の理想主義的な部分を認め、それだけで物事を判断しきれない、また政策として不十分な部分を解消するために、適切な経済成長や、適切な財政出動を推奨しているからだ。 一方で政策論はそれとして、その政策を実現するためには民意を動かしていく必要があるが、その民意が分断されている(=ソーシャルアパルトヘイトの)現状で、どう人々が交わっていくかについては、この本のスコープではカバーされていない。「リベラル」な自分が本当のところ「左派」になれないのは、この分断を作っている一員だからだと感じるが、これを乗り越えるために何ができるのか、強い課題意識を持った。
1投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時はよくわかっていなかったのだけど、野田政権の消費税増税、緊縮によって民主党政権に対してかなり悪いイメージがついたのだろう、とわかってきて、どうやって自公政権を倒せるのか考えていてたどり着いた本。 安倍政権は、改憲のために国民の機嫌取りの経済政策に力を入れた、というのをみて自民は上手いなあと思う。 難しい部分もあったので、また歴史なども勉強して読み直したい。
1投稿日: 2021.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「経済成長」という言葉がさしている意味が2種類あるということ、「アベノミクス」の第1と第2の矢という政策が反緊縮財政だったということ、金融緩和と金融市場の規制緩和を勘違いしている人がいるということ、ポピュリズムとポピュラリズムを勘違いしている人がいるということなどなど、これらすべてを知らず、勘違いしていたのが自分だったのか~…っていうことが分かった(ような気がした)。 また、「国の借金のせいで国民が苦しんでるならその借金を踏み倒せ!」という立場も分からなくはないが正直、「ちょっと過激だな」と思っていた。そこへ「インフレが進んだ時に民間に売ったり、借り換えを停止したりする一部の国債だけ返済が必要だ」という1文が付け加えられているのを初めてみたような気がして、安心したような、自分の中に勝手な落としどころが見つかったような気になった。 まだまだ分からないことが多いけど、とても興味深く読めました。
0投稿日: 2021.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ岸田内閣が発足し総選挙が行われることになった。岸田内閣に期待すること、あるいは、衆院選の論点として考えるべきこと、という内容で、日本経済新聞が朝刊に連載をしているが、今日の朝刊のテーマは「成長か分配か。まずは成長を優先すべき」という内容のものであった。 本書は、ブレイディみかこさんと、経済学者の松尾匡氏、社会学者の北田暁大氏の対談で構成されている。発行は2018年5月のことなので、今から3.5年前のことであり、岸田内閣はもとより、菅首相の前の安倍首相、経済政策で言えばアベノミックス時代の発行である。 本書の大きなテーマの一つは、書名にもなっているが、日本の左翼・左派に対して疑問を呈する、というものである。 経済だけが大事なことでないことは言うまでもなく、経済以外にも大事なことは山積していることも言うまでもない。ただ、私は、経済問題は現代の日本の大きな問題の一つだと思う。格差問題、あるいは、日本にも貧困層が生まれており、その格差や貧困は世代間で受け継がれる、要するに固定化・階級化しつつある、ということは、かなり以前から指摘されており、解決すべき政治的イッシューであるはずだ。 この問題へのアプローチには2つある。1つは経済成長が大事だとするもの。日本の1人当たりGDPはバブル崩壊以降、ほとんど増えておらず、今やそれを指標とすれば、日本は既に世界で最も豊かな国の一つとは言えなくなっている。これは事実であり、日本全体が豊かにならない限り、国民に所得として行き渡る原資はないのだから、まずは経済成長を優先させようとするアプローチ。冒頭に記した今朝の日経新聞の論調である。 もう1つのアプローチは、分配が大事だとするもの。格差があるのであれば、格差を均せば良いではないか、というアプローチである。富裕層への課税を強化したり、あるいは、大企業への課税を強化し、そこで得た原資を、例えば医療費や介護費や貧困世帯への援助に回そうとするものである。 本書でのブレイディさんをはじめとする3人の方が感じている違和感は、日本の左派が「経済」について語らないということである。日本の左派は、例えば環境問題、原発問題、等についての主張が多く、そのこと自体は何の問題もないのだけれども、日本の大きな問題の一つである「経済問題」、特に、如何に日本の経済を成長させるかについては、ほぼ語るところがない。なかんずく、不況時の重要な経済政策の一つである政府支出について、国の財政均衡(要するに国の借金は良くないことなので、単年度の国の税収と支出をバランスさせましょうという考え方。政府支出を減らすことは、GDPを減らすことに繋がる)を優先させる考えを左派がとる(民主党政権時代の「事業仕分け」は皆さん記憶に新しいと思う)のは、ほとんどあきれるという内容である。 「成長か分配か」という、ものの考え方では何も解決できない。正しくは、「成長も分配も」であると私は思うし、本書の主張も同じ。日本の左派が「分配」については語るが「成長」について語らないのは、政治家としての一種の責任放棄ではないか、と私も思う。 本書の主張に同感だ。
18投稿日: 2021.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「年収1000万円以下所得税免除」「消費税5%」=某野党の公約。本書が出された2018年からは大きな進歩。しかし、「プライマリーバランス」は”凍結”で、「消費減税」は時限的。両方とも廃止でよいではないか?英国でも労働党ブレア政権が緊縮だったが、現党首コービンは反緊縮で票を伸ばした。他の欧州各国も似たような動き。レフト2.0から3.0への進化とされる。米国で労働者の票を逃したクリントンに学んだバイデン政権。安倍一強に学べない野党。理想の啓蒙よりも目の前の暮らし。まだまだ本書に手にして欲しい左派がいる。
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと難しかった。拾い読み。 ブレイディ:左派とは本来、社会構造の下敷きになっている人々の側につくものであり、不公平は不可避だという考え方を否定するものではなかったか。 ハニス・バルファキス「誰もがきちんと経済について語ることができるようにするということは、善き社会の必須条件であり、真のデモクラシーの前提条件だ」これがトランプや極右政党台頭の時代に対する左派からのたった一つの有効なアンサーであると確信する。この対談は二人の学者から多くの貴重なことを教えていただいた時間の記録だった。 左派の人がイデオロギーばかり唱え経済にあまり言及しないのに違和感を持っている。育った家庭が経済的に苦しく、高校は遠方で中学を出たら働けという母に対し、定期代は自分で出すから行かせてといった高校。アルバイトをすると、今時定期代も出せない家は無い、と担任に言われる。そういう経緯から、まずは経済だ、という考えを持つブレイデイ氏。 北田:きっと担任は本当に嘘をつかれていると思ったんでしょう。背景の生活感が大切。 ブレイデイ:その時に私はUKの音楽を聞いて(15歳だと1980年)「ワーキングクラス」というのが英国にはあるらしい、わたしもワーキングクラスなんだって思った。それでいつか本当にワーキングクラスのいる国に行こうって決めた。 保育士になる前にはロンドンでフリーの翻訳をやりその時投資・金融関係の翻訳をけっこうやったという。英語の日本語訳も適切な語で訳す必要があるという。 もはや「右」対「左」の時代ではなく、今は「下」対「上」の時代。「移民や難民を受け入れる多様な社会政策というものは、緊縮とは絶対に両立しない」(ヤフーニュース・2015.9.7 欧州の移民危機:人道主義と緊縮のミスマッチとする文を書いた) あとがきにかえて 松尾匡:経済学者:日本に左派の反緊縮運動を! 北田暁大:社会学者:ソシャル・リベラリズムの構築に向けて 日本語訳は何? 2018.5.1第1版第1刷 図書館 2018.6.3NHKAM著者からの手紙 2018.6.16当初登録
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
左派と呼ばれる人たちは人権問題や環境問題等は取り上げるが、経済問題に真剣に取り組んできていなかったが、今政治の実権を握っている人たちに対抗して人間らしい暮らしをみんながしていけるためには、これからの暮らしを経済の観点からどう変えていくのかを語らないと人心を掴むことはできないということを語った本。 北田さんと松尾さんの話が高度すぎてたまについていけなくなるんだけど、ブレイディさんが庶民的な目線で理解したことを話してくれるので助かった。 ここでいう左派というのは平等主義とか平和主義とかではなく、稼いだものをきちんと分配して、働いたらきちんと食べていける世の中を作ろうと言っているにすぎないというのも大切なんだと思う。 現代の奴隷制度みたいなものを作り出し、脱税しまくってる企業が闊歩する世の中は、やはりどこかねじ曲がっているように感じるので、それを是正できるのは行政なのではないかと。
0投稿日: 2021.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「理念だなんだと言っても、世界を回しているのはやっぱり経済だな」とブレイディ氏は実感するわけだが、この本が出た2018年当時には想像すらつかないオリンピックイヤーのコロナ禍にあってもやはり経済を回すしかないんだ、と実感している遅れてきた一読者。日本の左派は下部構造(経済)に目を向けないからダメだとあるが、上部構造(政治・法律)はどうかといったら、当時のモリカケ騒動ごときでアベ極右政権が潰れるぞ(あとがき)と妄想しているようではこっちもダメだね。
0投稿日: 2021.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリス在住ライターのブレイディみかこ、経済学者の松尾匡、社会学者の北田暁大の3名による鼎談本。 ブレイディさんのヨーロッパ政治経済の知識と、松尾さんの経済学をベースに、北田さんが整理している感じ。「アベノミクス憎し」で経済政策が混迷している左派に警鐘を鳴らしている。 第二次安部政権のアベノミクスのうち、金融緩和はデフレ経済では当然の政策で批判されるものではないのだが、左派はアベノミクスに反対せざるを得ないので賛成できないという奇妙な立場にあった。 続けて財政出動も、脱デフレを目指す雇用創出のための妥当な政策だった。 これらは小泉政権の新自由主義ではなく、むしろ逆に左派的な経済政策なのだが、安部首相が主導しているせいで左派はなぜか逆にこれを批判する形になった。 アベノミクスで批判されるべきは財政出動が選挙前に限られていたことや、規制緩和は金融緩和・財政出動と関係がなく、場合によっては矛盾することにあり、左派は本来「もっと財政出動しろ」と言うべきだった、というのが本書の主張。 安部首相がこのように左派的な経済政策をとった裏には支持を得て改憲など「本当にやりたいこと」をやるための下地作りがあったと思われ、これは一定以上に成功したが、改憲などに移る前に、森友・加計問題や「桜を見る会」などのお友達優遇や支持率は下がり、そこに新型コロナウイルス対策も重なり体調不良により辞任し、菅政権となった。 菅政権は、安部政権以上に権力を好き放題に振るう一方、経済政策は方向性が全く見えないため、左派にとっては有利な状況と言える。 しかし本書に従えば、野党は相変わらず不祥事の追及などに終止していて、アベノミクスのような「期待を持たせる経済政策」を打ち出さない限り、積極的な支持を得ることは難しいだろう。
1投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ鼎談形式ではあるが、内容はかなり高度。それだけに議論が錯綜し、わかりづらい印象がある。しかし、本書の主張は一貫しており、左派(リベラル)も反緊縮経済政策を訴えよう、というのもである。日本の左派は、人権などの問題と経済とを別問題と考える傾向がある。それをあらためようという主張。社会福祉へ財政を投入すればそれが雇用を創出し、経済も活性化する。要は経済の舵の切り方を右派と違う方向に切ることで、経済を発展させ、かつ福祉も充実させようというとする試み。魅力的な考え方ではあるが、はたして本当に債務超過に陥っている日本で、財政出動を積極的に続けることができるのか、不安がぬぐえない。もっと、勉強をしないといけないと思わせる1冊である。
2投稿日: 2021.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからは左派も経済について語ろうというお話。現在の左翼の凋落は経済無策が招いたことの反省です。ここで語られる経済政策は、右派である私にとっても違和感のないものです。というか、現在のデフレ下では当然の政策ばかりです。驚いたのは欧州では反緊縮が左派(リベラル)の専売特許になっていることでした。日本では右派と目されている経済学者が反緊縮を主張してますね。マルクスとケインズがつながるという解説は目新しかったです。経済政策については著者たちに合意できるけど、その以上の思想はやはり私とは違うなあと思いました。この本はコロナ禍以前に出版されたものです。今は、さらに反緊縮が必要な時期です。
0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ英国在住のライター・コラムニストブレイディみかこと、慶座学者の松尾匡、社会学者の北田暁大による、左派視点での経済談義。 本書を読むまでは、緊縮財政はしょうがないよね~、プライマリーバランスは大事だよね~、などをうすぼんやりと信じていたが、本書を読んでそれらが必ずしも正しくないことを知った。 学者2名の知識量が膨大なため、ときどき言っていることについていけなくなったが、それを差し引いても再分配と経済成長は対立しない、や左派、右派という視点だけでなく、上か下かのの視点を忘れてはいけない、等の提言は非常に腹落ちした。 本書の著者たちと、右派経済の論客の人たちで討論し、それぞれの主張とそれらに対する反論をまとめてみたら日本の経済のこれからの指針になるように思うので、ぜひどこかの出版社が企画、出版してくれないかな~。
2投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020/12/15:読了 本が厚い分だけ、話が細かくなりすぎて、読みにくかった。 「左派・リベラル派が勝つための経済政策作戦会議」のほが、面白かった。たぶん、話がまとまっって、読みやすかったんだと思う。
0投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済、つまりどうやって食べていくか、がまず大事なことなのだということを考えさせてくれる。グラスルーツとか地べたというけどさ、理念うんぬんよりもまず食べていく不安をどうするのか。ナチスが支持率では決して高いわけじゃなかったにもかかわらず、強くなったのは、食べていくことへの不安になんとかしてくれるという信頼を勝ち得たからだ、という。そしてそれは現代においても、見られる話でね。 右とか左とかわかんないけど、面白かったな。自分が右か左かなんて、わかんないし、どうでもいい。ただ、生活していかなくてはいけない以上、いろいろ考えることは必要だよな。 ふだん見過ごされているような人たちに対して、何を求めているのかを聞いていくことが出発点になるんだ、というのは政治にかぎらず、あらゆる仕事、社会的な存在にとって必要なことだと思った。日本企業の凋落なんて、消費者は何を求めているのか、そこを忘れたからだよね、なんてさ。もちろん、自分自身にも言える話かもしんないんだけど。
2投稿日: 2020.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済が重要だということはわかった。ヨーロッパの現況もわかった。 だが、レフト1.0だとか2.0だとかはどうでもいい。オタクの言葉遊びだ。
1投稿日: 2020.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログいずれ読み返したくなるような、素晴らしい内容。 結局みんな自分の生活が1番大切なんだよ!っていう当たり前のことなんだけど、きちんとそれを説明してもらった感覚で、とても勉強になりました。
0投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ超面白い。 流行った消費社会論が経済の方向に行かずにアイデンティティ論に終始したというのは本当にその通りだと思う。 まだわからない部分が大きいけども、経済に興味が出てきた。
1投稿日: 2019.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ『「反緊縮!」宣言』に先立つ、松尾匡らの鼎談。 ヨーロッパの動向も理解できて興味深いものだった。 チャブの本も違う文脈で読んでいたのだが、本書の文脈につながって意味が広がった。 反緊縮を掲げる極右の台頭を招く前に、未来への投資を正しく行い、需要不足による不況を打破し、できる政権を確立したい。手遅れ感を感じもするが。
0投稿日: 2019.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ反緊縮政策の有効性や左派の思想史などについて学べる本。 ・左派の立場から、勢力を盛り返すために現在の安部政権を上回る経済政策を提案しなければだめだ。そのためには、いままでのような緊縮ではなく、反緊縮政策を提案し、福祉などしかるべきところに再配分をしっかりと行うべきだ。 ・WWⅡ前後の左派の歴史を整理、レフトの思想が歩んできた歴史とその総括について。労働者の味方だった左派が、下層の人々を忘れ多様性に焦点を絞るようになってしまったこと。 ・メリトクラシー(能力主義)が勃興した結果、下層の人々に対する差別が生まれたこと。「能力が無いのは自己責任」。グローバリズムについていけない人たちが新たな差別階級になった。英国ではチャブ。日本ではマイルドヤンキーやB層。また、そうした状況の中で下層の人々が社会の中で取り残されていること。 現在の世界での潮流。トランプ大統領やジェレミー・コービン氏、安部首相がなぜ支持されているのか。という説明を非常にわかりやすくしている本だと思う。「緊縮政策で国内経済がボロボロになり、上下構造や明日の飯を食えるかというのが大きな関心になっていたところに、大々的に財政出動を主張する政党や政治家が現れ支持された」という説明は非常にわかりやすいものだったし、最近見たヨーロッパ情勢の本を読んで得られた実感とも重なる。ギリシャ危機に対する、ドイツやeuの掲げる経済政策への不信とかね。 ただ、本書のコンセプト自体が左派の復権を目指したものというか。右派の否定でもある気がしたので、モヤモヤするところもあった。左派・右派という二項対立に陥ってしまっている気がする。「効果のある経済政策を行い、右派から支持層をもぎ取ろうみたいな」。 右派の極致はナチスかもしれないが、左派の極致はソ連や中国共産党やグローバリズムの中で多様性を認めることを強制される社会だと思う。良い部分と悪い部分がお互いにある。 階級による差別はいかんという意見には完全に同意するし、そこに目がいくのはやはり左派の人たちだろうなと思うからこそ。 イデオロギーは違う価値観を持つ世界みたいな。自分がそこに属していたら、その世界と相手の世界を分けてしまうみたいな。政治思想を理解するにはイデオロギーを理解しなければいけないけれど、そうなるとイデオロギーによって自分と意見の違う相手を分かつことになる。「こちら側とあっち側」が出来上がる。レッテル貼りも生まれる。それぞれのいいところを理解するための邪魔になっている気がする。 囚われてしまうと、政策は結局のところ「相手を倒す道具」になってしまう。そこを乗り越えて、みんなを幸せにするためにはどうしたらいいのかを必死に考えることが一人一人に求められていく視点だと感じた。理想論だけれども。
0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「リベラルは自由や平等や人権を訴える金持ち。レフトは自由と平等と人権を求める貧乏人」とは著者の一人の英国人の夫が息子に言った言葉らしいが、支配層であるリベラルの意識がレフトから乖離し、経済成長に気を配らなくなったことが特に欧州の経済停滞の原因だというのが、著者たちの共通認識だ。 経済政策を初め、安倍政権の政策に理由も示さず否定的コメントをするところはいかがかと思うが、それ以外は、欧州の実例を踏まえつつ、経済政策の変遷をまとめていて、参考になるし、ブレグジットやトランプ支持の背景がよくわかる。
0投稿日: 2018.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ3人の論者が「反緊縮派」という立場から日本の取るべき経済政策について、議論した本。現代政治経に関心はあるけど知識がない私にとっては格好の入門書だった。現代の国際政治では何が起きているのか、旧民主党系のどこが問題なのか、安倍政権の長期化の要因とその問題とは何か、など現代政治の様々な問題について経済政策の観点から一定の見識が得られるし、彼ら「反緊縮派」の主張には説得力もある。ただし、現代政治経済の入門になるとはいっても著者たちの議論が、「反緊縮派」という特定の政治的立場に立ったものであることには注意が必要ではある。いずれにしても、この本は現代政治に関心のある人に真っ先に勧めたい良書である。
0投稿日: 2018.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「無駄遣いヤメろ」も良いんだけど,それしか言うことないのかよ⁈ どうやったら豊かになれるのか,明日のメシにも困り,1年後の身分保障もままならない不安から抜け出せるのか⁈ 何でそれを大声で言わないんだよ⁈ 観念的な綺麗事ばっかり並べてんじゃねーよ! って思うから,左派は信じられないんだ〜って,ずーっと思ってきた. この本には,左派がそこから脱却するヒントが溢れていると思う.今までの左派の歩みに対する論評もなるほどと膝を打つものばかり. 願わくば,同じ内容で右派,特に虐げられてるにもかかわらず,安倍政権を熱烈に支持しているような人達が手に取るようなタイトルと切り口で再編して出版して欲しい.
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ野党の経済政策のなさや、成長が欠落していることに違和感がある人にはおすすめ。モヤモヤが無くなった。対話式だが読みやすい。章によって段組がバラバラなのが玉に瑕。
0投稿日: 2018.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログレフト3.0…いい響きだ(^-^) 小生もリベラルではなく、レフトを名乗ろう(^o^)/ もっと早く本書を読んでおけば良かった、と後悔。対談形式なので、分かりやすい、けど難しい議論もあり、という感じで、ボブの知的好奇心をくすぐってくれる。 経済学の再々々勉強をしなくては…と考えるわけだが…(^^;;
0投稿日: 2018.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
《Summary》 大雑把にいうと左派による左派自省の書。 現在の左派(日本でいうと旧民主党系・共産党系)は、経済について語られることなく、イデオロギーの戦いに終始しているということを、左派自身で反省し改善するための方策を中心に記載している。 面白いのは下記の4極の差異と比較を通じて、日本の左派として取るべき道を記載している。 ①. ブレグジットに揺れ動くUK ②. ドイツを中心とした緊縮財政のEU ③. 極右/立つグローバルに舵を切ったUS ④. 右派的な政治スタンスを取りつつ金融緩和を続けるJP 結論としては、右派左派というイデオロギーで思考を分断するのではなく、"経済"を物事の中心に据え置いて政治的な判断を行うことが良いと(まぁ当たり前のことを延々語っていたが) ケインズ経済学/新古典経済学を軸に記載しているので、割と理解しやすい内容かなと。 《Topic》 面白いのは、著者は左派だけど、左派のダメなところを指摘すると、左派の周りの方々から右派扱いされる…という、面白い現象が起きている。 回り回って、左派的な人が、「現政権は良いんじゃね?」という事を立証してしまっている事が、読んでいて面白かった。 《Forecast》 ただ、イデオロギーに関係なく日本の経済状況は、東京オリンピックを境に冷え込むことは見えているとの事。数年後を見越して準備しておいたほうがいい。
0投稿日: 2018.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
専門の異なる3氏の鼎談で、主に欧州の政治、社会から日本のそれを分析しつつ、「左派」に対する提言が行われています。以下、要約です。 <ネタバレあり> 若者をして「『ビッグになろう』と考えたらあかんのかな」と言わしめる左派主導の脱成長的な風潮。左派はアイデンティティポリティクスや文化の問題に耽溺し、「下部構造」を忘れてしまったのではないか。 一方、欧州ではドイツあるいはECB主導の緊縮政策に対し反緊縮(緩和的な金融政策と積極的な財政支出)を唱える左派(一部右派)が勃興。例えば英国では、2015年に労働党党首として強硬左派、”オールド・レイバー”のコービン党首が選出され、2年後の総選挙で善戦。かかる左派は、第2次大戦直後に勃興し70年代に行き詰まった”レフト1.0”、その反省の上に立ち90年代に隆盛を迎えるも貧困に対処できなかった”レフト2.0”の思想を乗り越える、”レフト3.0”と言えるもの。 ”レフト3.0”は、”レフト2.0”がもたらしたマイノリティによる多数派の抑圧から脱し、”労働者”全体を復権させることを目指し、金融緩和と”大きな政府”(財政出動)を通じた経済成長、雇用拡大がその政策の目玉となる。一周して”レフト1.0”に戻った感もあるが、現代的にジェンダーやマイノリティの問題も取り込んでいるもの。 このような欧州の状況を踏まえると、日本はどう評価されるか。まずアベノミクスについて。3氏は、アベノミクス≠ネオリベ政策と評価する。金融緩和と財政支出の組み合わせであるから。これに対し左派は緊縮主義的に批判する。欧州の状況と比べると”ねじれ”が存在。アベノミクスにも第2の矢=財政支出が不十分という問題があるが、(旧)民主党政権下と比べ明らかに安定している安倍政権下の経済を前にしては、「きちんとした経済政策を出していかないと、いつまでたっても有権者の支持を得ることはできない」(176ページ)。「『ご飯をたべたい』という、民衆として普通、当たり前の願いを拒否したり、侮蔑したりしていては、左派は信頼を得られない」(216ページ)。そのため「コンクリートから人へ」の実装、消費増税反対・反緊縮を訴えるべき。 (上記では端折っていますが、ブレイディみかこ氏のあげる欧州、特にイギリスの人の生き方、考え方の例がいちいち魅力的でした。是非入手してお読み下さい。) 以上が要約。経済政策だけ見れば3氏が左派に期待する理由は薄い訳ですが、そこはやはり”リベラル”(ただしこれも多義的)な社会を守るため、野党に期待せざるを得ない訳であります。 選挙を通じた民主主義政体を採っている以上、いつでも政権交代可能な緊張感のある状況が望ましいと思いますが、失業こそしなかったものの私も(旧)民主党政権下では経済的に苦労させられました。当時の主要メンバーが各所で生き残っている野党の状況をみると野党に票を投じることについては躊躇させられます。
0投稿日: 2018.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済運営で何とかいっている安倍政権。ただ、消費増税圧力に抗うことは難しく、東京五輪後の景気後退に対処できないとの予測は明快。では、対抗勢力は何をすべきなのか――という一考に値する内容。
0投稿日: 2018.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ左派が語るべき経済のあり方を学ぼうとすると期待外れ。そういう話題になると不思議と話がそれて、断片的にしか把握できない。対談本に書いてする必要があったかなーとも思う。対談をもとにもうすこしまとまりのある構成をとれたのではないか。反緊縮ってとこやケインズ的に需要を作り出すべきってあたりかな、せいぜい把握できたのは。需要が不足していたというのはアベノミクスによろしくという本でも学んでいたため、すとんと腹に落ちた。 左派が経済を語る必要性を啓蒙するための本としては、優れている。左派思想史としても鋭い分析が随所にある見られ、目を開かされる。過去の左派の思想へのツッコミは的確だし、新たな時代の左派像にも共感する。 地に足つけて金の話をしようや、という当たり前のことに改めて気づかせてくれる良書。
1投稿日: 2018.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、俺Leftだから、当然反緊縮だよ? 弱者だからこそ保護が必要だと思う側だ。 だから、この本でいうLeft1.0的なことを、この本で言う「日本型リベラル」が主張してないとも、ましてや緊縮を主張してるとも思ってないんだけど、 いわゆる「フツーの人たち」がLeftを批判している文脈が理解できたのは良かった。 Leftは緊縮を主張してると思われてるんだな。そりゃ排斥されるわ。 ぼくとしては「安倍政権はセイの法則だよりで、金融で反緊縮してるけど、効くわけがない。使う人間に直接分配しなきゃ、需要は喚起できない。成熟社会で、供給が需要を生む筈ないだろ?」ってこと また(若干の違和感はあるけど)右派は人々を左右に分けて区別し、Leftは上下に分けて区別をしてる。というのも、なんとなくわかった。 この本の主張は「もう安倍政権はこのまま完全雇用まで走り抜けるから、Leftは出る幕ないね」というもので、ぼくもトキすでに遅し。と覚悟せざるを得なかった。
0投稿日: 2018.05.09
