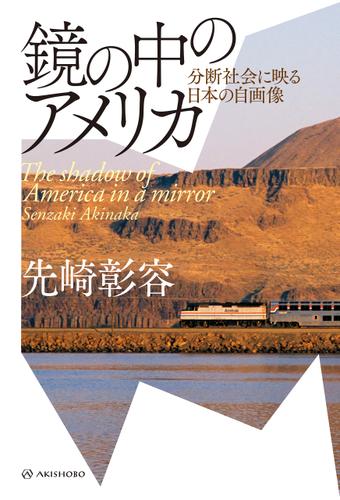
総合評価
(3件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ先崎彰容氏のアメリカ滞在記。40代、学者として見たアメリカ。金もある、プライドも地位も、語学力もある。だから事件は殆ど起こらない。大して出会いも無い。シナリオ通り準備してこなす講演。想定され、備えられた質疑。合理的な目的を持った行動。…そんな旅行記は楽しいだろうか。 日本を映す鏡のようだが、その光を少し自分に当てて考えてみる。いつからか予定調和に生きる人生は、著者にも私にも、抑揚と刺激を減らした分生きやすく、故に死に対し整合的に近接してくるようにも見える。40代の旅とはそんなものか。 目的もある。明治6年政変から征韓論争。これはアメリカを見たものと見てないものとの国家像をめぐる争いだった。岩倉使節団の足跡を辿ろうと、図書館や石碑を巡る。見て、考えて、歩く。 ー アメリカ人は自分の血の中を流れる出自とは何か、自分を構成する無言の蓄積とは一体どこにつながっているかっていうことに敏感。アメリカ人の大半がここに住んでいること自体が選択の産物であり自明ではない。日本人は、自らの出自を問う場面に出くわしにくい。 著者は考える。自分探しなんて無垢な理由ではなく、日本のアイデンティティについてだ。しかし、私は著者の目を通し、再び個人のアイデンティティについて、そして、この社会の縄張りについて考える。 外国語が上手に話せないのは、脳が幼少時の言語社会に合わせ機能選択したからだ。そのため、部外者を感知しやすく、集団は危険を退けた。大人になってから別の集団に馴染もうと勉強し言語を習得。それがどんなに流暢であっても微妙なアクセントで外国人だと分かる。言語だけではなく、思想にもそうした違和感は残る。アイデンティティは、その差で輪郭が定まるものだ。 理性的な年齢になり、大人しく生きてみても、気付くのは自らのミームや遺伝子レベル、いや脳機能レベルのバイアスだ。色の白黒を認め合う難しさと共に、この点が際立つ。若い頃の旅行では、それ以外の差やエピソードが起こり過ぎて気付きにくい。ならば偶には、大人の旅行記も良いかも知れない。そんな落ち着いた一冊だ。
57投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ青春気分を感じさせるエッセイです。明治に岩倉使節団がアメリカを訪ねた道程をノスタルジックに辿ったり、2、3の講演を含めたアメリカ旅行を好奇心旺盛に綴っています。中でも、アーリントン墓地に関する記述は気になりました。アメリカは現在も責任を持ってDNA鑑定を行った遺骨収集を続けているとあります。対して我が国のそれはあまりに杜撰で不誠実です。国家としてあまりに無責任で恥ずべき態度です。また、本文中、米国教授が、日本の左翼こそ民族主義的として、極東の現状を考えず情緒的な平和主義を主張することの非を指摘しているのは傾聴すべきです。また、かつて資本主義・議会制民主主義・国際秩序が揺らいだ時として、世界恐慌時をあげています。この混乱は第二次世界大戦の導火線となりました。今また、同じように3つの要素が揺らいでいます。人類は歴史から学べるのでしょうか。
15投稿日: 2022.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ表紙とサブタイトルから生じた、なんとなく小難しいのかな?などというイメージは全くの杞憂であった。とても正直な旅行記。岩倉使節団をトレースしていくような旅路で、過去が浮き上がってくるよう。 また、リアルに肌で感じる日本とアメリカの違い(戦争、銃など)に、やはり行ってその場の空気を吸わないとわからないことはあるなあ、と思う。
2投稿日: 2021.04.15
