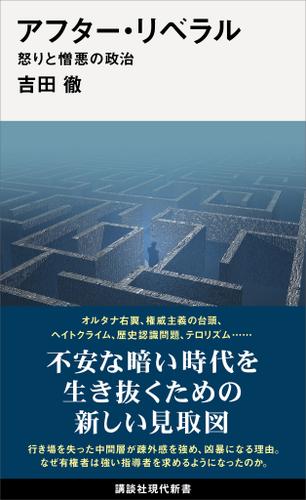
総合評価
(22件)| 7 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リベラルの後、というと、リベラルが終わった感があるけれど、 戦後リベラルの次、という内容、あるいは、Liberal one after anotherというような、 さまざなま角度からのリベラルがこれまで主流になったり合流したり、 つまり、個人の自由と社会の包摂のバランスがどのように取られたりぐずれたりしてきたかについて「リベラル」の変遷に焦点を当てて物語られているようでした。 個人の自由、解放、の思想、リベラル。 それにもいろいろあって、いろんなリベラルを唱える考え方が勃興してきたことが分かった。 この本は、2020年夏に出されていて、2010年代後半に西洋世界でもより勢いを増した権威主義的な世界情勢やテロといった出来事を切り口に、リベラルの歴史的な流れを紐解いています。 また、著者の議論は、関連の学術研究や統計も多々紹介され、それらの研究調査結の裏付けをもとに論じられていて、興味深かったです。
0投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新型コロナによるパンデミックを経験したこの世界では、権威主義的な政治が台頭し、リベラルな政治が後退した。人々が合理的になり、民族やナショナリズム、人種から解放され、グローバルな社会が実現し、社会の多様性や個人化が到来するはずだった時代に、なぜ怒りや敵意が政治の世界で繰り広げられるのか? 政治学者の吉田徹は、市民を有効に守れない国家の統治能力の脆弱性が白日のもとに晒されたことが原因のひとつだと指摘する。歴史認識問題とテロの脅威が浮上するのも、大戦後に成立した共同体や権力が崩壊しているからだという。 国民国家とは「記憶の共同体」だ 日本のいわゆる「自虐史観」を問題視する立場からは、日中戦争や太平洋戦争は必然だったことが喧伝され、さらに従軍慰安婦の強制連行や旧日本軍の南京大虐殺についての報道や教科書記載が指弾されるようになってから久しい。 こうした歴史修正主義の動きは、韓国や中国からの反発を招き、他方でこれらの国のいわゆる「反日教育」や「反日デモ」が日本の反発を招き、和解不可能な争点へと転化している。政策的な争点が解を見つけ得るのに対し、歴史認識問題はすぐれて価値的な問題であるゆえ、解決は容易ではない。 東アジアの市民社会同士の対立は、国の首脳同士の不仲へとつながっていく。安倍晋三首相が2013年末に靖国神社に参拝したこともあり、3年にわたって日中首脳会談が開催されないという異例の事態を招いた。竹島問題もあって、韓国とは2014年3月まで、約3年半も首脳会談が開催されないままだった。 安倍首相は2018年8月の時点で首相として歴代最多の世界76ヵ国の訪問を果たしたが、中国と韓国への単独訪問は実現することができなかった。 2018年に韓国の大法院(最高裁)が元徴用工への日本企業の賠償を認めたために、翌年には日本が安保問題を絡めて実質的な輸出規制をおこない、今度は韓国側が軍事情報に関する包括的保全協定(GSOMIA)更新を一旦、拒否した。歴史認識問題は、安全保障問題にまで波及するようになったのだ。 小泉純一郎元首相時代を含め、首相や閣僚の靖国参拝が問題になるのはここに太平洋戦争の戦犯、さらに日清、日露戦争の戦没者などが祀られているからだ。尖閣諸島や竹島の帰属問題など、日本と中韓両国の直接的な対立は領土問題のはずだが、こうした領土問題は原因ではなく歴史認識問題の結果に過ぎない。 互いの敵愾心を煽っているのは、過去の歴史についての異なる見解なのだ。 講演「国民とは何か」で有名な19世紀フランスの思想家ルナンは、「国民の本質とは、すべての個人が多くのことを共有していること」と、普仏戦争で帝政ドイツにアルザス゠ロレーヌの割譲を強いられた際に述べている。 そもそも国家という共同体そのものが、さまざまな対立や分裂を内包してきたものであることは、西南戦争、アメリカの南北戦争やフランス革命を思い起こせばよい。しかし、そうした事実を忘却し、互いに共有すべき記憶を担保できるからこそ、国家は完成をみた。 国民国家を指して「想像の共同体」といったのは文化人類学者ベネディクト・アンダーソンだが、これをルナン風に言い換えれば、国民国家とは「記憶の共同体」でもある。 だから共同体にとって、記憶をいかに処理するかは死活問題となる。日本が2013年にサンフランシスコ講和条約を記念した「主権回復の日」の式典を開催し、自らの主権を想起させたかと思えば、翌年にロシアと中国が「ドイツ・ファシズムおよび日本軍国主義への勝利70周年」を記念することで合意した。 2015年には中国が日本を除く先進国首脳と国連事務総長を招いた「中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利70周年記念行事」を開催、自らの体制の歴史的正当性をアピールしたのも、「記憶の共同体」を維持するための当然の行為であった。中国は2014年、南京大虐殺、抗日戦争勝利、戦死者追悼の3つを記念日に制定している。 日本の植民地支配を受けた韓国も2017年に文在寅政権が発足し、翌年に慰安婦被害者をたたえる日を制定することを決め、その後、慰安婦に関する研究所と記念館を作る計画を発表した。存命する韓国の慰安婦は2017年夏の時点で37名を数えるだけだったが、それはすでに共同体全体の記憶になっている。 日本の首相や閣僚の靖国参拝に対する中国や韓国政府による非難を「内政干渉」として退けられるのは、記憶が国境を越えないかぎりにおいてだ。しかし、記憶が本質的に時間や空間を越えるものであるかぎり、歴史認識問題という争点の性質は、それまでのものと大きく異なる。 歴史認識は争いと分断の原因にもなるが、そもそも歴史とは何だろうか。政治学者の吉田徹によれば、それは事実の集積というより、特定の共同体で集合的に作られていく「フェイク」だ。 文化的観念は「本来的なもの」ではない 歴史は当初、国家に固有のものとして、国民の共同的な記憶や教育のために構築されてきた。歴史を記録する公文書館がフランス革命以降の国民国家形成を目的に作られ、『母を訪ねて三千里』といったイタリアの児童向けの国民的物語も、建国期のナショナリズム意識を高めるために創作されたものだった。 日本という共同体の記憶で現在、最も重要なものは「終戦記念日」だろう。ただ、戦争の終わりを記念するならば、日本の無条件降伏を求めるポツダム宣言を受諾した1945年の8月14日でもよいし、連合国との平和条約が結ばれた1951年の9月7日でもよかったはずだ。 実際、日本と戦った国々が祝う「対日戦勝記念日」は9月であるのが通例だ。多くの国の終戦記念日や休戦記念日は、講和条約の結ばれた日だ。そもそも今のように8月15日に全国戦没者追悼式がおこなわれるようになったのは1982年の閣議決定を経てからのことに過ぎない。 8月15日が日本の終戦記念日とされたのは、いうまでもなく1945年のこの日に、昭和天皇による玉音放送(の録音)が放送されたからだ。メディア論が専門の佐藤卓己は、この日を終戦記念日としたのは、天皇制維持を求める保守派と、敗戦を日本の民主化のきっかけとしたかった革新双方の合意が得やすかったからだと説明している。 経緯や実際はともかく、それでも、日本国民にとって終戦記念日は8月15日であり、この日に全国各地で追悼の式典がおこなわれ、マスメディアが太平洋戦争にまつわる記憶や証言を報道し、高校球児が正午のサイレンとともに黙禱するのは、終戦記念日が人為的に歴史を創り上げ、集合的な記憶を再生産していく手段でもあるからだ。 もっとも、日本の敗戦の日は、アメリカやロシアにとっては戦勝の日であり、中国や韓国にとっては解放の日であり、日本国内だけでみても、沖縄にとっての終戦記念日の意味は本土のそれとは異なる。 つまり、歴史とは「事実」の集積というより、特定の共同体で集合的に「作られていく」ものなのだ。これは演歌や地方の方言にしても同じだ。 前者は、歌謡曲やフォークソングなど欧米経由の音楽が都市で流行していくなかで、日本の前近代的な価値観や男女観を歌い上げるために商業化され、方言はNHKの大河ドラマなどで歴史的人物(例えば西郷隆盛や大久保利通など)のイメージに添って使われて認知されるようになった。歴史的な文化は、時代の要請に従って再編される。 「伝統」が経済的・文化的要請から捏造されるものであることは、歴史家エリック・ホブズボームの『創られた伝統』(原題は『伝統の発明』)の解題以来、有名なテーゼとなっている。 この本では、例えばスコットランドの伝統的な作品とされる「キルトのタータンチェック」も、当時の繊維産業やマーケティングの産物だったことが論証されている。タータンチェックはスコットランドの氏族ごとに異なる柄模様があるとされたが、これは生地を市場に売りこむために作られたフィクションだったという。 16世紀のイングランド王ヘンリー8世がタータンチェックを禁止したためにスコットランド人というエスニシティがこれと結びつき、それまでアイルランド民族の一部とされてきたスコットランド民族が独自のアイデンティティとして我がものとした。 歴史とは作り上げられるもの、誤解を恐れずにいえば「フェイク」であるからこそ、それは称賛や恣意的な操作の対象となる。歴史が、捏造されるような記憶を伴わず、事実だけに基づくのであれば、それは多くの人びとに想像されたり、教訓を与えたりするようなものとはなり得ない。
0投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ1045 吉田 徹 東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒。日本貿易振興機構(JETRO)調査部、パリセンター調査ディレクターを経て、東京大学総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。日本学術振興会特別研究員等を経て、北海道大学法学研究科/公共政策大学院教授、現在同志社大学政策学部教授。その間、パリ政治学院ジャパンチェア招聘教授、同非常勤講師、同フランス政治研究所客員研究員、ニューヨーク大学客員研究員。現在、フランス国立社会科学高等研究院(EHESS)日仏財団(FFJ)リサーチアソシエイト。 アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治 (講談社現代新書) by 吉田徹 すでに長い民主主義の歴史を持つ国々ですら多くの変調を経験しているのであれば、民主主義を標榜してからまだ月日の浅い国々にあって、その震度はさらに大きい。こうした国々を襲っているのは、政治制度は民主的であっても、個人の基本的人権や報道の自由、司法の独立といった、戦後に制度的に完成したリベラルな制度を破壊するような非リベラル化の波だ。 この「非リベラル」な民主主義国の代表例がハンガリーだ。 ハンガリーは一九八九年に社会主義体制から脱して民主化を経験し、中東欧諸国のなかではチェコやラトビアなどとともに二〇〇四年にEU加盟を果たすなど、新興民主主義国のなかでも優等生とみなされてきた。ハンガリーは民主主義と市場主義が広がるポスト冷戦期の民主主義の輝ける希望の星だったのだ。 こうした措置はEUをはじめ国際社会から強い非難を浴びたため、法案は部分的に修正されたが、二〇一一年に今度は「ハンガリー基本法」という新たな憲法が議会で制定された。新憲法には、同国がキリスト教文明に属するものであること、男女の婚姻と胎児の保護、他国のハンガリー系市民に投票権を付与すること、個人よりも共同体が優先することなど、きわめて権威主義的かつナショナリスティックな内容が盛り込まれた。また、憲法裁判所の権限を縮減するなど、司法の独立や報道の自由、それらを保障する法の支配を政治の力で脅かす内容が含まれ、いわば民主化の道を歩んできた同国の「逆コース」への道筋をつけた。 オルバーン首相は、個人の自由を認めるリベラリズムを正面から攻撃する。彼は二〇一四年に民主主義は必ずしもリベラルである必要はなく、自由な民主主義では国益を守ることができないと公言し、ハンガリーはこれとは異なるナショナルなものを基礎とする「非リベラルな国家」となることをめざすと主張した。そして、シンガポールやインドや中国、ロシアといった「非民主主義国」にこそ見習う必要があるとした。安定した多数派を手にしたオルバーン政権は、コロナ禍に乗じて、非常事態宣言を無制限に延期できる法律を制定し、非常事態終了後も、同様の法律を通している。 こうした国のいわば「手本」となるのは、いうまでもなく中国だ。 中国は、とりわけ一九八九年の天安門事件以降、経済的発展をめざしつつも、民主化を抑制することに腐心してきた。民主化の砦だった香港も、国家安全維持法によって制圧された。歴史的にみれば、経済発展が必ずしも民主化を促すとは限らないものの、経済的な豊かさによって、その国の政治体制は維持されやすくなることがわかっている。中国は二〇三〇年までに一人あたりの所得が一万ドルの中所得国になると予測されているが、個人の経済的豊かさが維持できれば、それはそのまま政治体制の正当性につながる。一九九〇年代に途上国の指針となった市場主導で経済発展をめざす「ワシントン・コンセンサス」は後景に退き、権威主義的な政府のもとで人びとを豊かにしようとする「北京コンセンサス」がモデルとして生まれようとしている。資本主義がリベラリズムを生んだというのが近代の歴史だとすれば、リベラリズムなき資本主義の実践を試みる国が新たな歴史となりつつある。 この非リベラルなモデルは逆流をして、古くからの民主主義国へと伝播していく。冷戦後の民主化ドミノの逆転現象だ。トランプ大統領はプーチン大統領を称賛して止まず、資金提供を受けているとされる西欧の極右政党指導者はこぞってロシアを訪問し、同国の立場を擁護している。国際情勢はそのまま国内の対立軸へと転化し、リベラルな政党がロシアや中国と距離を取る一方、ポピュリズム勢力はこうした権威主義体制の国々との協調を訴えるようになっている。 はたして歴史は逆転しているのか。リベラル・デモクラシーはなぜ脆弱な立場に追いやられているのか、リベラルな価値はなぜ衰退しているのか。もっといって、なぜ競争的な権威主義体制こそが先進性と有意性を保っているかにみえるのか──それを知るためには、迂遠であってもリベラリズムの変遷を追いつつ、二〇世紀後半に成立したリベラル・デモクラシーがいかにして生まれたのかを、まずは知っておく必要がある。 一般的にリベラリズムは個人の自由を、デモクラシーは個人間の平等を尊重するゆえに相性が悪いとされる。ただ、こうした理解は一面的なものに過ぎない。それぞれの原理を薄めることによって戦後のリベラル・デモクラシーはその正当性を獲得できたからだ。 しかし、政治思想史や政治理論の観点からは、こうした理解はさほど一般的ではない。むしろ、個人の内面の自由や権利を尊重するのがリベラリズムであり、他方で共同体や人民の一体性やこの間の平等を希求するのが民主主義だったからだ。 これに対する西側のリベラル・デモクラシーの国々は、資本主義経済や自由市場を、人民独裁や一党支配を通じてではなく、法の支配や政治的な多元主義(マイノリティの権利擁護) といった制度によって実現していった。冷戦崩壊もあって、これが現在の民主主義でイメージされるものの基礎へとすり替わっていく。リベラリズムは、あらゆる「イズム(主義)」同様、多義的な言葉であることはまちがいないが、最終章でみるように、それは国家などを含む共同体よりも個人の権利を優先し、そのために権力を分散しておく制度設計をおこない、「多数者の専制」を絶えず警戒することを特質としてきた。 ただしここで注意しなければならないのは、こうしたリベラリズム理解は、政治的な意味合いのものであって経済的な意味合いではないということだ。リベラリズムが人びとの権利主張を意味するようになったのは、二〇世紀前半にそれまで資本主義を生み出した経済的なリベラリズムがあまりにも不平等を生み出し、多くの人が自己破産を余儀なくされたからだった。二〇世紀を「破局の時代」と形容した有名な歴史家ホブズボームは「一九世紀末生まれの人をもっとも強く驚かせたのは、おそらく自由主義文明の価値と制度の崩壊であろう」と記しているが、これはそれまでのリベラリズムが主として経済領域に立脚していたことを示している。 だからハンガリーなどの競争的権威主義体制、そして中国のような権威主義体制の非リベラリズムを考える場合、次に問われるべきは、資本主義とリベラリズム、そしてデモクラシーとの関係ということになる。 リベラリズムと民主主義の共存は、リベラリズムの経済的側面の抑制と民主主義の革命志向を抑制することで成し遂げられた。具体的には、基幹産業の国有化や福祉国家の確立を通じて不平等を容認する資本主義をリベラリズムから切り離し、他方では法の支配や立憲主義を徹底することで、ファシズムや社会主義に代表されるデモクラシーを抑制しようとしたのである。それは二〇世紀まで資本主義によって経済を牽引してきたリベラリズムを政治的次元に囲い込み、人民主権を掲げて政治を牽引してきた社会主義を経済的次元に囲い込むという逆転の発想でもあった。 二〇一六年のアメリカ大統領選の最中、プリンストン大学の研究者らが同国の働き盛りの白人労働者(ヒスパニック系を除く) の死亡率だけが九〇年代以降に上昇していることを発見、しかもその死因がアルコール依存症や薬物依存によるものだとして話題になった。その死亡者数は年間の交通事故死者数より多い。彼ら白人労働者たちは、その多くが高卒以下の学歴しか持たない人びとだ(ちなみにその薬物の多くは中国からの密輸入だともされている。そうした意味でも彼らはグローバル化の犠牲者である)。こうした傾向も手伝って、アメリカの平均寿命は過去一〇〇年間ではじめて三年連続で短くなった。フランスの統計でも、全雇用者のうち、男性の労働者層の平均寿命の延びが他の職種と比べて低いことがわかっている。つまり、収入の差だけではなく、先進国にあっても、職種、そしてその職種を決める学歴によって、命の価値さえもが不平等になっているのだ。 具体的にいえば、例えば、高学歴で専門職についている人はリバタリアン的な政治的志向を持ち、反対に利子・年金生活者や単純労働者などは権威主義的な志向性を持つ。これは、公共部門で働く事務職や労働者階層の人ならば左派を、企業経営者・自営業者などであれば保守的な政党をという、従来の階級政治で自然とされた生産様式による結びつきに加えて、「リバタリアン」と「権威主義」という脱物質主義的な価値観が交わって、政治的対立軸の四象限を形成する。 九〇年代以降、こうしたリベラルな勢力に対する反対の意識を担ったのが各国の「ニューライト」だった。彼らは、社会の個人主義化はアイデンティティを喪失させた「寂しい人びと」を生み出すだけで、自由と権利の履き違えを止めるためにも、社会の秩序と権威を取り戻さねばならず、社会の安定を保障する同質性を危機に晒す、行き過ぎたグローバル化や過度の移民受け入れは制限しなければならないという主張を展開していく。 社民のリベラル化を受けた保守の政治リベラル化という「リベラル・コンセンサス」は、CDUのポジション変化によってドイツでも完成した。二〇〇五年からのメルケル政権は福島第一原発事故を受けて脱原発を決め、二〇一五年からは中東・北アフリカ地域からの難民を率先して受け入れてドイツの「歓迎の文化(wilkommen kultur)」を強調し、その後、同性愛合法化にも踏み切った。 こうした反政治リベラルの運動を受けて、二〇一五年、新たにAfDの党首に選出されたのが女性実業家フラウケ・ペトリだった。彼女を中心とする新執行部は、ドイツの伝統的・旧来的な制度や価値観を掲げる新綱領を採択する。これを受けて反経済リベラルの極を代表していたAfD創設者のルッケらは離党して新党を立ち上げた。しかし、ペトリの新基軸は、失業者や工業部門の労働者へと支持を広げ、二〇一七年選挙で得票率一三パーセント(七〇九議席中九四議席) でもってAfDは連邦議会入りを果たした。右派政治に強い拒否感を持つドイツ政治で、戦後生まれの極右政党が議席を得たのは初めてのことだ。 第三章 歴史はなぜ人びとを分断するのか──記憶と忘却 まずは、メディアやネットを賑わしてきた歴史認識問題を扱おう。日本のいわゆる「自虐史観」を問題視する立場からは、日中戦争や太平洋戦争は必然だったことが喧伝され、さらに従軍慰安婦の強制連行や旧日本軍の南京大虐殺についての報道や教科書記載が指弾されるようになってから久しい。こうした歴史修正主義の動きは、韓国や中国からの反発を招き、他方でこれらの国のいわゆる「反日教育」や「反日デモ」が日本の反発を招き、和解不可能な争点へと転化している。政策的な争点が解を見つけ得るのに対し、歴史認識問題はすぐれて価値的な問題であるゆえ、解決は容易ではない。 東アジアの市民社会同士の対立は、国の首脳同士の不仲へとつながっていく。安倍晋三首相が二〇一三年末に靖国神社に参拝したこともあり、三年にわたって日中首脳会談が開催されないという異例の事態を招いた。竹島問題もあって、韓国とは二〇一四年三月まで、約三年半も首脳会談が開催されないままだった。安倍首相は二〇一八年八月の時点で首相として歴代最多の世界七六ヵ国の訪問を果たしたが、中国と韓国への単独訪問は実現することができなかった。二〇一八年に韓国の大法院(最高裁) が元徴用工への日本企業の賠償を認めたために、翌年には日本が安保問題を絡めて実質的な輸出規制をおこない、今度は韓国側が軍事情報に関する包括的保全協定(GSOMIA) 更新を一旦、拒否した。歴史認識問題は、安全保障問題にまで波及するようになったのだ。 反日教育がおこなわれているとされる中国では、日本軍のコスプレイヤーがいる。「精神日本人(精日)」と呼ばれる彼らは、「艦これ」といった日本アニメの影響から、旧日本軍の軍服を身につけ、旭日旗を掲げることを趣味とする人びとだ。中国当局は、彼らの存在に神経を尖らせ、「南京大虐殺の歴史」を持つ南京市では、コスプレを条例で禁止した。日本でもナチスの軍服によるコスプレが問題視されることもあるが、日中の若年層にとって過去の歴史は単なる「ネタ」でしかなくなっている。 このようにひとつの記憶が別の記憶を呼び覚まし、新たな対立の種となる──記憶をめぐる問題は国同士の対立となるばかりか、それぞれの国の内部で過去の歴史をめぐる和解不可能な分断線が引かれることに特徴がある。 旧西欧宗主国の支配に対する賠償請求や、反対に植民地支配を正当化する主張など、忘却に対する抵抗と記憶の承認要求というかたちをとって表れる事例は、後を絶たない。「歴史の記憶が薄れている」、「歴史認識が甘い」、「歴史の教訓に学んでいない」、「若い世代は歴史を知らない」──歴史についての知識のなさが指摘される一方で、実際には現実世界は、歴史についての記憶で溢れかえっているのだ。 ただ、アルヴァックスは、人が人としての尊厳や承認を得るためには、見知らぬ人びととの協力や協働が不可欠だとした。人は何かの役に立つことで、他人から認められ、自分に誇りを持つことができるためだ。そして、集合的記憶はこの個人と個人との間のつながりや絆を提供するもの、共有できる物語として機能する。醸成される人びとの結びつきは、共有される記憶や体験によって強まっていくことでさらに強化され、それが今度は自分がどのような世界に生きているのかについて意味を与え、個人は自尊心(自己愛) を得ることになるわけだ。個人が主張し、担うだけの「ウーバー化」した歴史は、歴史としての役割を果たせないのだ。 これはアルヴァックスがいったこととも類似している。先にみたように、元来、集合的記憶とは共同体に生きる人間の尊厳を獲得するために欠かせないものであり、他人との協働や協力を可能にするための資源として機能する。その反対に、他の共同体と共有できず、他人を傷つけるような記憶は、歴史へと昇格するのに値しないというのが、リクールの立場だ。独り善がりの記憶ではなく、他人と共有できるような「公正な記憶」こそが「幸福な記憶」なのだ。記憶に公正であることを求めるのを忘れたとき、それはもはや共同体同士が共有可能な歴史を失い、細切れで、場当たり的で、短命な記憶のなかにしか生きることが許されないということになるからだ。それは、記憶をなくすことと同義である。 韓国のベトナム戦争での加害は、韓国にとっての歴史認識問題でありつづけている。一九九八年、金大中大統領がベトナムに謝罪の意を表明したが、これは国内の保守派から強い非難を浴びた。いわば、日本の韓国との歴史認識問題と同じ構図が、韓国とベトナムとの間で再現されているのである。 キム夫妻の彫刻は──それが韓国の慰安婦像であれ、ベトナムの母子像であれ──、国を超えて、被害者としての記憶を留めるために作られたものだ。 ともに被害者であり、加害者であるということを確認することで和解をうながす行為は、イスラム教徒とユダヤ教徒の間でもみられる。EU離脱のイギリスや、トランプ大統領が選出されてからのアメリカの両国でヘイトクライムが増大していることは次章で確認するが、二〇一七年二月にアメリカのムスリム二名が、何者かが破壊したセントルイスのユダヤ教墓地修復のためにクラウドファンディングを呼びかけ、一六万ドル以上を集めた。同月末には、フロリダ州で焼き討ちにあったモスクを建て直すための募金が呼びかけられたところ、今度はユダヤ系市民を中心に目標額を大きく上回る六万ドル以上が集まったという。 こうした多発的で分散的な第三世代のテロは、次章でみる七〇年代の社会運動と同じように、自由な個人が主導する「ウーバー化」の事例だ。ウーバー社は、個人が事業主となって時々の注文や契約に応えて働くことをビジネスモデルにしているが、組織ではなく個人、供給ではなく需要、長期ではなく短期、継続ではなく断続であることを最大の特徴にしている。第一章で紹介した「ゼロ時間契約」もその系譜にあるが、戦後の共同体の崩壊は、テロの有り様にも作用している。 それゆえアイデンティティの空白を抱えがちな第二世代ほど、自らのルーツを追い求める誘因を持つ。次章でみるように、折しも一九七〇年代以降は、個人化と自己決定権というリベラル的な価値拡大によって、信仰や価値などに関わるものは、自らで決めることができ、決めるべきだとする社会規範が根付いていった時代にあたる。イギリスのムスリムを対象にした調査では、実際には若者世代ほど同性愛への抵抗感を持っていたり、ムスリム同士の婚姻にこだわったりすることがわかっている。これも自らの文化的なルーツに忠実でありたいという意識の表れとみることができる。こうした自らの文化的、民族的ルーツへの固執は、両親世代がそれを過去のものとし、過剰にホスト社会に適応していることに対する反発心によっても補強されていく。 人口学者ミシェル・トリバラの調査によると、一九九二年と二〇〇八年のアルジェリアからの移民家庭を出自とするフランスの若者(二〇~二九歳) を比べると、後者の方が宗教を信じているとする割合が二倍も多く、女性に限っては三倍も増えたという。若者であればあるほど、脱世俗化が進み、宗教回帰がみられるのだ。こうした傾向は、二〇〇〇年代に入ってから、ハラール(イスラムの戒律に従って処理された食品) 食料の市場が年間一五パーセントほど拡大していっていることからもみてとれる。 つまり、移民系市民を過激派に追いやってしまうのは、彼らを宗教を基準に見るからだ。だから、宗教テロを呼び込んでいるのは、社会そのものだ。FBIによると、アメリカでは宗教や民族を理由としたヘイトクライムは二〇一五年に五八五〇件と前年比で七パーセント増、そのうちイスラム教徒に対する犯罪は六七パーセントも増えている。移民や移民系アメリカ人を敵視したドナルド・トランプが大統領に選出された二〇一六年には、反イスラムを掲げる組織が三四から一〇一団体にまで増えたとされる(SPLC調べ)。政治的にリベラル化した左派は、イスラム原理主義は宗教的・文化的抑圧に起因するとして理解を示し、一部の極右も、イスラム原理主義の反ユダヤ主義的立場からこれを支援する傾向がある。第二章でみたような権力の多元化による脱物質主義的価値観の政治は、鏡写しのように、極右に代表されるナショナル・アイデンティティの極と、過激派に代表される宗教的アイデンティティの極との間に引き裂かれていっている。 二〇一七年にはヨーロッパの右派団体がクラウドファンディングで八万ユーロ(約一〇〇〇万円) を集め、地中海を渡ってくる難民・移民を阻止するための大型船をチャーターしてパトロールをするといった組織的なヘイト行為までもあった。なかには二〇一五年のパリの連続テロに対抗の意思を示そうと、パリの広場でスワッピングをフェイスブックで呼びかけて二万件の「いいね!」を集めた企画もあったが、ヘイトとは言わずともこうした悪ふざけも、敬虔なムスリムの感情を逆なでしたことは確かだろう。フェイスブック社は二〇一七年に一ヵ月で三〇万件弱もの世界のヘイトスピーチの投稿を削除せざるを得なかったと公表している。 イギリスを二〇一五年に騒がしたのは、パキスタン系のギャング団が過去数年間にわたって少女たちをレイプしたり売春斡旋したりしていた事件だった。これは、公権力が移民社会に介入しないという多文化主義の原則や反レイシズムを意識したことが事件解決を遅らせたとして大きな批判を浴びた。ポリティカル・コレクトネスの弱点が、逆にポリティカル・コレクトネス批判を招くようにもなっている。 コミュニタリアン(共同体主義者) として有名な政治哲学者チャールズ・テイラーは、世俗化の進んだ歴史を精査し、近代的な理知によって宗教が駆逐されたことは実際には一度もなく、現代にあっても、宗教的なもの以外に道徳上の源泉は存在しないという。例えば、人に固有の権利が認められるべきとする立憲主義の精神も、「人は神に似せて作られたから」ということ以外、その根拠を見出すのは難しい。だから、科学によって宗教は置き換えられることはない。例えば「2+2は4」という絶対的な定理が科学的に導かれたとしても、それで正義の実現や不条理が解消されるわけではない。正義や道徳の源は宗教によって供給されるしかない、と。 女性にもてないことをこじらせた中年男性を主題にした彼の代表作『素粒子』に典型だが、ウエルベックは人間を解放することはすなわち、その人間は自らの能力だけしか頼るものがなくなることを意味するから、結果として夥しい不平等を生むことにつながると、あるインタビューで答えている。人間の責任は、社会にも家庭にも伝統にも歴史にも負わせることができず、自分で負うしかなくなるからだ。そして、その負える責任の範囲は、個々人の能力や資本によって異なってくるゆえ、行き着く先は人生のあらゆる側面での不平等でしかない。 ここで出てくるのが、信仰の問題だ。小説後半、主人公フランソワは文学大全の編纂とイスラムへの改宗を承諾して大学への復職を決心する。主人公は過去にカトリックとして育てられた記憶もあって、カトリック修道院に救いを求めて修行するのだが、結局、自分の役に立たない宗教には意味がないということをその過程で悟る局面がある。自分の人生にとって使えるか、使えないかが、信仰心を持つか持たないかの基準なのだ。だから主人公フランソワは、自らの出世と性的願望(一夫多妻制!) のため、なんとなくムスリムになることを、あっさりと決めてしまう。 現代の正義論の基礎を作ったアメリカの哲学者ジョン・ロールズによる『正義論』も一九七一年に公刊されている。この著作もベトナム反戦運動や公民権運動など一連の「権利革命」を実現した現実社会への応答であり、個人に配分される価値として「自由」がなければならないと主張するものだった。第二章でみた「静かな革命」が進み、現代的な意味でのリベラルな価値は、この時代に生まれた。自身も六八年革命の当事者だった批評家の 絓秀実は、この時代に「『新左翼的な』文化はすでに常識的な心性と化して(略) エコロジカルに省エネを推奨するCMやセクハラへの嫌悪など、それは日常的な細部にまで浸透」したと証言する。同じようにフランスの六八年世代の代表的論者であるジョフランは、その後の社会での平等の意識や民主的価値の定着をみて「二〇年を要したものの(略) 静かに凱旋したのは〈五月の文化的〉な側面」だったと勝ち誇る。もっとも、こうした個人的なリベラリズムへの反発の端緒がこの時代にあったことは、第二章でみた通りだ。 もっともこの例をとれば、制服着用についてのルールと、制服があること自体とは分けて議論すべきだろう。制服は社会での個人の間にある不平等を覆い隠すものだ。義務教育は、かつての教会による教育では神の前で、近代国家によるものとなってからは法の前で、何人も平等であることを意味するものであったはずだ。 ヒース/ポターの『反逆は売れる』(邦訳は『反逆の神話』) は、戦後ベビーブーマーの子弟たちが学校に通うようになった九〇年代に制服廃止運動が全米で巻き起こり、その後子どもたちの多くが小遣いをファッションにつぎ込むようになり、ギャング文化の元凶となったため、制服回帰の現象がみられるようになったと指摘する。制服を廃止して、個人の自由な服装が許された結果、特に若者たちはブランドや流行に頼って自らを誇示するようになる。消費資本主義は個人の間の差異を付加価値とするから、終わることのない差異化がその原動力になる。同じブランドのスニーカーであっても、ちょっとしたモデルの違いが意味を持つようになって、企業はイメージ消費で収益をあげることになる。 日本は他の先進国と比較しても、規範意識(「こうあるべき」という意識) が強く、個人の自由に対する理解や寛容度は高くない。例えば「同性愛は許されるか」を問う国際意識調査では、日本で「絶対に許されない」としたのは二二パーセントだったが、これはドイツの一〇パーセント、フランスの一五パーセント、スイスの一〇パーセントと比べて高い(ちなみに宗教的規範の強いイタリアでは四七パーセント、アメリカでは三〇パーセント)。「売春は許されるか」という問いに対する否定的回答は、日本は六四パーセントで、フランス四一パーセント、ドイツ二三パーセント、イタリア五五パーセント、アメリカ四〇パーセントと、日本ではやはり売春行為への拒否意識が高い(「世界価値観調査」二〇〇五~二〇〇九年)。 第三章は、国と国、国民と国民、そして国内の人びとの間を切り裂いている歴史認識問題をみた。共通の歴史は、共有された認識と未来の土台となるものだったのが、逆に人びとを分断する要因になっており、問題は安全保障問題に比するまでになっている。その理由は、歴史と切り離すことのできない「記憶」の前面化にある。「公的な物語」としての歴史ではなく、「私的な歴史」としての記憶は、戦後世代が社会の中心となる一九七〇年代以降、親世代の戦争責任を問う姿勢、さらに民族的マイノリティの記憶の重視などと相俟って、国家間、イデオロギー間の新たな争点となった。戦後世代が主流となり、さらに冷戦が終わってからは、ショア(ホロコースト) のように、リベラル・デモクラシーと社会主義/共産主義との対立の影に隠れていた過去の記憶がせり出すようになる。
0投稿日: 2024.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉田徹(1975年~)氏は、慶大法学部政治学科卒、東大大学院総合文化研究科修士課程修了、ドイツ研究振興協会DIGESⅡ修了、東大大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学、JETRO勤務、日本学術振興会特別研究員、北大法学研究科准教授・教授等を経て、同志社大学政策学部教授、フランス社会科学高等研究院日仏財団リサーチ・アソシエイト。専門は、比較政治・ヨーロッパ政治。 本書は、近年世界的に広がる、リベラルな政治の後退と権威主義的な政治の台頭に加えて、歴史認識問題の拡大、世俗化に伴うテロやヘイトクライムの頻発、個人が扇動する社会運動等について、歴史的な背景を含めて、それらが相互にどのように関連しているのかを、政治学・社会学的に考察したものである。尚、内容の多くは、いくつかの共著や専門誌に掲載された論文をベースに書き改められたもの。 私は、昨今のリベラルの限界を指摘する多くの言説に強い問題意識を抱いており、これまでにも、田中拓道『リベラルとは何か』、萱野稔人『リベラリズムの終わり』ほか、様々な本を読んできて、本書についてもその流れで手に取った。 読み終えて、正直なところ、新書としてはあまり理解しやすい本ではなかった。というのは、初出が(専門的な)論文である内容をまとめているため、各章のつながりが見えにくく、各種引用もかなり広く深いためと思われる。 私なりに本書から読み取った理解を記すと以下である。 ◆第二次大戦後に世界に広まった「リベラル・デモクラシー(自由民主主義)」とは、個人の「自由」を尊重するリベラリズムと、個人間の「平等」を尊重するデモクラシーという、元来は相性の悪いものが合体して成立した。それは、リベラリズムが経済的側面(資本主義)を抑制し、デモクラシーが政治的側面(ファシズムや社会主義)を抑制するという、それぞれの原理のネガティブな側面を薄めることによって可能となった。リベラル・デモクラシーは、戦後成長の中で生まれた中間層が基盤となったが、成長の鈍化、将来展望の不透明化が進む現在、中間層は政治的な急進主義(非リベラルな民主主義)に引き寄せられている。 ◆19世紀以降、政治は、階級社会の対立軸である「保守vs左派」という構図をとってきた。しかし、階級政治の終焉、「ポスト工業社会」への移行に伴い、人々の価値観は、物質主義から脱物質主義(社会的・文化的価値観)」に変化し、政治の命題も、「社会はいかにあるべきか(資源・物質の再配分)」から「個人はどうあるべきか(価値の再配分)」に変わった。同時に、それまで対立軸を作ってきた保革政党が、保守政党の社会政策におけるリベラル化と、社民政党の経済政策におけるリベラル化によって、「リベラル・コンセンサス」を成立させたことにより、リベラルと、経済リベラルに反感を持つ労働者層と政治リベラルに対抗的な価値を掲げるニューライトが組んだ反リベラルの対立軸、即ち、「リベラルvs権威主義」という対立軸が生まれることになった。 ◆1970年代以降顕著になった歴史認識問題の拡大は、それまで基本的に「公的な物語」であった歴史が、戦後世代が社会の中心になるにつれて、バラバラの「私的な記憶」(場合によってはフェイクの)の集合体となったことに起因する。それに伴い、政治は、未来の理想を語るものではなく、過去がどうであったのか、どうあるべきだったのかを論じるものに成り下がっている。これはかつて勝ち組だった中間層が、過去を美化するポピュリズム政治に惹かれることにも繋がる。 ◆現在先進国を襲うテロやヘイトクライムは、社会に宗教色が強まったことが原因ではない。かつては、教会や宗教指導者の権威が強く、宗教が個人を操作していたが、現代では、社会が個人化したことにより、所謂「ウーバー化(サービスの提供者と利用者が直接結びつき、仲介者の役割を排除すること)」が進み、個人が宗教を自分のために利用するようになった。宗教の原理主義化は、伝統的な宗教・信仰のあり方から個人が離反したことによって生じているのであり、単に宗教を批判・抑制しても問題はなくならない。 ◆そういう意味で歴史的起点となったのは、1968年に世界中で起こった、伝統的な集団(階級、宗教、地域、ジェンダー等)からの個人の解放を求める、所謂「新しい社会運動」である。しかし、個人化・個人主義の進展は、反作用として、上記のような社会の変容をもたらし、また、新たな他人との結びつきや社会・集団の形成を必要とするようになっている。 ◆リベラリズムは歴史的に、「政治リベラリズム」、「経済リベラリズム」、「個人主義リベラリズム」、「社会リベラリズム」、「寛容リベラリズム」の5つのレイヤーに分けられるが、上記のような現象は、5つのリベラリズム相互の不適応(バランスの欠如)によるものである。個人の尊重は重要だが、その行き過ぎは、他人との差異を際立たせ、社会に対立と分断を作ることに繋がりかねない。リベラリズムの最大の強みは、多様な意味を持ち、かつ、自らを刷新・進化させられることにある。まずは、個人主義リベラリズムと寛容リベラリズムの均衡と、経済リベラリズムと社会リベラリズムの均衡を、そして、人間性の剥奪に抵抗する、整合的なリベラリズムへの進化を目指す必要がある。 「リベラル」、「リベラリズム」について一冊だけ読むなら、敢えて本書である必要はないが、相応に問題意識を持つ向きには、複数のうちの一冊として読む価値はあるだろう。 (2024年2月了)
2投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ各章のつながりがよく、読み進めていく中でリベラリズムが直面する難題が少しずつ理解できます。 日本人がイメージするリベラルではなく、左派だのパヨクだのすぐカテゴライズしたがる人に、ぜひ読んで頂きたいですね。
2投稿日: 2024.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ権威主義体制と対峙する今だからこそ考えたいリベラリズム。やや総覧すぎて焦点が絞りにくいけど、考えるネタを提供してくれている。
0投稿日: 2022.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界情勢はすっかり変わり、リベラリズムは衰退した。怒りや敵意に充ちた世界で、アフターリベラルはどのような世の中となっていくのであろうか。
0投稿日: 2022.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ21世紀初頭の先進資本主義国における右派ポピュリズムの躍進や関連するオルタナ右翼の人種差別主義、歴史認識の政治化、過激なイスラーム主義によるテロリズム、me too運動などは、すべて1968年革命でリベラリズムが「個人」を解放した結果として生じている(本書の言葉で言えば「ウーバー化」)ということを論じている。 “ 政治は作用と反作用からなる。作用する主体や次元が変転すれば、それに呼応する反作用も新たな性質を帯びる。既存の政治がリベラルという価値に軸足を置けば、それへの対抗軸は非リベラル、反リベラルなものとなる。その事実を認めないかぎり、次の時代の政治は見えてこない。権威主義的なニューライト、保革政党によるリベラル・コンセンサス、歴史認識問題、宗教的ラディカリズムやヘイトはともに、リベラリズムと呼ばれる潮流が内在させてきた本質の副作用とみることができる。つまり、リベラリズムは、自らの(←288頁289頁→)勝利によって、自らの敵を作り上げてしまったのだ。”(本書288-289頁より引用) 1968年新左翼革命の個人優先主義が、実は1980年代のレーガンらネオリベラリズムとその支持層の保守主義者の間で通底していたという議論は、ポリティカル・コレクトネスの誕生を巡る論説でよく目にするが、本書全体から、今現在我々が立ち会っている社会の崩壊は、68年的なものの結果であり、そしてその終わりなのだということを感じた。本書で示されるように、個人の尊重というリベラリズムの原理が勝利したからこそ、今日にあってリベラリズムを擁護するのは困難なのであろう。その点では特に、本書で示されたウエルベックの『服従』(2015年)の読み解き(231-236頁)は非常に興味深かった。 “ 女性にもてないことをこじらせた中年男性を主題にした彼の代表作『素粒子』に典型だが、ウエルベックは人間を解放することはすなわち、その人間は自らの能力だけしか頼るものがなくなることを意味するから、結果として夥しい不平等を生むことにもつながると、あるインタビューで答えている。人間の責任は、社会にも家庭にも伝統にも歴史にも負わ(←234頁235頁→)せることができず、自分で負うしかなくなるからだ。そして、その負える責任の範囲は、個々人の能力や資本によって異なってくるゆえ、行き着く先は人生のあらゆる側面での不平等でしかない。 だから、『服従』が告発するのはイスラム原理主義ではなく、人間精神を救済できない現代社会であり、それに宗教が利用されるという「ポスト世俗化」のロジックを描くものなのだ。 ここで出てくるのが信仰の問題だ。小説後半、主人公フランソワは、文学大全の編纂とイスラムへの改宗を承諾して大学への復職を決心する。主人公は過去にカトリックとして育てられた記憶もあって、カトリック修道院に救いを求めて修行するのだが、結局、自分の役に立たない宗教には意味がないということをその過程で悟る局面がある。自分の人生にとって使えるか、使えないかが、信仰心を持つか持たないかの基準なのだ。だから主人公フランソワは、自らの出世と性的願望(一夫多妻制!)のため、なんとなくムスリムになることを、あっさりと決めてしまう。 現代社会では、宗教こそが個人の欲望に服従することになる。個人の自己決定権が当たり前となった政治的リベラリズム優位の社会で、宗教への「服従」はあくまでも主体的に、自主的になされるという逆説が、小説のタイトル『服従』の意味なのだ。ちなみに「イス(←235頁236頁→)ラム」とはアラビア語で「服従」の意味だ。”(本書234-236頁より引用) 本書が見通す世界がそうであるからこそ、本書の特徴としては、個人に終始する発想の否定が挙げられるかもしれない。21世紀に入ってからのポスト・マルクス主義やアナキズムがコミュニタリアニズム志向なのはよく知られているが、リベラリズムもまた、共同体を重視する方向に向かうことで、リバタリアニズム的潮流との差異化を図るのかもしれない。
0投稿日: 2021.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでのリベラルデモクラシーのあり方について、最後にこれからのあり方を提言してくれているのはとても参考になりました。
0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと情報量が多すぎる印象。タイトル通り憎悪がぶつかって延々バトルしてるのどうするか、みたいな議論を期待したんだけど、意外に歴史的な記述も多い。でも歴史的な話は私はわかりやすいというか、そういうの理解しないとなんでこうなってるのかわからないのよね。
0投稿日: 2021.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ田中拓道「リベラルとは何か」からの吉田徹「アフター・リベラル」!このワンツーパンチは効きました。きついです。遡ってミチコ・カクタニ「真実の終わり」まで繋がりました。同時進行でBREXIT、トランプ、コロナ、香港、という出来事も、アフター・リベラルという眼鏡をかけると連環した流れとして見えてきます。20世紀後半の世界を作ってきたのはリベラリズムであること。そしてそれがパンデミックで崩壊しつつあること。そのふたつのことが明快に論証されていく本です。その時々で生まれてきたリベラリズムの多様性「政治リベラリズム」「経済リベラリズム」「個人主義リベラリズム」「社会リベラリズム」「寛容リベラリズム」…それぞれの均衡が破れて不整合が生まれている「暗い時代」、それが今なのです。ニューノーマルってコロナを乗り越えていくポジティブなキーワードだと思っていましたが、本書の副題にあるように「怒りと憎悪の政治」がスタンダードになる時代なのかもしれません。しかし、著者は言います。「リベラリズムの最大の強みは、それ自体が多様な意味合いを持っていることにある。実際に、過去のリベラリズムは、歴史の大きな転換点をみて、深い自己の刷新を遂げてきた。…」と希望を捨てません。あとがきも「もしも恐怖と破壊がファシズムの主要な情緒的源泉だとするならば、愛情こそが基本的に民主主義の側に立つもの」というアドルノの叙述で閉じています。コロナが「暗い時代」を作ったわけじゃなくて、もともと進んでいた「暗い時代」がコロナで噴出しただけであり、ニューノーマルはリベラルのアップデートにかかっているのだと思いました。
0投稿日: 2021.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ買った価値があった。 難しい内容だったが個々のトピックを丁寧に解説してあり、適宜要点を整理していてわかりやすかった。 冒頭で「リベラル」という言葉の意味するところが時代や国によって異なり、特に西欧と米国では反対になる点を説明し、まとめの章ではリベラルが主張する(求める)ものの変遷を歴史的な積み重ね(レイヤーという表現)で整理して、リベラルという主張自身が対立軸(個人の自由を主張すればするほど他者の自由と衝突する)を含むものである点を解説することで、主題に対する重さ、深さが伝わってきた。 安直によい、悪いという無責任な価値判断を慎重に避け、現在の分断や反リベラル的な潮流が1968年以降の学生運動的なものの負の側面に起因することをきちんと批判している点は納得した。 日本会議、トランプ、AfD、国民戦線についてもそれぞれの主張や政党の伸長率をきちんと取り上げ、それが支持される背景を冷静に分析している。 歴史認識問題についても、歴史と「記憶」の関連まで突き詰めて深堀りし、実質上解決はありえないのだろうがそれでも解決への糸口を探そうとして、対立の構造を明らかにしようと取り組んでいる。 ところどころで紹介してある小説も読みたくなった。 何よりも終章のタイトル「何がいけないのか?」にあるように、リベラルとは矛盾を含み、「自己」を批判できる思想であり、それゆえに大切なものであるという信念に共感した。 それにしてもネットやマスゴミに溢れるサヨクやフェミの「日本が悪い!」「自民が悪い!」「男が悪い!」「金持ちが悪い!」「ワタシは正しい!」という喚き声に比べて兆倍高尚な内容に触れた気がする。
0投稿日: 2021.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログやっとトランプ現象がわかってきたような。。。 というか、冷戦後の世界政治が理解できなくなっていたのが、ようやくわかってきたような。。。 いやいや、80年代の新自由主義のあたりからわからなくなっていたのが、ようやくわかってきたような。。。 ともすれば、日本とか、アメリカとか、ある国で今なにが起きているかという状況論的な話にちょっと歴史的な経緯を解説するというようなものになりそうなテーマなんだけど、これは、冷戦後の世界で起きていることをかなり包括的に、ロジカルにまとめたもので、相当の説得力をもった議論だ。 国によって、時代によって、その意味する内容がかなり違うにもかかわらず、戦後の世界で広く共有された理念であったリベラリズムが退潮していった理由をしっかりおさえ、なぜ権威主義的な政治が立ち上がっているのかを論じている。そして、その展開として、歴史認識の問題やテロリズム、ヘイトクライムなどについても、一貫性をもって解説していく手際はお見事。 とくに、新自由主義とナチズムの類似性の指摘は、驚きつつ、なるほどな論立てだったな〜。(まだ、納得まではしてないけど) 現実をしっかりおさえつつ、さまざまな学術研究や理論的、哲学的な議論を振り返りつつ、いわゆる「現実」の分析だけにとどまらず、社会構成主義的な視点も踏まえつつで、すごいな〜、と感動を覚える。 これだけの内容が300ページ強の新書におさめられているので、ページごとの情報の凝縮度は高い。多分、単行本、3冊くらいで扱うような内容だと思う。専門的な知識がないと読めないほどには難しくはないと思うけど、読み通すには一定のパワーがいるかも。
0投稿日: 2021.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログリベラル派が勢いをなくして久しいが,現在の保守が正しいとは言えないし,むしろ暴走を許していると思う.ではリベラルとは何か.しっかりと勉強してみたい.
0投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現在のポピュリズムに至る道筋がよくまとまっている リベラルといっても政治的リベラルや経済的リベラル、個人尊重リベラル、社会(保障)リベラル、(性や人種的な)寛容リベラルなど多様な意味を含む リベラルは普遍的な価値ではなく、ナチスや共産主義と対抗するために中間層に力を与えて、総力戦を戦った 対抗勢力を失い、経済的リベラルが幅を利かせ、マスとしての中間層が衰退し、作者がウーバー化と呼ぶ個人だけが存在する時代へと移行しつつある 一方で個人はなんらかの主張しなければ、自己の存在が確認できないともいえる そこで極端な主張や宗教などが主張される 政治思想、宗教、歴史は個人を縛るものから、個人に利用され声高に叫ばれるものとなった 過激な主張すればするほど、反作用も強くなりますます分断が強まる 宗教も人種も性もそのままあるものとして受け入れることが分断への処方せんである
0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「リベラル」って言葉が広がり過ぎて、経済的な自由を追求する資本主義と、その行き過ぎに歯止めをかけたい社民主義が両方リベラルを、自称して争ってたりする状況をすっきり整理してくれた一冊。
0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的に胡散臭さを感じる欧米のリベラルに対する疑問をよく調査してまとめた本だと思います。 歴史認識についての3章は「ホロコーストの問題が世界で広く認識されるおうになったのは1980年代に入ってから」「被害者としてのドイツの記憶が語られ始めたのは冷戦が終わった1990年代だった」という話が非常に興味深かったです。 リベラリズム再生の提案もしていて、内容が詰まった本多と思います。 可能ならば日本の共産主義や革命ごっこくずれの自称リベラルについてどういう見解か聞いてみたいなと思いました。
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ見通しの立たない未来。原因の分からない様々な社会事象や事件に彩られた今。 そんな時代に、データに裏付けられた「見取り図」を提示した力作である。
0投稿日: 2021.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなかためになる本。今まで不可解だった世界の政治・社会などの情勢に対し、納得のいく解説がえられ、新しい世界像を手にしたような気分である。まあ、至高の価値とされる自由でも、社会の側としては、バランスをとるため、コントロールせざるを得ないことは起こりうるか? もちろん、その際には、何のための自由かリベラリズムか、という認識がなければならないにしても。
0投稿日: 2020.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ私の最近の関心領域に合致するテーマだけに、大変に興味深く読み、かつ著者の多角的な視点から、大いに示唆を得た。かなりの力作。 ただ、テーマがあまりにデカいだけに、一読しただけではまだ消化不良…
0投稿日: 2020.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
よくよく冷静に分析している、40代の研究者の著書だ。 「リベラル」の多様性を多くの研究者の知見をもとに、戦後の政治・民衆の動きを丁寧に読み解いている意欲的な新書、いまの世相を俯瞰する良書だ。 五つのリベラリズムのレイヤー、「経済」「政治」「個人主義」「社会」「寛容」と分類して切り込んでいる 読み物としては難解な類になると思うが、読み手もいち読に終わらず、よくよく考えながら読みたい一冊だ。 若い層には丁寧に読みいてほしいと思う。
0投稿日: 2020.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルが気になり読んでみた。気になっていたことが論じられていて参考になったが、テーマが難しい分、難解な内容だった。 ただ後日、読み直してみるとある程度わかる気がしたので。
0投稿日: 2020.10.30
