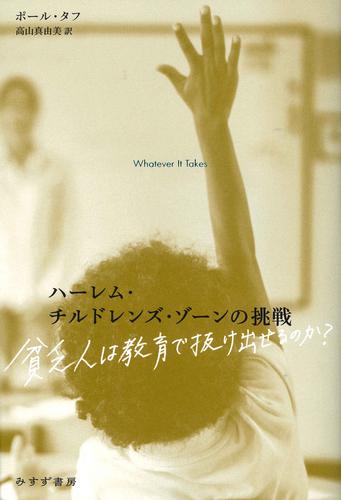
総合評価
(4件)| 0 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログどこに生まれたかで、その先の人生が決まってしまうような不合理。これを甘受してしまうような人間にはなりたくない。何か出来るとかではなくとも、それを認識していたい。 何もしなければ、貧困層に居続けることになるような子どもとその親に、継続的な支援を。家庭での教育、家庭環境の重要性。だからこそ、親へのフォローも大切にする。親といえども、まだ10代。 幼少期の親からの愛情と関心、声掛けで認知能力に差が出る。適切な声掛け、博物館や水族館などへの知的活動、本の読み聞かせの重要性。 ミドルスクールの一時閉鎖は、決断が早い気がしたし、子供達が見捨てられたと思うんじゃないかと、苦しくなった。投資者や、学校の評判を意識せざるを得ないと、子供の教育のための最適な判断が難しいのではないだろうか。 難しいことだけど、結果が伴ってきているのに安心する。先の未来を楽しめる子どもが増えてほしい。
0投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログオバマ政権も注目した、ハーレム地区の貧困に立ち向かうNPOの軌跡が分かる本。著者は、非認知能力に関する著書で名高いポール・タフだ。 プログラム創設者との5年以上にわたる対話や、貧困層に対する様々な学術的研究を基に、貧乏を抜け出すには「何が必要か」について書かれている。 私の知る日本の現状と比較すれば、当事者との関係性や早期からのサポートは、うらやましい限りだ。 事前に手厚い対策を講じることで、問題が発生しなかったことが評価される社会になってほしい、と私は願う。 その一方で、たかだか義務教育レベルのテストで良い成績をとるために、貴重な人材を総動員して子ども達に教え込む姿勢は、私には異様にうつる。(まあ日本も、共通テストなるものに、同じような状況ではあるのだが…) “形”に当てはめることで、無理を生じる典型になりはしないかと、危惧を覚えた。
0投稿日: 2021.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧困地区(ニューヨーク市ハーレム)でチャータースクールを運営するNPOの運営者の奮闘記。 貧困や犯罪の多発する環境等で教育を継続しにくい状況の中で、教育を受けさせ成績を向上させることに苦闘する関係者の姿が印象に残った。 早い段階で教育することが重要で幼児から教育を継続するベルトコンベア方式と、貧困により教育を受ける習慣がない子どもに教育を行うスーパーヒーロー方式。前者に効果があり、後者は効果が出ないというエビデンスがあり、しかも運営する学校(ミドルスクール)でもその通りになっている。 そうした中でNPO(学校)の運営者であるジェフリー・カナダは両方が大事と主張。スーパーヒーロー方式にこだわり結果が出ない中で苦悩するカナダの姿も印象的であった。
0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本人が書いたものではなく、著述家の聞き書きである。訳者の説明がないのも珍しい。大体の試みはわかる。話として読むにはいいが、卒論では参考文献にはならず、この本で言及していた人の論文を見るしかない。教育実践を著述家がわかりやすく本にまとめたもの、と考える方がいい。ヘッドスタート計画で実施したセサミストリートのようなデータは全く使っていないので、話だけである。
0投稿日: 2020.11.04
