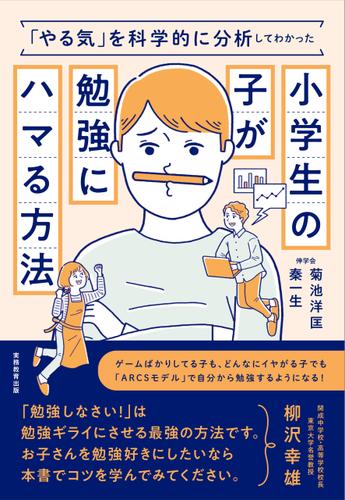
総合評価
(27件)| 6 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていたよりも参考になりました。 特に漢字の勉強方法は、従来書いて覚えるものという刷り込みがあったので、目から鱗でした。 小学生の子供にも伝えて、反復練習で学習していこうと思います。 全てを実践するのは難しそうですが、ご褒美作戦など、家庭でも取り組んでいけそうです。
0投稿日: 2025.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログもう一度読みたい 親も勉強している姿を見せる 本を読んだり 「考えるとは言葉にすること」 「わかっているとは、言葉で説明すること」 とにかく子どもに自分の状況を言葉で説明させる 自分のことを客観視できるようになる 我慢強さが大事 マシュマロ・テストをクリアするコツ 子どもが誘惑に負けないカンタンなコツ ・ゲームが終わったら決まった位置に片付ける ・マンガは本棚の後ろの列、手前には真面目な本を並べる ・テレビにはカバーをつけて、見ないときはカバーをかける 誘惑を目の前から遠ざけるだけで誘惑に負けなくなる 目標は子どもに設定させる 子どもが、自分で目標を立てられるようになるためにまず知識不足を補うことが重要 学歴と収入の関係を子どもに教える 職業体験や中学校見学も立派なやる気情報の源 親としては情報を与え続けて子どもの中から目標が芽生えるのをじっと待つ 子どもに能力は努力で決まると思い込ませる →子どもがなにか成功したとき絶対に才能を褒めず努力を褒めるようにする スモールステップを踏み成功体験を積む テスト点数悪く落ち込む我が子に慰めはNG 共感し次はどうすればよいか一緒に考えて課題改善策目標
1投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもが成長する勉強レベルとは少し難しいと感じるもの、わかったはずだと思ったのに忘れたというのパニックゾーンだから手を出さないというのは目から鱗だった。
0投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ簡潔で分かりやすく、漫画も適度な量で読みやすく、まとめがあるので実践のハードルが低い。 とても良い本だと思いました。 読書が苦手だとしても、目次とまとめを読むだけでかなり良い情報が得られるのではないかと感じました。 ここまで教育や子育ての本を読んで、読みやすさと、分かりやすさを兼ね備えている点で、勧められる一冊です。
0投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生を対象とした、やる気を出すために親がどう向き合えば良いのか、具体的な実践アドバイスと考え方が書かれています。 科学的で心理学的な立場から、客観的かつ具体的なアドバイスが実にわかりやすく、章割りやポイントのまとめ方も丁寧で誰が読んでも納得出来ると思います。 自分が思っていた事が明確かつ整然とまとめられて頭が整理されます。また、さらに深い思考と知らなかった情報がスッと入って来て、早く実践したい気持ちになりました。 親にも自信を付けさせてくれるような素晴らしい内容でした。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学校高学年〜中学生向け。心理学と現場での指導経験を踏まえた内容で、説得力があります。 親向けに書かれたものですが、親子関係ではなかなか難しい取組もあますが、この点のフォローのコメントも後半にあります。 指導担当者の立場の方には、かなり参考になる内容で、手元に置いておきたい一冊です。
0投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の息子がいます。学校の宿題をこなすことさえも一仕事で、勉強したくないと公言しているので、何かのヒントになればと思い、読みました。やる気をだしてもらうためにはどうしたらいいか、ということがたくさん書いてあり、自分では認識できなかった部分が認識できて、非常に参考になりました。
0投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの通り、子供が勉強にハマる方法が書かれている。 個人的に、そこまで目新しいものはなかったが、納得しながら読むことができた。 子供のやる気エンジンは6種類あり、外発的動機のりも内発的動機を高められると更に良い。 やってはいけないご褒美のあげ方は参考になった。 ご褒美のハードルを上げすぎない、回数が少ない、目標に反するご褒美など、自分の行動を見直すキッカケとなった。
0投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は自分達の学園で取り組んでいる「ブロックアワー」の際のコーチングに役立っている。学びのコーチとしたいることが多い、自立的な学びの時間に、どんなことを見取り、コーチングするべきかのアイディアをたくさんもらうことができた!
0投稿日: 2023.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ教育心理学をもとに勉強が好きになる誘導方法が紹介されています。 完璧主義と最善主義。 私も所々「こうあるべき」に囚われている部分があったことを反省しました。 冬休みを迎えるにあたって参考にしたいと思います。
18投稿日: 2022.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログさらば完璧主義、ようこそ最善主義 色々なるほど、と思う子どもへの対応が書かれているけれど、個人的には最後のまとめで出てきたこの言葉に尽きた。 完璧主義、親子ともどもこれにとらわれて怒りスイッチが入りやすいタイプ。 肝に銘じます。
1投稿日: 2022.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもは大人のように理性で勉強しないため、いかにモチベーションを持たせて勉強したい気持ちにさせるテクニックが紹介されている。 一番良いと思ったのは、他人との比較ではなく、過去の自分との比較に徹するというもの。我が家では塾の偏差値で推し測って良し悪しを判断していましたが、過去の成績と比べてどうかという話が良さそうです。
3投稿日: 2022.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長男の勉強方法について、少し考えなければいけない時期になったので、こちらの本を手にとりました。 著者の方は学習塾を経営されている方のようです。子どもへの接し方がよくわかってらっしゃるのだな、という印象の書き方でした。 小一の息子の勉強方法の参考にするには、少し早いかな?とは思いました。 どちらかというと、勉強にあまり向き合ってくれなくて困っている中学年以上の親御さん向けなのかな? でも低学年の親でも、いずれ来るかもしれない子どもの勉強嫌いを想定して親としてどう接してあげればいいかを考えさせる内容もありました。 この本は大筋として、【ARCSモデル】という流れに即した形で構成された内容でした。 Attention…注意、面白そう Reason…理由、役立ちそう Confidence…自信、できそう Satisfaction…満足感、やってよかった 子どもの学習意欲を引き出す工夫が沢山紹介されていて、実際私もすぐに活用させてもらいました。 例えば、スーパーで買い物しながらクイズを出す、などです。 また、褒め方、失敗したときの対処法も納得しながら読み進められました。 ご褒美のランダム性、なかなか凄い。実践してみようと思ってます。 また、勉強で落ち込む我が子に「一生懸命がんばったんだから」「君が悪いんじゃない」という言葉は逆効果なのも勉強になりました。 思わず言ってしまいそう。 「報われなかった努力をほめられると、人は自分の無力さを更に強く意識する」 これは、気をつけなければならないなと思いました。 最後の「完璧主義から最善主義」の部分、わたしとってはとても響く内容なので、忘れないようにしたいです。 教育って奥が深いですね… これからも日々勉強です。
0投稿日: 2022.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクロググサッとくる一文も、納得できる部分もあり、勉強になりました。自分も子どもの頃、同じように感じていたのにな…と、反省します。改善すべき点を整理して、明日から実践です!
0投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの勉強で悩んでいたので読みました。 特に自分で選ばせるということと結果が出ない子に怒らない技術。質問の仕方や声かけの仕方も参考になりました。
0投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログやる気の源には、大きく分けると4つのパターンがあることが分かった。自分から勉強したいと思う子どもは少ないので、まずは勉強がしたくなるきっかけを作り、ゆくゆくは学習自体が楽しいと思えるように促すことが大切である。本書では、科学的に分析された実践や声掛け例、心理学など、様々な手立てが載っている。小学生のお子さんだけではなく、勉強嫌いの中学生にもためになりそうである。
0投稿日: 2021.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ塾という教育のプロがやっていることなので家庭でこれができれば苦労はないと思わなくもない。けれど本書に書かれた間違ったほめ方や叱り方をしないよう心がけるのは悪いことではないだろう。
0投稿日: 2021.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
伸学会代表の著書 算数はパズルと呼ぶ 親も勉強しよう ゲーム要素を取り入れる スーパーの買い物でクイズ 知識おもちゃ ザイアンス効果 科学館博物館 YouTube活用 アプリ 自分で選択させることでやる気 やる気エンジン 目標を設定させる 子どもの話を聞く 努力が大事と伝える 比較より子どもの成長を誉める
0投稿日: 2021.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
勉強を強制されると子供は勉強嫌いになることや、親が子供に目標を与えてはいけない、難し過ぎる問題は子供がやる気をなくす、結果が悪いときの慰めはNG等、親が陥りがちな失敗を指摘しており、耳が痛いが、とても参考になった。結局、努力は才能に勝るという考え方も共感できる。ARCSモデルを今から少しでも活用していきたい。
0投稿日: 2021.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これなんで読もうと思ったか忘れたんだけどずっとkindleに入ってていい加減読もうと思い読了。ざーっとなぞる程度。塾の先生が短期的に効果を出す施策を並べてくれている感じ。
0投稿日: 2021.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://jitsumu.hondana.jp/book/b450449.html , https://www.singakukai.com/
0投稿日: 2020.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもに勉強をさせるには? →物事に対して、やる気を出させればいい ARCSモデル:注意、理由、自信、満足感の4つの要素が揃うとやる気が出る 【注意(Attention)】 ・子どもの前で一緒に勉強する ・勉強をゲーミフィケーションする 新鮮な刺激がある クリアすべきミッションがある ちょうどいい難易度である 結果がすぐに目に見える ・スーパーでクイズを出す ・知育おもちゃを遊ばせる 親自身も一緒に楽しむこと。 ・YouTubeを活用する 【理由(Reason)】 内発的動機に基づいた勉強のやり方を身につけることが大切。 ・自律性の欲求を満たすために、「自分で選択した」という感覚を与える。 (勉強するための6つの動機) ○報酬志向 →叱るのではなくほめる。 ○自尊志向 →近いレベルの競争相手と切磋琢磨する →スコアを可視化する ○関係志向 →目標を共有し、チームの連帯感を作る。 →親も勉強する ○実用志向 →現実に授業内容が役立っている場面を教える(ハードルは高い) ○訓練志向 →他者ではなく、過去の自分からの成長に着目する →「前回との差」に重きを置く ○充実志向 →面白く学べる施設にいく →学びを楽しくする工夫をする ・なぜ〇〇をしているの?、これからどう〇〇をすればいい?など、問いかけによってその子に考えを言葉にしてもらう ・誘惑を目の前から遠ざける →ゲームを決まった位置に片付ける →漫画は本棚の後ろの列に置き、手前には真面目な本を並べる →テレビにはカバーをかける ・子どもが自分で目標を立てられるようになるために、知識を与えてあげる。たいていの子どもは、よく知らないため漠然とした夢、目標を立てがち。 夢を親が設定するのではなく、情報を与えて夢を持つ手助けをしてあげる ・日常生活の会話において、子どもが親の2倍は喋っている状況を作る→言われたことをそのまま繰り返す。主観的な感情の発露に、「なぜそうなのかな?」と問いかけの形で会話する 【自信(Confidence)】 ・自己肯定感(自分は愛されている)と自己効力感(自分はできる)を身に着けさせる 自己効力感を養うには 成功体験を積む 他人の成功を見る 成功体験を積むためには、「ギリギリ」クリアすることが大切。最初は難易度をぐっと下げて、少しずつ目標を達成していく。 失敗しても責めない。できるだけ情報・教訓として扱うこと。 ・勉強レベルには、子どもが成長できる最適の勉強レベルがある。(今の実力ではやや難しい程度)それを超える難しいものはやっても伸びないし、勉強がキライになってしまう。 ・子どもがチャレンジに失敗しているところに、「慰めの言葉はかけてはいけない」。報われなかった努力を褒められると、無力感がさらに強くなるから。 厳しい内容であっても、「まだ勉強が足りなかった」「別の勉強方法を試してみよう」など、改善のために必要な情報を伝える必要がある。自分の能力・性格が悪いのではなく、勉強の量・内容・やり方といった行動がいけなかったと教えてあげること。 【満足(Satisfaction)】 ・褒めるときは、結果ではなく行動を褒めること。 ・褒めるときは、すぐに褒める ・人と比べて褒めない。自身の成長を褒める。(努力と結果は必ずしもリンクしないので、誰かと比べて出来た出来ないは語らない) ・ご褒美で釣るやり方はいいのか?→低いハードル、小さいご褒美、近い目標、回数多なら平気。 ゲーム機など大きいものではなく、どこかに遊びに連れて行く、などいった、その次の目標に向けた行動の邪魔にならないご褒美にする。 【まとめ】 結果は自分で変えられる、と覚えさせること。 結果が「才能・資質」によるものではなく、努力によるものだという考えに導いてあげる。
0投稿日: 2020.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで感じていた学習意欲を促すポイントが整理されてる。読んですっきりした。娘の教育と自分の成長に活用したい。
0投稿日: 2020.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ実践したいこと ・決まった時間で家族全員で勉強する時間をつくる ・勉強は子供がもっと続けたいのに…というタイミングで打ち切る ・知育おもちゃで遊んで気がついたら賢くなっているように誘導 (かるた、トランプ、カードゲームなど) →家にある都道府県トランプをつかう、科学すごろくを早速購入 ・おでかけは科学館や博物館で遊ぶ
0投稿日: 2020.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログやる気を引き出すメソッドの羅列。ほめるだけじゃだめ、ご褒美だけじゃだめ、やっぱり勉強する理由だよなー、と思わせてくれる。一つ一つのメソッドは陳腐なものが多いが通読すると、親としての在り方を教えてくれる。コロナ時代の家庭学習に必見。
0投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強をレベルアップゲームにさせるような遊びにさせたりとポイントカード理論のさらなる発展系の話が斬新。 また、運や才能で駄目と子供が考えると努力をしなくなるので、いかに努力をしたからいい点がとれたと、努力の価値を認識させる記述が認識できてよかったです。早速実践です。
0投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「「やる気」を科学的に分析してわかった小学生の子が勉強にハマる方法」 子どもだけでなく大人にも必要。 取り上げられているのは、勉強を楽しんで取り組む“技術”として知られる、アメリカの教育工学者J・M・ケラーがまとめ上げた集大成とも言えるARCS(アークス)モデル。 A:注意Attention、R:関連性(Relevance)、C:自信(Confidence)、S:満足感(Satisfaction)から成り、各要因に対応した動機付け手立てや設計の手順が提案されている。アメリカでは実用性の高さから、評価の高いモデルとなっている。 ビジネス(社会人の勉学)では、「面白そうだ→業務に使えそう→やればできる(現実より少し上の達成レベルを設定)→よかった」という流れを目指す。また、学習に対しては、「面白そうだ→やりがいありそうだ→やればできそう→やってよかった」というプロセスに準ずることを目指す。対象者は子供から大人まで。応用が効くこのモデルは理にかなっている(偉大な人が提唱したのだから当たり前かも知れない)。 問題はいつの時代も理論的にはイケるものをどうやって実用化するか?。モデルが提唱する内容にケチはつけるつもりは無く、次なる課題として、じゃあ、どうやれば実践できるのか?実践する為に解決すべき問題は何か?と言うこと。やってこそ意味がある訳で、とくに大人になると、Aに関して言えば、面白いを感じるよりはやんないといけないからやる、みたいなことが多い。その場合、Rはかなり大切だ。 どう実用化するか?に対しての答えのひとつが、本書で取り上げている「自ら伸びる力を育てる」メソッドである。あなたのお子さんを勉強好きにしましょう!をテーマに、ARCSモデルの理論を子供学習に応用している(よく見るとRはReasonにもなっている)。 AからSまで、子供を勉強させるためではなく、子供自身が進んで勉強に楽しみながら、時に悔しがりながら、取り組むためのアプローチを解説している。どれも良く練られている。実際の指導では、本書で提示しているアプローチが常に通用するわけではないだろうが(うまくいったものは残して、ダメだったものは捨てることを念頭にしているとある)、それは当然。 大切なのは、「何のために勉強するのか」と言う本質を見失わずに指導していること。また、将来を見据えて子供が知るべきことはなるべく情報を提供する等、人生と言う長いスパンで勉強する意味を見ていること。特に、受験に対する意見や完璧主義ではなく最善主義を!と言うメッセージは、非常に大切に思う。 塾は、体力的にも精神的にもかなり大変というイメージだが、そんな中、上記のような目には見えにくいもの(特に受験に必死な親は見えないだろう)を忘れずに指導し続けているのは凄いと思う。塾の授業料も其れ相応ではあるが、トライする価値はあるかなとは感じる。まあ、自分には子供はいないんだけど。こういう見方が出来る教育機関は必要だ。 因みに、前述した大人はどうするの?には、当然答えていない。これは子供の教育に関する本だからだ!しかし、当てはめることが出来る部分はある。子供の時は自分はどうだったかな?と反芻しながら、使える理論は、第2の子供期だと考え、大人でありながらも、自らの改革を推進したいところだ。 【目次】 はじめに 「やる気」を分解するARCSモデル 1章 Attention〜勉強に「ワクワク」させる〜 2章 Reason〜勉強に「やりがい」を感じさせる〜 3章 Confidence〜「自分もできそう」と思わせる〜 4章 Satisfaction〜「勉強してよかった」と実感させる〜
2投稿日: 2019.08.06
